お断り
このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたい方には不向きだ。
よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。
ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。
引退してからは、本は買うものではなく借りるものになった。理由は二つある。ひとつは先立つものがないからであり、もうひとつは待つ時間はいくらでもあるからだ。
いったい何を読むのだと聞かれるかもしれない。現役時代は小説なるものは読んだことがない。しかし今は家内の影響を受けて、剣豪小説から国産ミステリー、更にはネットに星の数ほどある悪役令嬢や異世界ものなど暇つぶしに読んでいる。とにかく活字中毒だ。
ちなみに今日は4月20日だが、今年に入ってから読んだ本は67冊、月18冊の割になる。
私が大好きなのは技術史関連である。現役引退してからは最先端よりも、昔使った機械や電子機器の発祥からの歴史を知ることが楽しみになった。
 二番目は飯のタネだったISO認証関係だが、こちらはもう枯れた技術なのでめったに新刊は出ない。
二番目は飯のタネだったISO認証関係だが、こちらはもう枯れた技術なのでめったに新刊は出ない。
次に興味があるのはこれも仕事だった環境関連だが、環境法令は興味を失った。だって法規制の規制基準の知識を最新化しても、相談に来る人もおらず使い道がない。それで今は環境問題全般、特に資源問題とか地球温暖化の本が出ると必ず読むようにしている。
いずれもマイナーなカテゴリーだから図書館の蔵書はとうに読みつくした。そういうカテゴリーの本は普通の図書館にはあまりなく、工学系の大学でないと整備されていない。図書館を公開している大学もあるが、そこに行く電車賃ももったいない。
なにしろ自宅から東京まで電車賃が往復千円かかる。借りて返すだけで電車賃が二千円じゃ、二千円以下の本なら買ったほうが安い。
結局住んでいる市と近隣の市の図書館くらいしか利用していない。市の図書館で興味がある本が見つかっても、新刊書は行列というか順番待ちが長い。昨年末に発行された温暖化の本3冊をお正月明けに予約したが、現時点で私は8番目・11番目・12番目だ。いずれも所蔵が1冊しかないから、一人平均10日間借りるとして、私の順番になるのは早くても7月か8月だろう。とはいえ1冊1500円とか2000円するわけで、買う気は全くない。
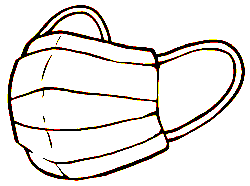 予約したら順番が来るまですることはないが、本を読まないと死んじゃうという不治の病に罹っているので、1週間に1度は図書館に行って何かは借りてくる。
予約したら順番が来るまですることはないが、本を読まないと死んじゃうという不治の病に罹っているので、1週間に1度は図書館に行って何かは借りてくる。
コロナ流行で緊急事態のときは図書館も閉館され、マンボウ(まん延防止等重点措置)のときは書架に入ることもままならず、ネットで予約、用意ができたというメールを受けたら取りに行くという方法でしか本を借りられなかった。
マンボウが解除されてからは書架をさまようことが解禁され、銀ブラならぬ書架ブラを楽しむ。とはいえ感染防止のため、書庫のあちこちにおかれていた椅子は撤去され、座ってじっくり読むことはできなくなった。
前述したように技術史とかISO関係はもう読み尽くしたので、今は行くたびに以前は見たことのない棚をさまよっている。
実を言って昨年からケガ・病気が連続している。そんな話を老人クラブですると、知り合いがいつまでも若い気でいるから無理をするのだと言われた。
じゃあ年寄りはどうすべきかと思い、老後の暮らしなどを書いた本を読もうと思った。実を言って退職してから10年、老後のための本など読んだことがなかった。図書分類を調べると、老後の生き方は倫理学・道徳の区分になると初めて知った。
というわけで今回は図書分類番号159の人生訓. 教訓の棚を眺めていた。老後の本といってもいろいろあるものだ。
とりあえず目についたこの「生涯現役の知的生活術」とボケ防止などの本を借りた。この本は発行が2012年、ちょうど10年前になる。まあ、こんな本は新しくなければダメということもない。読んで暇つぶしになればよく、面白ければ全部読むし、面白くなければ読むのを止め返却すればよい。なにしろただなんだから、元を取ろうなんて力まなくてもよい。
| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| 生涯現役と知的生活術 | 渡部昇一 | 育鵬社 | 9784594066888 | 2012.10.24 | 1500円 |
この本は著名な人たち13名が、20ページくらいずつ自分の老後について書いたものである。フォームというか書くべき事項を決めているわけではなく、人により書いているテーマも中身もバラエティに富んでいる。
発行当時の著者の年齢が72歳から90歳、だから今時点存命なら82歳から100歳ということになる。
みなさん、出版時に高齢であるにもかかわらずボケておらず元気で素晴らしいと思えるけど、長生きして元気な人に依頼したわけだから当たり前といえば当たり前だ。彼らと同様に著名な方々ですでに物故者となっている人は彼ら以上にいるのは間違いない。
そして発行されてから今までの10年間に、13名中5名の方がお亡くなりになっている。みなさん平均寿命を超えているのだから不運というわけではない。
| ご芳名 | |||
| 小野田寛郎 | 90歳 | ||
| 千 玄室 | 89歳 | 98歳 | |
| 東城百合子 | 86歳 | 不明 | |
| 三浦朱門 | 86歳 | 2017年 91歳没 | |
| 岡崎久彦 | 82歳 | 2014年 84歳没 | |
| 渡部昇一 | 81歳 | 2017年 86歳没 | |
| 曽野綾子 | 80歳 | 90歳 | |
| 屋山太郎 | 80歳 | 90歳 | |
| 伊藤 隆 | 79歳 | 89歳 | |
| 小川義男 | 79歳 | 89歳 | |
| 村上和雄 | 76歳 | 2021年 85歳没 | |
| 渡辺利夫 | 73歳 | 82歳 | |
| 江口克彦 | 72歳 | 82歳 |
書かれた内容は、若い時から変わらず文筆業とか研究者を続けているというのもあり、いかに体力が低下しないよう日々努力しているかを書いている人もあり、健康自慢・病気自慢もあり、いかに健康に長生きするか持論を書いている人もいる。
そしてそれぞれが考えている生涯現役の意味もいろいろだ。
大学の先生だった人は今も研究を継続しているのもあり、物書きは歳をとっても物書きをしているわけで、生涯現役というよりも、いまだ引退せずと表現したほうが正しいと思えるものもある。サラリーマンとか雇われ経営者ではありえない形態だ。
年を取ってから新しい生き方にチャレンジしているとなると小野田寛郎くらいだ。
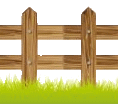 |
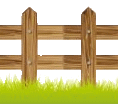 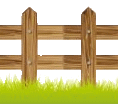 |
徒然草と考えれば、みなさん文章はうまいし、若い時苦労した・頑張ったとか、俺は今もすごいだろうという年寄りの自慢話もほほえましい。
だが内容がそういうものだから、この本を読んでも生涯現役で生きていけるアイデアが得られるわけではなく、知的なあるいはボケない生活を送る方法も得られない。
せいぜい得られるものは、著者たちがどんな時代、人生を歩んできたのか垣間見る程度だろう。もちろんそれを知って感動したとか尊敬したということもない。
はっきり言って、タイトルは羊頭狗肉である。
この本を読んでためになったとか、感動したという人はまずいないだろう。もし素晴らしい本だと感動したなら、あまり本を読まない人だ。
とはいえ、私はこの本を読んで私なりにいろいろ思うことがあった。そんなことを思いつくまま書く。
■ ひとつ、生涯現役も知的生活術も定義されておらず、皆好き勝手なことを語って終わっていること。
この本に寄稿した人は私より10歳から30歳年上だ。10歳違いなら多少時代は重なるが、30歳違うと私の親の世代になる。そうなると感覚というか価値観はだいぶ違う。
それからみな功成り名遂げた人ばかりで有名人だから、有名な大学を出ているし、交際も著名な政治家、作家、芸能人、財界人などセレブが連なる。まあそんなことで思い入れはまったくない。それは私が偏屈な田舎者というだけでなく、住む世界が全く違うのだから仕方がない。
そしてまた定年後、近隣住民とどう付き合うかとか、友人を作るとか、生きがいをいかに持ち続けるかとかいうことなどは、著者たちはまったく頭にない。著者13人にとって、そんなことは考えもつかないようだ。作家や研究者にとっては定年もなく引退もなく、50代、60代、70代……歳をとっても節目がなく、ただだらだらと続いていくと認識しているようだ。作家は歳をとっても作家であることに変化はない……としか思えない。
サラリーマンが引退すると、付き合う人が職場の人から近隣や趣味関係に変わるが、こういった人たちは全く変わらないようだ。
嘱託になるとこんなふうに・・
|
もちろん嘱託となり元の職場で働くということもあるだろう。しかし昨日の部下が今日は上司となり、同じ仕事をしても賃金も変わり、裁量権も変わり、心情的には相当変化がある。
ということで一般人にとっての生涯現役とは全く意味が違う……と私は受け取った。
それを素晴らしい人生と思うか、つまらない人生と思うかは人によるだろうが、そういう人生は普通のサラリーマンと生涯現役という意味合いが大きく異なるだろう。
もっとも曽野綾子は、生涯現役とは自分で炊事を含め身の回りのことができること定義している。この言い方は体感的に納得できる。いくら研究を続けようと足腰立たなければ自立した人間とは言えないだろう。
あるいは高齢になって足腰が立たなくなり要介護になったが、それに負けずに新しいことにチャレンジしているというならその勇気は称賛に値する。でも大学の研究をまとめるのが終わらなかったから継続しているというのは悪いとは言わないが、取り立てて生涯現役と言うほどのことがあろうか?
■ ふたつめは、若い時は共産党、共産主義に染まって活動したという人が多い。だいたいは30歳くらいになって共産主義がおかしいと気が付いたと変節するのだが、
 私が若い時1960年代、多くの大学生がデモとか大学紛争とか騒いでいた。彼らは純粋に共産主義体制が良いと考えていたのだろうか? ただ現状を壊せば世の中が良くなると思っていたのか?
私が若い時1960年代、多くの大学生がデモとか大学紛争とか騒いでいた。彼らは純粋に共産主義体制が良いと考えていたのだろうか? ただ現状を壊せば世の中が良くなると思っていたのか?
私はそういうのを見ると完全な間違い、アホとしか思えなかった。だって高校を出たら働いて稼いだ金を親に渡さなければ一家が食えないという状況で、そんな遊び半分どころか完璧に遊びのデモなんてしているわけにはいかない。そもそも親父は私が高校に行かず、中学を出たら働いてほしかったのだ。
貧しい人のためにと語る人は貧しくない。それは学生に限らず政治家も同じだ。共産党書記長が豪邸に住み優雅な生活をしているのは誰でも知っている。彼らは良い社会を作るためにではなく、単に騒ぎたかったからだと私は考えている。いやそれ以外考えられない。
まず資本主義であろうと共産主義であろうと、国富あるいはGDPが大きくなければ国民一人一人の分け前は大きくならない。
明治時代、日本で産業を興そうとした資本家たちが悪役として描かれることは多い。そして政府高官と資本家が結託して大儲けするドラマも多い。視点を変えた野麦峠とかその他、虐げられる人々を描いた小説も多い。
だが資本家が搾取したから国民は貧乏だったのか? 資本家は豊かな暮らしをしていたのか? 515事件のときの日本のGDPを人口で割ってみれば、国富をどう分配しようと国民みんなが貧しいことは変わりない。財閥の持つものを国民に分け与えても太平洋に水一滴、いかほども変わらない。
そしてまた国家が発展するためには資本を投入しなければならず、そのためには資本を集中しなければならないのは自明なのだ。
小川義男がソ連に行ってあまりの貧しさに驚いたと書いているが、アホかバカかと……行く前から当時のソ連のGDPをソ連の人口で割れば分かる。もちろん1990年になって、ソ連が公表していたGDPそのものがウソだとわかったが、ソ連の発表であっても豊かとは縁遠い
共産主義とはみんなを等しく豊かにする仕組みでなく、みんな等しく貧乏になる社会の仕組みなのだ。
しかし現実の社会主義国家/共産主義国家は、そして日本共産党も同じだが、指導者(支配者)だけが豊かになり、その他大勢は貧しくなる国家体制なのだ。
では過去から数多存在した王国や帝国と社会主義国家/共産主義国家は何が違うのだろうか?
それは王権神授説を語らず、指導者は人民の代表と騙るとこが違う。仁徳天皇の「民のかまどは賑わいにけり」なんてのとは無縁の思想であり体制なのだ。
頭の良い人たちが、なぜそういう嘘に騙され、貧乏な国にあこがれたのかというのが疑問だ。日本を占領したアメリカが嫌いだ、敵の敵は味方と思ったに過ぎないのか?
ともかくこの本に寄稿した人の中にも共産主義に傾倒した人が多い。私はそれをもって彼らは頭がよくないと言い切る。
15歳の私は共産主義など嘘っぱち、悪の体制だと考えていた。
もちろん両親の影響も大きかっただろう。親父は家長主義者で暴力は日常茶飯事であったから、私は親父を反面教師とした。その結果、反共でかつ家長主義を嫌う人間になった。同時に暴力は使わないけれど、必要な時もあると考えた。演繹すれば非武装中立など語義矛盾だ。
中立ってどの国とも仲良くすることと思っている人が多い。そういう人の頭の中はお花畑だ。
そうではない。中立とはどの国とも仲良くしないことだ。なにしろ戦争はめったに起きないが、戦争がないときでも同盟を結ばないのが中立国だ。どの国とも仲良くしないのだから、いつどこから攻められるか分からない。だから武装しなければならない。
私が親父の封建的な生き方に反発して共産主義に陥ることなく、また共産主義は悪だと旧体制に逃げなかったのは、微妙なバランスの結果だったのか? あるいはそれこそが親父の狙いだったのか?
少なくても私は人生の中でいっときも悪い道に入らなかったことは自慢できる。最後の審判で共産主義にはまったことを懺悔することはない。
21世紀になっても日本に左翼が政権を取ったり、共産主義の青年が国会で発言したりと、共産主義はまだまだ勢力を持っている。なぜその欺瞞が知られないのか、それが疑問だ。
単に流行を追う日本人の性かもしれない。
■ みっつめ、まともな人と思っていた曽野綾子もバカなことを語っている。
 民主党の松本 龍という復興大臣が語った「知恵を出したところは助けるが、知恵を出さない奴は助けない」という発言を、聖書にある「天は自ら助くる者を助く」そのままであると讃えている(p.281)。
民主党の松本 龍という復興大臣が語った「知恵を出したところは助けるが、知恵を出さない奴は助けない」という発言を、聖書にある「天は自ら助くる者を助く」そのままであると讃えている(p.281)。
そのセンテンスだけをみればそうかもしれない。だがあのやくざまがいの口調で知事たちを前にして上から目線で語ったその言葉はシャレにならない。
ましてそれ以外の松本の、知事や被災者たちを子供扱いする発言と態度はとても許せるものではない。
「生娘をシャブ漬け」と語った吉野家専務以上に悪質な発言と態度だ。許し難し!
曽野綾子はそういったコンテキストを知って擁護したのか?
聖書の言葉だって場面と使い方では不適なこともあるのだよ、
松本の傲岸不遜はYouTubeにたくさん証拠が残っている。
「自分が入ってからお客さんを呼べ」(注2)
まさに暴言!自分をお客さんとは、お前、何様 💢
「何市がどの県かわからない」
映像を見ると、単に己を無知だと語っているのではない。俺はそんな細かいことは知ったことないという意味だ。震災を受けた都市がどこにあるの知る必要がないとは不勉強ではなく、復興大臣として資質と姿勢の問題だ!
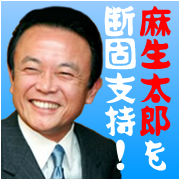 |
なお、麻生太郎は東日本大震災の直後、福島県相馬市を訪れ激励と指導を行った。どこかのバカ復興相とは違うんだ。
九州出身といってもピンからキリまであるのだねえ〜
サヨクベッタリのマスコミもよく松本 龍の暴言を報道したものだ。自民党嫌いなマスコミでも、あれを無視したら自分が叩かれると思ったのだろうねえ〜
曽野綾子もそんな傲岸不遜な松本 龍を擁護するようじゃだめだ。
私は福島県人として、松本 龍を許さない。その発言を支持する曽野綾子も許さない。そして決して忘れない。
吉田松陰の言葉を借りる
「みちのくの、痛み悲しみ薄れても、
注:辞書を引くと「愚見」には、己の意見を指す謙譲の意味と、単に愚かな意見の意味もある。
この本ですばらしいと思ったのは、小野田寛郎の次の言葉だけだ。
「私は神頼みしたことはない。お正月に手を合わせて「去年一年ありがとうございました」と言っても「今年もお守りください」と願ったことはない(p.62)」
この一文だけでこの282ページの本を読んだかいはあった。
意味するところは、胡寅の「人事を尽くして天命を待つ」とか、武蔵の「我、神仏を尊びて、神仏を頼らず」と同じだが、より平明で子供に教えるにも分かりやすい。
とはいえ、この言葉も特段、生涯現役とも知的生活とも関係ない。
私は知らなかったのだが、ルバング島で小野田少尉を発見した冒険家 鈴木紀夫氏は1986年ヒマラヤで遭難、1987年に遺体発見された。小野田寛郎は慰霊のためにヒマラヤに行ったという。
![]() 本日の疑問
本日の疑問
著者たちは本に書いたとおりに生きているのだろうか?
それならなんという薄っぺらな人生なのか?
それとも真の生き様なんてみせるものかと、フェイクを語っているのだろうか?
どちらにしてもあまり参考にはならないようだ。
注:どうでもいい話だが、作家、政治家、スポーツ選手には敬称をつけないのが基本らしい。
小野田寛郎や千 玄室がそれに該当するのかどうか何とも言えないが、とりあえずこの本を書いたのだから作家とみなす。
注1 | ||
注2 |
松本の暴言に怒った宮城県知事 村井嘉浩は、震災復興で活躍しその後も県知事を務め現在5期目である。現役知事で5期目は6人いる。目指せ最長不倒!
|
外資社員様からお便りを頂きました(2022.04.21)
おばQさま 本が読みたくてたまらない,知的好奇心が衰えないのは素晴らしい事だと思います。 いつも楽しい記事を有難うございます。 毎度の部分ツッコミで積みません。 鵬雲斎(千玄室)大宗匠は,つい先日:4/19に99歳になられました。 こちらのニュースでも,元気でお献茶しております。 40年以前,京都の裏千家でお会いして,当時でも若宗匠にバトンタッチされたところでした。 俳優の西村晃とは特攻隊同期で,大宗匠は徳島白菊特攻隊で特攻予定だった話を聞いた事があります。 今でもお元気なのです。 |
外資社員様 毎度ご指導ありがとうございます。 言い訳させてください! この文章を書くのに二日三日かかりました。初めにウィキペディアで年齢確認した時は98歳でした。今(4/21)確認すると99歳でした。なんとお誕生日が4月19日でありました。 ということでお許しください。 しかし外資社員様は交際が広くセレブのお知り合いもいらっしゃるのですね。掛け値なしに驚きました。 私にとっては新聞やテレビに出る人という存在でしかありません。それは千さんだけでなく、すべての政治家も芸能人も雲の上とは言いませんが、縁のない方々です。世の中は広いというかなんというか…… |
推薦する本の目次に戻る
     |

