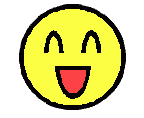第76条2項 (2002.11.07)
第76条2項 (2002.11.07)
「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」
この条項は二つの文章から成り立っています。
- では第一文
『特別裁判所は、これを設置することができない。』
ここで特別裁判所とはなんでしょうか?
この言葉は法律、施行令、規則でも言葉の定義もなければ、使われてもいません。ご自分で調べたい方は法令検索サービスで一発です。
ただ一箇所使われているのがこの憲法76条2項です。
広辞苑によると
『特別の身分の人や事件に裁判権を行使する裁判所。旧憲法の軍法会議、行政裁判所などがこれに当たる』とあります。
なるほど、そうなんだ・・・・日本には簡裁、家裁、地裁、高裁、最高裁しかないんだ!
と肯いちゃいけません。
ちょっと前に憲法64条というのがあります。
『第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。』
はあ〜、弾劾裁判所というのはなんなんでしょうか??
弾劾裁判所に関しては9本の法律がその規定をしています。
弾劾裁判所は特別裁判所ではないのでしょうか? じゃあ普通裁判所か? なんて突っ込んじゃいますよね、
憲法を書いた人は64条からたった12条進んだだけで前に書いたことを忘れてしまったようです。
ちなみに、日本国憲法原文(英文)では
弾劾は『impeachment』で特別裁判所は『extraordinary tribunal』です。
英英辞典では
tribunal: a type of court with the authority to decide who is right in particular types of dispute or disagreement
つまり権威(者)が正当か否かを裁く特別な裁判所ということです。
特別裁判所の一形態が弾劾裁判所であることは間違いないようです。
法学を学んでいる方がもし、弾劾裁判所とは・・・とか特別裁判所とは・・・と反撃してきても私は一向に困りません。
定義されてない言葉での議論は無意味なことです。
確固たる定義を持ち出してくださいね、
もっとも法で定めてない定義は『私は認めません』
『憲法の謎も極まれり!』というところでしょうか?
ちなみにアメリカ憲法では弾劾はあっても特別裁判所に対応する語句はありません。
- では第二文
『行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。』
この文章を字義とおり解釈しますと、『行政機関は1審、2審は行うことができない』とは言っておりません。
これまた矛盾ですね、
憲法第5章は内閣であり、定めているのは『行政』です。
憲法第6章は司法であり、定めているのは『裁判所』です。
第6章のはじめの条文 第76条1項では『すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。』と言明しています。
すべてといいながら少しは違うのでしょうか?
少しだけなら司法権を行政に分けてあげるのでしょうか?
ところで我らが憲法学者 土井たかこさんはどのような解説をされているのでしょうか?
ぜひ知りたいものです。
終審とはなんぞや?
2002.11.21追加
実を言って法律、憲法で『終審』の定義はない。
憲法ではここでだけ使われている。
法律ではただ1本次の法律でのみ使われている。
裁判官分限法(昭和二十二年十月二十九日法律第百二十七号)この条文からは『終審』とは三審制の最後の裁判として使われていることが分かる。
第三条(裁判権)○2 最高裁判所は、左の事件について裁判権を有する。
一 第一審且つ終審として、最高裁判所及び各高等裁判所の裁判官に係る分限事件
二 終審として、高等裁判所が前項の裁判権に基いてした裁判に対する抗告事件
広辞苑においても『審級制度における最終裁判所の審理』つまり三審制において三審めのことらしい。
三振じゃないよ!
しかし、この条文において『終審』を『三審である』で解釈しては『行政機関は、終審として裁判を行ふことができない』というのはいくら考えても意味が通じない。
毎度のことながら原文はどうなのだろうか?
No extraordinary tribunal shall be established, nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.するってえと、この文章は、
ええとですね、乏しい英語力ですが・・・
Final judgment なら最終的な裁判だろう
しかし、この文はいささか異なる。
final judicial power とは『最終的な司法上の権力』あるいは『司法上確定できる権力』ではないのだろうか?
『特別な裁判所は設立してはならん、かついかなる行政府の組織・部門も司法に関わることについて確定的な判断をする権力を与えられない。』
ということじゃないのだろうか?
そう解釈すれば、憲法76条1項と矛盾することはない。
この条項がおかしいと感じたのは日本語にした時、終審という言葉を当てたのがまったくの間違いではなかろうか?
司法試験の受験参考書によりますと、、行政機関による終審裁判の禁止とは?
行政機関も審判の制度として、人事院の裁定、公正取引委員会の審決、選挙管理委員会の決定などが行政機関による審判の制度であるというのが適切で、司法機関にかける前に担当行政機関が迅速に事件の処理にあたることが行政サービスの向上になるという考えだそうです。
難しい法の理論からの説明だそうですが、私は語義をそのままたどり、単なる誤訳であったというほうが論旨明快であろうと思います。
ではそろそろ本日のまとめに入りましょう
嗚呼、日本国憲法は文学的で、人により、時により、さまざまな読み方、感動を得ることが分かりました。
すばらしい文学作品です。
きっといつかはノーベル文学賞候補となるにちがいありません。
でも、このようなあいまいな、矛盾だらけ、混乱のきわみの文章が日本の国家のよりどころであっていいものでしょうか?
ますます、現憲法の価値を疑う私は非国民なのでしょうか?

故事成語ですが、『鼎(かなえ)の軽重を問う』とは権威を疑うとか実力者の地位を覆そうとすること
お待ちください、
私は日本国憲法の鼎の軽重を問うなんてつもりはありません、
だって、私はもともと日本国憲法に権威も認めず、存在意義も感じておりませんので
日本国憲法の目次にもどる