これをお読みになられて、どれが一番英文に近いでしょうか?
簡単な英文ですからみなさん自分なりに英文をお読み願います。
第9条第1項の英語原文にコンマがないために「as means of settling international disputes」が「war以下の全体」にかかっているのか、「the threat or use of force」にのみかかっているのか私には分かりません。かかり方によっては上記現行憲法かおばQ訳のいずれかになります。
しかし、
そのため、日本のわたしたちは、戦争という国家の特別な権利を放棄します。
国と国との争いを解決するために、武力で脅かしたり、それを使ったりしません。
「やさしいことばで日本国憲法」訳
ではないことは明らかです。
参考までに、
総司令部の原案はなんども見直されましたが、マッカーサー草案では下記のとおり、
War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means of settling disputes with any other nation.
「国家の権利である戦争を放棄する。他国との紛争解決の手段として武力による威嚇やそれを行使することを放棄する。 」となり、現行憲法の意味とはかなり大幅に異なりますが意味は明確です。
このばあいは「やさしいことばで日本国憲法」訳とほぼ同じになります。
ダグラス・ラミスさんは日本国憲法ではなく、マッカーサー草案を翻訳したのかしら? 
『この本の第9条第1項の訳文は間違い!である』 ということにご同意いただけるのではないでしょうか。
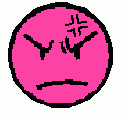
形容詞句がどこにかかるとか形容詞句の意味がどうであるという神学論争は皆さんご存知である。しかし、
形容詞句を別の文章としてしまうという裏技を私は未だかって見たことがない。
句読点、ピリオドを自由にいじるならば、これはもう翻訳とは言えない。
これは翻訳ではなく本厄であろう。お祓いを受けないとたたりがありそうだ。
冗談抜きに、このような解釈を国会でしたならば翌日は新聞・テレビが袋叩きにするだろう。
この訳文を読むと、過去半世紀にわたる神学論争でさえ十分価値のある議論であったとさえ思われてくる。内閣法制局、各政党の解釈いずれにしてもこの翻訳文よりはずっとまともであり、論理的である。
これは誤訳という範疇
(はんちゅう)ではない。意訳であろうが原文の意味をそのまま訳したという意味の意訳ではなく、個人の意思を示すという意味の意訳であろう。
異訳かもしれない。
著者はどうせ日本人は英語が分からんだろうと甘く見ているのでしょうか?
残念ながら、ISOの世界で生きている人間にとって、このような意訳は生理的拒否反応を起こしてしまうのです。
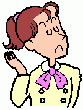
この訳文
(?)を子供があるいは大人でも読んで、日本国憲法の本来の意味はそのようなことだったのかと信じたらこれはえらいことである。
PL法
(製造物責任法)で訴えねばならない。
この文章だけなら「ああ、間違いか?」と流してしまうこともある。しかし「解説」で著者ダグラス・ラミスという方が次のように書いている。
第9条は、おそらく、これまで存在したどの文書にもまして読み間違えられてきた。言語的にはなにもむずかしいことはない。
ということはこの第9条第1項の記述は間違いではなく、確信して書いているのである。
私はダグラスさんと面識はないが、きっと英語が得意ではないのであろう。

主義主張や思想ではない。彼は、文章の理解を完璧に間違えている。
それとも自分の主義主張のためならば句読点もピリオドもずらしたり、形容詞句を独立させて二つの文章にしたり自由気ままにふるまえるとお考えなのだろうか?
もはや論ずるまでもない。
では第10条以降はどうなのであろうか?
まあ私はこれほど大きな瑕疵がひとつでもあればもうたくさんですね、

この本の初版は2002年11月で第二版は2003年1月、それ以降は重版されていないようだ。幸いなことである。
このような誤訳がまかり通っては大変なことになってしまう。
本日の結論
日本国憲法を解釈するには、句読点やピリオドを動かしてはいけません。
まして形容詞句を別の文章を分けたりすることはまかりなりません。
私は952円をどぶに捨てたようです。
|
オレンジ様よりお便りをいただきました。(2004.01.11)
2,3ヶ月前にこのホームページを知り、「一日1ページずつ見よう」と思っても、おばQさんの更新が早くてなかなか全部見きれません。(涙)でも、いつか読破します。
今日は「やさしい言葉で日本国憲法」をみてのお便りです。
僕は小説を読むのが苦手で、「読書感想文」の宿題を出されて以来見ていません。ただ、法律の本を読むのは大好きです。
ちょっと思ったのですが、本当はおばQさんが読んだこの本は、952円の価値があったのではないでしょうか?
僕は法学部生として、正義を愛しています。悪が大嫌いですが、悪と闘うことが好きなので、悪との出会いはすきなのです。
少し話がずれましたが、このホームページを批判する人がいてもおばQさんは一歩も引きません。そんな批判に対しておばQさんは楽しんでいるような気がします。
だからこの本との出会い、批判する人とてもいい経験かなと思いました。・・・・。
でも、952円は高いかな(笑) オレンジ
|
オレンジ様、お便りありがとうございます。
おっしゃるとおりです。いろいろな実験などをしておりますと「何も起きない」ということも非常に価値のあるデータです。
952円を使って「価値がない」ということを確認したわけで十分元は取ったということですね 
オレンジ様がおっしゃったことで1点大きく異なることがあります。
私は気が小さく(ほんとうですよ)  私の書いたものにコメントを頂くとそりゃナーバスになってしまいます。
私の書いたものにコメントを頂くとそりゃナーバスになってしまいます。
でもご批判が私を育ててくれる、親切に内容を検証して正否を教えてくれていると信じております。
いかなるコメントにも無視したり揚げ足をとるような回答をしたことはありません。・・・・というつもりなのですが・・・・
|
すずき様よりお便りをいただきました。(2009.06.26)
題名:やさしいことばで日本国憲法についてです。
現行日本国憲法及びおばQ殿の訳は、as means of settling international disputesが貴殿のいうような「第9条第1項の英語原文にコンマがないために「as means of settling international disputes」が「war以下の全体」にかかっているのか、「the threat or use of force」にのみかかっているのか」のどちらの解釈にもなっておらず、おばQ殿の主張が誤っているところです。現行日本国憲法及びおばQ殿の訳は、renounceにかかると解釈してしまっているのです。もし仮に英語原文が次のような英文だったのであれば現行日本国憲法及びおばQ殿の訳は正しい訳となります。
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people, as means of settling international disputes, forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force.
結論として、マッカーサー草案と第九条の英語原文は同じことを言っており、要は、
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce:
a) war as a sovereign right of the nation, and
b) the threat or use of force as means of settling international disputes.
ということです。言語的に難しいところはありません。
日本のわたしたちは、戦争という国家の特別な権利を放棄します。国と国との争いを解決するために、武力で脅かしたり、それを使ったりしません。「やさしいことばで日本国憲法」訳
であることは明らかです。
|
すずき様 お便りありがとうございます。
私は英検2級、TOEIC600点台半ばでして、まったくもって英語がわかりません。
まあ、間違いがありましたら、お許しください。
ただどー考えても、該当文章はワンセンテンスでツウセンテンスじゃありません。
そりゃおお違いです。
それについてはいかがなのでしょうか?
そんなの文章の意味に関係ないなんておっしゃっては、もう論議以前ですが?
|
向井様よりお便りをいただきました。(2010.05.07)
憲法9条の「誤訳」問題
はじめまして。
ラミスさんには沖縄でお会いしましたが、英語を母国語とする人であんなに自然な日本語で議論をされる方は珍しいと思いました。ラミスさんの書かれた著作を探していて、この果敢な議論に遭遇。私も原典を読み直し、大変なことに気がついてしまいました。現行訳が誤りだと思います。
文を分けたのはわかりやすくする手法として翻訳業界でも禁じ手ではありません。特許関係は別として。法律や契約書の正式な訳文でも文を分けることはしないと思います。ただ、ラミスさんは正規訳の対案として書いたわけではないので、そこはこの場合本質的な問題ではないでしょう。
結論:修飾関係を吟味すると 「 <A:国権の発動たる戦争>と<B:国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇およびその行使>を永久に放棄する。」となってます。ラミスさんは「Aを放棄する。Bも放棄する」と言っているので、「AもBも放棄する」という原典の意味を変更してはいません。
現行訳はBの修飾語「紛争解決の手段としての」をAの被修飾語にまでかかっているように解釈した点が誤りだと思います。現行訳だと「紛争解決の手段としての戦争」でない戦争はしてもいいように読めますが、そうではない。国家による暴力の発動を一切禁じているのです。英語圏の人が感嘆するわけです。単に侵略戦争を放棄する憲法ならたくさんありますから。米国憲法もそうですから、イラク戦争を批判する人たちは憲法違反だと言っています。
お陰さまですごいことに気がつくことができて感謝します!!
|
向井様 お便りありがとうございます。
私の英語の力は中学生並みあるいはそれ以下であることをまず申し上げておきます。
しかし、私はISO審査というものに関わっており、これが残念と申しますか英語が基準になっております。日本語に訳したものがJIS規格になっているのですが、解釈がもめた場合あるいは日本語で分からないときは英語を基に判断することになっています。まさに日本国憲法のようです。
ご異議ある前に申しますと、昭和30年頃までは六法全書には必ず英語の日本国憲法が載っていて、判断解釈に苦しむ場合は英語を基本としたのが事実です。ですから現在でも解釈は英語を基本とすべきと考えております。
それはともかく、ISOの世界ではそういうことですから、文章を分けたりすることはご法度です。ですから元の意味が同じであろうとなかろうと、文章を分けたりすることは生理的に受け付けないのです。
すみません、これは主義思想とは関係ないことです。右派が訳そうとそういう意訳は私は断固拒否します。
それだけのことです。
向井様のお便りに大変感謝しております。
再拝
|
向井様よりお便りをいただきました。(2010.05.08)
佐為様
ラミス訳に対して、ISOの世界のやり方と違う、という批判は成り立つかと思います。
なので佐為様個人の立場の表明については了解しました。世間一般にとってそれがどれだけの意味があるかはまた別問題でしょう。
一方、ラミスさんが原典の解釈を間違っていないのも事実です。
現行の訳と佐為様の訳が間違いと思います。この点についてのご意見がないのは残念です。
ISOの世界のやり方で訳すと次のようになるのではないでしょうか。
「国権の発動たる戦争及び紛争を解決する手段としての武力による威嚇ないしその行使は、これを永久に放棄する」
つまり、もっと簡単にいうと
A.戦争
B.(戦争以外の)武力による威嚇・武力行使
の2つともダメ!と言う構造になっています。いかがでしょうか?
|
向井様 毎度ありがとうございます。
論点がいくつかあります。
私がどう思うと残念ながら世の中には影響を与えることができません。それはともかくISOの世界とか技術的な翻訳の世界ではこのようの翻訳は相手にしてもらえないという業界(?)の認識があると受け取ってください。
二番目の点は私はどちらもだめと訳しています。つまり現行憲法と私の読み方は違います。再読してご確認ください。だから結果とすればラミス氏と私は同じなのでしょう。但し「as means of settling international disputes」がどこまでかかっているのか私の英語の力では分からないと書いております。
ラミス訳について言えば
そのため、日本のわたしたちは、戦争という国家の特別な権利を放棄します。
国と国との争いを解決するために、武力で脅かしたり、それを使ったりしません。
どう考えてもこのツウセンテンス分の単語数が原文にありません。単語の数を数えて、一語一語対照を確認してくださいよ
私が 「ダグラス・ラミスさんは日本国憲法ではなく、マッカーサー草案を翻訳したのかしら?」 と書いたのは、マッカーサーの原文がラミス氏と同じく文章構成がツウセンテンスだからそう書いたのです。
ともかく意味が私とラミス氏が同じでも文章構成としてはラミス訳は完全な間違いだと確信しています。あるいは翻訳としてはラミス氏は間違いでしょう。
超訳とか最近は超意訳とか題している翻訳本もあります。そういう類と思います。
日本国憲法の目次にもどる
 やさしいことばで日本国憲法 2004.01.11
やさしいことばで日本国憲法 2004.01.11
形容詞句がどこにかかるとか形容詞句の意味がどうであるという神学論争は皆さんご存知である。しかし、形容詞句を別の文章としてしまうという裏技を私は未だかって見たことがない。
この訳文(?)を子供があるいは大人でも読んで、日本国憲法の本来の意味はそのようなことだったのかと信じたらこれはえらいことである。
私の書いたものにコメントを頂くとそりゃナーバスになってしまいます。
