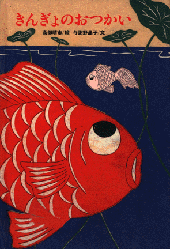| 第3回 「金魚のお使」電車路線マップ |
| 薄緑色の新しい芽が木々に息吹きはじめ、桜も満開。心地よい季節がやってまいりました。 散歩にはもってこいの季節ですよね。−が、しかし。 編集部員は今回、春だ、花見だ、酒盛りだあ〜、と浮かれてしまい、お約束の3月末までに、お散歩コースの写 真をとってくるのを、ついうっかりと忘れてしまっておりました。 で、突然ではありますが、今回は「机上散歩」をご紹介することにいたします。 歌人与謝野晶子の童話「金魚のお使」の金魚たちが乗った電車の路線を探る机上散歩です。 まずは、新宿の停車場(ステイション)から出発です。 |
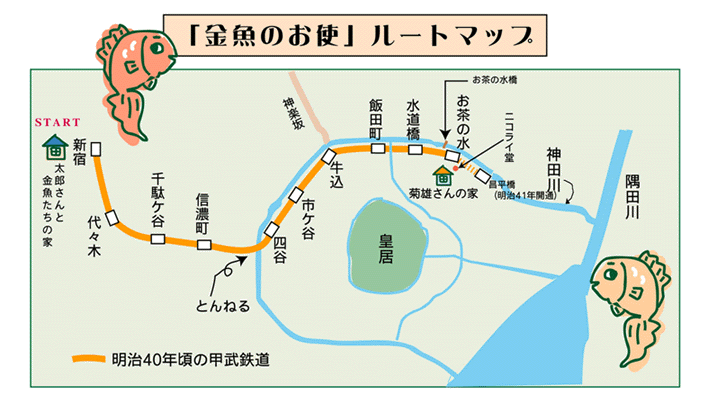 |
| 報告その1 母・与謝野晶子が書いた童話「金魚のお使」 |
|
「金魚のお使」は、歌人与謝野晶子が初めて発表した童話で、1907(明治40)年6月に発行された雑誌「少女世界」に初出掲載されたもの。雑誌では晶子の子どもの名前がそのまま使われたが、その後、童話集『おとぎばなし少年少女』(1910(明治43)年)に収録された時には別
の名前にするなどの変更が加えられた。 |
| 報告その2 高部晴市の絵本版「きんぎょのおつかい」 |
|
|
初めて部員が「金魚のお使」を読んだのは福武文庫に収録されていた文章だけのものだったが、現在は架空社さんから出ている素晴らしい絵本で楽しむことができる。 高部晴市氏の絵による『きんぎょのおつかい』である。高部氏のレトロな絵の感じが、まことに話にぴったりあっている。絵のポイントに用いられている赤色と群青色は、明治時代の錦絵のきつい原色を思わせつつ、地色の生成のような色がそれを柔らかく押さえている。うーん、うまい、と思わずうなってしまうような絵本なのだ。 文字だけの「金魚のお使」は、和泉書院刊の『金魚のお使』与謝野晶子童話集が入手可。文字だけの『金魚のお使』を読んで、その後絵本版を読んでみるのもまた面 白い。 |
| 報告その3 金魚たちが乗った「甲武線」ってどんな電車? |
| さて、「金魚のお使」で金魚くんたちが乗るのは「甲武線」である。この甲武鉄道(今の中央線の前身)は、新宿ステーションから立川・八王子までをつなぐ鉄道として、1889(明治22)年に開通
した鉄道だ(明治36年には甲府まで開通)。 甲武線はまた、新宿から都心へ向かう線路も徐々に延ばしていった。明治27年には牛込駅まで、28年に飯田町駅、37年にお茶の水駅、41年には昌平橋(現在の秋葉原付近)まで、神田川沿いを走る鉄道線が延長されていった。 つまり「金魚のお使」が書かれた明治40年には、まだお茶の水駅までしかなかったんですね。 そして、1904(明治37)年、甲武鉄道・中野−飯田町間では、汽車ではなく電力で走る“電車”の線が開通 した。 電車の車両はマッチ箱のようなかわいい1両編成。 金魚くんたちが乗ったのは電車開通3年後だが、当時はまだ、電気は恐ろしい、というイメージがあったのだろう。「電車は恐いものだってね」とか話しあっているさまは、現代に読むとほほえましいのだけれど。 甲武鉄道の開通 当時(明治22年頃)、乗客のほとんどが子供たちだったという。汽車が赤坂離宮下のトンネルに入ると「ワーッ」と叫び声があがり、トンネルの真っ暗ななかでは声をひそめ、出口の光が見えると、また歓声が上がったという(「大東京繁盛記」宮島資夫著より)。昔も今も、子供はトンネルを抜けるあの不思議な感覚が大好きなのだ。もちろん金魚もね。 |
| 報告その4 金魚がお使いに行った甲武線ルートのいま・むかし |
| ●新宿(出発周駅)
明治後期の新宿駅辺は宿屋や遊女屋が建ち並ぶ、東京郊外の宿場町だった。しかし交通 の便がよくなるにしたがって、次第に町は華やかになり、住宅も増えていった。 金魚くんたちがまず向かった当時の新宿ステーションはどんなだったのだろう。新宿駅は、ちょうどその前年1906(明治39)年に拡張工事が終わったばかりの新築の駅舎で、洋式の大屋根を持つ立派な建物が完成していた。高部氏の絵本「きんぎょのおつかい」に描かれた「えき」にイメージは近いが、本ものはもっと大きかったようだ。 ●代々木 代々木から牛込までの開通は、1895(明治27)年。 ●千駄ケ谷 ●信濃町 ●四ツ谷 “白”がぐうぐうイビキをかいて寝てしまうトンネルのある場所。現在のJRの四ツ谷−信濃町間にある、迎賓館の下をくぐるトンネルと同じ? ●市ケ谷 ●牛込 現在の駅名に「牛込」はない。当時の駅は、現在のJR飯田橋駅の神楽坂寄りにあったが、1928(昭和3)年に廃止された。ここで下車すると神楽坂はすぐ目の前。三味線の音が路地から流れる遊興街へと誘われる御仁も多かったのでは。 ●飯田町 「飯田町」も「牛込」と同じく今は存在しない駅である。現在の飯田橋駅の水道橋寄り、ホテルエドモントの裏手あたりに位 置していた。飯田町駅は1928(昭和3)年に旅客廃止され、その後貨物専用駅として利用されていた。しばらく前(だいぶ昔)までは本線からちょっとずれた場所に引き込まれている線路があり、総武線の電車の窓から「飯田町駅」という看板だけ見ることができた。現在はそれもなくなって開発地区となり、大きなビルが建設されている。 ●水道橋 ●お茶の水(終点) −電車はお茶の水の停車場へつきました。 「赤さん、彼処で人が身体を半分水へつけて何かをとつて居るが、あれは何なのだらう。」 白がかう云ひますと、 「あれはね、僕達の御馳走のぼうふらをとつて居るのですよ、金魚屋のお爺さんがよくくれたね、あれだよ、此の辺でとるのと見えるね。」と赤は云ひました。 「景色の好い処だねえ。」斑はかう云ひました。− 現在のJRお茶の水駅の出口は、お茶の水橋側と聖橋口側の2つ。駅を挟むようにして神田川にかかっている2つの橋のうち、お茶の水橋の方に当時の甲武鉄道・お茶の水ステーション(明治37年に完成)があった。美しいアーチの聖橋ができたのは1927(昭和2)年なので、金魚くんたちが見たのはお茶の水橋だけ。お茶の水のシンボル・ニコライ堂は1891(明治24)年に完成。順天堂病院は1903(明治36)年に建っている。 都心には珍しい渓谷美が楽しめるお茶の水は、当時東京名所の1つだった。なにせ金魚くんたちが「遠足」に来たがるくらいの「景色の良い処」なのである。昔の写 真を見ると、荷を運ぶ舟が行き来する神田川の土手は緑につつまれ、橋の向こうにはニコライ堂の銅板づくりの美しい塔がそびえている。橋下を流れる神田川は自然そのままのきれいな流れで、貝やドジョウなどを取る人たちも多かったのだろう(さすがに金魚の好物“ぼうふら”を取っている人はいなかったと思うけど)。 |
| 今回の机上散歩、お楽しみいただけたでしょうか。 5月3日発売の月刊MOEでは、「旅の達人」というテーマの絵本キャラクターベスト5にこの金魚たちが入る予定だそうです。 絵本の中で奔放に活躍するキャラクター達を楽しく紹介する、MOEのこのコーナー。 ぜひ、見てみてくださいね。 次回は、横浜をご紹介する予定です。 神奈川近代文学館の「子どもの本の世界展」を鑑賞した後に散策できる近辺のコースを紹介したいと思っています。 4月10日-15日頃アップしますので、どうぞお楽しみにっ。 第3回の机上散歩の執筆にあたっては、以下の資料を参考にしました。 参考資料 ●「日本児童文学大系 与謝野晶子」ほるぷ出版●「きんぎょのおつかい」高部晴市・絵/架空社●「与謝野晶子の童話「金魚のお使」考 ―初出誌「少女世界」と『少年少女』の異同を中心に― 」梅花女子大学大学院 古澤夕起子著●「新宿の今昔」芳賀善次郎著/紀伊國屋書店●「写 真集 山手線」毎日記念誌出版会/立風書房●「東京・市電と街並み」林順信著/小学館●「新文芸読本 与謝野晶子」河出書房新社● |
●このページのTOPに戻る●児童文学散歩の目次へ●
●HOMEへ戻る●