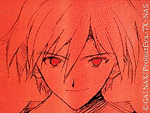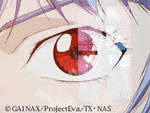しかし、「この私」は、様々な関係を結ぶにつれ、いろいろな「記号」を与えられていき、「私」はどんどん膨れ上がっていきます。
膨れ上がった「記号」が「この私」を次第に圧迫します。
たとえば、誰にでも愛されたくて、誰にでもいい顔をしようとすると、すぐにつじつまが合わなくなり、どこか無理をしなければならなくなり、だんだん自分が苦しくなりますよね。
与えられた「記号」に合うように「この私」を統一し続けるのが苦しくなるというわけです。
そうなると、だんだん、与えられた「記号」は本当に「この私」なのだろうか、という疑問を持つようになります。与えられた「記号」をもっともらしく見せていた根拠が、だんだん疑わしくなってきます。
だから、「この私」は、「私」を成立させてきた「記号」やその根拠を、それを「この私」に与える(あるいは押しつける)他の人間を、そして、そうやってできた「私」を、疑うようになるわけです。
あらゆる物事を「思いこみ」として疑うところから出発するわけです。

碇シンジは、「エヴァのパイロット」という「記号」を与えられ、それに基づいて自我を形成する。
が、それは疑わしい「記号」である。
しかし、「私」を周りの人々、特に、彼を「見捨てた」父親に認めてもらうためには、その「記号」に基づいた自我を「私」とするしかない。
このダブルバインドがシンジを苦しめる。