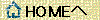
|
自由だからこそ戦術が選べる 一般には戦略が大事だと言われますが,戦略を具体的に遂行する戦術も重要です。私の場合は,戦術を良く練らなかったために総仕上げが出来たのは本試験3,4日前になってしまい,綱渡り的な直前期の過ごし方をしてしまいました。そんな状況で合格できたのは試験制度の改正による影響と運が良かったとしか言い様がありません。 この教訓を生かすために,戦術について考えてみました。 戦略と戦術 戦略とは大局的な計画のことです。独学を選んだあなたは,すでに戦略は決まったも同然です。いつまでに基本事項のインプットを終了しいつから最後の仕上げに入るのかは,各自の制約条件に従っておおよそ見当がついていることと思います。これについては,期間と日々の勉強時間という2つの条件しかないのであれこれ悩んでも仕方がありません。 問題は戦術です。戦術とは戦略を達成するための具体的方法のことです。この戦術については独学者は不利な状況にあります。専門学校生に比べて制約条件がある中で彼らと同じ戦術をとっては負けるに決まっているのです。 だからこそ戦術が重要なのです。 戦略確認 念のため戦略を確認しておきます。最終的に本試験2週間前までに総仕上げに入ることです。ここで重要なことは合格に必要な分だけ仕上げるということです。決して完璧を求めることではなく,本試験で余裕を持って合格できる70%の正答率を目指すことです。この戦略を忘れると戦術において大きなロスを生むことになります。 個別問題戦術 いよいよ戦術を練ります。本試験2週間前までに70%の正答率を得るための戦術です。 私の経験から言えば,インプットに時間をかけるのは得策ではありません。独学者にはインプットした情報を確認する手段が無いに等しいからです。前回の内容を確認するミニテストの類が無い・授業で折に触れて関連事項の確認をすることが無い等,専門学校でとられているであろう方法が利用できないのです。 それに代わる独学者の効率的手段は,問題集を解くことしかありません。アウトプットしながらその都度不足分をインプットすることです。しばらくしたら再びアウトプットし,前回のインプットが身についたかどうかを確認する作業を繰り返します。 独学者の理解度の確認は,結局アウトプットしかないのです。当初は基本書2:問題集8位の割合で学習しても問題無いでしょう。基本書は自分に問題意識が出てこないと殆ど目の前を通り過ぎていくだけです。専門学校の講義では重要部分を強弱をつけて講義してくれますが,独学では目にするもの全てが重要に思えてしまいます。まずは今自分に必要な知識を選別するために問題を解くことが先なのです。 具体的には,問題集の単元毎に正誤を書き留める表を作り,そこに記入して行くことです。間違えたところの知識をインプットして問題を見直してください。次に時間が許せばすぐにその単元をもう一度解いて下さい。 この2回の解答で両方とも間違えたところは,読んだだけでは理解できないあなたの苦手項目なので,印をつけるか別のノートに記録してください。苦手項目はまだこれ以上手をつけてはいけません。 両方とも解けたところは,一応現段階では理解していると思って良いでしょう。しかし,学習が進むにつれて混乱して間違えないとも限りません。とはいえ,まだこの段階ではそのままにしておきましょう。 1回目に解けずに2回目に解けた個所は,今回あなたがマスターした個所です。ここは重要ですので専用のノートに内容を記入しておきましょう。(ノート作成のヒント) さて,仮にあなたの1回目の正答率が50%だったとします。2回目の正答率が80%だったとしたら,次回あなたの目指すこの単元の正答率は80%に決定です。 この作業を初回は法令なら法令全部(憲法〜諸法令)終わるまで先に進んでください。この作業は,どんなに時間が掛かってもどんどん先に進んでください。安く早くという観点からは法令で1ヶ月以内に終わらせてください。苦手項目だらけでも気にせず先に進んでとにかくこの作業を終わらせないと先に進みません。 作業が終わったら,インプットせずにもう一度問題を解きましょう。目標正答率に達したかどうかを判定します。多分目標正答率に達していないことと思います。たとえば,初回正答率50%で目標正答率80%・今回正答率70%であれば,あなたは30%分前回マスターしたのに20%分しか覚えていないことになります。これを学習の歩留まり66.6%と呼ぶことにしましょう。(このとき初回に正答したのに今回誤答した問題は前回マスターした項目を記録したノートに記入しておきましょう。) この段階で,少し焦ることと思います(焦ってください)。残りの期間はこの学習の歩留まりとの戦いと苦手項目の克服の2点に時間を費やすことになります。
|
|
|