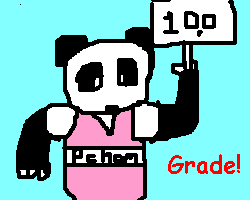
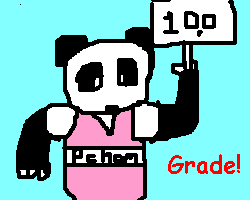
監督 スティーブン・スピルバーグ 主演 トム・ハンクス、トム・サイズモア、エドワード・バーンズ、マット・デイモンほか
(10月1日までの採点は、『プライベート・ライアン』、
10月8日までの採点は『プライベート・ライアン(2)』
に掲載しています。まず最初に、そちらをごらんください。)
じゅんこ(10月12日)
junko003@eis.or.jp
プライベート・ライアン(追記) ごめんなさい。みなさんの意見をよく読まずに安易に感想を述べていたようで、あらためて読みかえしましたので、ちょっと追加で書かせてね。またまたパンちゃん(10月12日)
(といっても3ページもあるもんだから全部は結局読み切れていないのだ。気を付けないとディベートとは時に、解決へ向かうのではなく「自分がいかに正しいか」の証明に走ってしまう危険性を秘めているのです) 戦争は無意味か、という点について。
個人的には無意味であると考えます。もちろん、先日の「テポドン事件(なんだかマヌケだぞ…)」以来、自分の生活を自分で守ることの必要性というもの(そして独立国としてのプライド…アメリカは突如「ミサイルだというのは間違い、あれは衛星の打ち上げだった」と発表し、その後、一切情報公開をしようとしませんが、北朝鮮との間で何らかの取り引きがあったのだろうとささやかれているようです。日本のことは日本で守れといわれるけれど、日本に偵察衛星を持つことも許されていないでしょ。それでいて日本の安全に関わる情報をもみ消してしまうアメリカも失礼だけど、日本政府は何をしてるの〜。日本が独立国家だなんて幻想なのね)をひしひしと感じる今日この頃ですが、それでも敢えて戦争反対、と言いたい。私は戦争経験なんていらない。心に大きな傷を作るような悲惨な体験はしたくないし、させたくない。ベトナム戦争にいった兵士の精神を切り刻んだのは、正義がどうこうというイデオロギーの問題ではなく目の前で人が殺されていく悲惨な戦争体験そのものだったのでは?そこをスタート地点にしたい。
これはある雑誌の受けうりなんですが、私も今日のアメリカに「正義の暴走」を感じる。クリントンのセックス疑惑の過熱報道にしろ、先日のスーダン攻撃にしろ、自由と民主主義という理念があれば何をしてもいいのかしら?私がここで言いたいのは、実際に軍で働いている人々を非難しろ、ということでも、アメリカの正義が間違っている、ということでもなく、あくまでも「戦争は悪である」ということを誰かが言い続けなければならないということです。「戦争は避けるべき最悪の事態」だと言い改めるべきかも。とにかく正義の名の元での暴走を差し止める力として、異なる意見が必要なのでは?色々な見解が拮抗し、牽制しあい、互いの暴走にストップを掛けているというのが理想形。そして反戦を訴える手段として映画は非常に有効な媒体であると思う。
それにしても、もし『プライベート・ライアン』が本当に反戦映画を目指すのなら、やはりラストシーンは必要なかった。マヌケというレベルを通り超して本末転倒だとさえ。アレックスのパパさんが解説されていたEarn this.のセリフがなんだったのかと思わざるをえません。高校教師で愛妻家だったハンクス(役名失念)が死んでまで敬礼されたいなんて思うでしょうかね?
ここまで書いてバレバレかと思うのですが、予告編採点に文句を書いたトム・ハンクス、予想に反して私の中では評価が上がりました。反対に自分の役がなんなのか理解していたのか怪しいマット・デイモンの評価は下がったんだけど…(いや、あれは脚本と演出のせいか…)
あるビジターから、この欄について、きつい非難を受けた。(ビジターのことばを直接転載することができないので、いかに書くことは私の誤解を多分に含んでいると思う。そう思いながらも、書かずにはいられない。)じゅんこ(★★★)(10月11日)
ここで展開されている『プライベート・ライアン』についての感想は、「映画」そのものについて語っているのではなく、「映画に関する話題」である。「映画に関する話題」で『プライベート・ライアン』を評価するのは間違っている、というのである。
そのビジターによれば、この映画は映画として絶対的に優れている。映画としてのキレがある。それは「結論」であって、それを認めないのは、映画を見ていないからだ。映画を見ないで、「反戦」のメッセージだけを受け取ろうとして受け取ることができず、それが気に食わなくて『プライベート・ライアン』を批判しているだけなのだ、とそのビジターは主張する。
そのビジターはまた、私がこの欄で、『プライベート・ライアン』批判の「署名集め」(反戦メッセージを含まない映画批判の署名集め)をしている、とも非難している。
私は、この欄で『プライベート・ライアン』について話題になっている、意見を聞かせてください、と何人かに直接呼びかけ、また幾つかの掲示板にも書き込んだ。しかし、私は「あなたの反戦メッセージを聞かせてください」と依頼したことはない。
そのビジターにとっては「映画に関する話題」で、『プライベート・ライアン』を汚す(?)ことが我慢がならないのかもしれない。
しかし私は「映画」と「映画に関する話題」を区別することはできない。
ノルマンディー上陸作戦の描写を見て、それを悲惨だと感じる、悲惨だと感じ戦争はいやだと感じる。そこから「戦争反対」という思いを強くし、何事かを語る。それはこの映画の勝利である。
あるいは、この描写を見て、私たちの今の自由は、こうした多くの犠牲の上に築かれたものである、と感じ、そうした犠牲者に対して敬意と感謝を感じる。それは同様にこの映画の勝利である。
どちらの側の感じ方が正しいか、など誰にも言えない。それはその人の信条の問題であり、その人がこれからどう考え、行動して行くかということの問題だ。
「映画」を離れ、個人の問題に変化して行くから、それは「映画の問題」ではなく「映画に関する問題」だと、たぶん、そのビジターは主張するのだと思う。
しかし、そんなふうに何もかも引き寄せてしまうものが「映画」なのではないか。「芸術」なのではないか。
あるシーンが映像的に迫力があり優れている、あるシーンの音響の使い方が優れている、あるシーンは過去の映画のこのシーンの引用である、このシーンの映像によってこの映画は新しい映像の可能性を切り開いた、この映画は映画史のなかでこのような位置を占める、このシーンの映像はハンディカメラで撮っている、この俯瞰シーンはクレーンで撮っている、このシーンのスローモーションは効果があるなどと分析し、評価することだけが「映画」を見るということではないだろう。それだけが「絶対的に正しい映画の見方」とはいえないだろう。
映画を見て感じたことすべてが「映画」そのものである。
『プライベート・ライアン』を見て、反戦メッセージが不十分であると感じるにしろ、戦争の犠牲者に対する追悼の思いを強くするにしろ、それは、この映画を見たからである。そうした思いは観客のこころのなかに潜んでいたものであり、この映画が引き出したものなのだ。
こころに潜んでいたものは、徐々にしか語ることができない。たとえば「反戦メッセージが不十分である」あるいは「戦争犠牲者への追悼を感じる」。その感じ方はたぶん観客がそれまでどのような社会の中で生きて来たか、どのような戦争観が支配的な社会で生きてきたかということと関係すると思うが、そのビジターは、そうした無意識的なところから映画を語るのは「映画を抑圧する」ことだ、そうした反応は「既成のことば」で「映画を抑圧する」ことだ、とも言っている。映画は、そこに「ある」ものとして、絶対的存在として見つめなければならない、そうしないのは「映画への抑圧」であるとも主張している。
しかし、そんな超人的な見方は私にはできない。多くのビジターもできないと思う。衝撃的な映像を見れば、無意識的に反応する。そのときのことばは「反戦メッセージが不十分」とか「戦争犠牲者への追悼」とか、たしかに「既成のことば」かもしれない。これは仕方ないことではないか。自分のなかで起きた突然の衝撃をオリジナルなことばで語ることのできる人間などほとんどいないと思う。自分の知っていることば、自分が聞いてきたことばを手掛かりに語り始めるしかない。
自分で語り、他者の語りを聞き、少しずつ自分の考えを見つめなおしていく、そうすること以外に、どんなことができるのか私にはわからない。
映画にしろ、他の芸術にしろ、観客(鑑賞者)に衝撃を与え、様々な反応を引き出す。そうして引き出された反応そのものが、本当は「映画」そのものより大きいし、実はそれこそが「映画」でもありうると思う。「映画」を映像のキレだとか音響だとか、映画史の位置づけだとかに閉じ込めるのは、私に言わせれば、映画の矮小化である。
『プライベート・ライアン』の上映時間はたかだか3時間である。フィルムのなかの世界は3時間で終わってしまう。しかし、それを見たものの思いは3時間では終わらず、様々な形で続いて行く。その思いは「映画」のように終わりがあるわけではない。結論があるわけではない。また、その思いは、「映画」のように目に見える形でくっきりと存在するわけではない。ああでもない、こうでもない、と形を変えながら存在し続ける。そうした不定形の思いこそ、大切なものだと思う。不定形の思いのなかで、私たちは何度でもその映画に出会う。
映画について、何度も何度も語る。そのたびごとに、思いのなかで映画は生き続ける。よみがえり続ける。そのよみがえりこそが「映画」そのものである。スクリーンに写っている影は「映画」の一部に過ぎない。
『プライベート・ライアン』を通して、戦争に対する思いを語ることを、そのビジターは「映画に関する話題」と呼び、それを語ることを「映画に対する抑圧」と呼ぶ。
しかし、この映画を見て、戦争についての思いを語ること以外に何か必要なことがあるだろう。戦争と結び付けずに何事かを語って意味があるだろうか。
スピルバーグはどう思っているか知らないが、こうして語られていることは、それがどんなにスピルバーグ批判、あるいは『プライベート・ライアン』批判を含んでいようが、この映画の勝利である。この映画は私たちに、何度も何度も語り合うことを強いている。戦争について語り合い、考えることを強いている。そうした力を持っている。
こうしたことを語ることは、「この映画は20年に1本の傑作である」と「結論」づけるより大切なことだ。
*
「映画」自身について。
私は前半の30分と後半のライアン救出劇をつなぐものがない、と批判した。前半の30分が8人の行動にどのように反映しているかわからないから、前半の30分のリアルな映像に衝撃を受けるが、真に感動(?)するわけにはいかない、と批判した。スピルバーグはただ、ものすごい映像を撮りたかっただけなのだと感じ、それを不気味だと思うからだ。
私を批判するビジターは、前半の30分と後半をつなぐものなどない、断絶がある、それこそがこの映画のテーマである、と言う。
そのビジターにメールで書いたことだが、私は、実はこの見方こそ、このビジターから聞き出したいことだった。
これは本当にそのビジターが言うとおりだと思う。
前半のものすごい30分の殺戮--その衝撃は救出劇を演じる8人にどのようにも影響しているようにもみえない。それはけっして影響しないのだ。なぜなら、その30分の殺戮の状況は悲惨すぎるからだ。衝撃が強すぎて受け止めることができないからだ。戦争の一瞬一瞬の衝撃は、どう受け止めていいかわからないくらい強烈なのだ。
れいなさんが「銃で打たれると痛すぎて痛みを感じない」というようなことを書いていたが、衝撃は強すぎるとどう感じていいのかわからない。体とこころがそれに反応しないのだ。
スピルバーグは確かにそこまで戦争を直視しているのだと言える。
後半の救出劇にあらわれる断片的なエピソード(トム・ハンクスと友人が語るイタリアの小人、マット・デイモンが語る兄の初体験の笑い話)がえぐり出す断面、戦場にふさわしくない断面、その断絶、そこにこそ確かに戦争の真実がある。今彼らが体験している惨劇はことばにならない。ことばを超えている。語ることができるのは、この惨劇と直接結びつかない過去のことだけである。
人間の意識は、そんなふうにして、やっと耐えているのだ。
それは十分にわかる。わかるけれども、私はスピルバーグのこの映画を評価しない。
その時、つまり実際に戦争を体験しているときはどんなつながりも見いだせないにしろ、どこかにつながり、ノルマンディー上陸の際の衝撃が影響し、彼らの行動を支配していたはずである。それを明るみにだすことこそ映画の仕事だろう。
どのような大事件も、すぐには語れない。そこで起きたことは当事者には断片の寄せ集めにしか感じられないと思う。それはしかし、断片のままにしておくのではなく、何度も何度もつなぎあわせ、ことばにならない形で起きたものを明るみにだそうと努めることが必要なのだ。
あの悲惨なノルマンディーの体験がいったいどのように人間を変えたのか、そのことを描かないことには、この映画は何も描いたことにはならないと思う。ただ、悲惨な状況をリアルな映像と音によって再現しただけの見せ物になってしまう。それでは戦争で亡くなった多くの人に対して失礼というものではないだろうか。こうした思いも「映画に関する話題」であろうが、それを抜きにした「映画」だけの話題など、何か意味があるのだろうか。
最初の30分が8人にどのような影響を与えたか描いていないからこそ、救出されたライアンが救出されることによってどのような影響を受けたかも描くことができないのだと思う。
戦後何十年もたって、やっとトム・ハンクスの墓にやってきて涙ぐみ、「自分はいい人間だっただろうか」というようなとぼけたことしか語らせることができない。彼の受けた衝撃がそんなとぼけた思いしか語れないほど強いものだった、と言えば言えるのだろうが、そんな「断絶」の羅列で、戦争は悲惨なものなのだ、と伝えるのではあまりにもいいかげん、としか言いようがない。
戦争の当時は肉眼で見ていても意識には見えないものがある。見ていながら見なかったものとして意識の奥に隠しているものもあるかもしれない。そうしたもの、深く意識に潜在したものをえぐり出し、物理的現象としての「戦争」を超えたもの、内面の「戦争」の痕跡こそが描かれなければならないと思う。
私が書いているのは、スピルバーグ批判であると同時に、スピルバーグへの期待である。期待があるから批判するのだ。何の期待もなければ批判などしない。
「映画」について語るのではなく「映画に関する話題」を語ることは「映画への抑圧」であるという態度こそ、「映画への抑圧」ではないのか。
「トム・ハンクスのもも、太かったねえ」
「戦争だもん、あれくらい太くないと生きて行けないよ」
「射撃の巧い役者、かっこよかったねえ」
「やっぱり戦場の緊迫感が男を鋭敏に磨くのかしら」
これは、たまたま耳にした、なんだかぶっ飛んだ会話だが、ここにも「戦争」がちらりと影を出している。
語りが始まっている。その「始まり」ということが、私はすごいことだと思う。
人はどこからでも語り始める。語り始めずにはいられない。そうした語りを「映画に関する話題」とくくって、「映画」とは関係ない、「映画を抑圧するもの」と定義付け、「映画」をまつりあげるという姿勢は、私には納得がいかない。
まあまあ、映画を見るまでは…と思ってここを覗いていなかったのですが、すごいことになってますねえ。私なんかたんなる役立たずのOL給料泥棒(むかし入社試験で言われたのね)、私の意見なんて誰が聞きたいかしら?とも思ったけど、一応。
そもそもこの映画が言いたかったのはどっちなのかなあ。
1)戦争は空しい殺し合い。
2)この自由で民主的な世界(ほんと?)は彼等の尊い犠牲の上に成り立っているのだ。
最近程度が低くてこまってしまう雑誌「ニューズウィーク」の論調がたしか2)だったのだ。
個人的にはこの2つのテーマを両立させるべきではないと思う。
1)を訴えたかったのならラストをリンカーンの言葉で締めくくるのは解せないし(それともあれは皮肉な意味合いだったのかな)
2)だとテーマそのものに疑問がある。ようするに冒頭とラストに申し訳程度に描かれた「その後」がなければ良かったのにねえ、というところかな。本当に反戦を訴えるつもりで「その後」を描くのなら、もっとその後の苦悩(多くのベトナム戦争映画が描いてきたような)に切り込むべきだし、そんな余裕がないのなら「その後」なんていらないよね。私の好きな(というか子供心に大変ショックをうけた)戦争映画のひとつに『西部戦線異常なし』というのがあるんです。見た人も多いと思うけれど、ラストシーンで一匹の蝶が戦場に舞降りてくる。銃弾の飛び交うなかで、ふっと何を思ったのか主人公が身を乗り出して蝶に手を差し伸べる。ところが、彼の手が蝶に触れる手前で彼は頭を打抜かれて死んでしまう。それで暗転して映画は終わってしまうの。
子供心にすごくショックだったなあ。
閑話休題。『プライベート・ライアン』に話を戻すと、よく出来た映画であるのは間違いないと思います。ハンクスが戦闘の真っただ中でまるで夢を見ているような、外界から遮断されたような感覚に陥る演出とかオリジナルではないのだろうけれど、素晴しいと思う。ま、全体的にはリアリズムに基づいたアメリカ版「忠臣蔵」とか「百虎隊」って気もしますが…。
ポジティブに評価できるのは、戦争経験(軍隊にいても実践経験のないひとはこれに含む)のない若い人がこの映画を見ることによって「とりあえず戦争は怖い」ということが認識できるあたりでしょうか。特に「戦争=人殺し」の分野についてはハリウッドって未だにマッキントッシュに対するウィンドウズ3.1みたいなもんだからね。批判する前に日本映画にもこれだけの腕力があればと思わなあかんわな。ただ『プライベート・ライアン』を批判するなら『プライベート・ライアン』に勝てるよーな日本映画で対抗するべきなのかも。児童文学にあんなに素晴しい反戦作品があるというのに、それを世界に発信できない日本もなさけないよね。
みなさんの真剣な議論に敬意を表しつつ、なかなか噛み合わない論点が整理できればと思い書き込ませて頂きます。はるひこ(10月10日)
◆"Earn this."について
最後のこの台詞がやはり重要だと思います。
これは、麗奈さんが書かれていた通り、ライアンへ帰郷(君を生きて母親の許へ帰すという自分たちの任務)を促しているのは勿論です。けれども、この"this"は、それの意味を越えて、「連合国、枢軸国、戦争体験世代、非体験世代の区別なく、この血の代償としての平和を受け止めよ」という意味に聞こえました。
主人公達米兵の行動にも、捕虜の一人目を射殺する、戦死者の認識票の扱いに敬意を欠くなど、「絶対的な善」には描かず、逆にドイツ軍に同情的な描写も埋め込んでいるなど、あの大戦を善悪の二分法で描くことから自由になろうという意思を感じました。
ですから、この"this"、つまりこの戦後秩序の恩恵は、現代の日本人、にも受け止める権利があると思います。
更に言えば、その代償としての流血、その犠牲者への追悼には、単に「自由と民主主義」を信じることが出来た連合国の兵士だけでなく、枢軸国、そして非戦闘員の犠牲者への追悼も含んでいると思います。
◆星条旗について
日本に住んでおられる方は、映画の最初と最後に映る星条旗は眩しく、また妬ましいのかもしれません。けれども、逆光ににじんだ、そしてほとんど色彩を失った星条旗の映し方には物凄い覚悟の上での節度というか、深い感慨を覚えました。
無批判な愛国ではなく、理不尽とも言える代償を払い、自身が血で汚れ、常に正しさを問われ続けながらも、近代や自由、個人の尊厳といった価値を信じ、信じるメリットにコミットするものには降ろすことの出来ない旗。そんな密やかなはためき方と思いました。
◆世代ということについて
ご承知の通り、スピルバーグは戦争を体験していない世代です。体験をしていないのに、何故こんな作品を撮るのか?そういう声もあるようです。
けれども、体験をしていない世代の責任ということもあるのではないでしょうか。
体験世代には、直接、間接の生々しい記憶があり、それゆえにどうしても自由になれない限界があるのでしょう。
例えば、日米の戦争の記憶がそうです。アメリカにとっての真珠湾の屈辱。日本にとってはレイテ、沖縄、硫黄島の惨劇。ミズーリ号の屈辱。そして東京裁判。
世代が下り、冷静な歴史評価をしながら、戦後秩序の恩恵を噛みしめることの出来る若い世代にこそ、そうした恩讐の清算をしてゆく責任があるように思います。
昨今の経済の混乱で、またぞろ「アングロサクソンの陰謀」とか「IMFの暴虐」であるとか。自分の非力を知りながら、「近代」にへそを曲げるような惨めな「繰り返し」は恥ずかしいと思わねばなりません。
勿論、「近代」は絶対ではありません。
欧州大陸奪還の戦勝にしても、太平洋戦線の終結のさせかたにしても、「絶対善」などあるはずがありません。けれども、明らかに夥しい血が流れ、その結果としての平和があり、その結果としての現代の我々の生活があるのなら、我々の現在もまた、あの"this"なのです。
◆沖縄からの平和の打ちたてについて
麗奈さん、キリヤマさんの議論。真剣な内容ですが、「上の世代」が犯してきた議論の平行線から逃れられない回路に入る危険を感じました。
小生の拙い文章を、「バーチャル政党、フェデラリスト」の掲示板
http://www.federalism.org/
に掲げていますのでご感想を頂ければ幸いです。
◆印象の深かったシーン
どちらもトム・ハンクスの演技ですが、「大事な人の顔を思い出すには、光景を思い浮かべるのが良いんだ。」と、マット・デイモンに語るところで、奥さんが薔薇の生け垣の刈込みをしているシーンのことを言いますね。それが何故だかは、一切説明がないんです。ただ、その表情と台詞の演技技術が凄いのと、前のレーダー・サイトでの戦闘後の口論を鎮める時に「大勢殺し、部下も大勢失って顔が変わってしまった。もう家内には、俺の顔だって分からないんじゃないか。」という台詞と呼応して、どうしようもなく心に残りますね。
それから、最後に、苦しんでいた手の震えが止まる描写。単なる作為を越えて、気持ちに突き刺さってくる表現です。苦痛からの解放というか。静かな死というか。ハリウッド的なセンチメンタリズムと言ってしまえばそれまでですが、やはり心が震えました。
パンちゃん、お久しぶりです。ななんぼ(★★)(10月10日)
スウィート・ヒアアフターのちゃんとした感想をそのうち書こう思っていたのですが、いろいろ考えてしまうばかりで、なかなか言葉にできません。プライベート・ライアンについても、いろいろ感想があるのですが、そのうち書きますね。
今日は麗奈さんが書いたことの中でちょっと見過ごせないことがあったので、ちょっと発言させて下さい。
麗奈さんが「帰ってきては市民に唾を吐かれるなんて」と書いておられますが、この事については、自分自身ベトナム戦争を戦い、その後社会学者となったJerry Lembckeという人が詳しい調査をし、The Spitting Image: Myth, Memory and the Legacy of Vietnam(New York University Press)という本を書いています。その結論はタイトルにMyth(伝説)という言葉が使われている事からも予想できるように、帰還兵が唾を吐かれるような事件は実際には無かったというものです。自分の友達が唾を吐かれたとか、自分の父親が唾を吐かれたと主張する人はたくさんいたそうですが、よく聞くと「友達の友達」だとか「父親の知人」ということになって、当事者は見つからなかったそうです。もちろん、広いアメリカで一人位そういう経験をした人がいたという可能性までは否定できません。でも一般に信じられていることは事実に反します。
論理的には、反戦運動家と(職業軍人ではない)兵士達が同じ側に立てないことないと思うんですよね。反戦運動家は、戦争によって犠牲者が出ることに反対の立場で、兵士達は戦争の犠牲になる立場なのですから。上に書いたLembcke氏もベトナム帰還兵ですし。でも人間というのは自分のしたことが無意味(場合によっては有害)である事を認めるよりも、それは有意義なことだと思いたいものなのでしょう。それが命を懸けたことであればなおさら。だから反戦を唱える人に反感を持つのでしょう。これは洋の東西を問わず共通しているように思います。
ついでに、もう一言。「友達が死に直面しているのに、おまえのやってることは無意味だなんていえませんでした」というのは僕にはよく理解できない。友達が無意味な事で死ぬのは無念ではないですか?同じアメリカ在住日本人で考えが全然違うのは面白いです。
映画の感想以外のことをだらだらとすみません。感想もちゃんと書きますから。そのうち。
冒頭の残酷な戦闘シーンは前々から聞いていたけど、逆に聞いていなければ本当に耐えられなかったシーンだったかもしれない。それだけ、残酷でとにかくそれしかない場面だった。そして、冒頭でこれだけの殺し合いを見せつけられたせいか、ラストの戦闘シーンには何も感じなかった。ダグラス・タガミ(10月10日)
「殺し合い」に対して完全に感覚がマヒしてしまっていた。なんか、これが「戦争」そのものなのかもしれないと痛感した。
しかし、冒頭などの戦闘シーンのリアルさを強調しすぎたせいか、ドラマ性では何の魅力も感じなかったのは事実だ。たった一人の二等兵の救出のために、なんの関係のない兵士が更に危険な戦地へ赴かなくては行けないのだ。この設定は、たとえ現実のことだったとしても無理がある。無理がある分、緻密な内容を組まなくてはいけないはずなのに、メインは戦闘シーンである。だから、基本となるはずの二等兵ライアンの救出劇は何の意味のないものになっていた。
もちろん、戦争という世界では、どんなドラマをも無意味にし「残酷」というものしか残らない、ということを表しているのかもしれないけど、その割にはラストのライアンのセリフは変にドラマ性を強調していて、今までの戦闘シーンで築いた重厚な雰囲気を玉砕させてしまった気がした。
所詮、アメリカ万歳という作品だったのかな・・・と思った。
そして、ミラー少尉の約1ヶ月半後には、この国は私達の国へ原爆を落としたんだよな・・・と思い、妙に醒めてしまった。ラストのあのセリフがなければそうは思わなかったかもしれないけど。
戦闘シーンをメインにするか、ドキュメンタリーをメインにするか・・・そのバランスが全然なっていなくて、かなりつまらない作品になってしまっていたのが残念だった。
こんにちは。ダグラス・タガミです。長文です。また、また、また、麗奈です(10月10日)
今は、もう一度観たい衝動にかられています。
どうも私には、スピルバーグのねらいは、やはり、オマハビーチの再現が 目的のように思えてなりません。(他の事も書いてと言われていたのに、ごめん なさい。)
彼のメッセージは、「現実の戦争とはこんな事なんだよ。良い悪いじゃなく、 これが戦争だという事をみておきなさい。」と言いたかったのだと、今は考えて います。
ですから、多分、ライアンを救うとか後半の内容は、エンターテイメントとして の 映画を成立させるための方便だったのでは無いのでしょうか。
(オマハの激戦だけだと、ただの再現フィルムですからねぇ。あと、CMもライア ン救出 を前面に出してるのがおかしすぎる。わざと、オマハのところを表に出さない ように して口コミでオマハのシーンの衝撃を伝播させているような気がする。) 戦時中の記録映画もいろいろ見てきましたが、自分がその中にいるような 錯覚に陥るようなものではありませんでした。あくまでも第三者として 記録資料としてみていました。
ですが、この映画は違います。あくまでも、観てる人たちを最前線に引きずり込 み、 修羅場を疑似体験させようという作りにしていたように感じます。ですから、 ほとんど俯瞰の写真がなかった筈です。ミラー大尉か他の兵士としての目で カメラは映していたと思っています。(そんな記憶しかありません。)
以上、私の推測でした。
私も、皆さんの意見を読みながら考えていますが、レイナさんは、目的を達成 するための手段としての戦争であり、軍隊であるといっています。
それもあるでしょう。でも、パンチャンの言う通り、戦争自体を否定する事も、 奇麗事かもしれないが正しいと思います。
ただ、どっちも理想を達成するためにはやはり代価がいるのでしょう。
人はその代価が発生する事を、どこか他人の事のように考えているから、 今回は、スピルバーグが自由を守るための代価は、こんなに大変な事だと、 改めて、見せつけたかったのではないでしょうか。
レイナさんの投稿でトム・ハンクス達が出演前に軍事キャンプを受けたと 書いていましたよね。トムのその後のコメントがある映画の本に書いていまし た。
「こんな苦しい思いをするのなら、何でもいいから早く任務を終えて帰りたかっ た。
そんな気持ちになった。」と書いてありました。
ライアンを救う役の彼ですら、こういう風に感じて演技していたのですから、 私の推測も当たらずとも遠からずと思ってしまいます。
私は、これでオマハビーチとライアン救出への過程の違和感を払拭できました。
本当は、無しですよね。こういう納得の方法は。元も子も無いですから。
お許しください。長文もお詫びします。
それでは。
確かに、ライアンがトムのお墓にいくシーンはなんかしらけちゃいいました。SAO(★★★★)(10月9日)
で、最初の30分についてですが、前も書いたと思いますが、私は映画自体とは完全に切り離して見てます。ストーリーには関係ないけど、こういうことがあったということを知ってもらうだけって感じで。実際、ヨーロッパに上陸した人全員があの惨劇を経験したわけじゃないと思うしライアン救出部隊7名のうちあれを経験したのが何人いるのか言ってましたっけ?通訳の子なんて絶対経験してないと思います。だからちょっと離して考えてみてみてください。映画自体はライアン救出劇がメインではないでしょう。「ライアン救出」という任務でもなければ8人なんていう小隊をじっくり描くことなんて無理ですもの。前線ばかりを見せたんじゃ今までの戦争ものとそう変わらなくなってしまうし、兵隊一人一人が人間だということをわからせるのは難しいでしょう。また、前線から離れたところだけじゃ戦争の緊迫感がわかってもらえない。ちょうど良かったのがライアン救出劇じゃないですか?だからライアン救出は兵隊個人個人が私たちと変わらないユニークな人間であることをわからせるためのvehicle(日本語がわからん。。。ごめんなさい)なんですね。
今までの感想をすべて見させていただきました。パンちゃん(10月9日)
人によって感想というものはずいぶん異なるのですね。
私はやっぱり単純に最初のシーンの記憶しか残っていません。
雨のように降り注ぐ銃弾。次から次へと耳元をすり抜ける発砲音。
まるでその場に自分が佇んでいるようでした。
ただただ「怖い」という思いで頭の中がいっぱいになり、涙が少し込み上げてきました。本当にその場に自分がいたらどうするのだろうかと。
ここまで映画の中に入り込んだことは今までありません。
すごい映画なんだと思います。
その一方で、タイトルにもなっているライアンを探し出す話にあまり面白味を感じられませんでした。
冒頭のシーンがあまりにも私にとって衝撃的だったからなのでしょうか。
あのシーンがある限り、もう一度観たくても観る勇気がでないような気がします。
でも、この映画を観て後悔はしてません。
戦争を知らない若者ほど見ておくべき映画ではないでしょうか。
この映画は、戦争に対する考え方がとても影響する。麗奈(10月9日)
私は「戦争放棄」の憲法を立派な憲法だと教えられたし、実際にそう思う。私たちの憲法は世界に誇れる憲法である。戦争を描いた映画を見ると、どうしてもそれがどんなふうに戦争を描いているかが気になる。
この気になり方は、たぶん麗奈さんの味方とはずれる。
「自由を守るため」というよう大義は、「戦争放棄」の憲法で育った私にはなかなかなじめない。「平和のために武力を行使しない」ということを「憲法」として学んだ人間には、アメリカの大義はわかりにくい。
一方、歴史そのものを見れば、人間は確かに自由のために血を流して来ている。流した血によって獲得された自由は、血を流しても守らなければならない、という決意もよくわかる。そうすることが自由を獲得してくれた人々への義務でもある。
それがわかりながら、なぜ「戦争放棄」の憲法を自分の判断の基準とするか。それは日本という国が、自分たちの血を流すと同時に、それよりも多くの隣国の人々の血を流した、隣国の人々を傷つけた、という反省があるからだ。
「戦争放棄」の憲法というのは、まず、誰かを犠牲にはすまい、という反省に基づいている。
二つの憲法の立脚点が全く違っている。
これはどちらが正しいかではなく、どちらも正しい方法なのだ。どちらを選ぶかは、それぞれの責任なのだと思う。
ところが、この「責任」がなかなか自由にならない。一方から見れば他方は、自分とは全く違う立場にいるからだ。
「一国平和主義」というのは湾岸戦争のころからしきりに言われ出したが、それは自由に対してもっと責任を取れ、という概念的な要求だけではなく、戦争に参加し、犠牲(人的、金銭的に)をはらえ、という要求になった。
その要求に応えれば応えたで、中国や韓国からは、日本は強大な戦力を持っている、その戦力でまた侵略をしてくるのではないか、という不安を呼び起こす。
どのような行動にも作用と反作用があるから、簡単には結論は出せない。
*
ところで、この映画に対しては、別の見方もある。
戦争に対するメッセージが伝わって来ない、戦争の犠牲と、その歴史を記録する、というような見方は、映画を直接見る姿勢ではない、という見方だ。
映画からメッセージを引き出そうとするのは、映画を抑圧する見方だ、という視点だ。
そこに「ある」ものとして映画をみるべきだ、という視点だ。
私は、そうした視点をもった人と何度かメールのやりとりをしたが、実は、どうにもわからない。
誰でもそうだと思うが、何かに感動したり、驚いたりしたら、それは何によるものか明らかにしたいと思うものだ。感動だけではなく、がっかりしたとき、残念に思ったとき、わけがわからなかったときも同じである。
なぜなんだろう----そう考えるとき、「戦争放棄」の憲法を正しいものとして学んで来た人間と、自由を守るためには人間は戦う必要があると学んで来た人間では、どうしても最初のとっかかりが違って来る。
自分が育って来た環境(教育、文化、社会)と無関係に、「純粋」に映画を見ることなどできない。
「純粋」に、ただ「ある」ものとして見なければならないという視点もまた「抑圧」的な姿勢だと思う。
それぞれが自分の状況から映画を見る。感想を言う。そこには必ず違いが出てくる。違いが出て来ない方がおかしい。
*
抽象的に書いてもしようがないので、自分に即して書くと、私は麗奈さんの「体験の継承という意味がある」という視点には、目を見開かされた。
私は日本人で、当然アメリカ人ではないし、アメリカにも住んでいないから、この映画に「体験の継承」というものが含まれているとは、まったく考えていなかった。ノルマンディー上陸作戦はこんなに悲惨な状況だった、そこでは多くの血が流された、その血の犠牲を忘れてはならない、という思いが込められている、といわれれば、あ、そうか、と思う。それは気づかなかった、と言うしかない。
ただ、「体験の継承」ということを視点に入れればすべてが納得がいくかというと、やはりそうではない。
私はやはり、最初の30分と、ライアン救出劇とがつながらない。最初の悲惨な30分の体験が、どのように8人に影響したのかがわからない。
そんなものなどわからなくていい、最初の30分は30分として見ればいい。救出劇は救出劇として見る。そこにあらわれる人間描写を見ればいい、という見方もあるが、私にはできない。
私は、ある体験は必ずその人の意識に反映し、人間をかえると信じるからだ。
「戦争放棄」の憲法を学び、それが正しいと理解した人間は、戦争映画を見るとき、どうしてもそこから戦争は無意味だ、というメッセージを読み取ろうとする。戦争は自由を守るための必要なことだ、という教育を受けていれば、戦争映画から多くの犠牲によって現在の自由が勝ち取られた、というメッセージを受け取るだろう。
人間は常に過去に影響されながら現在と向き合う。これは当たり前のことだ。
ところが、この映画ではノルマンディー上陸作戦という惨劇が、どのように8人に影響したのか、その惨劇を体験することによって8人がどんな行動をとるようになったのか、そのことがさっぱりわからない。
トム・ハンクスと友人は古い戦争の体験を話す。マット・デイモンは故郷にいたころの兄の話をする。それは彼らの個人的な生活を浮かび上がらせはするが、それと同じように、ノルマンディーの体験が彼らの現在に結びつかないのはなぜなのか。
このことがわからないからこそ、最初の30分が不気味なのだと思う。
「体験の継承」というのなら、別にライアン救出劇と結び付けなくてもいい。ほかの映画でもいいのではないか。なぜライアン救出劇を描くために、あんなに悲惨な状況を、克明に描く必要があったのか。
それがわかれば、この映画は、もっと受け入れられると思う。
*
私には、もう一つわからないシーンがある。
ラストでマット・デイモンがトム・ハンクスの墓に参ったあと、「私はいい人間だっただろうか」というようなことを家族に向かって聞く。
おいおい、こんなときに、そんなのんきなことを言うなよ。8人の犠牲によってお前は生きているんだろう。いったい、アメリカに帰ったあと、お前はどんな生活をしてきたのだ。彼らによって救われた命をどんなふうに生かし続けて来たのだ。
ここにもとんでもない断絶がある。救出劇と現在のマット・デイモンをつなぐものが何もない。救出されることによって、マットがどんなふうに変化したのか、そのことが全く描かれていない。
その2点が、この映画に対する大きな不満だ。
まず、"earn this" ですが、これはトムがマットに言った台詞でしたっけ?この意味は何もしてない、普通の兵士なのに一人だけ家に帰ることなんてできないって言ってる「ライアン君」にトムがそれなら、ここで帰してもらえるだけの価値のあることをしろ!って言ってるんじゃなかったかしら?Shiroさんは英語でも大丈夫そうなので、私の楽なほうで書かせてもらうと。。。I think this phrase was used when Ryan felt that he didn't deserve to go home. He felt guilty going home leaving all his buddies in the war! Just like those Kamikaze pilots felt when they couldn't die and their friends died. They naturally feel guilty. So here, Ryan was saying that he didn't want to leave his pals and go home, at which point, Tom Hanks' character tells Ryan "well then, do something worthwhile to earn this trip back home. So you can tell your buddies, I'm going home because I did something." "Fubar" was used almost as a symbol, I think. It was funny because the naive one didn't know what it meant. It's a word (?) that is used often by people and yet this naive guy (the translator guy, I believe) didn't know what it meant. I think that was the whole point. Then again, I don't remember the entire movie scene by scene, so who knows....
キリヤマさん--どこの社会にもいるように軍にだってだらしのない奴、マナーのない奴がいます。日本にいる米兵でもそういった人達がいるために全体の評判を悪くしているような気がします。実際に湾岸戦争を経験して(私が行ったわけじゃないですが)、友達が行ってる最中に「戦争なんて無意味だ」なんて言えませんでした。確かにそう言って反戦運動をしている人達もいましたが友達が死に直面しているのに、おまえのやってることは無意味だなんていえませんでした。ベトナム戦争では「戦争は無意味」、「早くやめろ」という意見が主だったので帰ってきた兵隊たちはひどい扱いを受けました。確かにアメリカのために戦った戦争ではなかったけど、徴兵制度で無理やり行かされ、帰ってきては市民に唾を吐かれるなんて、あまりにひどすぎると私は思います。「でもやっぱり軍隊はあくまで殺人と破壊と諜報活動のために訓練されている人間の集団であって...」とありましたが、そう考えること自体が文化の違いなんですね。私は軍隊を「殺人兵器」のように言われることに我慢ができません。彼等は人を殺しに行ってるのではなく、アメリカの自由を守りに行っているのです。「世界中の人類の自由を守るため」といって米軍を送ることには大反対です。もし、北朝鮮が日本を攻めてきたら、日本人が勝手に守ればいいことでしょう。しかし、第2次世界大戦後、日本から軍を無くさせたアメリカ軍は日本の平和を守る義務を背負込んでしまいました。15年ほど前もしソ連が攻めてきたらどうする?と言う街頭インタビューに答えた日本人のほとんどが「逃げる」、「アメリカ軍が助けてくれるからいい」などと言っているのを聞いてとても悲しくなりました。米軍に出てけ、出てけというなら、自分でしっかり国を守るという自覚を全国民に持ってもらいたいと思います。
これもライアンとはあまり関係のない話になってしまいましたね。