鷽八百機械工業(うそはっぴゃくきかいこうぎょう)は東証一部上場の機械部品メーカーで、50年の歴史がありこの業界では老舗といってもいい。20世紀末より環境問題がクローズアップされてきて、鷽八百機械でも1990年代末に本社にも環境保護部が設置された。ISO14001認証については工場では90年代に認証したが、本社は21世紀になって認証した。
環境部門といっても担当役員の下に専任者はたったの3名であり、対外広報や環境報告書の編集、本社のISO事務局などを担当している。もっとも公害防止、廃棄物管理、省エネ活動、それらのデータ収集などほとんどの実務は工場が行うし、環境報告書などは外注しているから仕事の負荷がそんなにあるわけではない。そして環境担当役員といってもその他の担当役員を兼ねており、それがこの会社の環境の位置づけを現わしていた。
ISO事務局を担当していた人が間もなく定年ということで、後任を社内募集した。この会社では社内公募という制度があり、人が欲しい部門は社内に職務内容と必要条件示して募集をする仕組みがある。
山田太郎は今年42歳。大学を出て入社して、今までずっと営業畑で仕事をしてきた。山田は、今年も課長になれず、同期ではとうとう最後になってしまった。そんなことで最近仕事に嫌気がさしていた。営業の仕事にいささか疑問というかファイトをなくし疲れを感じていた山田は環境部門で働いてみたいというのは、逃避であると自分自身知ってはいたが、20年営業をしてきて残りの定年までの20年は違った仕事をしてみたいという気持ちも嘘ではなかった。
環境保護部の部長と面接すると気に入られてすぐに異動が決まった。営業部門の上司は山田が応募したことにいささか心証を害した。だが公募制度は会社の文化であり、反対はできない。同時にいったん社内公募で異動した場合、何があっても元の職場に戻れないというのも会社の不文律である。もし環境保護部でやっていけない場合は、退職することになるかもしれないのだ。
ともかく山田は異動した。
前任者の退職日は今年の12月なので、引き継ぎは3カ月ある。通常の業務であれば十分といえる期間だ。前任者は平目(ひらめ)といういかにも善人という人で、ISO認証する時から活動してきたことを誇りにしていた。
「山田君、まず初仕事は環境方針の見直しだよ。今年6月の株主総会で社長が交代したでしょう。環境方針は社長のサインが必要なので、いつも新しい社長のサインをいただくことにしているのです。もうだいぶ時期が過ぎてますからちょっと急がないといけません。」
「平目さん、方針の文章は社長に書いていただくのですか?」
「いやいや、文章は私たちが書きます。といいますのは、環境方針に書くべきことがISO規格に決まっているのです。社長ご本人が環境に対する思いを書いても、ISO審査で不適合になってしまうのです。」
山田は変だなあとは思ったが、そんなものかとも思った。なにせまだISO規格など読んだこともないのだ。
「山田君も一度ISOの研修に行かないといけませんね。できたら審査員の5日間コースの研修まで受けておくといいですよ。私も審査員補に登録しているんです。ISO事務局ともなると、審査員と対等に話ができるようにならないといけませんからね。」
シンサインホ?なんだろう、山田にはわからないことがたくさんあるようだ。
「山田君、私は現在の環境方針のままで社長のサインだけいただければ良いと思っているのです。」と平目は続けた。
山田は正直なところ会社の環境方針など見たこともなかった。いや、何年か前、掲示板に貼ってあったような気もする。
平目は現在の環境方針を取り出した。
「ISO規格では環境方針にどのようなことを書く必要があるか、細かく決まっているのです。それをしっかりと入れ込まないと不適合なのです。」
平目はよほど不適合が気になるようだ。
鷽八百機械工業環境方針
当社は産業用機械の各種部品の設計・製作を行ない、社会と環境改善に貢献しているが、この生産活動に使用するエネルギー・原材料の消費、廃棄物の排出によって環境に負荷を与えている。当社はこの環境方針に基づき環境活動を推進する。
20XX年XX月XX日★★★★★★★★
嘘八百機械工業株式会社★★★★ 取締役社長 XXXX(先代社長)★ |
ISO14001:2004 4.2 環境方針 トップマネジメントは、組織の環境方針を定め、その環境方針に対して環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で次の事項を確実にすること。 a) 組織の活動、製品及びサービスの、性質、規模及び環境影響に対して適切である。 b) 継続的改善及び汚染の予防に関するコミットメントを含む c) 組織の環境側面に関係して適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を順守するコミットメントを含む。 d) 環境目的及び目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 e) 文書化され、実行され、維持される。 f) 組織で働く又は組織のために働くすべての人に周知される。 g) 一般の人々が入手可能である。 |
上記方針を読んで、「そんな、馬鹿な!」と笑った方はいらっしゃるでしょう。私も笑ってしまったのですよ。 実を言いまして、「環境方針」と入れてググって、すぐに見つかったものを社名と言い回しを若干変えただけです。世の中規格通りの環境方針などザクザクあるようです。 |
「山田君、ほらしっかりと規格とおりでしょう。これを作成するのは結構大変でした。これに社長のサインを頂けば大丈夫ですよ。」
山田は、仕事ってそんなに簡単なものだろうかと心の中に暗雲のように疑問がわき上がってきた。少なくとも営業の仕事はそんなものではなかったと思う。
数日後、山田は秘書室にお願いし社長の時間を10分とっていただいた。嘘八百機械工業は特段格式ばった会社ではないが、社長に会うのはやはり簡単ではない。
社長ともなるとただ者ではない。30数年に渡る業界他社との過酷な競争、社内政治の競争に勝ち残ってきたのである。
山田は社長室のドアは開いていたが外でノックした。
「環境保護部の山田と申します。社長が代わりましたので環境方針にサインをいただきたくお願いします。」
「山田君、方針は拝見しているよ。先代の時の文章そのままでサインをすればよいとのことだったね。」
「ハイ、実は私も異動後間もなく、前任者から社長のサインのみ頂けばよいとの指導を受けてます。」
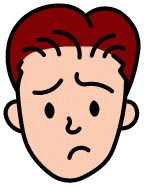 「あのね、君はあの文章を読んだかい? まっとうな大人ならはずかしくて最後まで読めないよ、悪いが私はこの方針にサインはできない。」
「あのね、君はあの文章を読んだかい? まっとうな大人ならはずかしくて最後まで読めないよ、悪いが私はこの方針にサインはできない。」面会時間はまだあったがもう終了である。
山田は社長の言葉は当然だなあと思いながら、はてどうしたものかと悩みつつ環境保護部に戻ってきた。
「山田君、社長のサインは頂いたかい。それじゃ環境方針カードの印刷を頼まなくちゃ、それで方針の周知は完了だよ。手順は説明するからね」
平目は屈託なくそう話しかけてきた。
「うん、実は・・」山田は言葉を濁しながら、平目さんは今までいったい何をしていたのだろうか?何を考えて仕事をしているのだろうかと思った。
エート、このままだと単なる小説になってしまうので以下を考えてください。
・環境方針は社長の思いを書いたらまずいのだろうか?
・方針は規格にあわせて書かなくてはならないのでしょうか?
・周知ってどんなことをすれば良いのでしょうか?
・あなたが山田太郎ならどうすれば良いのだろうか?
正解はありません。考えることが重要です。
ぶらっくたいがぁ様からお便りを頂きました(09.10.12)
山田は変だなあとは思ったが、そんなものかとも思った。なにせまだISO規格など読んだこともないのだ。 何とも思わない人が多い中、ヘンだと思う感性を持っていることは感心だと思います。 山田は、仕事ってそんなに簡単なものだろうかと心の中に暗雲のように疑問がわき上がってきた。少なくとも営業の仕事はそんなものではなかったと思う。 おお、いいぞ。それがマトモな感性というものです。 ・環境方針は社長の思いを書いたらまずいのだろうか? 誰に対して「まずい」のかが不明ですが、(大企業はいざ知らず、中小企業であれば)方針なんてものは社長の想いをストレートに語るものだと思います。誰にはばかることがありましょうや。 ・方針は規格にあわせて書かなくてはならないのでしょうか? そうお考えになる人が大勢いることを、とてもヘンだと思います。 ウチの方針なぞは規格を考慮すること皆無で、「一般の人に公開する」どころか法令順守さえ書いてありません。当たり前だからです。 そんなので審査が通るのかですって? これでいいのだ。 ・周知ってどんなことをすれば良いのでしょうか? 業務を遂行する上で周知しなくてはならないことができていない組織などあるはずがなく、それでも周知されていないのであれば、それは業務を遂行する上で周知しなくても差し支えない程度のものだからです。 何も特別なことをする必要などないと思います。 ・あなたが山田太郎ならどうすれば良いのだろうか? では、私が山田君ならどうするかをシミュレーションしてみましょう。 「うん、実は・・・・ 社長からサインを拒否されました」 「あれ? 誤字脱字がないように何度もチェックしたはずだが?」 「いや、そうじゃありません」 「じゃあ、日付か? しまった。社長が就任された日付にするべきだったか」 「あいにく、日付でもありません」 「アンビリバボー! じゃあ、何がまずかったんだろう」 「たいへん言いづらいんですが、内容そのものらしいです」 「な、何だって? これほどカンペキな方針のどこが社長は気に入らないとおっしゃってるんだ?」 「社長がおっしゃるには『まっとうな大人ならはずかしくて最後まで読めないよ』とのことでした」 「うーーん。社長がおっしゃる意味が私にはわからないよ」 「そうでしょうか。私もおかしいと思いましたが」 「キ、キミィ! 何がどうおかしいんだね!」 「だって、これは規格とかいうもののオウム返しで、会社名を変えればどこの会社でも使えそうですし、とてもわが社の方針としてふさわしいとは思えません」 「な、な、なんてことを言うんだキミは。そんなことで審査が通るとでも思っているのかね」 「え? 方針を立てるのは審査に合格することが目的なんですか?」 以下、略。 |
たいがぁ様・・・ そりゃ、有段者の回答ですよ 山田君はまだ白帯 そこまでは無理なんじゃあ〜 |
湾星ファン様からお便りを頂きました(09.10.12)
佐為さま 湾星ファンです。宿題回答でございます。 ・環境方針は社長の思いを書いたらまずいのだろうか? ・方針は規格にあわせて書かなくてはならないのでしょうか? いいですか、ISOは世界の英知を結集して作成されたものです。 法律や条例なんかよりも、よっぽど重いものなんです。 社長の思いを書くなど、もっての他です。規格条文をそのまま一字一句違えずに(ここ、とっても重要なのでメモしておくように)忠実に書き込むことが大事です。 ・周知ってどんなことをすれば良いのでしょうか?? 環境方針カードを作成するのは、当然というか基本中の基本。 自社の従業員はもちろん、協力会社へ来客にも漏れなく配布することが肝要です。環境方針ポスターも受付だけでなく、全ての会議室、工場の運転室や控え室、取引先にも配りまくらないと周知とは認められません。あ、ホームページも忘れずにね。 審査員の先生方は、必ずチェックしてますから。 ・あなたが山田太郎ならどうすれば良いのだろうか? 社長、この方針にご署名いただけないなら、認証を返上するしかありません。って、いきなりクビですか。そうですか・・・orz 湾星ファン |
湾星ファン様 すばらしい! 素晴らしすぎる! たいがぁ様と甲乙つけがたい。 ぜひともこれからも山田君をご指導いただきたくおねがいします。 ところで・・・このケーススタディ・・一般の事務局や並みのレベルの審査員に受けるだろうか? 疑問 |
外資社員様からお便りを頂きました(09.10.14)
佐為さま お久しぶりです。 御茶ノ水駅で見つけられなかった外資社員です(笑) 私自身 ISOは素人で勉強中なので、ぜひご批評を頂ければと意見を書いてみます。 当社は産業用機械の各種部品の設計・製作を行ない、社会と環境改善に貢献しているが、この生産活動に使用するエネルギー・原材料の消費、廃棄物の排出によって環境に負荷を与えている。当社はこの環境方針に基づき環境活動を推進する。 前文は、会社としての考えを述べるのでしょうから、ここが重要と思います。 まず、日本語として変ですよね。 会社の目的と、一方で環境に負荷がある。ここまでは判ります、その後 唐突に「この環境方針」とありますが、文章の前後関係が不明で、この環境方針とは、文章構成から言えばすでに説明したことですから、会社の環境方針は「会社が生産により社会貢献していることと環境に負荷を与える」という並列事項になります。 これは単なる事実で記載であり、これをもって方針というのは変です。 私が読み手ならば、貴社の環境方針は何でしょう?と質問します。 多分、それ以下の項目なのだと回答があるのでしょうが、それは方針を受けて具体的に実施する推進するべき事項ではと思いました。 少なくとも、「会社の生産量に対する環境負荷率を下げることに継続的に努力」のような意味が環境方針としてふさわしいように思います。 これならば定量的な管理や、目標設定も可能になりと思います。 小説家のような美文や、専門家を唸らせるような内容は書けませんが、論理的に破綻していない文章を書くのは、まず必要なことであり専門家でなくとも出来ることと思います。 |
外資社員様 いつもご指導ありがとうございます。 まず、この文章を考えたのは私ではありません。もう会社名も忘れてしまいましたが、実在の会社の実在の環境方針の固有名詞を置き換えただけです。私の日本語がなっていないなどとお怒りにならないように といいつつ、それを変だと考えなかった私はやはりアホ?
反省! |
しょうちゃん様からお便りを頂きました(09.10.14)
おばQさま、毎度お世話になります。しょうちゃんです。 山田太郎さんの立場は、ほんの数年前、ISO認証活動をしていた当時の私の姿そのものです。 平目さんに相当するのがコンサルです。 ・環境方針は社長の思いを書いたらまずいのだろうか? ・方針は規格にあわせて書かなくてはならないのでしょうか? 方針策定の時、コンサル提案(規格の裏返し)では社長は納得せず。 社長が自ら作成するというので、社長には「社長の思いを書いてねー」ってお願いしました。 社長が作成したものは勿論、規格要求の文言の裏返しではなく、コンサルは審査で指摘される可能性があるとのことで納得せず。 で、私が間に入って行ったり来たり、調整を繰り返しましたが、そのうち私がキレて「この方針にケチをつけるような審査機関は使わん。」「スケジュール調整するから、社長に直接言いたいことを言え!」と言うと、コンサルはもう何も言わなくなりました。 ・周知ってどんなことをすれば良いのでしょうか? ISO14001:2004 ポケ本 215頁 3.改訂中に問題になった事項 g) communicate(communication):伝達する、周知する、コミュニケーションを行うによると、「周知する」には「理解を求める」の意があるようです。 だから従業員や協力会社等へ、方針を印刷してばら撒いても、「周知」には該当しないように思います。 私は未だにどうするのが良いやり方なのか分かりません。 ・あなたが山田太郎ならどうすれば良いのだろうか? ちゃんと「形式的なISOの仕事」を無難にこなし、窓際族を極めます。 だってファイトをなくし、逃避したんですから。 (^^ゞ |
ISOのプロ、しょうちゃん様 登場! 私の最近の実体験ですが、方針に「枠組みという言葉がない」「一般に公開すると書いてない」「汚染の予防という語句がない」と方針だけで数件もの不適合を食らったことがあります。 審査員のご芳名もCEAR登録番号も十分に存じ上げており、今度何かあったらタダでは済まさんぞと今でもアドレナリンはふつふつと・・ でもそのときはなんとか穏やかにまとめようとあっし(ボランティアコンサル)はおろおろするばかりでありました。 その後、認証機関の取締役に電話して文句言いましたけど、後味良くありません。 結局、審査員が日本のISOをだめにして、いや現在完了進行形でダメにしつつあるのでしょうか? これは山田君以前に私がいっそう頑張らねば・・ 今後ともご指導のほどよろしくお願いします。 |
名古屋鶏様のご了解を得て転載いたしました(09.10.14)
お題、下の句。 つい先日、おばQ様から『環境方針に関するケーススタディを作ったから下の句を作れ』とお題を頂戴いたしました。 と、いうわけで今回は、その下の句パート1です。 「・・・平目さん、あの環境方針なんですが、社長が『こんなものにはサインできない』というですよ」 山田は平目に報告をした。 「おいおい・・・そんなことじゃぁ困るじゃないか。それで山田君は『はい、そうですか』と引き下がって来たというのかい?冗談じゃないよ。ISOの定期審査までもうそんなに日数がないんだ。サインを貰って、カードを印刷して配付する時間を考えたら悠長なことを言ってられないんだぞ」 平目は困惑したように言う。 「新社長も新社長だよなぁ・・・自分の考えなんかで認証は取れないというのに・・」 平目のつぶやきに、山田は少し間を置いてから唐突に切り出した。 「・・平目さん。そもそもISOって何ですか?」 「へ・・・・?」 平目はキョトンとしている。 「何・・・・ってキミ、ISOはISOだよ。まぁ強いて言うならISO14001は『環境マネジメントに関する国際規格』ってところかな?」 「なるほど。それでその『環境マネジメントに関する国際規格』をすると何かいいことがあるんですか?」 山田が尋ねる。 「変なことを言うなぁ・・・会社が決めたことに良いも悪いも無いだろう。確かにISO14001の取得は先代の社長が決めたことだけど、今更『代替わりするから止めます』という訳にもいかんだろう?一応我が社も『環境に優しい鷽八百機械工業』を謳っているからね」 やれやれ、と平目がため息をつく。コイツは42歳にもなって、何を今頃になって青臭いことを言い出すのやら・・・ 「それともうひとつ、大事なことがある。わが社は東証一部に上場しているから、毎年日本経済新聞から『環境経営度ランキング』という調査があるんだ。アンケート形式になっていて、それに対する回答結果から全国順位が毎年、紙面で発表される。・・・わが社は今年10位上がって、156位だったけどね」 平目は少し胸を張った。 「その『環境経営度ランキング』の調査項目にはISO14001の認証取得、という項目もあるんだよ。本社が遅ればせながらISOを取得したのは、その順位を上げるためなんだ。『環境配慮』を掲げる鷽八百機械工業としては、『環境経営度が低い』と見られるわけにもいかないんだ。だからISOの認証は継続する必要があるし、そのためには審査で適合判定をもらわにゃぁならん。そして、それには規格に適合したと審査員から認めて貰える環境方針が必要なんだよ。わかるかい?」 「・・・・お話はわかりました」 山田は軽く頭を下げた。 「そうかい。じゃ、それを社長に説得してみてくれ。なに、私もね、最初に社長のサインを貰うには中々と苦労をしたものだよ。けど、『それでは認証が取れませんから』と粘って交渉した末に何とかサインを勝ち取ったんだ。キミもまだ若いんだから、そういう苦労をしてみるといいよ」 平目はそういうと、ニッコリ笑って山田の肩をポンと叩いた。 次の日、山田は休日を利用して『環境方針』でWEBサイトを検索してみたり、書店でISO14001に関する解説本を探してみた。 WEBサイトで見た、いくつかの『環境方針』は、どれを見てもほぼ同じで、平目が作ったとされる鷽八百機械工業のものと大差はなかった。また、買ってきた幾つかの解説本も読んではみたのだが『環境方針には継続的改善に対するコミットメントが必要です』とか『汚染の予防という言葉が規格によって要求されています』と書かれているだけで、山田の疑念に充分に応えるものには無かった。 だが。と、山田は考えた。 自分の常識で考えれば何かが変だと思う。 例えば自分が営業に居たときには、社長から『今年は営業利益○%UPだ』と方針が示され、『そのためには、この分野を伸ばそう』とか『この分野は斜陽だから投資は控える』といった方向性が示されていた。それでもって営業部長から『次回の展示会では、この分野の技術力をアピールしていきたい』などと指示があり、課長からは展示会での段取りやパンフレットの作成指示が出て、自分達はそれを持って顧客を訪問しながら『是非、今度の展示会に来てください』とお願いに廻ったものだ。 少なくとも、自分達は20年間そういう仕事をしてきたし、それが仕事の流れだと思っている。 しかし、平目のいう『ISOに適合した』環境方針はそれとは違う。『規格に適合した』文章を事務局が作成し、上手く言いくるめて社長にサインさせ、審査でOKを貰う・・めでたし、めでたし・・・・・いのか? それって本当に会社の『環境に関する方針』なのか?それに審査云々と言われるが、会社の方針・方向性について全くの他人から是や非をとやかく言われるものなのか? 大先輩である平目の仕事を否定するつもりは毛頭ないが、自分が『それ』を担当するのであれば、少なくとも自分の納得のいくようにしたいものだ。 けども、と山田は考える。 それでもし、審査で『いや、これでは不適合ですね』と言われれば、平目が気にしていた日経の環境経営度ランキングもオジャンになる。それはどうなんだろうか? 次の日、山田は意を決して社長にメールを送ってみることにした。 『社長、先日は大変に失礼を申し上げました。深くお詫び申し上げます。 さて、懸案であります環境方針の件について、社長のご見解を伺いたく思います。 私自身はこの職務に就いて日が浅く、経験も充分でありません。しかしながら、社長の仰るとおり、あの環境方針とする文章はおかしいと思います。私が思いますに、会社方針書というものは会社を代表する社長から、お考えを拝聴し、それを取りまとめて成り立つものであります。しかしながら前任者の平目さんからは、それでは認証が出ない、と言われております。 そこで、試しに社長のお考えを伺いながら「本来はこうあるべき」と思う環境方針書を策定し、それを審査機関に投げ掛けてみたらどうか、と思います。ただ、その場合「これでは不適合だ」と言われることも充分考えられます。そうした時に、社長は如何お考えでありましょうか? A:「それなら審査員の言う通りにして、元に戻せ」 と思われるでしょうか?それとも B:「それなら別の認証機関を探すか、それでダメならISOは返上しよう」 と思われるでしょうか?ただ、その場合においては日経の環境経営度ランキングは、現在の順位を維持できなくなります。 本来ならば、内容を充分に吟味し、事前にご相談を申し上げてから、お伺いすべき筋でありました。今になってこのような相談をいたしますこと、まことに申し訳ございません。 何卒、社長のお考えを頂戴したく、よろしくお願い申し上げます。』 次の日、返事は意外なほど早く帰ってきた。 『認証は必要だ。だが、会社の方針は私が考えて責任を持つものだ。 山田君の手腕に期待している。 それと、認証機関と意見交換するのはおおいに結構だが、喧嘩にならないように 以上』 山田は平目に、ことの次第とメールでのやりとりを見せた。 「ふう・・・ん。なるほど・・頑固だなぁ新社長も。こういう事は事務局に一任してくれればいいんだけどなぁ・・・」 平目は、何処だってそうしているんだし、とため息をついた。 「ともかく」 山田は平目に切り出した。 「一度、時間をとって社長のお考えを聞いてみたいと思います。それで、それを一度文章に直して、社長の了解が得られたら認証機関の方に話をしてみたいと思うのですが」 「ま、私の任期もあと3ヶ月だし、自由にやってみたらいいよ。あぁそうだ、JISQ14001の対訳本は持っているね?予め良く読んでおくといいよ」 山田の背中を軽く叩いて、平目が席に戻っていった。 一週間後、山田は社長から色々と聞いた話を元に文章を作りあげ、社長のOKを貰ってから認証機関先に電話をいれてみた。 「もしもし、J○×さんですか?鷽八百機械工業の山田と申します。ISO14001規格適合の関係でご相談したいことがあるのですが」 電話口に出てくれたのは、『上級審査員』という肩書きをもつ田井という人物だった。 「・・・お話は承りました。とりあえず、その素案をFAXかメールで頂けませんか?私が一度確認してみたいと思いますが」 丁寧な対応に山田は少し肩透かしを食らった気もしたが、すぐにその場でメールを送信した。平目の話で聴く審査員とは、自分ルールを理不尽に振り回す、怖い怖い鬼教官のようなイメージだったのだが。 「あー・・・来ました、来ました・・・どれどれ・・拝見いたします・・・」 電話口の向こうで田井がブツブツ・・と言いながら山田の文章を読んでいる。 そして、ややあってから、 「そうですね、これで特に問題はありませんよ。いい環境方針だと思います」 と、田井が電話口の向こうから返答してきた。 「・・・あのう・・不適合、ということは・・・」 おそるおそる山田が聞き返す。 「不適合?いえ、大丈夫ですよ。」 田井の笑い声に山田は少しホッとした。 「ありがとうございます。実はこの内容で先輩へ事前に確認をして貰ったのですが・・・こんなのでは全然ダメだといわれまして」 「ダメ?そうですか?何処がですか?」 田井が聞き返す。 「例えば、『継続的改善をします』という言葉がない、とかです。先輩によると、過去の審査では、この言葉がないと不適合だと言われたとかで・・・」 山田の話しに、電話口の向こうで田井の苦笑いが聞こえる。 「はは・・まぁ、確かに『昔は』そういう審査をしていたこともありましたけどね。でも本来、環境方針とは会社方針ですから『言葉が無い』とかそういう物じゃないです。逆にいくら『規格に適合』と判定されたとしても、その組織トップのオリジナリティある決意がなければ、方針として何の役にも立ちませんよね?」 田井は続けて言った。 「山田さん、継続的改善とは『企業の成長』そのものを指すものだと私は思います。だって継続的に改善をするから、企業は成長するんでしょう?現状維持なんてしていたら、あっと言う間に市場から置き去りにされてしまうじゃありませんか?御社の環境方針には、組織トップの環境に対する改善の決意がちゃんと見てとれます。ですから、充分に適合であると、私は確信しますよ」 ありがとうございます、と山田は田井に礼を言って電話を切った。 認証機関の電話対応に、平目は腕組みをしながら複雑な顔をしていた。 「ふ〜ん・・そういうものかなぁ。ISO14001を工場で初めて取得したときには、規格の文言、そのものが書いて無いとダメだったんだけどなぁ・・・時代が変わったのかなぁ」 ともかく、方針文書に関しての適合問題はクリアになった。山田は秘書室に社長のアポをとるための電話を入れた。サインをもらうためだ。 なんだか、頭の使い過ぎかオーバーヒートし掛けてきたので、方針周知の話はまた後日に・・・ |
真っ向勝負で力作だけど、先輩諸氏のオチャラケもいいなあ
|
しょうちゃん様からお便りを頂きました(09.10.15)
ああ、思い出しました。 当時、社長の作った方針でOKかどうか、契約候補の審査機関の審査部長クラスに直接面談して聞いてみました。 それだけでなく、めいっぱい手を抜いた著しい環境側面の決め方や、特定した法令規制の範囲(何処までを環境法として管理するか)など、不安なこと全部。 審査機関としてコンサルしてはいけません(組織の意思決定に関与してはならない)が、あくまで事例にする判定であり、根拠も含めて教えてくれました。 結果、殆ど問題ないとのことで(向こうも仕事が欲しいからね) 安心して審査を受けることが出来ました。 審査本番で審査員と揉めても、 「お宅の○○部長さんがこれでいいって言ってたよぉ、あの方、お宅のルールブックだよねぇ」 って言えるので、楽勝。 (^^)v のはずだったのですが、その方、普段は審査はやらないんだけど、心配だったのか、我が家の審査にメンバーで来てました。(◎_◎; <本日の結論> 審査機関を決める前に、その審査機関の判定に責任を持つ人に事例を提示して見解を伺い、それを審査機関の選考要素のひとつにすると良いでしょう。 PS ちなみに社長の環境方針、L■JのMセンセーにも見解を聞いたところ、「NG」判定でした。(^^; |
しょうちゃん様 毎度ありがとうございます。 認証機関にもよりますが、幹部が指示することが徹底するところもありますが、審査員が名刺を借りて仕事しているようなところもあります。そんなところは独立愚連隊ですから幹部が何を言おうと意味ありません。取締役に了解をとってもダメというおもしろいとかおよそ組織らしからぬところもあります。そんなところではしょうちゃん様の戦法でも通用しないような気が・・ おっと、そんな怪しげな認証機関を切り捨てるのが最善か! PS L■JのMセンセーでだめなら寺田さんに問い合わせましょう。 裁判だって三審制、ISOなら最後には認証辞退というてもあります。 |
名古屋鶏様からさらなる物語を頂きました(09.10.17)
さて。と平目は山田の方を向いた。 「今度はこの環境方針を抜粋して、環境方針カードを作らないとね。それから、そのサインを貰った環境方針書だけども、それも各部門に配布しなきゃぁならん。それに環境方針は主要な取引先業者に配布して『環境方針同意書』を取り付けないとダメなんだ。忙しくなるぞ」 平目は環境方針の文章に目処が立ったのが嬉しいのか、何処と無くウキウキしていた。 「『環境方針カード』ですか?あぁ、ありましたね。表に『省エネに努めます』とか『ゴミを減らします』とか書いてあって、裏面に名前と『そのために私は“ミスコピーに注意します”』とか描くヤツですね」 私も持っていますよと、山田は胸ポケットの名刺入れから『環境方針カード』を取り出した。 それを見て、平目は満足そうに頷いた。 「そうそう、そのカードだよ。審査の時には『御社の環境方針は何ですか?』とヒアリングされるのがデフォだからね。しかも最近は大抵の会社で『環境方針カード』を読み上げるのが通例だから、相手もヒネって質問してくるからね。『では、その環境方針を達成するためにアナタは何をしますか?』とか聞いてくるんだ。現場の連中は、そういう場合に漫才の宮川大介みたいにアウアウになっちまうからなぁ・・・予めカードに書かせて読み上げるようにしてあるんだ。」 山田はこのカードを作ったことを自慢したいらしい。 「・・・あぁ、そうですね。昨年、営業部の審査でウチの若手が捕まりましてね。その時に審査員から『失礼ですが、お名前を教えてください』と言われてテンパっちゃって、いきなり『えー・・環境に優しい製品の販売に努め・・』とか頓珍漢な回答をして失笑を買ってましたよ」 彼はいきなり『カンペ』を読み始めたのだったのが、山田もその場に居合わせたのだ。 「あー・・あったな、それ。アイツも緊張のし過ぎだよ。暑い日だったからなぁ。ああいうのを『キンチョーの夏』っていうのかな?」 ガハハと平目が笑う。いや、面白いのは言ってる本人だけなのは間違いない。 「・・・それにしてもコレ・・」 山田は聞かなかった振りをして話題を変えた。 「我が社の工場は半数近くが派遣か請負の外人ですよね?その人たちはどうするんです?この間読んだJISQ14001の対訳本には『組織のために働く全ての人に周知する』と書いてあったと思いますが」 あぁそれか、と平目が苦笑いをする。 「前回も苦労したんだよな。我が社の場合、ブラジル人の他にフィリピン、マレーシア、中国・・が福建省と四川に北京・・言葉が違うからな・・それと韓国もいるし、タイも居たかな?ボリビア人とかもいたぞ、確か。」 「凄いですね・・・まるで多国籍軍か東アジア共同体ですね。彼らに環境方針ポスターで『周知』しようとしたら、各国の言葉に翻訳する必要があるんじゃぁないですか?」 山田が尋ねる。 「いや・・それがだなぁ・・そう簡単な話じゃないんだ」 平目がため息をつく。 「そもそもブラジル人やボリビア人は基本的にポルトガル語が通じるんで、そこは共通できる。韓国人は派遣でなくて研修員だから日本語ができる。中国人は北京語で書けば、大体の意味は通る。タイも華僑が居るから中国語はそこそこ通じる・・後は英語、かな。しかし、問題はそこじゃないんだ」 「・・といいますと?」 「言葉がさ、1対1で翻訳できないんだ。日本語は漢字や言い回しで『言葉の圧縮』が出来るけど、ポルトガル語とかでは、こうはいかない。例えば『省エネ』は『電気やガスを大切に使います』と噛み砕いてやる必要がある。『汚染の予防』だと『川や空気が汚くならないようにします』とかね。中国語ならともかく、アルファベット圏国の場合は唯でさえ文字数が多いからさ。ポスター1枚に完全翻訳して記入しようとすると、文字が米粒みたいになっちまうんだ」 困ったものだ、平目が肩をすくめる。 「・・・そんなことじゃぁ、『環境方針カード』とかは論外ですね」 山田は思わず、顕微鏡サイズの文字が並んだ『環境方針カード』を想像した。 「世間じゃぁ、環境方針の全文を全社員が丸暗記しているところもあると聞くけどね。我が社のような大きいところで、それは無理だしな・・・」 平目はそういって天を仰いだ。 山田は、平目の『暗記』という言葉が、ふと気になった。 確かに。『環境方針』を丸暗記してしまえば、「私は環境方針を知りません」ということは無いだろう、と山田は考える。しかし、それは本当に『周知』と言えるだろうか? 受験勉強の時には『いいくに(1192)作ろう鎌倉幕府』のように、ひたすら丸暗記をしたものであるが、それは単に暗記をしたというだけで、何か意味付けがあるものではない。しかし環境方針は会社の方針、社長の思いなのだから、『それをどう実現するのか』という意味付けが必要なのではないだろうか。というか、環境方針の文章の一字一句を覚える努力をするよりも、実現に向けての方向付けや努力をすることに心血を注ぐべきことであるべきであるはずだ。 いや、逆に考えれば暗記やカンペを配布することが逆に足を引っ張ることになってやしないだろうか?『暗記かカンペがあれば大丈夫』という思い込みが、肝心な『方針の展開』を蔑ろにしてしまうような・・・  山田は認証機関の田井に電話をしてみることにした。
山田は認証機関の田井に電話をしてみることにした。「なるほど、ご事情は理解しました」 田井は愛想よく、電話に出てくれた。 「えー・・とですねぇ、稀にそういう会社があるので念のために聞くのですが、御社のトップは役員を含めて他の社員とコミュニケーションほとんどとらない、とかは無いですよね?」 田井の意外な問いに山田は、一瞬、答えに窮した。 「いえ・・・それはないですが・・」 「何か指示伝達がある場合は、役員や担当者に電話なり直接なりメールで接触がありますよね?」 田井は山田に重ねて問うた。 「え、えぇ、そうですね。定例の会議や役員会もありますし、担当者へ直接に指示が来ることもあります」 山田は田井の真意を測りかねていた。 「でしょう?でもって、その結果は報告されてトップの評価を受けてらっしゃるのではありませんか?でしょう?だったら、ホラ。『トップの方針は周知されている』じゃないですか」 「う・・・」と山田が言葉につまる。 「つまりね、『環境方針を周知』するということは、トップの意思が『それ』の実現に必要な人員全員にちゃんと伝わって、その結果がトップに報告されて評価を受けることなんですよ。」 「な、何と言うか・・・当たり前のような気もしますが・・」 田井の、あまりに思ってもみなかった回答に山田はびっくりしていた。 「そうですよ?普通の企業なら当たり前のことです。つまり『方針を周知する仕組み』とはトップの意思が従業員と相互に意思疎通するための会議や組織体制、指示・報告の仕組みが存在することだ、と私は思います」 電話の向こうで田井は明確に言い切った。 ついさっきまで、翻訳文をどうしようか・・などと悩んでいた自分が山田は恥ずかしくなった。そうだった。自分はISOのために仕事をしているのでなかった。社会と会社のために仕事をしているのだった。 「問題はねぇ、山田さん」 田井が続けた。 「トップのヤル気なんです。トップにヤル気がないと、『ああしろ、こうしろ』と指示も出ませんし、その結果についても興味を持ってもらえないんです。案外多いですよ、そういう会社さんは。でも、それではいい結果は絶対に出ません。ですから、『方針の周知』とは、言い換えれば『トップが環境対策についてヤル気があるかどうか』という話なんです。ただ、御社の場合はトップ自ら自分の意思で環境方針をまとめようと言われるくらいですから、その点は心配ご無用かと思いますよ」 ありがとうございます、と山田は礼を言ってから、「もうひとつお聞きしたいのですが」と続けた。 「実は先輩から、『主要な取引先業者に環境方針を配布して“環境方針同意書”を取り付けないといけない』と言われているのですが」 田井は電話口の向こうでカラカラと笑っていた。 「いくら主要な取引先といっても、会社が違えばトップの考えも違って当然でしょう?環境方針は会社方針ですから、『その会社のトップ方針を他社に押し付ける』なんて話はありえませんよ。・・・その取引先が御社の構内でラインごと請け負っている、とでも言うなら話は別でしょうけどもね」 山田は田井に充分な礼を言ってから、電話を切った。 「平目さん、今聞いた話では、・・・・という事なんですが。ですから、我が社の場合は特に何もしなくても、社内のコミニュケーションの仕組みを説明すれば、それでいいようですよ」 平目はまたしても不思議そうな顔をしていた。そして、一言だけ 「・・・ふ〜ん。まぁ、そこまで色々と教えてもらったのなら、自分からもお礼だけはしとかないとな」 と、電話をとった。 「・・・えー・・鷽八百機械工業の平目です・・・すいませんが、田井上級審査員様は・・はい・・はい・・え?・・・はい、はい・・そうですか、分かりました」 そして電話を置くと、山田に向かって 「おい、認証機関に聞いたら『そんな名前の審査員は居ない』って言ってたぞ?」 と怪訝な顔で言った。 「へ?!・・・いや・・しかし・・あの、J○×ですよね?認証機関って?」 山田が慌てて聞き返す。 「馬鹿言え!我が社の認証機関はJ■×○だ!」 「え゛・・・・」 あろうことか、山田は自社と全く関係のない認証機関に電話をしていたのだ。当然、田井は鷽八百機械工業が自社の顧客でない事を知っている筈である。よくぞ我慢して付き合ってくれたものだ。 「おいおい・・どうしてくれるんだ!勝手に動いてしまって・・・私も『上級審査員の言葉』という後ろ盾があるなら審査で文句を言われることもないだろう、と大目に見ていたんだ! J■×○から『そんな話は知らない』とか言われたらアウトだぞ!そうなったら環境方針とか、いまさら変更なんかできんぞ!」 イライラする平目に山田は言い切った。 「いえ・・・認証機関は私が責任を持って説得します。どう考えても田井氏の話の方が真っ当だと思いますから」 そうだ。他人に助言を頼んだとしても、良くも悪くも結局最後に責任を取るのは自分自身なのだ。 もう腹を決めるしかない。山田は覚悟を決めることにした。 そもそも、自分はマンネリが嫌でここの部署に来たのだ。丁度いいじゃないか。自社のルールを本来あるべき姿に『戻す』ために尽力してみようではないか、と。 |
名古屋鶏様、まいどありがとうございます。 これはもうケーススタディではなく、小説ISO14001とでもタイトルをつけて本にしましょうか? |
うそ800の目次にもどる