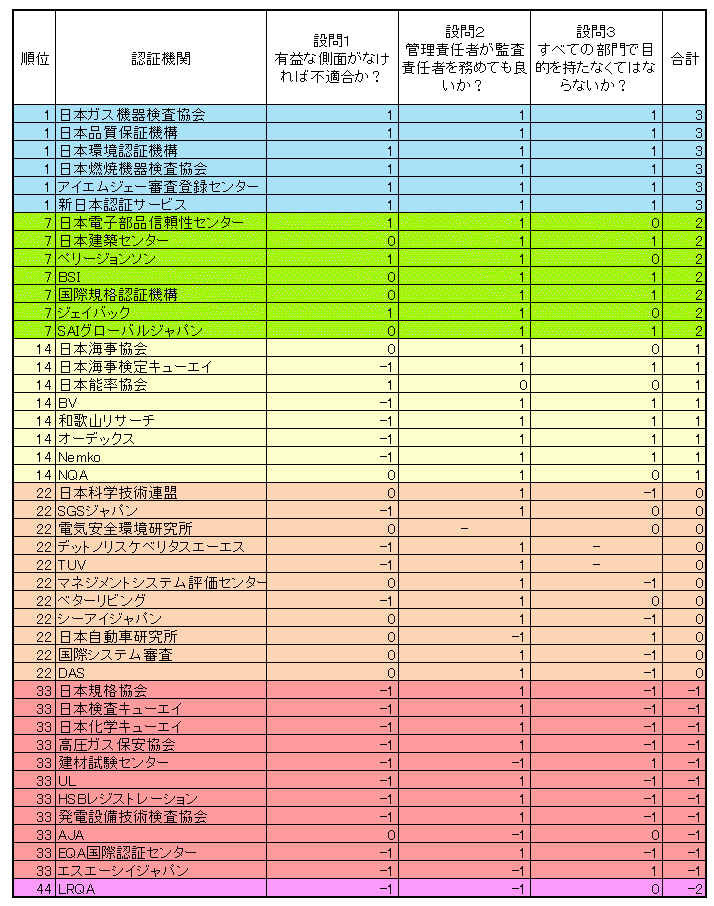
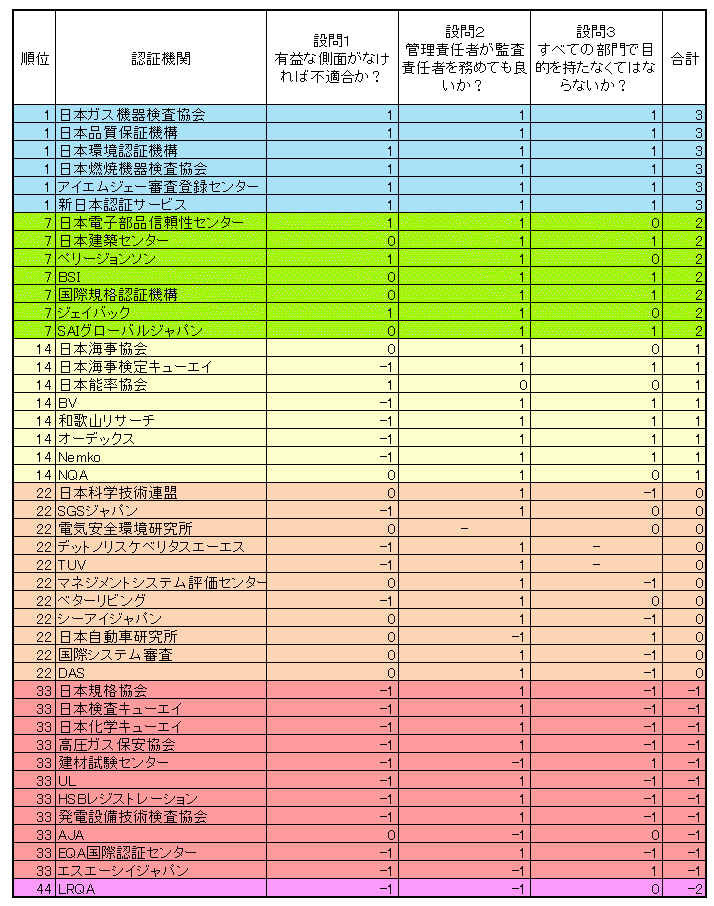
ここでの評価が誤っているのではないかと思われるかもしれないので、判定の根拠を以下に示す。 なお過去にもより具体的詳細を論じており、興味のある方はこちらをお読みください。 |
あのJ▲C○が同率首位で、LR○▲が最下位とは。。 皮肉な結果ですねー。どうなっているんでしょ? |
ぶらっくたいがぁ師匠 毎度ありがとうございます。 私がいかに無私公平で客観的かという証左でございましょう。 しかしながらJ▲C○とLR○▲の回答は矛盾していますから、どなたが評価しても、一方を良く判定すれば他方が悪いことは必然です。 ところで今回のアンケートと世間一般の評判から下図を作ってみました。 ご笑覧あれ |
| アンケートの評価が低い | アンケートの評価が高い | |
| 一 般 の 評 価 が 高 い |
認証機関の見識は低いが、審査員層の力量は高い よく言えば ・評判が良いから真面目にアンケートに回答しなかった。 ・アンケート回答者の勘違いであった ・企業が審査に指導や改善提案を求めていてそれに応えている 悪く言えば ・対外広報のチェック機能が弱い ・組織ではなく個人の力量で持っている ・不適合を出さないので組織に好まれる |
認証機関の見識は高く、審査員層の力量も高い よく言えば ・認証機関内部の教育・コミュニケーションが良い 悪く言えば ・まぐれである ・小さな認証機関では回答者と審査員が同一である |
| 一 般 の 評 価 が 低 い |
認証機関の見識も低く、審査員層の力量も低い よく言えば ・審査の質でなく納期や費用などでサービスしている 悪く言えば ・審査員教育が不十分 ・対外広報のチェック機能が弱い 認定審査は大丈夫なのだろうか? いや、それよりも認定審査はしっかり見ているのだろうか? |
認証機関の見識は高いが、審査員の力量が低い よく言えば ・実は審査員の力量は低くなく、厳格な審査を行っている 悪く言えば ・認証機関内のコミュニケーションや教育が不足 ・アンケート回答者が理想を書いた |
JABやJACBの方々は、虚偽の説明をした企業の認証は取り消すという。 それじゃ、規格の理解が間違っている認証機関の認定は取り消すのだろうか? |
おもしろい! 
|
しょうちゃん様 毎度ありがとうございます。 笑っていただけてうれしいです。 笑っていられない人も多数いらっしゃるようで・・・ |
佐為さま なるほど、こんなに認証会社により対応や解釈が異なるとすれば、認証そのものへの信頼が揺らいでしまいますね。 意外だったのは、SGSやULなど、大手外資の試験会社が入っている点です。 日本法人とは付き合いがないので知りませんが、英語圏以外でも本社とのグローバル・コプライアンスの統一などが厳しく要求されており、発注契約や守秘契約書などは、全て英語版で結んだ覚えがあります。 となると、ISO認証は同社海外法人でも同じ解釈になるのか、それとも日本と海外法人で解釈が異なるかが、非常に興味があります。 表にある会社でグローバル展開をしている企業の海外での解釈を調べてみようかな.... |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 外資系なら本国と同じ規格解釈だろうと期待するところですが、そうでもないようです。 ところで、みながみな同じISO規格を読むのですから、解釈が異なること自体おかしなことですが?? 外資系認証機関との審査契約では「英文の契約書を正とする」なんて書いてあります。あれはカッコ良く見せるためなんでしょうか? |
なるほど、こんなに認証会社により対応や解釈が異なるとすれば、認証そのものへの信頼が揺らいでしまいますね。 何の不思議もありません。それどころか、同じ認証機関に所属する審査員同士でも見解が真っ向から異なることもザラです。例えばこんな笑い話のようなことが茶飯事でおこっている世界です。 審査員「何でこんなムダな記録があるんですか? 廃止してもいいのでは?」 事務局「はあ? ウチだってこんなもの要らないですよ。去年ウチに来たおたくの○○審査員に言われて仕方なく作ったんじゃないですか」 また、実に根本的なことでも認証機関によってまったく見解が異なることがあります。笑えない話ですが、これは実話です。 【質問】 規格本文の「注記」は要求事項か否か? 【回答】 A認証機関「注記は要求事項ではない」 B認証機関「注記といえども本文の一部であり、具体的な事項が記されている以上、れっきとした要求事項である」 ※ ちなみに、正解はA認証機関の方です。 |
たいがぁ様 ありがとうございます。 外資社員様に伝えておきます。 |
ぶらっくたいがぁ様 詳しいお話有難うございます。 同じ認証会社でも担当により解釈が判るとは、恣意的な解釈をしているとの証拠ですね。 認証会社の目的は、「指導」を行ってクライアントも自分も仕事が増えることが一番大事で、それが大事な仕事だと思いこんでいるのでしょうか。(笑) ところで、 規格本文の「注記」は要求事項か否か? 「注記」とあるからには、日本語訳ですよね。 それならば、本文も含めて日本語訳は参考資料と思うのですが、如何でしょうか? |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 「注記」ですが、ISO9001:2008序文で「『注記』と記載されている情報は、関連する要求事項の内容を理解するための、又は明確にするための手引きである。」となっております。 そして重大なことは、序文の『注記』は英語原文にはありません。 私はいったいどうしたらいいの? 本文の注記は英語原文にもありますが、shallではありません。mayとか、can beという表現になっています。 まあ、ドーデモいいことのようです。 でも審査でイチャモンつけられるとアドレナリン全開です。そんなアホ審査員叩ききってやるう〜 おっと、ぶらっくたいがぁ氏に確実に(ISO用語)伝えておきます。 |
外資社員様 以下、不本意ながらマニアックな話になりますが、参考にしていただければ幸いです。 「注記」とあるからには、日本語訳ですよね。 日本語訳にだけあるのではなく、英原文に記載されているものを和訳したものです。JIS規格票で日本語訳にだけある文章は、点線のアンダーラインが付いています。 ところで、私がA認証機関の方が正解と言った裏付けは、本件についてJABに問い合わせした際の回答でして、「注記は要求事項ではありません」という実に素っ気無いというか、単純明快なものでした。 あいにくその回答には理由までは書かれていませんでしたが、おそらくその根拠は JIS Z 8301(規格票の様式及び作成方法)にあると思われます。 最新版である JIS Z 8301:2008には、次のように書かれています。 3.21 注記 本文,図,表などの内容に関連する事項を別に分けて記載し,補足するもの。 6.5.1 本文の注記及び例 本文の注記及び例は,規格の理解又は利用を助けるための追加情報だけを記載する。 注記には,要求事項又は規格を利用するために不可欠な情報を含めない。 B認証機関は、JIS Q 9001:2008の改正説明会で、「7.6の注記には『意図した用途を満たすコンピュータソフトウェアの能力の確認には,通常,その使用の適切性を維持するための検証及び構成管理も含まれる』とありますから、2008年版審査で組織がこの構成管理を行っていない場合は不適合として指摘します」と言い切りました。 もちろん、これは誤りです。 もしこの構成管理を要求事項として扱うのであれば、本文の中に「構成管理も含めなければならない」と記載されている必要があります。よって、実際の審査においては、審査員は7.6本文に照らし合わせて合理的な理由と監査証拠を提示しなければ、不適合と判定することはできません。 このような根本的なことでさえ、認証機関自身が勘違いしているのが現実ですから、認証制度の信頼が揺らぐのは当然の帰結であり、組織が隠蔽とかインネンをつける前に認証機関がまず襟を正して抜本的な改革に臨むことが肝要であろうと思う次第です。 |
ぶらっくたいがぁ さま。 詳しいお話を有難うございます。 不適合を出すならば「合理的な理由と監査証拠を提示」というのは当然のことですよね。 ところで、、まだ不明な点があります。 ISOというならば、原典は英語版(またはフランス語版)で、日本語版はあくまで参考ですよね。 外国語原典の規則書ならば、日本語訳は本文も含めてあくまで参考資料となるはずです。 日本文を認証に適用しても問題がないとすれば、日本国内で解釈に合意が構成されていることが必要と思います。 それがない場合には、「合理的な理由と監査証拠を提示」が必要なら、とても良く判ります。 私が関係する技術規格でも、日本語訳があるものが多いですが、その合意を構成する為に 国内の委員会を作り そこで解釈の確認をしたり、問題があれば日本語版の修正や、原典を作った国際機関との確認や調整をしています。 また利用者との交流の為にセミナーなども頻繁に開きます。 ISO規格では、それらの広報をしているが認証機関でさえ勘違いをしているのかが気になります。 また、お客に対して「合理的な理由と監査証拠を提示」を提示できないことは、ビジネスとしてはありえないことで、それをやれるのは御役所か聖職者のような無謬性を主張できる立場の人だけでしょうね。(だから国のバックアップや法制化を期待する認証会社がいるのか?) 本来 文書管理や記録に厳格なはずの、ISO規格の審査者が合理性や解釈の合意の構成に無頓着ならば、規格の認証もその程度の価値だという証明になってしまうかもしれません。意図的に、合意の構成や合理的な理由の提示をしないのならば、認証機関が受験側が驚くような「御指導」により権威となることを大事にしたいのかと疑ってしまいます。(笑) 素人なりに思うのは、これだけ日本国内でも認証が進んでいるにも関わらず、解釈の合意が形成されていないのならば規格としては、まだまだ「こなれていない」のです。 ならば合理的な理由の提示こそが審査では重要で、それらを認証会社の壁を越えて共通の物差しとして積み上げることこそが、認証の価値を高めることなのだと思います。 |
私は何のためにISOについて書いているのか? その理由は簡単で明白だ。 私は日本のISO審査の現場から、ふざけた審査を追放したいと考えている。 たとえば、もう4年くらい前になるだろうが、CEARの季刊誌に「環境目的の実施計画と環境目標の実施計画が必要」と書いていた審査員がいた。その審査員を私は知っていたが、彼は実際の審査でもまっとうな審査をしていなかった。思い込み、偏見、押しつけ、そんな審査だった。 それはその審査員だけではない。 今でも「環境方針に『社外に公開する』と書いてないから不適合である」なんて、もう気が狂ったとしか思えない審査をしている審査員がうじゃうじゃいるのが現実なのだ。 組織が虚偽の説明をするからISO認証の価値が落ちているなんて論は、まったく事実と異なる、うわごと、たわごとなのである。 私はそういう世界に薄ら20年生きてきた。そしてそんなことは絶対に是正しなくてはならないと考えている。 ISO規格を貶めているのは、規格を理解していない審査員、判定委員、認証機関、そしてそれを取り締まることのできない認定機関なのである。 そして現実をしらずに妄想を語っている大学教授に責任があるのだ。 この悪循環を断ち切り、ISOの価値を高めるためにはISOに関わっている我々すべてがそれぞれの立場で誠心誠意、そして最善を尽くして行動しなければならないと考えている。 ISOが大好きな人がいる。しかし、ISOに淫してもだめだ。ISOは目的じゃなく手段なのだ。企業を良くするために存在し、そして最終的に社会に貢献しなければ意義も価値もない。 みんな行動しよう。 おかしなことには、おかしいぞと裸の王様に出てくる子供のように声を上げよう。 我々はこ利口になってはいけない。愚鈍でも誠実であれば神は微笑んでくれるだろうと確信する。 |
佐為さま あけましておめでとうございます。湾星ファンです。 さて、認証機関の勝手格付けであります。本日、今年初出社にして、ようやくアイソス誌1月号を読みました。こんな記事が業界紙に出ては、さぞ認定機関は大騒ぎになっているに違いない・・・だって、規格の基本的な理解・解釈が認証機関でこれほどバラツキがあるということは、杜撰な認定審査がなされることの証左であり、直ちに是正処置が為されて当然、と思うわけです。 それが、全くのノーアクションということは、問題の深刻さを全く認識していないか、認識していても為す術が無いので放置したか、放置しても問題ないと認識したか、のいずれかですよね? つまり、審査の席では、不適合に対する是正や予防処置を偉そうに「指導」かます連中が、不適合の扱い方を知らないということを露呈し、自ら「審査登録証は無価値である」ことを証明した、と思います。 なんて頭に血が上ったのは、一瞬で、悲しくなりました。認証件数の減少が受審組織の虚偽説明が原因なんて、妄想するような方々がマトモと思うことが間違っているのでしょう。もはや、第三者審査制度は、誰からも相手にされなくなること必然です。ISO自体は、決して悪いものでは無いと思いますが、銭儲けにしか関心の無い、有象無象のセイで、ISO自体の価値まで否定されることに思いを致すと、なんともやりきれない。「おもしろい」とか茶化している場合では無いのでは? 新年早々、辛気臭いネタで恐縮です。 本年もよろしくお願いします。 湾星ファン |
湾星ファン様 あけましておめでとうございます。 いやいや、認証機関はノーアクションというわけでもないでしょう。アイソスの2月号にはドリフのように泣きが入って、「もう一度勝負させてくれ〜」とか「再度受験させてください」という認証機関目白押しではないのでしょうか? 2月号発行まであと数日ですから楽しみにしていましょう。 認証件数の減少ですが、今年挽回できなければもう回復の余地はないでしょうね。 私は認証制度の体制内ではありませんが、認証の信頼性向上、価値向上に反対ではありません。 私なりに活動していきたいと思います。 このウェブサイトも認証する側への叱咤と激励のつもりなのですが・・ |