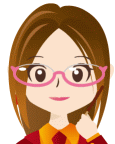12.07.28
本日の出し物は、同志ぶらっくたいがぁ様からのご注文によるものです。ISOケーススタディシリーズとは
環境保護部の出勤する順序は、横山が一番で山田が二番目だ。その他のメンバーは始業10分前くらいにどっと顔を出す。
横山も山田も混む電車は苦手なので、少しでもすいている時間帯と思って7時過ぎには出勤するのだ。7時といっても混雑はしているが、それほどではない。
一度山田は廣井に通勤の混雑は気にならないのかと聞いたことがあるが、しょうがないよという答えだった。
というわけで、今日も山田が朝会社に着くと、横山が一人で仕事をしている。
山田の顔をみると、横山が話しかけてきた。
「山田さん、環境保護部の部門のメールアドレスにメールがありまして、ISO認証機関との契約書の更新なんだそうですが、その文言が変だという相談がありました」
| |||
「はい、それで・・・」
| |||
「この案件は私に任せてほしいのですが、よろしいでしょう?」
| |||
「ちょっと内容を見せてください」
| |||
横山はプリントしたものを山田に差し出した。
| |||
「へえ、この会社はけっこうまっとうだね。普通の会社はISOの審査契約書とはこんなものかと思って疑問を感じないよ」
| |||
「調べましたが、この鷽山形機械は2年前に日系の○認証機関から、外資系のこのHTML社に鞍替えしたのです。だからふたつを比べてその違いに気が付いたのでしょう」
| |||
「それで、横山さんはこれらの項目についてどうお考えなのですか?」
| |||
横山は各項目について見解を述べた。それは一般的な商慣習からいって妥当だと思われた。
| |||
「よしわかった。私には異存はないが、ふたつ条件がある。 まず横山さんの上長は中野さんなので、中野さんの了解を得ること。 もうひとつ、僕が同行する。但し、交渉はすべて横山さんに任せる。 それと条件ではないが、事前にHTML社に連絡して、鷽山形の代理人として会ってもらえるか否か確認すること。ダメな場合は、鷽山形から任意代理人とする委任状を取ること」 | |||
「了解しました」
| |||
横山はオーラを発しはじめたようだ! 横山は中野の了解をとり、HTMLに連絡して了解をとった。そして山田に明日の午後16時から行きましょうといってきた。 ●
午後4時といっても暑さは日中と変わらず、地下鉄を降りて目的地まで歩いて10分もかからないのだが、それだけ歩いても汗は流れ、二人は汗を拭き拭きHTMLの入居しているビルに入った。● ● 二人が行くと営業部長の宗像 双方名刺交換して着席 | |||
「既にいきさつはご連絡した通りですが、弊社の子会社である鷽山形機械は御社と審査契約を結んでいます。今回、御社の方から審査契約書の更新の申し入れがあり、その文面の内容について鷽山形機械が納得できず改定を求めているとのことです。なにぶんにも山形からここまでは訪問するのも大変ですので、このたび私どもが任意代理人として御社と交渉させていただきます」
| |||
「いきさつはおっしゃる通りであることを確認しました。弊方としましてはお客様が多いものですから標準的な契約書を作成し、それで契約をしていただくようお願いしております。ご意見ありましたことについても、こちらとしましては標準形で問題ないと考えており、ぜひ原状で締結していただきたいと考えております」
| |||
「御社のお考えは分りました。しかしながら契約というものは1対多数というものではありません。私どもとしては御社と1対1で契約するのであって、他のお客様がどのような見解があろうと関係ありません」
| |||
「いや、多くのといいますか、鷽山形さん以外のお客様はこの文面で了解されているので、特段問題はないと考えております。鷽山形さんにもご了解いただくようお願いします」
| |||
「契約は甲乙の合意に基づくものであって、第三者の意思は無関係だと思います。御社が変更する意思がなければ、弊方としましてはこの審査契約は結べない。よって他の認証機関と契約するという選択しかなくなります」
| |||
「ちょっとお待ちください。まず現行の契約書の文言がそれほどに不都合なのでしょうか?」
| |||
「一般論では話が進みません。個々の問題点について議論が必要です。私どもとしては、見直しをお願いする箇所を提示しているわけですから、各論に入ってよろしいですか」 山下課長は営業部長の顔を見ている。向こうは各論に入る前に要求そのものを否認して追い返そうとしていたようだ。 | |||
「分りました、個別論を伺いましょう」
| |||
「一番目は、審査報告書の所有権についてです」
| |||
「おお、これはISO17021にもありますし、JABのルールでもありますので、納得していただくしかありませんね。『ISO17021:2011 9.1.10.1 審査報告書の所有権は、認証機関が維持しなければならない』と定めてあります」 先方二人はにっこりと、これで参っただろうという顔をしている。横山は、この二人はどういう考えをしているんだろうと思いながらもにっこりとほほ笑みかえして話を続けた。 | |||
「それは存じ上げております。しかし甲が現実にこの契約を遵守できるかどうかを考えてみてください。もし認証を受けていた会社が倒産したら、審査報告書の回収なんて不可能です。このたびの東日本大震災のような場合でも免責事項となっていません。災害の場合は特に許すなんて、お情けをいただくことはおかしいですね。 まして契約書には期限がありませんから、10年前20年前の審査報告書の返却を求められても対応できないでしょう。これは実行不可能な条項ではないですか。 また審査を受けた組織が審査費用を払った対価として受け取った報告書の所有権がなく、認証機関の都合によって返却を求められるというのはおかしいですね」 | |||
「では横山さんはどのようなご希望でしょうか?」
| |||
「そもそも審査報告書というものはどれかという定義も定かではありません。他の認証機関ですが、審査報告書の原本は認証機関内の判定委員会に提出する『もの』であると考えて、審査を受けた組織に出す『もの』はその写しという考えをしているところもあります。 それに倣って認証を受けた組織には審査報告書の写しを提出するとしたらどうですか。但し、認証を受けた組織は、客先から審査報告書のコピーの提出を求められることがあります。ですからその場合、コピーの再コピーの提出になりますが、それは問題になりますかね? あるいは現物に「COPY」の識別をせずに、御社が客先に渡すものは写しであるとみなせばそれまでと思います。どちらにしても審査報告書は私文書に過ぎず、行政の作成する公文書じゃありませんから、大騒ぎするような問題じゃありません」 | |||
「ほう、そういう認証機関もあるのですか。うーん、ちょっと検討させてください。必要ならJABやUKASと相談します」
| |||
「分りました、来週でもまたお邪魔することにしましょう。それまでにお願いします。 次は非常に単純な話ですが、著作者人格権ってなんでしょうか?」 | |||
「おい、山下君、この文章の著作者人格権とはどういう意味なんだ?」
| |||
「はあ、この契約書の原文は近藤さんが書かれたものでして、近藤さんはここに来る前は〇社の法務部にいて契約書に詳しいということでしたので、私はまったく・・」
| |||
「ご存じと思いますが、著作者人格権はみっつから構成されます。ひとつは氏名表示権で作品を書いた人の名前の保護、ひとつは同一性保持権で改変されないこと、もうひとつは公表権で外部へ公表する権利です。そして法的に、著作者人格権は譲渡することができません。よって、この契約書に著作者人格権を御社が保持すると記述することは意味のないことです。削除した方が良いです」
| |||
「実はですね部長、この件に関しては内部でもおかしいのではないかという声があったのですが、近藤さんの言うことに間違いはないだろうということで今まで来ています」
| |||
「弊社の顧問弁護士と相談して決めさせていただくということでよろしいでしょうか」
| |||
「それで、けっこうです。 では三番目ですが、契約書には疑義が生じた時は英文を基にするとありまして、末尾には裁判は御社の本部があるイギリスのロンドンで行う旨が書いてあります。これについて、そもそも英文の契約書をいただいていません。よって英文の契約書を確認して、それに双方がサインすることが必要だと考えます」 | |||
「当社グループはグローバルに認証事業を行っておりまして、どこの国でも契約書は英文を基本としております。ただ日本の皆さんは英文ではわかりにくい、特に契約関係については理解が難しいので全く同じ意味で日本語にしたもので契約していただいています」
| |||
「そうですか、でも日本語のものと英語のものが同じ意味かどうかは、こちらが読まないとわかりません。日本語の契約書に英文の契約書を基にするってあるのですから、うかつに日本語の契約書にサインできませんよね。それに双方がサインした英文契約書を保管していないということは、あとで英文の内容が変更される恐れがあるじゃないですか」
| |||
「まさかそのようなことはありませんよ」
| |||
「契約の重みってご存知でしょう。とりあえず英文の契約書を見せていただきましょう。話はそれからです」 横山はそう言って机をバーンと叩いた。先方の二人はギョットした。 山田も横山の行動に驚いた。横山は組合役員がお似合いかもしれない。あるいは極道の妻(おんな) が似合いか? やりすぎると脅迫だよ・・・これは
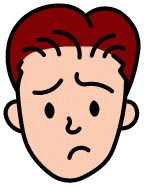 | |||
「山下君、英文の契約書を持ってきてくれや」
| |||
数分後、山下課長が書類を持って現れた。 横山はそれをさっと取り上げて広げた。山田は横山の肩越しにながめた。 山田は英語が苦手だが、横山はどうなんだろう? | |||
「はあはあ、この英文の契約書は日本文とだいぶ違いますね。英語が読めなくても一目でわかります。だって条項の数が日本文のものよりもはるかに多いですから。それに斜め読みですが、著作者人格権て、たぶんmoral right of authorだったはずですが、英文の契約書にはそのような語句はありません。 このような英文と日本文が異なるにもかかわらず、日本文の契約書を締結して、問題があった場合英文を基にするというのはインチキ、まさに詐欺じゃありませんか」 | |||
「詐欺ですって! それは言い過ぎでしょう」
| |||
「そうでしょうか? 詐欺とは、人を欺いて財物を交付させること、財産上不法の利益を得ることって刑法246条に書いてあります。御社の顧問弁護士にご確認してください」
| |||
「オイオイ、山下君、これはいったいどうなっているんだ?」
| |||
「はじめは英文をそのまま日本語に訳したのですが、その後、日本文をいろいろと修正して原文とのずれができてしまったようです」
| |||
「すぐには結論が出ないようですから、次週お邪魔したとき伺います。 次ですが、審査の都合が・・・」 | |||
「ああ、これは御社の、いや鷽山形さんの要望はよく分ります。盛り込みましょう」
| |||
「そのときは当然、英文の契約書も変更になるんでしょうねえ〜。あるいは英文の契約書によるという文言を削除するのかしら。 もう1件ですが、裁判はイギリスで行うとありますが、これは御社の本社所在地である東京都しましょう」 | |||
「確かに、横山さんがおっしゃるとおりですね。契約の当事者はイギリスの本部じゃなくて、日本法人である当社ですからイギリスで裁判をする意味がなさそうです。 おい、山下君、これはどういういきさつなんだろう」 | |||
「そこは英文そのままです」
| |||
「横山さん、これは当社で検討させていただきます」
| |||
「次は、ISO17021に基づくことを盛り込むことですが・・・」
| |||
「それは認証制度によって担保されていると考えます。我々は認定機関の認定を受けて事業を行っておりますので、わざわざ個々の契約書に盛り込む必要はないと考えております」
| |||
「御社との審査契約は、基本的に民民の契約ですから、書面で取り交わしたこと以外拘束力は持たないと考えます。御社がISO17021に基づいて審査を行うということは、認定機関の認定条件でつまるところ認定機関と認証機関の契約です。ですから、もし御社がそれに則っていない場合、認定機関は契約に基づき御社の認定取り消しにすることはできるでしょう。しかしそのとき弊方が御社を訴える法的根拠がありません。 もし、認証制度で我々が訴える権利が担保されているとおっしゃるのであれば、どこで保証されているのか教えていただけますか」 | |||
「あのうですね、何もない時点で、裁判とか法的根拠など物騒なことを考えることもないでしょう」
| |||
「何もない時点とおっしゃるなら、この契約書にロゴマークや登録証の不適正な使用があった場合、認証の停止または取り消しを行うと書いてあるのも、物騒なことですね。 実はそれもISO17021:2011に書いてあります。(8.4.4) 同じくISO17021で定めてあっても、甲が誤った行為を行った時は乙がその責任を追及する権利は契約書に明記し、乙が誤った行為を行った時は甲が責任を追及する権利を契約書に記載しないというのも不思議なことです」 | |||
「・・・」
| |||
この営業部長は、このようなことを疑問を持たれることを考えたこともなかったのだろう。 認証機関は契約不履行しないのは当たり前のことではないか、いや社会はそれを当たり前と認識すべきだと、上から目線で考えているのだろうか? 横山の話を聞いて、心中怒り狂っているのかもしれない。 | |||
「最後でございます、認定審査員の守秘契約についてですが・・・ 鷽山形社は製造メーカーで企業秘密もあります。御社の審査員の場合は、プロパーであろうと契約審査員であろうと御社と守秘契約をする旨、契約書に記載してありますが、認定審査員については一言もありません。これは普通の商取引では考えられないことです。当然守秘契約を入れてほしいと思います。」 | |||
「これは我々が決定できることではありません。認定機関の問題です」
| |||
「弊社は認定機関といかなる契約関係もありません。御社に対して要求するしかありません」
| |||
「一般の会社さんからそのようなことを言われたことがありません。 認証審査員ももちろんですが、認定審査員は業務上得た情報を口外しないことを信頼していただけませんんか」 | |||
「信頼で済むならば、ISO審査でもエビデンスを見る必要はありませんね。昔の話ですが、三重県のISO認証機関が認定取り消しになったのは、審査でエビデンスを見ずに相手の回答だけでOKしたからだったはずです。もし審査において審査員の質問に当方は口頭で応えるだけで良いのであれば、当方も秘密漏えいの危険性が大幅に減少しますからそうしましょうか」
| |||
「そこまで性悪説というのはどうでしょうかねえ?」
| |||
「審査も契約にも性善説も性悪説もありません。客観的で妥当なものであることが必要です。まさか、この要求がおかしいとは、お宅の顧問弁護士も言わないと思いますが」
| |||
「正直言いまして、これは弊社内部で決定できることではありませんので、認定機関との調整がいります」
| |||
「そうですか。じゃあ、調整してください。このようなことは普通の企業でしたら当たり前です。もし外部の者が社内に立ち入る場合、入場者が守秘義務を負うことの契約を結ばずに問題が起きた場合、担当者も決裁者も善管注意義務を怠ったと責任を問われるでしょう。状況によっては背任になるかもしれません。 それに、ないとは思うのですが、認定審査員が外国人・・正確には非居住者である場合、外為法の規制を受けます。とするとこの条項に『認定審査員は外為法で定める居住者に限る』と追加が必要です」 | |||
「外為法ですか・・・」
| |||
宗像部長は驚きの声を上げた。
| |||
「外為法違反はISO認証の不適合とは違い刑法犯で罪は重いですからね。その場合、御社だって無関係ではありませんよ。認定機関を含めて取り調べを受けるでしょう。 次回の予定ですが、なるべく早く処理することを依頼されておりますので・・・今日は木曜日ですか、来週の金曜日あたりではいかがでしょうか?」 部長と山下は顔を見合わせた。 | |||
「非常に難しい問題ばかりでして、とても1週間では結論がでそうありません」
| |||
「鷽山形社は既にひと月以上も前から、御社にメールで問い合わせしていたわけですが」
| |||
「横山さん、お話は承りました。当方にて検討しまして、次回日程については一両日中に回答いたします」
| |||
「わかりました。鷽山形社も御社と審査契約を止めたいわけではありませんが、御社が対応できない場合は、認証機関の移転はやむを得ないと考えております。認定機関と調整がつかない場合は認定機関を変えるということも考えております。よろしくお願いします」 ●
まだ1時間も経っていなかった。外はまだ日差しも暑く、更に足元はアスファルトからの熱が暑かった。
● ● | |||
「山田さん、どうですか、今日の交渉は?」
| |||
「うーん、立派としか言いようがない。私の心配というか懸念は、横山さんが調子に乗っていつか転ばないかということだよ」
| |||
「なにをおっしゃる山田さん、そんなドジはしませんって」
| |||
だが山田は、横山が天狗になって、いつかとんでもないミスをするのではないかという気がするのだった。
|
私がこんなことをしてきたのかという、ご質問があるかもしれません。
まず、このような契約書があったことは事実です。もちろん一つの契約書に上記課題が全部あったわけではありません。何社もの審査契約書に、これ以外も含めていろいろなおかしなことがありました。みなさんの組織が今現在契約している実際の契約書も大差ないはずです。審査契約書なんてしげしげと見たことがないかもしれませんが、これを機会によくご確認ください。あれっと思うような文言があったり、あるべき文言が無かったりしませんか?
過去に私はそんなおかしな点について、認証機関に対して見直しを求めたことはありましたが、要求しても半分くらいしか対応してもらえませんでした。横山のようにゴリゴリと改善を求めたことはありません。まして、机を叩いたり大声を出したこともありません。紳士だったからではなく、気が小さいからでしょう。私は極道にはなれそうありません。
次回は当然、横山がこけるお話です。そうでなくっちゃ、物語がつながりません。
いよいよ認証機関や認定機関から刺客が送られそうだ。定年後は暇をみては木刀を振っているから返り討ちにできるだろうか?
坂本竜馬のように、むざむざとは斬られないぞ!
ぶらっくたいがぁ様からお便りを頂きました(2012.07.28)
たいがぁです。 リクエストに応えていただき、ありがとうございます。 次回は当然、横山がこけるお話 つーことは、HTML社が反撃に出るわけですね。楽しみですー。 |
たいがぁ様 まいどありがとうございます。 HTML社が反撃に出るとは考えていませんでした。だって反撃しようないと思いますから、 横山がこける話は、それとは別のテーマでと考えていました。 |
名古屋鶏様からお便りを頂きました(2012/7/28)
審査機関の選択権を持たない我々にとっては(それって第三者か?)契約書ってのは正直タダの隷属宣言書ですね。そこに何が書かれていようと「イヤ」と言えないのですから。 それにしても横山女史は異常に法律に詳しいですねw バックグラウンドが気になるトコロではありますが。さて、これがどうコケるのか。楽しみにしております。 |
鶏様 毎度ありがとうございます。 業界のしがらみで依頼する認証機関が決まっているとしても、おかしな契約にはいちゃもんつけるべきでしょうし、つけなければ職務怠慢と思います。少なくても私はそう思いますし、そう行動してきました。 いや、認証機関が決まっているならばこそ、改善要求をするべきでしょう。選択権があるなら改善要求しなくても鞍替えすればよいわけですから。 ただ私は複数の認証機関との付き合いもありましたし、業界設立の認証機関との付き合いもありまして、勉強になりました。いや勉強というよりもいろいろとトラブルがあってためになったというべきでしょうか。 横山が語っていることは、異常に詳しいなんてことありません。どこでも外国人の見学とかあればその手続きをしているはずです。海外駐在の人が出張で帰ってきただけでも、外為法では非居住者として情報や物品の持ち出しを管理しなければなりません。そんなことのほうがISOなんてものよりもはるかに重大深刻です。 |
外資社員様からお便りを頂きました(2012.07.30)
横山さん 大活躍ですね。 頭の良い人は、結構 理屈で攻めてゆきますが、ある程度の容赦をしないと相手との関係もありますので、難しい問題になる場合もありますね。 むしろ欧米系の会社ですと、契約では理屈は理屈と切り分けられますが、この事例では外資系日系企業とは言えかなり理屈で押されっぱなしです。 私も会社では法務担当をしているので、この手の契約はの調整は仕事でやっています。 横山さんの言い分は、いちいちごもっともですから、私ならばその場で殆ど受け入れて文言も決めてしまいます。 但し、4項の損害賠償については、彼女の言い方は変で、契約書に記載があろうがなかろうが、損害が発生すれば相手に請求する事は可能です。 それが無いからと言って、請求出来ないと思っているならば間違いですね。 乙が求める 支払い遅延損害金等は、予め利率や損害金を定めるから、契約の中で必要なのです。 ですから、私ならば、4項の甲の損害賠償権については、3項と同じで言わずもがなの事と思いますけれど。 もちろん、認定に問題があった場合に予め損害を定めたいのならば、話は異なります。 せっかくですから、審査会社側の立場にて追加です。 もし、私が言われている立場でしたら、「他社に変える事も考えなければ」という彼女に対して「それは、仰るような請求を受け入れなければ 仕事を出せないという意味ですか?」と切り返します。 まともな下請法の教育を受けた人ならば、自分の言い方の危険に気づくでしょうが、彼女がそれに気付けるかは興味深いです。 あと一点 横山さんに切り返すとすれば、彼女は「自称代理人」にしか見えない点です。 話の説明のに記載しなかったかもしれませんが、子会社の代理として交渉するならば、自身が任意代理人である事を示す委任状等を示す事は、始めに行うべきです。 もちろん、事前のいきさつの中で、それは提示済、合意済ならば余計な話でした。 横山さんの高転びにこける話も楽しみにしております。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 実を言いまして、過去の事例から推測して外資社員様から法律的なツッコミがあると予想していました。 では、横山に代わりまして・・・ 4項ですが、実は私の体験による思い入れもあるのですが、法的に訴えることができるできないということだけではないのです。「甲(企業)が契約違反したとき乙(認証機関)が甲に対しての損害賠償請求する」と書いてあり、「乙が契約違反したとき甲が乙に対する損害賠償請求が書いてない」こと、延滞金なども甲についてのみしか書いてないなど、おかしいと思います。私はこういった乙に都合の良い偏りを許容できませんでした。今もですが。何事も認証機関の文章というのは上から目線が気に入りませんでした。 審査に異議申し立てできるということさえ書いてない契約書は多々ありました。そういうことはISO17021を根拠に異議申し立てできると考えることもできるかもしれませんが、はじめからバシッと明記しておくことが、審査員にたいする示威行動ともなり、審査に対して圧力をかけることができると考えていました。もっともこちらが上位になるという意味ではなく、対等の立場であると審査員に認識させるという意味です。審査員から組織側は下位と思われているのが現実でしたから。 また、認証機関から審査に来る認証審査員については忌避できることが明記されていますが、認定機関から審査をチェックに来る認定審査員については、「忌避できない」と書いてあります。認定審査員であれば、どのような人であっても企業が断れないのでは立ち入られる企業としてはたまったものではありません。 ただ、私の経験では一度だけ認定審査員が来るという通知がありましたが、その後先方の事情で来なかったことがありました。認定審査員が陪席する確率は非常に低いのかもしれません。 外資社員様は私の経歴をご存じないでしょうけど、圧倒的に弱い立場に置かれていたのを、なんとか対等の条件にしようという歴史でした。 下請法の件、役務提供の場合、自社資本金が5000万以上であれば5000万以下の企業・個人事業者に発注した場合、自社資本金が1000万以上であれば1000万以下の企業に発注したときに適用されます。鷽機械工業はお話の中で資本金が数百億あるいはそれ以上と推定されますが、鷽山形はたぶん1000万程度でしょう。そして認証機関は資本金1億以上です。なにか基準があるのかどうかわかりませんが、それ以下という認証機関はないようです。だから単純に下請法に該当するかどうか考えると非該当になります。 しかし資本金からは下請法の対象としても、ISO審査には適用されないでしょう。というのは審査契約は自動継続ではありません。認証を受けていても、次年度以降もその認証機関に発注するという約束をしたわけではありません。毎年今年の審査の見積もりを出してくるので、それを受けて審査を受けるか否かを回答することになります。ですから、今年は発注しないという回答をすることは、下請法が適用されたとしても違反ではありません。 また、この場合は認証機関が契約書を見直すことを提案しているわけですから、それには同意できないと契約を更新しないことを告げても下請法には関係ありません。 同様に認定機関を変えることも認証を受ける組織の自由です。そのため対外的な宣伝効果がなくなるかどうかはもちろん組織の考えることです。 自称代理人については、初めに山田がHTML社に代理人として会ってもらえるか、必要なら委任状をとっておくこととしておりました。ですから話の流れからして、HTML社は横山を委任代理人として了解したことにしています。 ということでいかがでしょうか? |
外資社員様からお便りを頂きました(2012.07.31)
おばQさま お相手有難うございます。 横山さんが代理の立場をもっている点と、本件では下請け法に該当しないとの点は了解しました。 なるほど、認証会社の殆どは、一億円以上の資本をもっているのですね。 設備も不要でオフィスがレンタルなら、それほど資本は不要とも思えますが、事実ならその資産内訳は興味深いです。 私自身も、「これが定型の契約だから変えられない」という「上から目線の話」を聞くたびに、その会社の法務は仕事をしていないと思うし、そうした会社のコンプライアンスとは何だろうと非常に疑問に思います。 なぜなら 会社の環境、外部事情は、常に変化しますので、「定型をもって良し」とした時点で、状況に合わせたコンプライアンスの実現などは不可能ですから(笑) 委託業務だろうが、契約は相互対等で行われるもので、ましてやISOでは認証会社は委託先ですから、本来は弱い立場のはずです。 事実、私の会社は、客先の定型契約を受け取って、問題点を修正依頼をします。 殆どの場合は、おばQさまと同じで「定型だから変えられない」と言われます。 ところが、覚書や、メールで解釈の確認を求めると、あら不思議 これは簡単に認めてくれます。 会社によっては、担当が法務をすっとばして解釈を開示してくれます。(いったい法務は役割は???) 当然ながら、民法の契約規定では、相手側は誰が代表であるかは問題にしませんので、その会社の窓口が解釈を提示し双方が合意すれば、口頭だろうがメールだろうが、覚書だろうが、有効になります。 ここまで書くと、似たようなものが、日本国憲法である事に気づきます。 制定から五十年以上を経て、未だに内容の変更はされない、出来ない。 解釈をあれこれ変えながら、なぜだか環境や時代の変化に合わせて変えてはいけないし、それが「護憲」だと信じている人々もいます。 どうやら定型文が好きなのは、上から下まで同じなのかもしれません。 |
外資社員様 まいどありがとうございます。 認証機関の資本金は最低1億以上というルールがあるようです。根拠はわかりません。 契約書が定型の附従契約であるということは、保険などのように行政の監督下にある場合を除き、合理性がないと思います。 とはいえ、現実には長いものに巻かれて、煙に巻かれて、首を絞められているのです。 |
ケーススタディの目次にもどる