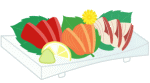13.10.20
マネジメントシステム物語とは
「マネジメントシステム」という言葉はISO9001:1987にはなく、1996年にISO14001で初めて使われて、そして大流行した言葉である。じゃあそれはまったく新しい概念なのかといえば、そんなことはない。そこで書いていることは昔からどの企業でも大なり小なりしていたことにすぎない。ただISO規格のように特別に環境だけとか品質だけを取り出して大書していた会社は少なく、また表現が異なっていることもあった。 だがISO規格で「マネジメントシステム」という語をみたとき、多くの人はまったく新しいアイデアであるように受け取ってしまった。そして「システム構築」とか「システムを導入する」などという、おかしな言葉、言い回しが使われるようになった。更にはISOで会社を良くしようという発想(妄想)を持つ人まで現れた。 この物語では、そういう勘違いを正すために、 ここで書きたいのは、ISOについてではありません。マネジメントシステムについてです。マネジメントシステムとISOとは直接関係ありません。ISOが出現する以前から、組織があればそこには必ずマネジメントシステムというものは存在しており、その本質は昔から変わっていません。 ISOMS規格に書いてあることは昔からやるべきことであったということ。ISOなどあってもなくても会社がなすべきことは変わらないのです。ましてISOに会社を合わせるとか、ISO規格に合わせてシステム構築するなんて論はまったくのデタラメです。 このシリーズのボリュームとしては30回くらい、週2回として4ヶ月くらいを予定しています。といってもみなさんからチャチャが入れば、ストーリーはそれを受けて流れていきますので、どうなりますことやら・・・ なおこれはフィクションであり、私自身の物語ではありません。いや、そうかな? |
この物語は20数年前の1990年に始まります。当時の日本はバブル満開、そしてISO9001などは口の端にもあがりませんでした。
 佐田です。 山田太郎同様 ご愛顧をよろしく |
佐田の勤めているのは東証一部上場している
佐田は高校を出て入社して20年、まじめに働いてきたし仕事においてはそれなりの、いや人並み以上の成果を出してきたと自負している。ただ本人も自覚しているが、社内コミュニケーションは得意ではない。まして上長におべっかを使うなんて無縁である。お歳暮など届けたことはないし、マージャンで上役にわざと振り込むなんてこともしたことはない。そういう点では社会通念が不足していると言われてもしょうがないかもしれない。
10年前係長の試験を受けた時、高卒同期では最初に係長の資格を得た。低い職階では仕事の成果で判断されたのかもしれない。しかし職階が上ると、社内の評価や昇進は仕事の成果だけではないと十二分に思い知らされた。「何年入社組」とか「修士何年入社」なんて言い方を知り、そういう観点での人事処遇がされているのを知った。高卒で課長になろうなんてのは、身の程を知らずと陰で言われているのも聞いた。
だが佐田は一生懸命働いているのだから上を狙うのは当然であり、評価されるのも当然だろうと考えていた。それが努めている会社の文化というか風土に合わないかどうかなどを考えたこともなかった。ともかく今回は3度目の受験で、なんとか合格したいものだと心底願っていた。高卒同期でも既に何人も合格しているのだから。
朝一番に川田部長
 のところに行けと課長から言われた。これは不合格という意味であることを佐田は知っていた。合格者は同じ時刻に工場長の部屋に呼ばれるのだ。
のところに行けと課長から言われた。これは不合格という意味であることを佐田は知っていた。合格者は同じ時刻に工場長の部屋に呼ばれるのだ。佐田はともかく部長室に行った。
「やあ、佐田君、かけたまえ。今回も残念ながら君は課長試験が不合格だった。」
| ||||||||
「そうですか」
| ||||||||
「もう受験するのは止めたまえ。はっきり言って君が合格することは難しい。この試験は学力試験じゃない。というかそもそも試験じゃないんだ。会社が幹部にすると決めている人を合格させるのだから。君は幹部候補とみられていないということを認識すべきだ」
| ||||||||
「わかりました。ひとつお願いがあります」
| ||||||||
「なんだ?」
| ||||||||
「職場を変えてください。私は今まで現場で係長をしていましたが、今回のことを受けて心機一転して、まったく別の仕事に就きたいと思います」
| ||||||||
「まあ、その気持ちはわかる。すぐに対応は難しいが、いきさつから希望に沿うように考えておく」
| ||||||||
それで面談は終了した。
●
佐田は正直これが世の中の仕組みなのだろうと思う。江戸時代は士農工商というい大きな区分だけでなく、侍といっても更に下士と上士と身分があって、下士は下駄を履けないとか傘をさせないとかいろいろ差別があったという。それと同じく、高卒なら特別の者以外課長になれないのは分っていたことだ。ただ自分が特別の者に入っていると思っていたのも事実だけど。● 昼休みに同僚から高卒同期の鈴田が課長試験に合格したと聞いた。佐田は正直驚いた。あいつは生産計画を担当していたはずだが、特段なにか大きな仕事をしたということもない。特許も取ったこともないし・・と思った後、人間関係かと砂を噛んだような気持になった。 さらに追い打ちをかけたのは今日付けの人事異動で、課長職の資格試験に合格したばかりの鈴田が課長になったことだ。 佐田は頭がもうろうとして、もうすべてがどうでもいいような気がした。 そして仕事はどうでもいいと思えて、定時になるとまっすぐ家に帰った。 ●
●
直美は佐田の顔色で、試験がだめだったということを悟った。 | ||||||||
「どうしたの元気ないじゃない?」
| ||||||||
「例の件、ダメだったよ」
| ||||||||
「また来年があるでしょう」
| ||||||||
佐田は川田部長に言われたことを思い出した。試験を受けても合格しないだろうとまで言われたなら、今後受験するのは無駄なことだ。だけどそれは直美に言うべきじゃないと思う。
| ||||||||
「そうだね。鈴田って知っているかい? 俺と同期の奴なんだけど」
| ||||||||
「先週末、みんなでスーパーに買い物に行ったとき、会ったわね。向こうも家族連れだったでしょう」
| ||||||||
「そうだそうだ。奴は試験に合格したんだ」
| ||||||||
「そう、でもねたんだりしてはダメよ。お祝いを言ったの?」
| ||||||||
佐田は、直美はおれには過ぎた嫁さんだといつも思っている。今もそう思った。
●
半月後、佐田は製造係長を解任になって品質保証課に異動になった。● ●
佐田の新しい上司は野矢課長である。職人気質の人で、人を使うよりも自分が仕事をするのが好きらしい。 | ||||||||
「ここは品質保証をする仕事だ。品質保証ってどんな仕事か知ってるかい?」
| ||||||||
「いえ、知りません」
| ||||||||
「そうなんだよなあ、そもそもこの工場は一般消費者向けの量産工場だったろう。そういう業種では品質保証っていう概念は無縁なんだよね」
| ||||||||
「まったくの素人で申し訳ありません。つまり品質保証とは特定顧客向けの製品にのみ存在する仕事なんでしょうか?」
| ||||||||
「そうでもない。お客さんが製品仕様だけでなく、製造工程にいろいろと注文を付けることがある。品質保証協定なんてことを聞いたことがないかい?」
| ||||||||
「あります。私が作っていたのは一般消費者向け製品でしたけど、OEMだったので客先から品質保証協定を求められたケースがありました」
| ||||||||
「おお、それは話が早い。それだよ、それ。お客様が製造工程とか調達先の管理なんてのを要求するのが品質保証協定で、それをしっかり実施することと、ちゃんとしていますよとお客様に説明するのが品質保証というわけさ」
| ||||||||
「なるほどそう教えていただくと簡単明瞭ですね。もちろん仕事そのものは簡単じゃないということはわかります」
| ||||||||
「つまり品質保証とは品質を保証することでもなく、品質を上げることでもない。お客様と約束をしたことをちゃんと守っていますよとお客様に説明することなんだ。 製品が少数の時は納入時に立ち会いを受けるし、継続して生産している場合は年に数回客先の品管が来て品質監査というのをするんだ」 | ||||||||
「品質監査というのは?」
| ||||||||
「つまり品質保証協定に書いてあることをしっかりと守っているかどうか点検に来るわけだ。製品そのものの検査が合格になっても、品質保証協定が遵守している証拠が不十分だと受けとってもらえない。ということは売り上げにならないって重大問題なわけだ。 現物をしっかり作るのは製造と品質管理の責任だが、品質保証協定を守らせること、その証拠を確保することは我々、品質保証の責任てわけだ」 | ||||||||
「なるほど、世の中には色々な仕事があるのですね。お話を聞きますと、品質保証の仕事というのはラインや品質管理の業務を点検したり、調達先に監査や指導に行くことになるのでしょうか?」
| ||||||||
「そう、そのとおり。それと大量の文書や記録を作成することかなあ。君はワープロは得意かい? 我々はワープロ専用機を使っていない。DOSVマシンで、マイクロソフトのワードというアプリケーションソフトを使っている。世の中では一太郎というワープロソフトが大勢のようだが、海外とのやり取りなども考えるとマイクロソフトワードが標準なんだよねえ。 ともかくこの仕事では大量の文書を作るので、一本指打法じゃ困る。ブラインドタッチができないとねえ」 | ||||||||
野矢はできないだろうという顔をして佐田を見た。
| ||||||||
「ワープロはあまりしませんでしたが、NCプログラムを作っていましたのでキー入力は速いですよ」
| ||||||||
「それはうれしいねえ。品質保証課でブラインドタッチができるのは俺だけなんだよね。じゃあ、期待できるなあ」
| ||||||||
●
品質保証課に来てひと月が過ぎた。佐田にとって見るもの聞くもの初めてのことばかりだった。● ● だが、仕事の内容はすぐに理解できた。品質保証という仕事は、要するに客から言われたことを社内に展開し実施させることにすぎない。すぎないというと不遜のように聞こえるが、今まで新機種立ち上げとか不良対策をしてきた佐田にとっては楽な仕事に見えた。少なくても創造的な仕事ではなさそうだ。 仕事の流れは、だいたい次のようになる。 まず、新しい取引をする際に、客先から品質保証協定書というものが提示され、営業部門がそれを品質保証課に回してくる。品質保証課はその内容に対応できるかどうかを検討する。はっきりいって対応できませんという回答はありえない。対応するしかない。 対応できるという回答を営業に返すと、営業は顧客と契約を締結する。調印された品質保証協定書が回ってくると、品質保証課はそこに記載されているひとつひとつの要求事項に見合ったことを、社内の規則や要領書から探し出す。探しても見つからない場合はそれに対応する新しい仕事を追加する。とはいえ新しいことを追加せずに過去からしていたことで見繕うのが品質保証屋の腕である。 そして品質保証協定書に書かれている要求事項ひとつひとつに対応した実際に社内でしていることの概要を書き表した文書を作る。理由は分らないがそれは従来から「品質マニュアル」という名称がつけられていた。あるいは客先の要望で「品質システム説明書」とか「品質保証システム概要書」などとネーミングすることもあった。 もちろん顧客は複数あり、それぞれが要求する品質保証協定書の内容は異なっている。例えば計測器について、ある会社は「計測器を管理すること」としか書いていないが、別の会社では具体的に校正間隔を決めているものもあったし、更にはどの校正機関に依頼することとまで指定している会社もあった。そのように顧客によって要求が異なるときは、それぞれに個別対応するのではなく、最大公約数的にどれをも満足するように社内のルールや運用を合わせるのも品質保証屋の腕なのである。そのために、品質保証を担当していると工場規則を作るのは日常茶飯事だし、場合によっては本社に会社規則の変更を要請することもある。 佐田もこれからその仕事を担当していくことになる。 実際の仕事にとりかかる前に、佐田はまず会社のルールを覚えようとした。 佐田は、今まであまり会社規則に縁がなかった。製造現場の係長なら、会社の規則を知らなくても仕事はできる。しかし品質保証業務では会社の規則を覚えることが、現場におけるNCプログラムの作成技能と同じレベルの必要条件のようだ。まず佐田は会社規則を徹底して読んだ。それから工場規則を読む。品質関係や製造関係だけでなく、経理や資材、その他安全や衛生関係の規則も徹底して読んだ。暇があれば、始業前にも昼休みにも読んだ。何度も何度も読み返した。 読んでいると、分らないことはたくさんあった。 会社規則には②とか③から始まる項目はたくさんあるのだが、なぜか①から始まる項目がない。 佐田は先輩格である島田  に質問する。 に質問する。
| ||||||||
「島田さん、①(まるいち)というのがないのですが、これはどうしてなのですか?」
| ||||||||
「うちの会社規則というのは法律の真似をして作っているんだよ。法律は、大きい方から、章、条、項、号というふうに階層化されている。章や条はそのまま第一章とか第一条と書くのだけど、面白いことにというか変な話だが、項は第一項とか第二項とは書かないんだ。まず第一項は番号を付けない。そして第二項は②と書く」
| ||||||||
「すると・・番号がないなら第一項とは呼ばないのですか?」
| ||||||||
「ところが①がついてなくても第一項と読まなくちゃならない。おれもはじめは第何条第一項とあるからどこに第一項があるのかと一生懸命に探したもんだよ。 それと普通の感覚では(1)の方が①より上の階層に使うことが多いけど、法律や会社規則では項番を②、③と表し、その下の号を(1)(2)と書くんだ」 | ||||||||
「ええと、それともう一つ疑問があるのですが、①も②もなくて、条の次に(1)(2)とあるのはどういうことなんでしょう?」
| ||||||||
「それはさ、第一項しかないときで、第一項の下にある第一号、第二号のわけなんだ。その場合、(1)の前に、一つ文章があるはずだ。それがその条の本文になる。ちょっとわかりにくいがそういう約束だと思うしかないね」
| ||||||||
「なるほど、勉強になりました」
| ||||||||
そのほか、及びと並びの違い、又はと若しくはの違いなども教えられた。直ちに、遅滞なく、速やかにというのもニュアンスの違いがある。 そのように覚えなければならない約束事はたくさんあった。だが1週間も読み続けるとあらましのことはわかる。 そして佐田は会社のルールを理解してから仕事に取り掛かった。佐田は能無しではない。現場スタッフを長年してきたし、係長もしてきた。ひとたび会社の規則類を読み尽くせば品質保証協定書を読みこんで、それに対応する会社規則を抜き出して、要求事項を満足していることを説明することなど、彼にとってはたやすいことであった。 そしてそれを文章にするというのも、今まで毎年多くの新機種を立ち上げるたびに数多くの作業指示書を書き、NCプログラムを作ってきた佐田にとってはなんということのない仕事である。 通常、品質保証協定書1件に対応して、社内の対応規則を見つけてその実施状況を調べるには、一人でひと月かかるという。まず品質保証協定書に書いてある「〜しなければならない」と言う語句に対応する会社規則の該当箇所のリストをつくり、その実施部門に行っては実際にどのようなことをしているのか、その部門の課長や担当者にヒアリングして実態を把握する。規則で立派なことが書いてあっても実際には運用されていないこともあり、また規則にはないが部門内で手順を決めていることもある。そういったことを基にして、文章を考えワープロ入力するだけでもかかりきりで1週間くらいかかると聞いた。客先の要求内容にもよるが、品質マニュアルはだいたい50ページから60ページになる。 だが今の佐田は、品質保証協定書の要求事項をみると、それがどの会社規則のどこが該当するかは考えなくても頭に浮かんでくるようになった。そして現場の実態は調べるまでもない。頭の中で概要がまとまると、下書きもせずに機関銃のようにワープロ作業をして二日とか三日で「品質マニュアル」を仕上げた。先輩たちは佐田を見てその処理能力のすごさに呆れた。そして間もなく佐田に追い越されると感じた。いや既に追い越されているのかもしれない。野矢課長だけが佐田を見てニヤニヤしていた。 それだけではない。佐田はそれぞれの要求事項に対応するために部門ごとに何をしなければならないかをまとめて、関係部門に教育をした。あなたのところはこれこれをしなければなりません。言い換えると他のことはしなくて良いですと。 各部門は品質保証課の担当者から、そう言われるのは初めてだった。今までは新しい顧客と品質保証協定を結ぶと、それ用の品質マニュアルを作ったのでそれをもとに各部門のルールの見直しをしてくださいと言われただけだ。 そして客先の立ち会いや品質監査を受けるときも、佐田は頼もしかった。 やって来た監査員が問題であるといっても、佐田があわてることはなかった。仕様書と品質保証協定書をめくって、その指摘が妥当なのか、元の契約にないのかをはっきりさせて、その対応を話し合うのだ。今までの品質保証の担当者はそんなとき、客先の発言は絶対正しいという認識ですべて受け入れてしまったものだ。 だから品質管理部門や製造部門から、今度の契約はぜひ佐田に担当してほしいと野矢は言われた。とはいえ全部が全部、佐田が担当するわけにはいかない。 野矢は川田部長からなんとか引き取ってくれよと押し付けられたことを思い出して、佐田を引き取って良かったと思った。 ●
三月ほど過ぎたある日、野矢が佐田を飲もうと誘った。● ●
ビールで乾杯したあと野矢が佐田に話しかける。 | ||||||||
「どうだい佐田君、品質保証の仕事は慣れたかい?」
| ||||||||
「ハイ、面白い仕事だと思っています」
| ||||||||
「面白いか? 今まで品質保証に異動してきた人はいろいろな文書を読むのが大変だとか、ワープロ入力が大変だとかこぼすのが普通だ。面白いといった人は初めてだな」
| ||||||||
「こんなこといっちゃ失礼かもしれませんが、物を作るよりは簡単ですよ。会社規則など暗記してしまえば、品質保証協定書を読んでその要求が既にしていることか、どこをどれだけ補完すれば間に合うかが目に浮かんできます」
| ||||||||
「お前が努力家だということは見ていて分る。会社規則のどの規則のどこに何が書いてあるかを知っている奴なんて、会社中探しても何人もいないだろう。それに毎回各職場に説明会をするなんてまめな奴も今までいなかったなあ。ほかの奴らもお前を見習ってもらいたいものだ。 しかしそれだけに、お前が今回も課長の試験を落ちたのは、だいぶショックだったろうな」 | ||||||||
「正直言いまして、おっしゃるとおりです。あのとき川田部長の面接で、今後受験しても合格しないからもう受けるなと言われました」
| ||||||||
「そうか・・・川田部長はこの工場では勢力があるからなあ〜 だけど、お前ももう少し上長に気に入られようと付け届けするとか、そういうのも必要だぞ」 | ||||||||
「じゃ野矢さんにはお歳暮を贈りますよ」
| ||||||||
「ばかいえ、俺はそんなことは嫌いだ。だが、川田センセイにはそういうのは必須だ。今回お前と同期の鈴田が合格したけど、試験前あいつは川田部長にべったりだった。ゴルフの時など運転手兼荷物持ちだったしなあ。だいたいお前はゴルフもしないそうじゃないか。そういう社内の付き合いが嫌いなのかしらんが、会社の仕組みというか文化というか、そういうのを理解しないとだめだ。 あるいはお前のような生き方をするなら、課長試験に合格しようなんて思わないことだ」 | ||||||||
「おっしゃることは良く分ります。つまり私も覚悟というか割り切りが足りなかったんですね」
| ||||||||
「でもさ、課長とか部長になるとことばかりが価値の尺度じゃない。俺も現場や他の部門の話を聞いているけど、お前は下から評価されていて、鈴田は上から評価されている。お前の生き方なら下から高く評価されているということで満足することだ。それは名誉なことなんだから」
| ||||||||
「言われるとその通りですね。じゃ新しい目標は品質保証課で一番になりますよ」
| ||||||||
「お前は既にそうなっているよ。だけど井の中の |
本日は最初の最初です。今回は佐田の勤めている会社の概要と彼が置かれた状況を知っていただくことが目的です。本当の物語は次回以降です。
「なんだ、今回は単なる小説か?」なんておっしゃらないで
マネジメントシステムとは何かを語るつもりなのです。それを書くだけの時間をください。
この作品はフィクションであり、実在する人物、団体等とは一切関係ありません。
もし、思い当たることとかそれらしい人がいても、それはあなたの勘違いです。
名古屋鶏様からお便りを頂きました(2013.10.20)
半沢直樹は金融監督庁が悪役でした。この物語は相手先の品質担当者がソレに該当するのでしょうか? 期待しております。 |
名古屋鶏様、そういうことは期待しないでください。 まず、世の中にはそんなに悪い人はいませんよ。 それと、この物語は勧善懲悪じゃなくて、マネジメントシステムの誤解を追及するお話ですから・・・ |
N様からお便りを頂きました(2013.10.20)
まともにサラリーマンをやっていなかったのでよくわかりませんが、こうしたヒラメのような生き方をしている人たちもいるんですかね。 品質保証部というと、製造現場から疎まれている会社もあるようです。 会社には不要な仕事はないので、お互いが尊重し合って物事を進めてゆければよいのですけれどもね。 |
N様 まいどありがとうございます。 世の中のコンプライアンスというか、して良いこと、して悪いことの基準というかレベルは、時代と共に変わってきていると思います。 昔は会社ぐるみで選挙応援をして、協力しない人は追及されたなんてことがありました。購買担当者が外注にたかるなんてのもありました。仕事でミスをすると残業代なしで手直しをさせるなんてこともありました。セクハラなんて今だからセクハラなんていうのであって、20年前は事務所にヌードカレンダーをかけるなんて普通にあって、猥談を職場でしているのも普通のことでした。 今、そんなことをしたら従業員は監督署に駆け込むか、公益通報制度を利用するでしょう。 私は昔(20年あるいはそれ以上以前なら昔と言ってよいでしょう)は今よりもはるかに公徳心のレベルも低く、一般人の問題意識も低かったと思います。いや、内心は嫌でもそういうのを表に出せない時代でした。 世の中は時代と共に良くなってきていると思います。時代相応でないと、ブラック企業なんて言われます。それは当然ですね。 それと品質保証の職で、社内から疎まれるようであれば、その担当者が未熟なのだと思います。客と同じ立場になって厳しいことを言うだけなら誰にでもできます。物を作る立場で一緒に悩む人でなければ、品質保証という職務についてはいけないと思います。 |
外資社員様からお便りを頂きました(2013.10.21)
おばQさま お元気で活躍の事と思います。 課長試験の件は、ちょっと切ないようなおはなしですね。 佐田の名前ですが、出雲市佐田町に因むのでしょうか? 素戔嗚と聞いて思いました。 今後の佐田氏の品質部門での活躍を楽しみにしております。 さて、「品質保証協定書」の事で、ご経験やお考えを教えて頂ければ幸いです。 私の会社でも取引先から似たようなものを頂きますし、契約書にも同様な規定が存在する場合もあります。 しかしながら、その内容が定型文書も多く、当社の実態に合わない場合も多いのです。 そのような場合には、私は相手の会社に変更を求めますが、多くの場合は「定型だから」と修正を大変嫌がられます。ひどい場合には、請負のくせに客に向かって生意気だと言う購買担当さまもいらっしゃいます。 もちろん、受け入れられる事は、当然当社でも実施すべきと思いますが、実態に合わない事を出来るがごとく飲み込む方が、取引としては不誠実と思い、私はいつもお客様に向かって修正を求めます。 おばQさまのご経験では、このような実態に即してない要求の場合には、如何されますか? ご経験では、相手が修正を拒否する場合はありませんでしょうか? 簡単な例では、当社は物品の製造をしない会社なので、製造に関する法規の順守を求められても困るし、破棄物のリサイクルと言われても、それこそ紙ごみパソコンくらいしかできません。 にも関わらず、膨大な管理体制と調査票を送られる会社さんがいらっしゃいます。 (ISO14000認証が必須と仰る会社も過去におりました) 結局、こうしたやりとりの時間が無駄なので、始めに修正点を理由をつけて提案するのですが、定型文書を変更するのは大変だった経験が多いです。 ご意見やご経験を伺えれば幸いです。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 まず、お断りですが、これはすべて私の実体験ではありません。自身の体験、見聞、伝聞を基に、細かいところは脚色、創作です。 名前の件、バレバレですか、最近、記紀とか邪馬台国に凝っておりまして、今回は出雲関連でまとめようかと・・・まあダジャレです。 品質保証協定書のこと 本文では「拒否することはありえない」としていますが、現実にはそんなことはありません。官公庁以外は協議で決めることであると思います。とはいえ買い手が強いのは当然で、法に関わらない製造上の管理であれば言われた通りするしかないというのが現実ではないかと思います。 もちろん無縁なものがあるときはどうするのかとなりますが、あってもしょうがないなら無視ということになるのかなあと思います。なにせもう20年も前のことなので半分忘れました。 ただなにがなんでも受け入れたという記憶はありません。 |
たこ親父様からお便りを頂きました(2015.02.12)
ISOの違和感 はじめまして、いつも拝読させて頂いています。 有意な内容に対し、ROMばかりでは申し訳無い観があり、非力を省みず感想等を記します。読み始めた当初、言わんとしていることが理解できませんでした。しかし「マネジメントシステム物語」頃から自分の現状に近い面があり、少々理解できる面も増えてきました。(私は工場務め、工場全般のISOを含めた環境管理?を約5年担当している一員。)自己評価すれば貴内容の理解度は60%程度でしょうか。 さてISOに関しては何か根本的なところで違和感を払拭できないでいます。(もう5年も担当しているのに・・・。他責にするつもりはありません。)その違和感が何から生じるのか?が大事であり、多少整理すると?自分の理解不足、?工場のISOへの誤解、?日本でのISOの誤解(捏造とは申しません)、?そもそもISOは虚構なのに過大評価している事、になると思っています。?、 ?については自責であり、その状況を理解いただき何らかのコメントを頂くにはかなり多くの具体例を挙げる必要があり、別途の機会にしたいと思います。 さて、貴内容では?についての記載が多いと思いますが(刺激を受けています)、?の面については如何でしょうか?見聞の範囲でもかまいませんので貴認識を伺えれば幸いです。英語圏ではISOのほぼ正しく認識され、運用されているのでしょうか?興味があるところです。 尚、ISOとはISO14001です。 感想を記す、といいながら質問になってしまいました。申し訳ありません。 (追伸) 朝日新聞に対する貴対応からも刺激を受けています。 |
たこ親父様 お便りありがとうございます。 本心から申し上げますが、お便りをいただきますと本当にうれしいです。常連の名古屋鶏様、ぶらっくたいがぁ様、その他の方々も初めはお便りを頂いて意見交換をし、やがて実際にお会いして飲んだり食べたりして付き合いが始まりました。もちろん一度もあったことのない方もいますが、袖触れ合うもと言いますので、是非とも今後もいろいろとご意見、茶々をお願いいたします。 さて、本論ですが、 違和感! 私もありました。なにか場違いな上品な会合に出てしまって、言葉使いもわからず価値観の違う人たちの中で途方に暮れるという感じでした。私たちは会社で安く作れ、事故を起こすな、品質をあげろ!というような仕事(暮らし)を何十年もしてきました。そういう価値観というか発想でいたのですが、突然なにか得体の知らないISOというのが現れてこれが正義だ、これが本来のあるべき姿だなどと言い出されて、この人なんなの?って感じではないのでしょうか。 ただ私がISOと出会ったときは、まだそんなたいそれたものではありませんでした。私は元々が現場でしたが、事情によって品質保証部門に流れてきて、顧客対応の品質保証の仕事をしていました。そのときにお客さんから購買条件としてISO9001認証を要求されました。ですから私の発想というか認識は、お客さんの要求事項としてISO9001があるというだけのことで、その規格を基に会社を見直すんだとか、会社を良くする手法だなんて思いもしませんでした。だって客先から要求されることはさまざまですが、その要求を受け入れることによって会社の仕組みを見直すとか、それを行えば会社が良くなるなんて思うはずがありません。 そういう認識でしたが、ISO14001が現れた時は、審査員がISO規格は経営の規格だとか、経営に寄与するとか言い出して、上記のなんかオカシイゾ!という思いを持ちました。その思いはたこ親父さんと同じだと思います。 ISO規格を作るISO-TC委員の方が「今から備えるISO」なんて連載を「日経エコロジー誌」に書いていますが、私には「なんでわざわざ備えるの?」という発想しか起きません。ISOがあって会社があるのではなく、社会に貢献するために会社がある、そして第三者がその会社が並みレベルかどうか判断する基準としてISO規格があると考えています。普通の会社ならISO規格レベルはクリアしていると信じています。 英語圏ではどうかというご質問ですが、実を言いまして私は英語圏でISO認証に関わったことはありません。ただイギリスで実務を行った人に聞くと、日本のような変な、例えば有益な側面とか点数とかいうことはまったくないそうです。イタリア、スペインで認証に関わった人の話では、かの地ではコンサルに審査員との交渉をしてもらわないととても無理と聞きます。不適合の値引き交渉などいろいろ大変だそうです。とはいえ聞いた話なので確かなことは言えません。 朝日新聞については個人個人見解があって当然です。気にしないでください。 |
マネジメントシステム物語の目次にもどる
| Finale Pink Nipple Cream |