13.12.01
マネジメントシステム物語とは佐田と武田が
武田は着任すると、すぐに現場を歩きまわり、また製造部門の管理者、監督者一人一人と面接して問題点や改善についてのヒアリングを始めた。武田も職長をしていたくらいだから、現場を一目見て、個人レベルの技能の点だけでなく、作業管理や指導方法にいろいろ問題があることに気が付いて、それをどういう方向で改善していくか、管理者や監督者を指導していくべきかを考えている。
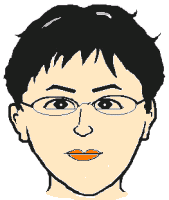 武田 |
だがこの10日間だけでも、武田はタレパン加工の時間短縮をはじめ、物の置き方やマテハンの改善を指導しており、それらによって星山専務や伊東委員長をはじめ、作業者や係長などの信頼をかち得てきた。その分安斉が浮いてきている。このままではまもなく安斉は名目上は課長でも、実質的な権限は武田に掠め取られてしまうだろう。
一方の佐田は、文書や記録の実情調査を行っている。現実を最大限に尊重するというのが、佐田の考えだ。最近設立された会社ならともかく、歴史がある会社はそれなりの固有文化があり、害がない限りそういう文化というか社風を大事にすべきだと佐田は考えている。社長から半年という期限を切られているが、時間は十分だろう。
ところでふたりの生活の方だが・・・・
武田は毎朝、始業1時間前には来ている。奥さんも一緒に引っ越してきたので、炊事、洗濯の心配はないし、通勤時間も車で数分しかかからない。実を言って大した距離ではないし、帰りは飲みに誘われることが多いので、健康のためにも車をやめて歩いた方がいいと思っている。ともかく後顧の憂いなく会社に全力投球できる。
 佐田 |
佐田も武田と同じ頃には会社に来て仕事をしている。そして二人とも、毎晩7時過ぎ、8時過ぎまで会社にいる。それでも二人とも福島工場にいたときよりは、通勤時間が短いので時間的には楽だ。まして鈴田たちのように片道100数十キロも通勤しているのとは大違いである。勤め人は良い仕事をするのが当然であり、そのために会社で全力を出せるように住むところを含めて考えることは必要だろう。
もちろん長時間、会社にいるだけでなく、二人はそれぞれの分野でどんどんと改善を進めている。
この二人と、安斉と鈴田の違いは、社長はじめ他の従業員の目に明らかだった。当然、川田はまわりの目、まわりの評価に気が気でない。しかし、当の安斉も鈴田もそんなことに気が付かない。毎日、始業時間すれすれに出社して、定時になると姿を消す二人は、そんなことに気が付く暇もないのかもしれない。
星山専務も朝早く来る。今までは出社すると自分の席に座っていたが、今ではときどき佐田や武田とコーヒーを飲みながら、会社の問題や作業改善について話すようになった。
川田はそれも気にしている。星山の新しい出向者2人に対する態度と、川田たち3人に対する態度は大違いだ。それをみて川田は自分たちがもっと頑張ればよかったと思うが、いったいどうすれば良かったのかとなると、そこが分らない。自分たちは元々力がなかったのだろうか、真面目に仕事をしなかったのだろうか。それとも長距離通勤をしていることや、川田にしても自炊したりしているために、会社に力を注げなかったのだろうか・・・
もっとも川田は、一番初めに大蛇に挨拶に来たとき本社の宍戸専務と一緒に来て、社長をはじめ人々の反感を買ったことには思い至らなかった。
これから川田たちが頑張れば、自分の場所を確保できるのだろうか。あるいは新しい出向者が改善を進めて、川田たち3人はお払い箱になってしまうのだろうか・・・元の会社に戻るにしてもここで実績を出さなければ、向こうにも居場所はないだろう。川田は悶悶としている。
●
●
●
ある朝のこと、佐田がパソコンの前でカシャカシャとキーボードを叩いていると、星山専務が資料を手にしてやって来た。
●
●
「おはようございます、専務」
| |
「おはよう、いつも早いね、佐田さん」
| |
「私は部下なのですから、佐田君とでも呼んでくださいよ」
| |
「いやいや、佐田さんは私の先生だから。 ところで、ちょっと相談があるのだが」 | |
佐田はパソコンを叩くのを止めて立ち上がった。
| |
「なんでしょうか?」
| |
「まあ、コーヒーでも飲みながら・・」
| |
 星山と佐田はコーヒーメーカーからコーヒーを注いだ。組合の伊東委員長が買ったコーヒーメーカーは結局、佐田のところに置いていったのだ。 といっても伊東委員長もここにいることが多いから損をしたわけではない。 | |
「社長が新しいお客様を見つけてきたのだが、そこは品質保証協定書というのを締結しなければならないというのだ。これがその品質保証協定書だ」
| |
そういって星山は佐田に、A4サイズで10ページほどの書類を手渡した。
| |
「とりあえずそれにこちらが押印して返せばいいらしい。しかし社長も私もこの品質保証協定書を読んでみたが、どうもわからない。書いてあることが、品質を保証するような書きものじゃないんだなあ。これは一体何なのだろう。 またその協定書を読むと、後でこちらがその品質保証協定書に見合った品質保証マニュアルというのを作成して提出しなければならないと書いてある。品質保証マニュアルというのは簡単に作れるものなのだろうか? ちょっと見てくれないか」 | |
佐田がパラパラとながめると、それはクシナダ機械という会社の品質保証協定書で、内容は定型化しているようで、受注メーカーが社名を書き込み責任者が署名、押印すれば出来上がりになる。どんなことを要求しているのかと見ていくと、特段厳しいものではなく、内容もそれほど詳細までは記述していない。
しかしこの大蛇機工では会社規則というものが存在しない。今、社長命令で佐田がその文書化を検討しているところだが、社長から示された納期は半年先で、実際にもそれくらいはかかるだろう。それに作業指示のレベルの文書も必要だしと・・・とてもすぐにこの品質保証協定書を満足することはできそうにない。 佐田は少し考えた。 | |
「ちょっと込み入った話になりますね。どういうふうに説明したらよいか・・ 私が説明する前に、お聞きしたいのですが、この協定書はいつ提出で、品質保証マニュアルはいつまでに提出しなければならないのでしょうか?」 | |
「社長も私も仕事を取りたいので一刻も早く契約したい。そのためには品質保証協定書を添えなければならず・・・そうだなあ〜、1週間というところか そして品質保証マニュアルの期限は切られていないのだけど、仕事をもらう前には出さないとならないと思う。まあせいぜいひと月くらいかなあ〜」 | |
佐田は頭の中で考えていた。熟読しなければ詳細はわからないが、この品質保証協定書には設計については要求事項がないものの、文書管理、記録管理、工程管理、不適合品の管理から計測器管理など多岐にわたっている。引用するというか、それを支える規定はそうとうな数になる。まったくゼロの現状からダッシュかけてどのくらいかかるだろうか。佐田が全力を投入するとしても、これはけっこうな仕事だ。 品質保証マニュアルを出すときには、形だけでもそれを支える規定がほしいだろう。規定の作成日付がマニュアルを提出した後ではまずいだろう。最低限、どれほどになるだろうか 佐田が黙っているので星山が心配して話しかけた。 | |
「佐田さん、どうかしたのか?」
| |
「星山専務、脅かすつもりはありませんが、これは大仕事になります。こちらに来たとき社長から会社規則を半年で整備しろというご指示を受けていますが、この品質保証協定書を結ぶには、その仕事を今おっしゃった納期で仕上げなければならないことになります」
| |
ちょうどそのとき始業のチャイムが鳴った。
| |
「話が難しそうだな。会議室で説明してもらえないかな」
| |
二人は会議室に移った。
| |
「まず品質保証という言葉の意味から説明します。品質保証とは、普通の日本語の意味で品質を保証することではありません。当社ではこのような体制で物を作っていますと説明することです。もちろん口で言うだけではなく、その通り実行していなければなりません。 この品質保証協定書は、お客様が発注する物を作るときはこのような管理をしなさいという要求でして、こちらが署名押印して返すということは、お客様が求めている通りの管理をしますという約束なのです」 | |
「なんだって、品質保証とは品質を保証することではないのか? それで私がいくら協定書を読んでも訳が分からなかったのか」
| |
「品質保証協定書の中に『なになにをせよ』と書かれていることを、要求事項と言います。契約するには、この要求事項を守りますといわなければなりません。つまり要求事項に同意して取り交わしたものが品質保証協定書です。もちろんそこにはどのようにして要求事項を満たすかは書いてありませんので、具体的にどのようにしてその要求事項を担保するか、ここでは担保とは守りますとか実行するという意味ですが、それを書き示したものが、品質保証マニュアルというものになります」
| |
「品質保証協定書には会社印と社長の署名だけでいいのだろうが、品質保証マニュアルを書くのはどれくらいかかるのかね?」
| |
「品質保証協定書は確かにすぐに提出できるでしょうが・・・・品質保証マニュアルは簡単に書けません。といいますのは、この中にはたくさんの要求事項があります。細かいことは良く読まないと分りませんが、項目だけでも従業員の教育から計測器の管理その他、10数項目に渡っています。それについて単に私どもはやりますと書いても意味がないのです」
| |
「というと?」
| |
「それを裏付ける手順が必要なのです。手順とは5W1Hを書いたものと思ってください。そしてその手順は頭の中にあるだけでなく、それを書いた文書が必要なのです。従業員の教育についてなら、当社の教育体系とか個々の業務についてどのような教育をした人を従事させるとかを決めた文書が必要になるのです」
| |
「うーん、それはおおごとだな・・・」
| |
「それらを個々の規定にしないで、マニュアルの中に書ききってしまったらどうなんだい?」
| |
突然、伊東委員長の声がしたので、星山専務と佐田は驚いて声のした方を見た。
| |
「いや、失礼。先ほどからいたんだけど、二人が真剣に話していたので黙って聞いていたのさ」
| |
「おい、いくらお前だと言っても、内緒話も人事の話もあるのだから、遠慮というものがないのか」
| |
「当社の経営は組合委員長の最重要事項だからな」
| |
星山はため息をついて佐田を振り返った。
| |
「伊東の言うように、マニュアルの中に書ききってしまったらどうなのだろうか?」
| |
「そういう方法もあります。但しその方法にはいくつかの問題があります。 その1、書くだけなら簡単ですが、現実にはここに書いてある要求事項に見合ったことをしていないように思うのです。ですからいずれにしても新たに実施しなければならないことが発生しますし、それを決めたルールが必要になります。そのルールを別の書き物に書くか、マニュアルに書くかの違いですね。 その2として、会社規則、それを規定と呼ぼうと手順書と呼ぼうと同じですが、それは重要な会社の財産であり、社外に公開するわけにはいきません。そもそもマニュアルを作るのは会社規則そのものを社外の人に見せないために、関係するところだけを、しかも要点というか相手が要求したところのみをサマリーして見せるためなのです。 その3として、一番目でも言いましたが、すべてを書き込めば品質保証マニュアルは膨大なものになるでしょう。60ページ70ページや、いやそれ以上になるかもしれません。いずれにしてもボリュームは変わらず、それを書く時間も変わらないと思います」 | |
「そんなに!」
| |
「例えば教育一つとってみても、いつだれがどんな人に対してどんなことをどのようにするかと、要求事項に見合った必要なことを書けば数ページになるでしょう。大きな項目だけで15くらいありますから、掛け算するとそんなものでしょうねえ」
| |
伊東は黙ってしまった。
| |
「その4に、だいぶ前にみなさんに、規則を作るときは全体の姿を思い描いて、規定を作るときはその一部を作るつもりで部分を作ると申し上げたと思います。一つの規定はジグソーパズルのピースであって、完成した体系はピースが余ることも足りないこともなく、しっかりと組み合わさるものでなければなりません。全部をマニュアルに書いてしまうという姑息な方法では、あるべき姿から離れてしまいます」 すべてをマニュアルに書ききって下位文書をゼロにすべきとか、下位文書は作らないほうが良いと語るコンサルがいる。 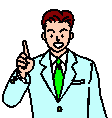 インターネットでググるとそんな宣伝をしている人はすぐに10人くらい見つかる。
インターネットでググるとそんな宣伝をしている人はすぐに10人くらい見つかる。私は思うのだが、そういった人たちはマニュアルとは何かとか、文書とはどうあるべきかということを分っていないのだと思う。 あるいはISOについてしか知らず、現実の会社の動きを理解していないのかもしれない。 私の言葉に、文句がある方がいらっしゃいましたらぜひとも議論したいです。 | |
「このお客様対応でまとめてしまって、あるべき姿はじっくりと取り掛かるというのはないのかね?」
| |
「それはありですね。ただ全体を見れば余計な仕事をするように思います」
| |
「とりあえずの納期に間に合わせるには、それしかないならしょうがない」
| |
「おっしゃるとおりです。そうしたとしても先ほど述べたように、今時点、要求事項に見合ったことが全く何もないので・・・はたしてひと月でできるかどうか・・」
| |
「クシナダ機械の仕事は、ぜひともとりたいのだが。佐田さんに何かアイデアはないか?」
| |
佐田はホワイトボードに歩み寄って、マーカーを手に取った。
| |
「まず、品質保証マニュアルの納期を確定することが第一です。可能なら納期を伸ばしてもらいたい。 次にこれをみると品質保証マニュアルを提出後に品質監査に来るとあります。そして品質監査の結果OKになってから発注すると書いてあります。まあ順序としては当たり前のことですが・・・ 品質監査の時までに、こちらがどの程度の整備状況でなければならないかということが重大問題です。仮にマニュアルに書いた仕組みの運用が半年なんて言われたら、規定を作ってから半年ですから、注文がもらえるのは1年も先になります」 | |
そう言って、それらの要点をホワイトボードに書く。
| |
「ともかく、この協定書の中を良く理解して、必要十分条件を理解しなければなりません。最低限どこまでしなければならないか、どこまですればよいのか。その上で納期を守ることができるアプローチを考えなければなりません」
| |
「わかった。とりあえずわしの仕事としては、クシナダに品質保証マニュアル提出の納期と品質監査のときの状況というか条件を問い合わせることだな。 佐田さんは要求事項を良く調べて対応するための時間と問題点を検討してくれんか」 | |
「もうひとつ、大事なことがあります」
| |
「なんだろう?」
| |
「先方の図面を当社が作れるかどうか、製造部門で検討してほしいです。 一生懸命、規定を整備して品質保証マニュアルを作っても、実際に物作りができないのでは困ります」 | |
「わかった。クシナダは金型を貸与するという。大至急、技術と製造にクシナダの図面を検討させよう」
| |
●
それから佐田は品質保証協定書を何べんも読んだ。そしてコピーを取り、重要なところに赤線を書き込んで、また何度も何度も読み返し、重要か所をメモにしてまたそれを読みかえす。● ● 佐田の名誉のために説明するが、彼は要求事項を満たすことを考えていたのではなく、要求事項を満たすためのアクションを最小にすることを考えていたのである。 ●
二日後のこと、星山専務が佐田に話しかけてきた。
● ● | |
「クシナダの件だけど、先方から日程の回答があったのでちょっと話したいのだが」
| |
「専務、私の方も見積もりできました。打ち合わせましょう。前回の件もありますから伊東委員長にも出てもらったらよいのではないでしょうか?」
| |
「うーん、とはいえ奴は管理者じゃなくて組合だしなあ」
| |
と言ったとき星山専務の後ろから伊東の声がした。
| |
「おいおい、星山、おれを他人呼ばわりか、まあ一緒に議論しようや」
| |
星山はぶすっとした顔をして会議室に入った。
| |
「まず専務さんからどうぞ」
| |
「まず品質保証マニュアルの提出期限も環境監査の実施日も簡単じゃないことがわかった。 まず先方は、こちらからの品質保証マニュアルの提出を受けて、その内容を審査してOKだったら・・・向こうでは適合判定という言葉を使っていたが・・・それから先方は品質監査に来るという。品質監査を行う条件は、運用期間が二月以上あることと言っていた。 監査結果、品質保証協定書を満たしていると判断し、かつ部品のサンプルを検査して合格だったら発注するというのだ。やれやれエライことだ」 | |
佐田にとってはその流れは特別なことではなく、特に客先が官公庁や大手企業の場合は一般的である。そういうことは何度も経験していた。
| |
「ということは言い換えれば期限はないが、こちらとしては一刻も早く品質監査を受けたいということだな」
| |
「そういうことだ。部品製造の方は吉田部長に頼んでいるので、今日明日にも報告があると思う」
| |
「わかりました。 では私の方ですが・・・」 | |
といってコピーした紙を二人に配布した。
| |
クシナダ対応の文書体系
破線は別の項目で既出のもの
 |
「なんだこれは!」
| |
「なんだって言われても・・・クシナダ姫と戦うには、これくらいの文書と記録で武装しないとならないということです」
| |
「俺たちからみたらクシナダ姫と戦うわけか」
| |
ダジャレです。分らない人はパスしてください。
いや、勉強のために古事記を読むことをお勧めします。 | |
「前回話がありましたように、クシナダ対応だけでしたら、マニュアルに書ききってしまうとか、ここに仮に示した複数の規定をまとめてしまうという方法もありです。しかし将来のあるべき姿を目指すなら、ボロは着てても心は錦〜♪でいかなくちゃなりません」
| |
「これがボロなら、錦とはどういうものなんだ?」
| |
伊東の質問は単なるダジャレあるいは形而上の質問だったのだが、佐田はちゃんとそれへの答えを用意していた。佐田は先ほど示した図と似たような文書体系図を二人に配った。見た目は似たようなものであるが、そこに載っている文書の数は倍、いや三倍くらいありそうだ。中には名称が空欄になっているものもある。
| |
大蛇機工の包括的文書体系

|
「私なりにあるべき姿を考えたものがこれです。もちろんみなさんのご意向を伺って、今後リファインしていくつもりです。この図で色を染めている規定が前のクシナダ向けの品質保証マニュアルで引用しているものになります」
| ||||||||||||||||||
星山と伊東はしばし黙ってながめている。 やがて星山が口を開いた。 | ||||||||||||||||||
「大したものだと言いたいが、これはこの会社が創立時にあったような膨大な文書体系のようだ。重すぎるのではないだろうか?」
| ||||||||||||||||||
しばし沈黙があった後、伊東が言う。
| ||||||||||||||||||
「いや、そうではないように思う。もちろん中身は分らないが、規定類のタイトルを読むと、それぞれが何について書いているか想像できる。規定の数が多いより少ない方が好ましいだろうが、それがどんなものかということがより重要だ。いろいろな業務の目的や方法がわかりやすく、もちろん実態通りに書いてあるものなら、それを読んで仕事ができるだろう。俺はこれで悪くないと思うよ」
| ||||||||||||||||||
「何度も言いますが、この図は私が考えたあるべき姿です。もちろん、みなさんのご意見が優先します。しかしいずれにしても私が文書化しなければならないだろうと考えたボリュームは変わらないと思います。つまり規定の数を減らすことは、規定一個あたりのボリュームが大きくなるということです」
| ||||||||||||||||||
「以前、俺が言ったように、必要なこと全部を客先に提出するマニュアルに書けば、マニュアルがこの規定体系と同じボリュームになるということか」
| ||||||||||||||||||
「そうなります。しかし以前もお話しましたが、品質保証を要求する客は、当然どのような仕組みと手順で品質保証をしてもらえるかを知りたいわけです。そのときマニュアルに全部を書き込んでしまうと、我々のノウハウ、会社の秘密が全部外に出てしまうということになります」
| ||||||||||||||||||
「確かに・・・会社の規定は十分に機密に該当する。だからこそ今我々が困っているわけだ」
| ||||||||||||||||||
「そうです。ですから提出するマニュアルには、社内規定の名称とそこで実施することをほんのちょっぴり記載し、その詳細手順や数値などは書かないのです。詳細は規定を見てくださいというわけです」
| ||||||||||||||||||
「佐田君は分りきったように言うが、そういう考え方は世の中では当たり前のことなのか?」
| ||||||||||||||||||
「私が品質保証屋だということはご存じでしょう。品質保証屋というのは経理や人事と同じように、普遍的な業務であって、どの会社でもやるべきこと、秘密にすること、文書化することなどは基本であり共通なのです」
| ||||||||||||||||||
「佐田さんが単に文書の専門家でなくて、品質保証の専門家ということは我々にとって幸運だったわけだ」
| ||||||||||||||||||
「品質保証屋ではありますが、まだ駆け出しです」
| ||||||||||||||||||
「福島工場の人事課長の話では、佐田君は先輩を超えてしまったと言っていたが」
| ||||||||||||||||||
「それが真実かどうかは、人のうわさでなく、これからの首尾いかんですね」
| ||||||||||||||||||
「話を戻そう。 伊東や私のような品質保証のことなど分らない素人が議論してもしょうがない。佐田さんが最低限の規定を作った上で、マニュアルを書いた方が良いというなら、それを尊重しよう。 佐田さん、結論から言って、最初に示した文書類を整備するにはどのくらいの日数がかかるのだろう」 | ||||||||||||||||||
「まず規定をはじめとする文書を作るのに取り掛かる前に、当社の体制をどうするかを決めなければなりません」
| ||||||||||||||||||
「体制とは? 現在の職制では不足なのか?」
| ||||||||||||||||||
「不足かと問われれば不足ですと言うしかありません。 クシナダから頂いた協定書には『経営層または上級の管理者の中から品質保証の責任者を決めること。その責任者は製品が仕様を満たしていない場合、出荷を停止する権限を持つこと、かつ製造及び検査に関わらないこと』とあります」 | ||||||||||||||||||
「品質保証の責任者が製造に関わらないことはなんとなくわかるが、検査にも関わらないというのは妥当なことなのか?」
| ||||||||||||||||||
「うーん、品質保証においては『品質管理と品質保証は兼務できない』というのが原則です」
| ||||||||||||||||||
「品質管理とはウチでは検査のことと思うけど、なぜ品質保証と兼務できないのだろう?」
| ||||||||||||||||||
「私はその理屈を説明できませんが、三権分立のように、作る責任、合否判定の責任、外部に対する責任は別でないとならないと考えているのではないでしょうか。ある意味、品質保証部門は、社内においてはお客様の代理者でしょうから」
| ||||||||||||||||||
「わかった、ともかくそれを前提として進めるしかないのだな。そうすると製造責任は吉田部長、検査の責任を川田取締役とすると、品質保証の責任は俺しかいないことになる。当然俺一人ではどうにもならないから、品質保証部門を作りそこに佐田さんを置くことになる」
| ||||||||||||||||||
「そうするしか方法はなさそうですね」
| ||||||||||||||||||
「では体制を決めたとして次に進むと、この文書を作り、実際にその文書で仕事をするようになるには、どれくらいの期間が必要だろう?」
| ||||||||||||||||||
「当り前に考えると、まず規定類を作り、その下位文書で手順の詳細と記録様式を定めて、それらで定めたことを実際に運用し、その記録を残すというシーケンシャルでは記録を蓄積する時間を稼げません。 ですから順序を入れ替えて、作るべき記録の用紙様式を最初に決めて、できるところから記録を作成していく。そしてそれから必要な文書を作る手順でないと、先方の品質監査を受けることができません」 | ||||||||||||||||||
原則はこうだが、この方法では運用する期間
(記録を作る期間)の2か月を確保するのが難しい。

| ||||||||||||||||||
「ちょっと待ってくれ。俺は素人なので分らないが・・・記録を残すとはどういうことなのか?」
| ||||||||||||||||||
「品質保証の世界では文書がなければ手順がない、記録がなければしたことにならないのです。ですから『なになにをしなければならない』と書いてあることに対して、当社はそれに対応して『なになにをした記録』を作成しなければならないのです」
| ||||||||||||||||||
「なんだって! 紙、紙、紙か・・・星新一の小説に『紙の城』なんてのがあったけど、あれと同じか」
| ||||||||||||||||||
「確かに不合理とか無駄だと思われるかもしれません。しかし逆に伊東さんがよその会社に行ったとき、しっかり検査をしていると言われたとしましょう。伊藤さんはそれを信用しますか? 検査をした証拠がなければ信用できないでしょう?」
| ||||||||||||||||||
「そう言われればそうだなあ、でも例の品質保証協定書を読むと『しなければならない』という言葉がたくさんあったぞ」
| ||||||||||||||||||
「私が数えたら48か所ありました。ですからこちらは、それに対応する記録を作らないと、実施した証拠にならないのです」
| ||||||||||||||||||
「新たに48種類もの記録用紙を作るというのか?」
| ||||||||||||||||||
「いや48件の要求事項を実施した記録であって、48件の記録ではありません。一つの記録で複数の要求事項を満たせれば減らすことができます。とはいえ、一つの要求を満たすために複数の記録が必要になることもあります。例えば計測器の校正の記録は、計測器の数だけ、校正した回数分だけ存在しなければなりません。 あのですね、もちろん私も品質保証屋ですから、そのへんは最大限、省力化、簡易化に努めるつもりです」 | ||||||||||||||||||
「その辺は佐田さんにお任せするしかないな。私には議論する知識もないし、理解もできないよ」
| ||||||||||||||||||
「おいおい、まだ話はちっとも進んでないぞ。その佐田先生のいう方法で進めたとき、どのくらいの日数が必要になるのだ?」
| ||||||||||||||||||
「先ほどの専務さんの話では、品質監査をするとき、提出した品質保証マニュアルで最低2か月運用していることという条件が付けられています。つまり二月分の記録がないと監査に来てくれないということです。規則を作る前から仕事の結果を記録に残すことをしたとして、そりゃ最短なら明日から二月でしょうけど、全項目について明日からというわけにはいきません。私が精一杯やっても必要な記録を決めて、その記録の様式を作るには、ひと月はかかるでしょう。
ということはひと月にふた月足した三月後に、クシナダの品質監査を受けることができるということになります」
| ||||||||||||||||||
星山がため息をついた。
| ||||||||||||||||||
「そう計算通り3ヶ月というわけにはいかないだろう。実際には4ヶ月あるいはそれ以上・・・ 実を言って、白兎電気から | ||||||||||||||||||
佐田も伊東も顔を見合わせるしかなかった。
| ||||||||||||||||||
「佐田さんは期間を短くする方法を知らないかな?」
| ||||||||||||||||||
「まずクシナダさんが、ほんとうに運用期間として2ヶ月を要求するかどうかですね。私の想像ですが、向こうだってサバを読んでいると思います。そのときになって多少短くても良いというなら、それはありがたいことです。 次に、私の助手がほしいですね。パソコンを叩ける人がいれば、その方が文章入力をしている間、私は現場と打ち合わせたりすることができます」 | ||||||||||||||||||
「佐田君が叩いているのはパソコンだね。当社ではワープロ専用機を使っている人が多いが・・」
| ||||||||||||||||||
「キーボードを叩けるなら同じですよ。ただクシナダさんから来た文書もマイクロソフトのワードというソフトウェアで作られていますし、まもなくワープロ専用機はパソコンにとって代わられるでしょうから、これから作成する文書はワードで作ることが前提ですね」
| ||||||||||||||||||
「わかった。一人佐田さんの助手をつけよう。それにウィンドウ3.1のパソコンも2台用意しよう。それと当面、新しい文書の現場への周知や記録などを作成する指導のために、武田君と伊東が佐田さんの支援をすることにしよう。そういう体制でいこう。 クシナダが品質監査を具体的にどんな状況でなら実施するのかは、ゆくゆく確認する。 いずれにしてもクシナダから注文を取ることが我々の目標だ。 佐田さん、今の話を昼までにA4で1ページくらいにまとめてくれないか。社長に説明し、来週の幹部会議で徹底する。当社の生き死にがかかっているのだから」 | ||||||||||||||||||
注:windows3.1は1993年に出ている。物語は時系列からは1992年頃なので矛盾しているかもしれない。まあ、あまり気にしないでください。
| ||||||||||||||||||
品質保証協定書なんて触っていたのは、もう10年以上前になりましょうか・・・
ISO9001が流行りになったとき、1990年後半ですが、ISOとは逆に品質保証協定書を取り交わすことは下火になりました。
今はどうなんでしょうか。それにその中身も時代と共に変化しているでしょうから、現状はどんなものなのかと、ネットで探して3件ほど入手しましたので熟読しました。その労力たるや5時間以上かけました。アホみたいですね・・・
おっと今回は文書体系図を作るのにも1時間くらいかけました。バーチャルであってもバーチャルなりに矛盾のないようにしなければなりませんので、けっこう大変なのです。
おや、そんなことをしなくて良いという声が聞こえたような・・
でもさ、西暦2000年頃まで私は頼まれた会社に一人で行って、文書作成も指導も内部監査も、あげくにその是正もゼーンブやって、ISO認証を受けるのを仕事にしていたものです。あのときのようなことはもうできないね。50前と、60半ばの今では、体力が違いますよ。それに今は働かなくても食っていけるから、マネジメントシステム物語の目次にもどる
| Finale Pink Nipple Cream |