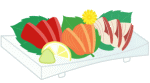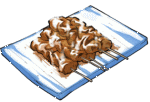14.03.19
マネジメントシステム物語とは今日の午後、出向した片岡がやってきて佐田と佐々木と雑談をした。その後、塩川課長と会議室に入ったままだ。まもなく定時になる。片岡が仕事が終わってから飲もうといっていたので、どうしようかと佐田は佐々木に声をかけた。
「佐々木さん、片岡さんとの件、どうしましょうかねえ?」
| |||||||||||||||
「あまり遅くなると店が混んじゃうだろうから、予約しておこうか」
| |||||||||||||||
「片岡さんが来るまで、佐々木さんと私で飲んでいるという手もありますが」
| |||||||||||||||
そんなことを話しているとドアが開いて片岡と塩川課長が出てきた。
| |||||||||||||||
「おい、佐々木さん、佐田よ、仕事を切り上げて行こうぜ」
| |||||||||||||||
「どこにしますか?」
| |||||||||||||||
「神田駅前あたりが安くていいだろう。おい、早くパソコン切れよ、帰るぞ」
| |||||||||||||||
まだ定時まで10分くらいあったが、佐田と佐々木は机を片付けて塩川の後についてオフィスを出た。 神田駅まで歩いて数分だ。塩川は最近はやりのチェーン店の居酒屋ではなく、裏通りの古くて狭い居酒屋に入った。まだ一般企業の終業時刻前で、座敷に座ることができた。すぐにビールが出てきて乾杯をする。 | |||||||||||||||
ジョッキからごくっとビールを飲んで塩川がいう。 | |||||||||||||||
「いやあ、生き返るよ」
| |||||||||||||||
「課長と片岡さんの話が長引いたようですが、深刻なお話だったのですか?」
| |||||||||||||||
「いやあ、深刻なんてことはないよ。秘密でもない。当社としては出向させたい人はいるのだけれど、受け入れてくれるかどうかが問題だ。公式に話を持っていく前に片岡さんに状況をお聞きしていたということだ」
| |||||||||||||||
「私が会社に残ったのは、まずかったのでしょうか?」
| |||||||||||||||
「佐々木さんの問題じゃありませんよ。当たり前といっては当たり前なんだけど、ウチにいてほしいという人はよそからも来てほしいと言われるし、ウチで要らない人はよそでもいらないと言われる」
| |||||||||||||||
「いや、自分が言うのもなんですが、全くその通りですよ。私の出向先では審査員の半分はプロパーで半分は出向者ですが、出向者の多くは認証機関が開催した講習会の講師に来ていて目をつけられたとか、あるいは特技があって自推してきたという方がほとんどですね。だからあまり変な人というか能無しはいない」
| |||||||||||||||
「どこでも、よそで要らない人を欲しいという人はいないよ」
| |||||||||||||||
「話を戻すと当社では審査員として送り出したいという人はたくさんいるのですか?」
| |||||||||||||||
「たくさんとはどれくらいを言うのか分らんけど、10人や20人はいるね」
| |||||||||||||||
「じゃあ、片岡さん佐々木さんに次いで、第二陣の育成を始めなければなりませんね」
| |||||||||||||||
「佐田よ、お前がそう言ってくれるのはうれしいが、段々と候補者のレベルが下がっていくわけよ。片岡さんや佐々木さんレベルが来ると期待するなよ」
| |||||||||||||||
「そういう人であればなおのこと事前の教育が大事ですね。今日も片岡さんのお話を伺っていましたが、礼儀作法とか言葉使いの教育も必要なようです。塩川課長、明日でも状況を教えてください。計画を考えないと」
| |||||||||||||||
「実はさ、また別の問題があるんだ。現在行っているグループ企業への環境監査が不十分じゃないかという声があがっているんだ。課長の俺としては針のむしろだよ」
| |||||||||||||||
「何か問題なのでしょうか?」
| |||||||||||||||
「お前も知っているだろう。半年ほど前のこと、四国の工場で硫酸流出事故があっただろう。あそこの工場の環境監査を事故の二か月前に実施していたんだ。監査で見つけられないとは何事だとお叱りを受けたよ。まったくその通りでさ、俺としては反省しきりだ」
| |||||||||||||||
「じゃあ、監査の改善をしなければなりませんね。何かアイデアがあるのでしょうか?」
| |||||||||||||||
「部長と相談して方向は決めた。そんなわけで新人の教育をするのはちょっと難しくなったなと思うわけよ」
| |||||||||||||||
「失礼な言い方かもしれませんが、佐々木さんも一人前になられましたから、私が新人二人くらいを受け持って教育することはできると思いますよ」
| |||||||||||||||
「それがさ、来月から環境監査の担当というか責任者を佐田、お前に担当してもらうことにした」
| |||||||||||||||
「はあ! 私は環境法令とか実際の運用なんて知りませんよ。元々は製造現場、それからは品質保証屋ですからね」
| |||||||||||||||
「一つに秀でた奴は何をやってもできるものさ。お前は公害防止管理者とかも持っているし、大丈夫さ」
| |||||||||||||||
「でも今まで担当していた人はどうするのです?」
| |||||||||||||||
「環境監査の責任者は谷川だったんだけど、奴も本社に来て5年になる。それで工場に戻すことにした。本社も長いから工場に戻しても、差し障りはない。もう一人は竹山なんだけどさ、あいつも大学院出でもう5年になるけどまだしっかりしていない。ということでお前が竹山の教育もする。 まあ部長とすれば、佐々木さんが来たのでその分削減しなければという気もあっただろうし」 | |||||||||||||||
「えっ、佐田さんが監査担当となりますと、ISO認証指導は私一人ということですか」
| |||||||||||||||
「そうはなりません。佐田もISO指導するのは変わらない。だから出向者教育は無理かなと思ったわけさ」
| |||||||||||||||
「それを聞いて安心しました」
| |||||||||||||||
「ISO指導も標準化してきましたから大丈夫でしょう。適当な候補者がいるなら二人くらい受け入れましょう」
| |||||||||||||||
「ほんとうにお前はものに動じないんだなあ〜」
| |||||||||||||||
「部長と塩川課長ができるだろうと考えたのですから、大丈夫でしょう」
| |||||||||||||||
「アハハハハ、私も佐田さんのそういうところを見習わなくてはならないね」
| |||||||||||||||
「佐々木さん、気になるのだけれど以前は佐田君と呼んでいたと思うけど、どうして佐田さんと呼ぶようになったのですか?」
| |||||||||||||||
「いや、年齢とか過去の職階ではなく、現時点私の師匠なのだから『さんづけ』すべきだと思ったのですよ」
| |||||||||||||||
「さすが佐々木さんですね。なかなかできませんよ」
| |||||||||||||||
そんな話をしながらビールから焼酎のお湯割りに切り替わった。 | |||||||||||||||
「ところで俺が外から帰って来たとき、三人でマネジメントシステムがどうとかって話をしていましたね。どんな話だったのですか?」
| |||||||||||||||
「とりとめのない雑談でしたけど・・・ISO認証が企業の遵法やパフォーマンス向上に役立つのかとか、遡ってISO規格要求が本当に正しいのか、更にさかのぼると環境マネジメントシステムというものが存在するのか、そして更に更にさかのぼると体系化された包括的マネジメントシステムというものが必要なのかという、まあ哲学的なお話だったような気がする」
| |||||||||||||||
「とりとめのない話が哲学的か、アハハハハ」
| |||||||||||||||
「我々がグループ企業にISO14001認証をしろと言った理由は、やはり流行に乗り遅れるなということだなあ。ああ、流行に乗り遅れないというのは単なるファッションではなく、ビジネスに不利にならないようにという意味だけど。 ISO認証することによって遵法とか会社を良くしようなんてはまったく考えていなかったね」 | |||||||||||||||
「最初の『ISO認証が企業の遵法やパフォーマンス向上に役立つのか』ということについては、役立たないということは間違いないことでしょうね」
| |||||||||||||||
「排他的にイエスではないでしょう。というのは元々良くしようという意思はあってもその方法を知らなかった企業においては、ツールとして使えるということはありますね」
| |||||||||||||||
「だが、そのケースは二番目の問いである『ISO規格要求が正しいのか』ということがイエスであって、認証についてはノウではないのか?」
| |||||||||||||||
「認証というのは自律していない組織に対して、定期的にチェックが入るという意味があります。だから認証が役に立つこともあることは否定できません」
| |||||||||||||||
「俺もそう思う。だから一定レベルになれば認証を辞退して自己宣言になるというのが論理的帰結だろうね」
| |||||||||||||||
「なるほどなあ、じゃあ次の質問である『ISO規格要求が正しいのか』ということも、方法論を知らない企業においてはISO規格が参考になる場合があるということで一部正解ということか」
| |||||||||||||||
「そうでしょうね。全面的にイエスでもなく全面的にノウでもない」
| |||||||||||||||
「三番目はなんだっけ?」
| |||||||||||||||
「『環境マネジメントシステムというものが存在するのか』です」
| |||||||||||||||
「実は俺も疑問に思っているのだけどね、元々ウチの環境管理部は昔からあったわけじゃない。リオでなんとかいう国際会議があって、それを受けて経団連の環境憲章とかが出て、各社が、まあ東証一部レベルがさ、これからは環境だあと走り出したのが1993年だ。そのときに設立されたわけだ。あれから5年少々になる。 じゃあそれまでは環境はまったく無視していたのかと言えばそうではなく、ちゃんと管理していた。70年代初めに公害防止の各種法規制がジャンジャンと作られて、企業はそれに対応しなければならなくなった。というか、それ以前の60年代だって自治体との協定や住民との申し合わせなどで排水とか煤煙などの規制をしてきたわけだ。そういったことに対応し、規制や約束を守るための管理は過去20数年してきたわけだよね。 いや、もう少し話を聞いてくれ、じゃあそのとき環境管理部門があったのかと言えば、なかったわけだ。 ウチでは生産技術部が公害防止とか法遵守の支援をしてきた。そのとき環境マネジメントシステムがなかったのかといえばなかったのだろう。だけど法の順守と汚染の予防はしっかりとしてきたわけだ。 では今はどうかと言えば、環境管理部があるが、生産技術部が公害防止を担当してきたときと何が違うのか? 確かに守備範囲はフロンとか製品の環境性能あるいは環境保護と拡大してきた。でもそれを環境マネジメントシステムと呼ぶのは羊頭狗肉、たいしたことのないものを大げさに呼んでいるように思うね」 | |||||||||||||||
「まったく同意です。佐田さんは塩川課長とは違った論理ですが、環境マネジメントシステムというものはないと説明してました」
| |||||||||||||||
「佐田の論理とは?」
| |||||||||||||||
「いえ、大した理屈じゃないですよ。これは佐々木さんのほうが専門なのですが、システムとは何かという形而上の話です」
| |||||||||||||||
「形而上か・・・・佐田の話は簡単なことでも難しく言うからなあ」
| |||||||||||||||
「いえ、そんなことはありません。システムとは何かと言えばさまざまな説明がありますが、本来は社会制度とか支配体制というのが語義です。最近はインプット、プロセス、アウトプットだとか言う人もいますが、そういう表現ができるシステムもあるということに過ぎません。ですからシステムの要素としては、組織、機能、手順というものになります。これは軍隊での考えですね」
| |||||||||||||||
「なるほど、今までのところは良く分る。納得だ。でその次はどうなるのかな?」
| |||||||||||||||
「良く考えてみると、環境マネジメントシステムと称するものは自己完結しません。要求事項というのはPDCAとなる一連のものと、そのPDCAを動かすためのインフラ的要素、つまり文書とか記録、あるいは教育とか是正処置と言ったもので構成されます。そしてPDCAの要素もインフラ的要素も環境に特化したものは実はないのです。すべて会社の業務全般の要素であって環境と冠しなければならないものはなく、普遍的、当たり前のものばかりだということです」
| |||||||||||||||
「わかるよ」
| |||||||||||||||
「ISO14001で環境マネジメントシステムと言っているものは、実はシステムではなく、包括的な会社のマネジメントシステムの中から環境に関係する要素を集めたものにすぎないのです。 以前も佐々木さんと片岡さんにお話したことがありますが、こんな関係でしょうねえ」 | |||||||||||||||
佐田はそう言って紙ナプキンにボールペンで図を描いた。  | |||||||||||||||
「なるほど、環境マネジメントシステムとは実はシステムではなく、包括的マネジメントシステムから環境要素を集めたものにすぎなく、そして要素だけを集めてもシステムにはならないと・・・ まったく俺もそう思うよ。俺の発想は佐田とは違ったが、元々生産技術部で公害防止をしていたときと、今環境管理部が環境行政をしているのを見比べて、環境マネジメントシステムなんてものがどこで発生してきたとか、これが環境マネジメントシステムだと言えるようなものが見当たらないものね」 | |||||||||||||||
「ということで、三番目の『環境マネジメントシステムというものが存在するのか』という設問の答えは『存在しない』となります。但し、ISO規格がいう『環境マネジメントシステムなるもの』はすべての企業に過去より包括的マネジメントシステムの要素として存在してきたと思います」
| |||||||||||||||
「待てよ、それは包括的マネジメントシステムがあると言っているわけだが、まだ最後の『包括的マネジメントシステムというものが存在するのか』という答えまではたどり着いてないぞ」
| |||||||||||||||
「塩川課長、『包括的マネジメントシステムというものが存在するのか』ではなく『体系化された包括的マネジメントシステムというものが必要なのか』ですよ」
| |||||||||||||||
「そうでしたっけ? ということは『包括的マネジメントシステムというものが存在するのか』ということは、問うまでもなく存在するのだろうか?」
| |||||||||||||||
「佐田さんが言ったように、システムとは本来、社会制度とか支配体制という意味ですから、いかなる組織も持つというか、組織が発生した瞬間に具備するのです」
| |||||||||||||||
「まってくれよ・・・うーん、そうなるのかなあ、もしシステムを持たない組織は組織ではないということか」
| |||||||||||||||
「少なくても目的を持った組織ではないでしょうね」
| |||||||||||||||
「目的を持たない組織だってあるだろう」
| |||||||||||||||
「組織の定義が『特定の目的を達成するために,諸個人および諸集団に専門分化された役割を与え,その活動を統合・調整する仕組み。または,そうして構成された集団』ですからね、それはないでしょう。片岡さんがいう『目的を持った組織』の目的とは目的がない組織もあるという意味ではなく、単に組織のまくら言葉でしょう」
| |||||||||||||||
「なるほど、そこまではわかった。 しかしそうすると包括的マネジメントシステムというのもひっかかるなあ。包括的という形容詞はいらないのではないか」 | |||||||||||||||
「いやシステムはサブシステムから構成され、階層化されます。包括的マネジメントシステムとは組織全体のシステムという意味です」
| |||||||||||||||
「だって環境マネジメントシステムは、システムじゃなくて単に要素の集まりにすぎないって言ったじゃない」
| |||||||||||||||
「確かに環境マネジメントシステムはシステムと言えないと思いますが、例えば文書管理システムとか非常事態における管理システムなどは、包括的マネジメントシステムのサブシステムとしての機能を持っていますよ。 あのですね、車を包括的システムと考えたとき、セルスターターとかトランスアクセルというサブシステムは存在するでしょう。でもワッシャーとかハーネスだけを集めてもサブシステムではありません。佐田説は環境マネジメントシステムと呼ばれているものは、システムではなくワッシャーとかハーネスだけを集めたようなものだということです」 | |||||||||||||||
「なるほど、サブシステムといえば目的を果たすための組織、役割、手順という要素をもつはずであって、単に要素をかき集めたものはシステムではないということか・・」
| |||||||||||||||
「いえ、単なる私の解釈です。 ただ、世の中にはISO14001認証で会社を良くしようとか、経営に寄与すると語る人が大勢います。私はシステムでさえない『環境マネジメントシステム』なるものをどういじっても会社に貢献するとは思えません」 | |||||||||||||||
「佐田の結論はなんだ?」
| |||||||||||||||
「そう問い詰められても困りますがね。私は会社を良くするには、単なる要素の寄せ集めをいじってもしょうがないということです。いやサブシステムであっても、それを改善しても会社は良くならないだろうと思います。会社を良くするには、包括的マネジメントシステムを考えなければならないということです。部分最適は全体最適とは異なるからです。 そして実は第4の質問でしたが、『体系化された包括的マネジメントシステムというものが必要なのか』でしたよね、それについては場合によっては必要だろうし、場合によってはいらないだろうというのが私の考えです」 | |||||||||||||||
「おい待てよ、包括的マネジメントシステムは組織があれば付随して存在するって言ったじゃないか。システムを持たない組織が存在するのか? 矛盾だぞ」
| |||||||||||||||
「そうじゃありません。体系化されたマネジメントシステムが必要か否かと言うことですよ」
| |||||||||||||||
「なんだその形容詞句は? お前は形容詞句とか形容詞節とか、とにかく条件付とかが多くて逃げを打っているようだ」
| |||||||||||||||
「そうじゃありませんよ。厳密に論じようとすると一般論では済まないというだけです。 本題ですが、組織の構成員の質、組織の目的によっては体系化されたマネジメントシステムがなくても機能というか目的は果たすことはあります。 うーん、卑近な例をあげれば老人が集まって囲碁をするとしましょう。囲碁クラブはれっきとした組織です。しかしお互いが親しくて気心を知っているならばどこでいつ集まるか、クラブの費用はどうするかといったことはわざわざ文書にすることもなく、あるいはお互いに確認することもないかもしれない。囲碁のルールそのものは最低限了解しているわけですし、お互いの棋力つまり何段とか何目差ということも暗黙に了解しているならばですがね」 | |||||||||||||||
塩川はしばし黙って考えている。 | |||||||||||||||
「うーん、なるほどなあ。マネジメントシステムなんて簡単にいうけれど、良く考えると奥が深いものだ」
| |||||||||||||||
「塩川課長のアプローチとは違いますが、そういう佐田流の考えで、審査の効果、認証の効果、環境管理と認証の相関を考えると、論理的にその意義が分るように思います」
| |||||||||||||||
「佐田君は若いけれど、いろいろと考えているものだ。感心するよ」
| |||||||||||||||
「ちょっと待ってくれ、ISO14001では『マネジメントシステムの継続的改善』と言っている。佐田流の解釈ではあれはどう思う?」
| |||||||||||||||
「当然それは必要なことでしなければなりません」
| |||||||||||||||
「あれ、佐田さん、会社で議論したときはマネジメントシステムを改善する必要はないようなことを言っていたじゃないか?」
| |||||||||||||||
「佐々木さん、それはISO14001の範疇では不要だという意味でしたよ」
| |||||||||||||||
「そうです。ISO14001の要求事項は事細かに何を具備せよとか書いてありました。私はそういうものは一定レベルの組織においては必要だろうと思います。しかしレベルが高い組織、あるいはレベルが低い組織においては必要じゃないこともあるだろうし、場合によってはもっと根源的なものに限定すべきケースもあるだろうということです」
| |||||||||||||||
「ということは?」
| |||||||||||||||
「そもそも組織のメンバーの力量とか、組織の目的や業務の性質や複雑さによってシステムの具備すべき要素は異なります。 会社でも言いましたが、すばらしいマネジメントシステムを持っている会社は人の質が悪い会社だからそういうすばらしいシステムが必要なのかもしれないし、優秀な人しかいない会社は明文化されたマネジメントシステムなんてないかもしれない だからシステムの継続的改善は人間社会においては当然のことですが、その結果としての改善は、ISO規格の要求事項の範囲を超えるものだろうと思います」 | |||||||||||||||
「つまり規格要求事項の範囲内の改善にとどまらず、要求事項を変える、いや変え続けていかなければならないということか」
| |||||||||||||||
「そうです。先ほど課長が当社の環境監査の仕組みを変えるとか人を変えると言ったことだって、ISO規格要求事項に止まらない、もっと大局を見たドラスティックなものになるでしょう。 私は最近考えているのは、会社を良くするということは、ISO規格を実現することではなく、小集団活動とか提案制度とか、組織そのものが活性化して、細胞のように分裂し成長していくものではないかと思うのです。規格通りの行儀良い組織はISO9001のように安定して生産するという目的に合っているけれど、活性化した組織の実現とはつながらないように思います」 | |||||||||||||||
「そういうふうになるのかなあ?」
| |||||||||||||||
衝立の陰で二人連れの男が飲んでいた。佐田が話しているとき、二人はじっと耳をすましてその演説を聞いていたのを4人は気付かなかった。 頭を使った話の後は、しばらく雑談をしていた。 | |||||||||||||||
「俺たち三人はずっと本社勤務だったけれど、佐田君は田舎の子会社から来たって聞いた。都会で飲むのは田舎とは違うかい?」
| |||||||||||||||
「大違いですね。田舎では住まいと職場が近いです。車通勤と言っても自宅が10キロ以上離れている人は少ないです。それと公共交通機関がありません。ですから飲んだら奥さんとか子供さんが車で迎えに来る人が多いですし、奥さんが怖い人は運転代行で帰ります。それでも金額的に高くありません。それで飲むのときはトコトン飲みます。私の場合は通勤距離が2キロくらいでしたから、飲まなくても飲んでも歩いて帰りました。飲んだときは、大声で歌を歌いながら30分とか40分かけて帰ったものです。 でもこちらでは家まで電車で1時間とか揺られなくちゃならないのでそうはいきませんね」 | |||||||||||||||
「都会じゃもう少し飲みたいとか語り合いたいと思っても帰ることを考えないとね」
| |||||||||||||||
「飲みすぎると乗り越したりするし、電車の中の酔っ払いは周りから白い目で見られるよ」
| |||||||||||||||
「俺だって飲んでないときは、酔っ払いは嫌いだよ」
| |||||||||||||||
「私は本社に転勤になったとき、あまり通勤時間が長いのは嫌でしたし、乗り換えも難しそうだったので電車1本で来れる市川に住みました。ドアツウドアで30分というところです。でも家賃が高いですね」
| |||||||||||||||
「私は平塚で、ドアツウドアで1時間半かかる。でもここじゃ普通じゃないだろうか」
| |||||||||||||||
「そいじゃ、ここらで切り上げて、群馬県まで帰るとするか。私は片道2時間ですよ」
|
ISO14001規格の意図は「遵法と汚染の予防」なのだそうだ。だがそれは意図であって、ISO規格を満たせば「遵法と汚染の予防」が実現できることが立証されているわけではない。
そしてまた「遵法と汚染の予防」のために、ISO規格が必要条件であるとも十分条件でもあるとも序文にも書いてない。ましてや経営の規格だとか経営に貢献するなどとは書いてない。
じゃあ、いったい何のためにISO規格要求を満たそうとし、お金をかけてISO認証を受けようとするのか? 信じる者は救われるとばかり、ISO14001規格の意図が実現できると解釈して盲従しているのか?
私にはわからない。
ただ認証制度は完全なビジネスモデルであることは間違いなく、認証制度に属する人々にとって認証は善、規格要求は尊重すべき宗教教義であることは間違いない。企業や社会に貢献するかどうかは、二の次三の次であろう。
先日のこと、N師匠と飲んだ時に「マネジメントシステムとはなんぞや」ということが議論になりました。今回、及び前回の文はN師匠への私からのレポートであります。
え、それにしては余分なものが多すぎですか? 及第点はくださいよ。
マネジメントシステム物語の目次にもどる
 前回までのあらすじ
前回までのあらすじ