2016.02.08
お断り |
このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたいという方には不向きだ。 よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。 ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。 |
| タイトル | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| 不合理だから すべてがうまくいく | ダン・アリエリー | 早川書房 | 9784152091758 | 2010.11.25 | 1900円 |
昔、環境経済学なんてのを習ったことがあるが、行動経済学なんてのは初めて聞いた。インターネットで調べると、一般的な経済学のように経済人(経済的合理性の基づいて行動すると想定した人間像)を前提とするのではなく、実際の人間による実験やその観察を重視し、人間がどのように選択・行動し、その結果どうなるかを究明することを目的とする学問なんだそうだ。
ちなみに○○経済学と名がつくものを眺めたら、ミクロ経済学、マクロ経済学、マルクス経済学、資源経済学、交通経済学、実験経済学、空間経済学、計量経済学などなど20も30もあるのに驚いた。いやもっとあるのだろう。
ともかくこのダン教授は行動経済学を研究しており、この本はその易しい解説である。
この学問は頭の中で考えても数式をいじっても意味がない。実際に多くの人に依頼して実験をする。
実験をするには、知りたい判断や行動について、いかなる実験をすればよいのかを考えるアイデアが重要だ。お金をあげらりもらったりするときの判断基準を見極めるにはどんな実験が良いのか、男女交際相手を判断するときどんな方法が良いのか、そこらへんに実験結果がうまくでるかでないかのポイントがある。
実験に日常生活以上のお金を使うときは、生活水準の高い国では費用が掛かるからと、低賃金の国、例えばインドなどで実験するとアメリカの数十分の一で同じことができるという。人間の行動はリッチとプアーではいささか違うだろうが、ま、それも実験のうちなのだろう。
インドで実際にお金を渡して実験したら、持ち逃げされたこともあるそうだ。
どんな実験かというと、次のような状況を想定してほしい。
あなたは2000円渡された。そのお金は、顔も合わせない見知らぬ人と分けあうことができる。このとき、いくらといくらに分けるかはあなたが決めることができ、それで良いかは相手が決めるというわけだ。相手が拒否すれば、相棒だけでなくあなたも1円ももらえなくなってしまう。もちろんその条件は見えない相棒にも伝えてある。
仮にあなたが2000円もらうと言えば、誰だって即拒否するだろう。あなたが1500円、相棒が500円にわけようと提案しても、相手は納得しないだろう。
普通に考えて1000円ずつ山分けするなら拒否されることはまずないだろう。もちろん相手の方が多ければ文句を言われないことは間違いない。でもそれじゃあなたが納得しない。
実際に実験すると。6、4くらいなら大体納得するらしい。4割の800円でももらえるならゼロよりはいいと考えるのは、まあわかる気がする。自分の取り分が700円くらいになると悩み、600円なら分けた方にも渡してなるものかと、ちゃぶ台をひっくり返すというのもわかる気がする。
そんな研究がどんな意味があるのかと思われるかもしれないが、人間は合理的ではないし、理性的でもないから、交渉ごとはそういうことを踏まえて行わなければならないということだそうだ。
| ケース | あなた | あいて | 相手の反応 |
| 1 | 1500 | 500 | フザケンナー |
| 2 | 1400 | 600 | 納得いかねー |
| 3 | 1300 | 700 | うーん悩むな |
| 4 | 1200 | 800 | 手打ちするか |
| 5 | 1000 | 1000 | オッケー |
| 6 | 800 | 1200 | ハッピー |
ここからは私の想像である。
 北朝鮮の核開発を止めるにしても、北朝鮮の連中が核開発の代わりにエネルギーや食糧を援助してもらうとするとき、支援のメリットが核兵器の効果と同等では面白くない、核開発による国威向上より多くの支援を得なければ核開発を止めないということもありえる。
北朝鮮の核開発を止めるにしても、北朝鮮の連中が核開発の代わりにエネルギーや食糧を援助してもらうとするとき、支援のメリットが核兵器の効果と同等では面白くない、核開発による国威向上より多くの支援を得なければ核開発を止めないということもありえる。もちろん北朝鮮に対する勢力側としては核開発を止めるにも、話し合いだけではなく経済制裁さらには軍事制裁という方法もあるわけで、あまり北朝鮮が横暴なら軍事行動という選択肢はもちろんある。お互いに疑心暗鬼、最終的には国家の命運と多くの人命のかかったおおがかりなポーカーゲームとなる。
韓国が従軍慰安婦の謝罪をしろ賠償しろという。日本にとってはそもそもそんなことはなかったと認識しているが、韓国はあったということを信じている。
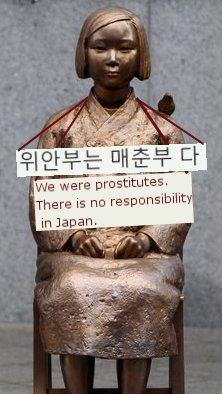 事実認識が異なるのだから、お互いに歩み寄って間を取るというのは、あきらかに日本のほうが分が悪い。交渉ごとの基本から言って過去の交渉スタンスでは既にフィフティ・フィフティなゲームではないのだ。日本はお互いのスタンスを認めて韓国と交渉するのではなく、まずは相手側の認識を断固拒否するというところから始めなければならない。
事実認識が異なるのだから、お互いに歩み寄って間を取るというのは、あきらかに日本のほうが分が悪い。交渉ごとの基本から言って過去の交渉スタンスでは既にフィフティ・フィフティなゲームではないのだ。日本はお互いのスタンスを認めて韓国と交渉するのではなく、まずは相手側の認識を断固拒否するというところから始めなければならない。それどころか韓国は恥知らずで自分の行ったことをすぐに覆すのを厭わないから、既に2015年末の日韓合意を反故にして、日本に謝罪と賠償という要求をしているありさまだ。
ポーカーのような心理ゲーム、外交交渉はそういうジャングルの掟を認識し、対応を熟知してかからねばならない。自分が武力を持たなければ戦争は起きないなんて無邪気な考えでは身ぐるみはがれて命もなくすのが関の山である。
民主党、社民党、共産党はそういうことも知らないのか、それとも中国や北朝鮮あるいは韓国の利益代表なのか、定かではない。いずれにしても日本の大損害をもたらすということでは同じではある。
|
年金が破たんすると言われているからと、年金を納めなければ年金が破たんするのは間違いない。もちろん、年金がもらえなくていいから納めないという決断も個人的には正しいのかもしれない。しかしそれでは
それは年金だけでなく、日常のマナー全般に言える。例えば車内で携帯電話を使うなというマナーが気に食わないと無視すれば、最終的には全員が無視するようになり、その結果は社会秩序が乱れるということになる。行列を守らなかったり教室の私語や電車の中の化粧も同じ、そんなことが定常化すれば礼儀作法が乱れだらしがなくなる一方である。
自分が何かを作るとき、苦労すればするほど出来上がったものの価値があるように思うらしい。
ことわざで「馬鹿な子ほどかわいいって」というのはまさにそのことだろう。
 著者は
著者は私も数年前イケアからトップを広げたりたたんだりできる安物のテーブルを買ってきて組み立てたことがある。組み立て説明は本当に簡単なポンチ絵だけ、ねじが数種類あったが使い分けなど説明なし。不注意な私は、ねじを間違えてしまった。そのためにねじが突き抜けた穴が残って見苦しく、愛着がわかない。
ともかく家具だけでなくプラモデルでも手芸品でも苦労して作ったものはいつまでも大事にするが、簡単に出来上がったものは人にあげたり捨ててしまうということはありがちだ。
多数の男女がいてペアができるとき、ハンサムな男とビューティが対になり、破れ鍋ととじ蓋が対になるという。男性も女性も初めは高いレベルから付き合おうとするが、レベルが高い方が妥協しないので、だんだんと対象レベルが落ちてきて同じレベルに落ち着くので、自然とそうなるのだという。なんかゲームの理論のようだ。それを打破するには、お金持ちになるか、有名になるとか、ルックス以外で優位にならなければならない。人間が合理的に理つめで物事を考え決定していないのは間違いない。つまるところ我々万物の霊長も、メスに餌を貢ぐ昆虫と同じである。
この本は、まあたくさんの事例を挙げてくれる。確かにそうだなあと思うことは多い。だがその結論から得られるものとなるとなんなのだろう? 例に挙げた交渉ごとなどにおいて、相手のペースの飲まれないようにというのは重要ではあるが、それこそ相手も合理的ではないから数字で対応を予測できるわけではなく、実用上はどうなのだろうか、いささか気になる。
人間は合理的じゃないから、多少の判断ミスや失敗を気にするなよということなのだろうか? それならこの本を読むまでもないのだが・・
けっこう多数の実験(ケーススタディ)が載っているのでなんと400ページもあり、読むのに結構時間がかかった。
暇つぶしにはちょうど良いのかもしれない。
この本によると、思い出に残るのは素晴らしい成果を出したことではなく、多くの労力を投入しかつそれが成就した場合だけとある。
大きな成功をおさめてもあまり努力を要しなければ記憶に残らない。他方、一所懸命努力しても結果が出なかったことはすぐに記憶が薄れてしまうというか、むしろそのことを忘れようとするらしい。
仮に私がこれからドクターになろうとして、そのために投入する費用、時間、家庭的犠牲などを考慮すると、
最初70過ぎてと書いたのですが、それはありえないから80に直しました
いえ、私は同志が見事博士課程修了することを願っておりますよ 
ダン先生の本を読んで面白かったので図書館に行って彼の著書を探し2冊ほど借りてきました。
| タイトル | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| 予想どおりに不合理 | ダン・アリエリー | 早川書房 | 9784152091666 | 2010.10.22 | 1900円 |
| ずる-嘘とごまかしの 行動経済学 | ダン・アリエリー | 早川書房 | 9784152093417 | 2012.12.07 | 1900円 |
おっと値段ですが、図書館ならただ、中古なら半値八掛けです。
さて読みましたが・・・
論評を一言でいえば、「同工異曲」ならぬ「同工同曲」で読むまでもなかった。
そりゃ本の中で取り上げている実験は異なりますが、テーマも同じ言い回しも同じ。この先生は1冊読めばもうおしまいって感じですね。
もちろん行動経済学を学んでいる方は読む甲斐があるのかもしれませんが、雑多なことに対して好奇心を満たそうとしている私のような者にとっては1冊で十分です。
大学の先生と言っても、常に新しいことにチャレンジしているわけではなく、学生は毎年変わるわけでこんなものでよろしいのでしょう。
とはいえ単行本をじゃんじゃんと出しても買う人がいるのでしょうか?
そういえば三橋貴明なんて毎年10冊くらい書いているようですね。私も数年前は出るたびに買ってましたけど、もう満腹、お腹ゲップーという感じで今は買いません。本屋で立ち読みするくらい。とはいえ三橋の場合は中のデータがどんどんとアップデートしていますし見解も進んでいますから良い意味の同工異曲で新たに出す意味はあると思います。
でも、アリエリー先生はアリエネーよ♥
推薦する本の目次にもどる