新型コロナウイルス流行で、ほとんどの公共施設も民間施設もお休みだ。私のよく行くところといえば、図書館、公民館、老人福祉センター、フィットネスクラブ、スーパーマーケット、ショッピングモールというところだが、ほとんど休館/休業で、開いているのはスーパーマーケットくらいである。大好きなスイミングも、もう二月プールに入っていない。
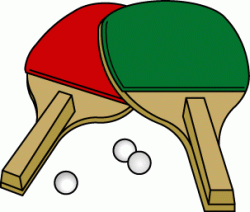 家内も卓球とバレーボールが命という女(婆)であるが、こちらも活動拠点である公民館、市営体育館、小学校の体育館、町内の集会所は、すべて休館である。
家内も卓球とバレーボールが命という女(婆)であるが、こちらも活動拠点である公民館、市営体育館、小学校の体育館、町内の集会所は、すべて休館である。
今は毎日、仲間とLINEや電話で話している。家内が言うには卓球よりもおしゃべり、バレーボールよりもランチが目的というから、方法はともかくおしゃべりできれば良いのだろう。
外出自粛と言われても買い物以外は出かけないというわけにはいかない。まず暇を持て余してしまうし、疲れてないから夜眠れない。それに大事なことだが老人だから体力が落ちたら、元に戻るのは至難と実感している。
過去に整形外科にかかったとき半年くらい運動禁止だった。治癒後、再び以前の前のように泳げるようになるまで数か月かかった。運動禁止どころか出歩くのも禁止が続くと、寝たきり老人になってしまうのではと…
幸いというか我が家は市街地ではない。マンションのベランダから見渡せばどこまでも続く畑と、所々に建売住宅の塊があるという風景だ。さらに遠くには市営墓地が広がる。
こんなところを歩いても、人と出会うのは1時間に二人か三人、散歩しても罰は当たらないだろう。よし出かけるぞ!
千葉県の北半分は下総台地と呼ばれる海抜25mほどの低い平な台地で、それは北は利根川低地、東は九十九里浜、南は上総丘陵、そして西は東京湾に囲まれている(注1)。
分水嶺というのは降った雨が別の海に流れる境目のことで、ほとんどの分水嶺は高い山脈だ。しかし下総台地は低くても左右が海なので、松戸〜津田沼までの新京成線が分水嶺だそうで、分水嶺の北東に降った雨は太平洋に注ぎ、南西は東京湾に注ぐ。その標高が25〜30mしかない。こんな低い分水嶺はめったにありません。
なお、日本で最も低い分水嶺は新千歳空港付近で13.7mだそうですが、本題と関係ありません。
注:新京成線が分水嶺を走るのは意味があります。分水嶺には当たり前ですが川がありません。だから橋梁を作る面倒がないからです。
私の住んでいるところは、下総台地の東京湾側の端です。10年前にここに住み着いたとき、まずは住んでいるところの地形や土地利用を知ろうと、休みの日はマンションから半径数キロの範囲を歩きました。畑ばかりで高い建物がありませんので、1キロや2キロ離れてもマンションが見えるだろう。ならば迷子になることはなかろうと……
甘かったです。
数百メートルも歩くと必ず谷間というか細長い窪地があり、いったんそこに降りると見晴らしはゼロです。そのときはまだスマホを持っておらず、グーグルマップも使えません。迷子になる一手です。
このたくさんある細かい谷間はいったい何だろうと不思議に思いました。とはいえ、そのときはその不思議を解明せずに近隣の探検を終わってしまいました。
定年になり嘱託を勤め63歳で引退しました。
会社を辞めると毎日が日曜日、することがありません。たまたま知り合いに市民大学(俗称:老人大学)に行ったら面白いよと言われました。好奇心フルパワーの私ですから、早速申し込みました。
パソコン、園芸、陶芸、文学、地域研究なんて学科があります。学科によっては希望者が多くて3回も抽選に落ちたなんて方もいます。特にパソコンは競争率が10倍くらい。こういうものは競争率が低い学科を狙うのが鉄則です。一番競争率が低い「地域研究」という科目を選びました。当選確実です。
街の歴史、文化、産業、有名な出身者など毎週2時間くらい座学があり、月一度くらい市内を歩きます。電車に乗って一駅とか二駅移動することもありました。
これが結構面白い。いろいろなことを学びました。江戸時代は天領だったとか、佐倉惣五郎はいなかったとか、関東大震災ではどうだったとか、江戸時代の有名人のお墓とか……
そのなかで千葉県は貝塚が日本で一番多いという話を聞きました。日本全国で貝塚は2,500か所見つかっているそうです。そしてなんと!700か所が千葉県だそうです。
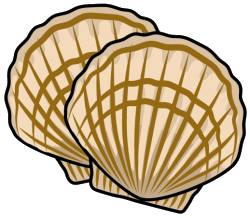 私の住んでいる近所でも、○○貝塚という地名は何か所もあります。最初聞いたとき、こんなに高いところになんで貝塚があるのかと不思議でした。
私の住んでいる近所でも、○○貝塚という地名は何か所もあります。最初聞いたとき、こんなに高いところになんで貝塚があるのかと不思議でした。
私は邪馬台国や古事記が大好きで、それに関する本を200冊くらい読みました(定年退職者は暇だけはあります)。それらによると縄文人がしていた貝殻の腕輪は、千葉県で量産していて全国に出荷していたらしい。ひとつの村で食べた貝殻を捨てた程度では、縄文時代を通しても貝塚の量にならないらしい。また貝塚には、腕輪を取った残りの形状の貝殻がたくさん見つかっているそうです。
私は老人大学を終えてからも、個人的に新たな住んでいるところの歴史を調べました。
驚いたことに千葉県が今の形になったのは、たかだか400年の歴史だったのです。利根川は江戸時代初期までは東京湾に流れていたのですね。流れを変えたのは田中角栄以上の土建屋である徳川家康だったそうです。家康が土建屋の社長だったとは初めて知りました。
お前の話は前振りが長いぞ! タイトルの話が出てくるのはいつだ!
そんな声が聞こえそうです。ごめんなさい。では始まりです。
縄文時代は海面が上昇していて、当時 下総台地の周囲はリアス海岸だったのです。以前私が近隣を歩き回ったとき気づいた小さな谷は、昔リアス海岸だったとき陸地に食い込んだ入り江だったのです。
では時代とともに地形がどんな移り変わりをしてきたのかを知りたくなります。
人の手が入らなければ土地の形が大きく変わることはなさそうです。
なぜなら下総台地は周囲より高いから分水嶺であり、他から川が流れてくるわけはない。下総台地は小さいから大きな川ができない。故に河川によって浸食されることが少なく地形が変化しにくい。川がなければ田も作れず森林ではなく草地が広がる。
江戸時代に藩があったのは小さな川が流れ農業ができるところだけで、田畑ができない残りは天領で馬の放牧場でした。これを開墾して田畑にしようと田沼意次が計画したのですが、失敗して失脚したといわれます。
明治以降は陸軍の演習場だったというのも、それ以外に使い道がなかっただけです。
第二次世界大戦後、入植者を募集して開墾が始まったものの、完了前に高度成長期となり、東京のベッドタウンになって今があるわけです。
さて海面は先史時代から上がったり下がったりしてきました。貝塚が作られたのはBC7,500以降という(注2)。8世紀初めに伝承を編纂した古事記には貝塚に関することは書いてないから、貝塚は民族の記憶にないはるか昔であることは間違いない。その少し後の奈良時代には、貝塚は古代の巨人(ダイダラボッチ)が作ったと考えられていたという。なぜ巨人かというと、人間が食べた貝殻だけでは貝塚になるほどの量ではないからそう考えたらしい。
海面のレベルは時代によって異なる。ネットに「最終氷期以降の海水準の変化(注3)」という図があった。貝塚の作られた時代が正確にわからないが、BC5,000〜7,000年とすると、当時の海面は今より4〜16mくらい高かった。今現在、貝塚跡と言われるところは海抜8mから20mくらいに分布している。また今港町の多くは海抜4mくらいある。
海抜8mの貝塚が作られたとき海面上昇が4mとすると当時貝塚は海抜4m。海抜20mの貝塚が作られたときの海面上昇が16mとすると当時貝塚は海抜4m、いずれも今の港町と海面からの高さが同じになりおかしくはない。
海面が上がり下がりした時の地形を知りたければ、ウェブサイトflood map(注4)で海面をシフトすれば推測できます。
ではやってみましょう。
まず今現在でも江東区、荒川区ではあちこちが水面下に表示されます。ゼロメートル地帯ですね。東京だけではありません。浦安、市川、船橋、習志野、千葉市と海岸沿いはゼロメートルのところが散在しますが、それだけでなくどの市にも海岸から数キロ離れていてもゼロメートル地帯のところがあります。それを知って私はざわざわしてしまいます。高地に生まれ住んでいた私にとって海抜が一桁というところは、恐ろしいとしか思えません。もっとも10年間働いた丸の内は海抜が2mだし、海抜ゼロのサンゴ礁が大好きなのはどうしてなのでしょうか? 人間は矛盾に満ちた生き物なのです。
おおっと、話がまたそれました。
flood mapでは16mがありませんので一番近い13m上昇させると。もう完璧なリアス海岸の完成です。下図ではわかりませんが拡大すれば細かい峡谷がたくさん存在しています。
 |  |  |
市民大学を終えてから、地形を調べることに凝りました。地図を見ただけではイメージがわかないので小学校の社会科で立体地図を作ったのを思い出し、2万5千分の一の地図を買い、それをコピーしてボール紙に貼り等高線にそってナイフで切り、貼り重ね立体図を作りました。それとマンション近辺の様子を比較したりしたものです。
また横道か?
おお、叱られてしまいました。急ぎます。
2020年は新型コロナウイルス流行で開けました。3月には首都圏の非常事態宣言が出され、4月には全国に非常事態宣言となりました。ということで冒頭につながります。
運動をしないと死んじゃう病気の私は、サメのようにひたすら歩き続けました。

注:サメといっても種類がいろいろあって、泳がないと死んでしまうものばかりではないそうです。
今は下総台地の成り立ちやリアス海岸のことを知っていますから、昔ここは入江だったはずとか、この辺りは船着き場で、あそこに貝加工場があり貝塚ができて…とか想像しました。
しかし歩いているうちにそんなのどかなことではなく、危険だなあと思うことがたくさん見えてきました。
リアス海岸といえばだいたいが急峻です。なだらかなリアス海岸なんて聞いたことがありません。私のマンションは田舎にあるといっても、どんどんと都市化が進んでいます。私が住んでからの10年間でも、いくつものマンションが建ち分譲住宅は毎日のように建てられています。
マンションはともかく木造の分譲住宅は、まったいらな農地をつぶして建てられるわけじゃないんですね。農家だって良い畑は売らないんじゃないですか。真っ先に売るのは使い道のない雑木林とか傾斜地とか。
実際に建売住宅は、荒れ地とか雑木林を切り開いて建てられています。その多くは昔リアス海岸だったときの海面と左右の斜面なんです。底地の海抜が数m、上面が25m前後です。石段の勾配から推測すると、崖の角度は35度になります。傾斜が35度で高さ20mのとき底辺の長さは30mです。階段なら普通の勾配ですが、家を建てる敷地となると急傾斜です。
一戸の敷地を100m2(30坪)とすると10m四方です。となるとこの斜面に3戸建つことになります。まあ限界いっぱいに建てることは少ないでしょうけど。
グーグルマップを航空写真にして眺めると面白いです。畑の中を住宅地が幅10戸くらいでうねうねと続いているわけです。どんどん都市化されると農地がなくなりすべて住宅地で埋め尽くされますが、このうねうねはなくなりません。まさに現代のリアス海岸です。
 |
実際に傾斜地に建ち並んでいる家々を見るとゾッとしますね。上の段と下の段の家は良いですが、ひな壇の中ほどに建てた家は道路に出るには石段を昇り降りしなければなりません。
 車椅子はもちろん老人とか足腰が不自由な人は、家に出入りすることが重労働でしょう。
車椅子はもちろん老人とか足腰が不自由な人は、家に出入りすることが重労働でしょう。実は今回も散歩で上の道路と下の道路をつなぐ石段を登っていたら、階段途上にお住いの老人が顔を出して、「すまんが上のゴミ集積場までごみ袋を持っていってくれんかね」と頼まれました。
70過ぎの私でも、その老人より若そうでしたから、ここは片肌脱ぐしかありません。
下の段の人は1階部分を、上の段は屋根を駐車場にしているところもあります。途中の家で駐車場を付けられなければ、近くに駐車場を借りるしかありません。
普段の出入りだけでなく、ひな壇の途中の家が火災になったら避難や消火をどうするのか? 狭い石段を消防車からホースを持っていくのでしょうか? 急病人がでたらストレッチャーを使わず、抱っことかおんぶして運ぶのでしょうか?
市原市に住んでいる家内の友人は、2019年の台風で崖が崩れて犠牲者が出た近所です。数年前に家内と私が遊びに行きました。
屋敷の裏を見ると、家のすぐ後ろが高さ15mほどの崖です。台風や地震でがけ崩れなんて起きないのだろうかと思いました。私が心配しているのに気付いた友人は、建ててから20年経つけど、そんなこと起きてないから大丈夫といいました。
まあ危険がないと考えたからそこを買ったのでしょうけど。20年災害がなくても21年目にあるかもしれないとは想像できないのでしょうか? 今は近所でがけ崩れが起き住民が亡くなったわけで、心中穏やかじゃないんじゃないかな。
基本的に傾斜地は時と共に必ず崩れます。永遠にくずれない崖は存在しません。
注:崖に限らずすべてのものは崩壊する。
ちょちょっと作ったコンクリートののり面は、7,000万年どころか70年はもたないだろう。
崖崩れが起きたとき、土盛りしたところが崩れたとき、どうするか考えておかなければならないでしょう。
リアス海岸の斜面が悪いなら、元海であった底地ならいいのか?
くぼ地であっても広ければいいですが、元々小さな入江ですから、底部の幅が30mとか広いとこで50mしかない。道路がありますから、小さな分譲住宅でも4軒も並べばいっぱいいっぱいです。左右は急な崖ですから、日当たりが悪い。日が差すのは良くて半日、崖の上に家が建てばなお短くなる。
もっと心配なのは水害です。台風などでがけ崩れが起きれば交通途絶。元々底地で海抜が数メートル、津波とか高波がきて海岸の堤防が決壊したらおしまいです。台地の上の水路が決壊しても同じ。リアスの谷にある川/堀が溢れたら即洪水です。
別にそれほどのことが起きなくても、普通に雨が降ると上から下に水が滝のように流れるようで、石段の上には土嚢が積んでありました。土嚢で水を堰き止め勢いをそぐらしい。
注:歩いていて気が付いたのですが、くぼ地の崖の上の海抜は海から離れるほど高くなります。といってもマックスで25mくらいです。しかし底地の海抜は5mくらいなのは変わりません。川なら勾配分だけ海から離れれば高くなりますけど、海面の高さは一定です。だから海岸から離れるほどリアス海岸の崖の高さは高くなります。
スマホのアプリに「高度計」というのがあります。私がインストールしているものは、気圧計、座標に基づくもの、GPSに基づくものと3種類入っています。これで海抜をチェックしています。メートル単位でわかります。
 もっとも液状化は起きそうありません。なにしろ海から陸地になって数千年というときが経っていますから地盤はそこそこしっかりしているようです。
もっとも液状化は起きそうありません。なにしろ海から陸地になって数千年というときが経っていますから地盤はそこそこしっかりしているようです。
実はここに書いたことは、わざわざ歩き回ったり、flood mapをいじったりすることはなかったのです。住んでいる市が配っているハザードマップに全部書いてありました。もちろん紀元前数千年前に海面はここまで来ていたとか、リアス海岸だったとかは書いてありません。でも洪水の危険、津波の危険、がけ崩れの危険、そういうことが網羅されています。
2018年の大雨で洪水になった倉敷市真備町の、水害を受けたところとハザードマップが完全に一致していたのには驚いた。この災害対策は、まずはこの地区への建築制限ではないのだろうか。いや、家を買うとき建てるとき、ハザードマップで危険性を確認することは当たり前のことではないのか? それをせずに購入したり建築したりする人の気が知れない。
もちろん我々は家を買ったり住まいを借りたりするときは、ハザードマップを見て決めなくてはならない。そこに住まなければならないなら、避難場所・避難経路を知り実際に試行しておくのは当然。常在戦場である。
![]() 本日の故事成語
本日の故事成語
「敵を知り己を知れば百戦殆からず」と孫子は語ったそうです。
でもこれって真理だと思いますか?
私は違うと思いますよ。いつどんな災害が起きるか分かっても、対応できないこともあります。関東大震災、南海大震災その他いろいろと懸念されていますが、それらに完璧に対応するなんて不可能でしょう。
できることは、失われる命や被害を減らそうとすることだけではないですか?
それでさえ、危ないものには近づかないという条件付きです。崖をひな壇にして住むとか、谷底に住むという選択はないでしょう。
![]() 本日のごめんなさい
本日のごめんなさい
脇道に逸れっぱなしで終わりませんでした。
次に続きます。
注1 | ||
注2 | ||
注3 | ||
注4 |
ひとりごとの目次にもどる
うそ800の目次にもどる