退職してから英会話教室に通っていたが、1年半ほど前にやめた。理由はまずお金がかかる。年金生活者には月1万は大金である。それと学ぶ内容についてである。
 何年も前 入会するとき、海外旅行のとき出入国管理とか買い物などで、今のようにワンワードとかフレーズだけでなく、文章にして話せるようになりたい、そのほか言い回しを略されたり早口で話しかけられたりしたとき、瞬間的にそれに対応できるようになりたいと言った。
何年も前 入会するとき、海外旅行のとき出入国管理とか買い物などで、今のようにワンワードとかフレーズだけでなく、文章にして話せるようになりたい、そのほか言い回しを略されたり早口で話しかけられたりしたとき、瞬間的にそれに対応できるようになりたいと言った。
私はあまり高尚というか複雑な話でなく、即物的なケースにおける対応力を上げたかったのだ。先生は相分かったと言った。
ところが実際に始まったレッスンの内容はそういった即物的なことでなく、テーマが日本と欧米の文化の比較とか生活習慣を話し合ったりするもので、話題も設定も希望と違った。しかしそれはともかく私にとってネイティブと話すのは、めったにない体験だから文句を言わず面白くやっていた。しかし数年やればもう十分だ。
英会話教室をやめても英語と縁切りする気はもちろんなく、初歩からやり直そうと本屋で中学英語が1冊になったテキストを買ってきて、毎日2ページずつ例文を読み、書きとり、タイプを打ち、解説を読み、ヒアリングするというのを繰り返している。実を言ってもう同じ本を頭から尻尾まで5巡くらいした。しかしそれでもやる度に あれっ!ということがあり、まだまだ中学課程さえ卒業に至らない。
そんなことをしていて文章にWednesdayとあるのを見て、なんで「d」があるのに読まないのだろうと疑問に思った。
ネットでググると、「北欧の神話でWoden(ウォーデン)という神様がいて、水曜日はそのウォーデンの日だったそうです。なお今現在のスウェーデン語やノルウェー語では、水曜日をOnsdag(オンサ)というそうです。
それが英語に入ってきてWoden's Day(ウォーデンズデイ)となり、更に一語となってWednesdayになった。ときが経つにつれスペルは変わらないが言いやすいように読みがウエンズデイに変わった」とあります。もっともイギリスでは昔ながらのウェーデンズデイと読む地方もあるそうです。
なるほど、そういう謂れを聞くと納得してしまいます。
ところが音とスペルが異なる単語はたくさんあり、そうなったいきさつは一通りでなくさまざまなのです。
knifeとかknowは「k」を読みません。昔々はいずれも「k」を読み「クナイフ」とか「クノウ」と言っていたそうです。それらは単に言いにいくいために時とともに読まなくなったようです。
もっともアメリカ人にスペルに「k」が無用だと言ったら、「
実はこれにはいきさつがあります。昔々「泉の国(今の大阪の南西部)」がありました。713年に「二字佳名の詔」というお達しが出て、国名はすべて漢字二文字にすることになった。理由は中国の地名がみな二文字だったのでその真似らしい。
それで「平和な泉の国」の意味を込めて「泉の国」を「和泉の国」に改名した。それで泉さんも和泉さんに改名したそうな。
じゃあ、今もいる泉さんはどうなんだとなるけど、「二字佳名の詔」は個人の名前まで強制しないから、気にしない(気が付かない)人もいたということらしい。
では借金のdebt(デット)はどうかとなると、複雑怪奇。これは元々ラテン語のdebitum(デビタム)がフランス語に入り、使われるうちに言いにくいからとdette(デット)となり、それが英語に取り入れられdette(デット)のまま使われた。
ところが時代が下りラテン語が変化してdebte(デット)となり、ラテン語でもスペルと読みに乖離が生じた。13世紀にルネサンスが始まりフランスでラテン語に原点回帰しようという機運が高まり、改めてラテン語のスペルと読み方が取り入れられた。
これが更に英語に伝わり、debt(デット)となったという。
当時はフランスでもイギリスでも、識字率が非常に低く、文字を書くのはほんの一部であり、スペルが変わっても影響を受ける人はわずかだった。一般人は古代から現代までスペルの変化に関わらず「デット」と言うことに変わりはなかった
三人称・単数・現在、俗に三単現と言われますが、動詞の末尾に「s/es」が付きます。中学のとき「三単現のSを忘れるな」と英語の先生に耳にタコができるほど言われたものです。
なぜ三単現には「s」が付くのか?
ネットをググったら、これまたその解説がたくさんある。他の言語との関連などいろいろな考察があるが、私のような言語学の素養がないものは理解しがたい。
ただ分かったことは、三単現だから特別に「s」が付くのではないということだ。
昔々、といっても英語が成立したのは奈良時代くらいでそんなに昔ではない。その頃は人称と時制に対応して動詞の語尾が変化した。つまり一人称単数現在ならこうなる、二人称単数現在なら……三人称複数過去なら語尾はこうなると、
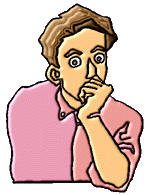 |
そのため通常は主語を省略したらしい。主語と時制によって動詞の語尾が変化するから、主語がなくても誰が言ったかわかるのが日本語と違う。
しかしどの言語も時代とともに体系化され文法が整ってくる。英語の場合、人称/時制による語尾の変化がなくなり、三人称単数だけが残った。もちろんその代わり、主語を省略しなくなった……というか省略できなくなった。言語が標準化、構造化されてきたのだろう。
それを知ってなるほどと思いました。しかし動詞の変化だけでなく言葉の変化も不規則極まりないと感じました。言葉の変遷を一般化できる法則がない。言葉を覚えるにはひたすら暗記しかないのか!
まあ疑問を持ちたびたび調べるようになり、そういうことを単発的に知るのでなく、英語の歴史を体系的に知りたいなと思った。
英語の歴史の本てあるのだろうかと、市図書館の蔵書検索で「英語+歴史」で検索すると、なんとなんと600冊もヒットした。これは暇つぶしになりそうです……いやいや、勉強になりそうです。
会社を辞めた年に、邪馬台国と古事記関係の本を200冊ほど読んだ記憶があります。当時はものすごく興味を持っていて集中できたのだと思います。ならば英語の歴史の本を200冊も読めば……
ということでとりあえず読んだのが下記の通り。
| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| はじめての英語史 | 堀田 隆一 | 研究社 | 9784327401689 | 2016.12.01 | 2200円 |
| スペリングの英語史 | サイモン・ホロビン | 早川書房 | 9784152097040 | 2017.09.21 | 2970円 |
- 「はじめての英語史」
難しくないのだが、とんでもないボリューム。大量の情報の海でほんろうされます。
私たちが興味がある動詞や複数形の不規則変化とか、サイレントの発生した理由など、ほとんどが網羅されています。
すばらしい! - 「スペリングの英語史」
難しくて途中でギブアップ!
単にトリビア的に知識収集なら、つまみ食いでも良いでしょう。しかしスペルの変化とか意味の変化などを包括的に体系的にとなると、理解しなければならないことは膨大です。とても無理! すぐに音を上げました。
ところで英語の歴史を読んでいると、じゃあ日本語の成立から変化は、どうなのだろうと思うのは当然の流れです。
これも市図書館の蔵書検索で「日本語+歴史」で検索すると、700件くらいヒットしました。さすがに英語の歴史より日本語の歴史のほうが多い。
その中から初歩的と思われるものと、古代の日本語が書いてありそうなものを選んで読みました。下記に示します。
| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| 倭人語の解読 | 安本美典 | 勉誠出版 | 9784585051220 | 2003.05.01 | 3520円 |
| 日本語の歴史 | 山口仲美 | 岩波新書 | 9784004310181 | 2006.05.19 | 902円 |
| はじめて読む日本語の歴史 | 沖森卓也 | ベレ書房 | 9784860642556 | 2010.03.25 | 2000円 |
| 日枝阿礼の縄文語 | 辻本政晴 | 批評社 | 9784826505352 | 2011.01.01 | 890円 |
| 図説日本語の歴史 | 今野真二 | 河出書房 | 9784309762371 | 2015.11.25 | 2200円 |
| 日本語全史 | 沖森卓也 | ちくま新書 | 9784480069573 | 2017.04.05 | 1320円 |
| 漢字と日本人 | 高島俊雄 | 文芸春秋 | 9784166601981 | 2001.10.19 | 720円 |
一読してなるほどと思ったものもあり、こりゃなんだ!ふざけるなと思うものありの玉石混交です。
- 「日枝阿礼の縄文語」
読んで呆れた。研究も論理もなく、思いつき、こじつけ、想像、願望を書き連ねているだけ。いずれにしても脈絡がなく話が飛びすぎていて説得力はない。
「相手を呼ぶとき、ガガとかキキというより、ヨヨと言ったほうがなんとなく振り向いてくれるように思う」と言われても、私はそう思えない。
ひょっとして、この本全部がネタとかジョークなのか? - 「倭人語の解読」
著者が書いていることが事実か否かはわからないが、アプローチとその労力は本物だ。ただ「倭人語の解読」というよりも「魏志と記紀の解読」のような気がする。
いずれにしても縄文とか邪馬台国時代の日本語はどうであったのかは、証拠不十分で想像の域を出ないようだ。 - 「日本語の歴史」
文字に書かれるようになってからのはなし言葉の変化がメイン。もちろん文字のない時代の記録はないわけだが、他の本では半分想像であっても検討しているが、この本では物的証拠がある範囲だけ。
実際の発音はどうだったのかとわずかな証拠から考えるのがすごいと思う。
ともかく書き言葉はもちろんだが、話し言葉というものは移ろいやすいどころか、常に漂い変化していくということを知った。
そして絶対に戦国時代以前とは外国語と同じで、語彙も言い回しも違うから意思疎通はできそうない。江戸時代以降なら方言とか訛りの違いでコミュニケーションは可能だろう。とはいえ50年前、北東北を旅した時、土地の古老と話が通じなかったが、それと同じ状態になることは間違いない。 - おすすめ
「はじめて読む日本語の歴史」と「図説日本語の歴史」がお菓子の食べながら読めてためになる。
これ以外は、正座して読む感じ、
さて、古事記の本は200冊読んだと書きました。日本語の歴史の本は、まだその1割も、いや5%も読んでいませんが、もうたくさんという感じになりました。
なんといいましょうか英語の場合、もともと身近な言葉ではありませんから規則性がないとどうしてだろうと気になります。
しかし日本語の場合、動詞の変化だって英語に負けず複雑で、五段・上一段・下一段・カ行変格・サ行変格とあるわけです。ところがですよ、普段は、いやいや生れてから死ぬまでそんなこと気にせず日本語を話しています。自分が日常使っている言葉の不規則性に疑問を持たずに、playはplaysなのに、studyはstudiesではおかしいって、思うこと自体がおかしいじゃないですか。
例を挙げます。oftenって中学校で「オーフン」て習いました。そして「オフトン」と読む人もいるとも習いました。しかし英会話教室でカナダ人の先生が話すと、ときによって「オーフン」もあり「オフトン」もあり……、
先生にどっちが正しいのと聞くと、「?」てなもので、そもそも本人が二通り発音しているのに気付いてない。前後の関係でゴロがいいほうで話しているくらいの感じなんでしょうか。
とはいえ、それは英語だけじゃない、日本語だって同じ。類似例を挙げてみましょう。
我々は「やっぱり」という言葉を日常使う。「やっぱり」は「矢張り」の変化。「矢張り」は当て字で漢字に意味はないらしい。「矢張り」は「従来と変わらない」「思った通り」という意味で、江戸時代以前から使われている。
夏目漱石が書いた小説の原文には、「矢張り」と「矢つ張り」が混在していたという
私の場合、普段は「やっぱり」が多いが、人前で話すときは「やはり」を使う。上品とか正しい言い方という思いがあるのだろうか?
もし英会話の英語の先生に「やはり」と「やっぱり」の使い分けをどう考えているのかと、問い詰められると答えに困る。
「オーフン」も「オフトン」も似たようなものではなかろうか。
スペルと読みが違うことを、おかしいと思うのがおかしいとも言える。
日本語だって前述した「和泉」もある。
ともかく「泉」と「和泉」は関連がなんとなくわかる。しかし
ならば、knowとか、high、climb、hour、wrongくらい、不思議と思ってもおかしいというのは言い過ぎだろう。
「ら抜き言葉」というものが話題になったのはもう昔の話。今は市民権まではいかずとも、永住権くらいはゲットしたようだ。だが私は今も「ら抜き言葉」に賛同できない。「食べれる」なんて聞くとザワザワする。
とはいえ実は私も「ら抜き言葉」を使っている。「食べれる」と話したことはないが、例えば「起きられるか」と言ったことは一度もない。生れてから古希を超えた今まで、ずっと「起きれっか」と言う。親兄弟、周りの人もみなそう言ってたからだが、それは方言なのだろうか?
ともかく「食べれる」に拒否感を持つのは、私がダブルスタンダードだと認識する。
「ら抜き言葉」に納得しない私だが、私が正統日本語を使っているかというと、ぜんぜんそうじゃない。マイクロソフトWordで文章を書くと、誤字・脱字、主語と述語が対応しないなどあると、青いアンダーラインがついて入力者に教えてくれる。
今書いているこの文章にも、青いアンダーラインが10数個表示されている。そのほとんどは「い抜き言葉」である。「い抜き言葉」とはあまり聞いたことがないかもしれない。「おっしゃってます」とか「住んでた」「してない」という言い方、書き方だ。このアンダーラインを消すには「おっしゃっています」「住んでいた」「していない」と「い」を加えないとならない。私は修正しませんけど…
なお大学の先生などによると、「い抜き言葉」はカジュアルな会話ならOKで、公式な話や文章においてはダメという。もっともこれは社会に出る人への教育的指導だろう。
言葉の意味は固定しているわけではない。報道機関や官公庁で使われると新しい意味を持つし、それがどんどん変わる。
以前書いたことがあるが、現役時代、通勤時に京葉線の市川塩浜あたりで毎日「あらた」というひらがなの看板を見ていた。「あらた」とはなんだろうと気になった。
社名の由来は中国の古書「大学」からで、現代語にすれば「自分を向上させようと日々励めば、自分は新しくなる」のだそうです
待てよ、「あたら」と「あらた」は違うではないか?
「あたらしい」の古い言い方は「あらたしい」で、「あらためる」の派生語だったらしい。それが平安時代に言いにくいためだろうか、「あたらしい」と言われるようになった。そして元々あった「あたらし」とは「惜しい」の意味であるが、「あらたし」が「あたらし」と言われるにつれ使用されなくなったとのこと。とはいえ今でも「あたら若い命を散らす」など特定の表現に残っている。
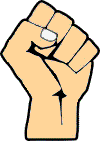 「総括」とは辞書によると「全体をまとめる」意味である。しかし1970年代、連合赤軍などの過激派では「反省する」から「責任を追及する」そして「罰を与える」となり、さらには「考えの違う者を文字通り殺す」意味となった
「総括」とは辞書によると「全体をまとめる」意味である。しかし1970年代、連合赤軍などの過激派では「反省する」から「責任を追及する」そして「罰を与える」となり、さらには「考えの違う者を文字通り殺す」意味となった
従来からある言葉でないが、オウム真理教が使った「ポアする」が同じ意味で使われたのは1990年代であった。
時が流れ「総括」は本来の意味に戻り、「ポアする」は死語となった。幸いなことである。
都知事の小池百合子氏は英語大好き人間で、カタカナ流行語を量産している。都民ファースト、オーバーシュート、ステイホームなんてね。そんな意味なら、カタカナ語を使わずとも日本語でも十分表現できるだろう。小池都知事は、目立ちたいのか?
日本語を使えと言いたいのは私だけではあるまい。実際に河野太郎大臣は「なんでカタカナを使うのか」と疑義を呈している。
ともかく上記のように日本語の歴史の本を読み、2週間ほどいろいろ事例を考えていると、言葉の変遷を知りたい、日本語の歴史を知りたいという意欲は薄れた……いやいや、目的を果たしたと言い換えよう。
日本語も英語も長い歴史がある。けれど1000年もさかのぼると、語彙も文法も大きく違い日本語とも英語とも言えなくなってしまう。
そして現代語とコミュニケーションが成り立つ、つまり今我々が使っている言葉で会話できるのは、せいぜい過去150年くらいに過ぎない。そう言うとあまりにも時間的に短くて驚くかもしれない。
とにかく言葉というものは科学や数学と違い、移ろいやすくその変化は理屈じゃなくて多様な外乱とか人の感情によって動くということだ。
また必要に迫られれば言葉を統一したり、標準語を強制することもある。
そしてマスコミュニケーションの発達によってしぜんと統合化、標準化もされる。そして変化する速度も加速される。
こんな話を読んだことがある。西郷隆盛が九州で兵をあげた西南戦争は1877年(明治10年)のこと。それを制圧するために日本各地から集められた政府軍が九州まで行って戦ったのだが……政府軍の士官が号令をかけると各地から集まった兵隊がちゃんと行動するのを見た人が驚いたという。当時あまりにも方言の違いがひどく、遠い地方の人とは意思疎通が難しかった。それを士官の命令を聞いて行動したことが驚きだったのだ。150年前のことである。
そういうことを踏まえると、タイムスリップで江戸時代に行ったり、戦国時代に行くお話は多いが、現実にはあり得ないのは間違いない。
TVドラマ「仁」も、コミック「最後のレストラン」も、ネット小説「戦国小町苦労譚」も、みーんなありえない。と言っては夢がないけどね、
私は足利義満とも、織田信長とも、徳川吉宗とも、会話できない自信がある。坂本龍馬とか徳川慶喜でも無理だろう? 東郷平八郎とか高橋是清あたりなら、言葉が通じるだろうか?
明治16年生まれの父方の祖母と話ができたのは間違いない事実だが、それは祖母のデータベースが昭和にバージョンアップされていたからだ。
それは日本語だけでなく英語でも同じだ。
500年前のシェークスピアの原文を読めるイギリス人は一般人にはいないらしい。また喜劇を観てもなぜ面白いのかわからないそうです。喜怒哀楽の感覚も時代によって大きく変わったのでしょう。
だいぶ前、チャールズ皇太子が来日したときに、日本にシェークスピアを研究するグループが多数あるのを知って、イギリス人が理解できない古典を、日本人が理解できるとはすごいと皮肉を語ったそうだ。
いやいや反発することはありません。文化も宗教も価値観も違う人を理解するって難しいと思いますよ。
「日本語の歴史」となんてすごいタイトルをつけた割に、しょぼいぞというお叱りが来ることを予想する。私もそう思います。
まあ、おばQが大それたことを考えても、やることはたかが知れているという証左でありましょう。
でも「雨がしょぼしょぼ」って言いますかね? 「雨がしとしと」じゃないのかなあ〜
ともかく本日の出し物は、しょぼくて相済みません。
「はじめての英語史」堀田隆一、研究社、2016、p.55 | ||
「はじめての英語史」堀田隆一、研究社、2016、p.58 | ||
「日本語の歴史」今野真一、河出書房、2015、p.151 | ||
| ||
外資社員様からお便りを頂きました(20.12.18)
おばQさま いつも興味深い話題を有難うございます。 何と「二字佳名の詔」とは、ずいぶんとマニアックなものが出てきました。 ISOを離れると、深いエッセイになってきて、勉強になります。 例によって主旨と無関係の部分突込みです >主語がなくても誰が言ったかわかるのが日本語と違う。 源氏物語を読んだ時に思いましたが、主語の無い文章をダラダラと続けていて、技術文書とは対極にある文章と思いました。でも主語が無くても誰が言ったかわかるのですね。 日本語には主語による格変化は無いですが、敬語は多種多様に存在し、目下、同格、目上(年齢上と身分上、主筋)、高貴など敬語表現が様々にあるから、結局誰に言っているか、誰が言っているかわかる、というよりも、それが判る事が「源氏物語」を読めるという事。 習得しないと判らないというのが表現として適切かは別にして、そのような世界があったのが面白かったです。 とは言え、記事にもおかきになっているように、日本語も変化してゆく。 私もWORDで「一つづつ」と書くと青線を引かれ旧仮名遣いだと言われることしばし。 でも接続助詞の「つつ」は「すつ」にはならないだろうと思いつつ、言葉は変わるのだと感じております。 日本語については、高島俊雄さんの「漢字と日本人」などはお勧めです。 (すでにお読みでしたらご容赦を) 何で日本語での漢字の読みが、難しいのかという事を上手く説明してくれます。 そして、日本語が哲学や科学表現に向いていない、というよりもそうした分野には漢字やカタカナ語を使わざるを得ない理由も良くわかりました。 名前のネタ:日本は漢字を多言語の中国から借りてきたから、文字の意味と用法の乖離がおきますね。 中国で仕事をしていた時の同僚で「浅見(あさみ)さん」 名刺を出すたびに微妙な顔をされていました。「浅見」は中国語では「見方が浅い」という熟語なので信用されない。 その後は「ASAMI」と名刺を変え漢字は使わず。 スポーツ選手で「米田共子(よねだともこ)」さん、中国で国際大会があった時にある問題が。頭の体操としてお考え下さい。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 おっしゃるように技術文書と詩歌は対極ですね。文系の頭脳を持っていない私には、源氏物語どころか大日本憲法どころか、旧民法でさえ?(ハテナ)でございます。 「ひとつずつ」とか「ちかじか」とかどう書くべきかわからないことが多いですね。辞書を引くのも面倒なのでワープロで打ち込んでアンダーラインがでなければOKというのが私の流儀です。 「漢字と日本人」読んだことありません。図書館の蔵書にありましたので予約しました。 米田共子さん、わからずネットをググりましたが引っ掛かりません。縦書きしてみてわかりました。中国でなくてもお習字などすると気が付きますね。名前変更申請するレベルでしょうか? |
うそ800の目次にもどる
独り言にもどる