私は過去より第三者認証の改善について何度も何度も書いてきた。というよりもこの20年も書き続けたウェブサイト全体が、ISO審査の問題提起と改善提案である。
前回は力量不足の審査員が存在することが問題であり、だから審査員登録や更新時の評価をしっかりする必要があると書いた。今回はその続きである。
注:ISO審査の問題・トラブルの原因がすべて審査員にあるわけでもなかろうというご意見があるかもしれない。
そのとおりだ。
だからこそ実情調査が必要であり、その結果、審査員が原因でないと判明すれば、それはそれで結構なことだ。
審査員の登録時や更新時の評価や判定を、精度よく漏れなくするにはどうすれば良いのか?
「改善は測定に始まる」といわれる。お仕事なら品質向上でも省エネでもコスト削減でも、個人的なことなら家庭の炊事や掃除あるいは友人間のコミュニケーションでも、いかなることの改善においてもそれは真理である。
測定といっても数値で表せないこともある。だけど代用特性や定性的な表現でもよいが現状を正確にきめ細かく把握することが必要だ。代用特性がないなんて言ってはいけない。それなら自分が考えてあみださなくてはならない。
審査員の評価や判定をしっかりするためには、まずは現実の審査の状況を把握しなければならない。そしてその現実と現状の問題を考慮し、問題のない人をパスさせるという単純なことだ。いや問題の人をはじくというべきか?
第三者認証の顧客である企業から見れば、派遣されてくる審査員が今まで問題を起こしたような人でなければ必要十分である。
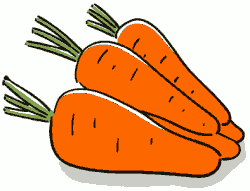
|
我々企業から見れば、問題のある審査員の是正したり力量向上を図る必要はない。もっともLMJのお話では審査員に不向きな2割の人はどうしようもないわけだ。ともかく問題のある審査員をどうするかは認証機関が考えることだ。
前回も述べたがスーパーで良いニンジン(審査員)を選ぶ権利は消費者(受査企業)にある。売れ残りのニンジンの処置はスーパーのバイヤー(認証機関)がすればよく、売り物にならないニンジンを減らすのは農家(審査員研修機関)が考えることである。
さてあるべき姿とか問題を起こさないは、何をもって測るのか?
ISO17021とかISO19011を持ち出してもあまり意味はない。現に起きている問題が何なのか? それを解消するのが顧客要求水準である。
従来の審査員研修修了の試験では不十分であることは明白だ。前回は審査で多々問題があり、認定機関の理事長がおっしゃるように企業が虚偽の説明をしてもそれを見つけることができない人がいるのだ。そしてまた彼ら節穴審査員(注1)も現行の審査員育成のコースを経て試験合格して審査員になっているのが事実だ。
要するに求めることは「良い審査」ができることである。つまり前述した「ISO17021に基づく社会常識とマナーを守った審査」ができる人である。
具体的に言えば、それはビジネスマナーがあり、規格要求を理解して個人的見解を含めず見逃しをしない人。また審査報告書を正しい日本語で論理的に記述できることくらいだろう(注2)。それは審査員に限らず社会人として当然のレベルでもあろう。
そしてそれができない人を審査員に登録しないこと、既に審査員であれば資格更新しないことが次のステップとなる。
ともかくそのためには従来に増して、試験や評価の精度を上げ、厳密に運用することが必要だ。
とはいえ、その全体像を語ると膨大であるので、本日は審査トラブルをなくすための方策に限定して語る。
現状のISO審査での問題とは何だろう?
では最初のステップは現状の問題を把握することだ。
まず現状把握で重要なことは一般論ではなく、個別論・具体的事例である。キプリングではないが5W1H、つまり、いつ・どこで・誰が・何を・どうしたが必要だ。
水質測定データの改ざんがあった、虚偽の説明があった、記録がない、そんな散発的な問題の把握では統計処理もできない。なにごとも「現場・現実・現物」である。
次にデータは数が勝負だ。もちろん正しいデータという形容詞付きだが。QMSとEMSの登録件数が減少しているとはいえ、2020年現在4万件あるわけで、毎年の審査でその1割に意見の相違があったとすれば4000件、ISO認証している会社の1割4000社も抜き取れば400件くらいのトラブルを収集でき、統計処理をするには十分だろう。
- 今ある情報が使えないか?
- 認証機関が審査後に取っているアンケート?
そんなものが役に立つはずはない。どの会社だって認証機関への回答はきれいごとを書いて、社内では「あの審査員は次から拒否しろ」とか「認証機関を変えることを考えよう」なんて話し合っていますよ。 - 苦情、異議申し立て?
顕在化しているのは氷山の一角、ダークマターは見えません。
ここはひとつ大規模な調査をすべきです。第三者認証制度の存続のためですから何億円かかけても良いじゃないですか。
- 認証機関が審査後に取っているアンケート?
- 調査方法
私が考えているのは、認証機関単位とかJACB、JABがするのではなく、専門の調査機関に依頼して、全認証機関の認証企業から抜き取りして訪問面接調査でなければならない。
何を聞き取るのかといえば、過去に行われた審査での問題・トラブルを聞き取り、それが発生した推定原因についてISO19011を参照して聞き取てばよい。
この調査は監査と同じく簡単なことではない。まずクローズドクエスチョンでは不適である。オープンクエスチョンで対応者から実態を聴取する必要がある。
だから収集する情報は決まっているわけだが、アプローチ方法、質問の仕方など具体的なことは、相手を見て調査員が考えることになろう。
となると調査員は、ISOMS規格はもちろん、ISO第三者認証制度、ISO17021やISO19011などの審査規格、また第三者認証の問題や不祥事についての知識が必要となる。
そのような知識がある人となると一般のアンケート会社や総研では能力不足かもしれない。
ぜひ私がと言いたいところだが、無名の私にお呼びがかかるとは思えない。
おっと審査員登録機関の判定委員はどうかというご提案は却下する。だって審査員認定機関の判定委員の中には「有益な環境側面が必要です」なんて語る方が複数いたから論外だ(CEARからJRCAに代わった今はどうだろう?)。それに彼らが節穴審査員を合格としてきたわけで、節穴判定委員なのかもしれない。
もちろん最終的に問題とその評価などが公表されれば、それは多くの人の目にさらされるから審査員の評価は同時に判定委員の評価でもある。そうなれば必然的に判定委員の力量が暴露される。そう考えると初回は審査員登録機関の判定委員が行うことが良いかしれない。
Sセンセイ、いかがでしょうか?
どんな問題でも同じだが、実態調査をするとたくさんの問題が出てくる。それらを似たようなものをグループにまとめるだけでそれぞれの原因が見えてくるものだ。そんなことを大昔の小集団活動で習った。
ところでKJ法とクラスター分析は同じことなのだろうか? それとも違うのか? ネットでググったがわからなかった。
もちろん類似の問題を集めても原因がわからないこともあるだろうが、まとめることにより問題点は整理される。
- 結果の広報
人名は出さずとも次のような情報があればよい。
どのような問題が起きたか、
分類分け(ex. 規格解釈、発言・態度、要求事項の過大/過小、証拠/根拠、ビジネスマナー)
問題点と判定結果が公開されれば、審査員と企業側が何が問題か問題でないかの認識を持つだろう。それは以降の審査に反映されるはずだ。
そして審査において判定に疑義があったとき、審査員評価結果の中にある過去の異議申し立てや苦情の判定結果が判例として有効だろう。
もし審査側が納得できないならその調査結果を基に異議申し立てすることができる。現状でも異議申し立てはできるししているが、過去の判例がわからないし、そのトラブルの処置が共有されていないのだから改善されていないのだ。
- 活用
広報結果は、認証制度側では非常に有効に使える情報だ。
まず認証制度側にとっては、企業が虚偽の説明をしているかどうかはともかく、認証機関ごとの成績がはっきりして認定機関は動きやすいだろう()。
 問題を起こした審査員研修機関は研修方法や試験を見直しすることになるだろう。
問題を起こした審査員研修機関は研修方法や試験を見直しすることになるだろう。
審査員登録機関は当然その結果を更新の是非に反映するに違いない。
認証機関は己のパフォーマンスを把握でき、その改善策をとるはずだ。その中には雇用している審査員の査定も訓練も契約解除もあるはずだ。
受査側にとってもいろいろ役に立つ情報だ。調査結果と同じトラブルが起きれば議論することなく正しい見解がわかる。それによって審査での議論を回避できる。
また審査員の事前の忌避も根拠を明確にして行うことができる。
その結果、忌避された審査員は仕事がなくなるというフィードバックが図れるだろう。
各認証機関は審査後のアンケートを調査結果に合わせ、審査を受けた企業は曖昧模糊のお世辞ではなく、審査での問題、議論となったことを回答する仕組みとする。用紙様式は認定機関や審査員登録機関それに認証機関協議会などで決定し統一することが望ましい。
認証機関はその回答を受けて是正を行い、企業へ回答する義務を持つこととする。
審査員更新に当たっては、その審査後のアンケートに記載されたトラブルをすべて添付することとする。審査員登録機関は更新の基準を設けて、一定水準以上のトラブルを起こした審査員は更新しないものとする。
- 効果
トラブルの減少、不適切審査員の排除がされる。
それにより企業側においては、審査でのトラブル減少が期待できる。それから審査員の評価が低い認証機関は避けることができる。
認証機関においては審査員の力量を具体的に把握でき雇用の継続はもちろん評価・査定に使える。
結果として企業そして社会から審査と認証への信頼性が向上する。
なによりも大きな効果は、企業は虚偽の説明をしていたという汚名を晴らすことができるはずだと私は考えている。JABの理事長もきっとそれに納得しいただけるだろう。
こんなことを提案すると昭和30年頃勤務評定制度を導入というとき、気が狂ったように騒いだ先生方のように、審査員の方々は胸に勤務評定反対と騒ぐのだろうか?
ちょっとそんなことを期待する私である。
だが先生たちは日教組という強力な圧力団体を有していたが、ISO審査員は日本審査員組合なんて組合を組織してないからそうはならないか?
だがそもそも2015年版の審査員の定義「審査をする人」というのは間違いなのだ。それ以前の定義であった「審査を行うための個人的特質及び力量を持った人」が正しいのである。
この定義を変えたのはいったい誰だ?
ISO9000のTC委員の責任を問うぞ、
力量がなければ誰が金を払うものか!
 そんなことISO審査員に限らず、コンビニのバイトだってテッシュ配りだって同じだ。
そんなことISO審査員に限らず、コンビニのバイトだってテッシュ配りだって同じだ。
元大企業の部長であっても企業の人を小僧とか坊主と呼ぶことは許されない。博士号を持っていようと企業の人より上のわけではない。企業を良くしようと規格にないことを求めるのは余計なお世話である。審査員が企業担当者より知識があるとか知恵があると思うのは勘違いである。LMJは「会社を一番知っているのは会社の人だ」と語ったそうだ。
そういうことを認識して審査というお仕事をしなければならないということを、骨の髄から認識してほしい。
まあ、認識していないから今があるわけで……
私はJABの理事長飯塚先生に反旗を翻すものじゃありません。その真逆で飯塚先生がおっしゃることにまったく同意です。先生が唱えた節穴審査員を撲滅しましょう。そしてISO審査の質向上を図り、第三者認証の躍進を図りましょう。
お互いの認識が一致し利害が一致したなら共同戦線を張れるはずですよね?
現実を見ずに「虚偽の説明ガー」なんて言ってるようでは進歩がありません。
![]() 本日の提案
本日の提案
改善は測定に始まるといわれる。まずはISO審査の実態を定期的に調査し、その調査結果を公表することはISO第三者認証の有効性向上だろう。
そしてその結果を審査員の更新時の評価に反映したら審査員の質向上に効果があるのではないだろうか。
注1 |  「節穴審査員」なる言葉は2010年に開催された「2009年度JAB/ISO9001公開討論会」で飯塚教授が言い出したものである。飯塚先生はその後も講演会などでたびたび節穴審査員という言葉を使っている。
「節穴審査員」なる言葉は2010年に開催された「2009年度JAB/ISO9001公開討論会」で飯塚教授が言い出したものである。飯塚先生はその後も講演会などでたびたび節穴審査員という言葉を使っている。なおその定義とか、いかほど存在するかのデータは不明である。 | ||
注2 |
21世紀は審査報告書はエクセルでマクロを組んで作成する認証機関もいくつもあり、その結果 主語述語が合わないとか意味不明なものがある。それが認証機関名で出されるという不思議? | ||
注3 |
2018年版環境レポートにはIBMが過去5年間に何件環境事故を起こしたか、そしてどんな罰を受けたか罰金をいくら払ったか記載してある。それを素晴らしいと思わない人がいるだろうか? 日本の環境レポートでも、報道された環境事故の是正処置を書いたものを記載したものはいくつかあるが、どんな処罰を受けたかを書いたものを見たことがない。 | ||
注4 |
「IBMの環境経営」、山本 和夫/国部 克彦、東洋経済新報社、2001、ISBN 9784492500941 |
コマゴマ様からお便りを頂きました(2020.04.24)
いつもお世話になっております。 こうしてみると認証機関側は企業に好き勝手言って、高いお金もらってきたツケが、認証件数減少という形で出ているんでしょうね。そういう現状をどう考えているのかは是非聞いてみたいものです。予想もしてなかったのでしょうかね 審査を受ける側としても審査員の情報は是非欲しいので、大賛成です!変な審査員が来たら面倒だなぁと悩んでる部分もありますし |
コマゴマ様 毎度ありがとうございます。 弁護士相談が30分2000円から5000円です(地方によって違います)。超難関の司法試験に合格し、修習生の研修を終えて、どこかの法律事務所で見習いをして、一人前になってそんなものです。 誰でもなれるISO審査員で審査料金は1日10万から高いところは18万なんてところもありましたね。時間当たり1万以上。もっとも値引きがありますけど。いずれにしても弁護士と違いすぎますよ。 おっと、ISO審査はオーバーヘッドがあって手取りじゃないといわれるかもしれませんが、弁護士相談料だって弁護士事務所のオーバーヘッドが入っているわけで同じです。 言いたいのはISO審査って高すぎです。いや高いなら審査のレベルも高いことを期待します。規格解釈を間違えて会社の担当者から突っ込まれると逆切れするようなお方では、それだけの価値がないでしょう。 でも事前の審査員諾否のとき提示される情報はプアそのもの。そのお方がいかほどの力量か、どんな審査をしてきたのか、まるでわかりません。 実は私は現役時代知り合いのネットワークで審査トラブルの情報を集め、審査員のえんま帖を作っておりました。仲間は当然それを知ってますから、「○○認証機関の○○審査員はどうですかね?」なんて私にメールとか電話してきたものです。 審査員の必要な情報の開示は一企業担当者が要求してもダメですから、認証制度が自浄作用として行うべきでしょうね。 それまでISO認証制度が続くのかどうか…… |
うそ800の目次にもどる
うそ800始末にもどる