さあ!いよいよ待ちに待った楽しい審査である、
 お祭りである、旧正月である、パーティーである。
お祭りである、旧正月である、パーティーである。年に一度のせっかくの催し物なのだから、楽しまなくては損である。
しかしお正月にはお年玉、パーティーにはクラッカー、七五三には千歳飴というふうにお決まりの添え物ってえのがある。
監査を受けるにもオヤクソクがある。
あなた!手ぶらで審査会場に行っちゃいけません。
-
次のようなものを忘れずに
- 環境マニュアル
これを忘れていく人はいないよね?
- ISO14001規格
あなた内部監査のとき、マニュアルを持たずに監査できますか?
同じく審査を受ける時、ISO規格忘れちゃいけません。
何か審査員が言ったら「オカシイナア」という顔をしてページをめくるというのは有効な技です。
できたら規格の本にはあちこちにポストイットを貼っておいたり汚れているとなお良し
真新しいのは経験値が低い。
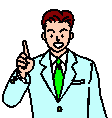
- ガイド66
ガイド66ってなんだっけ〜? なんてボケをかましているあなた!
いけませんねえ〜環境事務局失格ですよまだプリントアウトしていないなら今すぐにプリントしておきましょう。
ダウンロードはここから
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html
これにもポストイットやアンダーラインがわざとらく引いてあるといいですね〜
特に環境側面や異議申し立てについてよく読んでおきましょう。
これを常に手近におき、審査員が変な質問した時に、ページをめくったりすると審査員ビクッとしますよ。
もしビクッとしないような審査員はガイド66も知らないダメ審査員です。(注意)
ガイド66(JIS Q 0066)は無償で公開されていますのでプリントアウトしても問題ありません。
ISO規格、JIS規格の複製は違反です。なお、各アイテムの力と値段は表の通りです。
名称 攻撃力 守備力 買値 売値 入手場所 環境マニュアル 0 10 0 0 社内 ISO14001 0 7 2800 0 日本規格協会 ガイド66 5 5 0 0 工業標準化委員会 審査機関の登録ガイドブック 0 5 0 0 審査機関 ISOロゴマーク管理規定 0 3 0 0 審査機関
- 審査機関の登録ガイドブック
審査はISO規格、ガイド66、そして審査機関の定めたものが審査基準です。
相手の要求を知らないで審査を受けることはできないでしょう。
これも一読してますか?
エッ 審査機関からそういったものをもらっていない?
そりゃいけません、すぐに審査機関に異議申し立てしましょう。
また、ロゴマークの審査のときは、審査機関のロゴマーク規定を準備します。ロゴマーク管理の審査ではこの資料を基にしますから
ロゴマーク管理の規定をもらってますよね?
- メモリーレコーダー
通常、オープニングミーティングで審査員は撮影や録音をしてはいけないといいます。ですけど、審査は仁義なき戦いです。敵対する組長の首を取るにはまっとうなことをしていてよいはずがありません。凶器を隠し持つのは当然です。
審査結果に同意できなかったときは後でじっくり聞き、相手の言い分を分析しましょう。
もっとも録音がばれて苦情を言われても鉄砲玉が殺されて終わりです。
組長(私)は知らぬ存ぜぬです。
- ノート
私は昔は相手の言うことを全部記録するなんてことをしたものです。速記は禁止されませんからね。私は速記などできませんから、必死に手書きしました。
速記録を取っておくと役に立つか?
あとでその場にいなかった人のために役に立ちます。
そして、こちらが必死にメモする風情を見せれば、相手も発言が慎重になり、過剰な要求、おかしな発言は控えます。これは私の経験で事実です。
紛糾したときは、その場でノートを読み返す振りをするのは有効技です。
次に心構えというか気をつけることとして
- オフハンドでは話をしない
「環境側面の特定については会社の手順書で決めてます。」
オイオイ、そんなことはいけないよ
イントラネットで探して・・・というか探す振りをして・・・
「エートですね、その件に関しては会社手順書XYZ文書番号1234のですね・・・エートどこかな?アアここだ、3条に決めてます。なになに・・・」
あるいは分厚いファイルを机の上にバーンと置いてそれを指差しして発言します。
私たちは詳細を記憶しておくことはない。逆に間違えたことをいう可能性もあるから、常に書き物を読んだほうが間違えない。
覚えておかなくてはならないことは、どの規則で決めているかである。
- 知ったかぶりをしない
知らないことは知らないということは恥ではない。
- 聞かれたことに答えるようにする。
相手が何を聞いているのかを把握して、それにマッチする回答をする。
あがってしまって論点、質問を把握せずに回答するのは良く見かける。
相手がグリーン購入の仕組みを聞いているなら、仕組みを説明する。
グリーン購入比率などパフォーマンスを説明しても相手が気を悪くする。
- 聞かれたことしか答えない。
聞かれたこととに対応する回答【のみ】をするのが良い。
余計な自慢話、これもしている、あれもしているなどというと脇が甘くなってしまう。
猿も木から落ちる、語るに落ちる
- 審査員にツッコミを入れたり揚げ足をとったりしない
これは私が良く犯す誤りである。
ついつい私はオチャラケモードや戦闘モードに入ってしまう。なにしろ審査員を見ると指導したくなる気持ちを抑えることができないのだ。
「○○審査員だってそんなことできないでしょう」
そんなことを言うと気を悪くする。
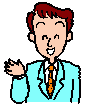 「規格ではそんなこと書いてません」
「規格ではそんなこと書いてません」
これはマズイ言い方。
そんなときはこう言います。
「規格のどこにありますか?」
- 簡単に非を認めないこと
マニュアルや文書に不足があるとき、エビデンスがないとき、その場で「これはまずいですね」とか「してません」とは言わない方が良い。とりあえず「調べてみましょう」と言うほうがいい。
ただしポカミスなどについてはあまりこだわらず、「ああ、間違いです」といったほうがよい。
相手も人間ですから。
- 審査が紛糾しても、不適合を出されても、相手を叩きのめしても、送り出すときは笑顔で行きましょう。
いつまた再びお会いするかもしれませんから。
主任審査員が存命なら次回も間違いなく同じ人ですし、他の審査員も半数は変らないことが多いです。
- いつも笑顔で
あるがままに、自然体でいきましょう。
これが本日の結論です。
この拙文にご異議をもたれました、審査登録機関あるいは審査員の方は当機関(うそ800)に異議申し立てをすることができます。
うそ800の目次にもどる