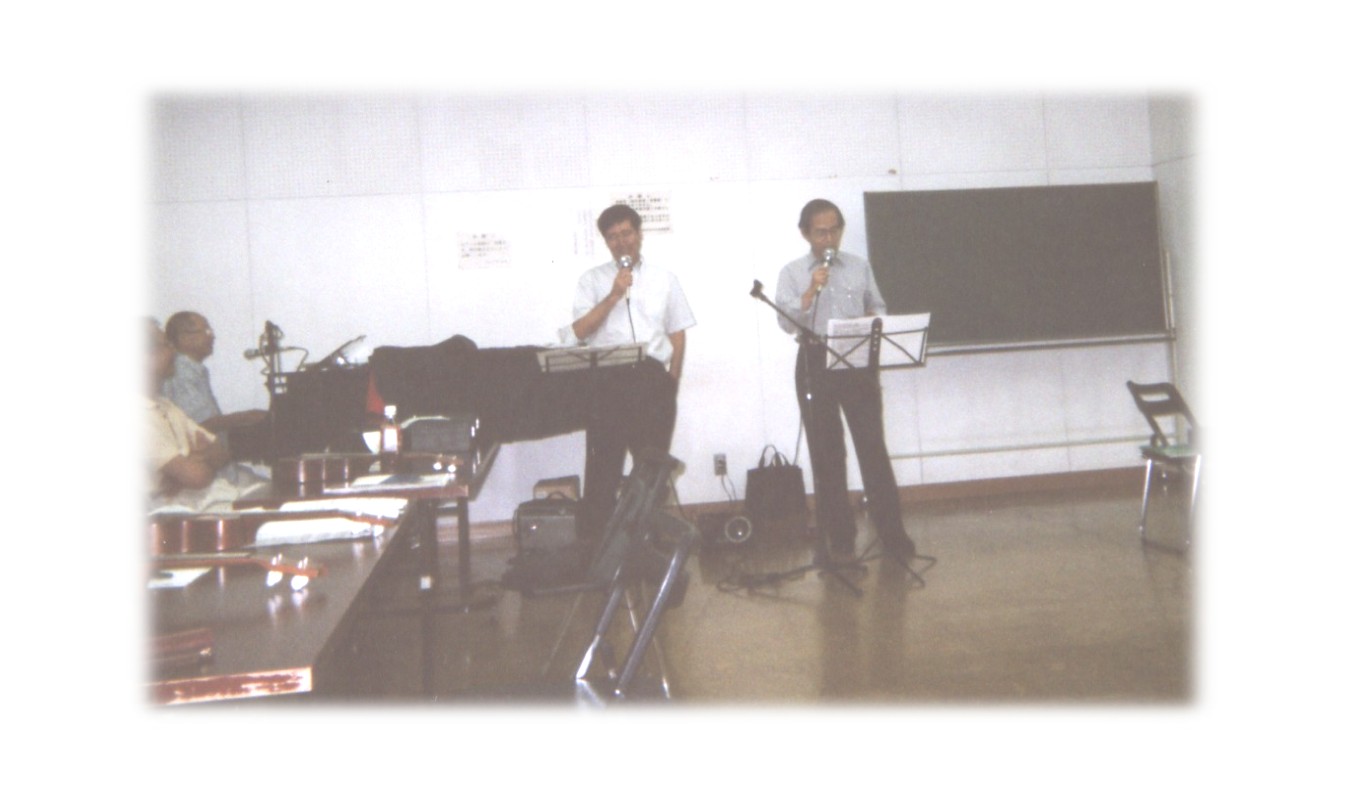-
前号の2005-8-14号でご紹介した日本橋のたもとにある「日本橋魚市場発祥之地」という碑について
祖父の著書「魚河岸盛衰記」に関連の章節があるので一部を抜粋して転載します。
(「魚河岸盛衰記」田口 達三著 1962年 いさな書房発行)
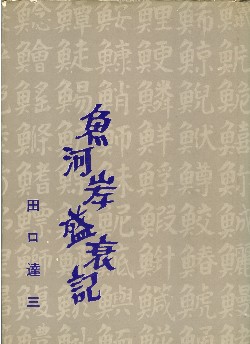 記念碑と水神祭
記念碑と水神祭 記念碑を建てよう
日本橋魚市場は、徳川三百年の歴史とともに栄えて来た。日本橋は由緒ある史跡でありながら、今 ではビル街となり、やがては日本橋川の面影がなくなってしまうかも知れない。古えを偲ぶよすがは あの辺にすし屋、天ぷら屋が、三、四軒並んでいる程度にすぎない。
市場が築地に移る前に、日本橋で働いていた私どもには全く淋しい限りであった。そこで日本橋市場 に記念碑を建てよう。こんな話は戦前早く出ていたが、大東亜戦争突入で沙汰止みになってしまった。
戦後になって、再び記念碑建設の話が出ていたが、たまたま名橋日本橋補修協賛会というのが地元 に出来て日本橋復旧運動を起すことになった。この機に乗じなければと、この協賛会をはじめ、各 方面に、日本橋と魚市場との歴史的な深いつながりを説いて廻り、遂にその賛同を得た。
初め日本橋川畔に高さ 十二尺、巾十五尺という大きなものを計画したが、四・三尺に五・五尺程度 (転載時注釈: 十二尺は約3.6m 十五尺は約4.5m 一尺は約30cm) なら許すということになった。ところがその敷地内に、室町一丁目町会の国旗掲揚塔があって、 これが他に移らない限り建立の望みがない。そこで一丁目の人達に頼んで、これを移転してもらう ことで話がついた。
碑の大きさについても、都庁や警視庁、区役所を説得して廻り、高さ九尺、巾九尺ということで折合い がついた。これでは小さくて貧弱だが、何んとかこれで踏み切ることにした。そこで、旧日本橋魚市場 関係者四百二十二名で発起人会をつくった。昭和二十八年三月中旬に第一回の発起人会を開いて、 私が総代、佐久間仙一郎君が実行委員長となり、副委員長は大村市太郎、吉田幸十郎、関本徳蔵君 らが選ばれ、具体的な計画を立てることになった。
このとき決まったことは、台石は万成石を使って、出来れば高さ十二尺、巾十二尺の気品高き芸術 作品、日本橋魚市場沿革碑文及び江戸時代の魚市場繁昌の図を銅版にする。像は台石の上に海に 由緒ある石彫を置く。費用は二百万円とする等であった。
過去の碑石を調べてみると、大部分は石屋が中心で、彫刻家は石屋が適当に先生方に頼むという ことであった。これではいかん。誰かしかるべき彫刻家に直接依頼すべきである。そこで上野の芸術 大学の教授田中青坪先生を訪ねた。青坪先生は、それでは手腕の優れた同大学の教授山本豊市先生 がよかろうと、早速紹介してくれた。こうして山本先生が中心になり、石工は田鶴年氏、碑文は久保田 万太郎氏、文字の彫刻は発起人の一人である松丸東魚先生に依頼した。出来上がったのは昭和 二十九年六月上旬である。碑文には三月建とあるが、これは予定より原石の発送が遅れたりしたため である。
除幕式には安井都知事、久保田万太郎先生、豊道慶中先生、山本豊市先生等と発起人代表参列 のもとに盛大に行った。
| 日付 | 会場 | 演奏楽器 | 演奏曲目 |
|---|---|---|---|
| 4月24日(日) | 大磯「旬庵」 | ビブラフォン | 見る |
| 4月26日(火) | 中延「ボナペティ」 | ビブラフォン | 見る |
| 4月27日(水)、29日(金) | 尾山台「ブラッサリー・シェ・ヌー」 | ピアノ | 見る |
| 4月30日(土) | 新橋「アルテリーベ」 | ボーカル | 慕情 |