
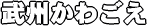

Part 3
舟 留 め
◆
舟会所の店土間からあふれ出た何人もの男たちが軒先に群がり、背伸びして暖簾のなかをのぞきこんでいる。
ザンバラ髪の男がいる。顔中ひげだらけの男……どの顔も汗と土埃とでどす黒くくすんでいる。男たちは眼を血走らせて、なにやらしきりに叫んでいる。
折り重なる人波がくずれて、番頭らしい男が軒先に現れた。
頭に白いものが目立ちはじめているかれは群がる男たちをなだめにかかっているが、かれが口をひらくたびに、ののしりと罵声がとんでくる。
「佐吉、はやく半蔵さんを!」
荒くれた男たちの間からこぼれ出てきた小僧が番頭らしい男にうながされて、川沿いの道を走り出した。飲食店街の軒先をすりぬけ、麻金の店先をよこぎり、子犬がころがるかのように炭屋の暖簾をくぐった。
四月七日。
半蔵はその日も、朝から土蔵のなかにこもっていた。
八兵衛や河岸の世話役たちと深夜まで謀議をこらした翌日から、半蔵は思い立って炭屋の文庫蔵に文机をもちこんで、過去の騒動の記録を読み返していた。
炭屋はすでに一八〇年あまりも舟稼業をつづけてきた。初代仁兵衛は松平信綱に御舟役を仰せつかり、飯能の岩淵から川越城下にやってきた。河岸ができあがると同時に屋敷と舟一艘をあたえられて舟稼業をはじめた。それが炭屋のおこりである。
炭屋の店主は利兵衛あるいは治兵衛を名のるのが習わしである。半蔵にとって兄にあたる利助も八代目当主についてからは利兵衛を名のっている。
五河岸の舟持問屋のなかでも炭屋は老舗だが、屋号を「炭屋」としたのは、それほど昔のことではない。七代目利兵衛のときから、つまり半蔵の父の代からである。最初の屋号は「藤屋」であった。信綱のときにゆるされた苗字の「遠藤」から一字をとって「藤屋」である。
炭屋というのは高名な打物商である。本店は京都にあって、打刃物や大工道具を手びろくあつかっている。
七代目の利兵衛は日本橋通油町にある炭屋江戸店へ奉公にあがり、一般の奉公人と同じように二三年間にわたって修行し、最後は支配人にも抜擢されている。利兵衛のように番頭までのぼりつめた奉公人は、一年のお礼奉公のあと別家するのがふつうだった。
舟問屋の総領息子の利兵衛は、もとより商人として終えるつもりはなかった。お礼奉公が終わると、帰郷して生家の舟問屋を継いだのだが、そのときに屋号を「炭屋」にあらためたのである。
文庫蔵には創業当時からの大福帳、判取帳、請証文、道中記などの書類が年ごとにきちんと整理して保管されていた。
河岸ではかつていくたびか出入りがもちあがっている。半蔵は埃をかぶった文書の束から、先考が書き残した騒動の記録を探しあて、覚え書きをつくりながら、たんねんに読み解いていた。
それにしても……。
船頭たちはどうしたというのだ。
八兵衛は船頭たち無視するというかたちで舟賃の増銭要求をにぎりつぶした。船頭たちは満足のゆく回答がなければ、ただちに舟留をすると息巻いていたのだが、翌日はいつもと変わるところなく暮れてゆき、二日目を迎えていた。
「あのう……」
背後で声がした。
「会所からお迎えが……」
後ろに立ったのは妻女のやすである。
事態がやっと動き出したらしい。半蔵はゆっくりと身をおこした。
「わかった。承知した……と伝えておくれ」
半蔵が立ちあがると、「それではさっそく身繕いを……」と、やすは小走りに居宅のほうに向かって先に立っている。
若い嫁である。
半蔵とは一九歳もの隔たりがある。
やすは城下高沢町の商家の娘である。八年前に一六歳で嫁いできた。そのとき半蔵は三五歳だった。商家に奉公にあがった者なら、誰でもそうするように、定められた年季が明けてから、嫁を迎えたのである。
三五歳といえば、婚期が遅れているようにみえるが、商家に奉公した者ならば、相応の年齢である。小僧から手代へ、やがて番頭になり、お礼奉公をすませると、いくら早くても三〇をすぎてしまう。嫁をもらうのはそれからになる。
あれから八年……。
やすは七歳になる女の子の母である。だが後ろ姿をみていると、まだ一七、八の若い娘のようにみえる。
半蔵夫婦に居宅は炭屋の別棟である。
やすは土間にいた。水を張った手桶をふたつならべ、手ぬぐいを浸している。半蔵の顔をみると、
「あれ、あれ、眉が真っ白ですよ」
と、明るい声で笑いながら、絞った手ぬぐいをさしだした。
半蔵が顔をぬぐいはじめると、「頭も、まあ、すっかり白髪だらけ……」と澄んだ声で笑いながら、彼女は乾いた手ぬぐいで手際よく埃をはらった。
「さあ、さあ、埃をかぶった着衣はみんな、ここで脱いでください」
やすの無邪気な声にうながされるままに半蔵は手早く身支度をすませた。
若いがなかなか機転が利く。
やすのきびきびとした身のこなしはきっと生まれついてのものなのだろうと半蔵は思っている。
「どんなぐあいだ?」
舟会所に向かいながら、半蔵が先に立つ佐吉に訊くと、
「舟がきません。朝から、一艘も……。それに船頭もいなくなりました」
と、急きこんで言った。
「それで馬方が騒ぎ出したのか?」
「はい」
佐吉は神妙な面持ちである。
新河岸で舟からおろした積荷は馬子たちが荷車で川越城下まで運んでゆく。かれらは近在の農民たちで、河岸には手間稼ぎにやってくる。
会所にゆくと、半蔵はたちまち馬子たちにとりかこまれた。
「半蔵さん、舟が着かない。これは、いったいどういうことだい」
馬子のひとりがいえば、ほかのもうひとりが、「理由を訊いても、分からない……というんじゃ、おれたちどうしたら、いいんだ」と詰めよってきた。
「皆の衆、聞いてくれ」
半蔵は一同が静まるのを待って、「船頭との間でちょっとした取りもつれがあってな。談判のことだから、どちらが悪いというわけではないが、それで舟が留った。しばらくつづくやもしれぬ」と落ち着いた口調で言った。
舟留め……。
馬子たちだけでなく、問屋から判取りにやってきた手代たちも初めて事態の深刻さ気づいたらしく、どよめいた。
「そんなわけだから、悪いが、今日のところは、これで引きとってくれぬか」
半蔵は一人ひとりを見わたした。
かれの刺すような鋭い眼光、射おろすような視線に出会うと、荒くれた馬子たちは身がすくんだようにおとなしくなった。
「仕方あんべいや。船頭が舟を留めたというのなら……」
馬子たちは顔を見合わせて、たがいに何事か低い声でぶつぶつつぶやいている。
荷の積みおろしの駄賃、城下までの車駄賃も船頭の懐から出る。その船頭が舟を留めたというのなら、黙りこむほかなかったのである。
やがて、かれらは肩をおとし、重い足どりで、馬をつないである上新河岸の日枝神社のほうに散っていった。
「半蔵さん、寝耳に水とはこのことで……」
会所の支配人として事務をとりしきる繁蔵は半蔵をみて救われたように大きな吐息をついた。
船頭たちは一夜のうちにすっかり河岸から姿を消した。上がりの舟も中河岸のどこかで停められているらしく、朝から入津した舟は一艘もないという。
舟会所では支配人の繁蔵や手代がかならず送り状に眼を通す。帳簿に記録してから判を捺すというのが決まりである。旭橋の下流にある寺尾河岸から出航する舟も、問屋の小僧が毎日まとめて送り状をもってくる。
会所の目をかいくぐって舟稼業はなり立たない。会所の押し切り判がなければ、荷主は舟賃の支払いを拒否することができるからである。
「出居仕舟だけかい?」
半蔵がたずねると繁蔵は、「どうやら、そうじゃないようで……」と、自分でも納得できないというふうに首をふった。
「問屋持ちの舟も……か?」
半蔵は思わず声を高めた。
河岸の舟には問屋の持ち舟のほかに出居仕舟とよばれている船頭持ちの舟がある。五河岸の問屋はもともと、それぞれの持ち船だけで舟稼業をはじめたが、やがて河岸に出没した出居仕舟をとりこんで、丸抱えするようになった。半蔵が河岸にもどってきたころには各問屋とも持ち舟を減らし、出居仕舟が大半を占めるようになっていた。
問屋持ちの舟の船頭は舟床という賃貸料を問屋に支払って営業しているから、ほとんど問屋の使用人にひとしい。出居仕舟の船頭も問屋をぬきにして稼業はできないが、問屋とのつながりは契約によっている。自前の舟を持つかれらは、気にいらなければ契約を解除して問屋を変えればいい。だから問屋持ち舟の船頭にくらべて、はるかに自由なのである。
舟留は出居仕舟の船頭たちがはじめたにちがいないと半蔵は読んだのである。ところが繁蔵は妙に歯切れが悪い。
「それが、まるで神隠しにあったというあんばいで……」
問屋持ち舟の船頭たちも朝から忽然と姿を消したと繁蔵は言うのである。
出居仕衆がたとえ舟を留めても、どの問屋にも二、三艘の持ち舟がある。問屋がこころざしをひとつにして手を組めば、積荷をそれほど滞らせることもなく、事態を乗りきれるだろう。半蔵はそのようにみていたが、どうやら甘かったようである。
船頭がいなければ舟があっても破舟にひとしいのである。
「そうかい、心得ていやがる。こんどの相手はかなり手強いぞ」
「脅かさないでくださいよ」
繁蔵の声が裏返ったので、半蔵は声をあげて笑った。
午ごろになると、いつものように問屋の番頭や手代たち、城下からは商家の手代たちがやってきた。かれらは河岸に入津した舟の積荷と送り状の引き合わせにやってきたのだが、舟留めという現実に直面して、どういうことなのか理解しかねるというように、驚きととまどいとで呆然としながら、ひきあげていった。 半蔵は八兵衛に使いの者をやり、暮れ六ツから寄合をひらくことを決めると、ただちに佐吉をはじめ小僧たちを各河岸の世話役のもとへ走らせた。
半蔵は繁蔵ともども、ひっきりなしに問い合わせにやってくる者たちの応対に追われ、八ツ半ごろになって、ようやく昼餉をとるというありさまだった。
旭橋のうえに立ち、一息いれていると、上流の柳原がにわかに騒がしくなった。馬のいななきや牛の鼻息が聞こえてくる。
四頭の馬に曳かれた馬車、さらには三頭の馬と牛二頭に曳かれた荷車、次つぎに土堤にあらわれた。いずれも材木を満載している。 河岸に待機していた人足たちの動きもにわかにあわただしくなった。
かれらは「おわり車」とよばれている車に材木を積み換える。何人かの人足たちがかけ声もろともにそれを岸辺まで運ぶ。
土堤まで達すると、かれらは「よーいとまけ……」とかけ声もろともに、てこ棒を突っ立てる。すると材木は葦の茂る河原にころがり落ちていった。
材木の荷おろしは、おそらく日暮れまでつづくだろう。
問屋の舟着場は静まり返っているというのに、材木置場だけが異様に沸き立っている。
「やっと、もどったところだ」
弥重郎が肩口から声をかけてきた。
年行事のかれは異変が発覚したその日の朝から各河岸の探索にを走りまわっていたのである。
「ごくろうでしたね。さぞ骨がおれたでしょう」
半蔵はそう言ったが、弥重郎は材木置場のほうに視線をすえて、
「あれをみてると、気が気じゃないよ」
と溜息をついた。
同じ問屋でも弥重郎の伊勢屋は材木のあつかいが多いのである。
「出居仕舟だけではない……という話ですがどんなぐあいです?」
「問屋舟の船頭は、みんな捕らわれの身だ」
弥重郎は天をあおいだ。
「捕らわれの身?」
「そうだ」
「誰に?」
「舟魂さまだ……」
弥重郎は意味ありげに微笑んだ。
昨晩のことである。南畑で船頭たちの講の集まりがあったと弥重郎次は言った。
舟魂さまとは船頭たちの守り本尊である。 霞ヶ浦の南、桜川村阿波に大杉神社の本社がある。もともと利根川をはじめ江戸川、荒川などの船頭たちの信仰が篤いのだが、いつのころからか新河岸の船頭たちの間にも信仰がひろまった。利根川や江戸川の船頭が出居仕衆として新河岸にやってくるようになったときからである。
船頭たちは大杉神社参拝の講をつくっている。昨晩はその講の集まりに五河岸の問屋持ち舟の船頭たちも出かけていった。
「それで、神隠しというわけですかい?」
「そういうこと」
出居衆に〈おれたちの酒は飲めぬというのか〉と酒をすすめられ、つい度を過ごして酔いつぶれてしまった、というよりも、酔い潰された、というのが弥重郎のみるところだった。
「やられましたな」
「まんまと、ワナにおちた」
「敵ながら手強い。相手は……」
「ああ、ただの舟留ではない」
思案げに川面をみつめて、二人はためいきをついた。
五河岸問屋の惣代であり、上新河岸の名主をつとめる望月八兵衛の屋敷は氷川神社のふもとにある。
新河岸には望月姓を名のる舟持問屋が四軒もある。上新河岸の名主である八兵衛、綿権の綿屋権兵衛、綿儀の綿屋儀兵衛、下新河岸の綿善の綿屋善兵衛である。
望月家は寺尾村の開祖のひとりである。
寺尾村や新河岸の周辺は、もともと北条氏康の家臣たちによってひらかれている。
氏康が関東管領の上杉信興を破ったあの川越夜戦のとき、北条側の使者として小田原からやってきて川越城にはいった諏訪右馬之助が、居城と家臣たちの集落をそこにつくったのである。
北条氏が滅び、家康に時代になると、諏訪氏の家臣たちはそれぞれ帰農して土着していった。
寺尾村の名主をつとめる蔦屋の河野藤五郎、そして八兵衛を始め望月姓を名のる上下新河岸の四軒は、いずれもその末裔なのである。
暮れ六ツをすぎたころ……。
提灯をさげた小僧や手代を道案内にして、いかにも大店の主人らしい男たちが、次つぎに上新河岸にやってきて、八兵衛の屋敷にはいった。
六つ半になると、豪勢な境襖をぶちぬいて二〇畳敷にしつらえた奥座敷に、五河岸三〇軒の店主の顔がすべてそろった。上新河岸八軒、下新河岸七軒、扇河岸七軒、寺尾河岸七軒、牛子河岸一軒……。
安永三年(一七七五)に株仲間がみとめられていらい、七五年ものあいだ問屋の数に変わりはない。
二日前の世話役の集いにはやってこなかった寺尾河岸の蔦屋藤五郎、扇河岸の橋本屋市郎兵衛も何食わぬ涼しい顔で世話役の席についていた。
「いや、はや、思いがけぬ事態に相なった……」
八兵衛は豪華な白羽二重の座布団に座って、話の内容とは裏腹に終始落ち着いた口調で話を切り出した。
城下の商人たち、十組問屋との談合が不調におわったことからはじめて、出居仕衆の強談判のなりゆき、かれらの早急には初めから応じる腹がなかったこと、だからかれらの舟留はあらかじめ予測されたことで、とりたてて驚くことではない……と、鋭い眼つきで一座をながめまわした。
「だが、舟床持ちの船頭をかっさらわれた。これではわれらは、まるでダルマじゃ。手も足も出せやしない」
上新河岸の麻屋金兵衛が薄笑いをうかべたが、すぐにかたわらから河内屋兵六が、
「他人事ではないぞ。さしあたって河岸に山積されている丸太を、いったいどうするつもりじゃ」
と、あざけるように言った。
「いまさら、老袋や平河へ回すこともできませんからね」
年行事の弥重郎も顔を曇らせている。
河内屋も弥重郎の伊勢屋もともに材木の扱いが多い。
「舟が留まれば、御公儀の積荷をながしろにしたと、お咎めを受ける。このままでは、申し開きのしようもあるまいて」
と、重苦しい声をあげたのは、綿儀とよばれている綿屋儀兵衛である。望月一統である綿儀もまた材木をあつかっている。
江戸で大火があったのはちょうど一月半まえのことである。
四ツに麹町一丁目あたりから火の手があがり、おりからの北風にあおられて、芝一丁目界隈まで延焼、暮れ六ツすぎになってようやく鎮火した。三八カ町を火の海にのみこんだ大火によって、神社五〇、寺院一二〇、大名屋敷三六、旗本屋敷二五〇あまりが失われている。
川越藩の中屋敷もこのとき焼失している。藩邸再建の材木や屋根瓦、建具、調度品などの積み出しもまだ終わっていない。
「手抜かりはそのことだ。たとえ出居仕衆が舟を留めようとも、われら問屋の持舟をすべて集めればとなんとかなると思っていたが……」
八兵衛は一同を鋭い眼つき見わたして、「
儀兵衛さんの言う通り、時が時だけに、いかなるお咎めを受けるやもしれぬ。事はわれら問屋一統のゆくすえにかかわることでもある。そこでじゃ、皆の衆に考えがあれば、とくとうががっておきたい」と言った。
腕組みをして聞いていたひとりが、どこか間のぬけたような声でたずねた。
「というと、舟役所のお役人を押さえるために、もっと運上、冥加の額を増銭すると、おっしゃるのか?」
つづいて、もうひとりが声をあげた。
「それは無理というものだ。われらの商いが立ちゆかなくなる」
「ちがう、そうではない……」
八兵衛はふたりをほんの一瞬にらみつけ、
「商いが立ちゆかなくなる。同じ科白をどこかで耳にしたぞ。あえて、いまは、どこで……とは言うまいが……」と言って声をあげて笑い出した。
「それにしても、太っ腹ですな。舟留だというのに、皆さん、泰然としておられる……」
半蔵はゆっくりと座り直した。
舟持ち問屋にもかかわらず舟が留まってもそれほど深刻には受けとめていない。まるで緊張感がない。そのことに驚きを感じている自分のほうが、むしろ浮きあがっているような雰囲気なのである。
八兵衛が揶揄したように、それは河岸問屋の変容に連なっている。五河岸の舟問屋はもともと舟稼業で出発したのだが、舟運を利用して商いをどんどんとひろげていった。倉敷業、さらに塩や肥料の仲買にのりだして財力をたくわえ、いまでは城下の商人とならぶほどの羽振りである。
綿善のようにいつのころからか金貸しをはじめ、川越藩にも多額の金子を用立ていているという店さえもある。
「橋本屋さん、どうですか? 何か妙案はありませんか?」
半蔵は落ち着きはらっている市郎兵衛にあえて水をむけてみた。
扇河岸の名主をつとめる市郎兵衛の橋本屋は、毎年のように藩に献金しているという噂である。
「皆の衆、舟留、舟留……と、あまりにも大げさに考えすぎやしませんか」
市郎兵衛は薄笑いをうかべながら、薄くなった頭を撫でつけて、「船頭どもは甘い顔をすればつけあがるだけだ。こちらから尻尾を振ることはない。何食わぬ顔でうっちゃっておけばよろしい。こちらから機嫌をとりにゆくことなない」と言った。
「橋本屋さんのおっしゃる通りですよ、そのうちに、あちらから尻尾をふりながら、チンチンしてくる。船頭とのことは、とかくそういうものですよ」
蔦屋藤五郎が肥った躯をのけぞらせて、得意そうに言いそえた。
「そんな悠長なことを言ってる場合じゃありませんよ。いいですか。橋本屋さんも蔦屋さんも……」
勢いこんで反発してきたのは年行事の弥重郎だった。
「よろしいですか。このたびの西川材の江戸送りは、御公儀の荷運びにひとしい。よもや、そのことをお忘れではありますまいな」
弥重郎はさらに声を高めた。
「河岸の仕事は御公儀が第一じゃ。しかし……だ、船頭をひっくくられては、いかんともしがたいではないか」
市郎兵衛は余裕のある表情で一同をみわたして、「ここは辛抱のしどころ、果報は寝て待てじゃ。そういう、ちがった思案も、これまたあり……だよ」と言って、愉快そうに笑った。
一同のなかには市郎兵衛の言外に含むところに思い当たる向きが多いらしく、低いどよめきが横にひろがった。
「ほほう。橋本屋さん、舟留を楽しんでおられるようじゃ。さすがに腹が太い。しかしですぞ。見方をかえれば、舟留が長びいても一向にかまわんと仰せではないか。それは結果として城下の商家と同腹ではありますまいか。商人どもは、一日のびるごとに、利鞘が増えると内心は笑いがとまらない。だから舟賃の増銭にはハナから応じるつもりはないのは道理というもの……」
半蔵がそこまで言ったとき、市郎兵衛がどなり声でさえぎった。
「炭屋さん。あなたは何ということを……。それではわれらが商人どもとツルんでいるように聞こえるではないか」
「何もそこまでは言ってません」
半蔵は明るい声で笑った。
「そのように疑われては、この市郎兵衛の男が立たぬ。よろしい。このたびの西川材の荷運び、わが持ち舟はすべて損得ぬきで、みなさんに供出しよう。のう、大嶋屋さん」
市郎兵衛が水をむけると藤五郎も大きくうなずいて、
「もとより承知ですよ。われらは河岸のためになるなら、たとえ火のなか、水のなか……ですよ」
といって、顔を見合ってうなずいている。
「とにかく……だ。御公儀にゆかり深い積荷は、問屋一統の持ち船を繰り出して、掃かせねばならん。問題は船頭のことじゃ」
八兵衛は思案げに一座をみわたした。
「ともかく、このたびの舟留、われらは後手に回っています。そのあたりが、心配ですよ」
弥重郎は急き込んで言った。
「なあに、思い過ごしじゃ」
「やつらには、そんな知恵はあるまい」
あちこちから声があがり、一座はにわかにざわめいた。
「伊勢安さんの言う通り!」
静まれ……といわんばかりに半蔵声を高めて、
「このたびの舟留、弥重郎さんが言うように周到にしくまれている。龍吉という頭を立てて掛け合いにやってきたことが第一、第二には舟床持ちの船頭をとりこんでしまった。油断をしていたら、足もとをすくわれますぞ」 と、決めつけるように言いきった。
半蔵の一言で一同はふたたび不安そうに伏し目がちになったが、それを待っていたかのように八兵衛が、
「皆の衆、よろしいか。われらは、いま、何をしなければならないか。思案はそこのところだ」と身を乗り出した。
「知れたこと、まず舟床持ちの船頭たちをとりもどすことですよ」
弥重郎が言った。
落ち着いてひかえめな口ぶりだったが、皆の視線は一気に弥重郎にそそがれたのは、中身がそれだけ過激だったからである。
「神隠し……などと、のんきなことを言うておれませんぞ」
半蔵もうなずいた。
「ほう、掛け合いで船頭をとりもどすというのか? 半蔵さんは……」
市郎兵衛が薄ら笑いしながら訊いた。
「当然のことでございましょう。いかに子細があれ、わけもなく拉致するという法はありますか」
半蔵は怒ったようにはげしい口調になったので一座の店主たちは、唖然としてかれの顔をながめていた。
扇河岸の名主であり、問屋のなかでも有力者のひとりである市郎兵衛を軽んじるような物言いをしたからである。
市郎兵衛はいかにも太っ腹だといわんばかりに笑みを浮かべていたが、隣にいる藤五郎にそれとなく目配せしているのを半蔵は見逃していた。
「半蔵さん、いい心がけですな。いや若いというのは実にいいもんだ」
藤五郎は軽く咳払いして、
「われらは見ての老体じゃ。出居仕舟の船頭どもとの掛け合いは、この若いお二人の采配におまかせするというのは、どんなものだろうか? のう、惣代……」と、やにわに八兵衛のほうに向き直った。
「それは名案だ。実はわしもそのように考えておったのじゃ」
八兵衛は思いのほかあっさりと同意した。
石橋を叩いて渡らない……というほど慎重な八兵衛にしてはめずらしい即断即決だったが、それは自分に火の粉がかからないせいだと思えば分かるような気がした。
やがて八兵衛が一同に向き直りながら、あらためて口をひらいた。
「さあ、皆の衆、話はきまった。炭屋の半蔵さんと伊勢屋の弥重郎さん、このお二方を名代にしたいと思う。異存はありますまいな」 居ならぶ問屋の主たちは、顔を見合わせながらうなずいた。反対する意思がないというよりも、舟留という事態がいまひとつのみこめなくて、思考そのものが現実に追いついていなかったのである。
「皆の衆、それでは二人が十分な働きができるよう、お力を貸してくだされ」
八兵衛は上機嫌でそう言い渡すと、あらためて半蔵と弥重郎に向かって、「よろしく頼みますぞ」と微笑みかけたが、すぐに真顔になって、つけたした。
「よろしいかな、皆の衆、このたびの舟留のことですがね……」
八兵衛はするどい眼つきで一座をみわたして「あれは船頭が勝手にやったこと、われらはあずかり知らぬ……などとは口が裂けても言ってはなりませんぞ。その理由は言わずともご承知でしょう」と念を押すことを忘れなかった。
夜が更けている。
炭屋の店先も板戸をとざしていた。
閂をあけてひろい店土間にはいると、障子に灯りの影が映っている。半蔵の帰りを待っていた番頭の清七をのぞいて、店の者たちは部屋にひきとったようだが、帳場にはまだ誰かがいるらしい。
炭屋には番頭が二人いる。ひとりは河岸をあずかる亥三、もうひとりが帳場の清七である。
あれは……というふうに亥三に視線をおくると、「大旦那さまですよ」と小声でささやいた。
「兄さん……が? こんな時刻まで……」
半蔵が聞き返すと清七は、「へい、さようで……」と大きくうなずいた。
店の者たちは半蔵を旦那とよび、兄の利兵衛を大旦那と呼んでいる。
障子をひらくと奥帳場の帳場格子のなかに兄の利兵衛がいた。利兵衛も額がひろく、鼻筋が通っていたが、半蔵とはちがって頬骨が突き出て、年齢よりは老けて見える。頭髪にも白いものがまじっていた。
利兵衛は俯きかげんにすわっているので眠っているかのようにみえる。だが眠ってはいなかった。それは骨ばった手でときおり冊子の頁をめくっているさまからも判る。
「兄さん、だじょうぶですか。こんなに遅くまで……」
「ああ、お帰り。頭が冴えて眠れなくてね。それに躯の調子もいいんだよ」
利兵衛は半蔵のほうに向きなおって微笑んだ。
炭屋の八代目当主利兵衛は半蔵にとって二歳ちがいの兄である。
「それは結構ですね。でも、お疲れが出ますよ。夜ふかしは……」
半蔵は向かい合って座った。
利兵衛の心の病は不治のものである。一一年前にかれが倒れたとき、医師は生命の保証はないとさえいった。
半蔵が江戸の奉公先からよびもどされたのはそのときである。
五河岸では兄弟で舟稼業を営む問屋はめずらしくない。問屋の商いそのものが舟運だけでなく、仲買や倉敷業までひろがっているからである。
けれども半蔵は自分が家業につくことになろうとは考えてもみなかった。
それから一〇年がすぎている。
半蔵がもどってきて、療養に専念しできたからだろう。利兵衛の病状は医者も驚くほど恢復した。
健康をとりもどしたといっても不治の病である。いつ病魔が暴れ出すかもしれないが、店に出ていると気持ちに張りが出てくるという。季節の変わり目や体調のすぐれないときをのぞいて、利兵衛はつとめて帳場にすわるようになった。
利兵衛が店に顔を出すようになってから、半蔵は河岸惣代の八兵衛にのぞまれて舟会所の差副役をつとめるようになっている。
「ところで、どんなぐあいだ? 会合のなりゆきは……」
「それが、まあ、とんでもない結末に……」
半蔵は苦笑いしながら、その夜の会合のなりゆきをかいつまんで話した。
「後になって考えると、どうやら、八兵衛さんや市郎兵衛さんにうまく謀られたようなあんばいですが……」
「いや、いや。よくぞそこまで言ってくれた。私ははうれしいよ」
「いや、むしろ出過ぎたマネをしたんじゃないかと……」
「それはちがうな。いまは火急のときだ。ぼんやりしていては商人の冥加にかかわる。これは、つねひごろのおまえさんの口ぐせじゃないか」
「まいりましたな」
「店のほうは心配しないでいいんだよ。おまえさんは惣代の差副なんだ。八兵衛さんにみこまれたときから、河岸のために差し出したと思ってるよ。だから存分の働きをしておくれ」
「兄さん……」
半蔵はとまどっていた。
利兵衛は勢いこんで躯ごと投げ出すかのように話しつづける。
「いいかい。半蔵、炭屋のため……というような卑小な料簡じゃいけねえよ。河岸のためにひとはたらきしてほしい。お役目を立派に果たしてくれさえすれば、それでいいんだ。躯の調子もこんなぐあいだから店のほうはわたしがなんとかするよ」
「さようですか。兄さんにそこまで言われれば、もう、男として退くわけにはまいりませんなあ……」
半蔵は利兵衛のいつにない饒舌ぶりに、ただ驚いていた。 半蔵は利兵衛のいつにない饒舌ぶりに、ただ驚いていた。
