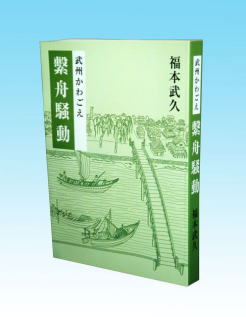 |
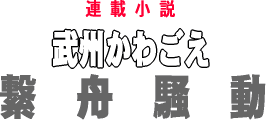 |
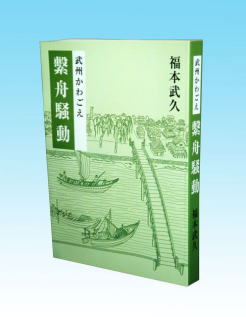 |
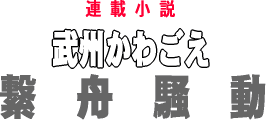 |
江戸時代……。武州川越は東国の穀倉といわれ、あらゆる物資の集散地でした。川越にあつまった諸物資は陸路ではなく、舟にゆられて江戸に運ばれてゆきました。 荒川の西側にあって、川越城下よりにほぼ一里の間隔を保ち、並行して流れる細い川筋が現在もあります。松平伊豆守がひらいたという新河岸川です。今ではほとんど知られることのないこの新河岸川は、川越と江戸を結ぶきわめて重要な水路でした。川越には扇河岸、上・下新河岸、牛子河岸、寺尾河岸の5つの河岸がひらかれ、新河岸川にはつねに300〜500艘もの高瀬舟が往来していたのです。 嘉永3年、川越では藩をゆるがす騒動がもちあがりました。 舟賃の増銭をめぐって、船頭、舟問屋、川越商人が3つどもえの様相! 船頭たちは4月と8月の2度にわたって舟を繋ぐという実力行使に出たのです。江戸では米騒動が起こり、川越では諸物価が高騰……! 夜明け前の日本、政治的にも経済的にも混乱が深まるなか、台頭してきた新しい労働者層(船頭、馬子たち)と、新興の市民層(川越商人、河岸問屋)の利害が対立、それは幕藩体制にもゆさぶりをかけることになります。河岸問屋のリーダーである主人公の炭屋半蔵は、河岸の将来を冷静にみつめ、利害対立する舟問屋をとりまとめ、船頭と川越商人、さらには街道の馬子たちの間を奔走します。 (本作品は最終更新からほぼ3年間、公開してきましたが、このほど電子書籍、ならびにオンデマンド印刷本としてBookWayから刊行しました。タイトルは同名の「武州かわごえ繋舟騒動」です。 |
| 電子書籍・オンデマンド印刷本として刊行! |
|
| All Right Reserved (c)Copyright 2004-2011 Fukumoto Takehisa |