
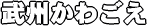

Part 1
旭 (あさひばし) 橋
◆
生い茂った葦萱のあいだをぬけると、川幅はくびれ、流れがにわかに速くなった。
櫓()を押すのは久しぶりだという亥三()の吐息が少し荒くなってきた。かつて亥三は腕利きの船頭だった。まもなく六〇になるかれは、二年まえに陸にあがり、いまでは川越五河岸のひとつ、上新河岸に店をかまえる舟積問屋・炭屋の番頭のひとりとして、舟着場をとりしきっている。
「手をかすぞ」
半蔵は立ちあがった。
「なんの、まだ、まだ……」
亥三は真顔で強がったが、半蔵は笑いながら立ちあがって棹()をにぎった。
右にむかって、ゆったり弓なりにのびていた川筋がやがてまっすぐになった。
ゆくてがひらけた土堤の両側には杉や欅()がつらなり、左岸かなたの高台には日枝神社のこんもりした森がかすかにみえてきた。そのふもとに視線をうつすと、川筋にそってつらなる白壁の土蔵がほんのりとみえる。
陽は西に落ちたが、まだ暮れきってはいない。茜色()の空を背景にして、ゆくて遠くに旭橋が濃い影をおとしている。
まるで一幅の絵のような世界ではないか。
半蔵は思わず眼をみはったが、その静謐()なたたずまいに緊張感が走った。橋桁()をくぐりぬけた一艘()の高瀬舟がみるみる半蔵たちの舟に接近してきたのである。
亥三はたくみな櫓さばきで素早く舟を左岸よせた。
「あれは?」
半蔵は身をのりだした。
早舟ではない。
川越夜舟()として知られる早舟()とはすでに一時ほどまえに行き交っている。
いつものように七ツに河岸を発ったであろう往来夜舟は、三艘が連なって川をくだっていった。いまごろは南畑あたりにさしかかっているはずである。舟の姿かたちからみて乗客をはこぶ舟ではない。
「まさか……」
半蔵は亥三をみた。
早くも川舟役所が動き出したのか。そんなわけがあるなずもないのに公役舟ではないか、といぶかしんだのである。
「ちがいますよ」
亥三は蔑むように笑いながら、「あれは扇河岸の舟だね……」と言った。
「飛び切り……か?」
「おそらく……」
「なら、とんだ見当ちがい、というわけか」
「まあ、そのようで……」
「いまから、ちりちりしていたら、どうしようもないな」
「長い舟路になりそうですからね。取り越し苦労もほどほどに……」
「爺()さんに、それを言われたんじゃ、世話がない」
半蔵は声をあげて笑った。
河岸の主といわれるだけに、亥三の眼はたしかである。
みるみる近づいてくる舟は夜を徹して川をくだるのだろう。早くも火を灯した舟提灯、橋本屋という文字が読みとれるようになると、舟を怪しく縁どっていた黒い影が溶けた。
艫()の間には積荷はない。胴の間に角ばった菰()づつみの荷が三つばかりある。
船頭をふくめて舟手の者は五人である。二人が櫓をつかい、二人が棹をあやつっている。はげしく上下する舳先()に波しぶきがぶつかっては崩れ、ときおりかれらの頭上にふりかかる。
船頭も水主()たちも、亥三にとっては顔見知りなのだろう。擦れちがいざまざま、かれは航路をゆずるかっこうで、舟を川縁によせ、櫓を押す手を休めた。
「恩に着るぜ」
ざんばら髪の船頭が手をあげ、日焼けしてどす黒い顔の水主たちも柔らかい笑みを返してきた。
「御用筋のものかもしれませんね、荷のほうは……」
橋本屋は川越五河岸のなかではもっとも城下にちかい扇河岸の舟問屋である。
城中からの荷物を請け負った急ぎ舟だというのが亥三のみるところだった。
慌ただしく下っていった舟を見送って、旭橋の橋桁ををくぐるぬけたとき、半蔵はゆっくりと河岸をみわたした。
岸辺にはは海鼠()壁の土蔵が軒をつらね、問屋の舟溜りには、それぞれ何艘かの舟が結わえられている。
暮六ツ、夕暮れである。
舟手の者を相手にする饂飩()屋や居酒屋、飯屋の軒先にある提灯の明かりがちらほらとみえる。
出舟入舟で賑わう商いの河岸場として名の聞こえた武州川越の新河岸の舟着場も、この時刻になると人影がまばらである。
だが……。
右岸に眼をこらすと土地の者が柳原()とよんでいる葦の生い茂った湿地には、刺し子の袢纏()をはおった人足たちが短い声かけ合い、はげしく行き来している。かれらは日暮れになっても馬車で運び込まれる丸太を積みあげていた。杉が多いようだが、松、欅、樫などもある。
(河岸は西川材で埋まっている)
半蔵はあらためて眼をみはった。
西川材とは江戸からみて西方の川によって運ばれてくる材木のことをいう。産地は飯能、青梅、名栗、越生あたりである。
「爺さん、いままでに、こんなこと、あったかい?」
「さあ……ね。昔から江戸で火事があるたびに西川材はまわって来ましたよ」
亥三は舟の舳先()を炭屋の船着場に向けながら、「それにしても柳原にまで丸太を積みあげたのは初めてのことだね」とかすれた声で言った。
「ありがたいことだがな」
「それは、もう、いつもなら荷枯れになるこの時期に、あれだけの荷があれば、船頭としては文句のつけようがありませんや」
「ありがたすぎる」
「ありがたすぎて、それで騒動の火種になるというわけですかね」
「こまりものだよ」
半蔵は低い声を立てて笑った。
炭屋の舟着場に降り立った半蔵は、「世話かけたな」といって亥三に酒代を握らせ、「会所のほうですかい?」と後ろから声をかけてくるのに、「兄さんには、今夜も遅くなりそうだ……とな」と手をあげて答え、舟問屋が軒をつらねる川沿いにひらけた河岸道に踏みいれた。
河内屋、そして半蔵自身の店である炭屋とつづき、通りひとつへだてた向かいには船宿の伊勢吉がある。半蔵は炭屋のまえにさしかかったが、表格子ごしにちらと帳場をのぞいただけで通りぬけた。
炭屋のはずれには酒屋、小料理店、居酒屋、湯屋などがある。斜向かいには同業の河岸問屋・麻屋があり、そのならびにも居酒屋や飲食店が軒をつらねている。
町のあちこちには、いつものように陸にあがった船頭や舟手の若い衆がたむろしていた。
舟を洗い終わった若い衆が連れだって湯屋に駆けこんでゆく。湯屋から出てきた年嵩()の水主たちは、酒屋の軒先で折り重なるようにして飲りだしている。
あたりはまだ暮れきっていない。
縄のれんのある居酒屋や小料理店には提灯の灯りがぼんやりと周囲を照らしている。暖簾()の向こうの障子には、手拍子を打つ人影が淡く重なって映え、さびの効いた濁声がかすかに脈うつようにもれている。
船頭は酒に始まり酒に終わる。出舟に一杯ひっかけ、入舟のときは一升というのが相場である。
ところが……。
男たちの息吹で泡立つ河岸の宵、半蔵にはどことなくいつもの活気が感じられないのである。
(気のせいなのだろうか)
半蔵は思案げに腕組みしながら、店先をのぞきながらすすんだ。
もしや……と、ひるがえってきたひとつの思案を、まさか……と、押しもどした。
いまひとつ心中がすっきりしないまま旭橋のたもとにある舟会所までやってきたが、大行事の望月八兵衛がやってくるまでにはまだ半刻あまり余裕があった。
半蔵は会所の前を素通りして、いましがた舟で橋桁をくぐった旭橋のほうに歩いた。
陽は西に落ちたが、あたりはまだ暮れきってはいない。
旭橋のかなたには半蔵が幼いときからかわらぬものとしてそこにある大柳がそびえ、そのまばゆいばかりの淡い緑がかすかに茜色に映えている。
橋のそばまでやってきて、ふとみるとひとりの老婆がうずくまっている。仙波村からやってきたお駒婆()である。
旭橋のたもとには古ぼけたちいさな石塔がある。馬頭明王と刻されていたという者もあれば、地蔵さんだったという者もある。表面はぼろぼろに風化して、いまでは判別つかないのだが、土地の者にしてみればどちらでもかまわない。祈りの心にあふれた新河岸の民によって昔から敬われてきたのである。
「橋のたもとにはね、死人の魂があつまってるんだよ」
お駒婆は出しだぬけに言った。
「おや、頭()かい」
お駒婆は顔をあげた。眼は虚ろで視線はどこか遠くをさまよっている。
「おれは、頭じゃないが……」
半蔵は思わず苦笑いした。
背丈は六尺ちかくもあるかれは、肩幅ひろく胸も厚い。河岸を歩いていても、船頭や馬手の者えさえも目をそばだてるほどで、会所の半蔵といえば、誰も知らない者はない。 毎日のように顔をつきあわせているのに、お駒婆が見誤ったのは、その日の半蔵が船頭と同じように三尺帯を締め、炭屋の印袢纏()をまとっていたからだろう。
「そうかい。でも、いい男だねえ」
お駒婆がいうように、まれにみる偉丈夫でである。
「旅先で死んだ者、水で死んだ者の魂が集まってくるんだよ。橋の下に……。あんた信じるかい」
「信じるよ」
半蔵は穏やかな声でこたえた。
刺すような鋭い眼光、ひきしまった口もと、黙っていると、射おろすような視線に威圧されて、誰もが一歩のけぞるほどなのだが、口もとがほころぶと、やにわに眼もとがあどけなく溶け、まるでこどものように剣がなくなるのである。
お駒婆は仙波村の農家の隠居である。かつては田畑の持高も多い本百姓だったが、文政四年(一八二一)の夏、武蔵野を襲った旱魃()で田畑は干あがった。年貢の負担に耐えられなくなっただけでなく、ふくれあがった肥料問屋への借金が返済できなくなった。田畑のほとんどは借金のかたにとられ、一家はちりじりになったのである。
「ここから旅立って、遠い異郷の空でたおれた者も、ちゃんともどってくるんだ。信じるかい、あんた」
「ああ、信じるとも」
お駒婆のひとり娘、一四歳になるきぬは江戸に売られていった。一五歳の次男坊も奉公に出立していった。お駒婆はふたりを旭橋で見送ったのである。いまではふたりとも消息がとだえ、その生死さえわからない。
「橋をわたる人に悪さをしないように……というわけだよな」
「そうだよ。どうか悪い魂から救ってくださいって……ね」
「そいつは、いい心根だ。きっと、そういう婆さんの心も救ってくださるだろうよ」
「あんた、いい人だねえ」
半蔵はお駒婆の声を背中で聞きながら、橋のなかほどまでゆっくり歩いた。
新河岸はもともと舟着場のためにひらかれた新田村落である。旭橋をさかいにして上流が上新河岸、下流が下新河岸である。旭橋をわたった対岸には下新河岸と向かい合う恰好で牛子河岸がある。
川の両岸には何艘もの高瀬舟がつないである。どの舟も西陽をあびてほの赤く縁どられ、ひっそりと波にゆれている。川筋にそって視線をあげてゆくと、日枝神社のこんもりとした森がみえ、はるか遠く野の果ての空が赤く映えている。茜色を撥ねるふもとの川沿いに寺尾河岸の村落がかすかにくすんでみえる。
半蔵は物心ついたころから、旭橋のうえに立って、川面と舟、野に落ちてゆく夕陽を見つづけてきた。
旭橋から見わたすことのできる上下新河岸、、牛子河岸、寺尾河岸、そして新河岸よりさらに一五町あまり上流にある扇河岸をふくめて川越五河岸という。新河岸の御用場には国方丸、武虎丸、大野丸、三芳丸という四艘の藩船が繋がれている。五河岸は川越藩の外港でもある。
旭橋は川越五河岸の中心である。橋のたもとには舟会所があって、新河岸川を上り下りする舟は、そこでかならずの請け状や送り状を書き写し、押切印を打つきまりになっている。
川も河岸も舟も、半蔵が生まれる一六〇年もまえから、変わらぬものとしてそこにあり、川越城下と江戸を結んでいるのである。
川越城下は江戸の穀倉である。武蔵国一円の穀物が蔵づくりの町にあつまってくる。諸国からもちこまれた年貢米だけでなく、飢饉のときには舟をつらねて、蔵屋敷の城詰米を浅草の御米蔵まで運ぶ。
河岸はあらゆる産物の集散地である。川越名産の甘藷、素麺、狭山茶などもこの川をくだってゆく。ときには甲斐や信濃からの荷がもちこまれることもある。
帰りの上り舟は、赤穂塩や斉田塩をはじめ、酢、油、砂糖、酒、塩肴など暮らしの必需品、太物や小間物、瀬戸物、さらには農家で消費される大坂糠や尾張糠、干鰯などの金肥を満載してもどってくる。
積荷は物資だけではない。
舟は江戸にのぼる旅人も運んだ。川越と江戸を行き来する商人や僧侶たち、売られてゆく女たちも夜舟でひっそりと旅立ってゆく。
七ツ半に新河岸を発ち、舟のなかで一晩すごせば、翌朝はもう千住大橋である。花川戸には午まえに着く。陸路の川越街道をゆくよりはるかに速いのである。
鉄砲や大筒も川をくだった。
外国船が近海に出没するようになった文政三年ごろから、川越藩は相州浦之郷陣屋の警備についている。およそ三〇〇の藩兵が陸路をゆき、陣屋送りの武具は河岸問屋の持舟を動員して花川戸まで運ばれた。七年まえの天保一四年の春、川越藩が相模の沿岸警備をまかれたときには、半蔵も公儀積荷の後見として舟にのりこんだことがある。大長持におさめられた鉄砲、粗筵()につつまれた大筒や砲台普請の工具、いずれも湿気をきらうだけに気むずかしい航海だった。
新河岸川は奇妙な川である。
城下の東端にある伊佐沼を水源とする川筋は、仙波沼やいくつかの沼を抱きこみ、まがりくねりながら台地をのびてゆく。それは沼や湧き水の湿地を縫うように南下するせいである。川幅は定まることがない。扇河岸あたりでは四〇間ほどもあるのだが、半蔵が立っている旭橋のあたりまでやってくると、わずか一〇間ほどになっている。
下流のたとえば福岡河岸あたりまでゆけば八〇間をこえるほどになるのに、五河岸の中心をなす上下新河岸の船着場あたりだけは川幅がくびれたように細くなって、行き来する舟がすれちがうのさえままならない。
櫓を押すことすらできない。棹だけしか使えない。見栄えのしない川筋というほかないが、江戸城の北方にあって、守りをかためる川越藩にとっては物流の要路であり、城下の町人や郷村の民にとっても、生命の水脈となっていた。
笛の音がどこか遠くから聞こえてくる。半蔵はふとわれにかえった。薄暮の川に眼をこらすと、ほのかに舟影がみえる。苫屋のある高瀬舟である。笛の音はそこからもれているらしい。
むせぶようで、どこか狂おしいひびきである。笛の音は舟が近づくにつれて、静かに哀切にひびきわたり、まるで夢幻の境地にいざなうかのようであった。
半蔵は憑かれたように接近してくる舟に眼をこらしていた。かつて江戸の商家にいたことのある半蔵は粋人である。新内や小唄、端唄、あるいは関東各地の風流踊りなどにくわしいかれでさえも、耳にしたことのない音色だった。
いったい何者なのだろう。奏者は女のようである。濃い影にふちどられて、姿かたちはよくわからない。名のある奏者なのではあるまいか。それにしても、どこからやってきたのか。
河岸の町は芸事もさかんである。商家の子女たちは舞踊や琴だけでなく、長唄、新内、清元、新内、常磐津()などの稽古にはげむ者さえいるのである。最初は城下の商人の誰かが江戸から招いた師匠のひとりではないか、と思ったが、どうやそうではないらしい。
悲痛な叫びともいおうか。不思議な笛の音に半蔵はひきつけられた。夕闇せまる川辺に、この世のものとは思えない旋律がただよい、思わずことばすら失って、ひたすら近づいてきる舟に眼をこらしていた。
舟が旭橋にさしかかろうとしたときであった。まるでくるったように速くなった笛の音がふいととぎれた。次の瞬間、奏者は橋の上にいる半蔵にちらと視線をなげた。
薄闇につつまれた女の顔はよくみえなかったが、澄んだ大きな瞳が、射るような烈しさで半蔵をみつめていた。
なんと……
半蔵は息をのんだとき、橋のたもとにいたお駒婆が、
「舟留めだ。あんた、舟が留まるよ」
と、いきなり叫びだした。
「たしか五年まえだよ。お江戸で大火事があったんだ。同じだよ。まったく。そのときも、あの笛が聞こえたんだ」
お駒婆は咳きこみながら言った。
笛の音を耳にした翌日から、河岸は舟留になったとお駒婆は繰り返した。年寄りの世迷い言とは思えないほどはっきりした口調である。
「あの笛の音色だよ。あんた。まちがいないよ」
「そうかい」
「あんた、信じるかい?」
「ああ、信じるよ」
半蔵がしきりに訴えかけてくるお駒婆に相づちを打っているうちに舟は橋桁の下に消えた。
半蔵は上流側の欄干()に移った。艫側からもういちど女の姿をとらようとしたのだが、舟が現れたとき、苫()の影にかくれてしまったのか女の姿はなかった。笛の音も断ちきるように消えてしまったが、半蔵の耳奥には、あのどこか狂おしげな響きだけが、余韻となっていつまでも残った。
