
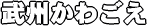

Part 2
舟 会 所
◆
夜はふけている。
宵の口まら河岸の居酒屋や小料理屋で気勢をあげていた舟手の男たちも、連れだって引きあげてゆく。
旭橋から西にのび、新河岸の集落を上下に二分する河岸街道を折り重なるようにしてやつてくる人影がある。空徳利をふりまわして、なにやら大声で叫んでいる男を、年嵩らしい三人がしきりになだめている。
川沿いの飲食店街のほうからも四人の男たちが河岸街道のほうに出てきた。袢纏
姿の男は船頭らしく、陽気に唄いながら、奇妙な手つきで踊り出し、配下の若い衆にも、「さあ、おまえたちも、踊らないか」と、さかんにけしかけている。
空徳利をさげている男たちが美濃屋の前にさしかかったとき、踊りながら河岸街道に出てきた袢纏姿の男とぶつかった。
「やい、てめえ、どこに眼をつけてるんだ」
「なにを言いやがる。当たったのは、てめえのほうじゃないか」
「なんだと!」
「おっ、やるか」
男たちはやにわに勇み立った。
男たちが気合いを発して、取っ組み合いをはじめた。
ちょうど舟会所の向かいあたりである。
店土間の格子戸ごしに、表の騒ぎは聞こえていたが、会所の奥まった部屋には緊張して張りつめた雰囲気がただよっていた。
もっとも河岸の者たちは夜ふけに喧嘩があったところで、誰一人として驚きはしない。
船頭は稼ぎも荒いが、気性も荒っぽい。酒と喧嘩で憂さを晴らす。新河岸では毎夜のようにあちこちで船頭や舟手の者たちがもつれあって、派手な大立ち回りをはじめるのであった。
船頭や水主たち、舟手の者は土地の者だけではない。近くでは荒川、遠くは利根川や那珂()
川あたりから流れてきた者たちもいる。土地の船頭と渡り者の船頭、酒の場で顔を合わせると、まちがいなく諍いがおこるのである。
舟会所ではふだん常雇いの使用人たちの控えにつかっている狭い部屋に、五河岸問屋の惣代()や世話役たちが膝をつきあわせ、すでに一刻あまりも密かに談じ合っていた。
上新河岸の名主であり河岸惣代でもある望月八兵衛をはじめ、五河岸の世話役たちの顔がそろっていた。
惣代の八兵衛を中心にして、右どなりには年行事をつとめる伊勢屋の弥重郎がひかえ、惣代の差副()役で書記役もつとめる炭屋の半蔵が、なにやら苛立ちながら、筆をもてあそんでいた。
川越五河岸の舟持問屋三〇軒の長ともいうべき八兵衛が客用の羽二重の座布団にあぐらをかいて、険しい眼つきで一同をみわたしながら説明しつづけていた。
「そういうわけで、このたびの舟賃のことは膝詰めで談判してみたのだが、まったくもって、どうも、こうも……」
八兵衛は苦笑いしながら首をふって、「伏見屋、近江屋、佐野屋、間坂屋、それに横田、榎本、十組問屋のおもな商家をまわってきたが、増銭については誰一人として耳を貸すものがない」と低いためいきをつき、「もはや、なんともはや、思案もつきた」と低い声を立てて笑った。
腕組みをして聴いていたひとりが顔をあげて重苦しい表情で訊ねた。下新河岸の小浜屋源助である。
「町方の者の料簡()は、いったい、どのようなあんばいで……」
さらに、もうひとり、扇河岸の中屋忠助が声をあげた。
「そうじゃ、諸色高値のこの時世、舟賃だけを据()え置け……とは、いったい、どういうことなんだ」
「さようなことは百も承知じゃ」と、八兵衛は口をはさんだ二人をにらみつけて、ことばをつづけた。
「おぬしらに言われるまでもないことじゃ。わしとて丁稚()の使いではないぞ。この数年をみて、われらが舟で江戸から運んできた商家の積荷は、みな眼をむくほど値がはねあがった。舟賃だけがどうして増銭がまかりならぬのか……とな。強談判()におよんだぞ。しかしじゃ……」
「しかし……なんと?」
寺尾の吉野屋勘七がもどかしそうに先をうながした。
「諸物がかように高値のおりに、そのうえ舟賃があがっては商()いが立ちゆかなくなる……と」
八兵衛はそういって一座の者の腹をさぐるかのように、さも、いわくありげな視線を投げてきた。
「商いに差し障りが出るのは、われらとて、同じでございましよう」
「そのこと、そのこと、ぬかりはないぞ。同じ科白をぶつけてやったぞ」
八兵衛はじれったそうに笑ったが、ふいに視線を膝もとに落として、「だが、相手は心得たものだ。最後はいつもながら例の伝家の宝刀だ」と言って鼻をこすった。
河岸に運びこまれる積荷はかならずしも、町方商人の荷物だけではない。城中からの御用荷や江戸勤番の家中に届ける荷物もある。公儀、御家中の荷物を優先するというのが、古来からの舟方趣法なのである。
春二月半ばの江戸大火で川越藩の江戸中屋敷が全焼した。藩邸建築の用材や資材、さらには家中侍の身の回りの品などの輸送が四月になったいまもつづいている。
「かようなおりに足下をみるかのように、舟賃を増銭するというのは、ご公儀をないがしろにするもの、不届き千万。まあ、そういうわけだ」
「なるほど、折りが悪いが……」
と、忠助がためいきをつけば、源助も腕組みしながら、「新河岸川は御公儀の川、そして舟稼業のわれらは御公儀あって舟問屋……というわけか。泣きどころを突きやがる」と鼻先で笑った。
御公儀の川であり、御公儀の河岸である……というのは 忠助がいうように五河岸の舟問屋にとって、ちょっとした殺し文句になる。
川越城の東を流れる内川に河岸場をつくり、舟運()をひらいたのは伊豆守信綱()である。正保四年(一六四七)年だというから、半蔵が生まれるより一六一年もまえのことである。
松平信綱が川越城主についたのは寛永一六年(一六三九)年の正月である。信綱は島原の乱を鎮圧した功によって、武蔵国忍()藩三万石の藩主から、七万石の川越藩主にとりたてられたのである。
川越にやってきた信綱は、ただちに城下町の整備にのりだしている。
まず川越城の増改築に着手した。城地の面積を二倍に拡張し、水壕と土塁をいくえにもめぐらし、本丸、二の丸、三の丸にくわえて新曲輪、中曲輪、南大手、西大手を新しくつくった。
かくして川越城は、三郭、二塹、八門からなる堅固な城郭に改築しうまれかわった。天守閣こそないが、城内の高台には五十尺もある富士見櫓()がひときわ高くそびえ、城下の中心をなすにふさわしいたたずまいになった。
新しくつくられた西大手と南大手にひろがる城下町の町割りもあらため、十カ町、四門前町にととのえた。
町づくりが完成すると、市をひらき、商業の振興にのりだした。市日を二・六・九の九斉にきめたのも信綱である。
信綱は寛文二年(一六六二)年まで二三年にわたって川越藩主をつとめたが、もっとも心血をそそいだのは武蔵野の新田開発であった。
川越の南は広大な原野である。水にめぐまれない原野をどのようにしてきりひらいて耕地にしたらいいのか。
新座郡の野火止()を開墾()して耕地をふやし、そこに集落をつくったが、台地ゆえに地下水が乏しく、農作物も不出来で飲み水さえも不足するありさまだった。
玉川上水から水を分けてもらい、野火止までもってくるという発想は、いかにも知恵伊豆といわれた信綱にふさわしいが、それが実現したのはやはり時の老中ゆえのご威光によるものだった。
信綱は家臣の安松金右衛門に命じて、多摩の小川から野火止までの台地に用水路を掘らせ、玉川上水からの分水を川越領までひっぱってきたのである。
野火止用水の完成によって、当初は三千石でしかなかった領内の収穫高が一万五千石までになった。
信綱の藩政改革によって、領内では林業、茶づくり、養蚕()がさかんになり、ほかに川越斜子()織、川越鋳物などの特産もうまれてきた。
農業の発展と殖産によって川越藩は豊かになり、城下町は武蔵国一円の産物集散地になった。
川越は江戸の穀倉といわれ、現実に武蔵一国から集まってくる年貢米だけでなく、たとえば災厄や飢饉()などの非常時に江戸に積み出す城詰め米なども藩の蔵屋敷におさめられている。
城下が繁栄し、江戸との交易が盛んになるにつれて、川越と江戸をむすぶ物資輸送の太い道筋が必要になってきた。
川越から江戸に向かう要路といえば、江戸往還()である。城下連雀()町の新宿()から入間郡の大井、新座郡の大和田、膝折、白子の四宿を経て、下練馬、上板橋、板橋の宿に達し、そこで中山道に合流する。およそ一三里のみちのりである。
最初のころは年貢米もこの往還をとおって江戸浅草まで運ばれていった。車馬をつらねて鈴の音で調子をとりながら、茫漠とした武蔵野をぬけていったのである。ところが信綱の時代になって大量の物資輸送が急務になると、車馬による陸路だけでは、どうにもならなくなってきた。
信綱は水路の開発を思い立った。
領内に水路がないわけではなかった。
川越の北部には入間川がある。武蔵野台地を環流する入間川は東にむかって流れ、やがて荒川とひとつになり、江戸湾をめざしてくだってゆく。
入間川には老袋河岸があり、さらに荒川との合流地点からほどなくの下流に平方河岸があった。俵物や材木など重量のある物資輸送には老袋河岸と平方河岸を外港にして、舟運を利用すればいい。ところが川越城下から老袋河岸までは一里二五町もあった。さらに冬になると水涸れで通船すらできなくなってしまう。
信綱はあれこれ物色したのちに眼をつけたのが、当時は内川とよばれていた新河岸川であった。
内川というのは外川の荒川に対する呼び名である。荒川の西にあって、川越城下よりにほぼ一里の間隔を保ち、並行して流れる細い川筋があった。それが内川である。城下の東にある伊佐沼から流れ出して、入間台地をまがりくねって、柳瀬川、黒目川と合流、新倉村あたりで外川と合流するのである。
信綱が着目するまでもなく、もともと内川は舟路として利用されていたこともある。
引俣(志木)の一里ほど北にある本河岸には川越藩の蔵屋敷があって、かつて蔵米がそこから舟で積み出されていたのである。
さらに信綱が川越にやってくる前年の寛永一五年(一六三八)年には、五河岸のひとつである寺尾村に河岸場がひらかれていた。
その年の一月二八日、川越城下が大火に飲み込まれ、喜多院や仙波東照宮までも類焼にみまわれた。再建の用材輸送を老袋、平方河岸で陸揚げすることになったが、春の渇水で通船できなかった。やむなく内川を物色したところ、当時は幕領だった寺尾村が舟着場として使えることがわかり、五反田とよばれていた空き地に建築用の材木を荷揚げしたのである。
信綱は内川を本河岸よりさらに上流まで延長、本格的な舟路としてととのえることを思い立ち、野火止用水をつくった家臣の安松金右衛門と小畑助左衛門に命じたのである。
改修工事は正保元年(一六四四)にはじまり四年後に完成した。
新河岸川という新しい水路は舟運の水路である。いくつもの沼地をつなぎ、あえて多くの屈曲をつけたのは、水枯れのときにも通舟できるように水量を確保するねらいからだった。
舟路ができあがると信綱は新しく舟着場をつくった。新しくひらかれた河岸というわけで新河岸なのである。
河岸ができあがると信綱は、土地の長百姓や城下の商人のなかから眼鏡にかなった人物を河岸守をえらんで、新河岸の新田集落に移住させた。惣代の八兵衛や半蔵の祖先も信綱に取り立てられて新河岸にやってきたひとりである。
新河岸川は御公儀の川であり、河岸も御公儀の河岸であるというのは、そういう経緯からである。
第一に御領主様御舟御用を大切に相勤め、第二に商人方荷物それまた大切に仕る……というのが昔からの川舟趣法としてかかげられてきた掟であり、舟問屋はながねん遵守したきたのである。
「八兵衛さん、ところで、こたびの、あのことは……」
源助がもどかしそうに声をあげた。
「口にせなんだ」
「どうして、また……」
「源助さん、考えてもみなさい。舟持問屋がね、あなた、たとえ口が裂けてもいえませんよ。舟留のことなどは……」
八兵衛は一同をにらみつけて言った。
船頭の龍吉たちが舟賃の増銭をもとめてきたのは半月まえのことである。
嘉永三年(一八五〇)年のその年は、年始めから米価が高騰していた。それにつれて諸物価がハネあがった。だが賃働きの料金については変わるところがなかった。酒代があがろうと銭湯の料金があがろうと、舟問屋の店先にかかげられた舟賃については、もう何十年も改められてはいない。冬場の水枯れのときなどには、多少の増銭はみとめられることもあるが、それはあくまで一時的なものでしかなかった。
物価の高騰に乗じて城下の商人や舟問屋は利鞘をふやしたが、舟一艘で食っている船頭たちはとっては、むしろ暮らし向きが苦しくなるだけだった。かれらは思案のあげくに舟賃の増銭をもとめてきた。
ひとにぎりの船頭が騒ぎ出し、思い思いに舟問屋にかけあったのではない。かれらは船頭のなかでも人望ある飛び切りの龍吉を代表者にえらび、五河岸惣代の八兵衛のもとにやってきたのである。あえて江戸送りの西川材の輸送で繁忙な時期を選んでいることからみても、一筋縄ではいかない、腰のすわった掛け合いであることが察せられた。
返答しだいによっては、舟を繋ぐこともある……というのが龍吉たちの口上だった。
「八兵衛さん、そうは言っても、期限が、もうとっくに過ぎておる」
忠助は重苦しい表情になったが、八兵衛は源助にむかって、「源助さん、前にも船頭どもが、舟をとめると騒いだときがありましたな。あれは、いつのころでしたかな?」と訊()いた。
「あれは五年前ですよ。そういえば、あのときも二月に江戸で大火があって、西川材の積み出しでわきかえっていましたよ」
源助の話を聞いて、半蔵は「あっ」と思った。
お駒婆の顔が脳裏によみがえたのである。
あんた、舟が留まるよ……と、お駒婆は言った。お江戸で火事があったんだ、と叫ぶように言って、あのとき、五年前に耳にしたのと同じ笛の音が聞こえた、としきりに繰り返していた。
世迷()い言ではないか。あのとき半蔵ですらも半信半疑だったが、虚()けた老婆の出まかせではなく、あの不思議な笛の音色によってひるがえってきた記憶から発せられたものにちがいない。源助と忠助のやりとりを耳にして、半蔵はあらためてそのように確信した。
「ところで半蔵さん……」と、そのときまで黙っていた年行事の弥重郎が顔をあげて、「どうだったね。あちらのようすは……」と水を向けてきた。その日、半蔵は八兵衛にたのまれて舟を出した。船頭たちの溜まり場になっている南畑までくだって、それとなく探りをいれてきたのである。
「どうも、こうも……」
半蔵は眼だけで笑っている。一同の反応を楽しんでいる。
「何か不穏な動きでも?」
身を乗り出してきたのは、牛子の大嶋屋卯兵衛である。
「なんの、それは、なんとも静かなものでしたよ」
「なら、何も案ずることはありますまいな」
忠助は安堵したかのように肩で大きな吐息をついたが、半蔵は微笑みながら、「だからこそ不気味じゃありませんか。かえって案ぜられてならんのですよ」と顔の表情をひきしめて、ことばをつづけた。
「いいですかな、皆の衆、大事をなそうとするときならば……ですよ、誰が相手に悟られるような下手なマネをしますか?」
「なら、連中はやる気だというのかね。半蔵さん」
勘七が青ざめた。
「十中八、九、まちがいありませんね」
「ほう、さようか。さようか」
八兵衛はせせら笑い、なぜか妙に落ち着きはらっている。
ほかの世話役たちの顔は半蔵の話を聞いてにわかにこわばったのに、八兵衛だけは、何もかもお見通しだといわんばかりの老獪()な顔つきで聞き流していた。
「……して、その五年前のときは、いかがな次第に?」
一座のなかではもっとも若い忠助が躯をのりだしてきた。
「舟留は三日におよんだが、あとはなんともはや……」
源助は低い声を立てて笑い、意味ありげな視線で八兵衛をうかがいみた。
「そうだったな」
八兵衛は薄ら笑いをうかべてうなずき、わけわからずにぽかんとしている忠助に向きなおり、「船頭どもは最初は威勢よくて、われらも肝をつぶした。ところがどうだ。四日目になると、なんと積荷の奪い合いをはじめたではないか。これにはたまげたぞ。われらはかえって拍子ぬけしたわ」
「騒動はそれまで……ですか?」
「そうだ」
弘化二年の舟留は一部の船頭の煽動によるものだった……と、八兵衛がもっともらしく説明すると、世話役たちは安堵したかのように大きな吐息をついた。
「皆の衆、それは、ちと、甘いんじゃないですかい。今回もそのときと同じだという料簡は……」
半蔵はゆっくりと顔をあげた。
「甘いとは、どういうことですか? 炭屋さん」
源助が訊いた。
「船頭にとっては舟が生命、その舟を留めるというのはよくよくのことですよ。私のみるところ、輩はもはや烏合()の衆ではありませんぞ」
「たかが船頭どものことだ」
「さように気に病むこともあるまいて」
蔑()むような低い笑いがよこにひろがったが、半蔵はそれを制するように咳払いして、口をひらいた。
「船頭どもを甘くみちゃ、いけませんぜ。やつらがなぜ、烏合の衆ではないか。たとえば、こたびは龍吉という男を世話役に立て談判にやってきた。腰をすえてじっくりかまえるつもりだ。そのことひとつをみても油断がなりませんぞ」
半蔵は皆の眼が自分に注がれているのを感じとると、一人ひとりをジロリとにらみつけ、「それにひきかえわれら問屋のほうはどうです。舟を留めるというのにまるで他人事じゃありませんか」と言いはなった。
「ところで忠助さん」
半蔵はふいに扇河岸の代表としてやってきた中屋の忠助に向かって、「どうして市郎兵衛さんは、おいでにならないのですか?」と笑いかけ、勘七に向きなおって、「あなたのところも、どうして藤五郎さんがお運びにならないのですかな?」と、とぼけた顔でだしぬけに訊きいた。
「さようなことは、私どもは……」
顔を見合わせた忠助と勘七の口から、「そこのところは一向に存じませんが……」と同じ科白がとびだしてきた。
「われらは舟問屋ですよ。舟問屋の売り物は何ですか。舟ですよね。皆の衆もよくご承知だ。その舟が止まるやもしれないというときに、河岸をあずかる名主が出てこないというのは、いったいどういう魂胆ですかな」
半蔵は乾いた声で笑った。
「わかった。半蔵さん。お前さんのいうことはよくわかったから、そのあたりで、もうよさないか」
八兵衛が見かねてかたわらでささやきかけたが、半蔵はさらにつづけた。
「肝をつぶしたような顔をしながら、裏ではむしろ舟留をよろこんでおられる向きもあるようだ。これはかの城下の大店の話ではありませんぞ。のう大嶋屋さん……」
名指しされた卯兵衛はひくりと背を伸ばして、「どうして、また、私に訊くんですか。半蔵さん、あんたは人が悪い」とあわてたのがのがおかしかったのか、半蔵は愉快そうに笑い、「これではいくら談じても足なみがそろわん。話が決まらないのはあたりまえというものですよ」と言った。
「ともかく皆の衆、城下の十組問屋との掛け合いのなりゆきは、いま申し述べた通りでな……」八兵衛はやおら口をひらいて、「舟賃のことは相手があることだから、われらだけではいかんともしがたい。さて、さて、身体きわまったとは、このことだ」と苦笑いした。
「返答の期日は、暮れ六ッですから、もう過ぎております。いったい、いかがなさるおつもりで……」
半蔵はあえて訊いてみた。
「相手のいうがままに返答しなければならないという道理はない。もともと強訴同然の掛け合いではないか」
八兵衛はふてぶてしく開き直った。
「それでは舟方が承知しますまい」
弥重郎が言えば、勘七もおおきくうなずいて、「半蔵さんの言うように、舟方が本気だたら、いったい、どうするつもりですかい?」と上眼づかいに声をあげた。
「なあに、そのときは、そのときの思案があろうて。いまは、あわてずに相手の出方をみるほかあるまい」
八兵衛は一同を見渡してから、「それに、五年前の例もあることだ」と微笑んだ。
河岸をとりしきる惣代がそんなありさまだから、いくら談合をひらいても名案がうまれるはずもなかった。
「皆の衆、そんなわけで、河岸へ帰ったら、船頭の動きに、ぬかりなく目配りのほど、くれぐれもたのみますぞ」
面倒なことは先送りにする。いつも変わらぬ談合のなりゆきだが、世話役たちは、それとはなしに、ホッとしたような顔をたがいに見合わせ、黙りこんで何やらうなずき合っていた。かれらは徒労に終わったながい談合から解き放たれると、挨拶もそこそこに立ちあがった。
二日後になるか。それとも三日後になるのか。こんどは肝をつぶしてやってくるだろうが、やることといえば、またしても、いつも変わらぬ徒労の談合だろう。
半蔵は提灯をさげて帰ってゆく世話役たちを見送りながら、ふと、そう思った。
「やれやれ、前門には城下の商家あり、後門には船頭どもあり……。身体きわまったとはこのことだ……」
八兵衛は苦笑いして、深いためいきをついた。
「船頭たちが舟を留めれば、問屋も同腹とみられましょうな」
年行事の弥重郎がぽつりと言った。
「そりゃ、そうですよ。船頭は舟問屋支配の者ということになっている。もし舟留になったとして、あれは船頭が勝手にやったことで……という申し開きは立たないだろうからね」
半蔵はそっけなく言った。
かれは弥重郎ではなく八兵衛を意識して口をひらいたのたが、その八兵衛から、「さて、さて何か、いい思案はないものかね」と、愚痴()がとびだしてきて、すっかり鼻白んでしまった。
