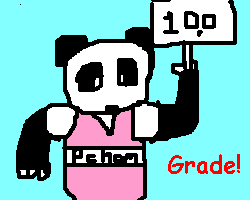
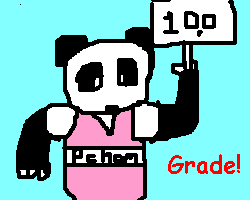
監督 スティーブン・スピルバーグ 主演 トム・ハンクス、トム・サイズモア、エドワード・バーンズ、マット・デイモンほか
(10月1日までの採点は、『プライベート・ライアン』、
10月8日までの採点は『プライベート・ライアン(2)』
10月11日までの採点は『プライベート・ライアン(3)』
に掲載しています。まず最初に、そちらをごらんください。)
はるひこ(10月14日)
ishii@binah.cc.brandeis.edu
冒頭の戦闘の場面には本当に圧倒されました。確かにスピルバーグが映画技術を駆使してひたすら衝撃的な映像を撮ろうとするのをあざといと見ることもできると思います。でも、僕としては(いろいろ演出はあるにせよ)説明抜きで戦闘の場面を描写したことで自分なりにいろいろ考えることができたのです。「戦争体験のない若い人」としてはこれを見て戦場というのはこんなに恐ろしい場所なのかと実感しましたし。それだけで単に映画を見るなんて事を超越した価値があったと思います。パンちゃん@サンドイッチ(10月14日)
それなのに、予想はしていたのですが、この後のライアン二等兵の救出という本題に入ると、とたんにリアリティーがなくなってしまいました。ストーリーや登場人物から、音楽の使い方まで紋切り型で、この登場人物達は生身の人間でなく、あくまでスピルバーグがメッセージを伝えるための駒に過ぎないように見えました。だから、僕には物語としてあまり魅力を感じられなかったんです。それはメッセージの中身そのものとは、すこしずれた問題です。(例えば、僕は北野武監督が「HANA−BI」の中で表現している世界観にはかなり違和感があったのですが、物語と、その表現の方法が面白かったので映画として楽しめました。)
とは言え、僕はこの映画に面白い・面白くないの問題だけではない違和感を感じた事も確かなので、その理由をつらつら考えて見ました。
パンちゃんが日記の中で、「ライアン救出劇は、私の思いでは、ベトナムでも湾岸戦争が舞台でも成り立つ」と書いていますが、僕もそれに同感です。でも、ベトナムや湾岸戦争では多分この「映画」は成り立たなかった。何故なら、スピルバーグが描きたかったのはおそらく「自由のための戦争」で、ベトナムや湾岸戦争では第二次世界大戦ほど堂々とは「自由のための戦争」と言いにくいし、ベトナムの場合それに勝利したとも言えない。でもこの映画の中でスピルバーグは第二次世界大戦でのアメリカの勝利の価値を、そのための代償・犠牲の大きさを強調することによってのみ表現しているみたいで、そこにどこか誤魔化しがあると感じるんです。だって、例え多くの代償を払った戦争でもベトナム戦争にはそれほどの意義があったとは言い難いのだから。
あれだけ凄惨な場面を見せつけておきながら、スピルバーグにはアメリカはこういう風に自由を勝ち取って来たんだという事に対する強い信念があるんでしょうね。だから、我々は戦争に勝利したが敵にも味方にも多くの犠牲者を出してしまったという見方ではなく、我々はこの犠牲の結果勝利したんだ、そしてそれに見合った人間、国家にならなければいけない、という結論になるのでしょう。
始めのノルマンディー上陸の場面を見て、僕はどうしても国家が国民を戦場に送ることの理不尽さも感じられずにはいられなかったんです。確かに、戦争は起きるときには起きてしまうかもしれない。その時には戦わなければいけないかもしれない。でも、その結果多くの人が死ぬことを割り切ってしまいたくはない。アメリカは尊敬すべき国で、だからこそ僕もここで勉強しているわけです。でもアメリカの、自分が正義であることに対する自信と、派兵によって犠牲者が出ることに対する事へのためらいの無さは少し怖いと思う。(そう感じているのは僕のような日本人に限らない。)そして、スピルバーグのこの映画にも、その単純な割り切りが見えてしまい、そこに抵抗を感じてしまう。
このコーナーでサンドイッチ話題が出ましたね。nahoko(★★★★)(10月13日)
私は、そのシーンをトム・ハンクスが「なんだ、こいつらのうのうとサンドイッチなんか食ってやがって」という風に誤解して見てたんだけれど、これは多分、私が空腹だったことと関係があると思う。(変な弁解)
朝11時50分からの映画を見たのだけれど、上映前に串団子を食べただけ。ランチはこの映画が終わったあと……という気持ちがどっかにあったんだなあ。
こうしたことは「映画」ではないし、「映画に関する話題」ですらないかもしれない。
でも、こういうことって、映画の評価に変なところで影響して来る。
無意識的反応は「正しい評価」とは無縁のものかもしれないが、「無意識」であるからこそ、自分だけでは気づかない。
他人に指摘されて、はっとする。
そのはっとする瞬間が好きなので、私はこのページを開いています。
これは「映画」について語ったこと、これは「映画に関する話題」と区別する人は区別する人でかまいませんが、区別しない人は区別しない人で、何でも書き込んでください。
誰が何に気づいたか、何を見落としたか、などということは、その人の感想を聞くまでわからない。そこからどんなふうに新しい感想が生まれ、新しい発見があるか、わからない。
少しずつでも何かが見つかり、映画が好きになっていく--そうしたページになることを願っています。
*
『ライアン』の悪口をたくさん書いたようなので、好きなシーンをいくつか書いてみます。(きょうは1回目)
マット・デイモンはこの映画では割のあわない役、あまり同情されそうもない役をやっているが、一か所、とてもいいシーンがある。
トム・ハンクスに兄弟の死を告げられて、兄を思い出そうとするシーン。
マット・デイモンが思い出すのは、兄の初体験にまつわる出来事だが、このとき彼は、笑いながら話す。エピソードが笑い話みたいだからだが、このとき、マット・デイモンは、口は笑っているが、目は笑っていない。
その感情の表現がなんともこころに迫って来る。
兄弟の死を知る--そのとき最初に思い出すのは、兄たちが親切にしてくれたとか、兄たちとこんな苦労をしたとかということではなく、どうでもいいこと、思い出さなくてもいいことだった。それが、つらい。
そして、ここには、とても深い人間観察の目も存在すると思う。
私たちはとても強い衝撃を受けたとき、それをどう受け止めていいか、わからない。それを受け止めるのにふさわしい状態にはすぐにはたどりつけない。
混乱してしまって、本当にどうしていいかわからない。
私は小さいとき、田舎の砂利道で男がバイクで転倒し、足から白い骨が剥き出しになっているのを見たことがある。はやく手当てをしなければならないのに、彼は、川に流されたゴム草履を拾おうと必死になっていた。
何かとんでもないことが起きたとき、私たちは、意味の脈略を失う。大切なものは何かという脈略を失う。
そして、失いながらも、失っていることにも気づく。
兄の初体験の笑い話を笑いながら語りながら、語りおえるとマット・デイモンは泣き出す。
泣きたいのに笑い話を思い出し、笑い話なのに泣いてしまう。
この感情の混乱には胸がしめつけられる。
この部分のマット・デイモンは本当にすばらしい。
*
あ、採点の★ですが、数の定義(?)は、私が思いつきで書いただけです。
基準はご自由に。★だけの書き込みだと、その人の考えていることはわからないけれど、感想が一緒だと、この人は★1個だけど、この映画が好きなんだなあ、とか、この人★4個つけてるけど何だかあんまり好きじゃないみたい、とか伝わるでしょ。
星は、「見る価値ありは4つ」って基準を読んだので、4コにしときま す。<今まで基準を気にしてなかったらしい。。。ひろみーぬ(10月13日)
見終わった後に「重い・・・」「語りたくない映画だわ・・・」「つら い・・・」と言った私でしたが、翌日にちょっと感想を言い始めたら、延々と語 り合ってしまったので、やっぱり出しておきます。
ノルマンディ上陸の場面については、散々感想を読み、心の準備をしてから行っ たので、ちゃんと観てないんです。正視していないの。指の間から観た。ちょっ とだけ。言葉はないです。みつからないと言うべきか。
それ以外の感想、強く記憶に残っているシーンだけを挙げます。
ライアンの母が、知らせを受けるために開けたドアの隣に飾ってある4兄弟の写 真。
死んで行く兵士たちが「ママーッッ」(確か)と叫び続けていたこと。
本当の戦闘に直面して、足が竦んで、どうにも動けなかったアパムが、最後に、 前に助けた(という表現で合っているのか)ドイツ兵を撃つシーン。
一発ごとに、神に祈りを捧げながらも、敵兵を狙撃していく不条理とか。
サンドイッチも、とっても覚えてる。
それをどう思ったか、全部細かく言葉にすると、正しく伝えたいために、ものす ごく長い文になるかもしれないので、やめます。なんか、観ていたときよりも、 思い出して書いてると涙出ちゃうんだなあ。不思議。
とりあえず、この映画が何を伝えたかったのか、本当の狙いはなんだったのか、 とか置いておいて、観る価値はある映画ですよね。そう思います。
特に、若者に観てもらいたい、とババアな気持ちになって勧めてしまいたい。
で、それぞれにいろんなことを感じて、考えるというだけでも、もしかしたらす ごい映画なんだろうか・・・と、今思います。
ここでも、こんなに感想の違いもあるし。 (まだ全部読んでいませんが)
関係ないんだけど、平和ボケ(と私も思う)の日本で、以前、湾岸戦争勃発のニュ ースに「やれやれー。殺し合いすればいいんだよ」と(とっても楽しそうに)仕事 中に発言していた人がいたんだよね。
元々その人に対して低かった私の評価(向こうのが上司だったけど)は、その一言 で地の底まで落ちた。
彼は当時38歳くらいで5歳くらいの子供の親だった。大きなお世話だけど、そ の子はどんなふうに育てられているんだろう、とすごく心配になった覚えがある の。
彼がこの映画を観たら、冗談にもあんなことを言わなくなるだろうか。と、ちょ っと思った。
・・・以上です。
短いつもりだったけど、結構長いな〜・・・そして、内容がナイ・・だけど、送 ります。
好き嫌いで言うと、戦争ものっていうジャンル自体が好きじゃないんだけど、そ ういう論点では言ってはイケナイ気になってしまっているので、星が4つです。
トム・ハンクスはどうでもよかったような気もしてるし、最初と最後のシーンは 要らなかった気もするんだけど、確かに衝撃でした。私には。
パンちゃんは『ウェルカム・トゥ・サラエボ』は観ましたか?
あれの、爆撃を受けたあとの一般人の姿も(多分、ホンモノの映像?)感情より先 に、つらくて涙が出る映像でしたけど、コレはまた違う。
今週は『友情の翼』観るんだけど、戦争モノを観て、戦争は良くない、とか、結 局誰が悪かったのか、とか考えるよりも、今後をどうしていくべきなのか、それ を考えたいですよね。
ぱんちゃんの日記にあったどんな感じ方でもOK!ってことに甘えての感想です。reina(10月13日)
きりさんと同じくワタクシも見るのに疲れて途中寝た寝た。見る前にシコタマ飲んでしまい、慌てて入れば空いてる席が最前列の隅っこ。ハスに構えてスクリーンを仰ぎ見るうち、揺れる映像はそこからの画面をさらに見辛くさせ、終った時は酒の酔いか画面酔いか、頭ガンガンでした。でも、それがかえって戦場の瓦礫の山に身を隠していたが如しの臨場感を得ることとなりましたが。
リアリズムを期待しての最初の戦闘場面は、整い過ぎたフィクションそのものに思えてしまいました。彼氏に眼を隠してもらいながら、それでも指の間から見ていた最前列の横に居た女性に気を取られてしまい、そんな映像の激しさに妙に白けてしまったからかも知れません。周りを気にして没頭できないのって変ですよね。でも、遊園地のホラー屋敷じゃないのよって突っ込みたくもなってしまった。
いつでも戦争映画で思うけど、邦画洋画を問わず、最期は「おかあさん」なんですね。母親の愛情が必ずしも子供だけに一心に向かっている訳ではない事をよく知ってる現代の母親としては複雑です。それから、ミラー少尉が眩しそうな眼でバラの手入れをする妻の事に触れ、口を噤んでしまうところも・・
戦争の悲惨さは二度と手に出来ないものを際立たせるんですね。それは、ただ庇護される立場の無防備だった幼い自分とか、日だまりの中に浮かび上がる家族の姿とか・・現実以上に尊く美しいものに変えてしまうのでしょうか。家庭だけが安住の場ではなくなりつつある平和な今、とても切ないです。だからラストの唐突なライアンファミリーの登場と、妻に自らを問うところは本当に嘘っぽいです。彼が生きて来た人生はそんな奇麗事で締めくくれる程単純である筈ないのに。アウシュビッツで神父が自分の身代わりになって生かされた人がいたけど、彼のその後の人生が必ずしも幸せではなかったと聞いた事がある。それを思い出しました。
最後に、このマット・ディモンは良いですねぇ。戦地で救出される事態に陥った自分の立場に抵抗しつつ、多くは語らなかったけど、彼の演じたどのキャラクターよりもミーハーは気に入ったです。何故って?オバサンは戸惑う若い男が好きなんです。は・は・は・・すみません。
★はみっつです。映画を見てから、こんなに後引くものって余りありませんから。
また書いてしまった。。。キリヤマ(10月13日)
まず、誤解が生じているようなのでストレートに2点。
1.私も戦争は嫌いです。戦争なんてしてほしくないし、実際に戦争に突入したときのショックは直面した人にしかわからないと思います。私は戦争開始後、湾岸戦争反対運動には参加しませんでしたが、戦争が始まるまでは極力避けてもらいたいと思っておりました。
2.私はアメリカ人です。在米日本人とは違うので、考え方も普通の日本人とは違うと思います。アメリカ人の中でも特に愛国心が強く育ったのは忠誠心が強い性格からでしょう。
あと、職業軍人は戦争好きの鬼のように考えていらっしゃる方が多いようですが、戦争はなるべく避けたいが、攻撃されたら守らねば!と思い軍にはいる人も決して少なくありません。私の婚約者は元職業軍人ですが戦争は大嫌いです。
ちょっとだけ書かせて − 最近、とあるハワイの沖縄県系人の言葉を新聞の書評で読みました。(その人について詳しいことは書かれていませんでしたが、恐らく第二次大戦中にはアメリカ兵として参戦して沖縄語の通訳をしたか、または日本兵なのに英語ができるのでスパイ扱いされたか、そういう年代の人だと思います。)きり(★★★)(10月12日)
「戦争を始めるのは国だけれど、殺し合いをするのは人間だ」という言葉です。
人を殺すことが「国を守るため」の単なる一つの正当な手段でしかないのが戦争であって、戦争にあっては、軍隊は国を守るだろうけど、人間は守らない。
私が「国を守るための戦争」を肯定できない理由をこう考えてみました。
ようやく噂の…ライアン君を観に行った。すぐに感想を書こうと思ったけれど、頭の中が上手くまとまらなくって…。じゅんこ(10月12日)
アタシはいつも観たままの感想しかないんだけれど、、結局この映画は何を言いたかったのかが良く分からなかった。アタシは、スピルバーグが嫌いだ。(ごめんね、パンちゃん)そして、アメリカ人の作る戦争映画も嫌いだ。(ごめんね、アメリカにいる人)でもそれは、アタシが日本人だからかなぁとも思う。いつもそうやって偏見を持って観てしまうので、今回は、「これはアメリカ人が作ったアメリカ映画なんだ。アメリカ人の気持ちになって観よう…。そうしたら、例えアメリカ万歳映画だとしても理解できるかもしれない…。」と1人でぶつぶつ考えながら見始めた。しかも、ここに書いてある感想を読んでしまっていたので、最初の30分がすごいのか…って少し構えながら…。
し・しかし…………めちゃめちゃ率直な感想は…長い…しつこい…。
最初のノルマンディー上陸(?)のところ?良く分からないけど、この辺で良いだろってところで終わってくれないし、途中の戦うシーンも、なんだか同じようで飽きちゃったし…。最近流行なのか知らないけど、ハンディカメラで撮ったようなゆらゆらの映像も、途中で新鮮味がなくなってくるし…。とにかく、途中、少し寝ちゃったのです(^^;でも、ライアン君に会えてからは良かった…かなぁ。
トム・ハンクスもいつんなったら死ぬんだよっと思ってたら、結構感動的に死んでくれたし……。ただ単に戦争が駄目〜っていう映画ではなかったとは思うんだけど、やっぱり良くワカンナイなぁ…。頭悪いのかなぁ? ま、これが私の観たままの感想なので仕方がない。
あ、もう1つ。。実際にこの戦争に行ったおじいちゃんとかが観たら、泣いちゃうかもなぁ…と思った。。。そんなに辛い過去を思い出させないでよ…スピルバーグ……。相変わらずしょうもない感想でゴメンナサイ。
プライベート・ライアン(追記) ごめんなさい。みなさんの意見をよく読まずに安易に感想を述べていたようで、あらためて読みかえしましたので、ちょっと追加で書かせてね。またまたパンちゃん(10月12日)
(といっても3ページもあるもんだから全部は結局読み切れていないのだ。気を付けないとディベートとは時に、解決へ向かうのではなく「自分がいかに正しいか」の証明に走ってしまう危険性を秘めているのです) 戦争は無意味か、という点について。
個人的には無意味であると考えます。もちろん、先日の「テポドン事件(なんだかマヌケだぞ…)」以来、自分の生活を自分で守ることの必要性というもの(そして独立国としてのプライド…アメリカは突如「ミサイルだというのは間違い、あれは衛星の打ち上げだった」と発表し、その後、一切情報公開をしようとしませんが、北朝鮮との間で何らかの取り引きがあったのだろうとささやかれているようです。日本のことは日本で守れといわれるけれど、日本に偵察衛星を持つことも許されていないでしょ。それでいて日本の安全に関わる情報をもみ消してしまうアメリカも失礼だけど、日本政府は何をしてるの〜。日本が独立国家だなんて幻想なのね)をひしひしと感じる今日この頃ですが、それでも敢えて戦争反対、と言いたい。私は戦争経験なんていらない。心に大きな傷を作るような悲惨な体験はしたくないし、させたくない。ベトナム戦争にいった兵士の精神を切り刻んだのは、正義がどうこうというイデオロギーの問題ではなく目の前で人が殺されていく悲惨な戦争体験そのものだったのでは?そこをスタート地点にしたい。
これはある雑誌の受けうりなんですが、私も今日のアメリカに「正義の暴走」を感じる。クリントンのセックス疑惑の過熱報道にしろ、先日のスーダン攻撃にしろ、自由と民主主義という理念があれば何をしてもいいのかしら?私がここで言いたいのは、実際に軍で働いている人々を非難しろ、ということでも、アメリカの正義が間違っている、ということでもなく、あくまでも「戦争は悪である」ということを誰かが言い続けなければならないということです。「戦争は避けるべき最悪の事態」だと言い改めるべきかも。とにかく正義の名の元での暴走を差し止める力として、異なる意見が必要なのでは?色々な見解が拮抗し、牽制しあい、互いの暴走にストップを掛けているというのが理想形。そして反戦を訴える手段として映画は非常に有効な媒体であると思う。
それにしても、もし『プライベート・ライアン』が本当に反戦映画を目指すのなら、やはりラストシーンは必要なかった。マヌケというレベルを通り超して本末転倒だとさえ。アレックスのパパさんが解説されていたEarn this.のセリフがなんだったのかと思わざるをえません。高校教師で愛妻家だったハンクス(役名失念)が死んでまで敬礼されたいなんて思うでしょうかね?
ここまで書いてバレバレかと思うのですが、予告編採点に文句を書いたトム・ハンクス、予想に反して私の中では評価が上がりました。反対に自分の役がなんなのか理解していたのか怪しいマット・デイモンの評価は下がったんだけど…(いや、あれは脚本と演出のせいか…)
じゅんこさんの最初の書き込みは『プライベート・ライアン(3)』にあります。
あるビジターから、この欄について、きつい非難を受けた。(ビジターのことばを直接転載することができないので、いかに書くことは私の誤解を多分に含んでいると思う。そう思いながらも、書かずにはいられない。)
ここで展開されている『プライベート・ライアン』についての感想は、「映画」そのものについて語っているのではなく、「映画に関する話題」である。「映画に関する話題」で『プライベート・ライアン』を評価するのは間違っている、というのである。
そのビジターによれば、この映画は映画として絶対的に優れている。映画としてのキレがある。それは「結論」であって、それを認めないのは、映画を見ていないからだ。映画を見ないで、「反戦」のメッセージだけを受け取ろうとして受け取ることができず、それが気に食わなくて『プライベート・ライアン』を批判しているだけなのだ、とそのビジターは主張する。
そのビジターはまた、私がこの欄で、『プライベート・ライアン』批判の「署名集め」(反戦メッセージを含まない映画批判の署名集め)をしている、とも非難している。
私は、この欄で『プライベート・ライアン』について話題になっている、意見を聞かせてください、と何人かに直接呼びかけ、また幾つかの掲示板にも書き込んだ。しかし、私は「あなたの反戦メッセージを聞かせてください」と依頼したことはない。
そのビジターにとっては「映画に関する話題」で、『プライベート・ライアン』を汚す(?)ことが我慢がならないのかもしれない。
しかし私は「映画」と「映画に関する話題」を区別することはできない。
ノルマンディー上陸作戦の描写を見て、それを悲惨だと感じる、悲惨だと感じ戦争はいやだと感じる。そこから「戦争反対」という思いを強くし、何事かを語る。それはこの映画の勝利である。
あるいは、この描写を見て、私たちの今の自由は、こうした多くの犠牲の上に築かれたものである、と感じ、そうした犠牲者に対して敬意と感謝を感じる。それは同様にこの映画の勝利である。
どちらの側の感じ方が正しいか、など誰にも言えない。それはその人の信条の問題であり、その人がこれからどう考え、行動して行くかということの問題だ。
「映画」を離れ、個人の問題に変化して行くから、それは「映画の問題」ではなく「映画に関する問題」だと、たぶん、そのビジターは主張するのだと思う。
しかし、そんなふうに何もかも引き寄せてしまうものが「映画」なのではないか。「芸術」なのではないか。
あるシーンが映像的に迫力があり優れている、あるシーンの音響の使い方が優れている、あるシーンは過去の映画のこのシーンの引用である、このシーンの映像によってこの映画は新しい映像の可能性を切り開いた、この映画は映画史のなかでこのような位置を占める、このシーンの映像はハンディカメラで撮っている、この俯瞰シーンはクレーンで撮っている、このシーンのスローモーションは効果があるなどと分析し、評価することだけが「映画」を見るということではないだろう。それだけが「絶対的に正しい映画の見方」とはいえないだろう。
映画を見て感じたことすべてが「映画」そのものである。
『プライベート・ライアン』を見て、反戦メッセージが不十分であると感じるにしろ、戦争の犠牲者に対する追悼の思いを強くするにしろ、それは、この映画を見たからである。そうした思いは観客のこころのなかに潜んでいたものであり、この映画が引き出したものなのだ。
こころに潜んでいたものは、徐々にしか語ることができない。たとえば「反戦メッセージが不十分である」あるいは「戦争犠牲者への追悼を感じる」。その感じ方はたぶん観客がそれまでどのような社会の中で生きて来たか、どのような戦争観が支配的な社会で生きてきたかということと関係すると思うが、そのビジターは、そうした無意識的なところから映画を語るのは「映画を抑圧する」ことだ、そうした反応は「既成のことば」で「映画を抑圧する」ことだ、とも言っている。映画は、そこに「ある」ものとして、絶対的存在として見つめなければならない、そうしないのは「映画への抑圧」であるとも主張している。
しかし、そんな超人的な見方は私にはできない。多くのビジターもできないと思う。衝撃的な映像を見れば、無意識的に反応する。そのときのことばは「反戦メッセージが不十分」とか「戦争犠牲者への追悼」とか、たしかに「既成のことば」かもしれない。これは仕方ないことではないか。自分のなかで起きた突然の衝撃をオリジナルなことばで語ることのできる人間などほとんどいないと思う。自分の知っていることば、自分が聞いてきたことばを手掛かりに語り始めるしかない。
自分で語り、他者の語りを聞き、少しずつ自分の考えを見つめなおしていく、そうすること以外に、どんなことができるのか私にはわからない。
映画にしろ、他の芸術にしろ、観客(鑑賞者)に衝撃を与え、様々な反応を引き出す。そうして引き出された反応そのものが、本当は「映画」そのものより大きいし、実はそれこそが「映画」でもありうると思う。「映画」を映像のキレだとか音響だとか、映画史の位置づけだとかに閉じ込めるのは、私に言わせれば、映画の矮小化である。
『プライベート・ライアン』の上映時間はたかだか3時間である。フィルムのなかの世界は3時間で終わってしまう。しかし、それを見たものの思いは3時間では終わらず、様々な形で続いて行く。その思いは「映画」のように終わりがあるわけではない。結論があるわけではない。また、その思いは、「映画」のように目に見える形でくっきりと存在するわけではない。ああでもない、こうでもない、と形を変えながら存在し続ける。そうした不定形の思いこそ、大切なものだと思う。不定形の思いのなかで、私たちは何度でもその映画に出会う。
映画について、何度も何度も語る。そのたびごとに、思いのなかで映画は生き続ける。よみがえり続ける。そのよみがえりこそが「映画」そのものである。スクリーンに写っている影は「映画」の一部に過ぎない。
『プライベート・ライアン』を通して、戦争に対する思いを語ることを、そのビジターは「映画に関する話題」と呼び、それを語ることを「映画に対する抑圧」と呼ぶ。
しかし、この映画を見て、戦争についての思いを語ること以外に何か必要なことがあるだろう。戦争と結び付けずに何事かを語って意味があるだろうか。
スピルバーグはどう思っているか知らないが、こうして語られていることは、それがどんなにスピルバーグ批判、あるいは『プライベート・ライアン』批判を含んでいようが、この映画の勝利である。この映画は私たちに、何度も何度も語り合うことを強いている。戦争について語り合い、考えることを強いている。そうした力を持っている。
こうしたことを語ることは、「この映画は20年に1本の傑作である」と「結論」づけるより大切なことだ。
*
「映画」自身について。
私は前半の30分と後半のライアン救出劇をつなぐものがない、と批判した。前半の30分が8人の行動にどのように反映しているかわからないから、前半の30分のリアルな映像に衝撃を受けるが、真に感動(?)するわけにはいかない、と批判した。スピルバーグはただ、ものすごい映像を撮りたかっただけなのだと感じ、それを不気味だと思うからだ。
私を批判するビジターは、前半の30分と後半をつなぐものなどない、断絶がある、それこそがこの映画のテーマである、と言う。
そのビジターにメールで書いたことだが、私は、実はこの見方こそ、このビジターから聞き出したいことだった。
これは本当にそのビジターが言うとおりだと思う。
前半のものすごい30分の殺戮--その衝撃は救出劇を演じる8人にどのようにも影響しているようにもみえない。それはけっして影響しないのだ。なぜなら、その30分の殺戮の状況は悲惨すぎるからだ。衝撃が強すぎて受け止めることができないからだ。戦争の一瞬一瞬の衝撃は、どう受け止めていいかわからないくらい強烈なのだ。
れいなさんが「銃で打たれると痛すぎて痛みを感じない」というようなことを書いていたが、衝撃は強すぎるとどう感じていいのかわからない。体とこころがそれに反応しないのだ。
スピルバーグは確かにそこまで戦争を直視しているのだと言える。
後半の救出劇にあらわれる断片的なエピソード(トム・ハンクスと友人が語るイタリアの小人、マット・デイモンが語る兄の初体験の笑い話)がえぐり出す断面、戦場にふさわしくない断面、その断絶、そこにこそ確かに戦争の真実がある。今彼らが体験している惨劇はことばにならない。ことばを超えている。語ることができるのは、この惨劇と直接結びつかない過去のことだけである。
人間の意識は、そんなふうにして、やっと耐えているのだ。
それは十分にわかる。わかるけれども、私はスピルバーグのこの映画を評価しない。
その時、つまり実際に戦争を体験しているときはどんなつながりも見いだせないにしろ、どこかにつながり、ノルマンディー上陸の際の衝撃が影響し、彼らの行動を支配していたはずである。それを明るみにだすことこそ映画の仕事だろう。
どのような大事件も、すぐには語れない。そこで起きたことは当事者には断片の寄せ集めにしか感じられないと思う。それはしかし、断片のままにしておくのではなく、何度も何度もつなぎあわせ、ことばにならない形で起きたものを明るみにだそうと努めることが必要なのだ。
あの悲惨なノルマンディーの体験がいったいどのように人間を変えたのか、そのことを描かないことには、この映画は何も描いたことにはならないと思う。ただ、悲惨な状況をリアルな映像と音によって再現しただけの見せ物になってしまう。それでは戦争で亡くなった多くの人に対して失礼というものではないだろうか。こうした思いも「映画に関する話題」であろうが、それを抜きにした「映画」だけの話題など、何か意味があるのだろうか。
最初の30分が8人にどのような影響を与えたか描いていないからこそ、救出されたライアンが救出されることによってどのような影響を受けたかも描くことができないのだと思う。
戦後何十年もたって、やっとトム・ハンクスの墓にやってきて涙ぐみ、「自分はいい人間だっただろうか」というようなとぼけたことしか語らせることができない。彼の受けた衝撃がそんなとぼけた思いしか語れないほど強いものだった、と言えば言えるのだろうが、そんな「断絶」の羅列で、戦争は悲惨なものなのだ、と伝えるのではあまりにもいいかげん、としか言いようがない。
戦争の当時は肉眼で見ていても意識には見えないものがある。見ていながら見なかったものとして意識の奥に隠しているものもあるかもしれない。そうしたもの、深く意識に潜在したものをえぐり出し、物理的現象としての「戦争」を超えたもの、内面の「戦争」の痕跡こそが描かれなければならないと思う。
私が書いているのは、スピルバーグ批判であると同時に、スピルバーグへの期待である。期待があるから批判するのだ。何の期待もなければ批判などしない。
「映画」について語るのではなく「映画に関する話題」を語ることは「映画への抑圧」であるという態度こそ、「映画への抑圧」ではないのか。
「トム・ハンクスのもも、太かったねえ」
「戦争だもん、あれくらい太くないと生きて行けないよ」
「射撃の巧い役者、かっこよかったねえ」
「やっぱり戦場の緊迫感が男を鋭敏に磨くのかしら」
これは、たまたま耳にした、なんだかぶっ飛んだ会話だが、ここにも「戦争」がちらりと影を出している。
語りが始まっている。その「始まり」ということが、私はすごいことだと思う。
人はどこからでも語り始める。語り始めずにはいられない。そうした語りを「映画に関する話題」とくくって、「映画」とは関係ない、「映画を抑圧するもの」と定義付け、「映画」をまつりあげるという姿勢は、私には納得がいかない。