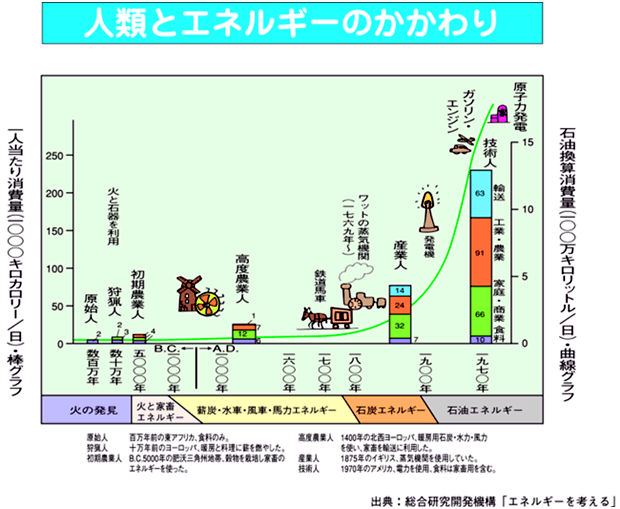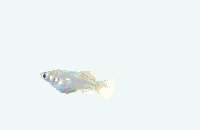地球の気候は温暖化しており、その原因は二酸化炭素であるといわれている。それが事実か否か、私はわからない。しかし本日はそれを前提に話を進める。
決して私がIPCCの与太話を信じているわけではない。
最近はロハスだとか、環境に優しい暮らしとか、グリーンなんとかとか、地球環境を大切になんて運動というか動きが目立っている。
反骨精神の塊である私だから、本日はそんなことはおかしいぞ!ということを書く。
京都議定書の約束を守ろうと日本では政府が音頭を取って、チームマイナス6%なんて運動を進めている。けなげなというべきか、無駄なあがきというべきか、焼け石の水と思える。
京都議定書を満足しても地球温暖化は止まらないことは間違いない。そして日本が京都議定書を守ったとしても世界の二酸化炭素排出は減少しない。アメリカが世界最大の排出国だからアメリカのせいだ!などというのはいまや通用しない。なぜなら世界最大の排出国という栄誉は今や中国のものとなった。そして中国の二酸化炭素排出量は2006年時点で、およそ日本の5倍、そして毎年日本の3割以上の増加である。
二酸化炭素排出量は日本が中国にかなわないもののひとつである。しかし不思議と思いませんか?
あるいは中国に勝てない唯一のものかもしれない。
中国の一人当たり国民所得は日本の1割、車だってそんなに走っているわけではなく、電化製品も少ない。停電だって多い。それなのに一人当たり二酸化炭素(エネルギーとほぼ同じ)が日本の半分ということは、いかにエネルギー効率が悪いかということだ。
二酸化炭素が地球温暖化の原因かどうかは分からない。しかし、二酸化炭素が地球温暖化の原因でなくても、地球温暖化が真実でなくても実は同じことなのである。
なぜなら、化石燃料はあとほんのわずかでなくなってしまうのは確実であり、そのときどのように暮らしていくべきかを考えれば地球温暖化が真実であろうと、なかろうと同じ対策が必要となるだろう。
ではどのような暮らし、生活様式、ライフスタイルがあるべきものなのか?
まず、エネルギー浪費をしないことが最重要だ。
チームマイナス6%なんてつましいことではなく、チームマイナス60%くらい実行しましょう。本当を言えばチームマイナス99.6%くらいしないと持続可能社会にはなれないのです。
エネルギー浪費の最たるものは車です。
たばこの害を知らしめようと箱に書いてある文句は
「喫煙はあなたにとって肺がんの原因の一つになります。喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。」
これを真似て自動車の広告には必ず警告文を入れましょう。
|
好きな人と一緒、 そして
青空と一緒  オープンカーでエアコンをかけながら走るのがおしゃれです。 快適なドライブを楽しみましょう。 警告 車は60歳を過ぎてから。若年者の運転は禁止されています。 ■■技研工業株式会社
|
|
ガソリン1L=2.4kgCo2 ⇒ 市街地の燃費を10km/Lとして0.24kgCo2 電気1kWh=0.43kg ⇒ Co2液晶テレビ32型で約150W=0.0645kgCo2 (環境省データによる) 実を言って私はいろいろなデータを探して算出するのは趣味に合わない。自分の知識と知恵でほとんどのことは解決できるはず(単に調べるのが面倒ともいう) 車は通常最大出力の30%程度で走っている。なこと運転しているときタコメーターを見てトルク特性と考え合わせれば当然のこと。そしてエンジンの効率と発電から送電までの効率を同等と仮定する。 25馬力で走行して1キロ2分弱で走ると仮定すれば次の式ができる。 30kW×100秒=150W×○秒 ○=20,000秒=5時間半 上記とは若干違った数値になったがいずれこの程度だ |
そして俺は悪いことを自分の意思でするんだものねと自覚している人だけが車を使うべきでしょう。
車メーカーが反対する心配ですか? 燃料がなくなることを思えば少しでも社会に貢献し、かつ自分の事業が長続きすることを望むのと違いますか?
じゃあ、移動手段としてどうするのか?と思いますか?
とりあえずとしては、電車を使いましょう。バスを使いましょう。自転車を使いましょう。歩きましょう。健康によく、メタボなんて問題はあっという間に解消します。
わざわざ遠くまでゴルフに行かなくても、毎日グリーンを歩いていると思えば楽しくありませんか?
じゃあ、田舎ならどうするのか?
エネルギーがなければ昔のように歩くとか、バスなどの公共交通機関に頼らざるを得ません。大人も子供も自分の車で通勤、通学、お買いもの、なんてことはできないのです。
ない袖は振れません。年配者には厳しい時代になるでしょう。それもやむを得ません。
いずれ化石燃料がなくなれば世の中からバスも電車もなくなるでしょう。
|
STOP  |
インターネットだってしてはいけません。今情報通信で総エネルギーの2%くらいが使われています。
インターネットするには、あなたのパソコン、光ケーブルや電話線、プロバイダ、メイン回線、海底ケーブル、すべて膨大な電気を使います。そして皆が快適にアクセスできるのは途中に多数の電気食いのコンピューターがあるからできるのです。
インターネットは実際に移動するより環境によいのかどうか?疑問であります。
人間関係には悪そうです。
インターネットにもたばこや酒のように警告を入れなければなりません。
食べ物は旬のものといえば聞こえがいいですが、その季節にとれる物しか食べてはいけません。そして遠くの地で採れる物も食べてはいけません。
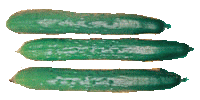 冬にトマトを食べたいとか、きゅうりを食べたいとかいうのはご法度です。
冬にトマトを食べたいとか、きゅうりを食べたいとかいうのはご法度です。地球環境のために、トマトときゅうりは夏、冬は漬物を食べましょう。
遠くでしか捕れないもの、マグロを食べたいとか、バナナを食べたいとか、そういうの環境にやさしくありません。
あなたの近くで採れる物を食べましょう。海の近くならお魚、山にお住まいなら山菜、海にいて山菜を食べるのは犯罪、山にいて刺身を食べようなんてものなら百叩きの刑です。
見方を変えれば、20世紀の後半は異常だったのです。
銀行から借りた金でお買い物をしていたようなもので、借金だったのですから返さなければならないようなものです。
これからはお天道様からいただいたエネルギーだけで生きていくしかできません。
泣いても笑ってもだめです。
それが環境にやさしい暮らしです。
まとめです。
ロハスとか省エネに努めましょうなんてことでは・・無理なのです。
ふっくん様からお便りを頂きました(08.03.17)
考えさせられます。 環境にやさしい暮らしはもはや我々にはできないのでしょうか?あるデータでは全ての人が日本人程度の生活を望むとき、エネルギー的に、食料的に…地球には20億人以上は絶対に住めないといわれています。人間が自然を離れて歩き出した時点(約1万年前)で、自然と同一化(自然の中でともに生活すること)はできなくなり、その後の産業革命を経て、人類は後戻りできないほどに地球資源を食いつぶすようになってしまいました。 でもここまで進化や発展を遂げても「オールウェイズ 3丁目の夕日」が爆発的にヒットするように人は昔の時代に郷愁というか「憧れ」に近い感情を持っているのも事実ですね。「古き良き時代」というのが一般語として浸透していることからも伺えます。人間とは不可解なものです。 せめて、それこそ1950年〜1960年代に人の意識が戻ることができれば、人類は継続的存続(継続的発展は捨てる!)が可能かも知れませんが、人間の脳みその前頭葉はそれを許さないでしょう。 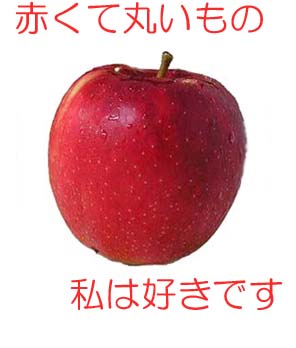 話は変わりますが、シェル・シルヴァスタインの「大きな木」という絵本があります。小さい頃からずっと仲良しだった少年とリンゴの木の話ですが、概ね粗筋はこうです。
話は変わりますが、シェル・シルヴァスタインの「大きな木」という絵本があります。小さい頃からずっと仲良しだった少年とリンゴの木の話ですが、概ね粗筋はこうです。木と少年はその日あったことを話したり、一緒にお昼寝したり、ブランコで遊んだり、木にとって幸せな毎日でした。(人類に喩えれば1万年前まで) やがて少年は青年になり恋をし大人になり、木の事なんかすっかり忘れてしまうが、ある日突然木のところにやってきてはお金がほしい、家がほしいとモノをせびりだします。しかし木は久しぶりに少年が訪ねてきて自分を頼ってくれたことを喜びリンゴを売るように提案したり、自分の枝・幹を切って家を作ればいいと提案したりするわけです(産業革命〜現代) 結局少年は老人になり何もかも失い疲れ切ってしまった姿で、木に休む場所を求め、木は残った切り株で休めばいいと言って老人はそこで休むのです。(人類の未来?)「何もなくなってしまったが、それでも木は幸せだった」という一文でこの絵本は締めくくられていますが、私はこの話が地球と人間の関係に見えて仕方ありません。そのとき地球は木のように幸せを感じますかね。静かに何も言わず太陽の周りを回っているだけですね。 ネットで調べると、「大きな木」で老人になった少年が来たときこのようなやり取りが交わされたみたいです。 最後に切り株だけになった木の所へ、老人になった少年がひょっこり帰ってくる。 木は泣きながら言う。 「ごめんなさい。 もう何もあげるものがありません」「いや、もう何も要らない。 私は休みたいだけだ」と彼は切り株に腰を下ろす。 なんとなく人類の未来を象徴しているような気がします。もしかしたらここに至るまでに崩壊するかもしれません。 しかし、中国からの無差別爆撃(黄砂)はどうにかなりませんかね〜。当面私の悩みは「花粉症」と「黄砂」です。 |
ふっくん様 毎度ありがとうございます。 20億さえ多すぎるような気がします。キリストが生きていた頃、2000年前の人口は2億前後だそうです。再生可能な自然エネルギーだけでは地球の人口維持力はこのていどなのでしょう。もちろん、気候は常に変動していますから、寒冷期はそれさえ厳しく、温暖な時期はもう少し多いでしょう。 3丁目の夕日であっても既に持続可能は無理です。もちろんたった50年前であっても現在よりは消費エネルギーは数分の1で今あと50年が文明が保たれる期間とすれば、当時の生活なら300年くらいは持つのかもしれません。少しの違いというより大きな違いのような気がします。 持続的発展とは詐欺的表現で、はじめは持続可能社会といわれたようです。結局経済界とかを説得するには発展の言葉がないと振り向いてくれなかったということでしょう。 リンゴの話! 初耳です。しかし何と悲しい話でしょうか。人間は狩猟生活で持続可能であったほうが良かったのか? 一時であっても宇宙にまで進出できたほうが良かったのか? 私が小学生の頃、学校の先生がいった話ですが 未開の原住民の所に来た文明人が「文化が遅れている、ばかだなあ」と言ったそうです。 その後、核戦争になって文明が滅んで未開人が言いました。「ばかだなあ」 1960年当時はアメリカとソ連がいつ核戦争を始めるか気が気でなかった頃ですから まあ、悩みないところに進歩がないともいいますから、環境問題も人間が一段と飛躍するために神様が与えたもうた試練なのかもしれません。 |
上々様からお便りを頂きました(08.03.18)
環境にやさしい暮らし 「環境にやさしい暮らし」拝見いたしました。エネルギーの調達が文明のすべてであると言うことも気が付かずに、環境環境と騒いでいる風潮には愛想が尽きます。 いまだに石油はあと300年で枯渇するなどととぼけたことを言っている人もいますが、そろそろ石油ピークと言うものがどういうものかも薄々とは皆気付いてきているのではないかと思います。 石油の供給がピークを越せば、需給バランスが大きく崩れ、価格高騰は言うに及ばず、場合によれば武力衝突もありうる情勢になる可能性が考えられます。 一刻も早くできるだけエネルギーを節約できる社会体制に移行することが、世界を地獄に向かわせるのを防ぐ方策なのですが。 この文章の中で引用していらっしゃるエネルギー使用の歴史の図ですが、将来の見通しを付け加えている人も居ます。その図では、今後すぐに急激にエネルギー使用量は落ち込み、20世紀の莫大なエネルギー使用というのがほんの一瞬の幻のように表わされています。もしも人類の文明が今後も続くことがあれば、将来の歴史家は20世紀をなんと表現するでしょうか。「幻のエネルギー時代?」 |
上々様 お便りありがとうございます。 恐ろしいことに気づいたとき、それについて考える人と、気がつかないふりをする人の二通りあると思います。 薄々とは皆気付いていても、自分の生きているうちは問題ないだろうとか、破滅のときまで楽しく生きようという人が多いのではないでしょうか? 危険や破滅を認識して、それに立ち向かうというのはそうとうな勇気がいるのでしょう。 ところでご教示ありました、未来のエネルギーの見通しですが、ググっても見つかりませんでした。ご存知でしたら教えてください。 |
上々様からお便りを頂きました(08.03.21)
お問い合わせの件 佐為様 お返事ありがとうございます。 ISOは職業柄色々と調べておりますが、エネルギー関係も主な興味の対象ですので一言申し上げさせていただきました。 さて、ちょっと判りにくいことを書いてしまいましたが、出典は東京大学名誉教授で元環境研究所所長、「もったいない」学会会長の石井吉徳先生のHPの中にある、石井先生の講演記録の中の図9がそれです。 文中にもありますように、この図は石井さんのオリジナルではないようです。しかし、私もこれを見た時には今の高エネルギー消費時代というのが人類の歴史の中では本の一瞬の幻のような時代に過ぎないのではないかと思いショックを受けました。 現代のような資源浪費の時代はどこかおかしいとは皆思っていると思います。また一部の経済人以外の、科学の考え方をもつ人は皆、いずれは資源が枯渇すると言うことは意識していると思います。ただそれが何年先か、10年先と思っているのか、100年先と思っているのかで思想や行動が大きく異なってくると思います。 ちなみに私は石油の枯渇はまだ相当先の話だと思っていますが、「石油ピーク」は既に来ており、供給量が徐々に減っていくため大きな社会不安につながるものと考えています。 |
上々様 ご教示ありがとうございます。 なるほど、確かにまっすぐな直線のたった一か所にピークがあるだけという感じですね。 しかし、そうしますと、更なる疑問がわき起こります。 上々様も私も、この人類史というか地球史のほんとうにまれな一時に生を受けて生きているということが確率的にレアケースであり、偶然にしては出来すぎという感じがします。 いいかえると、これは偶然ではないのではないか、レアケースではなく連続している状態に過ぎないのではないかという思いがあります。決して楽観とか問題なんて起きるはずがないということではないのですが・・ とかんぐるのは間違いでしょうか? |
上々様からお便りを頂きました(08.03.21)
この図の意味はあくまでも石油石炭等のエネルギー資源の消費量がほんの一時期にかたまってしまったというだけのことで、その他の時期にも人が居なかったわけでもなく、文明がなかったわけでもない。別の形の社会があったということではないでしょうか。 ただ現在のエネルギー源はあまりにも都合が良すぎたために爆発的に使ってしまった。その意味では人類の100万年の歴史の中でもレアケースと言えるのかも知れません。そのひずみがこれから一気に出てくるのかも知れません。そのひずみというものも100万年に一度のレアケースなのかも知れません。 文明の興亡というのはこれまでも世界中のあちこちで何度も起こっていたことですが、それが世界一体の文明となったがために、興亡も世界一斉ということになるのでしょう。 |
上々様 ご教示ありがとうございます。 だいぶ前、過去何度何度も文明は興り、それらは跡形もなく滅んだというマンガを見たことがあります。 現代文明が崩壊したとき、ビルや道路、その他現在の形あるものが消え去るにどのくらい時間がかかるのでしょうか? 1000年ということはないですよね、1万年なら石造り、コンクリート造りも崩壊してしまうのでしょうか? ストーンヘンジやピラミッドを現代人が見て思うように、1万年後マンハッタンの跡の草木も生えないがれきを見て、未来人は昔の人類は機械も使わずによくこんな大規模な神殿を作ったものだと感心しているのでしょうか? そしてその時には再び蓄えられた石油と天然ガスを使った文明があったりして・・・ 1万年では石油は蓄積されませんか? それじゃあ10万年後としましょう。いずれにしても地球はそれくらい執行猶予をしてくれるでしょう。 |
ふっくん様からお便りを頂きました(09.05.08)
ご意見お聞かせください。 水質問題によく言われるたとえですが、「しょうゆを大匙1はい流すと、魚が住める水にするのに、風呂3はいの水が必要・・・」私が環境問題を考え出してからいつも疑問に思っているフレーズです。これは多分水生生物が通常生きるためのBODなどを基準に、魚たちが住むためには希釈倍率がこんなにかかるんだよということを端的にあらわした言葉だとは思うのですが、現実にしょうゆを流して本当に魚は住めないの?って子供に聞かれると、どういう返事をすればいいのか非常に難しいフレーズでもあります。 かといって、どのくらいの家が流したら(実際に確信犯的にやる人はいないでしょうが)、そんな現象になるのか・・・など考えると、表現として妥当なのかなと考えてしまいます。これは啓蒙活動の一環として理解してもらうしかないのでしょうか?最近は、そういう突っ込みを入れるちょっとませた子供もいるんですよ。 どうか悩める子羊にそんな子供たちにも笑えるような解説をつけていただけませんでしょうか? |
ふっくん様 毎度ありがとうございます。 醤油と魚で検索すると下記のようなものが見つかりました。 http://www3.ocn.ne.jp/~qpc/b_q4_teian/4_teian_bod.html 醤油15mlを魚が住めるようにするには450リットルの水で薄めなければならないとあります。 この表ではBODだけを問題にしています。 この前提として、醤油のBODは15万mg/L、魚が住める水質を5mg/Lと仮定しています。 まず片づけなくてはならないことはいくつかあります。
それにしても魚といってもピンからキリまであります。一番なじみのあるコイとかフナを例にとって10mg/Lとすれば、まあ1万5千倍、15mL×15000=225L 最初の半分です。BOD5mg/Lを10mg/LまでOKとしたのだから当然ですね。 そんなものじゃないですか? 現在の都会の川はきれいかも知れませんが、案外田舎の川のほうが下水が完備していないし、農業からの排水でBODもその他の農薬なども多そうです。 |
あらま様からお便りを頂きました(09.05.09)
塩水濃度 佐為さま あらまです 水質汚染については知りませんが、一さじの醤油を金魚ばちに入れても、ぜんぜん問題ないと思います。 金魚には、0.5%の濃度の塩水浴をさせて元気付けることがありますし、河口付近の海でも、平気で淡水魚が泳いでいるのを見かけます。 むかし、小生が酔っ払ったとき、金魚にも酒をくれたことがありましたが、翌朝、金魚たちは二日酔いにもならず、元気でした。 ・・・といいますか、最初から金魚は赤いですからね ? (何か、意味不明なことを書いてしまいました。良い子は、絶対に真似をしないでくださいね) |
あらま様 毎度ありがとうございます。 お酒はお醤油よりさらに大変なようです。なにしろ命の水というくらいですから栄養満点、ということはBODももうたくさん・・ お酒のBODは20万mg/Lとありますから、お醤油の3割増しでございます。 ちょっと待ってください! 金魚蜂にお酒? 金魚蜂の水の量はふつう2L〜3Lです。ということは金魚さんが急性アル中(嘘ですよ、BOD多量による酸欠です)で死なないためには、お酒0.3mL以下でないとなりません。ピペットで1滴というと0.03〜0.05mLになるそうです。もっとも目薬は0.05mL以上になるらしい。いずれにしても10滴以上金魚蜂に入れたら、あらま様は金魚さんの幽霊に悩まされていたはずです。 きっとあらまさんが飼っている金魚さんはアルコールに強い体質だったのかもしれません。多分、あらま様が毎日アルコールを飲んでいるので、その影響があったのでしょう。 いやあ、この世は何が幸いするかわかりません。ヨカッタ、ヨカッタ |
ふっくん様からお便りを頂きました(09.05.09)
佐為さま お世話になります。お返事ありがとうございました。 大前提条件を書き忘れていたのですが、本来、川には風呂桶の何十倍〜何百倍もの水が流れています。(川の大小はありますが)でもなおかつ風呂桶3杯分の水が必要なのかとマセ餓鬼に聞かれた訳です。 確かに川が汚れている場合を除き、改めて希釈する必要はないように思いますが、かといってみんながみんな、「赤信号みんなで渡れば恐くない」的にやってもそれはダメなことです。 赤信号を無視して誰かが渡る。。。何人かが渡る。。。そのうちタンクローリーが赤信号で渡る人を避けようとして町のガソリンスタンドとかガスタンクに突っ込んで大爆発が起きて大勢の人が亡くなった・・・ そんな例えで少しだからいいやといろんなものを川に流しているといつかは川が汚れ、それは魚のみならず人にも被害を与えるのだよって説明してはいるのですが(笑) |
ふっくん様、毎度ありがとうございます。 川に汚水というか汚れを入れた場合にそのためにさらに水がほしいということはないでしょうね。まあ、考え方ですが、その汚水を浄化するためにそのぶんの川の水が消費されると考えればよいのでしょうか? 似たようなことですが。 日本の川は短く急流で水の滞在時間が短時間ですが、基本的には水は大気から酸素が供給されるので一回BODの酸化に使われたらおしまいというわけではなく、時間とともにDO(溶存酸素)は回復します。というか、一定以下のBODならそもそも定常状態ということでしょうね。 元々がたとえ話でしょうから、あまり真剣に考えることもないのかもしれません。 |
あらま様からお便りを頂きました(09.05.09)
佐為さま あらまです 小生は水質についてはまったく分かりませんが、人間と共生しているお魚さんたちは、けっこうたくましく生きているようです。 たとえば、ある家庭で、入浴剤に染まった家庭排水を川に流しても、鯉などは平気で泳いでいます。 ・・・というか、きれいに澄んだ水の中の魚というと、山の奥に生息するヤマメとか鮎ぐらいで、人里に住む魚たちは、かなり濁ったところで生きているようです。 海でも、透明度があるのかないのか分からない河口付近に魚が集中します。栄養価が高いからでしょうか。 もちろん、魚の種類にもよるでしょうが、まじめな話、そんなにきれいな水質でなければ魚が住めないなんて、何かの間違いではないかと思ってしまいます。 だいだい、金魚の餌やりでも、相当に水が汚れます。それなのに、さじ一杯の醤油を薄めるのに、風呂の水ほどの量が必要だなんて現実的でないように思えてしまいます。 逆に、そのぐらいきれいでないと魚が住めないのであれば、日本中の魚が絶滅してしまうのではないでしょうか。 あの虹色の川の中国でさえも、川に魚が泳いでいるといいますから。 ちなみに、小生が酔っ払って、金魚ばちに酒を入れた量は、ワンカップ 1/4でした。 でも、平気でしたよ ! ? ところで、江戸時代の狂歌を思い出しました。 「白河の清き流れに魚住まず 元のにごりの田沼恋しき」 いえ、けっして環境を良くすることを否定しているのではないですよ。 数字が、あまりにも現実的でないように思えて・・・・ |
あらま様 毎度ありがとうございます。 金魚蜂の容量を2.5Lと仮定しましょう。ワンカップ180mLですから、その1/4で45mL、そうしますとお酒をいれたとき水がこぼれなかったとして、そのBODは 45/(2500+45)×200,000≒3500(mg/L)となります。 うーん、確かにこの数値は下水どころじゃないですね しかしこの場合、BODだけじゃなくアルコールの毒性もあるし、浸透圧の問題もあるし、お魚さんて結構強いんですね。 |
ISO14001の目次にもどる