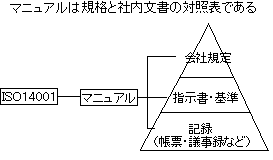���傤�����l���炨�ւ�������������B�i2009.03.20�j
����Q���܁A�����b�ɂȂ�܂��B���傤�����ł��B
�����Q���ԁA���ЍH���ISO9001�T�[�x�����X�R���ɃI�u�U�[�o�[�Ƃ��ė�������Ă��܂����B�����͖����Ȏ��ł���(?)�A�I�u�U�[�o�[�̕��ۂŎv�킸�R���Ɍ�������ł��܂��܂����B
�R�F�����č��v���O�����͂���܂����H
�S�F�͂��A����ł��B
�R�F����͍���̓����č��̌v�揑�ł��ˁB����̓v���O��������Ȃ���ł��B
�S�F�H�H�H
�R�F�v���O�����͂R�N���x���̊č������v��ŁA�u�č����j�v�ɂȂ���̂ł��B
�E�E�E���ɂ͔������͖����̂ł����A�v�킸�E�E�E
���F����A�`���b�Ƌ����Ă��������B�č��v���O�����̒�`�������Ă��������B
�R�F����႟�AISO19011�ɒ�`����Ă��܂��̂ŁA��������Ă��������B
���F���ႠISO9000�Ƃ������ł��ˁB�v�킸�R��������l�̒�`���Ǝv���Ă��܂��܂��āE�E�E�B
�u����̖ړI�Ɍ������A���߂�ꂽ���ԓ��Ŏ��s����悤�Ɍv�悳�ꂽ��A�̊č��v�ł���ˁH
�R�F�����ł��B���߂�ꂽ���Ԃ͒����v����Ӗ����܂��B�܂��P�N�ł��ǂ��̂ł����A�ł���R�N���炢�̓����č��ƒ���O���R�����܂߂܂��B
���F�i���C���C�j�u����̖ړI�Ɍ������v�Ȃ̂ł����A�����v��ŁA�����������E�O���R�����܂߂����̂̊č��ړI�Ȃ�č���ł��Ȃ��ł��傤�H
�R�F�ړI�Ƃ����̂͊č��̒����̊č����j�̂��Ƃł��B
���F�č��̎�ނ�A�č����ʂȂǂɂ���āA�č��ړI���ς��ł���H
�R�F���̂Ƃ��̓v���O������ύX���Ă��������B
�Ă����Ƃł��̐R�����A�č��ړI(=purpose)�́w�ړI�x�����ړI(=objective)�́w�ړI�x�Ɠ����Ӗ��Ɏ���Ă��܂��B������w�R�N�̒����v��x�����ā@�i�O�O�G
���������r���[�͗ǂ�����܂���B�ǂ����Ȃ�u�č��ړI�Ƃ́A�č����j�Ɛ�������S�ʓI�Ȋč��̓��B�_�v�ƌ����ė~���������ł��ˁB
�ƂȂ�ƂP�N�̊č��v��́u�č��ڕW�v���Č����낤���H�H�H�@�i�j
���̌�̉�b���������Ȃ������̂͗e�Ղɂ��z���ł���ł��傤�B
�܂��A�R�����o����x�����Ă���R�����Ԃ��K�i���߂̃o�g���Ŏg���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ň���������܂������A�ォ��ڐ��Ŏ����̋K�i���߂𐺍��ɍu�`����͎̂~�߂Ă��炢�����ł��˂��B�E�u�ȒS���҂��u���Ă��܂��܂�����B
|
���傤�����l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B
�u���ړI�Ƃ�3�N�̒����v�悾���`�v�Ƃ̂��܂킭�Ƃ������A�ǂȂ�܂���R�����͂�������q�����Ă���܂����A�č��v���O������3�N�X�p���ŕK�v�Ƃ͏����ł������܂��B
�����ƐV�����č��̗��_�ł��J�����ꂽ�̂ł������܂��傤�B�@

�Ƃ����Ă��܂��Ƃ����܂��ł�����A���̂��傤�����l���璸���������������ȃl�^���x�݂̓��A1���l���Ă݂܂����B
�����Ł`���B
�Ɠ��Ƃ���������ł���ׂ���H�ׂ���A�����|�������Ă��ē��ɕ����ϑz�����������ł��B�@

�č��v���O�����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��Ƃ�����ISO9001�{���ł͒�`����Ă��܂��A2000�N�łł�2008�N�łł�ISO9000�����p���Ă���AISO9000�F2006�@3.9.2�ł͎��̂悤�ɒ�`���Ă��Ă��܂��B
|
�y�č��v���O�����z����̖ړI�Ɍ������A���߂�ꂽ���ԓ��Ŏ��s����悤�Ɍv�悳�ꂽ��A�̊č�
|
������ISO14001�F2004�ł͊č��v���O�����͒�`����Ă��炸�A�܂����p�K�i�͂���܂���B�킸���ɂƂ������A14001�̃A�l�b�N�X�́u�Q�l�v��ISO19011���Q�Ƃ��Ă��邾���ł��B���̏ꍇ�AISO14001��4.5.5�̊č��v���O������ISO9000�̒�`�̊č��v���O�����Ȃ̂ł��傤���H�@���Ȃ݂�ISO9001�ł͖{����ISO19011�܂ŎQ�Ƃ���Ƃ���܂��B
�܂�����Ȃ��Ƃ��l����ƁAISO9001��ISO14001�̊č��ɑ��錵�����̈Ⴂ���ĂȂ�ł��傤���H�@���邢�͂ǂ����ĂȂ̂ł��傤���H
�i���}�l�W�����g�V�X�e���ɂ����Ă͊����������č����d�v���ƍl���Ă���̂ł��傤���H�@���邢�͕i���č��Ƃׂ͍������Ƃ܂Œ�߂Ȃ��Ƃł��Ȃ��̂��A�č��͂ł��Ă�������傫���Ȃ��Ďx�Ⴊ����̂ł��傤���H
�K�i�S�̂Ɍ����邱�Ƃł����AISO14001���肳�ꂽ�����͑�l�̋K�i�Ǝ��̂��Ă����悤�ɁA9001�ɔ�ׂĔ��R�Ƃ��Ă��āA�����č��Ɍ��炸���܂�ׂ����K�肵�Ă��܂���B
����͌ڋq�Ƃ�����̓I�ȗ��Q�W�҂ɕi���ۏ���Ƃ������ƂƁA���Ƃ��������܂��ōL���͈͂�ΏۂƂ��邱�Ƃ̈Ⴂ�Ȃ̂ł��傤���H
�Ƃ����Ă��č��v���O������
����̖ړI�Ɍ������A���߂�ꂽ���ԓ��Ŏ��s����悤�Ɍv�悳�ꂽ�Ƃ������Ƃ���ŁA��ʌ�Ƃ��Ă̊č��v���O�����ȏ�̏����Ȃ��A�܂��Ӗ�����͈͂����肷����ʂ��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�ǂ��ǂ�ł��A�v��̊��Ԃ��ǂݎ��܂��A�č����j�Ƃ��قȂ�悤�Ɏv���܂��B
�Ƃ���ŔF�؋@�ւ́A�F�؊��Ԃł���3�N�Ԃ͈̔͂ŔF�͈ؔ͑S�̂�R������v��𗧂ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��悤�ɓǂݎ��܂��B�i�Q�ƁF�K�C�h62���K�C�h66�AJAB�@RE300�Ȃǁj
����͐R���͔������ōs�킴��Ȃ����A�����T�C�N���̒��ł͔F�͈ؔ͑S�̂����邽�߂ɂ�������������������̂ł��傤�B
���̐R�����͒P�ɔF�؋@�ււ̗v���������g�D�ɂ��K�p�����Ɗ��Ⴂ���āA3�N�Ԃ̌v�悪�K�v�ƌ������̂�������܂���B�������Ƃ���Ƃ��܂�ӂ߂�̂������܂���B
�������Ȃ��玄�͂����v���̂ł����A�K�i�ł����Ƃ���̊č��v���O�����Ƃ������̂���������ƍ��肵�Ă���g�D���Ă���̂��낤���H�Ƃ������Ƃł��B
|
�����ƁA���傤�����l�̂Ƃ���ɂ͂������肵���č��v���O���������݂��邱�ƂƎv���܂����E�E
|
���̌��������Ă��鑽���̉�Ђ̊č��v���O�����Ƃ����̂́A�c���Ɋč��P�ʂ̑g�D���L���A�����Ɋč��ʒm�A�č����ł����킹�A�č��̎��{�A���쐬�A�o�c�҂ւ̕E�E�E�Ȃ�ă}�g���b�N�X������āA�}�X�ڂɗ\��������āA�v��̐i���ɍ��킹�Đ��ߍ���ł������̂ł��B
���ꂶ�Ⴀ�A
�č��̑ΏۂƂȂ�v���Z�X�y�ї̈�̏�ԋy�яd�v���A���тɂ���܂ł̊č������iISO9001)�Ƃ��A
����̏d�v���y�ёO��܂ł̊č��̌����i14001�j�Ȃǂ́A���̕\�́A�ǂ��ɁA�ǂ̂悤�ɐ��荞��ł���̂ł��傤���H
���́E�E�Ό���������܂��E�E�č��v���O�����Ƃ͊č��̕��j�Ƃ��P�Ȃ�X�P�W���[���Ǘ��ł͂Ȃ��A�č��̐v�}�ƍl���Ă��܂��B
���̕���ł͑O��Ȗ�肪�������A�������ȃg���u�����������A���̗v�f���č����邽�߂ɂ͂������������m�����K�v�����炻�������č������A�T�C�����Ȃ���E�E���X�荞���̂��č��v���O�����ƍl���Ă��܂��B
�����Ă��傤�����l�̌����Ƃ�����ƈႢ�܂����A�u�O��܂ł̊č��v�̌��ʂƂ������̂́A�����č������ł͂Ȃ��A�O���č��i��Ҋč�����O�Ҋč��j���܂ނƎv���܂��B���ɊO���č����u�č��v�Ɋ܂܂Ȃ��Ƃ��Ă��A���̊O���č����ʂ͉ߋ��̕s�����_�ɓ���ł��傤����A���̌��ʂ��t�H���[���邱�Ƃ͓��R�̂��Ƃł��B
�܂�A�u���ꂩ��̊O���č��̗\��v�荞�ޕK�v������̂ł͂Ȃ��A�u�ߋ��̊O���č��̌��ʁv�荞�ޕK�v������ƍl���܂��B
���ꂩ�猾�����Ƃ́A�����ߋ��Ɍ���Ă��邱�ƂƖ������邱�Ƃ�F�����Ă��܂����A�܂����������������B
�����č��Ƃ������̂͋K�i�v�������Ƒg�D�̌v���d�g�݂ւ̓K������������̂ł͂���܂���B�����č��Ƃ́A��č�����̖������o���ĉ�Ђ�ǂ����邽�߂̔C���ł��낤�Ǝv���܂��B
�ł����炻�̑�ړI��B�����邽�߂́A�����č��̒����r�W�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���N�͓K�������d�_�Ɍ��āA���N�͎d�g�݂̉^�p�����Ȃ����A���邢�͎d�g�݂���Ђ̕����ɍ����Ă���̂������悤�A�O�N��ɂ̓p�t�H�[�}���X�����サ�Ă��邩�����悤�Ƃ�����ł��B
|
�V�X�e���̗L�����Ȃ�ăP�`�Ȃ��Ƃł͂���܂���B��Ђ͍ŏI�I�ɂ͕i���A�R�X�g���̑��̃p�t�H�[�}���X�����P���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
|
���������X�^���X�œ����č����v�悷��ƁA�K�R�I�ɂ�����x�����r�W�����������A���N�̊č��v���O�����͂�����u���[�N�_�E���������̂ƂȂ�܂��B�����łȂ���s�������������ŁA��Ђ��p���I�ɉ��P���Ă������̂ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���邢�͉i���ɋK�i�K�����i�L�������܂߂��j�̃`�F�b�N���J��Ԃ������ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�v�揑�Ƃ����Ă��l�ɂ��������Ⴂ�܂��BISO9000�ł́y�č��v��z��
�č��̂��߂̊����y�ю�z���������������Ƃ��Ă��܂��B�Ƃ���Ły�č��v��z�Ɓy�č��v���O�����z�̊W�����܂����킩��Ȃ��̂ł����A���͊č��v��Ƃ͊č��v���O�������\��������̂ƍl���Ă��܂��B
�Ԉ���Ă����狳���Ă��������B
���͓����č��ł͂���܂��A��Ҋč�������̎d���ł��B�ł����邱�Ƃ͓����ł��傤�B�ЂƂ̉�Ђ��č�����ɓ����莖�O�����Ƃ��v�悷�邱�Ƃ͎R�قǂ���܂��B
���̉�Ђ̏��܂�A�Ǝ�ƑԁA�K�́A���ݒn�̏��A�ߋ��̊č����ʁA�ߋ���ISO�R�����ʁA���̂�N���[���̏E�E���ڍׂȏ�K�v���ۂ��A�K�v�Ȃ牽�����܂łɎ��W����̂��A���O���n�������K�v���A���܂�h���߂��ɂ���̂��ۂ��Ȃǂł��B�悭����8���Ƃ��i���W���ƌ����܂����A�����W�ɂ���Ď��ۂ̎d���̐��ʂ��������傫���ς��܂��B
�������������̂��W�߂邱�Ƃɂ���Ċč��v��͕K�R�I�Ɍ��܂��Ă��܂��B�č����Ƃ��Ăǂ�Ȏ��i��o�����K�v���A������́A�����Ă������̂��ς��ł��傤�B�ꍇ�ɂ���Ă͊č��̎��ԑт�ς�����A�����v���������A�Ƃ��܂��܂Ȃ��Ƃ����Ȃ���Ȃ�܂���B���͂���Ȃ��Ƃ�����1�N���߂����Ă���̂ł��B
|
����́A�܂��ɓ���̖ړI�Ɍ������A���߂�ꂽ���ԓ��Ŏ��s����悤�Ɍv�悷�邱���A�y�č��v���O�����z���̂��̂ł��B
|
�������܂��ƈ�N�Ԃɍs�������̊č����ꖇ�̕\�ɂȂǂł��܂���B
�ЂƂ̉�Ђɑ��čs���č��̌v�揑�i�v���j�����ł����y�[�W�ɂ��Ȃ�܂��B
�܂�Ȃ����Ƃł����A��ʋ@�ւ̗\��h����z�A���S�C���ƕ��̗v�ۂ�����܂��B�c�ɒ��ł��ƒ��т�H�ׂ�Ƃ�����m�ۂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�w�O�Ƀ^�N�V�[�����Ȃ���������Ȃ��̂ł��B�������������Ƃ��v��Ɋ܂߂Ȃ���Ίč��͏����ɐi�܂Ȃ��̂ł��B�ςɕ������邩������܂��A�č��̃`�F�b�N���X�g�Ȃǂ��A�d�Ԃ̎����\�̕����d�v��������Ȃ��̂ł��B
|
�ŋ߁A�����g���L���Ɋč��ɍs�����Ƃ��A�L����`�ł̔�s�@�ƃ����W���o�X�̏��p�����Ԃ��Â����āA1�{�o�X�ɏ��x��ė\�莞���ɒ����Ȃ��������Ƃ�����܂����B�܂��ɒp�ł��B�T�����C�Ȃ畠���˂Ȃ�܂���B
|
����ł͂ǂ��Ƃǂ�������̂��A�L�^�⒠�[�͉����ǂ̂��炢�̔������E���邢�͑S����������̂��A������葊���N�ɂ���̂��A�O��̃t�H���[���ǂ����邩�A�h������č�������̉������̐l�Ȃ�ł���̂��Ƃ������Ƃ��������Ȃ���Ȃ�܂���B
�����������č��v�揑�i�v���O�����j�͂������p�^�[�����͂ł��܂����A���e�͉�Ђ��ƁA�H�ꂲ�ƂɑS���قȂ�A���p�͂ł��܂���B
�����Ċč��v���O������������������A�č��̃`�F�b�N���X�g�ɐi�݂܂����A����͂����@�B�I��ƂƂȂ�܂��B���̓`�F�b�N���X�g�Ƃ������̂��d�v�Ƃ͎v���Ă��܂���B�d�v�Ȃ͉̂���ړI�ɉ������邩�����������肷�邱�Ƃł��B����͂܂��Ɋč��v���O�������Ǝv���܂��B
|
�ǂ��č��`�F�b�N���X�g������Ηǂ��č����ł���Ȃ�Č����l�����܂��B����Ȃ��Ƃ������l�͎��ۂɊč����������Ƃ��Ȃ��l���Ǝv���܂��B�A�C�\�X���Ȃǂœ����č��ɂ��Č���Ă���l�������ł����A���͏����o����20�s���ǂނƁA�{���Ɋč������Ă���̂��A���邢�͌`�����̊č������Ă���̂�����܂��B
�����č��̖{�Ɋč��`�F�b�N���X�g�Ȃǂ��t���Ă��܂����A����͖{���Ƀ`���[���S�җp�ł����āA��x�ڈȍ~�g������̂ł͂Ȃ��ł��傤�B�Ƃ͂����A�����������`�F�b�N���X�g��10�N�ԓ����č������Ă����Ђ������グ�Ă���܂����E�E
|
���Ď��ۂ̊č��̒i�K�ƂȂ�ƁA�č������ǁi�܂莄�j�́A�f��ēƎ����悤�Ȃ��̂Ŕo�D�Ƌr�{���ł����킯�ł�����A���Ƃ͂��̔o�D�̉��Z�Ɋ��҂��邱�ƂɂȂ�܂��B�܂����č��̌���Ŋč������w���ēA���B���シ��킯�ɂ͂����܂���B�����č����̗͗ʂ��Ȃ��Ċ��҂ɉ����Ȃ���A���̐l���A�T�C�������Ȃ̐ӔC�ł����A�v�揑�����n�������Ƃ������Ƃɂ����܂���B
|
���Ⴂ���Ȃ��łق����̂ł����A���͂�������イ���s�����Ă���܂��B���̐l�Ȃ�Ǝv���Ĕh�����Ă����҂ɉ����Ă���Ȃ��Ƃ��A�v�悵���������ڂ��������ė\�莞�Ԃŏ����ł��Ȃ������Ƃ��A�Ȃ̖��n��p�����ł��B
|
�܂��č��Ƃ�ISO�K�i�ɂ��邩��Ƃ��A�K�i�ł�����߂Ă��邩��A��������ׂ����Ȃǂƍl���Ă͂���܂���B
�����č����A���̉�Ђ̎d�g�݂�̐��̂ǂ̈ʒu�ɂ���̂��ɂ���āA���܂���̂Ǝv���܂��B���č��ł���i���č��ł���A������Ɩ��č��̈�ł���ׂ��Ƃ����̂����̎��_�ł��B�����l����ƁA�K�i�ɂǂ����낤�ƁAISO�R���������ƌ������Ƃ�����L�ۂ݂ɂ�����A�C�ɂ��邱�Ƃ͂���܂���B�킪�ЂŕK�v�Ƃ�������č��̏���������A��������ׂ������č��̎d�g�݂����݂���̂ł��B�ł�����킪�Ђ̓����č���ISO�K�i�����Ă��邱�Ƃ��������Ηǂ��̂ł��B���͂���Ȃ��Ƃ��l���邾���łȂ��A����������ɏ��荇�����Ƃ��͐R�����ɂ���������������������Ă���܂��B�Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ��R���������č��邱�Ƃ�����܂����E�E

�Ԃ�������������l���炨�ւ���܂����i09.03.21�j
�R�F�v���O�����͂R�N���x���̊č������v��ŁA�u�č����j�v�ɂȂ���̂ł��B
�������w�E�ł��ˁ[�BISO19011�͋K��v�������������̂ł��ˁB�m��܂���ł����B
�������̕����E�`��R��������A�����Ɓu�d��ȕs�K���v�����o���邱�Ƃł��傤�B
�R�u�����č����̋���P���Ǝ��i�F��̎菇����߂��Ă��܂���v
�R�u�����č������K�i�v�������Ƃ̓K�������m�F���Ă��܂���v
�R�u�����ۂ̓����č����ے����炪�s���Ă��܂��v
�Œ�ł����̂R�͊m���݂����ł��B
�E�`�ɂ͓����č������x���̂�����܂��A����ɊǗ��E�������č������Ă��܂����A�K�i�[�̓��e��m��܂���B
�Ƃ���ł����s�v�c�Ɏv���̂ł����A���Ԉ�ʓI�ɂ͂��炩���ߐR�����̖ʐڂƗ͗ʕ]���͂��Ȃ����̂Ȃ̂ł��傤���H
|
|
�Ԃ�������������l�@���x���w�����肪�Ƃ��������܂��B
���Ђɂ������č������x������܂���B�Ƃ������ȑO�͂������̂ł��������S�������Ƃ��ɔp�~���܂����B�����Č����Ίč����̗͗ʂ����邩�ۂ��������Č��߂܂��B
�����ĒN�ɂ����Ċč����̗͗ʂȂ�Ă킩��܂���BISO�K�i�Ȃ�Ēm��K�v�͂���܂���B��������Ђ̕����A��ЋK����m��s�����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł��B
����ƃR�~���j�P�[�V�����\�͂ł��B�R�~���j�P�[�V�����āA���ނƂ��S���t�Ƃ��J���I�P�ł͂Ȃ��ł��B�l���Ă��邱�Ƃ���₷���b�����ƁA�l�̘b����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃł��B
�����Ɓ������ɂ����������\�͂̂Ȃ������E�E�E
����F�������ɓ����͉����H
���Ԉ�ʓI�ɂ͂��炩���ߐR�����̖ʐڂƗ͗ʕ]���͂��Ȃ����̂Ȃ̂ł��傤���H
���̂˂��`�A����Ȃ��Ƃ����Ⴀ���Ⴀ�Ƃ���̂͂����������炢�����Ă�
|
���傤�����l���炨�ւ���܂����i09.03.22�j
���傤�����ł��B
�Ԃ�����������[���܁F
�R�F�v���O�����͂R�N���x���̊č������v��ŁA�u�č����j�v�ɂȂ���̂ł��B
�������w�E�ł��ˁ[�BISO19011�͋K��v�������������̂ł��ˁB�m��܂���ł����B
�������̕����E�`��R��������A�����Ɓu�d��ȕs�K���v�����o���邱�Ƃł��傤�B
����͎w�E�ł͂Ȃ��A�e�ȐR�����l�ɂ��u�L����w���v�ł��B
������s�K���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B
����Q���܁F
���̐R�����͒P�ɔF�؋@�ււ̗v���������g�D�ɂ��K�p�����Ɗ��Ⴂ���āA3�N�Ԃ̌v�悪�K�v�ƌ������̂�������܂���B
��l�̔��f�ł��ˁB
�R������ł͓��Ɍ�������Ă��܂������A�m���ɂ��̂悤�ɍl����ƕ�����Ȃ��ł��Ȃ��ł��ˁB
�Ƃ���ł��p���܂Ǝ��́u�č��v���O�����v�̑������������X�^���X���Ⴄ�悤�Ɋ����Ă��܂����B
�y��v���O�����z
����̖ړI�Ɍ������A���߂�ꂽ���ԓ��Ŏ��s����悤�Ɍv�悳�ꂽ��A�̊č�
���낢��C����͕t���Ă��܂����A�Ō�́w�č��x�ŏI����Ă��܂��B
�����ł��B�w�č��v���O�����x�́w�č��x�ł���܂��B
�܂�A�u���̊��Ԃœ����ړI�ipurpose)�Ŏ��{����i�����j�č��̏W�܂�v�ł��B
�E�E�E�����Ŋč��Ƃ����ƁA�v��`���{�`�`�t�H���[�A�b�v�ȂLj�A�̊����ł����āA�v�揑�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂������E�E�E
�y��z
�č������������Ă�����x�肷�邽�߂ɁA�č��؋������W���A������q�ϓI�ɕ]�����邽�߂̑̌n�I�ŁA�Ɨ����A���������ꂽ�v���Z�X
�Ƃ������Ƃ́A
�w�č��v���O�����x�́w���������ꂽ�v���Z�X�x��������ł��ˁB���C�t���܂����B
������
�y���L�z�č��v���O�����́A�č����v�悵�A��z���A���{����̂ɕK�v�Ȋ����̂��ׂĂ��܂�
�Ƃ���܂��B�w�č��v���O�����x�Ƃ͂ǂ���炨��Q���܂����Ă���悤�Ɋč����s�Ȃ��̂ɕK�v�ȃR�}�S�}�������̑S�Ă��܂݁A�������̕K�v������悤�ł��B
�y�č��v��z�Ɓy�č��v���O�����z�̊W�����܂����킩��Ȃ��̂ł����A���͊č��v��Ƃ͊č��v���O�������\��������̂ƍl���Ă��܂��B
�����ł��B�������̒��x�͑g�D�ɂ���ĈقȂ��Ă��ǂ��̂ł��傤����A�u�č��v���O�����v�́u�č��v��v�̕����������������Ă���Ƃ����̂��A���ł��傤���A�P�Ȃ�X�P�W���[�������ł����Ă��ǂ���Ȃ��ł��傤���B |
|
���傤�����l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B
�����Ȃ�ł��A�O����^��Ɏv���Ă����̂ł����A
�y��v���O�����z
����̖ړI�Ɍ������A���߂�ꂽ���ԓ��Ŏ��s����悤�Ɍv�悳�ꂽ��A�̊č�
�Ȃ���u�č��v���O�����v�́u���̊��Ԃœ����ړI�ipurpose)�Ŏ��{����i�����j�č��̏W�܂�v�Ȃ�ł��傤���H
�u�č��v�Ƃ͈ꕔ��ɑ�����̂ł�����ЂƂӂ��Ɛ�����̂ł��傤���H�@���͂��Ƃ��u2009�N�x�ɍs���č��S�́v�ň���Ǝv���Ă��܂����B�����ĐR�����̎��ѕ����Ĉ�A�̊č��ň��Ɛ����܂��B
������Ƃ��̂�����̍l����������܂���B
�܂������Ȃ��Ƃ������A���ɂƂ��Ă͂ǂ��ł��������Ƃł����E�E
|
�Ԃ��炭���������l���炵�傤�����l�ɉ��܂����i09.03.23�j
���傤�����l
����͎w�E�ł͂Ȃ��A�e�ȐR�����l�ɂ��u�L���w���v�ł��B
������s�K���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B
�ȁ[��قǁA�u��w���v�ł����B�u��w���v�Ȃ�l�I�ɂ͑劽�}�ł����B�@ 
���̐R�������́A�����č����������ʂȂ��̂ƍl���āA�����ɐV���ȉ��l�ς���߂������������Ƃ��Ă���悤�ł��ˁB
�����v���ɁA�������������č��Ȃ�Ă��̂́A�ӎ������Ƃ������K���E��ōs���Ă�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�s�Ǖi���o��A���邢�͐ݔ��g���u������������A�ӔC�҂͌���ɔ��ł����A�菇�ʂ�ɍ�Ƃ���Ă����̂��A��߂�ꂽ�菇�ɕs�����Ȃ��������Ƃ��������_�ŏ̊m�F�ƌ����ׁA���}���u������Ƌ��ɑ��Y���ď�i�ɕ��܂��B������O�̍s���ł����A���ꂾ���ē����č����Ⴀ��܂����Ǝv���܂��B
�����Ɂu3�N�Ԃ̕��j������܂���v�ƌ����Ă�����܂��ˁ[�B
�������A������������Ǘ��ɑ�������č������łȂ��A�Ⴆ�Όo�c�҂̕��j���ǂ��Z�����Ă��邩�A�o�c�ڕW�̒B����͂ǂ�������������č������Ă���܂��B���`�ɂ́i�Ƃ��������Ԉ�ʂł́j�A���ꂪ�����č��ƌĂ�Ă���̂�������܂���B
������ɂ�������č��͎����̂��߂ɂ���Ă���̂ł����āA�R���ŋL�^�������邽�߂ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ��A�Ǝ��͎v���܂��B
�u�����č��v��v�Ɓu�����č��v���O�����v�̊W�ɂ��Ă��܂�[���l�������Ƃ͂���܂��A�u���̂��߂ɁA����ړI�Ƃ��āA�������҂��Ă��̂��v���܂����肫�ŁA��������Ɂu���A�N���A�ǂ��ŁA�ǂ�����Ă��̂��v�����܂�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
������ǂ������悭����Đ��ʂ������o�����ɂ��āA�����R�������I�m�ȃA�h�o�C�X�������Ă����̂Ȃ���Ŏ����X���邱�Ƃł��傤�B
���Ȃ݂ɁA�E�`�̓����č��v�揑�ɂ́u�č��̖ړI�v�Ɓu�d�_�č������v�Ƃ�����������܂��B�R�����������ɂ͒����������ł��B�ł��A�u���̂��߂ɁA����ړI�Ƃ��āA�������҂��Ă��̂��v�Ƃ��������č��̑z�����č��`�[���Ɣ�č������ɓ`���邽�߂ɂ͕K�{�̎����ł��B�����Č����A���ꂪ�č��v���O�����i���͂��̈ꕔ�j��������܂���B
|
|
�Ԃ�������������l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B
����30�N�ȏ�O�ł����A���������Ă����E��Ŗ�肪�N�����A���̌����Nj����č��Ə̂��čs���܂����B���ꂪ���Ɗč��Ƃ������̂̕t�������̎n�܂�ł��B�����������Ƃ���l����ƁA�E�E���ꂾ���ē����č����Ⴀ��܂����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂ɂ܂����������ł��B
���_�ŋ��k�ł����A�����č��Ɍ��炸�ł����lj�������Ɂu�K�i�K�����ǂ����v�ł͂Ȃ��A�u����͉�Ђɖ��ɗ��̂��v�Ƃ����ϓ_�ŋᖡ���Č������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
|
���傤�����l���炨�ւ���܂����i09.03.24�j
���傤�����ł��B�Ԃ�������������l�A���Ԏ��L��������܂��B
�����v���ɁA�������������č��Ȃ�Ă��̂́A�ӎ������Ƃ������K���E��ōs���Ă�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�s�Ǖi���o��A���邢�͐ݔ��g���u������������A�ӔC�҂͌���ɔ��ł����A�菇�ʂ�ɍ�Ƃ���Ă����̂��A��߂�ꂽ�菇�ɕs�����Ȃ��������Ƃ��������_�ŏ̊m�F�ƌ����ׁA���}���u������Ƌ��ɑ��Y���ď�i�ɕ��܂��B������O�̍s���ł����A���ꂾ���ē����č����Ⴀ��܂����Ǝv���܂��B
���ނށA���͖������̈�ɂ͓��B���Ă��܂���˂��B(-_-;)
���n�҂̎��ɂ͂���͐������u�̂悤�Ɏv���܂��B
�ȑO�A�H�꒷������������Ƃ��A�~�[�e�B���O�ŏ��q�A�����O����Ȃǂ̓���Ɩ�������č��̈ꕔ�ɂ��悤���Ƃ��v���Ă��܂������A���̕ӂ�8.2.3�v���Z�X�̊Ď�����Ƃ��������A�n�}��悤�ȋC�����܂��B
���ǁA�����č����v���Z�X�̊Ď�����̈ꕔ���Ƃ����l���ɂȂ�܂����B
�܂��A�K�i�̉��߂⌾�t�̒�`�͒u���Ƃ��āA���ǂ̂Ƃ���u��Ђɖ��ɗ����Ȃ���ΈӖ��������v���Ă��Ƃł���ˁB
���Ȃ݂ɁA�E�`�̓����č��v�揑�ɂ́u�č��̖ړI�v�Ɓu�d�_�č������v�Ƃ�����������܂��B�R�����������ɂ͒����������ł��B�ł��A�u���̂��߂ɁA����ړI�Ƃ��āA�������҂��Ă��̂��v�Ƃ��������č��̑z�����č��`�[���Ɣ�č������ɓ`���邽�߂ɂ͕K�{�̎����ł��B�����Č����A���ꂪ�č��v���O�����i���͂��̈ꕔ�j��������܂���B
�����d���Ă�������č��̌v�揑���u�č��̖ړI�v�Ɓu�d�_�|�C���g�v�͕K���L�ڂ��Ă��܂��B
���������A�����������Ɩ��n�ȍ��iISO19011���s�O�̂��Ƃł��j�ɁA�č����Łu�č��ړI�v�ɑ��āu�č����_�v�̐��������C�}�C�`�ł��˂ƓƂ茾�������R���������܂����B
�����A�����č���PDCA�ł̌p���I���P���K�v�ȂƐg�������ċC�t�����Ă��炢�܂����B
�����I�����Ȃ�ƁAPDCA�̖ڎw�������Ƃ��ē����č����j���K�v�����B�i�O�O�U
|
|
�Ǘ��l�ł��B������X�~�}�Z���B
�č��Ƃ������͖̂|���ł��B���audit�ŕ������Ƃ������Ƃł����Â����̂ł͂Ȃ��A��蒲�ׂƂ����j���A���X���Ǝv���܂��B
���X�̔��˂͉��l�̎g�����g����S�����������m�F����t���l�̂��Ƃ������ƕ����܂����A���{�ɂ��ڕt�Ƃ�����ӂ��ԈႢ�Ȃ��`���������m�F���邽�߂ɂ��Ă�����ڂ�����܂����B�Ƃ������ƂŁA�q�ϐ��Ƃ��������Ȃ�Č�����O����A�č��Ƃ������̂͂������Ƃ����܂��B�B
�ł�����č����������u�̏ꍇ������Ƃ������A�s����������ꍇ�č����s����Ƃ������ƁE�E�Ⴆ�A�ߋ��ɌR���ł̍��~�X�A���Y�}�̓����R���Ȃǂō���Ƃ����̂͂���܂����B���������̂Ɗč��Ƃ������̂̍��͈ꏏ�ƌ�����ł��傤�B
�č��ƕ����A�����̐l�͉�v�č��̂��ƁA�����̐l�͈�����\���Ɩ��č��Ȃǂ��v�������ׂ�ł��傤�BISO�K�i�ŋK�肷��č��̕�����ʓI�ȈӖ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����āA��Ђ�ǂ�����A���邢�͈����Ƃ�������o�ł���l�A���č��̐ӔC����l�ƂȂ�ƁA��Ђ̏㋉�Ǘ��҈ȏ�łȂ��Ɩ����ł��傤�B
ISO�̒�`�Ƃ��K��v�������ɂ�����邱�Ƃ͑S���Ȃ��Ǝv���܂��B
|
�Ԃ�������������l���炨�ւ���܂����i09.03.25�j
�Ƃ��܂��ƁA�����ȑg�D�ŁA�Ǘ��҂łȂ��v��������č����ɔC����ISO���C�����������č��v���O�������쐬����Ƃ�����l�ȃp�^�[����ISO�R���ŋ��߂���̂͂�͂肨�������ł��ˁB
�O�i�_�@�͂��Ă����A���͕ʂ̐�����炻����u���������v�Ǝv���܂��B
�@�Ǘ��҂łȂ��v��������č����ɔC�����邱�ƁB
�AISO���C�������邱�ƁB
�B�����ȑg�D�ł���Ȃ�������č��v���O�������쐬���邱�ƁB
�C������ISO�R���ňÂɁi�Ƃ��ɂ͖��m�Ɂj���߂邱�ƁB
�@�{���A�č��Ƃ������̂́A���i��g�D�̊����ɉ��P��v������_���Ȃ����ǂ����ׂ邱�Ƃ��ړI�̂͂��ł��B�ł���A���ꂪ�ł��闧��Ɣ\�͂��������l���č������Ȃ���Ȃ�܂���B�ʏ�A����͊Ǘ��E�̐l�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��A���������\�͂ƌo��������Ă��邩��Ǘ��E�߂Ă���͂��ł��B�i�������A��Ǘ��E�̐l�ɂ͂���ȗ͂�����킯�Ȃ��ƌ����Ă���̂ł͂���܂���j
�܂��A�Ȃ��킴�킴�u�����č����ɔC���v����K�v������̂����킩��܂���B�C���Ȃǂ��Ȃ��Ă��u�Ǘ��E�����邱�Ƃɂ��Ă��܂��v�ł����͂��ł��B
�A��ɏ������č��̖ړI���ʂ�����ŁAISO�K�i�̉��߂Ƃ���Ɋ�Â����s�K�������E���쐬�̂������K�v�ƂȂ闝�R���킩��܂���B
ISO�K�i�[�Ȃnj������Ƃ��Ȃ��Ă�����͂ł��܂��B���������A�ǂ��ɂǂ�Ȗ��_������ł��邩��k���t����{���\�͂Ǝ��W�������̕��͗́A�������̃q���g���l����v�l�͂�{���悤�ȃJ���L�������ɂȂ����u�����č����{���u�K�v�Ȃnj������Ƃ�����܂���B�ʏ�A�����������j���[�́u�����Ј��{���u�K�v�Ƃ����������ނ̂��̂ł��B
�B�����č��v���O�����ȂǂƏ�������Ƃ��Ђ˂���o�����Ƃ��A�Ƒ������ł���Ă��鏬���ȉ�Ђł����Ă��i�o�J�ɂ��Ă���̂ł͂���܂���j�A�����č��Ȃ�đn�Ǝ��������Ă܂��B���ꂱ����������Ă܂��B
�}�l�W�����g���r���[�ɂ��Ă������ł����A�Ȃ��u�����č��v�Ƃ����Ɖ������ʂō����Ȃ��̂Ƃ��Đg�\����̂ł��傤���B
�C�F�؋@�ւ́A�o�^�g�D�ɑ��ĐR���̐^�����̂悤�ȃX�^�C���Łu�����č��v���邱�Ƃ��Âɋ��߂܂����A����𒉎��ɂ�邱�Ƃőg�D�Ƀ����b�g��������ƃz���L�Ŏv���Ă���̂ł��傤���H
�����{���ɂ����v���Ă���̂Ȃ�A�A�z�ł��B
�ȏ�̂��Ƃ���A�u���������v�Ǝv���܂����B
|
|
�Ԃ�������������l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B
�Ԃ�������������l���������AISO�Ɋւ���Ă����ʐl�́A�R�������܂߂āA�R���̐^�����̂悤�ȃX�^�C���Łu�����č��v���邱��������ׂ��p�ł���ƍl���Ă���̂��ǂ������ł͂Ȃ��A���ꂪ�����̂悤�ł��B����́A���������l�̂����悤�Ɏ��͂̂���Ǘ��҂������č��s���Ȃ��Ƃ��ɁA�����łȂ��l���Ȃ�Ƃ��č����s�����@������ł͂Ȃ��ł��傤���H
���ꂩ��ISO���C�����������č��v���O�������쐬�������Ƃ������Ƃ�������ς���ƁA�Г��ŊǗ��ҋ��炷��̐����Ȃ��Ƃ��A�������u�̕��@�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����ꍇ�A�ЊO�̓����č���������Ǘ��Ҍ��̋���Ƃ��Ďg���Ă���Ƃ��v���܂��B
�����l���܂��ƁA�����ȑg�D�ŁA�Ǘ��҂łȂ��v��������č����ɔC����ISO���C�����������č��v���O�������쐬����Ƃ�����l�ȃp�^�[����ISO�R���ŋ��߂����̂́A��Ђ̊Ǘ����x������̂��߂̎Ј�����ɂȂ�܂���Ƃ����R�����̐e�S�����m��܂���B
|
|
�������͖{���͉����H�Ƃ܂��l����ׂ��ł��B
ISO�K�i�Łu�����č��v�Ƃ�������A�����i���č������悤�Ƃ��A�������č��Ƃ����d�g�݂���낤�ƍl���邱�Ƃł͂���܂���B
�{���́u�K�i�Œ�߂Ă��邱�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�܂�A�K�i�ɏ����Ă���悤�ɁA�q�ϐ���������ۂ������x��݂��āA��Ђ̎��Ԃ����ăg�b�v�o�c�҂ɕ���Ƃ������Ƃł��B
��������A�u������Ƒ҂Ă�A����Ȃ��Ɗ��ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ����H�v�Ǝv���A������K�i�ł��������č��ɂ��Ă͂߂�Ηǂ��̂ł��B�����ɂ������������z�Ƃ������A�A�v���[�`������ׂ��p���Ǝv���܂��B
���������āA���͂������������@�ł����ߋ�17�N��ISO�Ɗւ���Ă��Ă���܂���B
�u���Ђł͐̂��玖�Ƃ����Ă���̂�����AISO9001��14001�͖������Ă���͂����A�Y�����Ă�����̂����������Ă݂悤�B��������}�j���A�����ł�������v�ƍl����̂��܂��Ƃ��ł��B
�K�i����Ƀ}�j���A���������āA������x����菇������낤�Ƃ����̂͑傫�ȊԈႢ�ł��B
|
|
����ȊԈႦ���A�v���[�`�����Ă���l�������A�uISO�K�i�����肳�ꂽ����Ή����邽�߂ɂȂɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����H�v�Ȃ�ăo�J�Ȃ��Ƃ��l����̂ł��B
ISO�K�i���ς�낤�ƁA�ς��܂��ƁAISO�K�i�Ȃǂł���O�����Ђ͂���܂��B���̉�Ђ̃}�l�W�����g�V�X�e����ISO�K�i�������k�ŗL�@�I�Ȏd�g�݂�L���Ă���ƂȂ��l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��傤���H
����������d�������Ă��āA��Ђ̎d�g�݂�m��A��ɉ��P���Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł����H
����ISO�̗͂���ĉ������������Ƃ͂���܂���B�̂��玩���̗���łł��邱�Ƃ����Ă��܂����BISO�������Ă�����ȏ�̂��Ƃ͂ł���͂�������܂���B
|
|
�ȑO���\���グ�܂������A�}�j���A���Ƃ͉�Ђ̖{���ƋK�i�Ƃ̃C���^�[�t�F�C�X�Ƃ������A�Ȃ�����������̂ɂ����܂���BISO9001:2008�ł�4.2.2b)�Łu�i�i���}�j���A���Ƃ́j���������ꂽ�菇���͂������Q�Ƃł�����v�Ƃ���܂��B
��������������Ɖ������Ă����Ȃ��ƁA��ɖ������ƂɂȂ�܂��B
�����Ȃ�܂��ƁA�R���T���Ȃǂ������Ă���}�j���A����菇���̂ЂȌ^�Ƃ��A�ʔ̂�CD-ROM�ɂ��Ĕ̔����Ă��邳�܂��܂ȕ����̗l���́E�E���ׂĂ���܂���B
����Ȃ��̂����݂��邱�Ƃ����{��ISO���_���ɂ��Ă����̂ł��B
�����A�܂��A�h���i���������ӂ�Ă��܂����@
�A�h���i�����ɔC���āA�ʕ���lj�
ISO�����ǂƂ������̂��s�v�ł���Ƃ����˂Ă���\���グ�Ă���܂��B�������ǂ����Ă������ǂ�݂���̂��Ƃ����ꍇ�́AISO���D�����Ƃ��ڂ����҂ɂƂ��A�g�������Ȃ�����ISO�ł���点�邩�Ƃ��A���������ނ����l�̒�N�܂ł̖�ڂȂ�Ă��Ă͂����܂���B
��Ђ̎d�g�݂���Ԓm���Ă��āA��Ђ�ǂ����悤�Ƃ����l�����A�T�C������̂��őP�ŁA����ȊO�̑I���͂���܂���B
ISO�͌o�c�̎d�g�݂��Ƃ��A�}�l�W�����g���̂��̂��Ƃ����Ȃ���A���������\�͂������Ȃ�ISO�����ǂ�ISO�K�i���߂�_���A�u�߂����A���ʂƂ��ĉ�Ђ��������Ă����̂��~�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
���ɂȐl�́A�C���^�[�l�b�g��ISO�R���T���⎖���ǂ��z�[���y�[�W�łǂ�Ȃ��킲�Ƃ�����Ă��邩���Ă��������B���邢�́A�_�ɂ����ɂ�������Ȃ�������Ȃ�ISO�̕������}�j���A���ЂȌ^���Ă���̂����Ă��������BISO�����č��̌��C�Ƃ������悭��`���Ă܂����낭�Ȃ��Ƌ����Ă��܂���B
����Ȃ��Ƃ�ςݏグ�Ă��A��Ђ͗ǂ��Ȃ�܂���B�ׂ��͑����܂���B���i�i�����ǂ��Ȃ炸�A�i���ۏ��ǂ��Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
ISO���}�l�W�����g�̋K�i�Ƃ����Ȃ�A������O�̉�ЂȂ炻��Ȏd�g�݂͓���Ă���͂����B�������A����͊����ł͂Ȃ����A�����e�i���X�����Ă��邾�낤�B�������A��������������Ɣc�����āAISO�K�i�Ƃ�����{���Q�l�ɒ����ɉ��P���Ă������Ƃ����AISO�K�i�̒l�ł��ł͂Ȃ��̂��H
�����č��ɂƂǂ܂炸�AISO�K�i�̈Ӑ}��ǂ݉����Ȃ��Ă͋K�i�������Ă܂��B
|

ISO14001�̖ڎ��ɂ��ǂ�