ある日、社会人大学院生の藤田氏が訪ねてきた。一度鷽八百社に来て以来藤田氏はたびたびアンケートの回答や調査結果の見解などを廣井とか中野に相談しに来ているのだ。廣井たちにしてみればいい迷惑だったのだろうが、山田の教育に役立つと考えて対応してくれるのだろう。 今日は廣井が千葉にある工場の指導に出かけており、中野は日経新聞の環境経営度調査対応で忙しく、平目は「会ってもしょうがないよ」というので、山田が一人で対応した。 |
「こんにちは藤田さん、すみませんが今日はみなさん用があって私だけです。私じゃ藤田さんの相談に乗る力はありませんね、藤田さんに教えてもらうだけです。」
山田が応接室に入りがてら言った。
|
「環境側面のどんなことでしょうか?」
「ISO14001認証している組織は環境側面を特定し、著しい側面を決定する手順を確立しなければならないと規格にあります。
ほとんどの組織はこの文言に沿って、環境側面を特定するフローを考え、そして著しいものを決めるロジックを作っています。決定する方法に点数法なんてしているいいかげんな会社もいまだにありますがそれは論外としても、ロジックゲートで該非で決める方法も私は実態と離れたバーチャルじゃないかと思います。」
山田もそう思う。環境保護部に来て嘘八百社の工場をいくつか訪問してそれぞれのEMSの仕組み・・いや正しく言えばISO対応の仕組みを見てきたが、やはり環境側面の特定・決定方法は過去から行われている実際の業務とはかけ離れたデッチアゲ的な印象を持った。
|
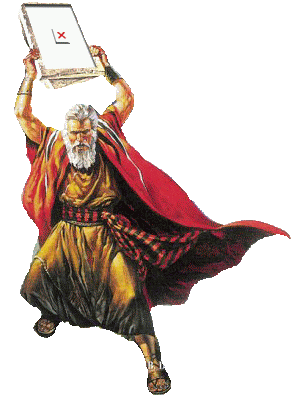 「『ありてあるもの』って? 旧約のエホバとか?」
「『ありてあるもの』って? 旧約のエホバとか?」「いえいえ、キリスト教とかユダヤ教の神様のことじゃないです。単に初めから存在しているものといった意味だけです。」
「うーん、いまいちおっしゃることがわかりませんね〜」
「藤田さん、環境側面というものをなぜ見つけようとするんですか? そんなものはじめから分かり切っているじゃないですか?
環境側面って一体何か?といえば、規格の定義から考えるより、規格本文を読んだ方が分かりやすいです。つまり、必ずしも文書でなくても良いが手順を作り、それに基づき教育し、実行し、運用を監視しなければ事故、違反、重大な不具合が起きるおそれのあるものが著しい環境側面なんですよ。そんなことを計算にしろ、ロジックゲートにせよ、わざわざ考えなければ分からないなんておかしいじゃないですか?」
「えー、というとどういうことでしょうか?」
「どの会社でも、ちゃんと管理しなければ大事故や大損害が起きる恐れがあるものは、しっかりと内部牽制をかけるでしょう。銀行なら二人いないと金庫が開かないとか。有毒ガスを使っていれば漏洩探知を二重三重に付けるとか、法律違反すると懲役や罰金があれば、違反しないような仕組みを作るはずです。そんなふうに過去から管理していたものを、そのまんま著しい環境側面としたらどうでしょうか?」
「うーん、規格ではまずはじめに環境側面を特定すること、その中から著しいものを決定することとツゥーステップでないといけません。これは2004年版で変わったと聞きますが・・」
「藤田さん、規格についてはあなたの方が詳しいです。ただ基本的なことですが、規格のために会社が存在するわけではありません。会社の管理のために規格を使うのです。規格はツールに過ぎません。そして規格が絶対だということでもないのです。もし規格が絶対で誤謬がないものなら、ISO規格改訂というのはありえないことになります。
もし単に審査での論理のつじつまがご心配なら、『当社においては過去より管理していたものが環境側面である。当社ではそれらをすべて著しい環境側面とする』と会社のルールを決めたらいいじゃないですか。」
「うーん」
藤田は腕組みをして空中をにらんだ。 山田のいうことももっともらしいが、どうもおかしい。そもそも過去から管理していたものですべての環境側面を網羅しているとは限らない。 環境側面とはなんらかの方法で見つけるという改めてのプロセスが必要ではないのだろうか? もちろんそれは点数方式のようなおかしな論理であるはずはない。しかし、たとえば法規制に関わるかどうかで判定するというふうな客観的な判断基準がなければ単なる恣意にすぎない。 |
「藤田さん、私はずっと環境側面について考えたのです。そして思ったのは、規格が求めているのは環境側面をしっかり把握するということであって、ある時点で一度に環境側面全部を調べろということではないと思うようになりました。つまりです、会社で新設備を導入したり、新しい薬品を使うようになったりしたとき、その都度それが法規制に関わらないか、つまり設置届が必要か、有資格者がいるのかと調べたり、異常が起きた時外部にまで影響するような問題がないかと検討したりしなければなりません。そんなことはどの会社でも昔からしていたことです。それこそがISO規格でいう環境側面を特定し、著しいか否かを判定することだと思うのです。」
藤田の頭の中が一瞬にしてスッキリしたように思えた。
|
「藤田さん、規格の文言の『計画された若しくは新規の開発、又は新規の若しくは変更された活動、製品及びサービスも考慮に入れて特定する。』ってそのまんまじゃないかと思うのです。」
「すごい!環境側面の決め方については多々意見を聞きましたが、時間的なことを含めた考えを聞いたのは初めてです。しかしなぜ今まで多くの人がそんな簡明な方法で理解しなかったのだろう?」
「結局日本でISOを広めた認証機関や審査員がISOの意図を理解していなかったからではないでしょうか? 20世紀にISO14001を教え審査した人々は根本から間違えていたのです。
環境側面を点数で決めることがバーチャルでうそ八百なのは言うまでもありませんが、それは手法が間違っているからだけではなく、考えそのものが間違っているからなのです。ISO14001を認証しようとしている会社で、設備やエネルギーや薬品をリストアップして点数を付けて順序を付けるというプロセスをしたとき、おかしいなあと思う人がいないかもしれない。
しかし、新設備を導入するとき、点数を付けて何点になったから市の環境課に届をしようとか、手順書を作る必要があるというプロセスだったら・・どう思うでしょうか?」
「ハハハハハ・・」藤田は笑い出してしまった。
「そりゃ、そんなことを考える人がいればまっとうな社会人、プロビジネスマンではないことは間違いありませんね。」
「でしょう!? 法律に該当するかしないかを調べて市役所に届ける必要があるか、有資格者が必要かを知らなければなりません。取扱説明書を読んだり、実際に試運転あるいは思考実験をして危険性を考えるでしょう。その結果、手順書を作らないと危ないと判断するか、機械の付属の取説を見れば間に合うかを判断するんじゃないですか? それこそが・・」
「それこそが環境側面の特定であり、著しいか否かの決定だというんですね?」藤田が引き取った。
「その通り!」
「そんなふうなスタンスで考えると、緊急時の環境側面とか非定常時とか定常時なんて発想も変なことになりますね。」
「藤田さん、定常時の環境側面はなんだろうか? 緊急時の環境側面はなんだろう? という発想は完全にずれています。この環境側面は定常時は著しいが緊急時は著しくないとか、この環境側面は定常時も緊急時の著しいという考え方が正しいのではないでしょうか?」
「山田さん、その場合は規格でいう文書化しなければならない情報・・つまり環境側面の特定や決定した記録に相当するものはどうなりますか?」
「藤田さん、どの会社だって新設備を入れるときは投資計画書とかイクイバレントはあるでしょう。化学物質であれば安全管理者に使用許可申請をするでしょう。そういう実際の会社の生きて動いている書類がそれに当たるのではないでしょうか?」
「認証機関は審査前に著しい環境側面のリストを出せといいますが、それに当たる文書はどうなりますか?」
「そのへんになると認証機関のためという発想ですね。そもそも規格では環境側面の特定・決定の情報を文書化せよと言っていますが、リストが必要とはありません。まあ最悪、認証機関のためにリストを作るか、あるいは著しい側面になれば手順書を作っているはずですから手順書の台帳で代用することもありでしょう。」
藤田は唸ってしまった。藤田が山田に会ってからまだ二月たっていないはずだ。あのとき山田は営業から異動してきたばかりといった。たった二月でISO規格をこれほどに理解してしまった山田とは何者なのだろうか?
|
「私はISO9000であろうとISO14000であろうと、絶対とかすぐれものとか思っていません。私だって会社に入って20年選手です。その間、いろいろな経営手法が流行し、当社でも取り入れたものもあります。その結果役に立たなかったものもありますし、いっときは効果があったように見えても意味がなくなったもの、あるいは時代に合わなくなったものなどいろいろ経験があります。
そんな目で見るとISO14001が過去のさまざまな経営手法や管理のツール以上のものとは思えないのです。冷めた目で見るとISO規格にあるから大事だとか、やらなくてはならないなんて発想は出てきません。ISO規格に書いてあることがよさそうならやってみればよし、あまり意味がないように思えたら、しないで済ますこと、あるいは過去からしていることで代用するべきだと思うようになったのです。」
本日の課題
次のことを考えてみましょう。
(1)山田の過去から管理しているものが著しい環境側面であるという説を否定してください。
(2)上記否定論を再否定する論を考えなさい。
ぶらっくたいがぁ様からお便りを頂きました(09.11.09)
異議アリ! ワシは国内大手の権威ある認証機関で長年審査員をやっておるがの、 (1)山田の過去から管理しているものが著しい環境側面であるという説を否定してください。 ワシが指摘するまで、コンプレッサの届出義務は知らんわ、MSDSって何ですか?新しいゲーム機ですか?とか聞くヤツはいるわ、そんな会社が今までゴロゴロあったぞ。 企業が認証前からもともと把握して管理しているなんてのは幻想にすぎんのぢゃ。 だいいち、審査員が一目見てわかる文書・記録が整っていなくて審査が通るとでも思っておるのか? そもそも点数評価とか客観的に判定できる基準を用いずして顧客が納得するわけがなかろう。もしワシが第二者監査をしたとしたら、取引不可と判定するじゃろな。 なんせ、顧客が不適合といえば不適合なのぢゃ。理屈は後からついてくるわい。不適合ではないと言うのなら、適合している証拠を見せてみい。 |
ぶらっくたいがぁ様 早速の突っ込みありがとうございます。いやあ〜強烈な論ですね 正直言いますと、現実の審査員にはこのようなお方が多いですね。ではさっそく山田君に応えてもらいましょう。 腰砕けコース 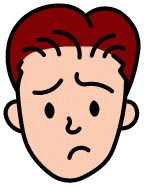 えー!そうなんですか? すみません、私も経験がなくて、頭で考えただけじゃだめなんですね〜ごめんなさい
えー!そうなんですか? すみません、私も経験がなくて、頭で考えただけじゃだめなんですね〜ごめんなさいおっしゃるとおり、さっそく環境側面の特定、決定方法を旧来に戻します。すみません。 方法はもちろん点数方法にします。いわゆるJ△C○方式ってやつにすればOKですか? そうですか、ありがとうございました。ほんとうにすみません〜 ごめんなさい、ごめんなさい、すみませんでした ・・・ ケンカ腰コース いや元気のいい審査員の方ですね。 論点を整理しましょう。コンプレッサでもコンデンスミルクでもMSDSでもMLSSでも何でもいいんですが、そういう法規制を知らない組織があれば、バッシと不適合をかましてくださいよ。 単純にそれだけのことでしょう? そんなことをすると客が逃げて困りますか? そんなことと違って、審査は規格に基づいてしっかりと適合、不適合を判定してほしいですね。 審査員が一目見てわかる文書・記録が整っていなくて審査が通るとでも思っておるのか? だってあなたをはじめとする審査員のために当社のEMSは存在してませんよ。 文書・記録が整ってなくちゃ審査できないなら力量不足じゃないんですかねえ〜 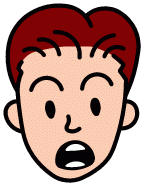 顧客が不適合といえば不適合なのぢゃ。
顧客が不適合といえば不適合なのぢゃ。顧客って誰ですか?審査員とか認証機関はISO9001なら顧客の代理者と呼ばれたこともありますが、顧客ではありませんよね。あなたは顧客じゃないですから、顧客が不適合といったという証拠を見せてください。 しかし待てよ?最近では審査機関は組織を顧客と呼んでますよね。そうすると私が顧客であなたは供給者ということになる。なんか矛盾しているなあ〜 それにISO14001では顧客のためではなく、利害関係者のために審査するのかと思っていました。 審査員さんは利害関係者でしたっけ? 理屈は後からついてくるわい。 いやはや、今のお言葉は録音してましたので抗議文と一緒にJABと貴社の社長に送らせてもらいます。それと当社のウェブサイトにアップさせていただきます。 とりあえず今日はお帰りくださって結構です。 おどしたりすかしたりコース 審査員さん、お互いに仕事じゃないですか、大人の対応をしましょうよ。 もめたりして異議申し立てなんて食らうと次回のCEAR審査員更新は難しくなると聞いてます。いえ、私は異議申し立てなんてしませんよ。だけど今周りで聞いていた人も多いじゃないですか、 それに御社で登録している企業さん、最近相当減ってますよね。アッ、そんな情報はJABのウェブサイトに行くと載ってますから。 もめて登録組織が他の認証機関にくら替えしたなんて言ったらお宅の審査部長も営業部長もいい顔をしないでしょうね。審査員さんは今年定年で、子会社に移られるとか聞いてましたが・・それも難しくなるかもしれませんねえ〜 世の中には規格不適合でもOKにしろなんていう企業の方もいると聞きますが・・いや私はそんなことを言いませんよ。 でも規格に則った審査を希望する企業は多いでしょうね。私もあまりおかしな考えの審査は好きじゃないんですよ。 あ 分かってくれました? そうですよね、お互いにビジネスマンだから分かりあえますよね いやあお互いに同意できて良かったですね。 |
外資社員様からお便りを頂きました(09.11.11)
佐為さま、ぶらっくたいがー様 お二人の掛け合いは絶妙ですね。 こういうのを本音の教育というのだと思います。 お陰さまで、何が問題なのか、ISO素人の私にもよく見えるようになりました。 私なりに感じたのは、認証の基準を書類が整っているという“形式”に求めては、本質から離れてゆく危険があるという点です。 そうは思いながら、実は審査員の言葉でも共感した部分があります。 「企業が認証前からもともと把握して管理しているなんてのは幻想」 この危惧があるから、第三者なり、第二者による認証をするのだと思います。また経営者の立場で言えば、社内での業務が法規や安全性を配慮して行われていると判断できる根拠は相変わらず必要なのだと思います。 法律に該当するかしないかを調べて市役所に届ける必要があるか、有資格者が必要かを知らなければなりません。取扱説明書を読んだり、実際に試運転あるいは思考実験をして危険性を考えるでしょう。その結果、手順書を作らないと危ないと判断するか、機械の付属の取説を見れば間に合うかを判断するんじゃないですか まさにこの部分で、ここで言っていることは正しいのですが、それが正しく行われていることをどうやって経営者が担保できるのかが重要で、経営者が納得できるならば顧客にも説明が可能だと思います。 それこそが、本来の認証のあるべき姿なのだと思います。 もし、そのような考えが的外れでないならば文末の質問として「著しい環境側面が管理されていることを経営者はどのように担保できるでしょうか、また その証明は山田はどうすればできるでしょうか」を提案したいと思います。 それが出来ているならば、経営者も会社幹部も自社が問題なく管理できていることを外部に説明できるでしょうし、第三者認証は、その念押しや証明であることがはっきりするように思いました。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 「企業が認証前からもともと把握して管理しているなんてのは幻想」 その可能性はあります。いかにして法規制の把握を確実にするかというのが課題です。 では審査において法規制を確実に認識することができるかと言えば・・できません。 なぜできないかと言えばいくつもの理由があります。 第一に、現実の審査員は法規制をあまり知らない人が多いです。だって考えてごらんなさい。会社にいて役員になれないから審査員に出向とか、品質管理とか営業一筋で来た人が審査員になったりというのは普通です。そんな人が環境に限らず法規制をどのくらい知っていると思います? そりゃ勉強すれば知識はつくでしょうけど、その会社で環境一筋で来た人以上にその会社に関わる法規制を知っている可能性はかなり低いでしょう。 もちろんISO審査はマネジメントの審査だという理屈はありますが、それならなおのこと法規制に踏み込むこと、あるいは会社の法順守に貢献することとは遠くなります。 第二に、弁護士法によって弁護士でないものが法に関するコンサル行為を行うことは禁じられています。よって審査員が言えるのは法規制の把握に漏れがあるのではないか、行政に確認しなさいということに限定されます。もちろん実際にはもっと踏み込んだ発言をしているのですが、もし何らかの問題が起きた時、あるいは誰かによって弁護士法違反として訴えられる危険は大です。 私自身、審査で法規制に関して間違った判断、判定をされて、判定を見直してくれという会社に同伴して認証機関に行くこともあります。実際に審査員の誤った指示でおかしくない記録をかいざんしてしまったという事例も知っています。それが現実です。 「企業が認証前からもともと把握して管理しているなんてのは幻想」であると同時に、「審査員が法規制を理解しているなんてのは幻想」なのです。 結果として、その会社が法を守っているかを担保するためにISO審査をするのだという発想はあり得ない、あるいは間違いでしょう。 ISO審査はその会社が法を守る仕組みがあるかということしかできません。 実際にはそれさえできない審査員は多いです。 それこそが第三者認証の限界であり、最大の問題点ではないのでしょうか? |
外資社員様からお便りを頂きました(09.11.13)
佐為さま 法規制に関するお話についてです。 審査員の資質については、言いにくいことをズバッで言わせたようで恐縮です。もちろん、納得です。 会社の立場としては、法規制は審査の中で、会社側が不足な部分の補間が期待されているが、期待にこたえていない場合があるという点では意見は一致していると思いますが如何でしょうか? 一方で第2の点は、私は違う意見です。 認証に関連した説明の中で、関連法規の提示や、解釈の見解を示すことは問題ないと、私は思っています。 弁護士法で規制しているのは法律事務と、「非弁活動」についてと思います。 ISOのコンサルや審査員に法律事務を期待する人はおりませんし、非弁活動については審査員に法的問題の仲裁・代理・鑑定などは期待しないと思います。 確かに、法規に関して発言すると、問題が起きた場合(例として抜けがあった場合)に、イチャモンのネタになる危険はありますが、本気で指導したければ佐為さまのように勉強するべきですし、判っている範囲で言っているならばその旨を明確にするか、免責事項を書面で明示しておくのが、まともな審査会社の法的対応なのだと思います。 ですから、「生兵法でかかるならば何も言わない方が良い」という点ではご意見に賛成ですが、かといって弁護士法を持ち出して逃げるなら審査員の不勉強の言い訳に聞こえてしまうように思うのは、私の性格が悪いからでしょうか(笑) 私は今でも、技術系の国際標準化に関わっていますが、開会前に関連法規である独占禁止法、外為法の輸出管理規定、守秘情報、知的財産の扱い(これは団体の規則)について言及し、注意を喚起しています。 こうしたことが、自然な感覚として関係者の中で意識されるのが、望ましい状態なのかと思います。審査を受ける側が、何をしてもらいたいかはっきり伝えられない場合には、問題点を見つけるのが大変とは思いますが... |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 おっしゃる意図は分かります。弁護士法を持ち出すまでもなかったかもしれませんね。 結局、語ることがまっとうか否かということに還元されるでしょう。 確かに審査員が確固たる知識、経験を踏まえて語るなら資格云々をとやかくいうことはないでしょう。 一応の経験者の誰が見ても「そりゃ変」ということを語る審査員がいるということが問題であるということに過ぎないのでしょう。そしてそんな審査員が多すぎるのです。 間違えた判定をするだけでなく、間違えた指導(本来審査では指導は禁止です)をしたことによって組織が間違いを重ねるということがあることが事実。 JABやJACBが審査で企業が虚偽の説明をすると声を大にして叫んでいますが、実態はそんなもんじゃないです。 審査で誤った法律の判断をして、誤った指導をして企業を困ったことに追い込んでいるということが問題ではないのでしょうか? 私はJABやJACBではないですから、れっきとして証拠根拠を提示することができます。 虚偽の説明をしていると語る人たちは確固たる証拠根拠を提示することができるなら拝見したいです。 |
リス様からお便りを頂きました(09.11.27)
おばQさま、こんにちは。 「ケーススタディ 環境側面」拝読しました。 というほどでもなく、流し読んだくらいなのですが…(時間がなく、すみません) はじめて名古屋鶏さんのところへお邪魔した頃から、「著しい環境側面」についてまだまだずっと悩んでいます。 おばQ様は「著しい環境側面」は、「ちゃんと管理しなければ大事故や大損害が起きる恐れがあるもの」という定義でいらっしゃるのでしょうか。 私の会社にいらっしゃった審査員の方は、「努力して改善できるもの」ということをおっしゃいました。 すみませんが、もう一度「著しい環境側面」の定義をおしえてください。 |
リス様 毎度ありがとうございます。 環境側面の定義はISO14001 3.6「環境(3.5)と相互に作用する可能性のある、組織(3.16)の活動又は製品又はサービスの要素。 参考 著しい環境側面は、著しい環境影響(3.7)を与えるか又は与える可能性がある。」以外のなにものでもありません。 どう読んでも改善をすべきこととは書いてありません。 では環境側面を規格ではどうしろと論じているのかといいますと・・
逆説的ですが、これが環境側面の定義というか形質を現していると考えております。 リス様がおっしゃるように「ちゃんと管理しなければ大事故や大損害が起きる恐れがあるもの」ということです。 上記には目的目標に関して「著しい環境側面を考慮に入れること」とありますが、改善しろとは言っていません。 定義から言っても、上記規格の文言から言っても、「努力して改善できるもの」であるはずがありません。 もしそのような新説を語る審査員がいらっしゃるなら(いることは間違いありません、私も大勢見ております)まあ、そんなぼけを語る審査員にはたいした審査は期待できませんね。 サポーズ! PCBを保管しているとします。これが著しい環境側面であることは間違いありません。努力して改善できるのでしょうか? JESCOが処理してくれるまで、じっと何年も待つだけです。 シアンを大量に使っているとします。これが著しい環境側面であることは間違いありません。努力して改善できるのでしょうか? 廃業するなんていっちゃいやよ 「努力しても改善できないもの」は著しい側面でないなら、PCBもシアンも環境側面ではないのでしょうか? もしPCBやシアンを環境側面にしていない組織があるなら、危ないから絶対に近寄っちゃいけません |
ぶらっくたいがぁ様からお便りを頂きました(09.11.28)
リス様 ぶらっくたいがぁです。その節はたいへん失礼しました。 私の会社にいらっしゃった審査員の方は、「努力して改善できるもの」ということをおっしゃいました。 これはヘンですね。規格の4.3.1(環境側面)には「組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面」を管理することとありますから、審査員たるものそんな狭い解釈では困ります。 まあ、「著しい環境側面」とはなんぞやについて、規格の小難しい解析と解釈はおばQ様にお譲りするとして、私のようなアホにはその審査員の唱える説は規格要求事項以前の問題としてたいへん奇異に感じます。 「努力しても改善できないもの」は対象外なのか? それらは何も手を打たないのか? およそ現実の事業運営においてそんなバカな話はありますまい。「ちゃんと管理しなければ大事故や大損害が起きる恐れがあるもの」が起きたときにはどうするかを考えて手を打っておくのが当たり前です。 また、そうしたリスクマネジメントとは別に、環境負荷軽減の観点からも奇異に思います。 例えばある会社で次の2つの施策を実施したとします。 施策A 全社員でコピー用紙の削減に取り組み、1年間努力した結果、コピー用紙の使用量を10万枚削減した。(金額換算で5万円の削減) 施策B ○○工程に廃熱回収装置(投資金額500万円)を設置した結果、年間の電力費を200万円削減した。 その審査員氏からすれば、○○工程でエネルギーが大量に浪費されていることは、人の努力ではどうすることもできないので著しい環境側面ではないという理屈になり、施策Bはただお金を投じただけで評価に値しないということになってしまいます。 一方、施策Aは全員で努力したことが大事で高く評価されるということでしょう。しかし、その結果、多くの文書を見づらいパソコン画面で見なければならず作業効率の悪化を招いたり、コピー用紙を使うことが憚れるために個人ベースでのメモ書きが増えて誤記や誤読による不良が多発したといった弊害が起こっているかもしれません。 実務の視点で見た場合、いったいどちらが経営的メリットを生み出したのでしょうか。 おそらくその審査員氏には「全員参加」という考え方が根底にあり、「ISOによる環境活動」とは全員で努力して現状を改善していくものだという思いがあるのでしょう。 それはそれで大事ですが、それが全てでも至上でもないと思います。 |
ぶらっくたいがぁ様 まいどありがとうございます。 ここで一句 秋深し、環境側面謎深し オソマツ |
うそ800の目次にもどる