| 著 者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 定価
(入手時) | 巻数 |
| 新井 暢 | Qプレス | 書籍ではなくカラープリント
をクリップで綴じたもの | 2009年8月8日 | 1575円 | 全一巻 |
これはアイソス誌12月号に載っていたので即注文しました。
インターネットに注文を受けたら翌日発送と語っている割には、注文しても10日も来ないので督促してやっと来ました。
看板倒れですよ〜
さて、本の中身というかアラスジとか内容を知りたくば新品でも中古でもお買い求めいただくとして、ここでは個々の論評ではなく、これらを読んだ感想を書く。
実は、このお三方はそろって現実のISO認証制度を批判しているが、ISO規格を立派なものというか、正しいというか、真理だと考えている。そして愛しているようなのである。
まあ、ISO規格が立派なのか真理なのか愛すべきかは人それぞれ、めざしの頭も信心からというくらいで、他人がとやかくいうことはない。
しかし、私はいずれの本を読んで、ものすごく違和感を持ったのである。
ISO規格が良いものか、そうではないか、ということはその人の立場により時代により、あるいは生い立ちというか業歴によって見解が異なるのは当然だ。
第三者認証制度を盛りたてようと考えても、消滅してもしょうがないと考えても、あるいは第三者認証制度に敵愾心をもっても、人により、職務の違いによっていろいろいても当然である。
しかし、私は納得できないことがこのお三方の本に共通してある。
それは、
「ISOに合わせて会社を直す」とか、
「ISO規格に合わせてマネジメントシステムを構築する」と語っていることである。
「ISO9000シリーズの講義を受け、その精神に共鳴し早速就業規則をそれに沿ったものに改定した」(新井氏 アイソス誌09/12 p4)
みなさん、それっておかしいと思いませんか?
社会に貢献するために設立され、事業を推進している企業が、なんであとからでてきたISO規格に会社の仕組みを合わせなくてはならないのでしょうか?
そして実際にISO規格に合わせて会社の仕組みを見直した方は実在するのだろうか?
マネジメントシステムを真に構築した方、品質保証体制を作り上げた方、環境管理の仕組みを作り上げた方は存在するのだろうか?
もちろんこれは反語であり、そんな人はいないだろうと私は考えている。
そしてまたこれらの方々は、規格に書いてないことを見出しているのである。
『「継続的改善は品質マネジメントシステムの継続的改善であり製品の改善も効率の改善も含まれない」とはトンデモナイ』と語っている。(続くたばれ p72)
ISO9000:2006を読みなおすことを推奨する。
「役立つISOにするにはどうやって運用するかが問題なのだ」(続くたばれ p58)
これを読んで「そのとおりだ」と思った方ははっきり言っておかしいです。
なんでISOを役立つようにしなければならないのですか?
ISOが役立てばヨシ、役立たなければほおれば(捨てれば)いいじゃないですか?
「経営の中にISOを一定のビジョンとして位置付ける」(続くたばれ p43)
ビジョンてなによ? ISOはビジョンになるの?
お考えが完璧にずれている。ISOは仕組みだ。ビジョンではない。それともISO規格を読んで企業の将来像を見い出したのだろうか? うつろう空の雲を見て、ああ人の顔だというようなものか?
「審査機関独自に審査員を認定しているケースは正しい姿ではない」(崩壊は何故起きた p73)
なにゆえに正しくないのか? 何を根拠にそう語るのか?
最近JABなどが出した
「MS信頼性ガイドライン対応委員会報告書」で審査員はJRCA/CEARに登録した者であるべきだと書いてあった。私はJABの論理もおかしいと思う。現状では審査員登録機関に登録してなくても良いのであり、正しいもへったくれもないだろうが
JRCAやCEARに登録している審査員と、IRCAに登録している審査員と、認証機関が認定した審査員との力量の差があるのかどうか、私には分からない。
西沢さんはその差があることの証拠を示さなければ、そんなアホなことを語ってはいけない。
『「自分の会社が(ISO)をとるのであり、社員が一番よく業務を知っているのだから、コンサルは不要で、自らやっていることを書けばよい。」というのは間違いである。』(崩壊は何故起きた p80)
うーん、私には間違いだということが分からない。いや間違いでないと考えている。
偉大なるLMJは「会社をいちばん知っているのはその会社の人だ」と語っている。私の尊敬する某認証機関の取締役もそう語っている。偉大な松下幸之助は言ったそうです。「なぜ、コンサルタントが必要なんだ? 自分でできないのか?」と。
もっともコンサル側から見れば、各企業がコンサルを頼まなければ商売あがったりか

ならば「外部のコンサルが会社のことを一番知っている」と語ることは間違いない。
「ISOマネジメントシステム規格は、抽象的な内容なので、各企業はその意図を解釈して、実務運用レベルまで具体的なシステムを設計しなければならない」(崩壊は何故起きた p131)
これまた不思議、不可思議、摩訶不思議だ。なぜ改めてシステムを設計しなければならないのか?
その会社はたった今創立されたのか? 今まで事業活動は行ったことがないのか?
あなた、どう思います?
「崩壊は何故起きた」はあちこちおかしなところはあるが、まあいいことも書いていると読んできたが・・ついに決定的におかしなことがある。
「有益な環境側面とはその活動をやめたら会社の活動が停止するもの」(崩壊は何故起きた p163)
もうこれには妥協も見逃しもできません。これは完ぺき、完全に間違っています。許容しがたい。「有益な側面を把握しなければなりませんよ」と悪に誘うエデンの園の蛇のような審査員同様に、ISO規格を理解していないことは明白だ。
いずれにしても、このお三方は完全にISOのバーチャル思想に汚染されている。お三方がご批判している現状のISO認証制度の人々と全く同じ価値観というか、考え方なのである。
おっと考えが同じではなく、ずれているところが同じなのである。
私のスタンスを旗幟鮮明にする。
私は企業であろうとその他のいかなる組織であっても、それは目的実現のために設立されたのである。間違ってもISO規格のために設立されたのではなく、ましてやISO第三者認証制度で認証を受けるために設立されたのではない。
だから帳票一枚といえどISOのために変える必要を感じないし、ましてや会社の仕組みやルールをたかがISOのために改定すべきではない。
ISOは使いこなすべきだとさえ考えていない。ISOが役立てば使ってやる、役に立たないならポイするだけなのです。
しかし、こんな間違いはJISに翻訳した時「マネジメントシステム」と称したことから起きているのではないだろうか?
新井さんへの疑問であるが、彼は「JIS規格はISO規格の翻訳ではなく、誤訳である」と語っている。それはかなりの部分そうなのだろう。私の英語の力では新井さんの問題提起を理解することはできない。しかし彼が取り上げるのを忘れている重大な誤訳があると私は思う。
それはタイトルだ。ISO規格の「Quality management systems-Requirements」が「品質マネジメントシステム−要求事項」と訳されている。これが一対一であるとは私には思えない。
更に誤解を増幅するのは副題についている「品質マネジメントの国際規格」である。原文にはない。これは正しい意味を伝えているのだろうか?
|
西沢さんの「ISOマネジメントシステムの崩壊は何故起きたか」はタイトルからして間違っていると思う。
正しくは「ISOマネジメントシステム認証制度の崩壊は何故起きたか」ではないのだろうか?
|
以前も書いたが、規格のニュアンスは「品質マネジメントシステムに欠かせない要素」とか「環境マネジメントシステムに必要な条件」というようなことではないのでしょうか?
いずれにしてもISO規格/JIS規格を満たせば完ぺきだということでは、まったくない。十分条件ではなく必要条件なのだ。
本日のまとめ
5000円は私にとっては大金である。
これらの本を読んで、それだけの見返りはなかった。
本日のたわごと
私こそがISO規格を一番理解しているのではないだろうか?
おっと、それは勘違いだろう

ぶらっくたいがぁ様からお便りを頂きました(09.12.06)
しかし、私は納得できないことがこのお三方の本に共通してある。
それは、「ISOに合わせて会社を直す」とか、「ISO規格に合わせてマネジメントシステムを構築する」と語っていることである。
ISO関連のサイトや掲示板などをウロウロしていると、ISO規格を本業に役立てようだとか本業に落とし込もうだとか、あるいは審査用ではなくMSを有効なものに再構築しようとか、そういうことを主張する人によく出会います。
それってヘンじゃね? と常々ものすごい違和感を持っていたのですが、それと同じことだと思います。所詮は規格ありき、審査ありきであることに変わりはなく、およそ実務・実益の視点から物事を考えるスタンスではないからです。
某掲示板でも設計事務所が施主に提出する設計図面は「製品」か否か、その作成作業は「製造」か「設計・開発」かといった議論が盛んですが、私にはなぜそんなことを議論したいのか、結論を出すことで現実に何か変化が生じるのか、ありていに言えば何かトクになることがあるのかがサッパリわかりません。
もしISO認証制度が瓦解して登録証が無価値になったとして、それでも上記のようなことを主張して、その種の議論を賑々しくするのでしょうか。
「もしISO認証を返上したとして、それでも今の手順、文書、記録はそのまま運用し続けますか? そして、今のやり方のまま内部監査とマネジメントレビューを実施し続けますか?」
この質問に「Yes」と答えられる会社は世間にそう多くはありますまい。
しかし、「Yes」と答えられないのであれば、所詮はバーチャルMSであり、「ISOごっこ」に過ぎません。
もし審査員やISOコンサルを生業としている方がこのカキコを読まれたら、審査や指導の際には組織にぜひこの質問をしていただきたいと思います。
って、自分で自分のメシのタネをなくすようなマネをするはずがありませんよね。 
|
|
ぶらっくたいがぁ様 毎度ありがとうございます。
おっしゃるとおりでございます。そのような偏屈で井戸の中の天動説論者と関わるのは百害あって一利ありません。近づかないことがなによりです。
とはいえ、付き合わなければならないというのも渡世の義理、ISOゴッコを真剣に考えている人には世間の冷たい水をぶっかけてやるのが一番でしょう。
おおっと、私はそんなアブナイことはしませんよ。
たいがぁ様に名誉ある仕事をお願いいたしましょう。
|
名古屋鶏様からお便りを頂きました(09.12.06)
佐為様 まいどです。
「ISOマネジメントシステムの崩壊は何故おきたのか」ですか・・・タイトルは勇ましいですが、よくよく見ると著者が、「西沢総研」の西沢氏なんですね。納得。
彼の人のWEBサイトはある意味面白いので、タマに拝見することがありますが。
密林で目次だけ見ましたが、結局のところ西沢氏が心配しているのは地球環境の悪化や企業の環境パフォーマンスの低下でもなんでもなく、審査登録制度が崩壊することでコンサルタント業務でメシが食えなくなるという話でしょうね。
|
|
名古屋鶏様 毎度ありがとうございます。
この著者の西沢様って、名古屋鶏様が「かの西沢総研」とおっしゃるのでは、相当有名なお方なのですね!?
この私は電車の中つりのキムタクを誰だ?と家内に聞いたほどなので、有名人を知らないのですよ。
まああまり感心しませんでしたので、西沢さんを覚えておくほどのことはなさそうです。
|
湾星ファン様からお便りを頂きました(09.12.06)

湾星ファンです。
JIS版の問題は「直訳しなかったこと」だと思います。英語圏と日本では文化が異なるので、所詮、正確に訳すことは不可能です。management、performanceなど、適訳のない単語は枚挙に暇がありません。
佐為様がおっしゃるように、国際規格は、会社の役に立つか否かで判断すべきもので、金科玉条にように崇め奉るものでも何でもありません。
誤解するも理解するも利用者の判断に任せれば宜しいのであって、JIS委員の方々が勝手に意訳し、原意を損なうことこそ忌避すべきものと心得ます。
|
|
湾星ファン様 毎度ありがとうございます。
おっしゃる通りです。あるいはですが・・英語をそのままJIS規格にするというのもありかもしれません。もちろんそのままでは読みくだすのが難しいでしょうから、対訳を付けておきます。そして疑義ある場合は英文を基に解釈すると注記しておけばよかったでしょう。
驚くことはありません、なにせ日米安全保障条約などは疑義がある場合は英文を基に解釈することになっているはずです。
オオット、有名な外資系認証機関との審査契約書は「この契約書に疑義ある時は英文の契約書を基に判断する」という一文がありました。
そうすればわざわざ日本規格協会から高い金を払って対訳本を買うこともなかったのにね・・
|
外資社員様からお便りを頂きました(09.12.11)
「日本が世界標準に負け続ける理由」を読みましたが、一言でいえば看板に偽りありです。
内容は、1)JIS委員への質問、2)JIS委員会からの回答、3)回答への感想で構成され、これが誤訳と思われる条項ごとに記載されています。
表題にある世界標準に負け続ける理由は、一切書かれておらず、あえて言えば巻末に新聞の切り抜き記事2つほどがあり、これがそのような趣旨の内容です。 表題にひかれて読んだ人は、がっかりすると思います。
私も、技術標準の翻訳をやりましたが、従来にない概念を日本語にするのは難しいのです。
明治の先人達は、そのような場合には造語をして、それが受けいれられたから使われています。
(例として、坂の上の雲に出た、野球、打者、飛球など)
技術分野では、変化が速いので、訳語への共通認識が出来る前に廃れることが多いので、いきおいカタカナ語やアルファベット略語となります。
(ネットワーキング、ユピキタス、INS,ISDN)
今回のようなケースでは、業界の関係者:翻訳者、ユーザである企業、審査会社などが、訳語に対する合意を形成するのが重要と思います。
本来、英語と日本語は一対一で対応できる言葉ではないので、ケースごとに訳語を意味する所を明確にすることによって、訳語が使えるものになります。
つまり、正しい翻訳は いきなり存在するものではなく、合意により形成されるのだと思います。
(海外文学の翻訳は全く異なり、翻訳者は原語との壁やギャップを自己の創造で埋めることが許されるのです。その代わり、その能力が低ければ原作の良さをダメにすることもあるし、原作以上の素晴らしさが創造されることもあります。)
ですから、「負け続ける」の新井氏も、目指すべきことは合意の形成であり、JISの翻訳者をけなすのも良いのですが、次の段階として合意をどのように形成するかが、ISO翻訳を役立つものにするには本当に重要と思います。
私が同じ立場ならば、互いの意見交換を公開し、多くの関係者の意見をきき、関係者の合意を形成することに努力します。
それこそが、日本が世界標準で後れを取らない為に重要な事と思います。
おまけですが、その点では、HPを開き、意見を表明し、反対意見だろうが掲載する佐為さまの方が、数段立派だと思います。
以上
|
|
外資社員様 毎度ありがとうございます。
おっしゃることは一点を除き同意です。その一点は 佐為さまの方が、数段立派 というところで、これは外資社員様の完全な間違いですよ。
新井さんはともかく、現実のISO審査がJIS規格とも異なる、恣意的な、おかしな基準によって審査されているということは間違いない事実です。これこそが認証(審査)機関と認定機関が猛省して改善しなければならないことです。
アイソス1月号に 「指摘すると次回以降審査依頼が来なくなるので不適合を出せない」 というISO関係者の言葉がありましたが、笑ってしまいます。
そんな審査をしていながら、企業が虚偽の説明をしているから第三者認証の信頼性が低下していると語るとは・・まったく恥を知らない連中です。
暴れん坊将軍ではありませんが、切って捨てたい。
まあ、そんなアホらしい世界で禄をいただいている身、世過ぎのためには仕方ありません。
渡世の義理というのでしょう。
|
うそ800の目次にもどる
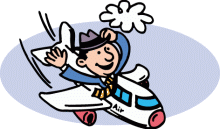 ときどき月曜日から金曜日まで一週間会社に行かないこともある。
ときどき月曜日から金曜日まで一週間会社に行かないこともある。 「続くたばれISO」
「続くたばれISO」 湾星ファンです。
湾星ファンです。