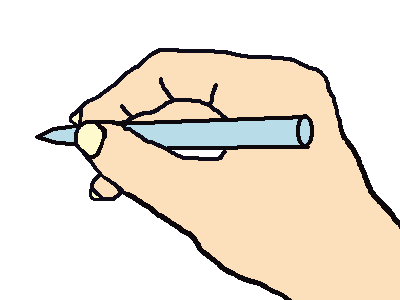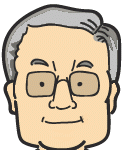12.11.14
ISOケーススタディシリーズとは前回までのあらすじ
山田の営業時代の元上司で現在関連会社
そして定例の環境保護部による環境監査を行った結果、案の定、たくさんの法律に関わる問題やISO規格への不適合などが検出された。
是正も相手に任せたらまともなことをするはずがない。そこで山田は是正処置の指導を行うことにした。
是正指導といっても、単に目の前の不具合をどう処理するかではことはすまない。
ISO規格の意味、解釈を説明もしたし、今回は別の認証機関の審査に立ち会わせて、世の中にはいろいろな審査をする認証機関があることを教えようとしている。
今回は、その続きでございます。
と、これだけではストーリーがお分かりにならないでしょう。ぜひ「10年目のISO事務局」をはじめからお読みください。
今日も山田は三鷹にある
藤本と五反田は勉強と称して、今日も山田に同行している。山田は心中、藤本と五反田にじれったさを感じているが、まあそれは我慢と・・
大法螺側は今日も、福原取締役と川端、桧垣が待っていた。

「では今日はISO認証とは何かということを考えたいと思います。川端さん、認証とはなんでしょうか?」
| |||||||||||||
「以前にも同じ質問をされたような気がします。 ひとつはその組織のマネジメントシステムがISO規格に適合していることの証明で、もうひとつは組織のマネジメントシステムの改善を進めるためということでしょうか?」 | |||||||||||||
「ご存じと思いますが、ISO認証はISO(国際標準化機構)と関係がある事業ではありません。そもそもISOマネジメントシステム規格は認証が目的ではありません。ISO認証とはIAF(国際認定機関フォーラム)という各国の認定機関の団体がISO規格を使って行っているビジネス、つまり早い話が金儲けです。そしてIAF/ISOの共同コミュニケというものがあり、そこでISOマネジメントシステム認証とはなにかを説明しています。 そこではISO認証とは川端さんのおっしゃったふたつのうち、前者しかあげていません。ですから公式には組織の改善という目的はありません。川端さんとしては異論があるかもしれませんが、とりあえずそういうことにして話を進めます。 とすると認証は外部への証明でしかありませんから、企業は必要な場合に認証を受けるわけです。必要とはつまりお客様の要求・・それは顕在の場合も潜在の場合もあるでしょう・・ともかくお客様からISO認証しろと要求されたから認証を受けるということです。お客様には公的なものや規制の場合もあるかもしれません。国土交通省の入札の際、ISO認証していると加点されるということは、建前はどうあれ半強制と認識するのが常識でしょうね」 | |||||||||||||
「質問だが、社会的評価を上げるためということもあるのではないかね?」
| |||||||||||||
「そういうお考えもあるでしょう。しかしそれも突き詰めて考えれば、潜在的顧客の要求だろうと思います。評価というのは他人がするわけで、自主的に認証するという発想はなさそうです。 私の言いたいことは、社会的に認証の価値が評価されていなければ、企業は自発的にISO認証など受けないだろうということをご理解いただければと思います」 | |||||||||||||
「なるほど、世の中でISO認証に価値があると思われているから、企業は特定の顧客から要求されなくても評価を上げようとして認証を受けるということか・・」
| |||||||||||||
「さようです。 再確認しますが、今の議論はISO14001規格に適合することの意味ではなく、認証することの意味ですからね」 | |||||||||||||
「山田さん、その違いはわかるけど、先ほど川端が申したように、会社がISO認証することによって社内の改善や仕組みの見直しをするという発想もあるでしょうね?」
| |||||||||||||
「あるかもしれません。しかしIAFはその目的を公式には述べていないです。 そしてISO規格に合わせることが会社の改善になるかどうかということも考えてみる必要があります。以前も申し上げましたが、ISO規格は設計図ではなく仕様書です。そしてこの仕様書が適正であると証明されているわけではありません。ただそれを議論すると収拾がつかなくなりますから・・とりあえずここではこの仕様書は適切であることにしましょう。 寺田さんからいちゃもんがつくかな? 笑
さて、素晴らしい仕様書を与えられても良い製品ができるとは限りません。良い製品を作るには良い設計が必要です」
| |||||||||||||
「脇から口を挟んで恐縮だが、山田さんの言うのはよく分る。立派なスペックの仕様書を作るのは簡単だがそれを実現することは難しいし、実現できるかどうかもわからない」
| |||||||||||||
「そうしますと、ISO規格は仕様書だから、それを満たしているかどうか確認することは、組織の仕組みの検証にはなっても改善にはならないことになります」
| |||||||||||||
「うーん、ここは良く考えないとその論理が正しいかどうか・・・」
| |||||||||||||
「私は山田さんの論に間違いがないように思うが・・・・」
| |||||||||||||
「論理の検証は省かせてもらいまして、次に進みます。 今まで確認したことはふたつあります。ひとつはISO認証は外部の要求に応えるだけの意味しかないこと、もうひとつはISO認証は一定レベルになっているかどうかの検証になっても改善にはならないこと。 では会社のシステム・・ここでは環境マネジメントシステムに限定しますが、を良くするためにはどうすればよいでしょうか?」 | |||||||||||||
「そうしますとISO認証によってとか、ISO規格を活用して組織の改善を図ることはありえないわけですから・・・会社を良くするのは、その会社自身が考えならないということになりますね。そしてそれはISO規格を利用することもできないように思えます」
| |||||||||||||
山田は川端がそう言うのを聞いて驚いた。まさか川端が地動説を語るとは想像もしなかったから。
| |||||||||||||
「おっしゃる通りですね。認証は外部への証明ですから、認証しようとしまいと組織内部への影響はなく、またISO規格は仕様書ですから改善のツールにはならない」
| |||||||||||||
「そして企業、すべての組織はそれぞれがすべてユニークだから、個々の組織を良くする方法はすべて異なり、それぞれの会社が自分にあった方法を考えなければならないということです」
| |||||||||||||
「待ってくれよ・・・・・例えば文書管理を考えたとき、ISO規格を参考にすることによって社内の文書管理の仕組みの改善が図れないものだろうか?」
| |||||||||||||
「福原取締役、ISO規格には文書は、制定前にレビューしろとか識別しろ、あるいは決裁をしろと書いてありますが、それは結局のところ仕様書ですから、どのようにレビューするのか、どんな方法で識別するのか、決裁方法などはそれぞれの会社がその会社に見合った方法を考案しなければならないということになります。 ISO規格を参考にしても、改善も仕組みの設計もできません。できるのはISO規格つまり仕様書の要求を満たしているか比較検証することだけです」 | |||||||||||||
「うーん、そういうことになるのか?」
| |||||||||||||
「私もそう思います。そうするとISOのため何かをするという発想はそもそも間違いです。認証そのものについては、社外からの要求があればISO認証せざるを得ない。そのときは現状を調査して規格を満たしているかを検討して、欠けているものがあればそこを追加することになります。つまりまず現実、実態から始めることになります。そして規格を満たした時点でそれ以上の改善はないことになります」 一同沈黙 川端がそのようなことを語るとはそこにいた全員が思いもよらないことだった。 福原が沈黙を破った。 | |||||||||||||
「しかしISO14001でいっている継続的改善はどうだ?」
| |||||||||||||
「あれはISO規格が継続的改善をすることを要求しているだけで、ISO規格通りにすれば継続的改善できるという意味ではありません。 良く考えるとというか、そもそもISO規格は仕様書にすぎませんから、好き勝手なことを書いてあるだけで、企業に貢献する内容ではありませんね」 | |||||||||||||
「うーん、そう言われるとそう思えるが・・・」
| |||||||||||||
「ちょっと話がそれますが、ISO事務局というものを考えてみます。この部門の機能は何かと考えると、何もないように思います。ISO審査で見せているものが会社の実態と違う場合・・俗にダブルスタンダードと言われますが・・その場合は、嘘を説明すること、上品に言えば審査員をごまかして帰すことでしょう。 しかしISO審査で会社の実態を見せるなら、うそをつくこともなく実態とISO規格を通訳する必要がありません。ですからISO事務局の存在意義もありません。 先日、藤本部長のご案内で関連会社のISO審査を見学してきたのですが、そこがすごいのです。会社のあるがままを見せて『さあどうだ!』という感じです。そして審査員も『規格では』などという言葉を語らず、現実をみてISO規格を満たしているか否かを判定しているのです。ああいった審査ならISO事務局はいりませんね」 | |||||||||||||
「審査員は一般社員にも質問すると思いますが、そのとき社員がISO規格を知らなくても、ISOの用語を知らなくても審査ができるのでしょうか? 実は認証機関への質問状でもそれを考えていたのですが、それで問題ないのかどうか自信がありません」 | |||||||||||||
「作業者も事務員も自分の仕事の意味と上長方針を理解してそれを実行すること、それがすべてじゃないのだろうか。そこにはISOとか規格の文言など介在する余地も必要もない。 審査員はそこから権限や力量やコミュニケーションや是正処置などを読み取るべきだし、それが審査というものだろう」 | |||||||||||||
「しかし『ISO規格ではこうなっている』というような言い方をされると、聞かれた社員は対応できません。そこはISO事務局が通訳する必要があると思います」
| |||||||||||||
「通訳が必要になるのは審査員がその会社の言語を理解しないからだ。審査員のほうでその会社のルールや文化を理解して、現実をみたり聞いたりすべきなんだと思う」
| |||||||||||||
「でもそういう審査員はいないですよ」
| |||||||||||||
「いや、そういう審査員を見てきたから私も驚いている」
| |||||||||||||
「川端君の話からするとその会社のISO審査見学は大変ためになったようだね」
| |||||||||||||
川端はあいまいにうなずいた。
| |||||||||||||
「お互いにISO規格とISO認証についての共通認識に至ったと考えます。とすると、弊社の環境監査における不適合の是正処置というのは、困難か否かはともかく、対策はもはや明白であると思えます」
| |||||||||||||
「弊社の環境監査では不適合が5つありました。 ひとつは環境側面をしっかりと把握していない、ふたつは環境側面の運用手順が不十分、三つは教育が不十分、4つは文書体系がふたつあること、5つは内部監査、順守評価が機能していないでした。5つあげられましたが考えると実際はひとつの問題なのかもしれません。 ともかく提示された不適合について対策案を考えてみましょう。 桧垣君、ホワイトボードを部屋の中央に持ってきてくれ」 桧垣が会議室の隅からホワイトボードを打ち合わせテーブルの脇に転がしてきた。 | |||||||||||||
「私が個々の対策案を書いてみますから、みなさんのご意見をいただきたいと思います」 川端は『環境側面をしっかりと把握していない』と書いた。そして対策案を説明した。 | |||||||||||||
「環境側面の特定と決定方法が見直すことが必要です。 まず点数方式は止めましょう。本来なら新設備導入や新化学物質導入時の使用可否判定結果を著しい環境側面の決定手順にするべきでしょうけど、一足飛びにそこまですると問題かなと思います。それにこれからの会社ではなく歴史というか現実がありますから・・ 以前の山田さんのご意見がありましたが、10年前に当社がISO14001認証をしようとしたときの方法、つまり法規制、事故の恐れ、損失金額の三つの観点で対応する必要性を検討して、対応しなければならないと判断したものを著しい側面とするという方法で行こうかと思うのですが・・」 | |||||||||||||
「方法というか切り口は妥当かと思うが、結果はどうなんだろう?」
| |||||||||||||
「福原取締役、先日とはお互いの意見が逆になってしまいましたね。ISO規格が言っていることから考えると、元々管理していたものが著しい側面であるはずで、結果がおかしくなるはずはありません」
| |||||||||||||
「なるほどなあ〜、じゃあ、この問題は単に審査員に説明する方法の問題で、実質的なことではないと理解して良いのだね?」
| |||||||||||||
「もちろん認証機関がどういうかという問題があります。それこそが10年前に当社がこの方法を止めた原因ですから。ですから方向が決まった後に認証機関の見直しも含めて認証機関との交渉が必要となります。それについては川端係長の説明の後に私から提案したいと思います」
| |||||||||||||
「わかった、川端君、じゃあ次に進もう」
| |||||||||||||
川端はホワイトボードに次の課題を書いた。
| |||||||||||||
「これは実は先ほどの環境側面の把握の問題と同じなのに気が付きました。 要するに真に管理をしなければならないものを著しい環境側面としていないからこんなことが起きるです。事故が起きる恐れがあるなら事故を起こさないように、法規制が関わるものなら法を守るように、運用手順を具体的に記述することでこの問題は解決するでしょう。 もちろん実際には真の環境側面を見直せば何十件あるのか、それについての手順書、具体的には要領書もありますし、掲示板もありますし、サンプルもあるでしょう、そういったものを見直すとその仕事量は膨大なものと思います」 | |||||||||||||
「川端係長のご心配はわかります。ただどうでしょうかね? 現場では文書にしてはいなくても暗黙知というか伝承もあります。我々がフォーマットを決めてそういったものを現場で書いてもらうような方法をとればその作業は進められると思います。そもそもISO事務局とか環境部門が手順を作るという発想がおかしいですよ。手順は仕事をする人が考えて決めることです。 それに一挙にしなくても順次整備していけば良いと思います」 | |||||||||||||
「そうだねえ、ISOの見直しということで各職制に私の方から指示することにしよう」
| |||||||||||||
川端は頭を下げて言う。 「こういう風に考えると、バーチャルではなく実際の仕事と密接なつながりがあると実感しますね。やりがいというのはこういうものでしょうか? 三番目ですが、教育が不十分というものでした。これも教育と考えるのではなく、手順書を整備する過程で、その業務に従事している人に確認してもらうという手順で進めたいと思います。 なにごとも初めに実態ありきですから、現実をそのまま手順といいますか作業標準にして、それを現に仕事をしている人に見てもらう、そしてそれを遵守してもらい、以降不具合とかあれば都度直していくということがまっとうな方法かと思います」 | |||||||||||||
「いや、実にわかりやすい、それがいいと思うよ」
| |||||||||||||
| |||||||||||||
「四番目ですが、4つは文書体系がふたつあることです。 この答は既に出てしまいました。ISO文書をなくしてしまい、なくては困るものについては本来の文書体系の中に取り込めばおしまいです。そうすれば文書の位置づけの問題もなく、矛盾も発生しません。ただこれも仕事量は膨大です」 | |||||||||||||
「川端係長、実際に進める前にISO文書の内容を精査して、仕事量を見積もる必要がありますね。膨大とおっしゃいましたが、単にISO規格条項対応の文書も多いですから、考え方を変えたことによって不要になるものは単純に廃止すれば良いと思いますよ」 もう6年くらい前になるが、私はISO14001認証して2年目の会社から文書の見直しをしてくれと言われたことがある。そこは典型的なダブルスタンダードであって、会社の正式文書ではなくISOの審査で見せるための文書をパイプファイル1冊分作っていた。 私への依頼はこのダブスタをなくしてほしいということであった。私はパイプファイルを一日かけて読んだ。そしてこのファイルにとじられているISO文書なるもの一切合切を捨てても全く問題ないと見切った。 そしてわずかばかりのごみの分別とか省エネのルールなどを総務課長の押印で各部門に配布することで間に合うと判断した。 もちろん環境マニュアルは見直さねばならなかったが、従来からの会社の規則やこれから総務課長印で発行する掲示物などを引用することでマニュアル改定もあっという間である。 もちろんあっという間と言っても数日はかかったが・・・ 私の失敗は、あまりにも簡単に処理してしまったので先方の感謝が足りなかったことだ。実際よりも困難で大変な仕事量だと思わせた方が、ありがたみがあっただろうと思う。 | |||||||||||||
「そうだねえ、今まではISO規格条項対応で文書を作っていたからね、2004年改定の時は条項番号がずれたところがあり、わざわざ文書番号を振りなおしたりしたけど・・考えてみると、あれはばかばかしいことだったね」
| |||||||||||||
「これもISO見直しということで各部門に協力依頼をすることにしよう。負荷を心配することはない」
| |||||||||||||
「5つ目は内部監査、順守評価が機能していないということです。 これは今後の方向性を十分議論しなければならない問題です。 まず今までISO14001の内部監査を独立して行っていました。今後はISO9001と合わせるのか、あるいは従来のままで行くのかということもあります。 しかし基本に立ち返れば、監査部の業務監査をこれに充てるというのが筋だと思えます」 | |||||||||||||
「うーん、確かにこれは品質についても同じことになるね。業務監査で行うようにするなら監査部と話し合わないとならないな・・ それこそ形式的に統合しても意味がないのだから、環境監査で何をするのかを明確にして、それは監査部でできるのか、環境の担当者でなければできないのか、ということをはっきりさせないとならないね」 | |||||||||||||
「従来のISO14001の内部監査は規格対応の質問が多かったですが、そういうのではなく会社規則を守っているかどうかを調べるなら業務監査そのものですね」
| |||||||||||||
「山田さん、業務監査だけでISOの内部監査の要件を満たすと考えますか?」
| |||||||||||||
「もちろん満たしますよ。ISO審査員の中には、ISOの内部監査と業務監査は全然違うなんて語る人も実際にはいますが、ご本人も何が違うか分っていないと思います。ともかくそれは間違いです。また監査部の人がISO規格を知らないからダメだと語ったISO審査員もいましたが、笑ってしまいますよね」
| |||||||||||||
「おいおい、そこは問題にならないのか? 監査部の者がISO規格を知らなくても大丈夫なのかね?」 | |||||||||||||
「そもそもISO認証とはISO規格とおりに会社の仕組みを作ることじゃありません。何度も繰り返して話していますが、ISO規格とは設計図ではなく仕様書です。環境マニュアルは規格要求と会社の実際の手順を参照する対照表です。そして社員はISO規格など知らなくても、会社の規則を知ってそれを守っていれば・・」
| |||||||||||||
「ああ、わかった、わかった。 つまり会社の規則がISO規格要求を満たしているのだから、会社の規則を完璧に守っていればISO規格適合であるということだ。論理学の三段論法そのものだね」 | |||||||||||||
「そのとおりです。もっとも、そんな基本的なことを理解していない審査員もいますので、指導が必要な場合も多いですね」
| |||||||||||||
「もう一つは順守評価をどうするかということです。これも考え方を議論してなにを順守評価に充てるかを検討する必要があります」
| |||||||||||||
「川端君、順守評価とはどういうことなのか、私に分かるように説明してほしい」
| |||||||||||||
「順守評価とは法を守っているかどうかを確認することです」
| |||||||||||||
「ああそうか、じゃあ毎年総務部が社内の遵法点検をしているよね。あれを順守評価に充てればどうだろう?」
| |||||||||||||
「環境法に限定していませんけど大丈夫でしょうかね? 山田さん」
| |||||||||||||
「ISO14001の序文にもあるように、別に環境法規制だけを調べるものでなくても良いのですから、全般的な遵法点検を順守評価に充てるのはまっとうなことでしょう」
| |||||||||||||
「ちょっと発言させてください。 遵法をしっかり確認できているかが問題ですね。例えば先日の私どもが行った環境監査ではマニフェストの記載漏れなどが見つかっています。また現場監査では資格のない人が危険物の作業に従事していました。ISOのための順守評価だけでなく、総務が行っている遵法点検でもそういった不具合を見つけていなかったわけですから、実効性という意味で不十分ではないでしょうか?」 | |||||||||||||
「うーん、確かに現状では問題だな。しかしそれは総務が行う遵法点検が順守評価に当たらないということではなく、総務が行う遵法点検の精度をあげなければならないということだ。 これは総務部長と相談して方法を検討することにしよう。もちろん環境法規制というのは多種多様だからそれぞれの法規制について総務の遵法点検でカバーしているかの確認がいるな」 | |||||||||||||
「大体こんなところでしょうか・・ これで今回の環境監査の是正の方向の目星がついただけでなく、ISO規格を素直に読んだときに当社の仕組みがそれを満たしていると言えると思いますが・・ 問題は認証機関をどうするかということがありますね。今までの認証機関と審査員のレベルでは不適合が多発するのは明らかですから」 | |||||||||||||
「まっとうなISO認証をしようとすると認証機関を選ばなければならないか・・おかしな話だが、それが現実だろうね。
おい、桧垣君、この前の話はどうなった。認証機関へ声をかけたのか?」
| |||||||||||||
「はい、まず我々がまっとうな方法を取ろうとすると、多くの認証機関はまったく話がかみ合わないだろうと思いました。それで説明に来てほしいという前に、先方のレベルを調査して一定水準のところへ当社に来てほしいと声をかけることにします」
| |||||||||||||
「よしよし、それでどこまで進んでいるんだ?」
| |||||||||||||
「まずいくつかの設問を設けたアンケートを送りまして、その回答をみて面接に進もうと考えています。今アンケート案ができたところです。こんなものでいかがでしょうか」 桧垣はそういって皆にA4の紙一枚を配った。
| |||||||||||||
「では少し、説明させてください。 考え方ですが、認証機関の考え方や審査方法について包括的な質問をしようとすると、膨大なものとなります。ここでは品質工学の手法を使って・・」 | |||||||||||||
「おいおい、本当に品質工学の手法なのか?」 藤本が茶々を入れる。 | |||||||||||||
「藤本部長、調査項目が多数ある場合、全項目について検討を行うのではなく、調査項目をカテゴリーごとにマトリックス配置し、対象の性質をティピカルに示す組み合わせをいかに少数選択して効率的な抜取調査を行うかという考え方はおかしくないと思います」 桧垣はまじめに応えた。 | |||||||||||||
「いや、すまなかった。冗談だよ」
| |||||||||||||
「今お話しましたが、認証機関の考え方について全般的に把握しようとすると大変なことになります。そこでいくつかの項目のみで、考え方と力量を把握できないかと考えました。 第一問の『貴認証機関の審査は弊社の経営に貢献するとお考えですか?』という設問は、ISO認証というものについての認証機関の考え方を問うています。 ここで・・」 | |||||||||||||
「待ってくれ、私にその心を当てさせてくれ。 経営に貢献する審査をすると回答した認証機関は、経営というもの、そしてISO認証の本質を理解していないと評価するのだろう?」 | |||||||||||||
「そのとおりです」
| |||||||||||||
「しかしそのような地雷というか明らかなことで、墓穴を掘るところがあるものだろうか?」
| |||||||||||||
「実際には多くの認証機関は『経営に役立つISO審査』という意味不明なことを語っていますから、最初のスクリーニングにはよろしいかと思います」
| |||||||||||||
「ハハハハハ、そう言われたんじゃ認証機関もいい面の皮だね。どちらが審査するのだかわからない」
| |||||||||||||
「ウェブサイトをながめただけですが、インターネットに掲示しているのがその認証機関の本音なら、この第一問で認証機関の半数は落第です」 一同賛意を示す。 | |||||||||||||
「第二問『有益な環境側面についてどのような審査を行いますか?』は単に有益な側面があると考えているかどうかの調査だけでなく、ISO規格を正しく理解しているかという観点からの質問です」
| |||||||||||||
「これはちょっとひっかけが見え見えのように思えますが、どうでしょうか?」
| |||||||||||||
「まあ、今でも有益な側面があるという認証機関が2割あるという調査もあります。そういうところを足切りするだけでも意味があるでしょう。細かくは面接で確認できますし」
| |||||||||||||
「なるほど、ここではオオボケの認証機関を振るい落とせばいいのだね」
| |||||||||||||
「第三問『ISO用語を使わずに審査ができますか?』ですが、これは審査員の力量をみるものです」
| |||||||||||||
「意図はわかるけど、どの認証機関も『できます』という回答をしそうだね。この設問では真の力量を見ることはできないのではないだろうか?」
| |||||||||||||
「そう言われると、そのとおりですね。 『お前はバカか?』という質問に『はい、バカです』と答える人はいないでしょうね」 | |||||||||||||
「しかし『できます』と答える認証機関は、『我々はISOの言葉で聞かれても知らないよ』というメッセージを了解したことになる。だから審査員に審査のさなかに『ISO規格も知らない』なんて言わせないという我々にとっての予防処置ではあるでしょうね」
| |||||||||||||
「審査をしていて会社の人に『ISO規格も知らない』なんて言う審査員がいるのかね?」
| |||||||||||||
「いますよ。ISO審査を受けるためにはISO規格を理解しなければならないというのはこの世界の常識です。審査員によっては企業のEMSがISO規格適合であるのを調べているのか、企業の人たちがISO規格を理解しているのかを調べているのかわからないこともありますよ」 一同ドット笑った。 | |||||||||||||
「いえいえ、笑いごとではなく、そういう審査も数多くあるのです」
| |||||||||||||
「わかります、わかります。ともかくこの設問は適切でしょうね」
| |||||||||||||
「では最後の設問です。『組織側に適合の証拠を出させるのではなく、審査員が組織の実態と運用を見て、適合・不適合は判定できますか?』 これは若干、前問とダブりますが、規格の理解や力量ではなく、審査手法に重きを置いたつもりです。このふたつがダブっているというご意見が多ければ、前問を修正しようかと考えています」 | |||||||||||||
「いや、切り口が異なるのでお互いに補完するものだと思うよ。しかしこの設問に対しては、ISO170214.4.1『適合させるのは組織の責任』という項目を持ち出すところもあるでしょうね」
| |||||||||||||
「そんなことをいう認証機関は・・・いやたくさんあるのは間違いないがね・・・ISO17021を読みこんでいないことは明白だ。そのときは4.4.2を読めと逆ねじを・・」
| |||||||||||||
「なんかそんなことを考えるとワクワクしてきますね」 みんなは川端の言葉を聞いてドット笑った。 | |||||||||||||
認証機関への問い合わせ内容については、同志ぶらっくたいがぁ氏が行っている方法を参考にした。
私も認証を指導した会社では認証機関を決定する前に、複数の認証機関を呼んで規格の見解を質問させている。しかし、私の場合は規格の理解にとどまっている。ぶらっくたいがぁさんは規格の理解だけでなく、審査方法や認証機関の考え方まで広い範囲について質問している。私はそこまでは至っていない。
なんとかこのシリーズの終わりが見えてきた・・・・ように感じる
その9に続きます。
外資社員様からお便りを頂きました(2012.11.14)
おばQさま 今までのお話が凝縮されただけあって、かなり長い連載になりましたね。 最後まで楽しみにしております。 それにしても、川端氏の転向ぶりは凄いです。始めから地動説だった人より、天動説から転向した人の方が、天動説に対して容赦がないのは、心理の面でリアルな気がします。 パラダイムシフトが起きて、無気力にならなかったのならば、旧来の考えを徹底的に徹底的に否定する事が自己を肯定する有効な方法になります。 こういう無定見という定見は、日本では多いのかもしれません。 ですから、仕事が無くなろうが信念を曲げない天動説原理主義者は、本当は少ないかもしれません。 桃山から江戸初期に、不干斎ハビアンという人がいるのですが、この人は禅僧から切支丹になり、『妙貞問答』という日本の在来宗教を罵倒し、切支丹の素晴らしさを説く本を書きます。 この人は、旧来の宗教の知識があるので、質問形式で切支丹の教えを判りやすい日本語で説明が出来たのです。 そして、何と、最後には、切支丹も捨てて、過去の知識を利用して幕府の禁教令に全面協力します。 そして『破提宇子』(デウスを破る)という、切支丹の批判書を書きます。 ハビヤンの考え方が、今では嬉々として地動説を否定する川端氏の姿にダブってきました。 当時の典型的知識人の行動ですので、現代にも通じる行動原理なのかもしれません。 |
外資社員様 いつもご指導ありがとうございます。 私は過去の審査での応答を基に書いているだけですが、外資社員様は知識豊富でさまざまな事例を示されるので驚きます。私はそんなたいそれた考えがあって書いているわけではありません。 ISO事務局の転向くらいならかわいいものですが、審査員あるいはISOの指導的な立場の人の転向は・・まずないでしょうね。 過去言っていたことを否定することは命に関わるんじゃないでしょうか? でも彼らもこずるいですよね、だいぶ前(といっても2・3年前)ある審査員が「著しい環境側面を点数で決めろと言ったことはない」と語っていました。実は私はその審査員の審査を何度か受けたことがあるのです。 その審査員は確かに「著しい環境側面を点数で決めないとだめだ」とは言いませんでした。しかし点数方式でないと「客観性がない」とか「恣意的だ」とか言って適合判定しませんでした。しょうがなく点数にしたら即適合判定でした。 そういうことをしていて、身が危なくなると「著しい環境側面を点数で決めろと言ったことはない」なんて語るのは、不干斎ハビアン以上の危険人物です。 もっとも各認証機関にはボス的存在があるらしく、ボスが「これはこう解釈するんだ」とのたまわくと陣笠審査員は「ハイルヒットラー」と言うかどうかわかりませんが、その解釈で審査をしていると聞きました。 ISO審査員と言えど、真理を追究するわけではなく、普通のサラリーマンと考えれば、上司が「これはこうせいや」といえばおかしいと思ってもそれに従うように、まあ、そんなものでしかないのでしょうね。 ただ企業サイドにいて、会社に貢献するもの、ISOの意図を実現しようという、純真な(?)担当者はそういう無定見な審査員と衝突するのは必然かもしれません。 引退して半年もたつのにまだ未練がましくこだわっている私が一番醜いかもしれません。 ご容赦を |
ケーススタディの目次にもどる