2013.05.18
最近、マネジメントシステムとはなにかと考えている。(その1・その2)そもそも「マネジメントシステム」なんて言葉を普段なにげなく使っているが、それはいったいなんだろう?
いや、もちろんそれはISO規格で定義されている。
ISO9001:2008では定義がないが、引用しているISO9000:2006で「3.2.2 方針及び目標を定め、その目標を達成するためのシステム」と定義している。
ISO14001:2004では規格中に定義があり、「3.8 組織のマネジメントシステムの一部で、環境方針を策定し、実施し、環境側面を管理するために用いられるもの」とある。
でも、それを読むとまた別な疑問がわき出てくる。
「システム」ってなんらかの「目的」を実現するためのものでしょう?
それが己の目的や方針を自ら作り出すなんて、なにか変ですよね? まるで再帰代名詞のようだ。いや再帰代名詞ではなく、ありてあるもの、神様じゃねーのか?
システムとは目的が与えられたとき、それを実現するためのものなら納得ですが・・・と疑問が浮かびます。
おっと、良く考えてみましょう。
ISO9000の定義の原文で目標は「objective」で「purpose」でないから意味は通じるようです。いやだけど「方針」がマネジメントシステムの下位にあるのは、やはり変な気がする。ちょっと待てよと、ISO9000:2006で「方針」の定義の英文を探すと、定義はなかった。しかしISO9001:2008「方針5.3」の項番の英文をみると「(Quality) policy is appropriate to the purpose of the organization」となっており、日本語で一般的に使われている「方針」の意味ではないようだ。それは日本語の「方針」よりも下位概念のように思える。それなら理屈は通じるのだろう。
つまりISO規格を日本語に訳すとき、英語の意味通りの言葉にしなかったために、意味がずれてしまい、日本語訳のISO規格(JIS規格)の意味が分かりにくく、そしてあいまいになってしまったのではないだろうか。
本来なら翻訳の際に、ISO14001では、「objective」を「目的」とせずに「目標」と訳していればよけいな誤解を招かないし、一般的な日本語として問題なく通じるのに思う。
そして「policy」の訳が「方針」で適切かといえば、どうも意味合いというかニュアンスが違うように思う。「会社の方針」というと、日本では「社是」とか「理念」そのものか、それに若干文字を足したような高尚なものが多い。
うそだと思うならネットで会社方針でググって、いくつか読んでください
そのような日本語の「方針」は、ISOの「方針」よりも上位概念ではなかろうか。
20年前、1994年改定で4.1.1方針で品質に関する記述が少し変わった。審査でいちゃもんを言われたくない私は工場の方針の文言を変えようと工場長に伺い出たら、工場長は「これは方針ではなく施策ではないのか?」と言った。
|
本来なら原文の「policy」を「方針」ではなく、「施策」とか「作戦」あるいは「フレームワーク(枠組み)」と言った方が誤解を招かないのではないだろうか。
おっと規格の中で使われている「枠組み」という語も、人によって様々な解釈がされている。方針の項に「目標の設定及びレビューのための枠組みを与える」なんて文言があるが、これを読んで「枠組み」とは一体何かと悩む人もいる。ここは「枠組み」なんてあいまいというか、普段使わないような言葉ではなく、いっそのこと「フレームワーク」と言い切ったほうが良いかもしれない。
正直言って私が初めて「フレームワーク」という言葉に出会ったとき、いったいいかなるものかと見当がつかなかった。悩む以前の話である。しかしその後、ビジネスの本を読んでいたとき、「フレームワーク」というものを、ストラクチャやアプローチや組織などの概念図をあげてこんなものだと述べていた。それを見て、ナーンダそうだったのかと思った。
|
「方針」だとか「目的」だとか、日本人が一般に使う意味では企業経営の上の階層にあたる言葉を使ったので、原文を読んでない人(審査員を含む)は、ISOマネジメントシステムは経営のことだと勘違いしたのではないか。規格でいうマネジメントシステムはそんな御大層なもんじゃなくて、経営層が決定したことをいかに展開して実行するかを決めたものではないのか。素直に経営ではなく現場管理の方法を決めたものと受け止めればよかったような気がする。
話しがあちこちに飛ぶというかさまよっているが、「マネジメントシステム」とは何かということである。
今までの話で語ったことを規格の定義に代入すると
ISO9000:2006の「マネジメントシステムとは方針及び目標を定め、その目標を達成するためのシステム」という文は「マネジメントシステムとは企業の方針を施策や目標に展開し、その目標を達成するためのシステム」と言い換えることができる、というか、この方が正しい訳に思える。
そしてISO14001:2004のマネジメントシステムは「組織のマネジメントシステムの一部で、施策を定め、実施し、環境側面を管理するために用いられるもの」となり、これも違和感はない。
まとめると、「マネジメントシステム」というものを、とんでもなく重大とか上位にあるものと考えずに、会社の目的を達成するための仕組みであると考えるべきだろう。決して「目的」を作ったり「方針」を定めたりする階層のしろものではない。「マネジメントシステム」とは、会社の「目的」や会社の「方針」よりも下位にあり、そういったものを推進するための仕組みにすぎないということを認識すべきだろう。考えてみれば当たり前のことだ。
ISO審査で形容詞なしで「御社の方針は不適切です」と言ったなら、社長は審査員を叩きだすべきだ。恐れ多くもいやしくも一国一城の
ISOの方針は、企業をどのようにしていくかを
異議ある方は、ISO9001:2008の5.3を熟読してください。
そこで要求しているのは中身ではなく記載項目だけです。
具体的に言えば、ある会社が時代遅れの事業に進出しようとか、売れる見込みのない商品を売ろうとしても、それはISO審査の対象外である。見込みのある事業に進出しようとしても準備が不十分であれば不適合だ。そこで要求しているのは中身ではなく記載項目だけです。
そもそもシステムとは何かと振り返ると、その本質を理解している人は、あまりいないというか、特にISO関係者には少ないように思う。
「システムとはインプット、プロセス、アウトプットだ」なんて語ったISO-TC委員もいたが、それはある分野においてそういう使い方があるということにすぎない。そしてそれはISOのマネジメントシステム規格におけるシステムの概念とは、違うのではないだろうか。システムとは元々は国家体制とか支配体制という意味である。インプットがないシステムもあるだろうし、プロセスがないシステムもあるだろう。
フレームワークとは元々家屋の構造システムのことであったし、奴隷制度(The slavery system)がインプット・プロセス・アウトプットから成り立っているとは思えない。
|
またシステムとは情報処理とも関係ないし、コンピュータとも関係ない。そんなものが現れる前から、システムという言葉も概念もシステムそのものも存在していた。
もっとも人類が誕生したときからシステムがあったわけではなく、物事が複雑になりあるいは複数の人が共同作業をするとき、それらをうまく調整するために考えられたものがシステムなのだ。
マンモスを捕えようとすると、誰が落とし穴を掘るのか、見張りは誰か、追い回すのは誰か、槍を投げるのは誰か、そんなことを決めないとうまく事は運ばない。また国家が作られたのは灌漑農業の水路を作るとか、外から食料を掠めようと攻めてくる敵から住民を守るために、力を合わせなければならなかったからだ。目的を達成するために役割分担を決めたり、それぞれの仕事の内容を決めたりしたことが即システムと言ってよいだろう。
もちろんそのシステムの中には、インプットをアウトプットにするプロセスが存在したかもしれないが、それはシステムの本質ではない。
じゃあシステムの構成要素は一体なんなんだとなる。それは簡単だ。いつも私が書いているが、「組織、機能、手順」である。これらを持たないシステムはない。
先ほどのマンモス狩猟プロジェクトにおいて、組織とは指揮官、ワナを作成するもの、勢子、槍部隊、とどめ部隊、解体部隊などであり、機能とはそれぞれの組織がする仕事であり、手順とは掘る穴の直径何メートルで深さ何メートル、それをどこに掘るのかと5W1Hで示したものになる。
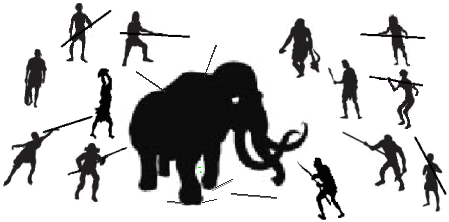
いやあ、あちこちからフリー画像を集めて組み合わせて描いたのですが、たっぷり30分はかかりました。
|
もちろんシステムは階層的に存在するから、上位システムの施策は下位システムの目的になる。この例で言えば、落とし穴を掘るという下位システムが考えられるが、そこでは落とし穴を掘ることはアプリオリの存在であり、それを実現するための組織、機能、手順が考えられる。
だからどの段階においても、その階層における目的や施策を実現するためにその階層のシステムは存在するというか発生する。決してシステムが、己の目的を生み出すとか施策を作るのではない。そうでなければ支離滅裂である。
回りくどいというか、私の頭の中にある低性能のCPUでも、なんとかマネジメントシステムというものが分ったような気がする。
しかし実はそれでも分らないことがある。
考えるのが面倒くさいからアイソス誌とかネットから見つけたなかで、私が理解困難な事例をとりあげる。
- マネジメントシステムの仕組みを活用しよう
マネジメントシステムは組織が対処しなければならないさまざまなものに生かせるはずである。 - 審査のためのマネジメントシステムから、経営に寄与するマネジメントシステムに変換する。
- 環境マネジメントシステムにより、組織全体での環境保全意識の向上や、省エネルギー、廃棄物の減量等を通じて長期的なコスト削減につながります。
- ISO取得により築いた"マネジメントシステム"を経営と結びつけられるよう、即ち経営改善にISOをうまく利用していただけるよう各種手法を用いてサポートさせていただきます。
- マネジメントシステムを使い倒す
組織を動かす仕組みがマネジメントシステムですよね?
↓
組織の活動を調整するのがマネジメントシステムであるなら・・・・これは今までの駄文から必然である・・・・生かす生かさないのではなく、マネジメントシステムに基づき動くしかないのではないのか?
はたして生かすべきだとか、生かせるはずだという議論の余地があるのだろう?
まあ、その発言者にはそう思えるということにしておこう。
第一点の疑問は、審査のためのマネジメントシステムというものが、マネジメントシステムと呼べるのかどうかである。もしバーチャルでお飾りならば、マネジメントシステムではなく真似ジメントシステムに違いない。
第二点として、そもそもその会社は過去からビジネスをしていたわけで、その会社のマネジメントシステムは存在しているはずだよね?
であればそれが真のマネジメントシステムであり、経営のツールとして機能しているのではないか。
第三点は第二点から演繹されるが、経営に寄与するマネジメントシステムに変えるまでもなく、今あるマネジメントシステムを表に表して、これが当社のマネジメントシステムだといえばそれでおしまいのようだ。
どうもよく分らない。マネジメントシステムとは活動を調整し管理するものである。だがそれは管理技術であり固有技術ではないし、モチベーションというかモラールをどうこうするものでもなさそうだ。環境保全意識向上に価値があるかどうかはさておき、意識向上のためにはマネジメントシステムよりも具体的活動や教育が必要ではないだろうか。そして省エネや廃棄物削減はマネジメントシステムでなく、固有技術やアイデアの収集とトライすることが必要だろう。
それともここで言う「つながり」とは、風が吹くと桶屋のように、ものすごく遠いつながりなのだろうか? いやつながっていると思われることなのか?
ものすごく難解な文章だ。ISO取得というのも変な言い方だが、今はそんなことに構ってはいられない。 笑
ISO認証のためのマネジメントシステムを経営と結びつけるとは、摩訶不思議な言い回しだ。経営と結びついていないマネジメントシステムというものが存在するのかという摩訶不思議
さらに経営改善にISOを活用するとは、またまた理解が難しい。
よって、パスしよう。もしこの文章を理解できた方はお教えください。
なお、この文章は日本の超大手企業の子会社のコンサルタント会社のウェブサイトから拾ってきた。
そういや昔「使い倒す」なんて言い回しが流行ったことがありました。女性を押し倒すのはいけません。それはともかくマネジメントシステムを使い倒すとか、使い足りないとか、使い過ぎとかあるのでしょうか?
会社(組織)の仕事はマネジメントシステムに基づいて動くのが鉄則というか、それ以外ありません。組織のマネジメントシステム以外にどんなシステムがあるかと言えば、労働組合のシステム、噂話のシステムくらいでしょう。仕事はすべて組織のマネジメントシステムで行われ、それ以外はありません。
はて、使い倒すとは??
マネジメントシステムとはなんだろうかと考えてみましたが、ISOコンサルタントとかアイソス誌に寄稿される方々にも、理解していない人は多いようだ。
理解している人がいないのかもしれない。
マネジメントシステムという概念を理解していない人が書いたものを読んでも意味がなさそうだ。
いやあ、この駄文は結構考えたのですよ。
それにしては日光の手前だったかも
名古屋鶏様からお便りを頂きました(2013/5/18)
30年ほど前、地元ラジオ局のパーソナリティの方が「ポリシーってのは、つまり好き嫌いのことなんだよ」と話しているのを聞いた覚えがあります。 つまり、ある目的を達成させるのに「どの程度、手段・美学に拘るのか」という事です。同じ目的地に辿り着くのに方法はひとつとは限りませんからね。 少なくとも「ご挨拶」を社員に周知したところで何も前には進まないんですけどね。 |
鶏様 そういやあ若者が(私から見てですから40か50)語るポリシーって軽いですよね。俺のポリシーはブラックしか飲まないとか生のウイスキーしか飲まないとか、演歌しか歌わないとか あまりまじめに考えることはなかったかと・・・ |
N様からお便りを頂きました(2013.05.19)
いつも拝見しています。いろいろ考えるきっかえになります。 ・情報システムに関わる身として・・・ Input-Process-Outputはシステムを理解するために便利なので使っているだけです。 モデルは現実を理解するための一つの方法で全てをカバーするものではないです。ですので、これがすべてではないですね。 でも、システム開発に関わっているとやはり考え方の整理には便利です。IDEF0が参考になるかと思います。 ・ISO9001の審査に関わる身として・・・ 「会社の目的を達成するための仕組み」 そうですね。これが一番すっきりします。 多分、議論をマネジメントシステムから出発するからおかしなことになるのかなと。 マネジメントシステムは経営をしっかりやっていこうとした時に必然的に出来上がる結果に過ぎないと考えています。もし経営に活かすというなら、マネジメントシステム自体を変えなくてはいけないし、マネジメントシステムの出来不出来、経営への寄与度を評価・分析しないといけない。そんなことは組織自身がやることで認証のため審査の対象外でしょう。 せいぜい話ができることは、第三者から見たリスクを話せるだけ。それすらも、相手組織にとっては自明の話でうやうやしく聞く話ではないだろうと思います。 「有効性評価」という言葉を使っていますが、なんだかなぁという気がして、悩みがどんどん深くなってゆきます。 |
N様 毎度ありがとうございます。 N様は経営コンサルをされています。それは成果を出さなければならないという逃げがない仕事のわけです。そのお仕事において、かっこいい言葉とか、難しそうな理屈というのは意味を持たないでしょう。要するに成果を出さなければお金を返せと言われるでしょうし、次の仕事はもらえないと思います。 私はN様ほど厳しい仕事ではありませんでしたが、二者監査で遵法上問題ないと言ってその後問題があれば私の責任であるのはもちろんですし、その責任は追及されます。 もしISO審査員が、その会社が有効で効率的であるか否かということの判定に責任を負うならば、浮ついた言葉を語る人はいなくなるでしょう。有益な側面があろうとなかろうと、方針の語句がどうあれ、数字で見える効果を出せとは言いませんが、その会社の仕組みが適正なのか有効なのか効率的なのかを、真剣に調べるはずです。 だけど現実はそうではありません。ですからシステムとはこうですよ、御社はおかしいよ、マネジメントシステムを導入しましょうなんて意味不明のことを語っていてもお足をいただける・・・そんなお仕事が成り立つというのが不思議です。 お金を稼ぐというのはもっと真剣に苦労するもののはずです。口先だけで、しかもその結果に責任を負わずしてお金を稼ぐというのは、世の中をバカにしています。 「御社の方針には枠組みという語句がありませんから不適合です」そんなことを語る審査員の頭をかち割って、脳みそが入っているのか、ぬかみそなのか、あるいはからっぽなのか見たいと思うのです。 |
うそ800の目次にもどる