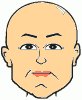14.09.18
マネジメントシステム物語とは前回の続きである。
佐田は大家からISO14001について教えてくれと言われ、関わりになりたくないので表で酒を飲んできた。ところが、夜遅く帰ってくると、大家とその息子、孫が佐田の家で帰りを待っていた。
「おお、佐田さん、失礼しております。お出かけと聞きましてお待ちしておりました」
| ||||||||
「はあ、そうでしたか。そいじゃお待たせして申し訳なかったですね」
| ||||||||
「佐田さん、夜分すみませんがお話をお聞かせください。父から伺いましたが佐田さんはISOの専門家とのこと、是非ともご助言をいただきたくお伺いしました」
| ||||||||
佐田はヨイショとテレビの前に座った。本来なら床の間を背に座らなくちゃいけないのだろうが、マンションには床の間もなく佐田にもそれほど威厳はない。 | ||||||||
「先ほど大家さんにお話を伺いました。なんでもお宅の菓子屋さんでISO認証するとのこと。私は認証するための方法とかどのくらいお金がかかるかの相談には乗れると思いますが、認証すべきか否かとか、認証の効果などについてはコメントしたくありません。結果が吉凶どちらであっても後々みなさんから感謝されることはないと思いますからね」
| ||||||||
佐田は正直に思っていることを言う。
| ||||||||
「佐田さんのその言葉を聞くだけで、どうもISOというのは胡散臭い感じがしますね。そういうものなのでしょうか?」
| ||||||||
「でも怪しいことなら佐田さんが大会社でお仕事としているわけはないですよね。ものすごくメリットがあるけどお金がかかるとかそういうことですか?」
| ||||||||
佐田は部屋を見回すと直美も娘も息子も立ったままだ。いったいどうすりゃいいんだと斜め上方を見上げてため息をついた。
| ||||||||
「うーん、まあお前たちも興味があるなら座りなさい。立ってられては落ち着かないよ。お宅は三人でお見えになられたので我が家も家族で対応します。私が暴れても家族が抑えるでしょう」
| ||||||||
大家は佐田の言葉を冗談とも本気ともつかぬ顔で聞いていた。
佐田はテーブルの周りに座った顔を見て、ヤレヤレとため息をついた。 | ||||||||
「ええと、まずお宅から質問に来たわけですから聞きたいことを聞いてください。私が考えるところを答えることにします。微妙なことは回答できないこともあるかもしれません」
| ||||||||
「まず一番聞きたいことですが、ISOすると商売が繁盛するのでしょうか?」
| ||||||||
「ISOというのはそういうことを約束するものではありません。ISOに合わせた活動した結果、会社が良くなることもあるでしょうし、その結果お客さんが増えるかもしれない。しかし会社が良くならないかもしれず、会社が良くなってもお客様が増えないかもしれない」
| ||||||||
「会社が良くなるってどういうことでしょうか?」
| ||||||||
「確かに会社が良くなるというイメージは人それぞれでしょうね。ISOでいっているのはルールを決めて、それを守りましょうということですかね。それ以上のことではないですね」
| ||||||||
「それが商売繁盛につながるのでしょうか?」
| ||||||||
「商売繁盛っていっても人によって思い浮かべるものが違うかもしれない。とりあえず、売り上げが増えるとかお客様が増えることとしましょう。とすると、ISOとは商売繁盛とは関係ないですよ。あるとしてもそのつながりは風が吹けば桶屋が儲かるというのと同じく、長いつながりの先にあるわけで直接的ではないです。 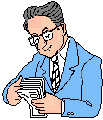 あのですね、商売繁盛というか利益を上げるというのはどうすれば良いか皆さんの方がお詳しいでしょう。利益を出すには売り上げをあげるか、費用をさげるしかありません。売り上げを上げるにはまずそのビジネスの規模がある程度大きいか、大きくないなら拡大しないとなりません。要するに損益分岐点を超えるある程度の規模が必要です。小さな市場しかなければ、その全部を占めても商売繁盛とは言えません。お宅はお菓子屋さんです。この市内のお菓子の市場規模はいかほどでしょうか。お宅が饅頭で勝負をするならば、お菓子の中で饅頭の規模はいかほどあるのか、それは過去拡大してきたのか減少しているのか、それは今後拡大できるのか、できないのか。競合する商品はどうなのか、そういったことを検討しなければなりません。
あのですね、商売繁盛というか利益を上げるというのはどうすれば良いか皆さんの方がお詳しいでしょう。利益を出すには売り上げをあげるか、費用をさげるしかありません。売り上げを上げるにはまずそのビジネスの規模がある程度大きいか、大きくないなら拡大しないとなりません。要するに損益分岐点を超えるある程度の規模が必要です。小さな市場しかなければ、その全部を占めても商売繁盛とは言えません。お宅はお菓子屋さんです。この市内のお菓子の市場規模はいかほどでしょうか。お宅が饅頭で勝負をするならば、お菓子の中で饅頭の規模はいかほどあるのか、それは過去拡大してきたのか減少しているのか、それは今後拡大できるのか、できないのか。競合する商品はどうなのか、そういったことを検討しなければなりません。ISOには種類がいろいろありますが、一般的には品質の9000と環境の14000です。それぞれ中身が異なりますが、どちらでいっても最終的には会社を改善していく到達点は同じになるでしょう。 さて9000で考えると、お客様の求める一定の品質の商品を常に提供するということです」 | ||||||||
「お客様の求める商品を提供できるようになるなら商売繁盛になるんじゃないか」
| ||||||||
「そうは言えんよ。さっき佐田さんがおっしゃったように市場規模が年ごとに小さくなっているときは良い商品を出しても、マーケット全部を占めても、ゆくゆくビジネスはおしまいだ」
| ||||||||
「なるほど、でも実際の市場規模の変化はどうなんだろう?」
| ||||||||
「日本全体を考えると菓子類すべてで3兆円、和洋菓子の市場規模は2兆円で微増だ。饅頭などの和菓子はほとんど変化がない。ただ和菓子が好きな人は高齢者が多く、若い人はケーキやプリンなどを好む。ということはこれから10年20年の期間を考えると減少していくのではないかという気がする」
| ||||||||
 「さすがにお詳しいですね。競合するのは同じカテゴリーの洋菓子やスナック菓子だけではありません。お菓子のかなりの部分は贈答用です。他家を訪問するときお菓子を持っていく代わりに、お酒とか商品券とかあるいはギフトのカタログに替わることも考えなくてはなりません。
「さすがにお詳しいですね。競合するのは同じカテゴリーの洋菓子やスナック菓子だけではありません。お菓子のかなりの部分は贈答用です。他家を訪問するときお菓子を持っていく代わりに、お酒とか商品券とかあるいはギフトのカタログに替わることも考えなくてはなりません。昔はタバコが贈答品の上位にありました。でも嫌煙ブームと愛煙家の減少、何よりも社会的にタバコを吸うことは不道徳とまではいかずとも上品ではないとみなされたことによって落伍しました。 あるいは訪問するとき何かを持っていくという習慣そのもののがなくなってしまうかもしれません」 | ||||||||
「なるほど、佐田さんもお詳しいですね。すると饅頭の売り上げを伸ばすには嗜好を変えることが必要になる」
| ||||||||
「三代目、おっしゃることはもっともですが、嗜好を変えることができますか? いくら有名俳優に饅頭を食わせてもその効果は一過性でしょう。あのですね、先ほど二代目がおっしゃいましたが、今は和菓子の中で饅頭は大きなシエアを占めています。しかし饅頭や和菓子を好むのは年配者です。20年後はその人たちはいません。饅頭の消費をより伸ばすには、若い人にお茶を飲む文化を伸ばさなくちゃならないでしょう。しかし今、緑茶の消費は年ごとに減少しているし、ペットボトルも多くなっている。ペットボトルのお茶で饅頭を食べるという文化があるのか、そのへんはどうなんでしょう。 あるいはコーヒーにあう和菓子の開発が必要なのか、その辺は専門的な研究が必要です。 ともかくISOが人々の嗜好を変えることは簡単にはできません。お宅がISO9000の認証をしてもお茶が好きな人が増えるわけがない。 そしてまた、お宅がISO認証しても新しい饅頭を作り出すにも役立たないでしょう」 | ||||||||
「それじゃISOってのはどんな役に立つんだい?」
| ||||||||
「ISOにももちろん守備範囲というか、持ち分があります。お宅が今作っている商品を、いつもばらつきなく同じものを作るようになるでしょう。お宅の売り子さんたちが、いつも同じ礼儀作法、言葉使いでお客さんに対応することになるでしょう。新人が入ればすぐにお宅の決まりを覚えることができ、同じ雰囲気を保つことができるでしょう」
| ||||||||
「そういうことになれば今よりも売り上げが増えるのかね?」
| ||||||||
「それはわかりません。しかしお菓子に出来不出来があるよりも、みな同じほうがお客様は喜ぶでしょう。またお客様の評判がいい売り子の挨拶や言葉使いを全員が真似れば、お店の評判が良くなるかもしれません。もちろん評判が良くならないかもしれません」
| ||||||||
「ISOの効果ってのはそういうものなんですか?」
| ||||||||
「そういうものです。私はお宅の頼んでいる税理士の先生がどんなことをおっしゃったのか分りません。あるいは私の思いつかないようなすばらしいアイデアがあるのかもしれません。しかしISOが約束できるのは、一定品質のものを作ること、一定品質のサービスを提供することですね」
| ||||||||
「でもそういった仕組みができるなら、それだけでも大きな効果ではあるね」
| ||||||||
「いや本当を言えば、そういう仕組みを作るのはみなさんです。更にその仕組みで実際に一定品質のものを作れるか、一定品質のサービスを提供できるかとなると、それは会社が工夫するしかありません。 いずれにしてもISOとはそんなものです。私は仲人口を語るつもりはありません」 | ||||||||
「会社が工夫するとは、どういうことでしょうか?」
| ||||||||
「ISOはこうあるべきというだけで、どうするかは私たちが考えるということですか?」
| ||||||||
「だけどさ、それだけなら、つまり商品のバラツキをなくすとか、売り子の言葉使いをちゃんとさせるということなら、お前が日々従業員の前で手本を示し指導すればすむことじゃないか。 お前が私用電話をしない、立ち寄った知り合いと無駄話しない、いつも笑顔でいる、客が来たら会釈する、そんなことをすれば皆が見習うだろう」 | ||||||||
 直美と娘がみんなにお茶を注ぐ。 訪問者が持ってきたらしい饅頭も広げる。 | ||||||||
「それだけならそういうことになるなあ〜」
| ||||||||
「確かにどう考えても会社の仕組みを変えても、客が増えたり売り上げが増えたりするとは思えない」
| ||||||||
「しかしね、佐田さん、それじゃどうしてISOの認証をしようとする会社やお店が多いのだろうか?」
| ||||||||
「はあ? そりゃそもそも勘違いしていませんか。ISOを認証している小売業は多いとは言えません。ISO9001はほとんどないでしょう。ISO14001にしても大手商社とかダイエー、イオン、コープのような大規模小売業だけと思います。小さくてもスーパーのチェーンなどで、チェーン店でない単独の商店でISO認証というのは聞いたことがないなあ〜 お宅は従業員全部で10名程度と伺いましたが、ISO認証で10名以下なんて製造業でもほとんどありませんね」 | ||||||||
「えっ、そうなんですか!」
| ||||||||
「つまり大企業向けということかね?」
| ||||||||
「必ずしも大企業向けということではないでしょうけど、大きなところでなければISOはいらないとも言えるでしょう。大家さんが先ほど言いましたように、お店ならご主人が手本を示し、注意してちゃんとさせることはできるはずです。 大きな会社では教育が行きわたらないかもしれないし、監督の目が届かないかもしれない。ISOとは経営者の目が届かない規模のときに、一定品質の製品、一定品質のサービス、愛想のよさといってもいいですが、そういうことを徹底させるのが狙いです。 お宅が10名程度なら二代目と三代目がいれば製造も販売も十分監督できてISOなんて必要ないのではないですか?」 | ||||||||
「なるほど、小さなところはそんな難しい手法を採用しなくても良いというわけだな」
| ||||||||
「会社の規模が大きいところでは経営者の目が届きません。ですからISOでなくても、職場というか仕事を細かく区切って、それぞれに管理者を置いて間違いの起きないようにするのが普通です」
| ||||||||
「間違いの起きないようにか・・・アハハハハ」
| ||||||||
「しかし経営者の目論見を管理者にちゃんと伝えるとか、仕事の判断基準を統一するには以心伝心ではできません。それで紙に書いたり見本を作ってそれで仕事をするようになります。そこんところはどんな会社でもお店でも同じでしょう。 このとき紙に決まりを書くにしても、見本を作るしても、どんな決まりが必要か、決まりにはどんなことを書くべきか、決まりの取り扱いをどうすべきかとなると、けっこう考えなければなりません」 | ||||||||
「ちょっと待ってください。決まりの取り扱いとはどういうことでしょうか?」
| ||||||||
「あまり専門的な言葉を使わないで説明しようとすると、かえって分りにくいかもしれませんね。 ええと、決まりを作るのは誰か、その決まりを決裁するのは誰か、どのようにみんなに周知するか、決まりを変更するにはどうするかなどがあります」 | ||||||||
「なるほど、言われてみればもっともな話ですね。私は経営工学を専攻しましたがそんなことを習ったことはありません」
| ||||||||
「専門的には文書管理といいますが、そういう手法は昔から考えられていてある程度決まった方法というのがあるのです。過去の試行錯誤で落ち着くところに落ち着いたということでしょう。もっとも最近は決まりというかルールを紙に書くのではなく、ウェブサイトで見るとか必要な情報を小出しにする方法などがいろいろあるようで、新しいテクノロジーを使った管理方法はまだ決定的なものがなく試行錯誤状況です」
| ||||||||
「なるほど、よく分ります」
| ||||||||
「俺はよく分らないが・・・ウチにだって会社の決まりはあるだろう。店長の仕事、工場長の仕事、シフトの決め方とか」
| ||||||||
「佐田さんの言っているのは、そういう決まりをどのように作るか、改定する方法などを決める必要があるということだよ」
| ||||||||
「ウチでは俺が決めたら、もちろん決める前には関係者に説明して同意を得てからだけど、朝礼で説明しているが」
| ||||||||
「もちろん御社にも仕事のルールがあると思います。その他、製造する手順や基準を決めておくことは必要になります。私は饅頭はまったくのしろうとですが、作るにあたって材料の配合とか時間とかいろいろあると思います。そういうのが職人の頭の中にあるだけでは、職人がいなくなると困りますし、あるいはレシピを忘れてしまうかもしれません。売り子にしても、お客様に、どんなときに、どんなふうに声をかけるか、どのような言葉使いをするか、ということを教育するでしょう。お客様から質問されたとき、苦情を言われたとき、どのように応えるとか、そういうことを決めておくと、なにかあったときいちいち考えなくても物事を処理していくことができます」
| ||||||||
「佐田さん、そういうのはお店をやっていると当たり前のことですよ」
| ||||||||
「じっちゃん、そうでもないよ。万引きがあったときどうすると決めてあってもなかなか徹底しないし、昨日だっけか、買って行ったのが古かったって文句を言われたよね。ああいったときどう対応するか決めておけば店の人が集まることもなかったのに」
| ||||||||
「確かに昨日は見苦しかったと思う。古かったのはともかく、どう処理すべきか決めていなかったもので、皆が集まってワイワイやっていてはお客さんの信用を無くしてしまう。」
| ||||||||
「話を戻します。会社やお店の規模が小さければ経営者の目が届きますから、あまりそういうルールというか仕組みを作らなくても仕事をしていくことができます。 しかし会社が大きくなると、あるいは支店を出したりすると、どこでも同じ客対応をすることはお店の評判を維持するためには必要です。そういうことはご理解いただけますね」 | ||||||||
「わかります、わかります。私はいつもそういうことで悩んでいますから」
| ||||||||
「そういう作るべきいろいろなことをまとめたものがISO9001規格だと思っていただければよろしいでしょう」
| ||||||||
「するとそのISOをすると仕組みがしっかりして問題が減るというわけですな」
| ||||||||
「実はそうではないのです」
| ||||||||
「そうではないとおっしゃいますと?」
| ||||||||
「ISO規格はこういったことをしなくてはならないと決めているだけで、そのためにはどうすれば良いのかはその会社やお店が考えなくてはならないのです」
| ||||||||
「ああ、さっきもそんなことをおっしゃいましたね。じゃあ結局私たちが考えて工夫しなくてはならないということですか?」
| ||||||||
「そうです。しかしなにをすべきかを全く何も知らないよりは、どんなことをしなければならないか、その項目と概要だけでも書いてあれば、仕事は早いでしょう」
| ||||||||
「ISO認証とか言ってましたが、認証ってなんですか?」
| ||||||||
「会社やお店がISO規格に合わせて会社の仕組みや決まりを決めたとしましょう。そのとき自分たちが決めたルールがちゃんとしているかは、ご本人たちには判断つかないと思います。他の会社のことを知らないとなおさらでしょう」
| ||||||||
「確かにその通りだな」
| ||||||||
「それでISO認証機関というのがありまして、そこにお金を払って会社の仕組みがISO規格に合っているかを点検してもらうのです。規格に合っていると認めてもらうと、免状がもらえることになります」 正確にはISO登録証は借り物である。 | ||||||||
「その認証してもらうとどんなごりやくがあるのかな?」
| ||||||||
「なにもありません。というか自分たちの会社の仕組みが間違いないと安心できるというわけです」
| ||||||||
「はあ!」
| ||||||||
「もちろんそのとき問題があれば、いろいろと指導してもらえるのですね」
| ||||||||
「いや残念ながら指導してはもらえません」
| ||||||||
「へえ!じゃあ?」
| ||||||||
「お宅にチェックに来る人を審査員と言いますが、審査員は良い悪いという判定はしますが、どうしたらいいということは言いません」
| ||||||||
「なぜ?」
| ||||||||
「ISO認証とはコンサルではないのです。仮に指導して問題があったら責任を負えないからでしょう。そこがコンサルとの違いです」
| ||||||||
「じゃあ審査を受けてダメだったとすると、会社の仕組みが不十分なことは分っても、どうしたらよいかわからない。審査を受けても何のメリットもないということですか?」
| ||||||||
「まあ・・・そういうことになりますか。でもまあ、不十分であるということが分かったわけです」
| ||||||||
「そしてISO規格に合っていると確認してもらっても、売り上げが増えることとは関係ないということですね」
| ||||||||
「そうですね、ただ一定品質のものができる、客の対応も一定のレベルになるとすると悪いことはないでしょうね」
| ||||||||
「先ほど佐田さんがおっしゃった、ISOと売上の関係は風が吹くと桶屋が儲かるくらいつながりが遠いってことがわかりました」
| ||||||||
「今の話を我々が良く考えて議論しなくちゃならないが、佐田さんのお話を聞くと、わしはISOなどする必要はないような感じだなあ〜」
| ||||||||
「もう少し調べてみましょうよ。市内でISO認証をしている商店とか工場はあるでしょう。知り合いに聞きあたってみますわ」
| ||||||||
「佐田さん、夜分大変申し訳なかった。ではこれで失礼いたします。」
| ||||||||
佐田がかけ時計を見ると11時近くになっていた。ヤレヤレ 大家一家が去った後、家族一同ドットため息をついた。 とはいえ、家族4人がこれほど長時間ひとつの部屋に一緒にいたなんて、過去数か月なかったことだ。これは大家一家のおかげか? |
こんな話し合いをしたことがあるかって?
ありましたね、20世紀のことでしたけど、難儀しました。まして私には一円にもなりませんし・・・
次回に続く
N様からお便りを頂きました(2014.09.18)
日本経営品質賞とISO審査は、もちろん基準や規格は異なるのですが、それにしても審査結果からのアウトプットの違いはどこから来るのだろうと思っていました。 大家さんとのやり取りを見ていると、もしかしたらと思うことがあります。 経営品質は、「事実前提ではなく価値前提」ということを標榜します。 これは、云ってしまえば、少々乱暴ですが「今の延長線上には未来はない。未来を見据えて線を描く」という事になります。 これは未来を題材にして議論するということになります。 一方で、品質問題は、過去と現在を問題にします。 品質問題が起きたらそれをどう修復するのか?あるいは品質問題が起きそうなインシデントを何で監視するのかといったことが興味の対象でしょう。 そこで議論するのはあくまでも過去と現在(近未来は含みますが)です。 この議論はどこまで行っても、将来の会社発展をするための議論はしません。 新しい規格がダメだなと感じるのは、経営環境・事業環境やリスクなどといったところに言及していることです。将来の事業リスクについては、深く考えると事業ドメインの再編や事業の拡大/撤退、新技術へのアプローチなど、今は手を付けていないことに対して議論することになります。 これは認証のスコープ外でしょう。 もし今の規格を、現在と未来にまで拡張したガイドラインと位置付けるのであればOKですが、認証のための要求事項と考えると無理でしょう。 経営者から見れば「余計なお世話」ですから。 |
ISO規格を作っている人たちは、自分たちが元々は品質保証とか品質管理を担当していたに過ぎないのに、いつのまにか経営の手綱を扱っていると、いや扱えるのだと勘違いしたのではないでしょうか? ですから、災害や事故などのリスクと事業上、コンペティターに関わることを同じリスクという範疇で取り扱おうとするところが勘違いも甚だしいのではないかと思います。 そういう意味では、<経営の規格>なんて自称することが笑いものではないでしょうか? |
マネジメントシステム物語の目次にもどる
 前回までのあらすじ
前回までのあらすじ