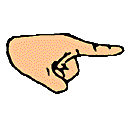15.06.01
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。但しここで書いていることは、私自身が過去に実際に見聞した現実の出来事を基に書いております。
審査員物語とは時は進んで2007年である。59歳になった三木は相変わらず審査員稼業を続けている。三木も年配になったこともあり、副部長なんて役職を仰せつかっている。ナガスネでは一般の審査員はすべて役職のないいわば平社員である。そして部長は取締役が就任するから、ラインに沿っての昇進というのはない。肩書もないので、それではモチベーションがあがらないので出向前に部長級であった人には、転籍して数年たつと副部長という肩書が付く。副部長といっても部下もなく何の権限もない。それに一人ではなく普通三・四人いる。それでも肩書が付いた人はそれなりにうれしい。
今でもナガスネの規格解釈は従来と変わらないが、三木は自分だけでも旧弊に拘らずまっとうな審査しようと心掛けている。何かの機会にナガスネの審査を批判されたり冷やかされることもあるが、事実なら仕方がない。メーカーだって性能が劣る製品には辛口批評を受けるのは当然だ。まあ、それを返上しようと努力するかしないかという点では大違いだけれど、
今日、三木はひさしぶりに会社にいて報告書のまとめと来週の審査の下調べをしている。
同期で審査員になった木村が三木のところにやってきた。木村は審査員になる前はナガスネのおかしな規格解釈をまともにするのだと抱負を語っていたが、今となれば悪しき考えそのものである。環境目的と環境目的のふたつの実施計画が必要です、環境側面は点数を付ける方法が一番です、方針には必ず規格の要件を全部盛込まなければなりません等々、木村はそういう生き方が楽だと考えたのだろうか。木村は結局金稼ぎが目的だろうと三木は思っている。社員の審査員はコンサルの兼業をしている人はあまりいないが、木村は休みがあればほとんどコンサルをしていると聞く。噂だが審査員の給料と同じくらいコンサルで稼いでいるらしい。まあ、それは個人の考えだからどうこうないが、規格解釈はまっとうになってほしいと心の中では思っている。
「三木さん、お久しぶりですね。会社にいるなんてお珍しい」
| |
「やあ木村さん、お久しぶり。そうなんだよ、今日は会社だけど昨日まで審査で月曜日からまた審査だ。木村さんもけっこう忙しいんでしょう?」
|
「三木さんと同じですよ。工場にいた頃は出張なんて年に数えるほどでしたが、今では毎年50回は飛行機に乗りますね」
| 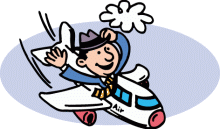 | |
「そんなにですか?」
| ||
「大阪に行くのも新幹線よりも飛行機が楽です。広島になるともう飛行機しかないですね」
|
「そうかなあ〜、広島空港からではリムジンで1時間以上かかるでしょう」
| |||||||||
「新幹線はいいのですが、そこまでのアクセスを考えると在来線は辛いですからね」
| |||||||||
「確かに、リムジンバスなら必ず座れますからね」
| |||||||||
「そういうこと。ところでちょっとお話を伺いたいのですが、お忙しいのでしょうねえ〜」
| |||||||||
木村が話しかけてくるのは何かあるのだろうと三木は思った。まだ時間はある、大丈夫だろう
| |||||||||
「私も少し休憩しようと思っていたところです。コーヒーでも飲みながら話を伺いましょう」
| |||||||||
二人は給茶機でコーヒーを注いだ。従来は紙コップを使っていたが、
 資源保護だとかISO認証機関で使い捨て紙コップは許されないとかいう声があって、今は全員マグカップを持ってきている。カップを洗う場所はトイレしかないので洗わない人も多い。三木は非衛生的だと内心思う。まあ余計なことを言ってもめるのも嫌だから黙っている。
資源保護だとかISO認証機関で使い捨て紙コップは許されないとかいう声があって、今は全員マグカップを持ってきている。カップを洗う場所はトイレしかないので洗わない人も多い。三木は非衛生的だと内心思う。まあ余計なことを言ってもめるのも嫌だから黙っている。と思って気が付いた。木村も規格解釈で正論を語ってもめるのが嫌なだけなのだろうか。とすると自分が大人げないということになるが・・・ 空いている応接室を探すと、今日は来客が少ないようで使われている部屋が一つあるだけだった。手近な部屋に入る。 | |||||||||
「今更なんですがね、マネジメントシステムを構築するってどういう意味なんでしょうか?」
| |||||||||
「どういう意味って、マネジメントシステムを作ることでしょう」
| |||||||||
「でもどの会社だって昔から公害防止組織とかは法律で決まっているわけで存在していたわけですよね」
| |||||||||
「そうですねえ。我々が使っているマネジメントシステム構築ってのは、ISO認証するために文書や記録を作る活動のことでしょう」
| |||||||||
「ええ、マネジメントシステム構築って認証活動のことなんですか。システムを構築するっていうと、全く新しいなにかを作ることとばかり思ってましたが」
| |||||||||
「マネジメントシステムといってもISO14001対応だけではなく、木村さんがおっしゃった公害防止組織とか、エコステージとかエコアクション21などいろいろあるよね。だから正確に言えばISO14001対応のマネジメントシステム構築という意味なんじゃないかな。つまり公害防止組織はあっても、ISO14001認証するための観点から見ると文書が足りないとか活動テーマが公害防止だけで全般についてはないというようなことですよ、そういった不足分を作ることをマネジメントシステム構築というと理解しています」
| |||||||||
「なるほど、でもそれって構築っていう言葉を使うほど大げさなことじゃないですよね。本でも講演でもマネジメントシステム構築という言葉がたくさん使われていますよね。あれってみなISO14001認証という意味で使ってるんでしょうか?」
| |||||||||
「さあてね、そこまではわからないけど。まっとうに考えると過去何十年と事業をしてきた会社に対してマネジメントシステム構築が必要ですなんていうのはちょっと大げさというか恐れ多いと思いますね」
| |||||||||
「私もそう思います。というか実は最近のことなんですよ。 コンサルしている会社の社長から『マネジメントシステム構築しなければならないと説明されたが、当社には過去からマネジメントシステムがある。それを改善するにしても見直しするにしても、構築という言い方はないだろう』と言われてしまいました。当社はそんないい加減な会社ではないと怒り心頭でしたよ」 | |||||||||
「まあそのへんは言葉の使い方だと逃げるしかないだろうなあ。あるいは木村さんがコンサルするときはマネジメントシステム構築ではなくISO認証のためのマネジメントシステムの見直しと言いかえるとか」
| |||||||||
「そうですねえ〜、ともかく誤解を招いたわけですし。それにISO14001で構築し、ISO9001で構築し、更には他のMS規格対応で構築するなんておかしいのを通り越して支離滅裂ですよ」
| |||||||||
「いや規格の数だけ構築するって言ってもおかしくないような気がするけど」
| |||||||||
「だって、ひとつのマネジメント規格対応でシステムを作ったなら、他の規格を認証するときは文書管理とか内部監査などは既に規格対応で仕組みがあるわけですから、ほんの少々補強するだけで完成するはずですよね。それを改めてシステム構築なんて言ったらおかしいでしょう」
| |||||||||
「確かに・・・・そうするとやっぱりシステム構築って言うのはおかしいよね」
| |||||||||
「元々はISO認証するのは大変なことだと認識させるために、そんな言い方をしたのでしょうか」
| |||||||||
「私は以前から疑問に思っていたのだけど、そもそもISO認証のためにしなければならないことって、そんなにはないんじゃないのかな。だけどあまりにも簡単だとコンサルの仕事がない、審査する方でも認証のありがたみがないということで、複雑というか重い仕組みを作らせてきたってことがあるんじゃないだろうか」
| |||||||||
「それは同感ですね。なんで素直に規格を読んであるがままを見せるという発想をしなかったのでしょうかねえ〜」
| |||||||||
「でもさ、従来からの会社の仕組みそのままでISO認証できますよなんて言ったら、木村さんの内職があがったりじゃないのかい」
| |||||||||
「それは・・・三木さんも口が悪い。」
| |||||||||
「もう何年も前のことだけど、審査員研修で木村さんと会いましたよね。早朝でまだ誰も来ていないとき、木村さんがおかしな審査や規格解釈を正すために審査員になりたいって言ってたのを覚えています。失礼だが、今の木村さんを見ていると、あのとき木村さんが批判していた審査員と同じようだ」
| |||||||||
「うーん、そう言われるとつらいですね。確かに長いものに巻かれろという生き方になってしまったかもしれません。でも稼げるときに稼いでおかなくちゃなりませんし」
| |||||||||
「だってだよ、木村さんだって私だって、世間並みの月給はもらっているんだし、退職すれば年金ももらえる。それに元の会社の退職金だって既に手にしているわけだし、なにをあくせくしているんですか」
| |||||||||
木村が言い返そうとしたとき応接室のドアが開いた。 柴田取締役じゃなかった柴田元取締役と営業課長の住吉が入ってきた。営業は対外的な折衝があるので全員、主任とか課長とか肩書を持っている。 | |||||||||
「おっと、失礼。空いているかと思った。ちょっとすまないが半分貸してもらうよ」
| |||||||||
「どうぞどうぞ、というよりも私の方はそれほど重要な話じゃありませんので失礼いたします」
| |||||||||
「ちょっと待ってくれ。うーん三木君は副部長だよな、いてもらった方がいいかな」
| |||||||||
「では私はこれで」
| |||||||||
木村は部屋を出て行った。 三木は部屋の奥、上座を柴田に譲って入り口近くに移動した。空いた奥の方に柴田と住吉が座る。 | |||||||||
「三木君も入ったことだから、改めて初めから確認しよう。 ええと住吉君が営業で訪問したとき、客先からいろいろと質問を受けたということだ。 質問内容は、当社の規格解釈と審査についてだ」 |
「最近は企業側も変にISO規格に詳しくなって、なにかといちゃもんをつけるのですよ。認証機関の考え方がまっとうかどうかを確認するなんてふざけたことを語っているところさえあるのです」
|
||||||||
「まあまあ、それはいいから。 それでどんなことを質問されどう回答したかということが問題だ」 |
「ええと10日ほど前に審査を受けたいので話を聞きたいと声がかかりまして、昨日お邪魔した会社でこのような紙を渡されて、当社の見解を回答してほしいとのことでした」
|
||||||||
住吉はA4の1枚ものを机の上に置いた。 柴田がそれを手に取りしげしげとながめてから、三木に渡した。 それには
とだけプリントしてあった。
「なかなか面白い設問だな」
「とりあえず私が考えたことをその場で答えましたが、先方は書面で提出願いたいということでした。」
| |||||||||
「住吉君は口頭ではどう答えたのかね」
|
「1はもちろんできますですね。 2は規格の意図を実現し、客観性、公平性を担保できるのは点数法であると答えました。 3はですね、ISO審査はマネジメントシステムの完成状況を見るので、原則として規格からマニュアル、手順書、そして実際の業務を見るという流れになると答えました」 |
||||||||
「まあいいだろう。三木君も異議はないね」
| |||||||||
「住吉さんのお話を聞く限り、私にはいずれも不適切に思えます」
| |||||||||
「はあ? 経営に寄与する審査ができない、点数法がだめ、審査方法が悪いというのか?」
| |||||||||
「うーん、反対のための反対ではありませんが、ウチの内部の考えでなく、世の中の一般的な基準とか方法を考慮する必要があると思います。 まず初めの経営に寄与する審査ですが、最近よく経営に寄与する審査をするというキャッチフレーズを使う認証機関がありますが、経営に寄与するってどんな意味でしょう?」 | |||||||||
「我々が行う審査は他社に比べて管理職の経験豊富な審査員が行うから、企業のあるべき姿を示す審査ができるという意味だ」
| |||||||||
「審査はIAF基準やJABの基準を基に行います。ですから本来は誰が審査しても審査基準に基づきIAF基準に則った一定水準であるべきです。もちろん気づきという形で個性を表すことはできるでしょうけど、それがもしアドバイス的なことになれば違反です」
| |||||||||
柴田は顔を赤くした。そんなことを真剣に考えたことがなかったのかもしれない。 しばしの沈黙ののちに口を開いた。 | |||||||||
「確かに、そもそも経営に寄与する審査とはどういうものなのだろう。住吉君はどう思っている?」
| |||||||||
住吉は鳩がまめ鉄砲をくらったような顔をする。
|
「それはあれでしょう、審査費用は安くはありません。最近は値崩れしているとはいえ、審査費用は数十万から百数十万はとりますから、企業にとっても大金でしょうね。 それだけのお金を払うなら、商取引に役にたたない登録証の紙一枚だけでなく、審査を受けて社内的に効果があったと経営者に思わせる必要があるということでしょう。言い換えると経営に寄与する審査をするのではなく、経営に寄与すると思わせる審査をする必要があるといえます」 |
||||||||
「お金を払う方はそう希望するのは当然でしょうけど、現実問題としてどのような審査が経営に寄与すると言えるのでしょうか。具体的に言えばウチの審査でオープニングとかクロージングあるいは審査の際のやりとりで、どのような話をすれば経営に寄与したと言えるのでしょうか。どうも私には経営に寄与すると言えるほどのことをしてきたつもりはありません。単なる作業改善とか危険についての注意喚起を経営に寄与するというのは針小棒大というか誇大広告でしょう」
| |||||||||
「経営者に他社の環境活動事例とか環境経営などの新しい情報を提供するというのはどうかな? 私はそういったことを常にしてきたが」 | |||||||||
「そういう指導というか情報提供を否定するわけではありませんが、それは経営に寄与するというほどのものでしょうか。それにあまり具体的なことになりますとガイド66などに抵触する恐れがあります」
|
「柴田取締役、他社に比べて当社の審査が優れていると良く宣伝していますね。具体的に何がどうすぐれているのですか?」
|
||||||||
「つまりインタビューや証拠のチェックをして、適合不適合をいうだけでなく、一層の改善方向を示したり、改善への気づきを出すとか、他社の事例などを教えるということだろうと思うが」
|
「そういったことは他社ではしていないということですね」
|
||||||||
「まあ正直言って他社がどうかは知らない。他社の審査を調査しているわけではないからな。ただ当社に出向してくる人や契約審査員の経歴をみると、元の企業で管理者をしていたり、一つの分野で専門家と言えるようなことをしてきた方ばかりだからそういう仕事をしてくれていると考えている」
| |||||||||
「実際に他社より良いかどうかわからないですよね。いやウチの審査が他社レベルかどうかさえ客観的な評価がされていません」
| |||||||||
「それは聞き捨てならないな。当社の審査が悪いというのか」
| |||||||||
「そうではありません。他社との比較したものを見たことがないということです」
| |||||||||
「だが、ウチの顧客というかウチに審査を依頼している会社には、毎回の審査の後にアンケートを出してもらっている。そこでは満足だという声が過半を占めている。そうだ、他社との比較と言えば、ISOの専門雑誌が行った顧客満足度調査でも当社は上位にいるぞ」
| |||||||||
「それは他社との比較ではありません。単に当社の心証を聞き集めただけに過ぎません。 だって普通の会社はISO審査を受けている認証機関は一つです。中には品質と環境が別の認証機関ということはあるかもしれませんが、同じ規格でふたつの認証機関の審査を受けているところはないでしょう」 | |||||||||
「三木君は何を言いたいんだ?」
| |||||||||
「別に何も主張していませんよ。話の始まりは経営に寄与する審査ができるかという設問に対して、できるにしてもできないにしても回答するには良く考えないといけないということです。 まず経営に寄与する審査とは何かをはっきりさせること、次に当社がそれを実行しているのかということ、他社に比べてそれは優れているかどうかということ、ついでに言えばIAF基準などに適合していることの確認でしょうか。明確に指導とかアドバイスなんていいますと支障がありますから」 | |||||||||
柴田は三木の言うことを聞いてしばし黙ってしまった。
|
「我々はトップが語ることを信じて営業しているわけですよ。他社に比較して審査が優れていると言ってくれないと困りますよ。今更経営に寄与するというのはなんだろうかと言われても」
|
||||||||
「柴田取締役、話しはちょっと変わります。先ほど住吉さんが見せてくれた質問状にあった点数方式ですが、もうあれを推奨するのを止めませんか。あれには私は以前から疑問を持っています」
| |||||||||
「三木君とは過去何度も点数方式について話したことがあったね。なぜ君はそれほどまでに点数方式に反対なんだ?」
| |||||||||
「反対するというよりも、点数方式が妥当だとは思えないからです。ウチの規格解釈は独特と言われていますよね、いろいろな意味で。中でも点数方式が典型的でナガスネ方式とかナガスネ流と呼ばれていることはもちろんご存知ですよね。実際にはかなり批判されているわけですが」
| |||||||||
「我々はウチが指導してきた方法に誇りを持っているがね。いちゃもんをつけるような奴らは無視していればいいんだ」
| |||||||||
「でも、いちゃもんかどうかわかりませんよ。彼らが正論かもしれません」
| |||||||||
「フン、彼らが正論だと、どうしてそう言えるんだ」
| |||||||||
「外資系の認証機関の多くは点数方式に懐疑的です。いや誰が言おうというまいと、初めから分りきっている結論を導き出すために、設定する多数の変数やその基準を調整していることに私は疑問を感じています。ISO14001の狙いである遵法と汚染の予防の実現は、そんなことではいけないと思うのです。 ナガスネ流は仕事を増やすだけですし、手段を目的化してしまっています」 | |||||||||
「君は元からおかしな考えだったが、君のような考えをする人がいるのでは私は引退できないよ」
| |||||||||
「はっきり言わせてもらいますが、ナガスネの名誉回復、ブランド価値をあげるには過去を反省してまっとうな方法を採用すべきです」
| |||||||||
「過去を反省だと!反省するほど悪かったと思っているのか」
| |||||||||
「以前のことですが、CEAR誌で環境目的と目標の二つの実施計画が必要かという議論がありましたよね」
| |||||||||
「あったな、朱鷺君がCEAR誌に寄稿したあれだな」
| |||||||||
「あれは結局ウヤムヤになってしまったようですが、ああいった考えが当社の考えである統一見解であるとみなされているということです。そして社内ではあれが正しいと信じられているわけです」
| |||||||||
「君はふたつ要らないということか?」
| |||||||||
「いらないというのが正解でしょう。ウチの対応は客観的に見ておかしなことを正当化、合理化しようとしてマスマス泥沼にはまっているという感じがしますね」
| |||||||||
「当社は日本の認証機関としては最初にISO14001認証を出してきた由緒あるところで、その考え方がおかしいとは思わんね。君自身の考えがおかしいと思わないのか?」
| |||||||||
「ISOは論理の世界ですから、こうあるべきとかこう考えるべきという発想そのものがおかしいのですよ。 規格を読んだとおりに理解して、現実がそれと矛盾がなければ適合と判断すべきだと思いますね。 ISO規格は要求事項に過ぎません。設計図面ではないのです。ですからその要求を満たす方法はいくつもあるだろうし、自分が予想したり好んだものでなくても要求を満たせばヨシとすべきなんです」 | |||||||||
「バカバカしい。そんなことでは企業を導いていくことなんぞできないよ」
| |||||||||
「認証機関の役割はその会社の仕組みがISO規格を満たしているかいないかを判断するだけです。その会社を導くと考えることが不遜というか間違いです」
|
「三木さんの話を聞いていると、経営に寄与する審査というのはそもそもがおかしいということになりますね」
|
||||||||
「私はそう考えています」
|
「うーん、そうすると他社以上の審査を提供するということは間違いだということになるのでしょうか?」
|
||||||||
「他社以上の審査というのもまた意味がいくつもあると思います。 指導や問題解決策の提供ということなら、そもそもがIAF基準違反でしょう。 しかし審査の質が他社以上であるというありえるわけでおかしくありません。もちろん当社が他社以上の審査を提供しているかどうかはかなり疑問ですがね」 | |||||||||
「いやはや、三木君がそれほどまでに当社を卑下していたとは知らなかったよ。君の認識では、ウチは規格解釈が間違っていて、審査の質も他社より悪いということかね」
| |||||||||
「はっきり言って当たらずとも遠からずでしょう」
| |||||||||
三木はなぜ自分がこんなふうなことを発言したのか不思議に思った。わざわざ柴田元取締役とけんかをするつもりはなかったが、成り行きからどんどんとおかしな方向になっていく。出向してから5年間のフラストレーションが抑えきれなくなったのだろうか。 最悪は辞表でも出すしかないなと内心思う。どっちみち来年定年になってナガスネMSに移ってもあと3年程度のこと、それからは契約審査員をするかしないかだ。ヘイコラするサラリーマン根性の生き方はもう御免だなという気がした。 |
「あのう、少し冷静になりましょう。 話を戻します。三つの設問についての回答についてですが、三木さんのお考えですと (1)経営に寄与する審査をしますかということについて言えば、そもそも経営に寄与するとは明確ではないので何とも言えない。当社としては審査とは規格適合/不適合を調査して判定することですということでしょうか」 |
||||||||
三木と柴田はホッとしたような顔をして住吉の方を見た。 | |||||||||
「住吉さん、そうだと思います。それと今気が付いたのですが、経営に寄与するかどうかは我々の範疇ではないと思います。経営に寄与するか否かは、会社側のすることです。我々が指導しようとアドバイスしようと、それを生かすかどうかは私たちではなく企業のすることです」
|
「なるほど、それはよく分ります。しかしそうすると経営に寄与する審査をするという言い方そのものが間違いになりますね」
|
||||||||
「その通りだと思います。経営に寄与する審査がいかなる意味であろうと、確かにその言い方は間違いでしょうね。」
|
「三木さん、点数についてはどうなんでしょうかねえ〜?」
|
「私は点数法を否定しません。ただ二つ条件があります」
|
「ふたつの条件とは?」
|
||||||
「まず一つは明らかなことですが、点数法でも良いが点数法でなくても良いということです。ウチでは点数法でなければ人にあらずという考え方が正論とされています」
| |||||||||
「やめろやめろ、お前たちは何もわかっていない。俺たちがISO14001の草分けなんだぞ」
| |||||||||
三木は柴田の声を気にせずにつづけた。どうせもうナガスネとはおさらばだ。予定より1年早くここを去ることになるが、もうどうでもいい。
| |||||||||
「もうひとつは本来点数法とは科学的なものであるはずです。例えば投資効率などを考えるときは点数法の考え方が使われています。例えばこのプロジェクトにいくら投資すればこれだけの効果があるというように、だからいくつかのプロジェクト案があればそれぞれの投資効率とかリスクを比較することができる。それは科学的と呼んでも良いでしょう。 しかしナガスネが世の中の企業に勧めている点数法はそうじゃありません。例えば電気使用量に点数をつけ、廃棄物発生量に点数をつけ、それらを比較するという点数法は科学的じゃありません。私は電気の10点と廃棄物の10点の環境影響が等しいという説明を見たことがない。では何を根拠に配点しているかと言えば、自分たちが希望するものが著しい環境側面になるようにということでしかない。あれは単なるごまかしです。しかも手間ひまばかりかかっている。 柴田さん、バカバカしいと思いませんか?」 | |||||||||
| |||||||||
「もう一つありましたね。三番目の最後は規格要求を質問せずに、現場をみて審査ができるかでしたね。 柴田さんはISO審査のプロだと自認されているでしょう。本当にそうなのでしょうか?」 | |||||||||
柴田は脱力したような顔で、住吉は生徒が教師を見るような目をして三木を見つめている。 | |||||||||
「審査の方法にはいろいろあるでしょう。しかし目的はなにかといえば必要な情報を集めて適正か否かを判断することです。 規格要求事項の文言にとらわれずにその意図を満たしているかを確認すべきです」 | |||||||||
「なんだとう、黙っていればいい加減なことを、 じゃあ、お前は規格要求事項の一字一句に拘らずに満たしているかどうか調べるというのか、そんな審査は正しくない」 | |||||||||
「何を持って正しくないというのですか。今のナガスネの審査の多くがいい加減な規格解釈、審査員が考えている方向への誘導、証拠・根拠を示さない不適合、そういうのを正しくない審査というのです」
| |||||||||
「一部に稚拙な審査員がいるかもしれないが概ねは適正だ」
| |||||||||
「そうでしょうか? 仮に一部であっても稚拙な審査があるならば判定委員会でそれをチェックし是正をかけるべきじゃないですか。過去の多くの審査報告書を見ると判定委員会が機能しているとは思えません」
| |||||||||
「なにもない黎明期から認証機関を立ち上げてきた俺たちの苦労を知らんくせに」
| |||||||||
「そういうこととは関係ないでしょう。昔からおかしかったんですよ、ナガスネの審査は、 今週行った会社では緊急事態にしたくないものだから、小規模なものは事故と呼んで緊急事態ではないという理屈でしたね。最近漏洩事故が発生して仕事を止めて全員総出で流出した油を回収していましたが、それは単なる事故で緊急事態ではないそうです。 どうしてそうしたのかと聞くと、数年前に柴田さんが指導したと言ってました。そういうことでいいんでしょうか」 | |||||||||
6/2追記 1997年の当時、名前は忘れてしまったが、ISO審査の前に審査合格するかどうか点検してもらうのが普通だった。なにかいかさま臭いし、認証機関も気にしていたのかホンチャンの審査で来る審査員とは別の審査員を派遣して客観性を維持しようとしていたようではあった。 ともかく当時私が働いていた工場でも30万円ほど払ってそのオプションを頼んだ。 文書が悪いとか表示が退色して読みにくいとか、いろいろダメ出ししてくれた。そんな中で、我々が「緊急に手を打たなければならないこと」を緊急事態としていたのを、緊急事態が多いから減らせという。その審査員が言うには「緊急に手を打たなければならないもので一定規模以上のものを緊急事態にする」のだという。そうしないと対応手順を決める、テストをする、教育するなどが大変でしょうという。 という指導を受けて、重油流出なら20リットル以下は除くとか、影響が室内で留まったものは緊急事態ではないとか改定した。 だが良く考えると、いかに少量の漏洩でも、室内で留まっても、緊急に手を打たなければならないものは緊急事態だと私は思う。それに報道されている水質事故には10リットル以下のものもある。人様に迷惑をかけるものはすぐさま手を打たなければならないんじゃないか? 確かにISO審査のためには緊急事態は少ない方がいい。もっとも緊急事態がないとイチャモンがつくから非製造業ではビルのエアコンからのフロン漏洩などを緊急事態にしているところもある。しかしビルの店子が大家が管理しているエアコンからのフロン漏洩を心配してもしょうがないだろう。 ところであれから18年、あの審査員はまだ生きているのだろうか? |
初めはなかなかキーボードが進まなかったが、書いているうちに過去のトラブルを思いだし怒りがわきあがりドンドンと進んだ。
なにしろ過去20年間の怒りはまだ消えていない。
審査員物語の目次にもどる