16.06.27
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。但しここで書いていることは、私自身が過去に実際に見聞した現実の出来事を基にしております。
審査員物語とは今、陽子は大学のISO事務局で働いている。といっても決まった仕事がなくて、そのときそのとき、資料を作ったり会議の手配をしたり関係部門と調整をしたりとか、なんでも屋だ。学生が作った手順書などの添削もする。誤字脱字や文法だけでなく、言い回しや言葉使いなどは、やはり社会人は学生より長けている。
 |
それとISO活動のメンバーの相談相手になっている。なぜかまわりから陽子はISOに詳しいと思われている。実は陽子がわからないことは多い。しかし素人の疑問は夫に聞けばまず解決する。質問を持ち帰り、夕方、三木が帰ってきたら教えてもらい翌日には回答できる。三木が出張でも夜メールで問い合わせれば翌朝までに返事がもらえる。そんなことを半月もしていれば他のメンバーよりも詳しくなるのは当然だ。もちろん夫がISO審査員をしているというのは内緒だ。
今までの大学のISO認証の活動は三葉教授の思い込みで走ってきたようで、陽子から見てもおかしなところが多々ある。学生や職員が疑問に感じていたこと、わからなかったことの悩み事相談を一手に引き受けているような感じだ。
昼休みになって陽子がお弁当を食べようとしていると、井沢と宇佐美がコンビニ弁当を持ってやってきた。
「三木さんもこれからお昼ですか、一緒に食べましょう」
| 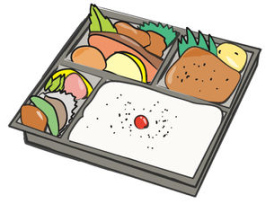 | |
「こちらこそお願いしたいわ、一人で食べてもおいしくないもんね」
| ||
三人は食べるより早くすぐに話を始める。 | ||
「三木さん、緊急事態ってなんでしょうかね?」
|
「ええ!宇佐美さん、何をいまさら? 宇佐美さんたちは研修を受けたんでしょう」
| |
「僕も特段ISO規格を習ったわけじゃないんです。内部監査員の研修の時にひととおり規格の説明を聞いただけです」
| |
「なにをおっしゃる、私なんて研修も何も受けたことがないわ。みよう見真似、門前の小僧じゃなかった門前の老婆ってとこよ」
| |
「アハハハ、三木さんは老婆じゃないわ」
| |
陽子は以前、井沢が陽子のことをオバサンと呼んだのを忘れていない。今回は余計なことを言わずにスルーした。
| |
「緊急事態って緊急に対処しなくてはならないことって書いてあるでしょう。それ以外何かあるの?」
| |
「内部監査員の講習の時、講師、講師は認証機関から来た主任審査員だったのですが、その人が言うには、事故や災害が起きてもすべてが緊急事態にならないということでした」
| |
「そりゃそうでしょう。自然災害だって緊急事態になるものと、ならないものがあると思うし、人が起こした事故だって全部が全部、緊急事態になるとも思えない」
| |
「人が起こした事故で緊急事態になるものとならないものがありますか?」
| |
「えっと交通事故でガソリンが漏れて側溝に流れ込んでいたら緊急事態でしょうけど、工場でタンクから漏れた化学薬品が防油堤内にとどまっているなら緊急でもないと思うわ」
| |
「それじゃ、災害で緊急事態にならないものがありますか?」
| |
「地震で人が生き埋めになったなら一刻も早く救出しなければならないけど、竜巻で屋根が飛ばされたとして、とりあえず怪我がなければ落ち着いて善後策を考えても問題ないでしょう」
| |
「でも屋根が飛ばされたら夜寝るところを探すのは緊急事態でしょう」
| |
「でもそれを緊急事態と言うのかどうか・・・対応するのに半日も時間的余裕があるなら緊急とは言えないでしょう」
| |
「緊急ってどういう意味なんでしょう? 辞書にどう書いてあるのかな」
| |
(井沢はバッグを開けてポケットサイズの国語辞典を取り出して開く) | |
「ええっと、『事が重大で、その対策などが急がれること』とあります」
| |
「あのう、ISO規格って元は英語でしょう。だったら国語辞典をみてもだめなのよ。英語の原文がどう書いてあるか、その英語の単語の意味を確認しなければならないの」
| |
「えっ、そうなんですか! そんなこと思いもよらなかった」
| |
「なるほどね〜、それじゃ・・・」
| |
(といいながらISO規格対訳本とポケット英和辞典を取り出す) | |
「緊急事態に対応する英語はemergencyだから、これを英和辞典でひくと・・・」
| |
「ちょいと、おじょうさん、それじゃ意味がないわよ。emergencyを英英辞典で引くのよ」
| |
「ああ、なるほどそういうことか、宇佐美君、英英辞典持ってる? 貸してよ emergencyとは・・・an unexpected and dangerous situation that must be dealt with immediately.ということは『好ましくなく危険ですぐに対応しなければならない状況』って、日本語と同じじゃない」 | |
「でも『すぐに対応しなければならない』だけじゃなくて、『好ましくない危険なこと』なんでしょう」
| |
「ああ、そうか、すぐに対応しなくちゃならないことであっても身に危険がない場合はエマージェンシーじゃないということか。 とはいえ身に危険がないけど緊急に対応しなくちゃならないってことがあるのかしら?」 | |
「彼女の誕生日に連れていくレストランの予約を忘れていたとか・・」
| |
「ああ、なるほど、でもさそれって彼女からビンタくらう危険がありそうね、 でも大体において日本語と同じイメージですよね」 | |
「ちょっとちょっと、immediatelyが日本語のすぐにという意味と同じかどうかも確認しなくちゃ」
| |
「ええっそこまでするの・・・immediatelyとはwithout delay、at once、very soon before or after something・・・待つことなく、何ものも置いてとか、可能な限りとか、なるほど漠然と急がなくちゃということじゃないのね。確かに夜までに決めればいいことはimmediatelyとは言わないみたいね」
| |
「以前、法律の時間に「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」なんて違いを習ったけど、あれでいえば「直ちに」にあたるのかな」
| |
「あったあった。「直ちに」はいかなる理由があってもすぐにって意味だったわね。ということは『好ましくなく危険で何よりも優先して今すぐ対応しなければならない状況』ってことになるのかな」
| |
「それでいうと竜巻で屋根が飛ばされて夜寝るところを探すのは、「速やかに」という程度でしょうかね」
| |
「うーん、そういう切り口からの見方もありますね。実は初めに僕が言おうとしたのはそういうこととちょっと違いました。その講師が言ってたのは別の観点だったのです」
| |
「別の観点というと?」
| |
「例えば薬品をこぼしたとき、一定量以上は緊急事態になるけど、それ以下は緊急事態ではなく単なる事故とかトラブルだって言ってました」
| |
「宇佐美さんの言っていることは、ボヤ程度で消火器で消せるなら緊急事態ではなく、119番しなくちゃならないレベルなら緊急事態だということかな。 うーん、なるほどそういう考えもあるのかもしれませんね」 | |
「でもね、統計をとるときならボヤと火災は区別できるかもしれませんけど、目の前で火が燃えているとき、大きくても小さくてもすぐに消火しなければならないんですから緊急事態ですよね」 | |
「そうよねえ〜。炎が小さいからって放っておくわけにはいかないし、いや炎が小さいうちに大きくならないように手を打たなくてはならないはずでしょ。それなら小さいことは緊急事態じゃないってのもおかしいよ」
|
「ただ実験室でアルコールランプを落としたようなことまで緊急事態にするべきかとなると、それも変だと思うんですよ。となるとその間に境目があるわけでしょう」
|
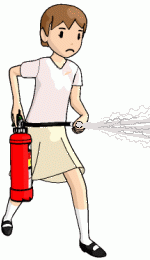 どうしたらいいのか | |
「そう言われるとそんな気もするけど・・・でもさあ、そうするとアルコール10リットル以上をこぼしたら緊急事態とか危険で、9リットルなら安全っていう理屈はないよね」
| ||
「そう考えるとなかなか面白いわね」
| ||
「三木さんは面白いっていうの? 私なら悩ましいっていうわ」
| ||
「だって悩むことないでしょう。単なる頭の体操よ」
| ||
「三木さんが考える緊急事態ってどんなものでしょうか?」
|
「あまりああだこうだと考えずに、すぐに手を打たなければならないものということだけじゃだめなんでしょうか?」
| |
「じゃあ、アルコールランプを落としたことも緊急事態となるの? そしたら緊急事態の対応手順を決めて、定期的にテストをしなくちゃならないわ」 | |
「ISOの緊急事態を特別なことと考えるのではなく、とにかくすぐに何とかしなくちゃおおごとになるというならそれは緊急事態じゃないのかなあ?」
| |
「でもアルコールランプも緊急事態になるかどうか気になるんですけど・・」
| |
「アルコールランプに火がついていようと点いていまいと、落とした割れたとなれば、すぐにふき取るとか水をかけるとかしなくちゃならないでしょう。まさか夜まで放っといて構わないということにはいかないわ」
| |
「アルコールの消火に水はいけないんじゃないのかな?」
| |
「アルコールの量にもよるでしょうけど、アルコールランプなら普通70から100cc、大きくても150ccでしょう。バケツ一杯水をかけたら消えるわ。 私が若い頃、コーヒーといえばサイフォンだったけど、一度テーブルからアルコールランプを落としたことがあってね、もちろん割れて炎が広がったの。あわてて水をかけて消したことがあったわ。 今はドリップだから楽だし安全よね」 | |
「フーン、油が燃えたときは水をかけてはいけないって習ったけど」
| |
「大量の油や石油なら駄目でしょうね。アルコールだってすぐには水に溶けず水の表面に広がるでしょう。けどアルコールランプ程度ならバケツ一杯の水をかければ楽勝よ。 あっ、今思いついたんだけどアルコールの火災でも小さいうちなら水で消せるけど、燃え広がったらだめよね。それこそ小さいうちに対応しなくちゃならないんだから緊急事態じゃないかしら」 | |
「そいじゃアルコールが燃えたときは、量とか状況によって対応方法を変えなくちゃならないってことになるのですか」
| |
「考える方向が逆というか、緊急事態が起きたなら、手近にあるものをいかに活用するかということが重要じゃないの? それこそが緊急事態への対応でしょう。 消火器がそばにあればいいけど、ないときは少しのアルコール火災なら砂でも水でも手近にあるもので消火しろということじゃないかな。消火器がないから手が出せませんなんて言ってるとそれこそ火事になってしまうんじゃないの」 | |
「えっ、緊急事態の対応ってそんな行き当たり場当たりなんですか?」
| |
「私も確固たる考えがあるわけじゃなくて、考えながら話しているんだけど、あるべき緊急時の対応とはそのとき使えるもので最善の策をとることじゃないのかしら。とはいえ臨機応変といっても適切な方法が思いつかないこともあるわけで、だからこそあらかじめいろいろと検討して最善の方法を緊急事態の対応として決めておくんじゃないかなあ〜、それが行き当たり場当たりを防ぐ標準化じゃない。 ただ宇佐美さんの論点である、アルコールランプ1個のときは緊急事態じゃなくて10リットル以上なら緊急事態という発想はおかしいという気がする」 | |
「ええと・・・・三木さんのご意見は、アルコールランプを落としたのも緊急事態に該当して、その時の手順を決めてテストをすることが必要だということかしら」
| |
「そう思いますよ」
| |
「そういえば緊急事態には教育訓練しろという語句はないですね。三木さん、どうしてなんですか?」
| |
「私もわかりませんけど・・・緊急事態が発生するものは当然著しい環境側面でしょうから、いや緊急事態が起こるかもしれないものが著しい環境側面になっていなければ4.3.1に不適合よね。 ともかく著しい環境側面であれば教育や訓練も必要でしょう。ただそれは既に規格の4.4.2教育訓練で著しい環境側面についての訓練を要求しているから、4.4.7緊急事態のところで改めて書くことはないといことではないかしら。法律とかこういった規格では同じことをダブって書くのを嫌うから」 | |
「なるほど、ともかく三木さんのおっしゃるように緊急に対処しなければならないことすべてが緊急事態なら理屈は一本通ってますね」
| |
「でもさ、そうなったら緊急事態だらけになって対応が大変ですよ」
| |
「対応が大変だっていっても・・・アルコールランプを落としたらどうするのか、こぼしたらどうするのか、そういう場合の安全な対応を決めておいて、実験の前に教えることが必要でしょう。さらに言えば実際には条件が細かく違う、部屋によって床の材質が違うかもしれない。消火器が近くにあるかどうか、蛇口が近くにあるかどうか、そういうことによって対応手順が違うから、そういうことも指示しなければならない」
| |
「それって、そういうたくさんのことについて危険性を検討し決めた手順を教えて、さらに大丈夫か定期的にテストをしなくちゃならないってことですよね、もう加速度的にすることが増えてしまうわ」
| |
「確かにそうなりますね。でもそれは必要なことじゃないのかしら うーん、思うんだけどISOで言ってることはそんなにおおげさなことではなく、文字に書いてある通りのことじゃないかって。緊急事態というのは日本語ではなにか重大なことのように聞こえるけど、元のエマージェンシーというのは『すぐに対応しなければならない』ってことだから、規格の『緊急事態への準備及び対応』ってところを『すぐに手を打たなければならないことについて』と読めばそんな大げさなことじゃないって気がしない? 現実にアルコールランプを落としても、学食でテンプラ油をこぼしても、とにかくすぐにふき取るとか消火するとかしなくちゃならないわけでしょう。単にそれだけだと素直に考えればいいんじゃないかなあ〜」 | |
「三木さんのお話を聞くとその通りと思うのですが、そうすると緊急事態が何十もあるいは百も二百もできるかもしれませんね」
| |
「でもね、学生さんの立場で考えてみて、実験する前にこういうことが起きたらこう対応しなさいと教えられていれば安心して実験ができるでしょう。緊急事態が増えては困るからとアルコールランプを落とす場合は緊急事態じゃないとして対応を教えなかったら、実際にそういうことになったらどうしてよいかわからないでしょう」
| |
「そういうことにも対応方法を決めておいて教えることにして、ただし緊急事態にしないという選択もありますね」
| |
「えっ、緊急事態にしないって、それってどういう意味があるの? 異常が起きたときどう対応するか検討し手順を決めて教育する、そして定期的に見直しをするのは同じでしょう。ISO審査員が来たときに緊急事態と説明するか、緊急事態ではありません、規模が小さいから事故と呼んでますといっても、しなければならないことは同じじゃないの」 | |
「でもさ、たくさん緊急事態があったら、そのテストをしたり、見直しをしたり大変な手間になるじゃないですか。すべて文書を作り記録に残さなくてはならないんですから」
| |
「でもね、必要なことならするしかないでしょう。まさかアルコールランプを落とした場合をISOの緊急事態にしないでいて、実際に起きたとき右往左往したらバカみたいでしょう。 それなら初めからそれを緊急事態にしておいて入学してきた学生に教えておくほうが気がきいてるわ さっき宇佐美さんは講師が大きなものを緊急事態、ちいさなものは事故に分けるとか言ったけど、その発想自体理解できないな。そうすればどんなメリットがあるのでしょう」 | |
「でも、でもですよ、そんなことをしたら手順書も記録もものすごい数になりますよ」
| |
「ああ、宇佐美さんが心配しているのは手順書のこと? 仕事をするうえで文書が必要なら文書を作り、記録に残さなくてはならないなら記録するというのはISOとは関係ないことじゃない?」 | |
「正直言いますけど、手順書をワープロするのは僕たちなんで、仮に緊急事態が100件もあったら・・・」
| |
「うーん、それじゃ、こうしたらどうかなあ〜、火事とかなにか一般的なことならそれをまとめて安全対応とか大学内の共通事項としてパンフレットのようなものにしておいて、それをみんなに守ってもらうというのはどうかしら。 実験室でアルコールランプを落としたとか、学食で食用油の缶を倒したというのは同じ種類だし、対応も同じように決められると思う」 | |
「そういうのは元から大学内の注意事項として決まっていますよね。入学したとき喫煙場所とか火災時の通報とか急病人が出たときの対応などについて教えられました」
| |
「あら、決まっているの? じゃあ、それをそのまま一般的というかどの部門にも共通な緊急時の対応手順としたらいいんじゃないのかな。過去からしていたことをISOに取り込むというのが一番いいことだと思うけど」
| |
「でもあれには急病人とか不審者とか犬猫が入ってきたときとか、環境以外にもいろいろと書いてあって、そのままでは緊急時対応の手順書とは言えないと思うけど」
| |
「そうだ、あの注意事項から抜き書きして環境対応としたらどうだろう」
| |
「あなたたち、どうしてそう環境とかISOの文書は特別という発想になっちゃうの? 過去からある文書や注意書きがISO規格を満たしていると考えたらいいじゃないの ISO審査で見せる文書は、『ISO規格要求=手順書』でなくて『ISO規格要求⊂手順書』なら問題ないでしょう。 あるいは規格の要求事項を元からある二つ以上の文書を合わせると満たしているならそれでもいいじゃない」 | |
「えっ、そういうことでいいんですか?」
| |
「なにがおかしいの? ISOのための手順書なんていらないのよ。必要なのはISO規格を満たしていること。過去からしていたことでISO規格を満たしているなら、なにもしないでもISO認証できるわ」
| |
「ほんとですか? 以前から三木さんのお話を聞いているとISOなんて大したことないって思ってらっしゃるようだけど、そこんところが・・」
| |
「たまたま緊急事態の話だったけど、私は全部が全部そう考えているの。環境側面だってISO認証のためにわざわざ調べたり決定したりするのはおかしいと思う。この大学は昨日今日できたわけじゃない。私が子供のころからあるわ。だから当時から法律を守り事故が起きないように仕事してきたはずよ。昔から施設課の永井さんのような人がいてそういった仕事をしていたはずよ。 だから環境側面は何かといわれたとき、各部門に使用している材料や電力や廃棄物を問い合わせて集計したり計算するまでもなく、今までどんなことについてどんな管理をしてきたかを問い合わせればよかったんじゃないかって思うの」 | |
「でもその方法では過去から漏れていたものを見つけることができないわ」
| |
「それはどうでしょう、ISOのために新たに調べたことだって漏れやミスがあるかどうかだってわからないわ。もちろんそれは審査でチェックされるでしょうけど、審査は抜き取りだしせいぜい数日間でしょう。それよりも何十年も日常の管理や行政の査察などで検証されてきたほうがミスや漏れがないだろうって気がするわ」
| |
「なるほどなあ〜、三木さんのお考えには現実はしっかりと管理してきたのだという自信というか信頼を持っているようですね」
| |
「確信があるのかと言われると困るけど、過去はでたらめだったという前提はどうかしら」
| |
「いままではたまたま緊急事態が起きなかったということはありませんか?」
| |
「確かにないとは言えない、けれどもリスクがゼロとか完璧というのは不可能でしょう。仮に今まで気が付かなかった不具合が起きたらその都度追加していけばいいんじゃない。 神ならぬ人間にできることには限度があり、できないこともあるのよ。私たちはできるレベルで妥協しているのよ」 | |
「緊急時に対応できないこともあるということですか?」
| |
「もちろん。ここにいて台風が来たら建物に戸締りをして室内で台風が過ぎ去るのを待つしかない。もし浸水したら上階に避難するだろうけど屋上まで水がきたらもう逃げるところはない。神様にお祈りするしかないわ」
| |
「まあそこまではともかくなにごとにも限度があるのはわかります」
| |
「話がどんどんそれるけど、ISO規格がいっているのは人間が解明したことをできる範囲でやれと言っているだけでしょう。わからないことも、できないことも、どうしょうもないのよ」
| |
「どうしようもないとは?」
| |
「科学的に解明できないこととか技術的にできないこととか、たくさんあるでしょう。 地球温暖化なんて言われているけど、二酸化炭素排出量を制限しても温度上昇は止まらない。だけどとりあえずCO2発生を少なくしようとか、その他の温暖化ガスの管理を強化しようということは、そういうことじゃないかしら」 | |
「緊急事態から話が大きくなってしまったわ」
| |
「でもそういうスタンスで緊急事態を考えると、ISOのためというのではなく万が一のとき被害を最小にするためということは理解してもらえたと思うの」
|

