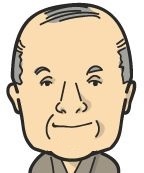17.10.02
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。
サラリーマンドラマで「給料を誰からもらっていると考えているんだ」なんてセリフは定番だ。
その問いに正解はないと思うが、ドラマでは「お客様です」と答えるのが正解らしい。
給料は誰からもらうのかという意味付けは多々あると思う。
それはからならずしも顧客、つまり製品やサービスを受け取る人から、その対価として支払われるものではない。
市役所の顧客は市民であることは間違いないが、給料は市民一人一人からもらっているとは思えない。そりゃ元をたどれば市民が払った税金ではあるが、税金を集めるところから市役所職員に賃金が支払われるまでのプロセスは複雑で長く、市民から頂いているという感覚はないだろう。ましてや「地方交付税」となると、直接行政サービスを受ける人から、サービスの対価としていただいているわけではない。「ふるさと納税」に至っては、明確に寄付金制度となっている。そうなると行政サービスを提供する人も受ける人も、見知らぬ人々の善意(お情け)で暮らしているわけか?
私は「ふるさと納税」制度がそもそも破綻しているように思う
デパートで販売員は客に売ってお金をいただいているという感覚はあるだろうが、デパートの施設管理を担当している人はそうは感じていないと思う。一般サラリーマンの顧客は誰かといったら、そもそも最終顧客ではない。自分に仕事を指示する上長だろう。より具体的に言えば何人も上に重なっているすべての上長ではなく、査定権限者というのが実感ではないだろうか。自分の給料を上げたり下げたりする人の言うことを聞いて仕事するということは恥ずかしいとかおかしなことでなく、当然のことだ。
「給料を誰からもらっていると考えているんだ」と問われて、感覚的に「お客様です」と感じている人は希少である。だがそういう考えを忘れてはならないと私は思う。
もちろん「お客様は神様です」なんてのはおかしい。客ならばなんでもいうことを聞かねばならないとか、客が上位であるという発想は私にはない。
20年くらい前、昔と言ってよいほど過去だが、深田雄介の本に「expected service」という言葉があった。「客は払った金に見合ったサービスしか期待してはいけない」という。深田雄介はJALのエライさんだった。ツーリストクラスでファーストクラスのサービスを要求するのは無理ですよと語っている。当然だ。
サービスの提供者と受益者は対等であるはずだ。そしてお互いが協力して製品サービスの質向上、お互いの満足度の向上を図るべきだと思う。
私は自分が当たり前と信じているし、そういう生き方をしている。いや、あなたがどういう考えか分りませんが、あなたも自分が当たり前と信じているし、そういう生き方をしているはずです。まあ、その点においては議論はないはずです。
違うのは信じている内容だけです。
 金正恩だって自分が正しいと信じ、トランプも自分が正しいと信じていることは同じはず。ただお互いの考えが違うだけ。
金正恩だって自分が正しいと信じ、トランプも自分が正しいと信じていることは同じはず。ただお互いの考えが違うだけ。しかし二人しかいないならどちらが正しいか定かではありませんが、クイズ100人に聞きましたとか、大勢で議論すれば、まあどちらが妥当かってのは分かるわけです。そしてほら吹き、約束やぶりは北朝鮮に軍配があがりますね。
それは嘘じゃありません。日本から大勢の人を誘拐(拉致)していき、その後の交渉で何度も何度も嘘をついた、エネルギー支援などでの協議をすべてうっちゃり、協定破りをしてきた北朝鮮を忘れてはいけません。私は北朝鮮の指導者だけでなく、北朝鮮すべてを許さない。
藤原に会ってから10日ほど経った某日午後4時、21世紀の渋谷駅山手線内回りホームに伊丹はいた。 ここで藤原夫婦と会う約束をした。午後4時と約束していたが、数分おきに来るどの電車なのかは来てみないと分からない。
ホームで簡単な挨拶をした後、3人は改札をでて外に出る通路の途中で表示のないドアにこちらですと案内する。ぽかんとする藤原夫婦を伴いそのドアを通る。 ドアを出た先はやはり駅の構内であるが、木造の建物で照明も暗く様相が全く違っていた。 | |||||
「はあ、ここは?」
| |||||
「ちょっと説明が必要ですね。ここは異世界というか日本じゃないんです。とはいえこの世界ではここは日本に当たる国です。時代的には1910年頃、日露戦争が終わって第一次大戦の前と考えてください。ここは東京都ではなく東京府です。山手線はありますが地下鉄はもちろん都電もありません。 これから私の家まで歩きます。なに10分もかかりません」 | |||||
駅を出た通りは舗装されていない あまり話をする間もなく伊丹邸に着いた。藤原は立派なお宅ですねと感心する。庭でも玄関でも、藤原夫妻は見るもの触るものすべてに驚いている。確かに立派な和風建築で庭木も植木屋を入れて手入れしているが、インフラとしての家は照明もプア、コンセントも少ない、光ファイバーもない、原始的なものだ。 幸子が玄関の外まで出て出迎えた。玄関で挨拶すると、藤原夫妻を客間に案内し風呂の用意ができているから入ってもらう。 そのあと幸子は張り切って台所を指揮している。 風呂から上がった藤原夫妻は客間に戻り二人で、おいおい、どうしようという感じで話し合っている。 ほどなく工藤が着流しで酒の一升瓶をぶら下げてやって来た。伊丹も着物に着替えて藤原夫妻を居間に案内する。 | |||||
「藤原さん、遠いところまでご足労頂きありがとうございます。ちょっと状況説明させてください。ここは私たちが住んでいる世界とは違う異世界です。実はこの世界が異次元なのか別の惑星にあるのかというのは私もよくわからないです。 この国は日本に該当するようですが、日本国ではなく扶桑国といい、天皇陛下ではなく皇帝陛下がいらっしゃる。時代は先ほど申し上げましたが1910年頃に相当します。  日露戦争にあたる扶呂戦争は終わりましたが、日本勝利ではなくぎりぎり引き分けて講和しました。それで賠償金も取れず領土も取れず、この国は今非常に貧しい緊縮財政です。
日露戦争にあたる扶呂戦争は終わりましたが、日本勝利ではなくぎりぎり引き分けて講和しました。それで賠償金も取れず領土も取れず、この国は今非常に貧しい緊縮財政です。そのおかげというべきか国民も軍隊も精神主義とか皇国不敗という思い込みはなく、論理的に国力を増強し軍備をしっかりしなければ国が滅んでしまうというリアリズムで動いています。それは良いことだと思います。 私もひょんなことからこの国に来て、曲折はありましたが品質管理や作業改善などを指導しています。それはこの国を強くするために力になりたいと思うからです。 ざっくばらんに私の提案を申しますと、藤原さんにこちらの世界で機械加工の指導をしてもらいたいということです 紹介遅れましたが、こちらは工藤さんといいまして、私が勤めている新世界技術事務所の社長です。技術コンサル会社と思っていただければよろしいです」 | |||||
「私は工藤と申しましてこちらの人間です。伊丹さんからもお話ありましたが、列強の圧力、日本を大国にさせないという、いやそれどころか半植民地にしておこうという諸外国の政策は厳しいものがあります。藤原さんのいる世界では、日清戦争、日露戦争に勝利した結果、不平等条約の改正を始めとして列強に近づいてきたわけですが、この世界の扶桑国は戦争に勝てず不平等のままというわけです。 この国は私の祖国ですから決して滅ぼさない、発展させなければならないと考えております。伊丹さんにはさまざまな指導をしていただいています。しかし技術というものは管理技術だけでなく固有技術がなければなりません。特に機械加工の技術です。伊丹さんから藤原さんのことを伺いまして、藤原さんにそれをやっていただけないかと考えたわけです」 | |||||
「はあ〜、もう、まったく驚きました。雲をつかむようなお話で・・・」
| |||||
そこに幸子と女中が御馳走を並べ始めた。 | |||||
「おいおい、まだ真面目な話中だぞ」
| |||||
「いやいや、食べながら飲みながらの方が話が弾むでしょう」
| |||||
「私も一緒させてもらいますね。こちらの世界では女性がお酌しなければならないのか知りませんが、みなさん手酌で飲んでください。その方がお互い気楽でしょう」
| |||||

実はそういうことは工藤と幸子で打ち合わせ済みだった。 幸子は藤原夫人、澄子の隣に座った。 伊丹はしょうがないというふうに首を振って藤原と工藤に酒を注ぐ。工藤が伊丹に注ぎ返す。 | |||||
「まあこれから長いお付き合いになると思いますんで、乾杯といきましょう」
| |||||
藤原は驚いた顔をしているものの乾杯といい杯を飲み干す。 | |||||
「伊丹さんもこちらに来た当初はあまりにも技術が遅れていて途方に暮れたようでしたが、計画的に着実に手を打ってきました。正直言ってあまり学問的な人とか、口だけの人はいらないんです。具体的には実際に仕事をやってみせることのできる人、問題があれば粘り強く頑張る人、そんな人が欲しいです」
| |||||
「藤原さんがみたら、目についたことを手当たり次第に改善しようという気になると思います。私もそういう感じでした。でも何事も一挙にはできません。まずは全体を把握して、指導していく順序を考えないと。すぐにできるもの、簡単ではないが重大なもの、現時点では実行不可能なものなどいろいろとあります。そういうことを考慮してまず大きな青写真を作って、それを基に着実に少しずつ少しずつ指導し改善していくという我慢ができないとだめです」
| |||||
「藤原さん、半年前、この世界にはノギスもなかったのですよ」
| |||||
「ノギスがないですって! ノギスがなくて仕事ができるものですかね? 想像もつきません」
| |||||
「それで伊丹さんがどうしたかというと、ノギスの基本形つまり物をはさんでバーニヤで細かい寸法が読める測定器
 の見本を作ってみんなに見せた。
の見本を作ってみんなに見せた。それを使ってみたこちらの技術者や作業者はすぐにその有用性を理解し、伊丹さんの作った見本を参考に、実際の物を測るにはどういう形がいいかと考えたんです。今ではその工場では自分たちが作ったノギスを使っています」 | |||||
「ほうー、そういう基本的なことからするのですか・・・それも自分がするのではなく、みんなにやらせる。大変な苦労をされているのでしょうね」
| |||||
「ちょっと重大なことなので、聞いてください。 工藤さんと私の基本的なスタンスですが、向こうの世界から最新の機械や道具を持ち込んで、そのまま使わせるということはしないんです。技術というのは自分たちが問題を解決しようと考え工夫することで進歩していくべきです。ものすごく進歩した機械を与えて使わせても、それはほんとの意味での進歩ではありませんしこちらの世界に貢献しません こういったアイデアがあるのではないかとか外国にはこういう機械があるよと示唆することで、みんなに考えさせて作り上げるという方法をしています」 | |||||
「わかります、弟子に教える時も一から十まで教えてはだめですね、方向だけ示してあとは考えさせないと」
| |||||
「そうです。ですから藤原さんが指導するときは、向こうから完成した機械とか道具を持ち込まずに、理屈とか機構を教えて考えさせてほしいのです」
| |||||
藤原はうんうんとうなずく。 | |||||
「ノギスさえなかったという話ですが、旋盤などの刃物は何を使っているのですか? 超硬はなくてもハイスはあるのでしょうか?」
| |||||
「歴史を紐解いたのですが、超硬合金はあと20年くらいしないと発明されません。 ハイスはアメリカのテイラーが数年前に発明したそうです。しかしまだこちらでは使われていません。日本で広く使われるようになるにはあと10年はかかるでしょう | |||||
「なるほど、そういう歴史を知っておかなくては、うかつなことを言ってしまう恐れがありますね。ついついダイヤモンドバイトを使えなんて口を滑らしそうだ」
| |||||
「藤原さん、ダイヤモンドバイトというのは実はハイスや超硬合金よりも古く、明治時代からあるのですよ | |||||
「えっ、そうだったのですか!、なるほど技術史を勉強しておかねばなりませんね」
| |||||
藤原は既に指導する気満々である。 伊丹が妻たちの方を見ると、幸子も澄子と仲良く酒盛りをして話に花が咲いているようだ。やれやれとちょっとホッとする。 | |||||
「工藤社長さん、それで私は切削加工の作業指導をすればよいのでしょうか? といいますか、それしか私はできませんから」
| |||||
「改善と言ってもいろいろあります。今伊丹さんがしているのは標準化です」
| |||||
「標準化とは?」
| |||||
「うーん、まずはこちらの図面の実態、工場の実情、生産管理の方法をご理解いただかなければなりません。 工場を眺めていただけるとお分かりになりますが、こちらの機械は機械ごとにモーターが付いているわけじゃない。ラインシャフトってご存知でしょうか? | |||||
「ああ、私が工業高校に入った頃にはもうありませんでした。でも子供の頃見たことがあります。天井に動力軸があって、それから個々の機械にはベルトをかけて動かす、あれですね」
| |||||
「そうです。もちろん機械はすべて単能機です。ただこの時代はけっこう | |||||
「なるほど、メカニズムという観点から見れば現代のNC万能、シーケンサー万能の世界よりも魅力あふれる世界ですね」
| |||||
「分かります、その気持ち。シーケンサーじゃ面白くない。リレーを組み合わせるとか、あるいはメカで論理回路もどきを組んだ入社当時が懐かしいです」
| |||||
「アハハハハ、まったくです。」
| |||||
「ともかくノギスもマイクロもない状況で生産するとなると、どういう方法になるかわかりますか?」
| |||||
「まったくの想像ですが、たぶん現物見本があって、それに合わせて作るということになるでしょうね。検査は限界ゲージですかね」
| |||||
「正解です。当然、寸法公差なんてのはありません。となるとバラツキの管理もありえない。測定できなければ統計的品質管理という概念はなりたちません。測定できないのですから、管理限界を引いて日常管理をしているところはまずないでしょう。理論的にも標準偏差というものが考えられてから、まだ10年しか経っていません。 いわゆる統計的品質管理というものを実施するには、必要な精度まで測定できること、統計理論が確立すること、計算する道具があることなど条件整備が大変です」 | |||||
「計算器というものはソロバンしかありません。計算尺は欧州では使われているようですが、この国ではまだです。実用化のためには理論だけでなく物を作れないとなりません。欧州の計算尺は木製なので、湿度の高いこの国では反ったり伸びたりで実用にならないのです。竹製で作ることを研究している人はいますが、まだまだこれから」
| |||||
「うーん、置かれた環境はとても厳しいのですね」
| |||||
「私はそういう現状を図面寸法を基に作るという形にしたいのです。そのためには、加工方法、機械、刃物、技能といったものを標準化しなければなりません。 しかし現実はなにもかもバラバラです。旋盤工もフライス工もみな自分で刃物研磨している。当然、自分がいいと思う形にバイトを作るし、人によって使う刃物も加工方法も切削条件も全く違う。とても管理状態じゃありません」 | |||||
「なるほど標準化とはねじとかIT公差ということでなく、刃物の管理とか加工時間の管理ということなのですね」
| |||||
「おっしゃる通り、とても一人二人の手におえるものではないし、1年とか2年で達成できるものでもない。日暮れて道遠しという感じですね」
| |||||
「そういうのをひとつずつしっかりと決めていかないと、大量生産とか互換性というものは確立できない。フォードの量産方法とかテーラーの科学的管理法と同様のことを、我々がここで始めたい。 一朝一夕ではできません。しかし30年後、1940年の製造現場を1960年代まで我々が進歩させることができたら、ものすごいことになります。戦争に勝つとかじゃありません。扶桑国は工業製品で世界を席捲してしまうでしょう。そうなれば戦争する必要がありません」 | |||||
「うーん、おっしゃる意味はよく分かります。それは大変な・・・・いや壮大でやりがいがありますね」
| |||||
「でもね藤原さん、仕事はそういうことですが、人間は仕事だけではありません」
| |||||
「はあ?」
| |||||
「生活があります。伊丹さんはご家庭ではあまり家事はされていないようです。しかし人間暮らしていくためには炊事・洗濯・お掃除、まあいろいろしなければなりません。 ここには電化製品がまったく存在しません。洗濯機、冷蔵庫、掃除機、いやいや電気釜もない。一般家庭で電気と言えば白熱電球しかない。藤原さんも奥様もそれで生活できますか?」 | |||||
澄子が自分のことを話しているのに気が付いて、工藤の方を見た。 | |||||
「はっ、なにか?」
| |||||
「今、こちらでは、家電品がなくて奥さんは大変だという話をしていたのです。 それからラジオもテレビもありません。そちらの世界の若者はゲーム機がないと生きていけないそうですが、こちらにはゲーム機もありません。藤原さんがテレビを観るのが楽しみなら生きていけないかもしれませんよ。 それから下水もありません。だから便所も水洗じゃない、それだけでお断りと言われるかもしれません」 |
「幸子さんのお話をお聞きしましたが、電気製品がないのは確かに大変ですね。なくて困るのは冷蔵庫、洗濯機、炊飯器かですかねえ〜 まあ下水は私たちだって結婚したときは下水はなかったですから驚きはしませんが。 このお宅には水道があるからまだ良いですけど」 | 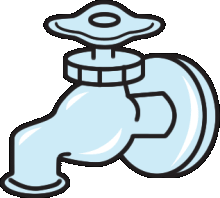 | |
「えっ、水道がない家もあるのか? それじゃ伝染病とか怖いなあ〜」 |
「区部では水道は普及しています。しかし長屋では1か所しかないところもあります。井戸端会議なんて言葉をご存知でしょう。あんなものですよ」
| ||
藤原は腕組みして考え込んでしまう。 | ||
「まあまあ、まだ藤原さんがこちらに来ると決まったわけではありません。それにこちらで仕事をするにしても、こちらに住まなければならないといこともありません」
| ||
「そうそう、実は私はこちらに住んでまだ半年です。それまでの数か月、伊丹は向こうからこちらに通勤していました」
| ||
「通勤? すると向こうの世界から山手線の駅まで来て、さっきのような・・・」
| ||
「そうです、そうです」
| ||
「ええと、大事な話ですが、こちらで指導できるかどうかというのがまずありますが、もしこちらで雇っていただけるとなると、いかほど賃金はいただけるものでしょうか。露骨な話ですが霞を食べては生きていけません」
| ||
「うーん、まず私たちと働くなら、賃金とか給料という発想をやめてほしいのです。 給料をもらうという考えではなく、皆さん一人一人が経営者だと考えてください」 | ||
「ほう、それはユニークな会社ですね」
| ||
「ハハハ、ユニークではありません。本来すべての会社はそうなのです。ただ会社が大きいとか、お客様と直接顔を合わせないなどから、そういう当たり前のことを忘れているのです。私どものように常にお客様のお相手をしていればその事実を忘れようがありません」
| ||
「おっしゃる意味がよくわからないですが」
| ||
「例えば伊丹さんの場合、軍の仕事、大学の先生への講義、企業の指導などをして対価を得ています。会社はそこから、所得税、建物の家賃、電気代、電話代、事務員、文具その他の費用を差し引きます。そして残ったものが伊丹さんの取り分です。こちらの世界は社会保険、健康保険などの制度が未整備ですから、それらは向こうの世界で個人的に加入してもらっています。それは皆さんがこちらの世界で差し引かれるお金が少ないということでもあります。 正直言って、私も藤原さんの技量というものを知りません。工作機械を扱う技術・技能が優れていても指導するにはまたべつの技能が必要です。 そしてまた次から次と問題にぶつかります。 あの、私たちはコンサル会社です。工場で問題が起きなければ、そもそも私どもに依頼がくるわけがありません。その会社の人が対応できなかった問題解決を依頼されるわけですから、私たちが請け負う仕事は簡単ではないことはお分かりでしょう。それを、逃げずに取り組む精神力、そして解決する能力が必要です。 ご質問の応えですが、藤原さんの力量次第としか言いようがありません。すごい力があるなら月10両以上稼ぐでしょうし、お客さんの依頼に応えることができなければ稼ぎはゼロです。 実を言って伊丹さんの給料は社長の私よりも多い。それは伊丹さんがそれだけの仕事をしているからです」 | ||
「ここの貨幣単位は円ではなく両といいます。1両が、そうですね10万か12万くらいですか。大卒初任給で月2両、女中が1両というところですか。私は月6両です。但しボーナスはありません。こちらでの生活費は現代の日本よりははるかに安い。そりゃそうですよ、物価が安いだけでなく生活水準が低いから。炊飯器や洗濯機がないということは、そういった費用がかからないということでもあります。 まあ月2両あれば夫婦で暮らすには十二分です。 それから向こうの通貨への交換などはそれなりのルートでちゃんとできます」 | ||
「なるほど工藤社長さんのおっしゃる意味がわかりました。それでは実際に工場を見せてもらってから、できるできないを正直に申し上げましょう。 ただ勤務形態に希望を言うなら、とりあえずは週2・3勤務でどうかなと思います。と言いますのはもしこちらでフルに仕事がないなら向こうでも仕事をしたいのと、こちらで指導する過程で検討とか試作することになれば、向こうの自分の工場でいろいろやってみることもあるかと思います」 | ||
「よくわかります。じゃあ仕事の話はおしまいとして飲みましょうか」
|
登場人物の名前 かってISO関係で名刺をいただいた人の名前を使わせてもらっている。木越、藤田、黒田、工藤、みなそうです。名刺はたくさんあるので名前が足りなくなる心配はなさそうです。
上野、後堂、南武、などは実在する人物は、お名前の漢字を変えて借用しました。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
日本で初めて舗装されたのは大津街道(京都―大津間の日岡峠)で石畳であった。東京都内では1873年銀座がレンガで舗装されたもの。アスファルト舗装は1878年頃から少しずつ使われるようになった。コンクリート舗装は1912年である。1910年頃は都内でもほとんどが非舗装だった。本格的に舗装されるようになったのは第二次大戦後である。
|
注2 |
ネット小説に「銀河連合日本」というのがある。好評のようで書籍版も出ている。 若干ネタバラシになるが、この物語の中では地球文明を「発達過程文明」と呼んでいる。生存のため、生活向上のため、いろいろと工夫し発明していくという文明をそう定義している。発展途上ではない、時と共に経時的に発展していくという意味である。 「発達過程文明」に対する文明は、滅んでしまった高等生物の古代文明を発掘しそれを活用するというもので、こちらには具体的な名称はなかったが、発達極相文明とか発展飽和文明とでもいうべきか? それはものすごくラクチンであるし失敗はないが、時間が経過しても新しい発明発見は起きない。結果として国民が成長しようという意思を失ってしまうことを小説の中で問題としている。 どことは言わないが、リバースエンジニアリングとか外国から技術を盗んできて大発展と誇っている国が東アジアにいくつかある。それに実を言えば過去の日本も「発達過程文明」ではなく、外国で発明発見された科学技術の工業的展開を図ってきただけではないかという気がする。 やはり自らが考え道を拓くということが人間の存在意義じゃないかなって私は思う。 |
注3 |
ハイス(高速度鋼)は1908年頃テイラーが開発して1910年特許とある本もあったが、ウィキペディアではテイラーよりも早く製造した人がいて特許にならなかったとある。正確なところは分からない。 参考文献 「ものづくりの科学史」、橋本毅彦、講談社学術文庫、2013 「新・機械技術史」、日本機械学会編、(社)日本機械学会、2010 |
注4 |
ダイヤモンド工具は明治時代中頃には鉱山の掘削で使われていた。昭和初期には製造現場でも使われるようになったという。
|
注5 |
昔の工作機械は個々の機械それぞれに電動モーターが組み込まれていなかった。 工場にひとつ大きなモーターや蒸気エンジンをおいて天井の動力軸を回し、それぞれの機械は天井の軸からベルトで動力を得て仕事をした。この天井に置かれた回転軸をライン・シャフトと呼ぶ。 古い映画を観ると工場のシーンでよく登場する。 |
異世界審査員物語にもどる
うそ800の目次にもどる