17.10.26
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。
ISO規格には版によって多少名称は異なるが「文書管理」という項目がある。だが文書管理というお仕事はISOなどできるはるか前からあり、その基本的事項、必須条件とかそれを満たす方法というのは確立されていた。だから元から文書管理の手順を定めていた会社では、ISO9001ができたからといって特段何事かが追加になったわけではない。
とはいえ文書管理とは簡単なものではない。
私が工業高校で機械製図という科目で習ったのは図面記号とか作図方法であった。会社に入ると図面に関わる仕事はそれだけでないことが分かった。入社時教育で初めて知ったことはいくつもあった。図面の効力つまり誰が書いて誰が検証して誰が決裁することにより、いつからその効力を持つのか。図面の発行方法、配布先、改定時の図面修正方法、改定記号、処理方法、旧図の処理方法、などなど。
図面改定が生じたとき、旧図をいかにして回収するのかということ、改定された図面をどのように周知展開するのか、旧版で作った部品の扱いをどのような打ち合わせで決め、どのように識別し管理するのか、そんなことを教えられたとき、いやはや、大変なことだと恐れ入ったことを覚えている。
高校生ごときにそういう実務を教えても、その必要性を理解できないだろうし、だからわざわざ教えないのだろう。
ISO9001:1987の4.5文書管理では次のように定めている。あれから既に30年、何度も規格改定されて記述は変化してきたが基本は変わらない。それは以下の通りである。
- 文書管理の手順を文書で定める。それは以下を満たすこと。
- 文書は発行に先立ち権限を持った人が審査し承認する。
- 関係部門において必要な文書の適正な版が利用できる。
- 廃止された文書は速やかに発行部門と使用部門から撤去する。
- 文書の改定は最初に承認した同一の者が審査し承認する。
- 変更内容を改定された文書または添付文書で明らかにする。
- 間違った版を使わないように最新版を台帳に記載するなどする。
- 何度も改定されたときは文書を再発行する。
ISO14001では上記のほかにlegibleという要件がある。JIS訳ではそれを「読みやすく」と訳していたために、難しい漢字とか言い回しがあると「読みやすくありません」なんて不適合が多々あった。そのように解説している本さえある。
残念ながらlegibleは「意味がわかりやすいこと」ではなく、「文字が鮮明で読みやすいこと」である。英英辞典を引くとlegibleとは「written or printed clearly enough for you to read」である。
「legible」の反対語は「illegible」で「difficult or impossible to read」で、「不鮮明」と訳される。「difficult or impossible to understand」でないことに注意!
「読みやすい」(legible) |
||
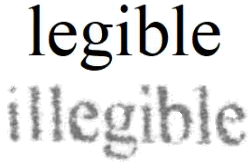 |
||
|
おっとそんなISO規格要求はない
なお更なる勘違いの予防だが、understandは「意味がわかる」ことで、recognizeは「認識する、気づく」である。あなたの考えはunderstandで、あなたが来たのにrecognizeである。ところで、そんな勘違いというかアホな不適合を出した審査員たちが、登録更新時に不適合になったのかどうか興味がある。
はっきり言って、審査員登録の更新時に不適合になった者は皆無だろう。それこそが問題なのだ。今ならそんな審査員をCEARの判定委員会は問題にするのだろうか?
話を戻す。しっかりした会社なら、どこでも会社規則とか手順書なるものを整備しているはずだ。
もちろん会社規則や手順書というものは紙に書かれたものであるから、必然的にそれをお
もちろん会社規則が空文化すれば文書管理もまじめに行われなくなり、その手順も形骸化する。そして何事においてもエントロピ増大の法則は真理であり、維持には常なる努力がいる。
前回の講義は管理図の話であったが、たまたま図面管理が不徹底という問題がみつかり、今月の講義は、対策案の説明とその検証ということになった。 | |
「前回、管理図の説明をしている中で業者に図面改定を通知していなかったことが判明し、その対策が宿題になっていました。今回はその是正策を考えましたので、その検証を皆さんにお願いします。ご賛同得られたら実施したいと思います。 そいじゃ軍曹から説明してくれ」 | |
「図面の発行管理を全面的に見直します。まず第一に配布した図面は絶対に朱記訂正させないこととします」
| |
「海軍工廠の中瀬大尉です。 それは、ええと改定があれば常に改定したものを複写して配布するということか?」 | |
「はい、そうです」
| |
「それは理想ではあるし素晴らしいことに聞こえるが、実際問題として実行可能なのか? 費用的にも負荷的にも大変なことになりそうだ。 砲兵工廠でそういう方法を採用されたら、海軍工廠でも同じくしろと言われかねない」 | |
「図面は絶対なものであるべきです。配布された図面に取り消し線を引いて改定後の寸法や注意書きが書かれるとか、それだけでなく再び改定されるとその朱記訂正した上に取引線が引かれというようなものは、見た目も良くありませんし間違いの元です。なによりも図面の権威、信頼性を損ねます」
| |
「うーん、今回の問題はそれとは無縁のように思えるが」
| |
「確かに今回は直接は関係ないかもしれません。しかし根本的なことを考えると、図面改定があれば常に改定図の配布と差し替えに旧図を回収するという仕組みがあり、そうであれば防げた問題です。いきさつがどうあれ、甲社から旧図は回収されたでしょう。 また朱記訂正された図面をみたとき、それが適正な修正なのか、悪意の修正かは判断できません。図面には決して書き込みを許さない、してはならないという意識付けにも朱記訂正するという方法は排除すべきと考えます」 | |
「複写するための工数は大丈夫なのだろう?」
| |
「現時点程度の改定量であれば問題ありません」
| |
「わかった。次に進んで」
| |
「発注及び納入また加工伝票や保管に際しては、図面番号だけでなく版も合わせて明示することとしました。照門であれば『図面番号SM002』ではなく『図面番号SM002改定0』あるいは『図面番号SM002改定8』というような表示とします」
| |
「なるほど、それなら間違いはなくなりそうだ。 しかししっかりやるのはいいが、ものすごく手間がかかるな」 | |
●
講義のあと、藤田中尉と黒田軍曹といつものように雑談である。今日は木越少佐は出張とのことで不在である。● ● |
「伊丹さんが品質管理について教育していこうというのはよく分かりますが、私どもの力が足りないようでなかなか進みませんね」
|  | |
「いえいえ、仮に今回問題がなかったとして、管理図の書き方を覚えて活用しましたと形だけでシャンシャンと進んでも意味がありません。今回は管理図を作ろうとして別な問題に気が付いて良かったと思いますよ。管理図の役割が理解していただけたでしょう」
|
「新しい計測器とか新しい加工方法なんてのは誰でも喜んで取り組みますが、図面管理ははっきりいって脇役、陰の仕事ですからみな関心がありません」
| |
「とはいえそれは必要だし重要な役割だ」
| |
「なにごとも単なる手法を覚えるという小手先に陥らないで、それぞれの仕事の芯になることを理解していただくことに重点を置いて進めていきたいと考えています。 品質管理が一通り終われば次は品質保証ですが、品質保証でも文書管理は重要な項目です」 | |
「ほう、なぜ文書管理が重要なのですか?」
| |
「文書管理に限らず品質保証というのは仕事をするための土台を提供するものです。ですから不良対策とか品質向上をいう仕事をするためには何が必要か重要かと考えるとお分かりと思います。 勘違いする人がいますが、品質管理段階に進むと検査がいらないとか、品質保証に比べて品質管理はレベルが低いということではありません。品質保証は検査や品質管理の上に載っているともいえます」 | |
「えっ、どっちが土台なんですか?」
| |
「なんといいましょうか、品質保証はやはり土台でしょう。雨風はしのぐための掘立小屋なら土台はいらないかもしれない。しかし長持ちして風雨を防ぐ壁とか床とかを作るとなると土台が欲しい。そう考えると矛盾はありません」
| |
「なるほどねえ〜」
| |
「みな伊丹さんのお話を楽しみにしていますが、そういう話は今まで聞いたことがありません。これから品質保証の段階になったら驚きの連続ですか」
| |
「いや品質保証でなにをするのかというのを聞くと、なんだそんなことかとか、そんなことが品質向上に役立つのかという疑問、反論が多々あると思います。しかしそうですねえ〜、例えば汽車で大事なことといえば強力な機関車とか運転する機関士などが思い浮かぶでしょう。しかしもっと重要なのは線路の維持とか線路に石が落ちてないか点検するとかそういうことが重要なわけです。 製品を作るためには、まず品物をどう作るか、納期は大丈夫かという検討も重要です。製造では計測器はしっかり校正されているか、作業者は技量のある人がそろっているかとか、今回のように誤った図面が使われていないかとか、まあそういう基本的なことがあって初めて生産ができるわけです」 | |
「そういうことが品質保証なのですか、なるほど我々は重要と認識していけませんね」
| |
「前にも申しましたが、これは品質管理だとかこれは品質保証だと区分けできるわけでもなく、また分けることに意味もありません。ただ生産工程の品質、能率、安全などを高みに上げていくためには、総合的に基礎固めをしてその上で活動しなければならないということです」
| |
「伊丹さんがここに来てくれるようになってまだ1年です。しかしこの1年で品質の向上、能率向上、また計測器とか管理とか1年前とは比べ物になりません。これからが楽しみです」
| |
「これもまた何度も語っていると思いますが、工場の改善は管理技術だけではなにもなりません。品質管理も品質保証も管理技術です。固有技術つまり切削加工とか塗装とか溶接とか検査とか、そういうものの向上が必須です。 それともうひとつ、働く人の意識向上ですね。これは大和魂とか臥薪嘗胆ということではありません。この工場はどんな方向に進んでいるのか、そのために自分はなにをしなければならないのかということを理解して行動するということです」 | |
「おっしゃることよくわかります。不肖藤田も伊丹さんの薫陶を受けて頑張ります」
| |
しばしの沈黙ののち、藤田が恐る恐るという感じで口を開いた。 | |
「伊丹さん、相談というかお願いなのですが」
| |
「なんでしょうか?」
| |
「実は・・・1年ほど前、練兵場建設が完了したとき日程管理についての論文を書いていただきましたよね」
| |
「ああ、そんなことがありましたね」
| |
「また皇国大学で紀要発行の季節になりましたので、指導教官から私に寄稿しろというお話がありまして、それでまた伊丹さんにお願いしようかと」
| |
「アハハハハ、カンニングはいけませんよ。この1年間、藤田中尉殿の活躍で論文のネタはいくつもあるでしょう。
 ええと、まずノギスやダイヤルゲージの導入による加工基準の変更による精度向上、互換性向上、それから機械設備の保守改善による工作機械の精度向上と故障低減、ブロックゲージを基準にした計測器校正体制確立、盗難事件をきっかけとして機密管理体制構築と・・ | |
「そのう、私は文章を書くのが不得手で伊丹さんに代筆お願いできませんか」
| |
皇国大学の先生の論文はネタが自分で作文は大学の先生で、こちらはネタは藤田中尉で作文は自分かと苦笑いする。まあどうせ大した手間でもないがひとつ気になることがある。 | |
「ご存知のように私は特殊なタイプライターのようなもので文章を書いています。それでそのままでは提出できないでしょうから、それを手書きするのは中尉殿の方でしていただけますか」
| |
「あっ、それはもちろんです。しかし伊丹さんあのきれいな文字で書くのはどういう機械なのですか?」
| |
「うーん、それは内緒です。ともかく論文の案を作ってみましょう。2件もあればよいでしょう。私も5件もは書けません、アハハハハ」
| |
「よろしくお願いいたします」
| |
「伊丹さん、私もお願いがあるのですが」
| |
「なんでしょう?」
| |
「実は今年、曹長の昇進試験を受けるのですよ。まあ試験は名目だけで過去の勤務成績とか功績で決まるというのが通説ですが、職務における提言というのを出すのです。それで・・」
| |
「その提言書を私が書くわけですか?」
| |
「いやあ、私は中尉殿ほどずうずうしくはありません。 案を作りましたので中尉殿に出す前に添削していただけないかと」 | |
「あっ、嫌味だねえ〜」
| |
伊丹に丸投げする藤田中尉より黒田軍曹の方が常識はあるようだ。とはいえ藤田中尉も気さくで鷹揚な人だと伊丹は思う。きっとのどかで仲の良い家庭に育ったのだろう。 黒田軍曹は茶封筒を伊丹に手渡す。手で持つと20枚程度入っているような感じだ。 | |
「了解しました。期限はいつまででしょうか?」
| |
「来月の講義の時までということでお願いできませんか」
| |
「私の方もそれまでということでお願いします」
| |
「承知いたしました」
| |
●
帰社すると、伊丹はまず黒田軍曹の封筒を開ける。力強い達筆な文字で書き綴ってある。昔の人は字が上手だったのだと改めて感じる。伊丹もワープロを使うようになってから下手になるだけでなく漢字を忘れてしまった。● ● 一通り読むと、伊丹は頭の後ろで手を組み鉛筆をくわえて考える。 藤原が声をかけてきた。 | |
「伊丹さん、何か悩み事ですか?」
| |
「いえいえ、そんな深刻なことじゃありません。黒田軍曹と藤田中尉からちょっと宿題を頼まれましてね」
| |
「ほう、不良対策とかですか?」
| |
「いやいや、昇進試験の論文とかですよ」
| |
「そうですか、こちらの社会でも昇進とか出世とか大変なんでしょうねえ〜」
| |
「こちらの社会でもとおっしゃると?」
| |
「私はご存知のように高卒です。高校を出て大手電機メーカーに入りました。そこでは中卒・高卒にも門戸が開かれていると言えば聞こえはいいですが、もう試験・試験でしたね。仕事を真面目にしていてもペーパー試験で良い点を取れないと上にいけません。言い換えると真面目に仕事をしてなくても、試験の成績が良ければ高卒でも職長、係長、課長とトントンと出世できました」
| |
「ほう、それはまたいいのか悪いのか」
| |
「結果として良くなかったようですね。ご存知のように私が勤めていたところは、20世紀末から左前になりましたでしょう。ですから私もリストラというか強制的に早期退職することになりました。 とはいえ試験だけで昇進していった同期の人たちもリストラでしたから、恨みっこなしですわ。人間万事塞翁が馬ですよ」 | |
「細かいことは違うけど私も似たようなものです。課長止まりで閑職にいたらISO審査員に出向しろと言われ、出向したら認証ビジネスの先行きが暗いから異世界で第三者認証を立ち上げろと言われ、来てみれば認証どころか品質保証など考えもつかない世界で、今はノギスの導入とか計算尺を実用化しようとかそんな基本をしているわけで」
| |
「いやいや、底辺というか基礎をしっかりすること、そして少しずつレベルアップを図ること、これが面白いのです。 はっきりいって21世紀の機械加工も製品も、私の手におえません。いや誰の手にも負えないんです。一つの製品の電気から構造からソフトまで一人で扱えるものじゃありません。だけどこの時代のものなら自分一人で扱える。機械加工について言えば、機械の操作、刃物の研磨、測定器の製作なんでもひとりでできます。そういうのって面白いですよね」 |
「我々が子供の頃、博士がひとりでロケットを打ち上げたり、タイムマシンを作ったりというお話がありましたよね」
| 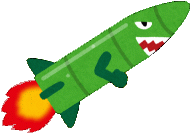 | |
「バックトゥーザフューチャーですな」
| ||
「そうそう、今の時代はそんなのありえないって思いますよね。ビッグサイエンスになりましたから。だけどレオナルド・ダヴィンチまで遡らなくても、100年前のこの時代はまだのどかというかこじんまりしているんですよね」
|
「そうです、そうです。製品でもプロジェクトでも一人で取り扱えるのです。そういうのって楽しいじゃないですか」
| |
「藤原さんがこちらに来て三月くらいになりますか。初めて会ったときに比べると明るくなられたと思います」
| |
「私は向こうにいたときはウツだったのでしょうね。神経だけでなく体調もおかしくなりました。今は朝起きると会社に来るのが楽しみです」
| |
伊丹は藤原の話を聞いて、自分がそのワクワク感を忘れてしまったのかマヒしてしまったのかといささか反省した。 |
私の先輩の一人に県の卓越技能者として表彰された方がいる。その方は毎朝、会社に行くのが楽しみでならないと言っていた。今日はこういう工夫をしてみよう、こういうチャレンジをしてみようと頭に浮かびウキウキするという。また多趣味でバイオリンを弾いたりものすごい着物を着て演歌を歌ったりしていた。既に80を超えているはずだが元気にしているだろうか。幸せでいてほしい。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
異世界審査員物語にもどる
うそ800の目次にもどる