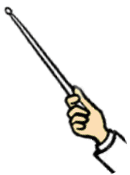17.12.14
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。
人は仕事をする。仕事といってもいろいろある。モノづくり、裁縫、料理、事務作業もあるし運搬もある。まあ、なにをするにも道具や機械を使い、手ぶらってことはない。なにせ人間は道具を使う動物
そのとき結果を決める要因として、道具・機械が大きな割合を占めるか、人の技量が大きな割合を占めるかということを考えてみよう。
道具・機械に出来栄えをゆだねようという発想であれば、道具・機械をしっかりと作り、誰が使っても結果が変わらないようにする。他方、人に依存するのであれば、使用者は腕を磨かなければならないが、道具・機械は重要でなく簡単なものになる。
人に依存する割合の大小のメリット・デメリットを比較すると下図のようになるだろう。
仕事をするとき技能と機械に依存する比率と得失
| ||||
|
西欧人は前者、日本人は後者だという人が多いが、実際にそうかどうか私はわからない。しかしISOなんてのに関わってきた経験からは、西欧と日本の制度を比べると、確かにそうに思える。
仕組みと手順をしっかり決めてそれを明文化する、そしてこの通りやれというのがISOMS規格の基本思想である。日本の多くの組織、それには会社もマンションの管理組合も入るが、それらは見た目では規則がありそれで運用しているようだが、実際は人間関係とか慣習を基にして動いており、イレギュラーなときは関係者が相談して決めるということが実態である。
仕事をするときルールと人の判断に依存する比率と得失
| ||||
|
どちらが良いかというと、まあ人材次第、状況次第だと思う。ただ標準化というのは前者の思想であり、標準化を図れば持続性が高まり、教育・伝承が容易になり、結果として長続きして改善もしやすいと思う。そうでない方法は精神主義に陥り、時が経っても「仕組みの進歩」がなく、先人と同じ修業を必要とするように思う。
但し留意しておくことは、道具・機械にすべてをゆだねる考えもISO9000の思想も、枯れた技術についてのみ適用できるということだ。研究開発や確立した方法論がなくて試行錯誤している業務には不適当なのである。というか、そもそもそういうことに対応するものではない。それを忘れてはいけない。
著名な科学者の伝記などを開くと、実験に見合った試験装置も測定器もなく、とりあえず手に入ったものを使って創意工夫で試行錯誤したというお話が満載です
道具・機械あるいはシステム(制度)に成果を依存しすぎると、創造性とか技量を向上させようとする気持ちがなくなってしまうのかもしれません。
そしてこの機械やシステムに依存する考え方は、その手順を継続的に見直しし、改定していかなければならないという枷があることも忘れてはならない。それができないならこの方式は取れない。
日本の栃木の工場がほぼ完成した。 開所するひと月前に製造部門の責任者に木越中佐、そしてその副官に藤田大尉が任じられた。木越中佐は伊丹が異世界から来たと聞いていたから驚かなかったが、藤田大尉はこのときはじめて異世界の存在を知った。 そして工藤社長は作業指導に藤原を、作業改善に上野陽二を派遣した。最近は上野も夢みたいなことを言わなくなり、地道にコツコツと仕事をするのが身に付いたようだ。 藤原は毎日、東京から異世界の工廠を経由して、栃木の工場に通うなんてことは願い下げだ。とはいえ自宅から栃木までの通勤は無理なので、工場から歩いて行けるところにアパートを借りて住むことにした。そして毎週末に東京の自宅に帰るつもりだ。 上野は通勤ではなく寮住まいを希望した。そして暇があれば現代日本を旅行して見聞を広めたい。もちろんそのときの身分証明をどうするかは今後の課題である。 情報処理関係の責任者はなんと憲兵隊の岩屋少佐である。情報処理部門の管理監督と工場で働く異世界、日本側の人間の監視を兼ねているのだろう。 日本と異世界を繋ぐ出入り口には両方に憲兵がいて出入りの際は身体検査も行う。 岩屋少佐は藤原に「怪しいものを運ぶときはこの通路ではなく、別の通路を使ってください」と言う。他の通路経由なら岩屋少佐の責任ではないからだろう。それに理由いかんに関わらず藤原を特別扱いはできないからだ。 工場長は吉本一族から就任した。これは異世界人では住民票さえないのでやむを得ない。 ●
製造関係の幹部である、木越中佐と藤田大尉そして藤原と上野が集まって打ち合わせをする。● | ||||
「この工場の目的は三つある。
| ||||
「これからは木越中佐ではなく木越部長と呼ばせてもらいます。 実は私が考えていることがあります。それは工場開設してもすぐに生産に入るつもりはないのです」 | ||||
「と言いますと?」
| ||||
「私は単に機械を使えるだけの人を養成したくありません。目指しているのは、図面を読める、加工方法を検討できる、機械材料について必要最低限の知識がある、簡単な強度計算などができる、そのためには四則演算ができること、そういう現場の中核になれる人を作りたい。 それで最初の二月は座学を半分、実習を半分くらいにして、基本的なことを習得してから生産に入るつもりです」 | ||||
「座学と言いますと具体的には?」
| ||||
「機械製図の講義と製図実習、機械工作法、機械材料、基礎力学、計算尺の使い方などを教えます。テキストには工業高校の教科書を使うつもりです。なによりも安いですし、網羅的ですからね」
| ||||
「うわー、それじゃ私にも聴講させてください」
| ||||
「いえいえ、藤田大尉殿には先生をしていただくつもりです。おっと大尉殿はこれからは課長でしたね」
| ||||
「教育が必要なことは分かったが、実際には工場操業初日から生産計画が入っているのだ」
| ||||
「2か月間は出来高ゼロと考えてください。しかしそれ以降は頭数で比べて砲兵工廠の3倍の生産を上げるつもりです」
| ||||
「分かった。そのように調整しよう」
| ||||
「それとまずは規律、決まり事を守るという意識付け、工場内の整理整頓、機械や計測器の取り扱い、そんなところから始めるつもりです」
| ||||
「私もぜひ藤原さんの指導する未来の工場の生産方式、管理方式、それを支える管理とか従業員教育を学んでいきます」
| ||||
「おいおい、君は学ぶ側じゃなくて教える側なんだよ」
| ||||
「何事も無事これ名馬ですから、事故や怪我だけはないようにいきましょう」
| ||||
●
機械加工の第一期生40名がやってきた。いずれも海軍工廠と砲兵工廠で勤続3年以上の者から選抜された。この時代は労働力の流動性が極めて高く、少ない年で従業員の1割、多い年には3割が出入りしている● 当初の勤務形態は8時始業、12時まで座学、1時から5時まで現場実習である。
また図面の数字を読み取り 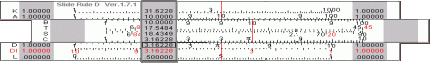 ただ第一陣はさすがに選ばれたという意識が高くものすごく熱心だ。帰宅時には教科書と計算尺を持ち帰り自宅で復習する者が多い。寮に住んでいるものは校舎に留まって夜まで勉強するものも多い。最初は40名中20名が寮住まい、20名が通勤だったが、半月もしないうちにほとんどが寮住みになってしまった。そのほうが勉強できるからという。通勤に時間がかかることもあるが、夜も蛍光灯の明かりで勉強ができる方が快適だ。そして寮にはテレビもあるし、パソコンもあるのだ。 実習の方は最初は旋盤とかフライスなどの説明から始まった。なにしろ今まではラインシャフトといって、工場の天井に1本の回転軸があり、そこからベルトで旋盤など工作機械を駆動しているのだ。そんなものしか見たことがない人たちだから、個々の機械にモーターが付いているのを見てまず驚いた。そしてそのモーターが強力で重切削をするのをみてさらに驚いた。 細かなこともいろいろ違う。バイトは標準の形のものを使う。今までのように自分でバイトを作ったり研磨したりはしない。しかも刃先は超硬合金というものでものすごく固い。今まで使っていた炭素工具鋼のように見ているうちに刃先が減るなんてことはない。 自分たちがその機械を使える日が待ちきれないのであった。 最初はどうなることかと不安もあったが、座学の方は先生も慣れてきたし生徒のほうも勉強する習慣がついてきた。二月経った今では藤田も上野もいっぱしの先生になったようで、堂々と講義をしている。 また生徒たちも元々レベルの高い人たちだから材料なり計算なり、興味もあり教えられたことは砂が水を吸い込むように吸収した。 今日から生産を開始する予定である。とはいえ藤原が40名を教えることはできないから、半分にして午前座学、午後生産と午前生産、午後座学の2チームのシフトである。 作業指示は図面と日程計画、そして加工手順表が与えられる。図面は製品仕様を示すもので合否の基準である。日程計画は自分の工程で今日何をいくつ加工するかが指示される。加工手順はどの材料をどの機械でどのような手順加工するかを5W1Hで詳細に示されている。使用する刃物、加工条件、切粉の処理に至るまでそれを見れば分かるようになっている。そしてそれに反する行為は許されない。 これは生徒たちにとってものすごい抵抗があるようだ。今までは刃物は自分が作り、加工手順は腕の見せ所で他人には教えないというスタイルだったからだ。 藤原はとにかくそれでやれと押し切った。もし別の方法の提案があれば、それを試験してみる。そしてそちらがより良いことが分かったら即切り替える。但しそのときから全員が新しい方法をしなければならないとはっきり言う。 初めはいやいやながら従ったものの、やってみれば藤原の指定した方法が速く仕上がりも良いことが分かる。もっとも中には天邪鬼、いや探求心旺盛な者もおり、藤原先生の切削条件を超える方法を考えようとする者もいた。 生産開始から1週間がたった。ここは木越部長の部屋で、藤原と藤田が先週の報告に来ていた。 | ||||
「藤原さん、生産開始から1週間たちましたが生産状況はいかがですか?」
| ||||
「初日は少しもたつきましたが、二日目以降は予定通りの生産ができてます。1週間まとめると計画表より0.5日先行です。それでもいくつか問題があります」
|
「どんな問題でしょうか?」
|  | |
「始業、終業のメリハリがありません。8時の時報時には現場に集合整列しているべきです。しかし時報が鳴るまで外でタバコを吸っていたり、終業前に掃除をするのは良いのですが、掃除を終えてしまってブラブラしているのが多い。もう少し規律を正さねばなりません」
| ||
「そういった趣旨を徹底してください」
| ||
「話をしてはいるのですが・・・」
|
「人に話せば分かってくれるわけではありません。何度も言い聞かせ、やらせる、その繰り返しです。 それと問題を見つけたなら、そのときに注意しなければなりません。時が経ってから話しても、何のことか理解できないものです。 それと問題があったらペナルティを与えることも必要です。朝礼に遅れたらその場で注意するとか、仕事から外すとか、対処することが必要です。藤原さんは教育の全権をもっているとお考え下さい」 | |||
「分かりました。話し方を考えます。 それと今の設備に慣れたのは良いのですが、向こうに戻ってから従来の機械を改善していくという意識が付いたのかとなると、そうは思えません」 | |||
「ただ単に新しい機械を使えるようになったというだけですか」
| |||
「そんな感じですね」
| |||
「ここに派遣された目的を、研修者だけでなく藤原さんも考えてほしい。 技能伝授だけでなく、職責と使命を教えるのも藤原さんの仕事です。あなた自身、自分の思い、技能をどう伝えるかをもっと考えて日々実践していただきたい。 研修期間は半年なので、まだ時間はあります。頑張ってください」 | |||
藤原が木越部長の部屋を出ていく。 | |||
「藤田君、今のやりとりを聞いて何か感じたか?」
| |||
「藤原さんは高い技能を持っています。しかし人を動かすとか教えることはあまり得手ではないようですね」
| |||
「ワシもそう思う。人を比較してはならんが、伊丹さんは初めての仕事も 彼が元の勤め先でリストラされたのは技能が時代遅れになったことではなく、彼が周りを動かせなかったからかもしれんな。下っ端なら技能・技術があれば務まるが、上に立つ人は人を動かせないといかん」 | |||
「おっしゃる通りです。この仕事は私にとっても一つの試練です。今のお話を自分のこととして受け止めます」
| |||
「さて話は変わるが、南武少佐からの依頼は検討したか?」
| |||
「ハイ、2週間前に仮称第一次自動歩兵銃の図面を受領しました。以前伊丹さんが持ち込んだAK47を参考にしたようです。口径5.5ミリ、銃身長450ミリ、全長950ミリ、銃剣付けて1100ミリ、重量3.4キロ、銃床は形状を中抜きにして軽量化したようです」
| |||
「38式歩兵銃に比べるとそうとう小さく軽くなったものだ」
| |||
「違いはわずか700グラムといっても割合では17%も軽くなっています。1時間も担げばありがたみを感じるでしょう。歩兵にとっては救世主でしょうね」
| |||
「歩兵にとっては救世主でも、作るのが難しくて我々には疫病神じゃないのか?」
| |||
「ええと、銃身は専用機械が必要なので砲兵工廠で作るそうです。それ以外の部品はここで試作するということです。今までと違うのはすべての部品に寸法公差が付いていることです。」
| |||
「どのように作るのかな?」
| |||
「今回は試験用として100丁作るのですが、現場で現物合わせをさせないために部品ごとに作り、組み合わさる部品を同じところに置かないようにという指示です。 それからねじ類は市販品、この場合は日本で市販されているという意味ですが、それを使うとのこと」 | |||
「なるほど、公差通りに作らせて組み合わさるかどうか、そして市販品がある部品はそれを使うと」
| |||
「ハイ、それで私は各部品について加工手順表を作りました。藤原さんに確認してもらったら、来週より生産に入る予定です」
| |||
「期待している。もちろん自動小銃が上手くいくことも期待するが、我々の工場で作ったものが公差内に収まることを第一に期待する」
| |||
「了解しました」
| |||
●
それから10日後、日本にある工場担当の全部品の加工が終わり、砲兵工廠に送られていった。● 南武少佐以下、設計部門の者は複数の工場で作られた各部品の測定結果をみて、すべてが図面公差内であることを確認した。  次は組み立て工程である。南武少佐以下全員が緊張したが、全数手を加えずに組み上った。次の懸案は、果たしてこれで動作するのだろうか?
次は組み立て工程である。南武少佐以下全員が緊張したが、全数手を加えずに組み上った。次の懸案は、果たしてこれで動作するのだろうか?だが結果はすべて作動した。南武以下、誰も拍手も万歳もせず、ただホットと安堵の息をついた。図面公差、加工精度、そういうものがすべてよかったのだろう。 既に欧州の雲行きは怪しく、既にいくつかの国へ38式歩兵銃の輸出の話は決まっていたので、これがダメなら日本軍が使う次期歩兵銃がなくなるところだった。 もちろん、制式化まではこれから様々な試験があるわけだが、とりあえず一つの峠は越した。 ●
こちらは情報処理部門の岩屋少佐もとい岩屋部長である。● ● 書籍などの情報収集は幸子の事務所の仕事であり、ここの仕事はパソコンの教育とワークステーションなどを使った技術計算、シミュレーション、暗号の研究などである。
次に一歩進んで、技術計算やシミュレーションを実際に行うことも始めた。研究所や工廠の設計部門の頭の良い連中約20名を選抜して、基本教育をしたのちパソコンやワークステーションをおもちゃにさせている。頭の回転が速い連中だから既にソロバンや計算尺でしていた計算は毎朝関係部門からきた計算依頼を処理して、午後には返すという仕事をしている。 そのほか風洞実験や水テーブルで行っていた飛行機や船の実験代わりに計算機のシミュレーションのプログラムも作った者がいる。実際に飛行機を飛ばさずに良否を判断できるから今までの10倍は開発が速くなった。シミュレーションソフトを改善すればもっと早くなるだろうという。 こちらは皆大人だし主体的に仕事をするから、岩屋が気を使うこともなく衣食住だけ用意すればいい。 三番目というか最後の仕事が最重要でもっとも難しい。それは政策研究所の国家プランニングのシミュレーションである。これは専門家しかプログラムが組めないと結論して、吉本一族に依頼してソフトハウスを丸ごと買い取ってしまった。といういことでこの部署は東京にある。もちろん腕が良くしかも守秘義務は大丈夫というところだ。そこのプログラマー10名ほどが異世界の政策研究所からの依頼を受けてプログラムを組みシミュレーションをする。 なにしろ「これこれの情報で、こういった要因を反映したら、どうなるか」という程度の仕様というか願望を聞いてそのロジックを考えることから始まる。コード化する前に、ロジックについて依頼元と大いに議論する必要があり、その結果変更は常につきまとう。 まあ、なにごともカットアンドトライだ、長期的にブラッシュアップしていけばいいかと岩屋も考えている。 実は今、第一次世界大戦開戦以降のシミュレーションもしているのだ。できることなら大恐慌を起こさない解を期待している。 岩屋はそれだけでなく、工場の警備、出入りの検査という仕事もある。だがこれはもう部下に任せていて問題ない。ときどき自分自身も外を歩き、周辺の人が工場をどう見ているのか探っているのだが、誰も関心がないというのが実際のようだ。ただ長引く不景気で職を求めて来る人は途切れることがない。そういったことは工場長である吉本一族の担当だが、ゆくゆく工場を拡大してそこでは秘密でないまともな仕事させるために数十名雇用してお茶を濁そうということになっている。 |
少数の卓越技能者が指導したところで一国の工作技術や技能を向上させることなど無理に違いない。それが可能なら、世界中の発展途上国は今頃は先進国になっているはずだ。

だけどまだ技術が一定水準以下であるときならば先進国に追いつき追い越すことは不可能ではないと思う。現に日本が欧米追い付けたというのは、先進国がそれほど日本に差をつけていなかったからだろう。ノギスにしてもブロックゲージにしても、日本が工業化を進めていた時、先進国でも研究中だった。もし日本が明治維新を迎えたときに、欧米が半導体の時代になっていれば日本は今でも追い付けなかっただろうと思う。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 | 「人間は道具を使う動物である」とはカーライルの言葉だそうです。しかし現在では多くの動物が道具を使うことが知られており、道具を使う動物は人間限定ではなくなりました。人間と動物の境目はあいまいというより、そもそもその差はないのかもしれない。
| |
注2 |
「困ります、ファインマンさん」R.P.ファインマン、岩波書店、2001 「宇宙をかき乱すべきか」フリーマン・ダイソン、ダイヤモンド社、1982 | |
注3 |
社会保険が貧弱で年功序列でない場合、一つの会社に勤続するメリットはない。常に待遇の良い会社へ移動する力が働く。日本で終身雇用とか年功序列という仕組みができたのは1960年以降である。 「科学的管理法の日本的展開」佐々木聡、有斐閣、1998、p.66 |
異世界審査員物語にもどる
うそ800の目次にもどる