17.12.21
�����̕���̓t�B�N�V�����ł��B�o�ꂷ��l����c�͎̂��݂�����̂ƈ�؊W����܂���B
�A�����p�����⏑�Ж��͂��ׂĎ��݂̂��̂ł��B�������[����̈��p�͂���܂���B
���͍��Z���o�Ă���45�N�ԃT�����[�}�������Ă����B���̊ԁA�ƍ߂Ƃ������̂Ɏ����߂����Ƃ͂Ȃ��B��������10�L�����x�̃X�s�[�h�ᔽ���������炢���낤�B�߂܂������Ƃ͂Ȃ����ǁB
��������Ђ̋��Ɏ��t�������Ƃ��Ȃ��A�l�l�����������艣�����肵�����Ƃ��Ȃ��B���ÎԂ��Ƃ��ɍ��\���ǂ��Ɉ����|���肻���ɂȂ������Ƃ͂��邪�A�K���ƍߔ�Q�҂ɂȂ������Ƃ��Ȃ��B
�����S���ƍ߂�Ƃ������Ƃ��Ȃ����Ƃ����ƁA���������C�ɂȂ邱�Ƃ�����B����͎d���ɂ����đS�͂�s���������A�Ɩ����Z�ł������Ƃ����őP��s���������Ƃ������Ƃł���B
�ߋ�40�N�Ԃ��v���Ԃ��ƁA���������w�͂��ׂ��ł͂Ɣ��Ȃ��邱�Ƃ͂���������B
�g���u���������ē����������s���s�x�Ŋ撣���Ă����Ƃ��A�������߂ł��Ɨ��E���ċA������Ƃ�����B���̐l�������������Ƃ������̂����x���ڂɂ����B�������������Ƃ͋������̂��A����Ƃ��G�O���S�ɂȂ�̂��H
�v�~�X�ʼn�Ђɑ��Q��^�����Ƃ��͂ǂ��Ȃ̂��납�H�@���̒m�����~�i���ꂽ�l�͂������A�E���Ӗ��Ƃ��w�C�ȂǍ߂ɖ��ꂽ�҂͂��Ȃ��B
�}�ʎw���㒷�w���ɏ]�킸�ɕ��������Ƃ��͂ƂȂ�ƁA�ǂ��Ȃ�̂ł��傤�H
�T�{�^�[�W���ł͂Ȃ������̓s���Ŏ蔲������悤�Ȑl�͏��a40�N���͕��ʂɂ����B�����͍������Ǘ����x�����Ⴍ�A�債�����ɂȂ�Ȃ������悤�ɋL�����Ă���B
 ���Ɋւ�邱�Ƃł́A���̏㒷���ォ��̐��Y�ύX�w�����Ȃ������ɓ`�����A�����ύX��m�炸�ɓ����̌v��ʂ萶�Y���Ă��Ė��ɂȂ������Ƃ�����B
�������̑Ӗ��㒷�ɂ͂Ȃ�̍������Ȃ������B���̏㒷�̓S���t����D������������A��Ђ̐��Y�����T���̃S���t�̂��Ƃœ��������ς��������̂�������Ȃ��B
���Ɋւ�邱�Ƃł́A���̏㒷���ォ��̐��Y�ύX�w�����Ȃ������ɓ`�����A�����ύX��m�炸�ɓ����̌v��ʂ萶�Y���Ă��Ė��ɂȂ������Ƃ�����B
�������̑Ӗ��㒷�ɂ͂Ȃ�̍������Ȃ������B���̏㒷�̓S���t����D������������A��Ђ̐��Y�����T���̃S���t�̂��Ƃœ��������ς��������̂�������Ȃ��B�������������Ƃ͌����Ɍ����ΐE���Ӗ��Ȃ̂��A�w�C�Ȃ̂��낤���H���̒��A�Y�@�Ƃ��A�ƋK���ʂ�ɏ�������Ȃ�Ă��Ƃ͂߂����ɂȂ��悤���B���������́A�Ȃ��Ȃ��A�܂��܂��ōs���̂��낤���H
�R���v���C�A���X�Ƃ����ƁA�ƍ߂Ƃ��s�ˎ����N�����Ȃ����Ƃƍl���Ă���l�������B����A�قڑS�����l���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
���͂����͎v��Ȃ��B�ǂ�ȎЉ�ł���Ђł��ƍ߂�����l�����Ă��������Ȃ��B���͂����������Ƃ��B���Ȃ����ƁA�@�Ɋ�Â��ēK���ɏ������A����������J���邱�Ƃ��R���v���C�A���X�ł͂Ȃ����Ǝv���B
����Ă���w�C�Ƃ��Г��ƍ߂Ȃǂ��݂�ƁA���������ŏ��̖��������ɏ��u�����B�����Ƃ��āA�܂��܂�����傫�����Ă���悤�Ɏv����B
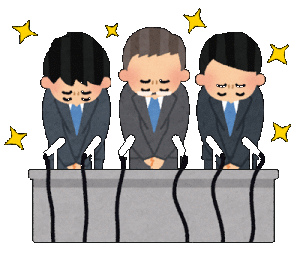 �s�ˎ����N����ƃG���C�T�������l������Ŕ����Ȃ�������������ĉ����āu���݂܂���v�u���߂�Ȃ����v�Ȃ�Ă��Ă���̂�����邪�A����Ȃ̂����Ă���ƁA�A�z���H�n�����H�Ƃ����v���Ȃ��B
�s�ˎ����N����ƃG���C�T�������l������Ŕ����Ȃ�������������ĉ����āu���݂܂���v�u���߂�Ȃ����v�Ȃ�Ă��Ă���̂�����邪�A����Ȃ̂����Ă���ƁA�A�z���H�n�����H�Ƃ����v���Ȃ��B����Ȉ������Ƃ������l�̓G���C�T���̐ӔC����Ȃ��B�����������Ƃ��x�ƋN�����Ȃ����Ƃ��G���C�T���̐ӔC�Ȃ̂��B
�����玄�����������Ă܂����Ċ�����āA�u�������������������l��������܂����B�@���Ɠ��ЏA�ƋK���Ɋ�Â��ď������܂����̂ł��������܂��v�ƌ�����������Ȃ����H
�I�t�B�X�ŃZ�N�n���E�p���n��������A�x�@�ɓ˂��o�������������āA�u�Z�N�n��������܂����v�Ɠ��X�Ƃ��Ă����������Ȃ��̂��B�������A�j���A�����|�[�g�ɉߋ�1�N�Ԃɂǂ̂悤�ȎГ��ƍ߂�����A�ǂ����u���������L�ڂ�������B�l�̐��Ȃ͕ς��悤���Ȃ��B�Z�N�n����p���n�����Ȃ������Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B
���ۂɂ���������Ђ�����BIBM�͂���30�N���O����A�j���A�����|�[�g�ɔƍߌ�����g�����݊z�ȂǂL���Ă���B����IBM�����h���Ǝv���B
�Ј����������N��������g�����݂����̂͌o�c�҂̐ӔC����Ȃ��B�������Ɛl�ɂ͌����ȏ������s���̂͌o�c�҂̐ӔC�ł���B���x���N�����Ȃ�A�V�X�e����Ǘ��������̂����炻��͌o�c�҂̐ӔC���B���̏ꍇ�̐ӔC�͌��ʐӔC�ł͂Ȃ��A���{�ӔC�ł���B
�����ɐM�ܕK�����s���Ȃ���A��Ђɐ��`�͂Ȃ��Ǝv���͓̂��R�ł͂Ȃ��낤���H�@���̌��ʁA�ǂ��l�͂��C���Ȃ����A�����l�͎��������������Ƃ��邾�낤�B
���C���H���Ő}�ʎw��ʂ�̉��H���@����炸�A�܂��}�ʌ����ɓ����Ă��Ȃ����Ƃ����m�ŏo�ׂ��Ă������Ƃ͑���ƂȂ����B�앐�����̍����ɂ��A�W�҂̏����Ɛ��Y���ꂽ�������e�̉��C�͏l�X�Ɛi�߂�ꂽ�B  �܂����ыZ�t�ƈꐙ�Z�t�́A�}�ʐ�����ɂ����Č����ɂ��w��Ƃ��������ɂ��Đ����������ƁA�����Ă���ɑΉ����������̋��^�Ǝg�����̎w�������ɂ�������炸�A����Y�ɓW�J���Ȃ��������Ƃ͐E���Ӗ��ł���Ƃ��ꂽ�B
�܂����ыZ�t�ƈꐙ�Z�t�́A�}�ʐ�����ɂ����Č����ɂ��w��Ƃ��������ɂ��Đ����������ƁA�����Ă���ɑΉ����������̋��^�Ǝg�����̎w�������ɂ�������炸�A����Y�ɓW�J���Ȃ��������Ƃ͐E���Ӗ��ł���Ƃ��ꂽ�B���ČY���ł��邪�A�펞���ł���Ȃ�R�l�����łȂ��R�������R�Y�@�ōق���邱�ƂɂȂ邪�A�����ł���A�Y�@�ɂ��Ɣ��f���ꂽ�B�Ƃ͂������R�Y�@�Ȃ疽�߈ᔽ�ŋ�5�N�ȉ��A�Y�@�Ȃ�d����4�N�ȉ� �㒷�̍��X�؏����͊Ǘ��s�\���ō~�i�l�����߂ƂȂ������A���̑O�Ɏ��E�����B�C���H�����͊ēӔC�Ō����ł������B �E�H�����ł��邪�A�Z�t�������}�ʌ����Ɋ�Â��ĉ��H���邱�Ƃ��������Ȃ��������ƁA�w�����ꂽ���H���@�����ۂ������Ƃ��Z�t�������ٔF�������Ƃ������ď����Ȃ��Ƃ��ꂽ�B ��A�̏�����A�����̐E�H�̓g���u�����N�������Ƃ������ċ����Ă��������قƂ�ǂ͎c�����B �o�ׂ��ꂽ�������e�͂��ׂĉ�����ꂽ�B�����čɕi�A���i�A�d�|�i�ƍ��킹�āA�S�����i��Ԃɖ߂��čČ������s�����i�i�݂̂��Ďg�p����A�s�ǂ͂��ׂĔp���������ꂽ�B �K������ȍ~�A74�������e�͕s��炵���s��͋N�����A��D�]�Ō}����ꂽ�B �Ђƌ�����ɉ����Ƃ���i�������Ƃ��A���̎w�������������c��т͑̏d��4�L�����������B�����Ƃ����ꂪ���_�I�E���̓I�ȋ�J�̂��߂��A�V�ȂƗ��ꗣ��ɂȂ����₵���̂��߂��͒肩�ł͂Ȃ��B ���āA���ꂩ�琶�Y�̐��̍č\�z�ł���B ���c��т͐E�H���W�߂��B�܂��͍l�����ł���B | |
�u�������Ƃ����̂͐}�ʂɕ\���ꂽ�ʂ�ɍ�邱�Ƃł���B��������肽�����̂���邱�Ƃł͂Ȃ��B�܂����H���@���������l�������@�Ƃ���肽�����@�ōs�����̂ł͂Ȃ��B�w�����ꂽ�@�B�Ǝw�����ꂽ�n���ŁA�w�����ꂽ�؍��ʁE���葬�x�ōs���v
| |
�u�Z�t�����H���@����̂���A���H�����Ȃǂ킩��̂���v
| |
�u�������ł��B�n�������H���@�������Ă���Ŏd�������Ă��炤�̂���{�ł��v
| |
�u���Ⴀ���ׂĂ̕��i�ɂ��Ăǂ̂悤�ɍ�Ƃ�����̂����߂Ă����킯���v
| |
�u�����ł��B�����āA�݂Ȃ���ɂ͂��̒ʂ�Ɏd�����Ă��炤�v
| |
�u�����lj������͐l���ꂼ�ꗬ�V��H�v���Ⴄ���猾��ꂽ�ʂ�ɂ͂��Ȃ����v
| |
�u���ꂩ��͂����������Ƃ͎~�߂Ă��炤�B�݂�Ȃ������n���A�������@�ł��Ă��炤�v
| |
�u��k����˂��A���͘r�Ɏ��M������B���̘A���Ɠ������@�Ŏd���ł��邩��v
| |
�u�܂Ă܂āA���ꂶ��Z�t���w�肷����@�Ŏd������̂ƁA���ꂽ�����l������̂Ɣ�ׂĂ݂悤����Ȃ����B��������Z�t�̂������Ƃ��_�����ĕ����邼�v
| |
�u����Ⴂ���A�Z�t�Ɖ�X�̑�\�����ۂɉ��H���Ęr��ׂ��悤����Ȃ����v
| |
�u��낵���ł��傤�B�Ƃ͂������X�̑�\���݂Ȃ���Ƌ��Z�����Ă��ʔ����Ȃ��B������̑�\�ɂ͐V�l�E�H�ɂȂ��Ă��炤���Ƃɂ��܂��v
| |
�u���N���Ђ������͉��l���炢����̂ł��傤���H�@�����A20�l�͂��܂��ˁB���ꂶ�Ⴛ�̒�����3���ɏo�Ă��炤�B�E�H��\��3�l�Ƃ������Ƃł�낵���ł����B�o��I��͊F�����߂Ă��������B �����͐V�l�ɋ����鎞�Ԃ��܂�����A��������Ԃɋ��Z�J�n�Ƃ��܂��傤�B�݂Ȃ���ɂ͍����H�}�ʂ����n�����܂��B�n������H���@�݂͂Ȃ���̓x�e����������A�������ōl���Ă��������v | |
�V�l�̒����玩��������3�l�����܂����B��\3���̌��ɓ����̘A�����c��A���c�����������邱�Ƃ��ꏏ�ɒ��u����B���\�M�S�ȓz�炾�Ɠ��c�͎v���B ������3�l�ɊȒP�ȉ��H�������Ă݂āA�ǂꂭ�炢�̘r�O�����݂��B��{�I�Ȃ��Ƃ͂ł���悤���B���ꂩ�疾�����H����}�ʂ������āA�g���n���A���t�����@�A���H�����A�؍��A���葬�x�Ȃǂ������A�K���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����B�������l���邱�Ƃ͂Ȃ��B����ꂽ�ʂ肷��悢�̂��B ���ꂩ�琡�@������@��������B�ŋߎg���n�߂��m�M�X�ƃ}�C�N�����[�^�[�̎g�����͒m���Ă������A�����������ڂ��Ȃ��B�����܂ʼn��ł������ė��K����Ƃ����B���ꂩ������̍l������������B | |
�u10�~���A�v���X�}�C�i�X0.1�Ƃ����10�~����ڎw���ĉ��H����B10�~���v���X0.2�~���A�}�C�i�X0�Ƃ�����̒��Ԃ�10.1�~����ڎw���ĉ��H����B�����������H | |
�u�}�ʂł͌����������Ƃ��}�C�i�X�̂��̂�����܂����A���̂Ƃ��͌����̒����ƂȂ�ƃ}�C�i�X���ڕW�l�ɂȂ�̂ł��ˁv
| |
�u���̒ʂ肾�v
| |
�u�g�ݍ��킳�镔�i�ɍ��킹�Ē�������K�v�͂Ȃ��̂ł����H�v
| |
�u�Ȃ��B�Ƃ��������̐��@�����̒��ɂ���ΕK���g�ݏオ��悤�ɐ��@�����͍l�����Ă���v
| |
�u�ւ��A�{���ł����H�v
| |
�u�{�����B�����玲�����H����l�ƌ������H����l�͕ʐl�ł��悢�B���������̎d�オ����m�F���邱�Ƃ��Ȃ��v
| |
�u���܂ł͊������鎲�ƌ��͕K�������l�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂������v
| |
�u�̂͂����������B��������ʐ��Y����悤�ɂȂ����Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�v
| |
�u�ő�ƍŏ��̑g�ݍ��킹�ł����v�Ȃ̂ł����H�v
| |
�u���̐��@�̍ő�ŏ��A���̐��@�̍ő�ŏ��̂Ƃ��ł����v�Ȃ悤�ɐ}�ʂ������̂��v�҂̎d�����v
| |
�u���܂ł���Ȃ��Ƃ�������ꂽ���Ƃ�����܂���v
| |
�u�Ƃ������Ƃ͉��H����l�͌�������ł͂Ȃ��A�K�����@�ʂ�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁv
| |
�����͎g���o�C�g�A���ߕt���A���H�����Ȃǂ���ʂ苳���āA3�l�ɂ��̒ʂ�d���������Ă݂�B���N�͎d�������Ă����A���ł������o�ꂷ��ƌ����Ă������炢�����猾��ꂽ�ʂ�ɂ����Ǝd��������B���������̂����c�����@�𑪂��Ċm�F����B������ƂƂ����̂��������̂ōX�ɐ����H������B | |
�u�}�ʂ̐��@�������ɓ����Ă���ΗǕi�ł͂���B���������H����Ƃ��͕K�������̒��S���@��_���ĉ��H���邱�ƁB�Ȃ����킩�邩�H�v
| |
�u���ۂɂ͑_�������@�s�^���ɂ͂Ȃ炸�o���c�N�Ǝv���܂��B���̂Ƃ���������O��Ȃ����߂ɒ��S���@��_���̂��Ǝv���܂��v
| |
�u���̒ʂ肾�B�����͉������Ȃ�����o�C�g�̏��Ղ͂Ȃ��Ǝv�����A���ʂ͍ޗ��̈Ⴂ�A�o�C�g�̈Ⴂ�Ɩ��ՁA�ȂǂŃo���c�L���ł�B�������Ɍ����̐^��_���B���ꂩ��������Ăѐ��@�̏㉺�ϓ��ł͂Ȃ����璍�ӂ��邱�Ɓv
| |
��
�����̒��ƂȂ����B�� �� | |
�u���ꂶ����H���Z���n�߂悤�B��\�҂͑o��3���A�}�ʂ͓������́A���H���͊e5���B���H���Ԃ͑�ڂɌ���1��7�E8�������玝������1���ԂƂ��悤�B���̎��Ԉȓ��Ȃ猸�_�͂Ȃ��B�S��������ɐ��@�𑪂�A�\�ʏ�Ԃ����Ĕ��肷��B �R���������瑤�̐l�Ԃ�������s�����낤����A�����炩���1���o���Ă���B������Z�҈ȊO���炾�v | |
�u�悵�A�������v
| |
�u�������ዣ�Z�J�n���v
| |
���ɓ�����6��̐��Ղɍޗ����e5�Ɛ}�ʂ����ăm�M�X�ƃ}�C�N�����[�^�[��p�ӂ��Ă������B�V�l�̏��ɂ͐}�ʂ̂ق��ɉ��H�菇���Ǝg�p����o�C�g3���u���Ă���B �S���@�B�ɋ삯����č�Ƃɓ���B ���c�͐R�����ďo���Î�̐E�H�ɘb��������B | |
�u���߂܂��āA�����͒�����ł����H�v
| |
�u����Ȃ��Ƃ͂���܂���B�������������܂�����ŁA�����͂܂�2�N�ł��v
| |
�u��Ђ�ς��̂́A��͂�ҋ��ł����H�v
| |
�u��������͂ǂ��������ς��Ȃ��B�l�������I����������͂ǂ��������тɂȂ�v
| |
�u���ꂶ��ߐ��ς��̂͂Ȃ��ł����H�v
| |
�u�l�ԊW���˂��`�A�C�ɓ���Ȃ����Ƃ�����Ɖ݂͊�ς���B��Ђ�ς���Ă��������ς��킯�ł͂Ȃ��Ȃ�A�C����������Ƃ��낪�����v
| |
�u�Ȃ�قǁA�ƂȂ�Ƃ����ō�ƕ��@���w���ʂ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ玫�߂�̂ł����H�v
| |
�u�����Ȃ邩������Ȃ��ȁv
| |
�u�����ł����v
| |
�b���Ă݂�Ό����Ĉ����l�Ԃł͂Ȃ����A�K�������邳���Ƃ���ł͓��������Ȃ����i�̂悤���B �O�ł������ł������ł��S���n������ďC�s����l�������������ゾ ���c�Ɠ��������ĐE�H��\�̐E�l��3�l�́A���̂���䂪�N���Ȃ��悤�ɂƂ��ǂ�����B 30��������ƐE�H��\�̕��͉��H�������n�߂��B�E�H3�l����������10�����炢�ŐV�l3�������H���I������B ���c�������ƐE�H��\�̐R���ɐ�������B | |
�u�}�ʂɐ��@�������Ă���Ƃ���͕K�����肷��B���@�����������Ă���Ƃ���͌������ɂ��邩�ǂ����肷��B���@�����L�����Ȃ��Ƃ���͈�ʌ����Ŕ��肷��B�\�ʎd�グ�L��������Ƃ���́��̐��ɍ����Ă��邩�ǂ������m�F����B ���ʂ�}�ʂɒ��ڋL�����č��۔�������Ă��������B��l�œ������̂𑪂�܂ł͂Ȃ��ł��傤���甼�����������Ă��炢�A�����炢���肪�����������̂��m�F���Ă��������v | |
20���������炸�Ɍ����͏I������B�E�H��\�����R�Ƃ���������Ă���B ���c�͌��ʂ����ĐE�H�S�����W�߂Đ�������B | |
�u�����m�̂悤�ɐE�l���l���ĉ��H����̂ƁA�Z�t�̎w���̒ʂ���H���鋣�Z�����Ă�������B���̌��ʂ\����v
| |
�u�����I���ʂ��y���݂��v
| |
�u���\�͐E�H����R���ɏo�Ă�����������炵�Ă��炤�v
| |
�u���\����B�V�l3�l�����H����15�{�͑S���Ǖi�������B�E�l3�l�����H����15�{��9�{�����@�������O��Ă����B�����ĕ\�ʎd�グ�����w����O��Ă����̂�8�{�������B ����ĐV�l�̏������v | |
�u��k����˂��`�A�������Ȃ��ƐM�p�Ȃ�˂��v
| |
�u���������A�ڂ�������̂���A�ǂ������Ĕ��f���Ă����v
| |
���Z��6�l�����łȂ�����ɂ����E�l10���l�����b�ƏW�܂��ĉ��H�������̂��肩���ɂЂ˂���܂킵���B | |
�u�m���Ɉ�ڌ��Ďd�オ�肪�Ⴄ�v
| |
�u���@���O��Ă�����āH�@���������}�C�N�����[�^�[���Ăǂ��g���v
| |
�u�}�C�N�����[�^�[���g���Ȃ��̂���v
| |
10���قǂō����͎��܂����B | |
�u���[��A�m���ɋZ�t�Ɏw�����ꂽ�V�l����������̂͗Ǖi���B�ƂȂ�Ƃ��ꂩ��͋Z�t���w�������Ƃ���̐n�����g������ꂽ�ʂ�ɉ��H���邱�ƂɂȂ�̂��H�v
| |
�u�������Ă��炤�B�����C���������邱�Ƃ͂Ȃ��B�����ɂ��铡���Z�t�͒��x�e�������B�ނ̎w���ɏ]���ĉ��H����A�ǂ̂悤�ȉ��H���@���ǂ��̂���������Ɗw�ׂ�Ƃ������Ƃ��B���ǂ݂Ȃ���̘r���オ�邱�ƂȂ̂��B���������������炦��w�Z���Ǝv�������v
| |
�u���܂ł͂��R�̑叫�������Ă��Ƃ��E�E�E�悵���͂��ꂩ��͋Z�t�̌������Ƃ��Ďd�������悤�v
| |
�u�Z�p���i�ނ��n�����i������B������������̕ω��ɕt���Ă����Ȃ��l�́A������@�B���H�̐E�l�Ƃ��Ă���Ă����Ȃ��Ȃ�B ����l���������߂͂��Ȃ��B��X�͍���Ȃ��B�V�l���琬���Ă������Ƃ��ł���v | |
���̐E�H�����͂��낢��b�����Ă���B�C�ɓ���Ȃ��Ŏ��߂�l�����邾�낤�B ���т�H�ׂɎ������ɖ߂�Ɠ����͓��c�ɘb���������B | |
�u���c��ѓa�A�Ȃ��V�l�ƌÎ�����킹��Ȃ�čl������ł����B��肭�����Ă悩�����ł����A��������̕����ǂ����ʂ�������܂��������ł��ˁv
| |
�u�����A����Ȃ��ƍl���Ă����܂���ł����B���͓�������ɑS���̐M���������Ă܂�����ˁB ���͂��̕��@�͈ɒO��������K������ł��B����������O�A�ɒO���C���H���̎w�����n�߂����ł����A�Z�p�m���Ƃ��Z�t�����ۂɎd�����ł��Ȃ����ƁA�E�H�Ɍ�����Ɣ��_�ł��Ȃ����ƁA�����������Ƃ��ɒO����͉��P���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝw�E������ł��B�Z�t��Z�p�m���͎��ۂ̎d�����ł��Ȃ��Ă��w���ł��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƌ������̂ł��B ����ɑ��Ė؉z�������A���Ⴀ�ɒO����Ȃ�ł���̂��Ɣ��_������A�ł���Ƃ����̂ł��v | |
�u�ق��A�ɒO��������̋C�������ł��ˁv
| |
�u���₢��A�����ł͂Ȃ��Ǝv���܂���B�����͈ɒO������d�����Ȃ��ĕK���������̂ł��傤�B �Ƃ������؉z�����͈ɒO�����������Ȃ�A�ɒO�����o���̃V���N����𑼂̐l�ɋ����Ă݂�Ƃ����b�ɂȂ�܂����B�����͍H���ɂ̓V���N����ł���l�����炸�A�O���̐����Ɉ˗����Ă����̂ł��B �ɒO����͂��̒��������ł��B�ł��Ȃ�������H���̎d�������ނ���Ƃ��������Łv | |
�u�����C���H���̎d�������Ă���킯�ł�����A��萋�����킯�ł��ˁv
| |
�u�����ł��B�ɒO����ׂ͍��Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ��Ă�������m���Ă����̂ł��ˁB������h�����ڒ��܂������Ƃ������Ă܂����B�Ō`���Ɨn�܂Ɗ�ߍ܂̊W�𗝉�����Γ����Ƃ��v
| |
�u�������ł��ˁB���͎��������Ă����d���ɂ͎��M������܂����A��������Ƃ̂Ȃ��d���͂ł��܂���B�܂��Ă₻���������ȂǂƂ́v
| |
�u�܂��A����Ȃ��Ƃ�����܂����B�����č����͓�������ɓq�����킯�ł���A�A�n�n�n�n�v
| |
�u�A�n�n�n�n�A���Ⴀ���c����͈ɒO����̌O��������Ԓ�q�Ƃ����킯�ł��ˁv
| |
�u�ɒO����͋Z�p�����邵�M�O������A�������l�ł��v
| |
�u�����ɒO����Ɍ����܂ꂽ�̂Ȃ�A�����𗧂��Ȃ����܂œ������܂���ˁv
| |
��
�� �� |
������A���c��т��H������Ă���Ɛ�y���V�l�������Ă���B����Ăċ삯����B |
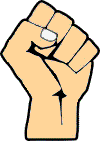
| |
�u���������A���\�͂悹�A���܂͎~�߂�v
| ||
�u���܂��Ⴀ��܂���B��V��@�������Ă�����ł���v
| ||
�u�ǂ������������Ȃ̂��ȁH�v
|
�u���V�����H���Ă��镔�i���^�ׂƌ������̂ł����A�������Ԏ��������ɍ�Ƃ����Ă����̂ł���v
| |
�u���̘b�̒ʂ�Ȃ̂��H�v
| |
�u�����ł��B�ł������������ޗ��Ɗ����i�̉^���͊e�����s�����ƂɂȂ��Ă��܂��B�����l�̂��Ƃ܂ł���Ύ����̎d�����x��܂���������������܂��v
| |
�u���@���@���@�A���V�������Ă���̂����瓖�R���낤�B���O�͂܂���l�O�łȂ��C�s���Ȃ���v
| |
�u�����͂Ȃɂ������Ă�����Ă��܂���v
| |
�u�E�l�͐�y�̋Z�𓐂�Ŋo������̂��B�܂艴�������Ă���̂Ɠ������v
| |
�u�����͂��Ȃ��̎d����^�����Ă��܂���B����̓����Z�t�ɋ����Ă���������Ƃ̂ق����͂邩�ɖ��ɗ����܂����v
| |
�u�ȂɁI�v
| |
�u�Ƃ��������̍H����Ŗ\�͂͋֎~���B�v
| |
���̓�����w�\�͋֎~�E�̔��֎~�x���K���ɒlj����ꂽ�B ���c��т�3�����œ����ɋA��A�����͌���10�����߂������B���c��т͏�i�ɋZ�p�m���A�Z�t�͓����Ƒ��̖C���H���̐l���ٓ������I�ɍs�����ƁA�E�H�����݂Ɍ��C������K�v������\�����B |
�Z�p�҂���Ǝ҂�������������ɂ́A�Z�p�҂���Ƃ���Z�\���K�v�Ǝ���邩������Ȃ��B���ۂɎ��͌���̐l�������߂ɂ��̂悤�ȕ��@���g���Ă����B
 ���������͂����ł͂Ȃ��ƍl���Ă���B������Z�\�����邱�Ƃœ������͕̂K�v�łȂ������łȂ��ԈႢ�Ȃ̂��B�l�����̂ɑ����肤�܂��ł��邱�Ƃ͂Ȃ����A�����łȂ��Ă��l�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���������͂����ł͂Ȃ��ƍl���Ă���B������Z�\�����邱�Ƃœ������͕̂K�v�łȂ������łȂ��ԈႢ�Ȃ̂��B�l�����̂ɑ����肤�܂��ł��邱�Ƃ͂Ȃ����A�����łȂ��Ă��l�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���Ⴀ�A�ǂ�����̂��ƌ����A�l�������邱�Ƃ��ł���悢�̂��B���c��т������ɍ�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A�������������l�ɋ��Z���������ƂŁA��������������肾�B
�X�|�[�c�Ńv���[���[�Ƃ��Ă̗͗ʂƃR�[�`�Ƃ��Ă̗͗ʂ͐������Ⴄ�B�����Əd���̂悤�ɁA
�싅�̖쑺�ē̂悤�ȓV�˃v���C���O�}�l�[�W���[�����邪�A����͋H�L�Ȃ��Ƃ��B�����͑I��Ƃ��Ă͓V�˂��낤���A�ēƂ��Ă͖}�˂��B�����đI��Ƃ��Ă͕��}�ł����Ă��ēƂ��č˔\�������l������B���E���[�j�������łȂ��A�v���I��łȂ������ē��v���T�b�J�[�̊ēƂ����͉̂��l������B�̂���A���I��͖��ēɂ��炸�Ƃ����B
| �����O�̘b | ���̘b���� | �ڎ� |
��1 |
�d�����Ƃ͋��Y�@�ɋK�肳��Ă��������ŁA�d���������邱�Ƃ������ƈႤ�B�ł͒����Ɖ����Ⴄ���ƂȂ�Ƃ킩��܂���ł����B | |
��2 |
���R�Y�@ ��57���@�㊯�m���߃j���R�V���n�V�j���n�Z�T���҃n���m���ʃj�n�e�|�ЃX 3���@���m���m�ꍇ�i���g�L�n�ܔN�ȉ��m�����j�|�X ��58��1���@�}�o�i�Ƃ���j�V�e�O���m�߃��ƃV�^���҃n���m���ʃj�n�e�|�ЃX 3���@���m���m�ꍇ�i���g�L�n��@�n�O�N�ȏ�m�L�������j�|�V���m���m�҃n���N�ȉ��m�����j�|�X ���Y�@�ł͔w�C�Ƃ����ߌY�͋L�q����Ă��Ȃ��B�̂͂���ȓ����ɔ�����悤�Ȕƍ߂͑z��ł��Ȃ������̂��낤���H ���̎���ł͎��̍ߏ���[�Ă邵���Ȃ��悤���B ��O�S��\���@�@�l���\㦃V���n�����V�e������N�n�؏��ރ��x��V�^���҃n���\����m�߃g�׃V�ȏ�l�N�ȉ��m�d�����j���V�l�~�ȏ�l�\�~�ȉ��m�����������X ����ɂ��Əd����4�N�ȉ������痤�R�Y�@���͌y�����H �Ȃ��A���݂̌Y�@�͉��L�̒ʂ肿���Ɓu�w�C�v�Ƃ����ƍ߂��L�q���Ă���B 247���@���l�̂��߂ɂ��̎�������������҂��A���ȎႵ���͑�O�҂̗��v��}�薔�͖{�l�ɑ��Q��������ړI�ŁA���̔C���ɔw���s�ׂ����A�{�l�ɍ��Y��̑��Q���������Ƃ��́A�ܔN�ȉ��̒��͌\���~�ȉ��̔����ɏ�����B �Ȃ��A�̖ʁE�ʖڂ��ێ����邱�Ƃ�"���Ȃ̗��v��}��"���ƂɂȂ邻���ł��B�Ə����Ă��āA�u�̖ʁv�Ɓu�ʖځv�͈Ⴄ�̂��ƒ��ׂ���A�̖ʂ͌`���I�Ȃ��ƁA�ʖڂ͌Ȃ��p���������Ɗ����邱�Ƃ炵���B�肩�ł͂���܂���B | |
��3 |
��̓I�ȃo���c�L����������������������̂ł����A�c�O�Ȃ���1910�N��̋@�B���H�̐��x�Ƃ������̂�������܂���ł����B ���L�̂悤�ɂ����������Ƃׂ��_��������悤�ł����A�{���܂ł��ǂ�܂���ł����B �u�����E���a�E�������ɐ��삳�ꂽ�H��@�B�ɂ����H���x�̔�r�ƍH�w����ւ̉��p�v���� �v�Y�A2012 | |
��4 |
�����q�����������a30�N���̐E�l�́A�g�̉��̕����������đS�����C�s����l�����������B�܂��Ƀt�[�e���̓Ђ���ł���B �ߏ��̏����̑��q�͗��e�t�ɂȂ��Ă����ɏo�z����30���炢�ɂȂ��ċA���Ă��ăI���W�̓X���p�����B����Ȑl���吨�����B���ƈ���Ĕ�s�@���V�������Ȃ����ゾ����A�����ɍs�����Ƃ͐e�����痣��ďC�Ƃ���Ƃ����C�����ɂȂ����̂��낤�B �ł��܂��ٗp�ی������N�ی����Ȃ����ゾ��������A�����������Ƃ����Ă��}�C�i�X�͂Ȃ������̂��낤�B���Ȃ��X�̐��������铦���ł������l�ȊO�A�����������Q�̓}�C�i�X�v�f���肾�낤�B |
�O���Ј��l���炨�ւ���܂����i2017.12.05�j
����Q���� ���ǂ�ȎЉ�ł���Ђł��ƍ߂�����l�����Ă��������Ȃ��B���͂����������Ƃ��B���Ȃ����ƁA�@�Ɋ�Â��ēK���ɏ������A����������J���邱�Ƃ��R���v���C�A���X�ł͂Ȃ����Ǝv���B �܂��ɁA��ʂ�Ȃ̂ł���B ����Ȃ̂ɉ�Ђɖ��W�Ŕƍߎ҂��o���ꍇ�ɂ́A��ςȂ��ƂƂ��ĕ���܂��B �Ӎ߉���݂�A�{���̃R���v���C�A���X�łȂ����Ƃ��킩��܂��B �u���Ԃ������������Đ\����܂���v�ƌ������́A���Ԃ������������Ȃ���Ηǂ��̂��H�Ɠ˂����݂����Ȃ�܂��B ��Ђ̑����u���Ԃ������������Ȃ���Ηǂ��v�Ǝv���A�s�ˎ����B�����ƂɈꐶ�����ɂȂ�܂��B �ꎞ�@�_�Ɂu���Љ�I���͂̔r���v���L�ڂ��邱�Ƃ����s�������Ƃ�����܂��B ��������Ă��āA�����l�]�ƈ�������A�Ј��{�l�ƌ���Ȃ��Ă��e�Z��e�ށA�z��҂̌W�݂�F�l�܂Ŋ܂߂�ΊW�҂����Ȃ�����܂���B ����͗ϗ��̖��ł͂Ȃ��A���v�̖��ł��ˁB ����Ȃ�A�e�Z��A�z��҂ȂnjW�݂̂ǂ��܂ł��u���Љ�I���́v�ɂȂ邩�A���������Ȃ�����Ǘ��ł��܂���B �^�ʖڂɂ�肽������A�_�������Ă�����Ђɕ�������u���̍��ڂɎ^�����Ȃ��ƌ_������܂���v�Ƃ̂��ƂŌ��ǁ@�������͋����Ă���܂���ł����B�@���̈ꎖ��m��A��Ƃ��R���v���C�A���X�ƌ����Ă������悤�Ȃ��̂Ȃ̂��Ǝv���܂��B ���̒��ɂ�IBM�̂��Ƃ���Ђ͋H�ŁA���Ђ��낤�������́u���Ԃ������������Ȃ��v�Ȃ�Ηǂ��Ǝv���Ă���̂��Ǝv���܂��B |
�O���Ј��l�@���x���w�����肪�Ƃ��������܂��B �\�r�����͗��s���Ⴀ��܂���B���Ō��܂��Ă���܂��Ė_��s���Y����ɂ͋L�q���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B ���č��ł͔p���������ϑ��_�̃`�F�b�N�Ƃ����̂͒�Ԃł����A����ɋL�ڂ��Ă��Ȃ��ƒNjL���Ă���Ƃ��肢����̂�����܂���Ԃł����B ���Ⴀ�s���̂ЂȌ^�ʂ�\�r�����������悢�̂��Ƃ����A�Ώ۔͈͂��A�u�i�@�l�̏ꍇ�́C��\�ҁC�����C�܂��͎����I�Ɍo�c���x�z����҂��܂ށj���\�͒c�C�\�͒c���C�\�͒c���\�����C�\�͒c���łȂ��Ȃ����Ƃ�����T�N���o�߂��Ȃ��ҁC�\�͒c�W��ƁC����C���������E�@�������E�Љ�^���W�ڂ��S���C����m�\�\�͏W�c���̔��Љ�I���́i�ȉ��u���Љ�I���́v�Ƃ����B�j�v�Ƃ���܂�����A�_�����ԂƂ��^�ʖڂɍl������n���R�����܂����ˁB �Ƃ͂����A���������Ȃ��킯�ł����玄�́u�NjL���Ă��������v�Ƃ����A��č����́u�NjL���܂��v�Ɖ��A�������ɏ����Ƃ������Ƃ�1�������A���ۂɂł��邩�ǂ����́H�ł���܂��B �ł��Ȃ��ƌ���ꂽ���Ƃ�1�x����܂��B�����̎В����u����Ȃ��ƌ����������ł���Ƃ���Ȃ�ĂȂ���v�Ƃ��������̂ŁA�u��������ꂽ�v�ƕ��ɏ����܂������A�N������ȏ�̃t�H���[�͂ł��܂���ł����B�܂����i����ǂނ̂���l�̐��E�Ȃ̂��A�悭�킩��܂���B�Ƃɂ����ȒP����Ȃ��ł��B �ł��A�����Ƃ��̗��s���Ⴀ��܂��炲���ӂ��I |
�ِ��E�R��������ɂ��ǂ�
�����W�O�O�̖ڎ��ɂ��ǂ�