18.10.15
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。
ISO認証が始まる以前の二者間の品質保証協定においても「品質マニュアルと同等のもの」(以下 品質マニュアル)を作成していた。名称は「品質保証体制」とか「品質システム記述書」とかいろいろだったが、品質保証要求事項への対応を記述していたのは同じだ。もちろんISOの要求事項と違うし、章立ても違う。ただ「客先の要求をいかに実現するかという概要を記したもの」であることは同じである。
もちろん客先は複数あったから、客先に応じて品質マニュアルの名称も形式も内容も異なった。「A社様向け品質保証体制概要書」とか「B社様向品質システム」なんて具体だ。
当然であるが、A社向けはA社の品質保証要求に対応したものであり、B社向けはB社の品質保証要求に対応したものである。だからA社向けの表紙の社名だけB社に書き換えても使えない。
まず要求事項が違う。会社によってトレーサビリティ要求があったりなかったり、形態管理を求めたり求めなかったり。要求内容も違う。A社の計測器の校正間隔は1年で、B社は半年のこともある。作成する記録も違うかもしれないし、保管期間も異なるだろう。故に客先毎に品質マニュアルは異なり、他への転用はできない。
同様に、納入者C社が客先A社に提出する品質マニュアルにはC社の組織体制や業務手順が書かれるわけで、客先が同じくA社であっても納入者C社の品質マニュアルを納入者D社の職制名に一括変換したところで意味が通じるわけはない。業務手順が違うかもしれないし、設計とか製造の一部を外注しているかもしれない。
だから品質マニュアルは納入者、購入者、品物によって異なり、すべてがユニークなものとなる。
品質保証部門は客先の要求に、いかに手間をかけずに対応するかを考えて実行するのが仕事だ。私はそんな品質保証の仕事をしていた。
ISO認証が始まった1992年頃のこと、参考にと他社のISOの品質マニュアルなるものを見て、なんだこりゃ!と思った。だってISO規格の「すること」を「します」と直しただけのものだった。審査員もそれで良しとしているのが更なる驚きである。
| 規格文言 | マニュアル完成 | ||||
| ○○すること |
|
○○します |
| そんなことじゃないだろう ! | 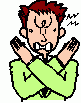
|
サポーズ、二者間の取引において客先の品質保証要求に「〜をすること」と記述してあるところを「〜をします」と書きなおした品質マニュアルを提出すれば、嫌味を言われて差し戻しになるのは目に見える。
いったいどこが品質システムを書き表しているのか !?
そこに書いてあるのは「要求されたことをします」という意味しかない。
そんな定義から外れた品質マニュアルもどきを見て、ISO審査員は疑問を持たずにOKするのを見て呆れた。彼らはISO審査員登録をしていたのだろうが、審査能力はなかった。それは審査員が世代交代した21世紀の現在に至っても変わらないようだ。
今日、伊丹は内務省に呼び出された。いや別にお叱りとか査問ではない。用件は第三者認証制度が始まって半年が過ぎ、今までの状況報告とその検討会である。 実際は真剣な報告や討論ではなく、半分 同窓会のようなもので和気藹々だ。会議が終われば内務省主催の懇親会だ。
認証制度に関わっていて日頃付き合いのある他のメンバーと違い、伊丹は彼らに会うのは最後の審議会以来7カ月ぶりになる。 会議は予定通りシャンシャンと終わって懇親会である。お互いグラスを持って話して歩く。 宇佐美は体重は変わらないようだが、貫禄というか偉そうな雰囲気が倍増している。 黒田も鬼軍曹だったとは思えぬ人当たりが柔らかくなり商店の旦那か会社員にしか見えない。 | |||||||||||||||||
「ドロシーさん、審査で忙しいと聞いてます。不適合なんてありますか?」
| |||||||||||||||||
「審査が始まった直後は不適合以前の問題でした。なにしろ内務省の品質保証規格を理解してないのですから。品質手引書に計測器管理を校正をしますとあるけど、実際にはしていない。どうしてかと聞くと、やると書いていれば良いと思っていたとか、イヤハヤ」
| |||||||||||||||||
「それどころじゃありません。会社の品質保証体制の概要を記述した品質手引書をどう書くのか分かってない会社がほとんどです」
| |||||||||||||||||
「そうなんですよ。それで認証を受けた会社の品質手引書が高い値段がついて売られています。先んじて認証を受けた会社はそれを商売にしているほどです」
| |||||||||||||||||
「ほう〜」
| |||||||||||||||||
「実はですね、当社とグループ企業は過去から品質保証を行っていて品質手引書はありました。それでそういったノウハウをビジネスに生かそうと、グループ企業の品質手引書を10社ほど選んで本にして出版しました | |||||||||||||||||
「へえ! そんなもの・・いや失礼・・そういうものが売れるのですか?」
| |||||||||||||||||
「売れますよ。結構高い値付けですが最初3000部刷ったのですがすぐにはけてしまい増刷しました。もちろん長くは続かないでしょうけど、品質保証の仕組みとか審査対応の準備が一般に知られるまでは商売になると思ってます。 実はね、審査会社の売り上げは大きく言って三つあるのですよ。うちでは3本柱と呼んでます」 | |||||||||||||||||
「そのみっつが何か知りたいですね」
| |||||||||||||||||
「ひとつは当たり前ですが審査料金。二つ目は審査員研修、ああ、審査会社と審査員研修は別物ですが、実際にはほとんどの審査会社が審査員研修を行ってます。三つめは今 話をしました認証の参考書出版です。」
| |||||||||||||||||
「ほう!そうなのですか。比率はどんな感じでしょう」
| |||||||||||||||||
「まあ割合としては、4対5対1というところでしょうか。へへへ・・あまり言っちゃうのもなんですが、まだ半年ですが年間では審査で1500両、研修で2000両、出版で500両を予想してます | |||||||||||||||||
「いやはや、私が心血を注いでいるコンサル業を軽く上回りますね」
| |||||||||||||||||
「伊丹さん、そりゃひどい。我々だって心血を注いでますって」
| |||||||||||||||||
「宇佐美さんねえ〜、何と言ったらよいか、そういう参考書が必要とされるのは分かるんですが、入札企業から品質手引書の提出を受けた官公庁の担当官からは、どの会社も同じ文言の品質手引書が出てくる、意味がないんじゃないかと問題提起されているのです」
| |||||||||||||||||
「何が問題でしょう? だって官公庁の入札条件のため品質保証認証は絶対条件です、そのために品質手引書を作らなければならない、その方法が分からない人のためにひな形を示すのもおかしくない」
| |||||||||||||||||
「そうこられると反論しがたい。しかしそもそも官公庁が調達する品物は良い品質であってほしいというのが本旨です。そのためにちゃんとした社内体制を作ってもらいたいわけです。 他社の体制を真似て、本当に品質が良くなるのかどうか・・」 | |||||||||||||||||
「実は私のところでも品質手引書をまとめて出版しています。私の会社は建設業ですので、土木建設業の品質手順書をとりまとめています。 宇佐美さんが編集された本も拝見しましたが、あの本は製造、建設、販売、運送など色々な業種の品質手引書を取り揃えてあります。それはそれで便利ですが、その反面、奥行きが浅い感じがします。 私どもの本では土木と建設に特化していますので、参考にしやすいと評判です」 | |||||||||||||||||
「なるほど、そういう切り口がありましたか。次回はそれを参考に・・」
| |||||||||||||||||
「あのう・・・そういう品質手引書が良いかどうかですが、私はこの半年、いくつかの業種の審査をしてきました。また私の研修を受けた方からお便りもいただいています。 そういうのを読みますと、例えば建設業といっても大手か中小か、工事の種類も違うし、単純な会社組織もあり支店や工事現場が多々あるところもあり、みな条件が違います。 だから品質保証の社内の仕組みはみな違うはずです。でも多くの会社は本に載っているひな形を金科玉条として品質手引書を作っている。それが行政から受注する手っ取り早い方法というのはおかしいと思います」 | |||||||||||||||||
「黒田さん、同意です。仰るようにそれぞれの会社の品質体制を記述すべきです。なぜそうしないのでしょう」
| |||||||||||||||||
「文書の構成が分からないからひな形を真似しているのですか?」
| |||||||||||||||||
「海老沢さんの話と違うのです。審査員は教科書通りの品質手引書でないとダメなのです」
| |||||||||||||||||
「なるほどねえ〜」
| |||||||||||||||||
「えっ、伊丹さんはそういうのを当たり前だとお思いですか!」
| |||||||||||||||||
「悪貨は良貨を駆逐するといいます。世に広まるのはまっとうな方法ではなく、見た目だけが良いおかしな方法とかが広まりやすい。そしてそれを信用する人が多いのですよ」
| |||||||||||||||||
「ちょっと、ちょっと! 聞き捨てなりませんよ、私たちの本を悪貨とは。伊丹さん、それは言いがかりだ。
掲載されているサンプルは、当社や子会社で実際の仕事で検証されている品質手引書です」
| |||||||||||||||||
「それはその通りでしょう。ただ御社の業種・業態で有効だったということです」
| |||||||||||||||||
「それで必要十分ではないですか?」
| |||||||||||||||||
「実証済といっても、それは御社においてです。会社はみな企業文化が違います。「組織の三菱、人の三 | |||||||||||||||||
「品質保証においては本質的なことじゃないですね」
| |||||||||||||||||
「企業は人と同じく個性があり、同じ人格なんてありませんよ。そしてその性格にあった行動でなければいずれ矛盾が現れるでしょう」
| |||||||||||||||||
「伊丹さんの仰ること全く同意です」
| |||||||||||||||||
「言いがかりのように思えますね」
| |||||||||||||||||
「しかし画一的な金太郎飴でないと審査員が納得しないとはおかしいですね」
| |||||||||||||||||
「審査員が納得しないなら、それは審査員が未熟なのでしょうね」
| |||||||||||||||||
「伊丹さん、大先輩に対して失礼なことを申し上げますが、現在は私やドロシーさんが審査員教育をしていて、我々の考えが審査員の基本的な考えとなっています」
| |||||||||||||||||
「この第三者認証制度の目的は、企業が一定品質のものを納入できる能力をもっているかを確認することです。 そのとき金太郎飴の品質手引書が審査員にとって分かりやすいことと一定品質のものを供給することと関係があるのかといえば、全くないように思います」 | |||||||||||||||||
「ちょっと待ってください。伊丹さんは第三者認証を受けていても一定品質のものを供給する能力がないと仰るのですか?」
| |||||||||||||||||
「いや金太郎飴の品質手引書で適合としているなら、審査員に能力がないのです。そして認証が信用できないことになる」
| |||||||||||||||||
「それはどういう意味ですか?」
| |||||||||||||||||
「だって金太郎飴の品質手引書と業務の現実に差異を見つけていないなら、審査能力がないでしょう」
| |||||||||||||||||
「ともかく現在は審査員研修も登録も我々の考え方で行われているわけで、タッチしていない伊丹さんに批判されたくありませんね」
| |||||||||||||||||
「まあまあ、加熱しすぎですよ。話題を変えましょう。 先日のこと、某新聞社から易しい認証制度の解説を書いてほしいと頼まれまして、小論を書きました。来週掲載されるので是非読んでもらいたいなと」 | |||||||||||||||||
「まあ、素敵」
| |||||||||||||||||
「大久保先生、それはすばらしい。認証制度のアッピールになりますね。この制度がまだ一般社会に認知されていないので残念に思っていたのです。官公庁と取引するところだけでなく、一般企業すべてが認証するようになってほしいです」
| |||||||||||||||||
「そうそう、私もそう思ってまして、文中で内務省の認証制度は官公庁と取引するところだけでなく、企業同士の取引においても品質を確実にするだろうということ、更には一般消費者に対して品質が良いというアッピールになると書いておきました」
| |||||||||||||||||
「それはすごい、多くの人がその記事を読んでくれることを期待します」
| |||||||||||||||||
「その新聞社にその部分だけ印刷してもらい、審査会社が広報のために配布するなど検討すべきですね」
| |||||||||||||||||
「大久保先生、認証は品質を保証するものではありません。品質保証体制が内務省の品質保証規格に適合していることを確認したというだけです」
| |||||||||||||||||
大久保は口をへの字に結んで斜め上方を見つめる。 | |||||||||||||||||
「うーん、そう言われると・・・・ミスってしまったか」
| |||||||||||||||||
「いいじゃないですか。そもそもの目的はそうであっても、結果として品質が良くなれば品質を良くする方法と言って間違いじゃありません」
| |||||||||||||||||
「ネガティブなことで申し訳ないが、審議会で私は何度も品質保証が品質の保証とか、会社を良くすると誤解される恐れがあると申しております。表現に注意しなければなりません」
| |||||||||||||||||
「しかし難しい概念を説明しても、なかなか理解されません。多少は四捨五入して説明しないと」
| |||||||||||||||||
「ねえねえ、そんな辛気臭い話を止めて明るい話題を語りましょう。私の場合は審査員研修事業がもう忙しくて大変よ」
| |||||||||||||||||
「いや、私のところの研修も同じです。もう数カ月先までの受講者が満杯です。アハハハ」
| |||||||||||||||||
「そんなに審査員が必要なのですか?」
| |||||||||||||||||
「企業で働いていても審査員資格があれば取引先から尊敬されるとか調達先監査で役に立つとか聞いています」
| |||||||||||||||||
「受講者が玉石混交であまり理屈とか厳密なことを言い出すとついてこれないのです。ですから審査員研修においても品質マニュアルはひな形を示して教えているのが現実です」
| |||||||||||||||||
「そういう教え方ではひな形は金科玉条になってしまいますね」
| |||||||||||||||||
「講義では断定していませんが、そう思う人もいるでしょうね」
| |||||||||||||||||
「伊丹さん、現状何らかの対策を取る必要がありますか?」
| |||||||||||||||||
「ちょっと、ちょっと!、審査の第一線で苦労しているのは我々ですよ。伊丹さんは草分けかもしれないが、口をはさまないで欲しいですね」
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
正直言って、25年前にISO審査に関わった人たちがその目的を理解してまっとうな審査をしていたら、今頃はQMS認証件数が20万、EMSが10万件とか隆盛していたのかといえば、何とも言えない。だけど「ISO9000で良くなったのは文書管理だけ、ISO14000で良くなったのは紙ごみ電気」なんて揶揄されることはなかっただろう。 まあ「マニュアルに規格のshallが漏れている」なんて指摘しかできない審査員がたくさんいるのだから、元々救いようがなかったのかもしれませんけどね、 「マニュアルに規格のshallが漏れている」のが不適合でないと理解できる審査員が何割いるものだろうか? 私はISO認証した会社や大学が、環境報告書やウェブサイトにISOについてデタラメ書いているのを見ると、私が恥ずかしくなってしまう。私にそんな思いをさせないでくれ |
いよいよ、この小説もどきの本論に入ります。いいかげんな方法で認証しても全く意味がない、いいかげんな審査がISO第三者認証をダメにした、というのは過去25年間の私の持論であります。
金太郎飴の品質マニュアル、審査員に言われた通りのシステム、有益な側面などというバカバカしい信仰宗教、そんなことを広めた人たちを糾弾したい。
今、ISO第三者認証制度は漸減の傾向にあり、多分2030年までに消滅するだろう。そういう事態を招いたのは、アホな審査員、監督不行き届きの認証機関、それを諫めなかった認定機関だ。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
異世界審査員物語にもどる
うそ800の目次にもどる
