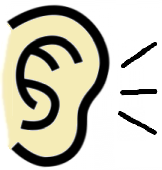18.11.12
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。
監査人は英語のauditor、監査はauditの翻訳語である。Auditは会計監査と解されているが、会計が重点になったのは15世紀以後のこと。元々の意味は「audit」が「聴く」という意味であり、Auditorは聞く人の意味。
|
時代や国が違っても、その言葉も機能も受け継がれた。
15世紀以降ヴェネツィアなどで経済発展により、投資家と経営者が分離したことにより、投資家が経営者の運用を監視するために置いた人をauditorと呼んだ
これ以降 auditとauditorはお金に特化した耳であったが、現代では品質、環境、情報その他業務全般についての耳となり、古代ペルシャ時代に戻ったようだ。
現代では「耳」も三様監査といわれ、内部監査、監査役監査、監査員監査のみっつがある。
注:会社の仕組みや選択によって、三つの監査をしない場合もある。 あなたが行っている、ISO9001、ISO14001あるいは労働安全などの内部監査はこのどこに位置するのかご理解されているのだろうか? 分からないというなら、次回監査の前に勉強しなければならない。 もしISOの内部監査は三様監査とは無関係だというなら、そりゃ問題だ |
日本にも同様な職務は古くからあったが、「耳」でなく「目」に例えられ「目付」と呼ばれた。
|
監視とは悪いイメージを持たれるかもしれない。そうではない。監視もモニターの翻訳であり、語義は「to carefully watch and check a situation in order to see how it changes over a period of time」つまり「注意深く時間的変化を見る」という意味しかない。秘密警察が人民を監視するのもモニターだし、大岡越前が目安箱を置くのもモニターである。
いかなる機械でも仕組みでも、オープンループ制御とフィードバックのかかったクローズドループ制御を比較すれば、クローズドループ制御の方が安定し精度が高いのが分かるだろう。
だからこそ行政でも民間でも監査とか内部統制という仕組みを持つ。そして古代ペルシャよりも優れているのは、国でも会社でも最高権力者が監視するだけでなく、最高権力者を監視する仕組みを備えたことである。
ところで本日は監査人が必要とする能力は何かである。ISO17021では力量(コンピタンス)とあり、それは「知識及び技能を適用するための実証された能力
それはともかく私は大事だと考えるものは、監査人の能力ではなく監査システムの能力ではないか。いや私が言うまでもなくISO17021で認証活動に関与する要員の力量を確実にせよとある
では現実はどうかと言うと・・・
JABは2007年 4月13日に発信した「マネジメントシステムに係る認証審査のあり方
あれから10年、2010年代末になっても項番順審査がメインであるのが現実だ。それは審査員研修機関が怠慢なのか、認証機関が審査員の能力向上を図っていないのか、審査員登録機関が節穴なのか、審査員がCPD
審議会が終わった。皆の顔を見回すとこれで解散ではなく、皆で一杯飲みたいという顔をしている。ここからなら伊丹の家まで電車と徒歩で20分もかからない。それで伊丹は「料亭さちこ」に招いたのである。 海老沢氏と大久保教授は伊丹邸は初めてだが、それ以外のメンバーは料亭さちこの常連である。 伊丹から電話を受けていた女中たちにとっては毎度のことで、一同が到着したときには、料理と酒が出てくる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「伊丹さんのお噂は皇国大学の先生方から聞いていましたが、さすがに我が国のトップクラスの能率技師(経営コンサルタント)ですな。このような立派な邸宅にお住まいで」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「私は「料亭さちこ」と聞いたのでほんとの料亭に行くのかと思いました。まさか伊丹さんのご自宅とは。それに政策研究所の有名な女性が伊丹さんの奥様だとは存じませんでした」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
伊丹は大久保先生と海老沢氏と社交辞令的な話をするが、常連たちは気を使うこともなく飲み始める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「無粋な話で恐縮ですが、例の続きをしてもよろしいですか」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「酒が入ると議論が進みそうですね」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「今日は個人の特性と業務経験の話で終わってしまいました。もうひとつ監査の技術が重要ということでしたね」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「今日はそこまでたどり着けませんでした。それは次回議論しましょう」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「問題の事例を見て疑問を持ちました。問題となったことに手順書という名前の文書がないとか、文書を探すのに時間がかかるとか、そのほかにも規格解釈に関わる問題がいくつもありましたね。 あれは監査の方法が、私の想定しているのと違うから起きたのだと思います」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「監査の方法が違うとは?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「監査とは基準と現実を比較して合っているか、合っていないかを調べることです。ところでふたつのものを比較するとき、同時に二つのものを見ることはできません。片方を見てからもう一方を見るしかありません」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「そりゃそうだろうけど、なにを言いたいのか分からない」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「具体的に言えば、初めに内務省の要求事項を見て、それから現実を見てそれに見合ったものがあるだろうかと調べる方法もあるでしょう。その逆に会社の業務全般について、書類を見たり帳票を見たり現場の動きを見たり、働いている人にいろいろ聞き取りをして、その結果 これらは要求事項のどれに対応しているとか、この作業は要求事項のこれに当てはまると思い当たることもあります。前者を演繹的、後者を帰納的と言い換えてもいいかと思います。 このとき前者の方法では要求事項が主語となり、考えも要求事項が最初に来るようになります。その結果、要求事項の記述と異なっていると、それは不適合と判断しやすいのではないでしょうか。 他方、現実をみて、そこから得られた情報で要求事項を逆引きというかどの要求事項に該当するかという見方をすれば形式的とか名称に囚われることなく、要求事項の本質が満たされているかどうかを判定できるのではないかと思ったのです」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「演繹法とか帰納法と呼んでも間違いではないけど、前者は項番順審査で後者はシステムアプローチと呼ばれている」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「システムアプローチ、つまり現実から探し求めろということですね。でもそれって当たり前じゃない。要求事項からたどっていっても実態は分からないわ」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「どちらから調べても同じ結果になると思うが」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「要求事項からたどって行けば、要求事項に適合するものがあるかどうか分かります。しかし現場で行われているそれ以外の仕事の手順に目が向きません。ですから規格要求に該当する文書や記録が、実際の業務に溶け込んでいるかどうかは分かりません。 他方、業務の実態をよく見てから規格に適合しているか考えれば、現実の仕事の手順が要求事項を満たしているかがはっきりします」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「私もそう言いたかったのです」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「私は審査員研修で、そういう見方で監査をしなさいと教えたはずだ。ええと、審査とは、規格の文言通りのものがあるかを見るのではなく、その企業の実質をみて規格を満たしているかを判断すると言ったように記憶しているよ」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「お話を聞くと、ドロシーさんや黒田さんは元から、その帰納法ですか、そういう監査をしているように聞こえましたが、それには何か理由があるのでしょうか?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「私の場合は伊丹さんから直々に指導を受けたからかしら」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「自分も伊丹さんから指導を受けました。この第三者認証制度のはるか前、砲兵工廠で品質保証を取り入れたときですから、もう6年も前になりますかね」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「私も伊丹さんに指導を受けました。しかし私はドロシーと黒田さんとは違うことがありました。それはお二人は二者監査がメインであり、私の場合は内部監査です。問題があれば自分が改善しなければなりません。 改善しようという目で見れば、規格要求事項でみてOK/NGというのは意味がありません。現実を見てそれが良いかどうかというのがまずあります。不具合を見つけたとき、それが規格要求事項に該当するとかしないとか、あるいはどの要求事項になるのかというのは規格適合を判定するだけの意味しかありません そう考えると、私の立場ではプロセスアプローチ以外ありません」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「審査で問題だと言われた不適合を出した審査員と、お三方の監査のスタンスが違うのですよ」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「スタンスが違うとは?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「普通の審査員は、訪問した会社が規格適合かどうかを調べればいい。その会社の実態がどうかということに関心がないのでしょう。 しかし黒田さんもドロシーさんも、そもそもは下請けや依頼された会社を監査するのが仕事だった。それは単に適合していますとか問題ありませんということでは済まない。要求事項がしっかりと会社の仕事の中に織り込まれて運用されているかどうか調べなければならない。だって適合かどうかではなく、自分が買う製品品質に関わることだからね。 そして宇佐美さんは自分の会社を監査していたわけだから、ひとごとではない。そこが違う」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「ああ、そういうことですね。そのためには要求事項がからたどってもその結果はあまり意味がない。そうではなく現実の業務を見て判断しないと」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「なるほど、神は細部に宿るといいますから」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「ちょっと待ってください。それなら審査員研修でその帰納法を教えれば・・いや伊丹さんは教えていたわけだ。じゃあ、なぜその判断を間違えた審査員は帰納法をとらなかったのだ?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「帰納法を使うには、その仕事を知っていないとダメなのですよ。現場を見て、その仕事を理解できなければ、要求事項が実際の仕事に織り込まれているかどうかわかるわけがありません。そしてまた自分がそこの製品品質に責任ある立場でないと、そういう発想を持てないんじゃないですかね」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「いや、実務を知らなくても観察力があればそれは分かりますよ。現実にドロシーさんは砲兵工廠の品質監査の仕事で、いろいろな会社を回ったと思いますが、そのとき加工方法が分からないからとか製品を知らないから監査できないとは言わなかったでしょう」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「うーん、どうだったのでしょうか。もう監査の仕事を始めた頃を忘れてしまいました。ただ問題ないと監査報告した後に不具合が出たりしては大変だと真剣に観察していたつもりです。 もちろん内務省の監査は手抜きしても良いとは思いませんが、内務省の審査で適合とした会社が、その後 問題が起きても、納入しているものを生産しているとき監査したわけではないから責任を感じないでしょうね。 おっと、そんな経験はありませんけど」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「つまり監査員、審査員が、自分が監査したときのもので問題が起きたりすれば、責任を感じるというわけか」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「そうですね、立会検査して納入された品物の合否判定は立会検査した者には密接に関連しています。他方、内務省の品質保証審査は、その後契約して調達した製品とのつながりはありません。 それに認証審査は抜取で行うから要求事項に100%適合していることを保証するものではない | |||||||||||||||||||||||||||||||
「先ほど出た審査方法の違いのほかに、審査員が負っている責任感が大違いということですか?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「発注者から依頼を受けて監査に行ったなら、製品に不具合があれば責任を感じますよ。それが監査員の矜持じゃありませんか」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「品質保証は製品品質を保証するわけではないでしょう」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「そうではありますが品質が良くなければ品質保証の意味はありません。自分が品質監査をして適合判定をしても、品質が悪いなら品質保証の仕組みや運用が適切とは言えません」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「もし監査で適合であり、品質問題あるいはライントラブルがあるなら、なにか異常があると考えてそれを探らないとなりません」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「規格適合だけで安心する審査員は現実離れしているのか」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「審査は適合・不適合の判定で終わりですが、内部監査や二者監査では是正して終わりなんですよね。 今、気が付きましたが宇佐美さんのおっしゃった通りなんですよ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
審議会の面々が酒も入って和やかに議論していると、幸子が帰宅した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「あらあら皆さん、お久しぶりです。今日はお初の方もいらっしゃるようね」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「奥さん、お邪魔しております」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「海老沢さん、大久保先生、こちらがこの料亭の女将です。 幸子、こちらが内務省の海老沢さんと皇国大学の大久保先生だ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「女将? さちこ? あっ、すると伊丹さんの奥様ですか?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「なにか議論されていたようですが、どんなお話だったのですか?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「品質監査には演繹と帰納の二つの方法がありますが、なぜ帰納法を使わないのかということでした」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「私は内容は分かりませんが、演繹と帰納と聞いただけで簡単に言えば、初めから設問があって合否をつける方が、混とんとした現実から回答を探すより楽だからでしょう」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
幸子にかかるとすべては一刀両断、難しい問題はないようだ。  しかし伊丹は幸子の即答を聞いて、そうか、これが元の日本の世界で項番順審査が大手を振っていた理由なのかと感じ入った。プロセスアプローチをしろとJABが言ったのは2007年。だけどそれ以降10年経っても項番順審査しかできない審査員がウジャウジャいた。彼らは、難しいから、面倒くさいから、プロセスアプローチなんてしなかったのだろう。それは人間の性なのか? だとするとこの世界でも延々と項番順審査が行われ、プロセスアプローチなど誰もしないのだろうなあ〜、そしてそれは、審査の質向上の大きな妨げになるだろう。
しかし伊丹は幸子の即答を聞いて、そうか、これが元の日本の世界で項番順審査が大手を振っていた理由なのかと感じ入った。プロセスアプローチをしろとJABが言ったのは2007年。だけどそれ以降10年経っても項番順審査しかできない審査員がウジャウジャいた。彼らは、難しいから、面倒くさいから、プロセスアプローチなんてしなかったのだろう。それは人間の性なのか? だとするとこの世界でも延々と項番順審査が行われ、プロセスアプローチなど誰もしないのだろうなあ〜、そしてそれは、審査の質向上の大きな妨げになるだろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「伊丹さん、審査は必ずプロセスアプローチで行えと決めればよろしいのではないですか?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「監査手法の違いはプロセスが違うだけですから、どちらで行ったかは結論にも報告書にも表れません。せいぜいがこの指摘はどういう発想で現れたのかと疑うトリガーになるくらいでしょう。とはいえ決定的証拠にはならないですね」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「審査員研修でその方式だけ教えたとしたら?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「なにをしても容易に楽な方に流れるでしょうね。難しい手法から安易な手法に移るのに労はいりません」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「実際問題として、その・・・プロセスアプローチですか、その方法にしたとしていかほどの改善が期待できるでしょうか?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「改善ですか・・・そうすれば良くなると言い切れるものではありません。そういう見方を続けていれば良い審査員になるだろうとは言えるでしょうけど」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「すると完璧な方法はないのですか?」
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「完璧な方法はありませんね。ただ職工だって常に腕を上げようと仕事をしているはずです。審査員もよりよい審査をしよう、それによって社会貢献になるのだと考え励むことでしょうね。 それが己の存在意義でしょうし、産まれてきた理由でしょう」 |
ISO認証の審査員は、審査が持つ意味、重要性を理解していたのだろうか?
それとも審査に行けば契約審査員の日当〇万円が入ると考えているのだろうか。
どうなんだろう?
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 | ||
ISO19011:2006 4.3
なおdictionary.comでは「possession of skill, knowledge, qualification, or capacity.」技能、知識、資格あるいは能力のもつことであり、どちらにしてもトートロジーとしか思えない。 | ||
注3 |
ISO17021:2006 7.2.1〜7.2.7 | |
注4 | ||
注5 |
CPDとはContinuing Professional Developmentの略で、特定の資格者が業務上の力量向上に努めることを必要とする制度。 土木施行管理技士が有名であるが、同様の制度は測量士、技術士、ISO審査員など多くの資格職で定められている。 | |
注6 |
監査した結果、適合/不適合を明確にしないなら、それは監査ではないという声もあるだろう。 1990年頃、ISO9001が登場したとき、品質監査とは適合/不適合を決めるものだ。それまで行われていた指導的な意味合いがあるのは品質監査ではなく品質指導あるいは品質診断と呼ぶべきものだという説が、当時ISOの特集などで正義のように語られたのを覚えている人もいるだろう。 確かにそうかもしれない。だが、目的はなんだろうと考えなければならない。 おっと、LMJの名言(?)「Rightness means nothing, only difference」とは趣旨が違う。審査員としては違いが重要だろうけど、企業においては違いよりも遵法であり効率である。要は視点によって価値観まではともかく、優先は異なる。 内部品質監査結果、会社規則や法律に適合です・不適合ですといって自動的に是正処置がとられるようなレベルならそれでもいいかもしれない。とはいえ、自動的に是正処置がとられるような会社で不適合がでるはずもない。 本来の目的である、会社の仕組みを良くするというスタンスで考えると明らかだろう。 その頃 品証部門にいた私は内部監査をすると、被監査部門の課長に集まってもらい、問題と当面処置、恒久処置、期限などをマトリックスにして、その場で升目を埋め、監査報告書を作成して各課長に配った。イカサマかもしれないが、結果として、早く、良く、手間をかけずに改善するという観点からはスバラシイと確信している。まあ、25年も前のことだ。 | |
注7 |
ISO17021:2006 4.4.2 注記 「いかなる審査も、組織のマネジメントシステムからのサンプリングに基づいているため、要求事項に100%適合していることを保証するものではない。」 | |
注8 |
この場合のホステスとは、もちろん女主人の意味である。 Hostess is a woman who receives and entertains guests in her own home or elsewhere. |
異世界審査員物語にもどる
うそ800の目次にもどる