18.04.09
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。
品質保証協定を結ぶには、まず品質保証要求事項がなければならない。品質保証要求事項といってもいろいろある。真っ先に思い浮かぶ出荷検査は、基本というか必須事項だろう
抜取検査のイメージ図

| ロット N 個 | サンプル n 個 | |||
|  |
|
||
|
〇:良 品 ●:不良品 | 不合格数 x |
広い意味の抜取検査というのは、遥か昔から行われていただろう。昔、現場監督だった私はライン巡回をすれば、生産ラインから適宜抜き取って眺めたり寸法を測ったりした。どこでも誰でもそんなことをしているはずだ。そういう自然発生的なチェック検査は、悪いことではないが統計的ではない
しかしAQLを決めるとか、統計的な抜取検査が自然発生するはずはない。それが行われるには、まず理論が確立していなければならない。調べると統計的抜取検査というものが考えられたのは1928年、日本に入ってきたのは1936年以降だという。そしてAQLというものが考えられたのは、なんと1950年のアメリカ国防総省だった。AQLが産まれたのが私より遅いのに驚く。私は1960年代半ばに工業高校でAQLを習ったが、それは産まれたばかりの最先端技術だったのだ。
それを踏まえると、この物語の1919年にAQLとかncがいくつとか語るのは荒唐無稽だ。
さて、どうしたものだろう?
ここは砲兵工廠、前回、伊丹が訪問してから3週間ほど後である。 | |
「どうですか?要求事項の案はまとまりましたか」
| |
「黒田准尉と二人で頭をひねりました。自分たちの望みをどう表現したらいいのか、具体的に示した方がいいのか要件だけにして向こうで方法を考えてもらう方が良いのか、ちょっと判断がつかないのです」
| |
「少佐殿がおっしゃったとおりでして、どう表現したら相手にわかってもらえるのか、そこが問題です」
| |
「具体的にはどんなことですか?」
| |
「例えば不良品に荷札を付ければいいのか、不良品置き場を決めてそこに置かせるのか、それとも不良品は良品とは識別しろと言うだけで具体的なことは一任するかということです」
| |
「なるほど、まずは拝見させてください。おお、これはいろいろな項目に分かれていて立派なものですね。ほうほう、検査、識別管理、文書管理、計測器の管理、保管、輸送と、なるほど。この項目を管理してもらえばよいわけですね」
| |
「もっと多面的に考えなければなりませんか?」
| |
「いえいえ、前回も申しましたように、お宅が必要だと考えたことを要求すればよいのです。カッコつけていろいろ書いてもしょうがありません。 まず検査から拝見しましょう。要求事項がだいぶありますね」 | |
「実は出荷検査は今まで何個ロットなら何個抜き取るということを指示していたのですが、よく考えると文書はあってもそれで検査しろという指示は口頭だけでした。指示が明確でありませんでした」
| |
「なるほど、それで出荷検査の方法も盛り込んだと・・・それは結構じゃないですか ええと、読みますね 『乙は、完成品が図面に適合していることを確認するために、納入ロットの数によって指定された個数を無作為に抜き取って出荷検査を行う。抜取数と検査方法と手順は、各製品対応の出荷検査要領書に基づいて行う。 出荷検査で合格になったもののみを指定された納入梱包を施し、注文書の数に合わせて納入する』 なるほど、立派ですね」 | |
「アハハハ、お恥ずかしい」
| |
「『出荷検査で不良となったものは不良を示す荷札を付けて、良品とは混入させないために生産ラインから離して保管する。
抜取検査で不良品が一定数以上あった場合、そのロットは不合格とする。不合格となったロットは全数検査して良品のみを注文書の数にまとめて納入する。 不良品については、砲兵工廠に連絡し、再加工するかその他の方法を取るかを協議する。 出荷検査の検査数、抜取数、出荷検査要領書に定められた寸法及び検査項目の検査結果を記録する。検査記録は乙が定めた出荷責任者が確認して了解したのちに、完成品を出荷する』 いやいや立派なものです」 | |
「アハハハハ、頭をひねりましたから」
| |
「内容的には運用していろいろ細かいところを調整して行かないとならないと思いますが、とりあえず気が付いたことを」
| |
「えっ、問題がないのかと聞いていましたが・・」
| |
「まあまあ、まずお聞きしたいのは出荷検査要領書というのは存在するのですね」
| |
「あります」
| |
「それは発注する品物それぞれにありますか?」
| |
「実を言ってありません。それは抜取数の一覧表と一般的な検査方法を書いたもので、ひとつしかありません」
| |
「となるとここにある「各製品対応の出荷検査要領書」という言葉を見直さなければなりません。まあ複数の文書があれば矛盾も出てくるでしょうから、十分読み合わせしなければなりませんね。 ところで一般的な検査方法とは?」 | |
「図面に記載されている寸法はすべて測定して許容範囲に入っていることを確認するとか、錆や傷などのないこととか、そんなことですね」
| |
「使用する測定器の指定とか精度などは?」
| |
「指定していません。まあ寸法公差から適切なものを使うだろうと」
| |
「ロット数と抜取数を決めた数表のようなものはありますか? | |
「これもあいまいなのですよ。例えばロットが100個以下なら10個抜き取って、不良が1個なら出荷して良い、2個以上ならロット不合格とする。ロットが500個なら30個抜き取り2個まで合格、1000個なら50個で3個まで合格というふうに決めてます。 ただ実際には検査がとんでもない手間になるようなときは、個別にもっと少なく指定しています。それと破壊検査になるものはごく少量にしています。だいぶ前に群馬の砲弾を実射する検査では、一日の生産が4000発で試射するのが3発と言ってましたね。この工場でもそのような事例があります」 | |
「抜取検査ということは、納入されたロットに不良品が入るのを認めていることは理解していますね」
| |
「そうなりますね。抜き取らなかった中に不良があるかもしれませんから」
| |
「お宅は入ってくるロットの不良率を、何パーセント以下にしたいと考えているのでしょうか?」
| |
「そりゃ、ないことにこしたことはないよ」
| |
「でも申しましたように抜取検査をするということは、不良の混入を許すのが前提です。もし不良が入って困るなら、抜取検査でなく全数検査するしかありません。 ところで、抜き取ったサンプルでの不良率は、ロットの不良率とみなせるでしょうか?」 | |
「みなせるでしょう。しかしそう考えると抜取10個に1個の不良までロット合格なら1割も不良があるわけか。それはちょっと多いな」
| |
「いや、抜取ったサンプルの不良率と元のロットの不良率が同じではないだろう」
| |
「おっしゃる通り、説明すると難しいのですが、具体的に考えると一目瞭然です。今ロット100個の中に不良が10個あったとします。10個抜き取ったら何個不良がありますか?」
| |
「元のロットの不良率が1割ですから、10個抜き取れば不良は1個でしょうね」
| |
「おいおい准尉、良品90個、不良10個から抜き取るのだから、10個良品ということも、10個不良品ということもあるぞ」
| |
「少佐殿、そんなことはないでしょう」
| |
「めったにはないでしょうけど、なくはないですね。
100個のロットに10個不良があるとき、10個抜き取ったら不良品はゼロのときも1個のときも2個のときも3個のときも・・・10個のときもある。そして、2個不良以上ならロット不合格になりますから、不良品が1個あるいはゼロならロット合格になるけど、もし2個以上10個まではロット不合格になる」
| |
「逆の例を考えると、ロット100個に91個不良があるときでも、10個抜き取ったら不良が1個でロット合格になるときもある」
| |
「ということは抜取検査など無意味ということか」
| |
「無意味ではありません。そういう問題があることを認識しておかなければならないということです。 ええとですね、ですから抜取検査を決める前に、合格とする不良品の混入割合を決めなければなりません。そして同時にそれ以上の不良品が混じる危険を決めなければならないわけです」 | |
「なるほど、抜き取る時バラツクからそれを考えておくということですな」
| |
「ええと、それって買い手の理屈ですよね、売り手から見れば不良品が少ないのに不合格と判定される危険を考えなければならないわけだ」
| |
「さすが良いところに気が付きますね、立場によって望むことが逆になります。ですから基本的に売り手と買い手の交渉で抜取方法とか合格水準が決まります」
| |
「伊丹さんの話を聞くとなるほどと思うけど、そんなことを聞いたのは初めてだ。実際に仕事をするとき、不合格とか合格を一々考えていては手間がかかります。そういう抜取方法を決めたものはないのですか?」 | |
「実を言って抜取検査での不良品の混入の危険というのは、外国でもまだ研究中で確立していません」
| |
「伊丹さんは向こうの世界から来たのでしょう。そういう数表はお持ちなら戴けませんか。出所は出さず、その数表を参考に利用することは問題ないと思います」
| |
「逆に提案ですが、私の持っている統計的抜取検査の本を差し上げますから、それを藤田少佐の大学時代の教官に渡して論文にして発表していただけませんか。そうすれば世の中に統計的抜取検査というものが広がるでしょう。それは現在行われている理論に基づかない抜取検査よりはるかに意味があります」
| |
「私の担当教官はとうに退官しています。でも後輩が教員をしていますから、奴にやらせましょう。私も博士になってからは皇国大学で講義をしていますので顔がきくのです」
| |
「その論文を基にお宅の抜取検査を行っていると言えば売り手も納得するでしょう」
| |
伊丹はあまりにも多くの発明発見が扶桑国で行われると、諸外国の科学者・研究者が不思議がるだろうという気がした。しかし向こうの世界では、発明発見の多くがユダヤ人、それもアシュケナジムがしていることを思えば無問題と割り切った ●
ここは政策研究所である。例によって後藤議員、幸子、米山中佐が話し合っている。● ● | |
「地震時の対応としては、第一に人命、第二に消火という優先順位で行きたいと考えている」
| |
「私は違います。一に人命、二にも人命ではないでしょうか」
| |
「火災は無視しろということか」
| |
「無視ではありません。優先順位が低いのです。そして人の命と言っても火災から逃すというだけではありません。避難場所の確保、水や食事の確保、医療の提供、風呂にだって入りたいでしょう。災害後の職住の支援もあります。 その代わりと言っては何ですが家屋や財産は二の次にするのは仕方ありません。具体的には私の世界の関東大震災の記録は皆さんお読みと思いますが、避難時に家財を積んだ大八車や、行李(こうり)に衣類を入れて背負って逃げたために、とんでもなく混乱、混雑をもたらしました」 | |
「それだけでなく火の粉が飛んできて、荷物が延焼の元になったとありましたね。特に被服廠跡の写真を見ましたが、持ち込んだ大八車や荷物で足の踏み場もない。もし大八車や荷物持ち込みを禁じていたら、あれほどひどいことにはならなかったと思います」
| |
「江戸時代は火事で避難するとき大八車はご法度だった | |
「更に向こうの世界より悪化したことがあります」
|
「なんだろう?」
| 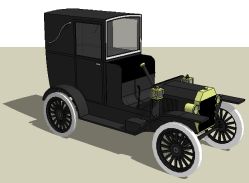 | |
「自動車です。向こうの世界では関東大震災発生時には全国で13,000台くらいでした でもこの世界では既に東京府だけで3万台以上と聞きます。15区内だけでも2万台はあるでしょう」 | ||
「渋滞が目に浮かぶわ」
|
「いや渋滞だけでなく、燃料のガソリンが燃える危険が増すわけだな」
| |
「そうです。人命の被害を防ぎ消火活動を推進するには、緊急時には身一つでの避難しか認めないことです」
| |
「お金持ちとか華族になると自動車での避難になるでしょうね。それを止めることができますか」
| |
「この私が男爵になるくらいで、華族といってもピンキリだからな。ノブレスオブリージなど分かっておらんわ | |
「自動車を通さないために新兵器をどんどん使いましょう。陸軍はFT17戦車を30台輸入したそうです。それを交差点などにおいて通行規制をしましょう」
| |
「30台じゃ足りないでしょう。交差点がいくつあると思うのよ」
| |
「確かに・・・何台あればいいですかね?」
| |
「1000台は欲しいわ」
| |
「ワシも考えておるのじゃが、戦車を破壊消火と消防車に使えないかと考えているのだ。昔なら鳶が長屋や商店を破壊消火することもできたろうが、最近は2階建て3階建ての木造も増えてきている。鳶口では壊せないだろう。 戦車を10台くらい横に並べて走らせたら一挙に30メートルくらいの幅で建物を片づけられる」 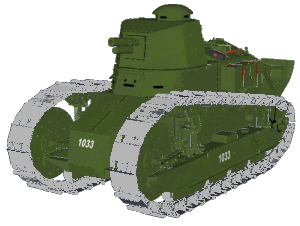
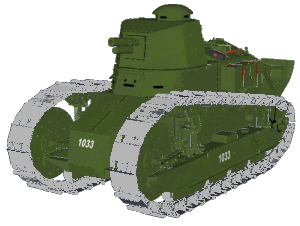
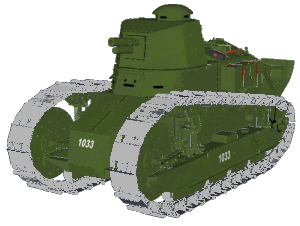
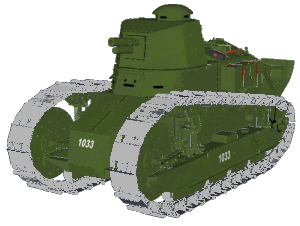
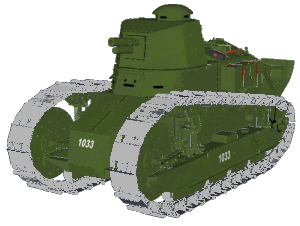
| |
「そういう昔ながらの方法でなくても、今は江戸時代とは違い消防ポンプもあり各所に消火栓もあります」
| |
「君は関東大震災の記録を読んだだろう。地震で水道管は破損し電線も切れた。だから水道も消火栓もビルに設置されたポンプも動かない」
| |
「はあ〜、というと破壊消火だけですか」
| |
「ダイナマイトによる爆風消火もある」
| |
「飛行機から爆弾投下ですか?」
| |
「飛行機もあるし、消防隊が設置してもよい。爆風消火だけでなく破壊消火に使える」
| |
「なんでもありですね」
| |
「10万人の死者を半分にできるならあらゆる手を使わねばならん。ロシアとの戦争で9万人が戦死した。この地震に手を打たないと10万人以上が死ぬ。我々は大戦争をしているのと同じなんだ」
| |
「閣下、半分などと言わず死者1万以下を目標にしましょう」
| |
「それからエンジンを付けた手押しのポンプ車を作りたい。そのためにはまずはエンジンだな」
| |
「隅田川に小型の艦艇を浮かべて放水するというのはどうでしょう」
| |
「船から直接放水しても水が届く距離はたかが知れる。船から消防車までホースをつないで送水したいね」
| |
「海軍に話を付けてポンプを設置するのですか?」
| |
「ある程度アイデアがまとまったら、関係省庁を集めて討議しよう。そこで消防用戦車も消火用飛行機も消防艦艇も話を出す。 もちろんさっきの交通規制とか・・・おっとどちらにしても戒厳令かそれに類する措置を取ることになるだろう」 | |
ドアが開いて二人の男性が入ってきた。小沢医師ともう一人、見かけない顔だ。 | |
「後藤閣下、ご希望の青年を探しました、こちらが島村君です」
| |
「おお、待っておった。火災時の医療体制について話を聞かせてほしい」
| |
「私は国境のない医師団という団体に属していて、世界中の戦場とか内戦地にいって被災した一般人の治療活動に当たっています」
| |
「ほう、奇特なことだ」
| |
「先輩医師である後藤閣下のためにお力になりたいです」
| |
「同じ医師でも月とすっぽん、私の知識など皆さんの前では子供同然だよ」
| |
●
更に半月後の砲兵工廠である。● ● | |
「おかげさまで品質保証協定書が完成しました。既に3社ほどと打ち合わせをして品質保証活動を始めてもらっています」
| |
「実際に実施してみてどうですか?」
| |
「記録を作るのが面倒くさいと言われましたが、契約した通りのことはしているようです。まだ通常の視察にいったていどですが」
| |
「これから実際に納入されるものの品質が変わったのか、不良が出た場合は品質保証協定の効果がどうかを見なければいけませんね」
| |
「定期的に品質監査もしなければなりません。計画しますから初めは伊丹さんが監査の手本を見せてくれませんか」
| |
「喜んで」
|
正直言いましてこのお話を書き始めたとき、私は単に昔にもどって第三者認証というビジネスを「まっとうに」始めたらうまくいくのだろうかという思考実験をするつもりでした。
実際に書き初めて見れば、戦争がないわけじゃない、大地震がないわけじゃない、経済危機がないわけじゃありません。100年前に設定したのが良いのか悪いのか定かではありませんが、過去の1世紀をたどろうとするとそういうこともあるというよりも、そういうことの連続であるわけです。そういう外乱を無視して第三者認証の物語が書けるわけがなく、それらを加味しようとすると、第三者認証は、むしろ二の次三の次になってしまいそうです。
とはいえ、これをなんとか大団円までもちこもうと足掻いております。
さてどうなりますか?
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
実を言って最も基本となるのはISO9003:1987だと気が付いた。 1987年にISO9000sというものが制定されたとき、3種類あった。オールマイティなISO9001、設計を含まないISO9002、そして最終検査のみのISO9003であった。知る限り日本ではISO9001とISO9002の認証が100%で、ISO9003の認証はゼロだったはず。誰もISO9003などに興味を持たず、その意義も理解していなかったと思う。私はそうだった。だけど客に良いものを渡すための最低限となると、この規格は意味あるものと思う。 | |
注2 |
チェック検査とは、抜取検査のように確率や理屈にこだわらず、品質が安定している品目や、それほど重要でない場合適当なサンプルを摘出して行う検査。 | |
注3 |
統計的抜取というのはいつ始まったのか定かではない。発端は1928年アメリカのダッジとロミングが統計的1回抜取検査を発表した。イギリスでは1935年にピアソンの抜取検査の研究をイギリス規格にした。このイギリス規格を日本で研究し制度化しようとしたとき終戦となったという。 参考:「品質管理」 戦前から抜取検査が行われていたのは事実だがほとんどがチェック検査であり、戦前は理論に基づく抜取検査はされていなかったようだ。統計的抜取検査というのは戦後ディミングが来てからである。 参考:世界と日本の品質管理の歴史 | 統計的品質管理SQCの歴史 | |
注4 |
アシュケナジムとは東欧系ユダヤ人のこと。 ユダヤ人が頭がいいと言われるが、実際には科学者、著作家、音楽家などのユダヤ人はほとんどがアシュケナジムである。有名人には、アイン・シュタイン、ファインマン、フロイト、バーンスタイン、ノイマン、キッシンジャー、ドラッカー、オッペンハイマー、ハイネ、スティーブン・スピルバーグ、ボブ・ディラン、カール・マルクス、ビリー・ジョエル、アイザック・アジモフ、ピーター・フランクル、ピーター・フォーク、セイン・カミュなどなど。 ひょっとしたらアシュケナジムは、この小説のように進んだ世界から情報を入手しているということは・・ないか? | |
注5 |
「江戸の火事と火消」山本純美、河出書房新社、1993、p.170 「火事の節、地車、大八車にて荷物を退くべからず(正徳元年1711高札)」 | |
注6 | ||
注7 |
後藤新平は産まれは貧乏士族だったが、功勲により爵位を得、陞爵(しょうしゃく)を重ねて伯爵までになる。このときは男爵だった。 |
異世界審査員物語にもどる
うそ800の目次にもどる