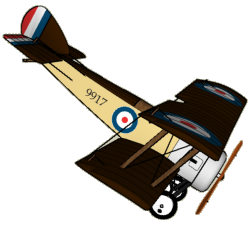18.05.17
*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。
防災訓練、避難訓練、火災訓練、その他名前はいろいろだったが、小学校のときから会社員になっても定年するまで毎年やった。いや嫌だったわけでなく結構面白かったし、その効果を否定するわけではない。
私が小学生だったのは1950年代半ば、当時の校舎は木造2階建てで広い校庭がありその周りは平屋建ての住宅が散在している田舎だった。だから万が一校舎が火事で燃えても地震で崩れても、避難するのは簡単だった。
 しかしその一方学校は簡単に燃え嵐が来れば壊れた。自分が通っていた学校が火事になったことはなかったが、近隣の市町村でなんども学校火災が起きた。だから火災訓練では皆ふざけたりせず、真面目にやった。
しかしその一方学校は簡単に燃え嵐が来れば壊れた。自分が通っていた学校が火事になったことはなかったが、近隣の市町村でなんども学校火災が起きた。だから火災訓練では皆ふざけたりせず、真面目にやった。今考えると、火事の原因は放火とか不審火が多かったように思う。当時はホームレスというか浮浪者というか、そういう人がけっこういて夜は神社とか学校の鍵のかかっていないところに寝泊まりするのは珍しくなかった。そういう人たちが火の不始末で起きたのが多かったようだ。
当時は学校の警備なんてまったくない。火災報知器があるわけでなくガードマンがいるわけもなく、そもそも警備会社というのが現れたのは1964年の東京オリンピック以降だと記憶している・・といいつつググったら、1962年に現れ、東京オリンピックから大発展したとある。
何事かあって気が付いた近所の人から連絡を受けると、先生が恐る恐るやって来た。
ともかく当時の学校は放火や盗難に対しては無力だった。
話の途中で気が付いたことだが、ホームレスというのは最近現れたように思っていたが、実際は私が子供の頃の方が多かったように思えてきた。昔はホームレスという言葉はなかったが、私が子供の頃、神主のいない鎮守というか社には、必ずといってよいほど怪しげな氏名や素性がハッキリしない人が誰かしら無断で住んでいた。
周りもそんなに警戒せず、食べ物を与えたり庭仕事をしてもらって手間賃を払ったりして共存していた。そんなに昔のことではなく、1970年頃まで田舎には普通にいた。ただ今のホームレスのように街中にはいなかった。当時はコンビニもなく飲み屋が残り物を捨てたりすることもなく、時代と共に少しずつ生態が変わってきたのだろう。
おっと、私が子供のときから避難訓練があり真面目にやってきたと書いたが、それは役に立ったのだろうか?
|
|
知らない人は知らないだろうが、当時火事になると火が燃えている最中に、近所の会社や取引先は火災見舞いの一升瓶を持ってきた。だから火事場にはたくさん一升瓶が並んだ。信じられないかもしれないが本当だ。
あれは消火したら飲んでくださいということなのか、一杯ひっかけて消火に励んでくださいという意味なのか、どっちなのだろう?
その後、環境管理の仕事をしていたが、その部署は環境だけでなく機械保全などもしていたので、非常ベルが鳴るとその部署の者は全員、ヘルメットをかぶりカケヤ、脚立、工具などを持って現場に駆け付けた。私ももちろん参加した。そんなことは月に1回はあったが、9割は誤報であり、誤報でなくても不心得者が禁煙の所でタバコを吸い火災報知機が鳴ったなどばかりで、実戦の体験はない。
当初の予定では1921年9月1日に第1回防災訓練をする予定であった。帝太子が関東大震災が起きるであろう日に実施したいと言ったからだ。だが各部門がいろいろ検討するにつれこの日は、学校の夏休みが終わって初めての登校日であり、登校しても挨拶と宿題提出で終わって下校してしまうなど、不都合が見えてきた。 帝太子もこの日に地震が起きるとは言えず、それならずらそうとなり、結局9月10日に防災訓練を行うことになった。 そして、今日9月10日となり、初めての防災訓練である。 | ||
8時00分 私は近衛師団の第二連隊長 橋本大佐である。本日は第1回帝都防災演習である。 大地震が起きて帝都で火災が多数発生したという想定で行われる。わが近衛師団は皇帝陛下及び皇居の防衛が本務であるが、今回は皇居と丸の内の間の外苑での被災者支援を命じられた。 大災害が発生し、怪我人や避難者が外苑と日比谷公園に来たという想定である。 もちろん治療に当たる医療関係者は近隣病院から来ることになっていて、我々の任務は担当地域の治安維持、天幕などの設営を行い医療行為の支援を行う。また避難者には水や食料を配布すること、便所の設営などが担当である。 1年ほど前に炊事車両と給水車が配備され演習に使っているが、この働きがすごい、きっと災害時にも役に立つだろう。 隊員には本日演習が行われることを通知しているが、実施時刻はもちろん伝えていない。また具体的な任務は今まで演習を行っていることから改めては伝えていない。大丈夫とは思うが他部隊に比べてみっともないことのないよう祈るばかりだ。 | ||
8時20分 俺は車屋鉄三郎という。もう70のジジイだが、かっては町火消しの花形纏持ち(まといもち)だった。だいぶ前に曳舟の方で軍隊が消火訓練をすると聞いて見物に行った。昔我々がやったように火が燃え移る前に家並みを壊して燃え広がらないようにするのは同じだが、昔我々がやったように鳶口とカケヤで壊すのではなく、なんと戦車で壊そうというのだ。 大きな戦車が何台も並んで進むのを見て、アッという間に防火帯ができるかと見ていたら、そんなにうまくはいかなかった。戦車が民家にぶつかると確かに家は破壊されるが綺麗に倒れずぐちゃぐちゃになる。挙句に家の屋根は戦車の上に載ってしまった。笑ってしまったよ。 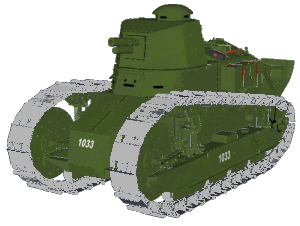 昔から一言多いと言われていた俺だが、ついつい戦車隊の親方のところに行って、押してはダメだ、引っ張れと言ってしまった。
昔から一言多いと言われていた俺だが、ついつい戦車隊の親方のところに行って、押してはダメだ、引っ張れと言ってしまった。幸いその隊長は俺の話を聞いてくれて、戦車を民家にぶつけるのではなく民家にワイヤーロープというそうだが、鉄の縄を引っ掛けて倒すのを試みた。するとキレイに倒れるだけでなく屋根が倒した建屋の上に載るようになった。そうそう、それでいい。俺はそのあとは綺麗に倒していく戦車隊を眺めていた。 一段落して戦車隊の隊長が来て、防火帯を作るとき火元と破壊する方向とか聞いてきた。俺は喜んで昔の経験を話して聞かせた。 それからそれっきりだったが、二三カ月前に家に来て、今度防災演習があるから参加してくれという。俺も孫守しかしていないからイイヨと応えると、演習日の前日に連絡するから翌日早朝に上野の戦車中隊に来て欲しいという。 ということで今ここにいるわけだが、さてどうなるのだろう? | ||
8時50分 私は海軍追浜航空隊の教育隊の友保中尉である。自分はもう1年以上、急降下爆撃の試験に携わっている。
しかし1920年だったと聞くが、アメリカが急降下をして爆弾を落とす方法を考えた。水平に飛んでいるときより投下する高度が低くなるばかりでなく、爆弾が飛行機の飛ぶ方向に進行するので命中率が良くなったのだ。それを聞いて我々も急降下爆撃を研究した。 残念ながら我々の使っているイギリスから輸入したソ式練習機はあまり頑丈ではなく、急角度の急降下はできなかった。とはいえ将来はこれが主要な爆撃方法になるだろうと試験を続けた。 面白いのは爆弾代わりに水を入れたタンクを地上に書いた目標に投下するのだ。本物の爆弾と違い危険はないし、爆発しないダミーだとどこに落ちたのか分かりにくい。水タンクは地面に当たると壊れてあたりに水がはじくからどこに落ちたか一目瞭然で腕の良し悪しが分かる。 陸軍航空隊も急降下爆撃の検討をしていて、ときどき稲毛の海岸で陸海軍の爆弾投下競技会をしている。稲毛は海軍の追浜飛行場と陸軍の下総基地の中間で広い砂浜があるので、こういった演習に向いている。 今日も稲毛の海岸で水爆弾の投下競技をすると聞いている。 | ||
9時10分 私は陸軍航空隊下総基地の加藤飛行軍曹である。下士官であるが操縦技量においては下総基地随一と自負している。1年ほど前から急降下爆撃という方法の試験に関わってきた。陸軍・海軍とも同じ飛行機を使っており、そのためかときどき急降下爆撃の技能大会が行われている。爆弾の代わりに水を入れたタンクを使う。 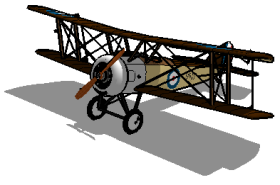 陸軍はこの下総基地、海軍は横須賀の追浜なので、大会はいつも中間にある稲毛海岸で行われる。砂浜に白布で作られた爆撃目標が100個くらいあり、間違えて自分が別の目標に落としたり、目標からはずれたりするのがよく分かるのだ。
陸軍はこの下総基地、海軍は横須賀の追浜なので、大会はいつも中間にある稲毛海岸で行われる。砂浜に白布で作られた爆撃目標が100個くらいあり、間違えて自分が別の目標に落としたり、目標からはずれたりするのがよく分かるのだ。そうそう、つい数か月前だが飛行機に新兵器(?)が取り付けられた。無線電話である。無線電話と聞いたときなんだか分らなかった 実際に装備されたのを見ると、確かに無線でお話もできるのだが、そのほかにいろいろな機能が付いていて、その他に地図が画面に表示され、そこに基地とか自分と僚機がどこにいるのかまで印が出てくる。もし敵が飛んでいればそれも表示されるのだという。こんなものがあれば四六時中きょろきょろと周りを見ることはなさそうだ。だが隊長は機械に頼るな、最後は自分の眼が頼りだという。まさしくその通りだ。だが基地と僚機との位置関係が常にわかることは、大革命だと思う。スピードが出るとか機関銃が大口径とかよりすごいことだ。 今日は今年2回目の競技会だ。海軍の野郎ども、待っていろよ | ||
9時20分 私は香川冨美子、尋常小学校4年です。4年生になったので、登校下校のとき近所の後輩を引率したりお勉強も教えたりするようになりました。大変ですがやりがいもあり、大人に近づいた気がします。 昨日帰るときに先生が「明日は防災訓練だ、下校のときは小さい子を連れて帰るようになる」と言われました。防災訓練とは初めてです。どんなことをするのですかと聞くと、先生も「初めてなのでよく分からない。でも学校だけでなく東京府全域で軍隊も警察も消防も参加するのだ」とおっしゃいました。 どんなものかわかりませんが、なんだかわくわくします。 何時に始まるのでしょうか。朝から緊張します。 | ||
9時50分 ここは皇居の東にある本丸である。この時代はここ皇居の一部ではなかった。中央気象台など普通の官公庁が所在している。とはいえ空き地というか林の方が多い。周囲がお堀で囲まれていて市街地が大火になっても、燃え移る恐れは皆無に思える。 数か月前からここでだいぶ土木工事が行われた。まずブルドーザーで林を拓き、長さ300mの滑走路を造った。次に100m四方ほどの広場を作りコンクリート舗装をした。そしてその周囲にコンクリート製の体育館のようながらんとした建物がいくつか作られた。 今、広場にはたくさんのテントが張られている。中央のテントに、帝太子、後藤新平、近衛師団長、警視総監、そして中野部長がいる。 | ||
「たくさん機械が並んでいるが、まずどんなことをするのか教えてくれ」
| ||
「かしこまりました。まず向こうに滑走路があります。ここから偵察機の発着が行えます。そして万が一の場合は陛下の脱出もできます。 ここは防災司令部です。被害状況は偵察機、地上の警察・消防からの連絡を取りまとめこの画面に映します」 後藤閣下が50インチモニターを前に説明する。 東京の皇居から錦糸町あたりまでの地図が描かれ、その上にたくさんの記号が表示されその中のいくつかはチョコマカと動いている。 | ||
「ほう、活動写真のようだな」
| ||
「天然色の活動写真ですね」(注2)
| ||
「殿下、この画面には火災の状況だけでなく、各部隊がどこにいるかも映し出されています」
| ||
「えっ、私には見えないが」
| ||
「この画面は拡大縮小ができるのです。例えば浅草方面を拡大しますと・・・ほれこの通り、白い□が陸軍1個歩兵小隊、緑の■が1個工兵小隊、青い■が消防車1台を表します。赤い▲は火災現場です。 この矢印を緑や青の印の上に置くと、このように文字が現れます。緑の脇に第2中隊第1小隊とあるでしょう。このように所属までわかるのです」 実は後藤は数日前に吉沢教授から説明を受けたところで、人に説明したくてたまらないのだ。 | ||
「ほう、するとどこかで火事が起きれば、近くにいる部隊に行けと命じることができるのだな」
| ||
「さようでございます。その命令も伝令が走るのではなく、例の無線電話ですぐさま直接隊長に伝えることができます。 もちろんそういった細かいことは我々がするのではなく、数個隣のテントに同じ映写機がありまして、そこで担当者が判断し命令することになっております」 | ||
「状況が分かっても対策がなければどうしようもないのではないか」
| ||
「殿下、そのようなことのないように消防車の整備、ポンプ舟艇の整備などをしてきました。最後の手段として戦車隊による破壊消火もあります」
| ||
「そうですか。後藤閣下、期待していますよ」
| ||
10時10分 私は警視庁 足立巡査である。今日は防災訓練である。といってもいつ始まるか分からない。 数日前に防災訓練にあたっての教育があった。私たち警官は上司の命令だけで動いているわけではない。基本的に法律があり条例があり警察の規則があり、我々はそれを理解してそれに基づいて行動しなければならない。 泥棒だと言われても、逮捕するにはそれなりの証拠が必要だし、また緊急性によって判断しなければならない。 防災といっても状況はいろいろだが、火事場泥棒の取り扱い、避難誘導、怪我人救出などのケースがある。 そしてそこには判断に苦しむ事例は多々ある。危険な状況にある人を自らの命をなげうっても救うべきなのか見捨てても良いのかというのもある。規則では避難民が火のつきやすいものを持って逃げているとき、それを放棄させなければならない。しかしそれがその人の全財産ということもあるだろう。簡単にそんなことができるものだろうか、自分は悩む。 火事のとき、大八車は使ってはいけないというのは徳川時代からの定めである。避難するのに大八車を使用している者があればそれを放棄させなければならない。また最近増えている自動車による避難もご法度だ。もしいたら停止させ、自動車を放棄させる。確かにそれが決まりなのだが、相手が華族だったら停止させる自信はない。 どうかそういうことが起きませんように | ||
 |
10時50分 私は連絡艇68号の艇長 大谷兵曹長である。自分は戦艦に乗りたかったし、それがかなわなければ巡洋艦せめて駆逐艦と願っていた。しかし入隊以来10有余年、東京湾内で連絡艇やタグボートばかり乗ってきた。あげく最近は連絡艇に消防ポンプを付けて船舶火災とか海岸沿いの建物の火災の際の消火訓練などをさせられている。 これも必要な仕事だと頭では理解するものの、故郷の友人たちには恥ずかしくてとても言えない。 今日は防災訓練ということで隅田川を川上に航行している。訓練が始まったら無線で来る指示に従い船を岸に付けて陸の消防車に送水するのが役目だ。やれやれ | |
11時10分 私は近衛師団歩兵連隊の中隊長の近内大尉である。我が中隊は機動化のテストケースとして兵員220名に対しトラックを12台保有している。本日は防災訓練に当たり火災現場の指定を受令した。 その役割は具体的には4個小隊が分担して東京府各所に火をつけることである。と言っても本当に火をつけるのではない。きわめて大きな発煙筒を指定されたところに設置し、火災発生を知らせる仕事だ。既に各小隊がトラックを使い、各10か所つまり40か所に発煙筒を設置した。それぞれに数名の兵士が待機して発煙開始指示を待っている。 40か所というと多いと思うが、実際に大地震が起こればこの大東京だ、100や200の火災が発生するだろう。訓練と言えど少ない気がする。 命令された火災発生は11時30分、既に各隊は発生現場で点火時刻まで待機している。あと10分か。部下が任務を果たすことを期待する。 緊張しているせいかタバコが吸いたくてたまらない。1本吸う時間はあるだろうか? |
これで終わりってことはありません、もちろん次回に続きます。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
軍用機に無線電信機が付いたのは陸軍の97戦(1937)、海軍の96艦戦(1936)からで、それも受信だけだった。 ゼロ戦(1939)には最初から送受信のできる無線電信と無線電話が装備されていた。しかし無線電話は単体では正常に通話できたが、エンジンをかけると実用にならなかったという。エンジンのスパークプラグからのノイズ対策が不完全だったらしい。いやノイズ対策が分からなかったのだろう。 | |
注2 |
二原色カラー映画は1916年に発明されたが、実際の色と大きく違った。三原色のカラー映画は1932年発明である。 |
異世界審査員物語にもどる
うそ800の目次にもどる