お断り |
このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたいという方には不向きだ。 よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。 ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。 |
昨年末に外資社員様から「漢字と日本人」がためになると教えてもらい、図書館から借りてお正月に読んだ。面白い。それで著者 高島俊男の本を数冊借りてくるとこれまた面白い。それでまた借りてきてということを続けている。図書館には40点ほどこの方の本があるので当分楽しめる。
これはその中の1冊である。
注:異なる本が何種類あるかの数え方を知らずググりました。「何点」と数えるそうだ。
ちなみに同じもの違うものを合わせた数は「冊」、同じ本の数は「部」だそうです。
| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| 漢字と日本語 | 高島 俊男 | 講談社新書 | 9784062883672 | 2016.04.20 |
この本のタイトルは「漢字と日本語」とある。先に読んだ「漢字と日本人」も同様だが、名は体を表しているわけではない。基本的に中国から来た漢字を日本人がどう使っているか、そして借用したことで起きた問題というか悲喜劇を書いている。だから本のタイトルと内容が合致しているわけではない。
「漢字と日本人」というタイトルで書いたから、続きは「漢字と日本語」というタイトルで書こうかというノリである。次は「漢字と日本民族」とか「漢字と日本列島」になるのかどうか……
とはいえ学者の書いたものだから、書いていることはふざけたこととかトリビア的なことではなく、証拠・根拠の裏付けはある。
どんなことが書いてあるかというと……
|
今どき、重箱も湯桶も 使うことはないだろう。 重箱はおせちに使うか? |
||||||||||||
お間違えのないように…上記は高島先生の論でなく、私の小学校担任の話である。
この本で高島先生は、過去から偉い学者はそう語っていたとした上で、「重箱読みごときにグダグダ言うな!」とバッサリと切り捨てる。
そしてお前たちは「
ちなみに私が本を買いに行くのは「
言葉は生きているのだから、今生きて使われていることばの由来やいきさつを研究することは価値あることであるが、現実に使われている言葉や言い回しに、難癖つけたり否定するのはおかしいだろうという。
もしそれが悪いなら、お前たちは現在 作られ使われている外来語と和語の混血なんて使わないのだろうと嫌味を言う。
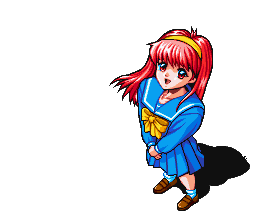 |
| セーラー服 |
現在は英語と日本語のハイブリッドも増加中だ。朝シャン、誕生プレゼント、防塵シャッター、ゼロ戦、レポート用紙、パンチラ、義理チョコ、コーヒー牛乳、期末テスト、セーラー服、短パン、ゴム紐、あげればきりがない。
政府が公式に使っていて、それ以外に言いようのないものも多い。例えば地球サミット、省エネ、新エネルギー、対テロ戦争、統合イノベーション……どれもMicrosoft IMEの初期状態で変換する。
湯桶読みは〜なんて古臭いことをいうなら、外来語の変化形とか和洋折衷語も、湯桶読みや重箱読みに合わせて、英蘭読みとか和英読みと呼ばないとまずいんじゃないか?
そしてそういう言葉を否定したり排除すれば会話ができません。
とまあ、そんなテーマがいくつかあり、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、歯向かうものは切り捨て、徹底的にやっつけちゃう。私惚れそう 💗
知識膨大な学者だから、なまじの物知りやハンパな先生では歯が立たない(笑)
私なるほどと思うだけである。この先生の書いたものに反論しようとか瑕疵を見つけようなんて大それたことを考えてはだめだ。
この本は学問そのものというより、そこにある面白おかしいいろいろなテーマについて語っている。
例えば、文学は「学」が付く。しかし医学、法学、数学は学問だが、文学は学問じゃない、芸術だ。ならば音楽に合わせて文楽にすべきだ!
あっ、落語家じゃありません。
日本で作られた漢語が中国に里帰りして全く異なる意味でつかわれている。
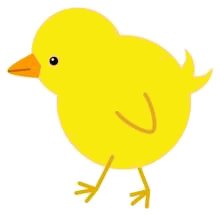 空巣という熟語は日本で作られた。日本では誰もいない家に入る泥棒だが、中国では子供のいない家庭の意味になった。子供(卵)がない家庭だから空巣だという。
空巣という熟語は日本で作られた。日本では誰もいない家に入る泥棒だが、中国では子供のいない家庭の意味になった。子供(卵)がない家庭だから空巣だという。
ちなみに鳥の巣は、人間にとっての家とは違います。巣とは卵を産みひなを育てるためのものです。大人の鳥は巣に住むわけじゃありません。理屈から言って中国語はもっともなことである。
「歩く」という字は元々、足を左右交互に出す意味で上下対象だった。戦争に負けて馬鹿な学者が標準化とかで下の部分に点を追加して「少」にしたんだ、とんでもね〜野郎だ〜と先生はのた うち まわっておられます。
そんな中で私が一番面白いと思ったもの、それは「やさしいことばはむずかしい」という章である。
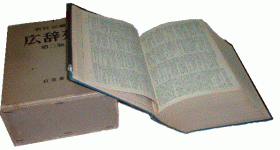 話の流れは、国語辞典を作るのには大変な手間がかかるとか、時代とともに収録される語句は変わっていくとか、他人の編纂の瑕疵をあげつらったり、先生は楽しそうに語る。
話の流れは、国語辞典を作るのには大変な手間がかかるとか、時代とともに収録される語句は変わっていくとか、他人の編纂の瑕疵をあげつらったり、先生は楽しそうに語る。
そして「辞書を作るときやさしいことばはむずかしい」と書いた人を取り上げて、まことにそうだと同意する。
そこでは「やさしいことば」として「(ものが)ある」「雨」「3」「ちいさい」をあげ、辞書にどんな説明が載っているかを調べて、省みて自分自身わかりやすく説明できるかと考える。
ものごとを短い文章(辞書に書く程度)で簡単に説明しろと言われたとしよう。
例えば「タンス」とは何かと問われれば、私なら「木製で引き出しがいくつも付いていて、衣類を保管する家具である」というように説明できるかと思う。
ちなみに国語辞典をひくと「衣類や小道具などを収納する家具、大小の引き出しや開き戸がついた木製の箱」とあった。今私が考えた説明と似たようなものだ。

|
|
るんじゃねえ〜 |
社会経験の短かい子供や若者には難しいこともあるかもしれないが、半世紀も世を過ごしてきた年寄りになればなんとか説明はできる。
だが「やさしいことば」はどうだ?
この本で例にとりあげた「(ものが)ある」を子供に分かるように説明しろと言われると困ってしまうのではないだろうか? 子供だってわかっているから説明する必要がないなんて言ってはいけない。
国語辞典で「ある」を引くと、「事物が存在する」とある。でもそれじゃトートロジー、堂々巡りだ。
説明というからには「ある」という言葉よりもむずかしい言葉である「存在」なんて漢字熟語などは使ってはいけない。
考えるとこれは面白い、そして暇つぶしになる。いや正解にたどりつけないことが多いかもしれない。
しばし沈思黙考、浮かんできたアイデアを紙に書き記す、そしたら辞書をいくつか見てみる。自分のアイデアがまっとうだったか、辞書のほうが良いか己のアイデアが良いか?
この本で例にあったものを考えてみよう。
| 「ある」 | 国語辞典 | (通常生物以外が)存在する 「ある」より存在の方が難しそう |
|
| 英英辞典 | 英語ならthere isかと思って引くと、used to say that something exists or happens、「何かが存在するか出来事が起きるか」 existでひくと to happen or be present in a particular situation or place、つまり前の逆で「特定の状況か場所で何か起きるか存在する」英語でも表現困難らしい。 |
||
| 「ないことの反対」 「ないとは何か」と問い返されそう | |||
| 「雨」 | 国語辞典 | 空中で冷えた水蒸気がしずくとなって降ってくるもの 小学前の子供が水蒸気なんて知らないよ |
|
| 英英辞典 | 空の雲から落ちてくる小さな水滴 晴天でも雨が降るときがあるぞ |
||
| 私のアイデア | 空から落ちてくる水滴 | ||
| 「3」 | 国語辞典 | 2の次の数、1足す2 それじゃ1とか2を説明しないとならないぞ |
|
| 英英辞典 | 数字の3 苦し紛れとしか思えない。 |
||
| 私のアイデア | 親指と人差し指と中指に対応する数 | ||
| 国語辞典 | 大きいの反対 ひとつしかなくても小さいということあるよね? ほかのものより少ない 少ないってなんですか? |
||
| 英英辞典 | 大きくなく中間でもない大きさ 説明になってない |
||
| 私のアイデア | お手上げ |
平易な言葉でわかりやすく説明しようとすると、非常に難しい。
私たちが日々使っているやさしい言葉でも、語彙を説明しろと言われるとお手上げというのは多いんじゃないだろうか?
難しい熟語を使わず、悪魔の辞典のようにおふざけでなく、真面目に小さな子供に説明しようとするととんでもなく困難だ。
それでは、みなさんがチャレンジする番だ。
下の問は私が考えたものです。右側はヒントというか参考意見かな?
参考までに手元の国語辞典を引いても、苦し紛れとかトートロジーのようなものばかりでした。
| 「諦める」 | 願うことをやめる | ||
| 「あこがれ」 | じぶんがなりたいことや人 | ||
| 「痛い」 | 相手をつねるのはナシ | ||
| 「お金」 | 経済学じゃなくて小学前の子供に説明 | ||
| 「くしゃみ」 | してみせるのはなし | ||
| 「時間」 |
英英辞典をひくと「時計を使って分や時間などで測れるもの」だって、アホじゃねえ! |
||
| 「しくみ」 | なかみ | ||
| 「好き」 | 自分の望みにあうこと | ||
| 「切ない」 | 都はるみを聞いた時の感情 | ||
| 「タレント」 | 実は私も知らない | ||
| 歩くと走るの境目は? | |||
| 「右と左」 | これは分子構造か何かを引用しないと説明できないはず 心臓のある方は万人共通じゃありません。方角を使うには磁石がないとだめ |
||
| 「 | 藤やスミレの花にはいろいろあるので例にできない。 |
良いアイデア思いつきましたらご連絡ください。ここにアップします。
賞品はありません(キリッ)
![]() 本日思いついたこと
本日思いついたこと
老後の趣味として自分が考えた「やさしいことば」をまとめて自費出版したらどうだろう? 題して「悪魔の辞典」ならぬ「やさしい辞典」。
家族友人に配れば、自分史や研究成果をまとめたものより喜ばれるに違いなし。
私は定年後入った大学院を修了したとき、修士論文を製本して家内と子供たちに贈った。即座にゴミ箱に捨てられました。
外資社員様からお便りを頂きました(2021.01.21)
>本日おもいついたこと ぜひ「やさしいISO」を書いて下さい。 このHP全体がそうなのですが、全部読むのは新人さんには大変です。 |
推薦する本の目次に戻る