*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。
カルタ取りという言葉を2005年頃、とある講演会でLRQAの星野取締役(当時)から聞いた。
 カルタ取りと聞いていかなる手法かと思ったら、会社の文書や帳票を集めてきて広い部屋に広げ、規格要求を読み上げてそれに該当するものを拾い集めることをいうのだそうだ。
カルタ取りと聞いていかなる手法かと思ったら、会社の文書や帳票を集めてきて広い部屋に広げ、規格要求を読み上げてそれに該当するものを拾い集めることをいうのだそうだ。
私はカルタ取りとは言わなかったが、取締役の言葉を聞く10年も前から同じことをしていた。私の場合広い部屋は必要なく、文書や帳票を集める必要もなかった。私は頭に入っている工場規則と帳票を思い出すだけで間にあった。
思うにISO認証をするには二つの方法がある。ひとつはISO規格を満たす仕組みを(リアルであろうとバーチャルであろうと)作る方法である。リアルで行えば会社の仕組みの再構築となり大騒ぎになるだろうし、バーチャルはどこでも見かける二重帳簿である。
もうひとつは現状の仕組みがISO規格を満たしていることを説明する方法である。カルタ取りは後者の一手法だ。
私はISO9001を認証した初期からカルタ取りをしていた。白状するとそのアプローチは私が独自に考えたものではない。1993年頃、BVQIの原田部長(当時)のISO9001の説明会を聞いた。説明会といっても大人数ではなく、おぼろげな記憶では5・6名だった。
当時はISO認証を受けようという企業を対象に、認証機関は無料で規格解説をしてくれたのだ。もちろんその認証機関に依頼するかどうか未定なわけだが、当時は実際に審査を行い認証していたのは外資系の少数の認証機関だけで、まだ日系の認証機関は立ち上がってない。そんな状況だから、彼らは間違いなく自分のところに来ると見ていて、説明会は獲物を集める撒き餌と考えていたようだ。
原田部長の説明は、会社のシステム
そして彼は会社のシステムは唯一無二のものである。
品質システムはそこからISO9001の要求事項に関わるものを抜き取ったものであると語る。文書化されている会社なら、要求事項に該当する文書や記録を見せればおしまいだと語った。
しかしシステムが文書化されている会社ばかりではない。文書化されていない会社も多く、そこはISO認証のために見せる部分については、最低限 文書化が必要だという。ここまでは当たり前のことだし、私も説明を聞く前から知っていた。
更に彼は重大というか思いがけないことを語った。
品質システムというが、それはシステムではない。システムとは分野によってさまざまな定義があるが、組織論においては、組織・機能・手順である。ISO9001の要求事項を全部集めてもシステムにならない。それは品質保証要求であり、顧客が必要なものを羅列しただけだから当然だという。要するに顧客から見た品質保証に過ぎないのだ。
だからISO9001のタイトルは「品質システム-設計・開発・製造・据付及び付帯サービスにおける品質保証モデル」とあるが、正しくは「品質保証要求事項集-○○」なのだという。要するに品質システムという名前であるが、システムではないという。
言われてみれば当たり前のことだ。だって本質は品質保証なんだから、品質保証要求事項以外を含むはずがない。
そのとき、私が勤めていたところでは、ある製品をイギリスに輸出しようとしてISO認証が必要だった。その製品の営業担当者はイギリスやアメリカ駐在が長い人だった。彼はISO規格の「品質システム(Quality System)」という言葉を見て、それはおかしいという。彼が言うには英語でシステムとはなにものかの一部ではなく、全体であり、品質なら品質保証だけとらえて品質システムと呼ぶのはおかしい。言葉の使い方が間違っているという。
確かに広義の品質管理は狭義の品質管理、品質保証、品質改善を含める。彼は門外漢であったが核心を捉えていたのだろう。
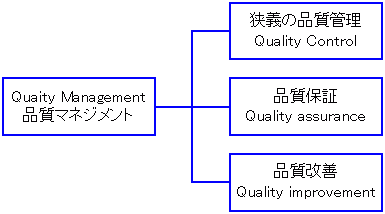
1990年頃の品質管理(広義)はこのようにJISで定義されていた。
ISO認証が一巡した1996年頃から「ISOで会社を良くしよう」なんて言い出されるようになったが、ISO9001が顧客から見た品質保証要求であるなら、そんなことはありえない。そしてそれは2000年版であろうと2008年版であろうと、2015年版であろうと変わりはないと私は考えている。だって項目が足りなすぎる。
2015年版の「10 改善」に書いてあることが本当に改善になるとは思えない。絶対やれと言っているのは是正処置だけ、継続的改善は刺身の褄ですか、
ISO9001はいくら改定を重ねようとシステムではないし、品質システムでもない。さらに言えばサブシステムでもなく、会社のマネジメントシステムから、品質にかかわるものを抜き出したもろもろを集めたに過ぎない。
更に原田部長の話は続く。
これから環境やそれ以外のシステムの規格が作られ認証が始まるだろう。認証規格がたくさんになっても、会社のシステムにある文書や記録の中からそれぞれの規格の要求事項に見合ったものを抜き取って要求事項を満たすことを説明すればよいのだと語る。
当時はまだISO審査を受けたこともない時だったから、そのとき私は彼の言葉をよく理解できなかった。
|
品質保証の国際規格 ◇ISO規格の対訳と解説◇ 増補改訂版 |
| 監修 久米 均 |
| 日本規格協会 |
私は日本規格協会の「品質保証の国際規格」という本をひたすら読んで暗記するほどだったが、彼の話はそれまで聞いたことのない貴重な情報であった。
なお、13,000円もした「品質保証の国際規格」は、今も私の部屋の本棚に鎮座している。30年間に数百回は読んだ。
それから1年くらい後にBVQIでないイギリスの認証機関から来たイギリス人による審査を受け、認証をゲットした。更に1年後くらいに別の製品でJQAの審査を受け、もちろんパスした。当時は製品ごとに認証を受けるのが普通だった。
その後勤め先だけでなく近隣の会社からも声がかかって恥ずかしながら指導をして、その方法でいくつかの認証機関のISO審査にパスした。
私にとってISO認証の準備とは、マネジメントシステム構築なんて言えるものではなく、今あるものを審査員が理解できるように見せることである。
ISO認証するのは特別な準備も不要、テクニックとか言葉巧みも不要であり、絶対に必要なものは自分の会社の仕組みを知り、文書・記録・帳票を頭に入れておくことだけだ。
私は1996年頃にはISOのプロを自称した。だがそうでないことはすぐに思い知らされた。
ISO14001が登場したとき、ISO認証のプロと思われていた私が担当になったが、その認証機関はそうではなかった。
不思議なことにマニュアルの位置づけは会社の最高位の文書でなければならないらしい。さらに不思議なことだが、ISO14001では初版から環境マニュアルを要求していなかったのだが。
品質保証をしていた人ならご存じだろう。新たな取引先ができれば、その会社と品質保証協定書を結び、品質マニュアルなどの名称の会社の品質保証体制の概要を記した文書を提出する。
それは会社の最高位の文書などではない。顧客対応の相手からの要求事項をいかにして実現したかを略記したものに過ぎない。顧客もそれが売り手の会社の最高位の文書と思うわけがない。その文書は従業員が存在さえ知らず・読むはずもなく、ウソは書いてないが、営業用の資料であることを認識していた。
それはISO9001の品質マニュアルも同じことである。
この段落を読んでスット頭に入らない、あるいはおかしいと思うなら、あなたは品質保証屋ではない。
さて、ISO14001の審査は当時、日本最大のISO14001の認証件数を誇ったところだった。審査では面白いこと(ほんとは面白くない)が続出した。
- 環境マニュアルのトップページ
最高位の文書と書いてありません。追記してください。
教育用にも使うと追記してください。
はて、審査員は環境マニュアルをなんだと思っているのでしょう? - マニュアルの内容
規格の文言が書いてないからすべて書き込みなさい。御社の方針には、継続的改善。汚染の予防・法規制その他の要求事項の順守・枠組み・周知の言葉が入っていませんね
審査員は寝言を語っているのでしょうか、意味不明です。 - 環境側面はスコアリング法ですか?
計算しても点数が上がらない? ならば工場長が特別に著しい環境側面としたことにしなさい。
ワケワカラン。そんなことするなら、初めからスコアリング法ではなく、これに決めたという一言で済む。それに指導するのはガイド66(当時)違反じゃないの! - 沢山あるけど以下省略……
ともかく私の方法は撃破された。
正しいか間違いかはともかく、審査に通用しないならダメなものはダメ。
私はカルタ取り方法をやめて、規格が最上位、それを元に怪しい文書を作り審査にパスする道しかなかった。バーチャルISOの始まりである。
矜持はないのかとおっしゃいますか? こちらのレベルを、相手に理解できるまで下げるしかありません。いや審査員のレベルまで上げ()なければならなかったのです。
何年かのちに、その認証機関の取締役にカルタ取り方法を話す機会がありました。その取締役はカルタ取り方法では大きな問題がある。それはISO認証しても会社が良くならないことだと語った。
ここで私は気が付いた。二者間の品質保証は、買い手は自分が必要だと考えたことを売り手に要求し、売り手は要求を満たすことを約束する。そこには品質保証契約だけが存在し、売り手企業を良くするなんて意味合いは全くない。
そういう世界からISO認証に関わるようになった認証機関も審査を受ける会社も、会社を良くするという発想は全くない。
その大手認証機関は、自分たちの使命は審査を受ける会社を良くすることだと考えたのだろうか?
だがISO9001規格の意図は犬でも知っている「顧客満足」であり、ISO14001は猫でも知っている「遵法と汚染の予防」であり、どちらも企業を良くする意図ではなかったはずだ。
それはともかく、その取締役の話を聞いて、ああ、この人は認証機関の経営者には向かないなと思った。
だってISO認証は会社を良くするという根拠は何もない。ISO/IAF共同コミュニケではそんなことを語っていない。語っているのは日系の認証機関のみという現実がある。
そもそも会社を良くするとはどういう意味なのか、その定義も定かではない。
認証企業の財務体質を強固にするのか、競争力を強化するのか、株価を上げるのか、従業員の働きやすさなのか、ブランドイメージを上げるのか? 要するに会社を良くするとはなんなのかをはっきりさせ、ISO認証はそれをできることを、証拠を上げるか論理的な説明がなければウソだといってもよい。
ともかく論理的には、カルタ取りがISO認証のための唯一のアプローチである。唯一というとそれ以外のマネジメントシステム構築を頑張っている人に申し訳ないから、唯一のまっとうなアプローチであると言い換える。
そのほうが一層馬鹿にしているって? 気にしてはいけない。
8月末の午後である。外はまだ夏の暑さであるが、オフィスは28℃で快適である。どこかのバカがエアコンの設定を28℃にとか言い出したが、元々の環境省通知は室温を28℃にしようであって、そのためにはエアコンの設定温度は調整しなくてはならない。
エアコンの設定を28℃にして室温が29℃なら、設定を少し下げたらよい。最近はその旨が理解されるようになってきた。
磯原は第二四半期もあとひと月で、使用エネルギーは削減計画に入るかどうかの確認をしている。
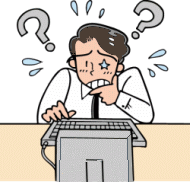 生産設備の削減はほぼパターン化がされてきており、突発的な生産計画の変化とか空調や生産設備の故障がなければほぼ計画通りである。
生産設備の削減はほぼパターン化がされてきており、突発的な生産計画の変化とか空調や生産設備の故障がなければほぼ計画通りである。
だがオフィス省エネは、いまだいろいろな工夫をカットアンドトライ中だ。残業の変化とか営業など不在時の省エネなど考えることは多い。朝夕全員いるときも庶務担当しかいない時も、照明、空調が同じなのはおかしいが、部屋を仕切るとかフリーアドレスにできるのかとなると、頭をひねる。
事務作業の生産性や品質と省エネはトレードオフできそうにない。
カシャカシャとキーボードを叩いていると磯原は肩をたたかれた。顔を上げると千葉工場の佐久間がいる。
![]() 「おっ、佐久間さん、お久しぶりです。来月からと聞いていました。今日は挨拶ですか?」
「おっ、佐久間さん、お久しぶりです。来月からと聞いていました。今日は挨拶ですか?」
![]() 「今日は入社・退社から昼飯の手配などを確認に参りました」
「今日は入社・退社から昼飯の手配などを確認に参りました」
![]() 「佐久間さんは施設管理課でなく、山内参与の直下で仕事してもらうことになります。山内さんにはご挨拶しましたか?」
「佐久間さんは施設管理課でなく、山内参与の直下で仕事してもらうことになります。山内さんにはご挨拶しましたか?」
![]() 「あの本部長室と看板の出ているところに行きましたら、本日は休暇だそうです」
「あの本部長室と看板の出ているところに行きましたら、本日は休暇だそうです」
![]() 「そいじゃ、まずは勤怠とか食事など庶務事項ですね。
「そいじゃ、まずは勤怠とか食事など庶務事項ですね。
ユミちゃん、こちらは来月から応援に来てくれる佐久間さんです。転勤者の説明一式をお願いできるかな?」
磯原は斜め向かいに座っている柳田に声をかけた
![]() 「佐久間さんのことは伺っております。よろしければ今から1時間くらい大丈夫ですか?」
「佐久間さんのことは伺っております。よろしければ今から1時間くらい大丈夫ですか?」
![]() 「それじゃユミちゃんのほうが終わったら私と打ち合わせお願いします」
「それじゃユミちゃんのほうが終わったら私と打ち合わせお願いします」
磯原がふたりをチラチラと見ていると、最初の30分くらいは打ち合わせ場で話していたが、それから事務所内を歩き回り、そのあと部屋から出ていった。きっと社内を案内して最後に受付ロビーでお茶でもしてくるのだろう。まあ、彼女が仕事で席から離れるなんてまずないから、機会あれば息抜きしたいのだろう。
1時間を少々過ぎてから二人は戻ってきた。
それじゃ、佐久間さんとこれからのことを話し合おうか。
二人は打ち合わせ場に座ってまずはコーヒーを飲む。
![]() 「まずタスクは、簡単明瞭です。年末の更新審査を滞りなくパスすること」
「まずタスクは、簡単明瞭です。年末の更新審査を滞りなくパスすること」
![]() 「まだまったく手つかずなんでしょう?」
「まだまったく手つかずなんでしょう?」
![]() 「ご明解。単に認証するだけでなく、条件があります。
「ご明解。単に認証するだけでなく、条件があります。
まず2015年版対応とすること、説明に当たっては従来までのバーチャルを止めて、会社の現実、本来の会社規則、過去より存在する記録類、それを基本とする」
![]() 「認証機関を変えるとか聞きましたが、どうなりました?」
「認証機関を変えるとか聞きましたが、どうなりました?」
![]() 「話はご存じでしょうけど、品質環境センターといろいろありましたが、向こうは鞍替えをしないでほしいという泣きを入れてきたので了解しました。
「話はご存じでしょうけど、品質環境センターといろいろありましたが、向こうは鞍替えをしないでほしいという泣きを入れてきたので了解しました。
見方を変えれば、我々の提示するものがまっとうなら、品質環境センターらしいおかしな解釈を持ち出すことはないように思います」
![]() 「その辺は何とも言えませんね。力関係が変わっても、信念は変わらないかもしれません」
「その辺は何とも言えませんね。力関係が変わっても、信念は変わらないかもしれません」
![]() 「考えていることはいろいろあるのですが、各部門に新たな作業をまったくさせないつもりです。もちろん各部門に新しい考え方の説明会、そして相手の質問には従来からのどんな文書とか記録を充てるということは理解してもらいます。
「考えていることはいろいろあるのですが、各部門に新たな作業をまったくさせないつもりです。もちろん各部門に新しい考え方の説明会、そして相手の質問には従来からのどんな文書とか記録を充てるということは理解してもらいます。
それが徹底できれば持てる時間を我々が理論構築に使えると思う」
![]() 「事前に品質環境センターに説明に行くんでしょう?」
「事前に品質環境センターに説明に行くんでしょう?」
![]() 「そのつもりです。実を言ってジキルQAには、今言った方式で良いか相談に行ったのです」
「そのつもりです。実を言ってジキルQAには、今言った方式で良いか相談に行ったのです」
![]() 「ジキルはどう答えたのでしょう?
「ジキルはどう答えたのでしょう?
うちはQMSもEMSもジキルです。その経験から言って、磯原さんの話を聞いただけだけど問題ないと思いますね」
![]() 「うん、問題ないといわれた。その代わり鞍替えしろともいわれたけどね」
「うん、問題ないといわれた。その代わり鞍替えしろともいわれたけどね」
![]() 「認証機関を変えるのはダメということですね」
「認証機関を変えるのはダメということですね」
![]() 「認証機関は変えないことは決定事項です」
「認証機関は変えないことは決定事項です」
![]() 「了解しました。では明日から磯原さんと各項番ごとに検討しましょう。そうですね、3日か4日あれば大丈夫でしょう。文書はイントラネットにあるのでしょう。記録は各部門に行けば見られますかね?」
「了解しました。では明日から磯原さんと各項番ごとに検討しましょう。そうですね、3日か4日あれば大丈夫でしょう。文書はイントラネットにあるのでしょう。記録は各部門に行けば見られますかね?」
![]() 「それは大丈夫です。QMSは文書や記録といっても少ないですから」
「それは大丈夫です。QMSは文書や記録といっても少ないですから」
![]() 「少ないですか?」
「少ないですか?」
![]() 「製造以外は法規制があるものは少ないですから、自分たちが決めたものだけですね。購買ならグリーン調達とか営業なら環境性能の情報提供と市場情報の収集、それに返品の扱いくらいじゃないですか?」
「製造以外は法規制があるものは少ないですから、自分たちが決めたものだけですね。購買ならグリーン調達とか営業なら環境性能の情報提供と市場情報の収集、それに返品の扱いくらいじゃないですか?」
![]() 「品質環境センターなら、お決まりの移動の交通機関とか紙ごみ電気もあるでしょう(笑)」
「品質環境センターなら、お決まりの移動の交通機関とか紙ごみ電気もあるでしょう(笑)」
![]() 「交通機関はビジネスはスピードを優先とするということで環境の観点は無視、というか出張に飛行機、新幹線を使うのは選択肢がありません。
「交通機関はビジネスはスピードを優先とするということで環境の観点は無視、というか出張に飛行機、新幹線を使うのは選択肢がありません。
紙ごみ電気は担当を総務一括にして、作業標準はビル管理会社の通知とします」
![]() 「了解です。ジキルといえば、例のカルタ取りの方法というわけですね」
「了解です。ジキルといえば、例のカルタ取りの方法というわけですね」
![]() 「ああ、ジキルの橋野取締役の講釈を聞いたことありました?」
「ああ、ジキルの橋野取締役の講釈を聞いたことありました?」
![]() 「橋野取締役? ああ、あの方ね。数年前に一度、うちの工場に審査に来たことがあります」
「橋野取締役? ああ、あの方ね。数年前に一度、うちの工場に審査に来たことがあります」
![]() 「どんな審査をしましたか?」
「どんな審査をしましたか?」
![]() 「品質環境センターとは全く違うね。どこの職場でもマニュアルなんて見ないで、職場の仕事は何か?、何を見て仕事をしているのか?、その作業で重要なことは何か?、そんな聞き方でした。
「品質環境センターとは全く違うね。どこの職場でもマニュアルなんて見ないで、職場の仕事は何か?、何を見て仕事をしているのか?、その作業で重要なことは何か?、そんな聞き方でした。
非常に一貫性がないような思い付きのような質問で、単なる行き当たりばったりかと思いました。でも結論を聞くと質問は事前に詳細な設計をしているように思いました。規格要求は漏らしてませんでしたし、何か異常があればどんどんとたどっていくという感じで……品質環境センターに比べるとレベルというか質が違いますね」
![]() 「感心するべきなんでしょうけど、一人一日15万も取るなら当たり前でしょうね。
「感心するべきなんでしょうけど、一人一日15万も取るなら当たり前でしょうね。
弁護士の相談料は30分5千円とかでしょう。法律相談が7時間半フルにあったとして、1日の稼ぎが75,000円。ISO審査で1人1日15万ならぼろ儲けですよ。もちろんオーバーヘッドがあるけど、それは弁護士も審査員も同じです」
![]() 「確かに要求される資格や力量とサービス料金は弁護士と審査員は逆転してますね。
「確かに要求される資格や力量とサービス料金は弁護士と審査員は逆転してますね。
おっと、そのカルタ取りでいくわけですね」
![]() 「カルタ取りは内部確認のためにしておく必要はありますね。ただ審査においてはこちらは何も提示せず、向こうがイニシアチブをとって調べてもらおうと考えてます。
「カルタ取りは内部確認のためにしておく必要はありますね。ただ審査においてはこちらは何も提示せず、向こうがイニシアチブをとって調べてもらおうと考えてます。
我々は具体的に質問されたら求められたものを示す。相手のあいまいな質問を解釈して回答するとか、相手の気持ちをおもんばかって期待しているだろうものを見せるってのはありえないでしょう
いずれにしても当社は社歴数十年です。過去何十年と仕事を継続してきた会社ですよ。だから現実が必要十分であり規格要求事項を満たしていると考えて当然です」
![]() 「うーん、確かにそういう思いは分かりますが……ただ、やってくる審査員が橋野取締役のようなアプローチができるかどうかが問題ですね」
「うーん、確かにそういう思いは分かりますが……ただ、やってくる審査員が橋野取締役のようなアプローチができるかどうかが問題ですね」
![]() 「それができることが認証機関の存在意義ですよ。できない審査員ならお帰り願うしかありません」
「それができることが認証機関の存在意義ですよ。できない審査員ならお帰り願うしかありません」
![]() 本日の予想される苦情
本日の予想される苦情
無駄に前半が長すぎる!……そう言われるのをお待ちしておりました。
私は下手なドラマを描いておりますが、言いたいことは現在のISO審査をいかに改善すべきかであります。
多くの会社でマネジメントシステム構築なんて語っています。それって本当?
昨日・今日できた会社でなければ、歴史があるでしょう。その期間、会社が正常に機能していたなら、そのマネジメントシステムは必要十分ということです。
「いやあ〜、不完全な仕組みです」なんて謙遜することはありません。堂々と当社のマネジメントシステムは立派であると言えば良いのです。
もちろんISO認証ではマネジメントシステムが文書化されていることを要求します。ですから最小限文書化は必要です。そのわずかな作業をマネジメントシステム構築なんて言わないでしょう。
規格要求事項を、現状のマネジメントシステムから拾い上げることをカルタ取りと言ったISOの重鎮もいました。それはマネジメントシステム構築なんてこととは違い、まことに正攻法であります。
では、現状が規格要求を満たすことを説明できるのでしょうか?
そして相手が納得するものでしょうか?
でもね、審査を受ける会社は、当社のマネジメントシステムは規格要求を満たしていると説得する義務はありません。審査を受ける会社は規格適合の仕組みを作らねばなりませんが、適合かどうかを調べるのは審査員なのです。わざわざ適合していることを立証し説明する義理はありません
それが現実かといわれるといささか自信がありません。というのはそれができない審査員は多いと思いますね。2022年の現在でも、観察から始めるのではなく、規格要求から始める審査員が多いのだから。
そういう審査員の力量がISO17021-1を満たしているのかどうかは何とも言えませんが。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
ISO9001:1987ではマネジメントシステムという言葉は出てない。 | |
注2 |
ISO17021-1:2015 4.4.1 認証の要求事項に適合することへの責任をもつのは、認証機関ではなく、被認証組織である。 4.4.2 認証機関は、認証の決定の根拠となる、十分な客観的証拠を評価する責任をもつ。 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |