*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。
ISO 3Gとは
昨日のこと、磯原は山内参与から、今日の午前中時間を取ってくれと言われた。どんな話でしょうと尋ねると、この前の続きだという。また七面倒くさいことを言われるのかと、磯原はいささか気が滅入る。
とはいえ磯原は以前話をしたときから、なにもしていないわけではない。各工場から毎年度初めに
 |
|
| 磯原です |
驚くことにというか、自分もしていたから驚くこともないのだが、8割方の工場で本社に提出した計画と、ISOの環境実施計画の数字が異なっているのだ。数字だけでなく項目も違う。
本社向けは当社の環境行動計画に合わせており、内容はテーマごとに予算と改善案が見合っている地に足のついた現実的なものだ。そして工場の2割くらいは法の定める削減率に達していないところもある。
とはいえそれが法規制に反しているわけではない。全社を合計すれば法基準を上回っている。なぜならスラッシュ電機は企業全体として省エネ法に対応している。だから省エネ投資は各工場一律ではなく、必要なところに投じているわけで、その選択は全社的に見て老朽化とか性能的にアップしなければならないと判断したところに投資するわけだ。その結果、個々の工場を見れば、改善は一直線に向上していくわけではなく、投資した年は大きく改善が進み、そして次に投資するまでの何年かは細かい改善工夫のわずかな省エネしかない。
改善とはアイデアだけでできるものではない。ネットで省エネのネタ集などを見かける。どんなことを言っているだろう?
- 照明の数を減らす
- 照明時間の見直し
- 不要な設備・機器の停止
- 有休機器を活線からの切り離し
- 空調温度の見直し
- インバータの採用
- OA機器の省エネモード、低電力OA機器への切り替え
- 夜間運転で済むものは日中停止(排水処理など)
- 照明機器や空調機器の定期的清掃やメンテナンス
まあいろいろあるが、なにをするにもお金がかかる。照明を減らせなんて言っても、簡単ではない。費用だけでなく安衛法も関わる。安衛法を満たしていても、安全・品質などの検証が必要だ。
蛍光灯をLEDに更新するなんてのは誰でも思いつくが、私の住むマンションで交換費用を電気代削減で何年で回収できるか試算した。工事代金、機器代金を考えるとペイするわけがない。現状の蛍光灯機器の寿命が尽きてから切り替えようという結果になった。
世の中に手間暇かからず、大幅改善ができるなんてものがあるはずがない。我々の先輩も我々も、一生懸命考えてきたわけで、ロスの見逃しなどしているわけがない。
思い出したのだが、2000年頃の話。会社ではCRTモニターを使っていた。ISO審査で審査員がなぜ液晶モニターにしないのか、省エネになるのにと問い詰めてきた。

当時15インチの液晶モニターは10万円以上した。15インチ液晶付きパソコンの価格でなくモニター単体でだ。2022年の今は15インチの安物なら1万円だ、2万円出せば立派なものが買える。
ところでCRTを液晶にすると何W節約できるのだろう。費用回収は可能なのか? なこと考えるまでもなくムリ!
その審査員が別世界に住んでいるとしか思えなかった。蛍光灯を使っていればLED電球が良い、CRTモニターより液晶モニターが良いと語るだけで良いとは楽なお仕事だ。
実を言って私が訪問したある有名企業の廊下は、安衛法の基準以下だった
注:今はスマホに照度計アプリがあるから誰でも測定できる。
他方、ISO用に作った環境実施計画はおしなべて<毎年>法規制や業界基準をわずかに上回る数字で継続的に改善が進んでいる。なぜなら設備更新した年は省エネが大きく進むが、投資しない年は細かな工夫による改善しかないのでは、ISO審査時に審査員から嫌味を言われ、不適合とまではならないだろうが要改善といわれる。それで設備投資をした年の改善効果を次に設備投資をするまでの期間で
決して嘘八百を書いているわけではない。例えて言えばエクセルの折れ線グラフをスムージングしたようなものだ
だがなぜそんなことをするのか? 何も問題でないのを、審査員の無知を想定して文句を言われないようにしているという涙ぐましい無駄・無益な努力である。
磯原は古巣の工場に、なぜ本社報告とISOの環境実施計画が違うのかと、冷やかし半分で電話をした。後任は過去からのつながりがあるので、本社報告とISOの環境実施計画を合わせることはできないという。やれば前年度と段差ができてしまうという。
磯原は冗談半分に、そいじゃ今後エネルギー管理監査をするから、そのときはバッチリ問題にするぞと言うと、後任は
指定された打ち合わせ場所は小会議室、つまり5・6人用の狭い会議室だ。オープンな打ち合わせ場でないということは、人に聞かれたくない話なんだろうか?
指定された時刻ピタリに磯原は小会議室に入った。山内参与と、なぜか鈴木課長もいる。
![]() 「磯原君は時間厳守だね」
「磯原君は時間厳守だね」
![]() 「みなさんをお待たせしてしまったようですみません。これからは海軍式に5分前がよろしいでしょうか?」
「みなさんをお待たせしてしまったようですみません。これからは海軍式に5分前がよろしいでしょうか?」
![]() 「いやいや時間通りで良いよ。世の中なかなか当たり前のことを当たり前にしないことが多いからね。私は今年度の目標は、当たり前のことを当たり前にとしようと思っている」
「いやいや時間通りで良いよ。世の中なかなか当たり前のことを当たり前にしないことが多いからね。私は今年度の目標は、当たり前のことを当たり前にとしようと思っている」
![]() 「当たり前のことを当たり前になんて運動をしている会社がありましたね。AA活動っていいましたっけ?」
「当たり前のことを当たり前になんて運動をしている会社がありましたね。AA活動っていいましたっけ?」
![]() 「いいね、真理は会社が変わっても真理だ。我々生産技術本部からAA活動を広めよう」
「いいね、真理は会社が変わっても真理だ。我々生産技術本部からAA活動を広めよう」
![]() 「山内さん、すみません、全然お話が見えないんですが」
「山内さん、すみません、全然お話が見えないんですが」
![]() 「これから説明する。この前、磯原君との顔合わせで話したのだが、当社の工場が本社に出す年度計画と、ISO14001審査で見せる環境実施計画の目的目標に差異があるから問題という話をした。そうするには理由があるのだろうが、経営という観点から見れば、許しがたいことだ。
「これから説明する。この前、磯原君との顔合わせで話したのだが、当社の工場が本社に出す年度計画と、ISO14001審査で見せる環境実施計画の目的目標に差異があるから問題という話をした。そうするには理由があるのだろうが、経営という観点から見れば、許しがたいことだ。
それから品質保証部の部長とも話をしただが、ISO9001でも審査で見せる計画と本社に出している年度計画とに齟齬があるそうだ。最近それが問題になった」
![]() 「私はISOの方はよく分からないのですが、審査用に資料を作ってはまずいということですか」
「私はISOの方はよく分からないのですが、審査用に資料を作ってはまずいということですか」
注:参考までに山内参与、鈴木課長、磯原の上下関係を説明する。
山内参与は本社に来るまで工場長と同格の研究所長であり、役職定年で所長をやめ今は常務のスタッフである。鈴木課長は工場で言えば部長級、磯原は今までは工場の係長で本社に来た今は役職のない平である。
ということで 山内参与>>鈴木課長>>磯原 という感じの序列となる。>>とふたつ重なるのは、それぞれコーポレートラダーが2段くらい違うということだ。
![]() 「鈴木君もそういう認識では困るな。そもそもISO審査のためにわざわざ書類を作る、作らなければならないという発想を止めてほしい」
「鈴木君もそういう認識では困るな。そもそもISO審査のためにわざわざ書類を作る、作らなければならないという発想を止めてほしい」
![]() 「私はISO認証と無縁でしたが、工場にいたとき担当していた者から当社の規則とか議事録や報告書を見せてもOKがでないから、ISO用にはそれ用のものを作っておいて見せるのだと聞いたことがあります」
「私はISO認証と無縁でしたが、工場にいたとき担当していた者から当社の規則とか議事録や報告書を見せてもOKがでないから、ISO用にはそれ用のものを作っておいて見せるのだと聞いたことがあります」
![]() 「うーん、確かに処世術としてはそういうのもあるのかもしれんが、本来は現実をそのまま見せて、規格適合か否かを判断してもらうべきだろう? 悪いなら悪いところを直すべきで、実態と異なるものを見せてOKをもらっても意味がない。
「うーん、確かに処世術としてはそういうのもあるのかもしれんが、本来は現実をそのまま見せて、規格適合か否かを判断してもらうべきだろう? 悪いなら悪いところを直すべきで、実態と異なるものを見せてOKをもらっても意味がない。
また当社グループの品質や環境の計画があるにも関わらず、それと違うもの新たに作って外部に見せるのはどうなんだ?」
![]() 「現実問題として過去からそうならば、それを継承するのもアリではないのですか?」
「現実問題として過去からそうならば、それを継承するのもアリではないのですか?」
![]() 「課長、工場の省エネ目標とか廃棄物削減目標は工場独自で決めることはできません。本社が全社の計画を策定して……もちろん策定時には工場の過去の実績をもとにしますし工場の意見を聞きまして、最終的に工場の同意を得るわけですが……それを対外的に発表し、また社内展開するという形になります。
「課長、工場の省エネ目標とか廃棄物削減目標は工場独自で決めることはできません。本社が全社の計画を策定して……もちろん策定時には工場の過去の実績をもとにしますし工場の意見を聞きまして、最終的に工場の同意を得るわけですが……それを対外的に発表し、また社内展開するという形になります。
そもそも工場は独立した組織ではなく・自立しているわけでもありません。地方自治体が外交や防衛などを決定する権限がないと同じく、工場が省エネ計画を立てる権限がありません」
注:磯原はこの場面で鈴木課長を「課長」と呼んでいる。私は磯原ではないから彼の真意は分からないが(笑)、想像で説明する。
まず磯原が山内参与を「山内さん」と呼ぶのは、役職についてないから役職で呼びようがないと考えているのだろう。
磯原は自分よりはるかに職階の高い山内参与を山内さんと呼んでいるので、鈴木課長を「鈴木さん」と呼んでもおかしくないが、この場面では鈴木の意見を否定する発言なので、鈴木の立場を尊重して「課長」と呼んだのだろうと想像する。
山内も通常は鈴木君と呼んでいるが、重要な話のときは鈴木課長と呼ぶ。
ちなみに私が最後に勤めていた会社では、目上でも目下でも役員でも性別関係なしに、すべて「さん」付けで呼んでいた。素晴らしい職場だと思う。
![]() 「まあそれはそうだ。大儲けしている工場ならともかく、設備投資など独自で行えるものではない。すべては事業本部に伺い出て認可を得なければならない。
「まあそれはそうだ。大儲けしている工場ならともかく、設備投資など独自で行えるものではない。すべては事業本部に伺い出て認可を得なければならない。
地方交付税より使途が限定され、結果を問われるのは地方自治体より厳しい」
![]() 「そう、そう。だから工場独自で計画策定などできない。ましてはISO用の計画を対外的に発表しているものと違うものを作成したり見せたりするのは越権行為ということだ」
「そう、そう。だから工場独自で計画策定などできない。ましてはISO用の計画を対外的に発表しているものと違うものを作成したり見せたりするのは越権行為ということだ」
![]() 「そんなことがあったのですか?」
「そんなことがあったのですか?」
![]() 「ひと月ほど前のこと、某工場で地方紙から品質保証について取材を受けて、ISO審査で使った品質向上計画を見せて講釈を語ったらしい。その数字が地方紙ではあるが掲載されて品質保証部が慌てている。本社に提出している品質改善のプランや数字と違うのでね、
「ひと月ほど前のこと、某工場で地方紙から品質保証について取材を受けて、ISO審査で使った品質向上計画を見せて講釈を語ったらしい。その数字が地方紙ではあるが掲載されて品質保証部が慌てている。本社に提出している品質改善のプランや数字と違うのでね、
そんなことがあったので、実は私も大川常務から環境はどうなのかご下問を受けていたんだ」
![]() 「そうでしたか」
「そうでしたか」
![]() 「うーん、ちょっと待ってください。ISO認証を受けるには、自立した組織であることが前提ではないのかな? 本社が言う通りしか行動できない自立していない組織では認証できるのだろうか?」
「うーん、ちょっと待ってください。ISO認証を受けるには、自立した組織であることが前提ではないのかな? 本社が言う通りしか行動できない自立していない組織では認証できるのだろうか?」
![]() 「結論から言えば、それはできます。それに厳密にいえば完全に独立している組織なんてほとんどないでしょう。
「結論から言えば、それはできます。それに厳密にいえば完全に独立している組織なんてほとんどないでしょう。
ISO14001の附属書……附属書とは規格の誤解を防ぐためのもので、本文の要求事項に加除するものではないそうです……そこでは大きな組織の一部が認証する場合のことについて書いています。いろいろあるのですが、
![]() これはズバリ本社と工場の関係でしょう。本社は実施テーマとその目標値を指示します。その策定時には工場の意見も考慮しますが、発令されれば絶対です。とはいえ与えられた目標達成のための施策をブレークダウンしますが、そこには裁量権があります」
これはズバリ本社と工場の関係でしょう。本社は実施テーマとその目標値を指示します。その策定時には工場の意見も考慮しますが、発令されれば絶対です。とはいえ与えられた目標達成のための施策をブレークダウンしますが、そこには裁量権があります」
![]() 「ええと、思い出した。省エネ法では事業所ごと年率1%削減だったはず。しかし法では事業所ごとでなく、会社全体で年率1%削減しても良いと語っている。だから全社的に見て、もっとも効果が出るよう選択と集中で投資をしているはずだ。
「ええと、思い出した。省エネ法では事業所ごと年率1%削減だったはず。しかし法では事業所ごとでなく、会社全体で年率1%削減しても良いと語っている。だから全社的に見て、もっとも効果が出るよう選択と集中で投資をしているはずだ。
となると工場によっては1%削減できないところもでる。だがそれは問題ないと磯原君の前任者から聞いた。
だがそういう工場はISO審査で法の基準を満たしていないといわれると、どう説明するのだろう?」
![]() 「課長、省エネ法でも書いてありますが、別に毎年改善を進めなくても良いのです
「課長、省エネ法でも書いてありますが、別に毎年改善を進めなくても良いのです
またISO規格にも毎年継続して改善を進めるのではなく、継続的に行う
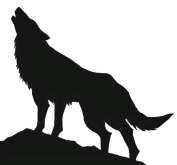 継続的あるいは定期的に何度も発生すること。オオカミが一晩中吠えているような状況。 継続的あるいは定期的に何度も発生すること。オオカミが一晩中吠えているような状況。 |
||
 時間が経過しても中断せずに継続すること。コンピュータのファンがずっと音をだしているような状況。 時間が経過しても中断せずに継続すること。コンピュータのファンがずっと音をだしているような状況。 |
![]() 「なるほどわかりやすい説明だ。要するに法律でもISO規格でも、それぞれの工場が単独で毎年省エネ基準をクリアする必要はないということだ。
「なるほどわかりやすい説明だ。要するに法律でもISO規格でも、それぞれの工場が単独で毎年省エネ基準をクリアする必要はないということだ。
磯原君 勉強しているな、なかなかよろしい」
![]() 「だがそうなると工場は独立していないだけでなく、裁量権さえないことになる。それでISO認証できるとは思えない」
「だがそうなると工場は独立していないだけでなく、裁量権さえないことになる。それでISO認証できるとは思えない」
![]() 「本社は工場に対して上位組織です。ですから本社の指示は法規制ではないですが、組織が「順守しなければならない要求事項(ISO14001:2015 3.2.9)」という位置づけになります。
「本社は工場に対して上位組織です。ですから本社の指示は法規制ではないですが、組織が「順守しなければならない要求事項(ISO14001:2015 3.2.9)」という位置づけになります。
工場に裁量権がないわけではないです。人事とか日程計画とか工場の運営は工場に決定権があります。ただ遵守しなければならないことは裁量権の外にあるというだけです」
![]() 「分かったような、だまされたような……要するに今後は省エネ計画はひとつしかないということ、それで省エネ法もISO審査も問題ないということだね?」
「分かったような、だまされたような……要するに今後は省エネ計画はひとつしかないということ、それで省エネ法もISO審査も問題ないということだね?」
![]() 「省エネ計画だけでなく、さまざまなことでだね、私はそう考えている」
「省エネ計画だけでなく、さまざまなことでだね、私はそう考えている」
![]() 「そうではあるのですが……」
「そうではあるのですが……」
![]() 「オイオイ、磯原君は実際は無理とか言いだすのかね?」
「オイオイ、磯原君は実際は無理とか言いだすのかね?」
![]() 「いや、そうではありません。このようなユニークなことを審査員が理解できないかもしれませんから、審査の場でトラブルが起きないように予防処置を取るべきと思います」
「いや、そうではありません。このようなユニークなことを審査員が理解できないかもしれませんから、審査の場でトラブルが起きないように予防処置を取るべきと思います」
![]() 「どんな?」
「どんな?」
![]() 「ひとつは社内各事業所に通知を出すことです。環境行動計画を各工場で展開したものをISO規格でいう環境実施計画とすること。二重帳簿を許さないと言えばよいと思います。
「ひとつは社内各事業所に通知を出すことです。環境行動計画を各工場で展開したものをISO規格でいう環境実施計画とすること。二重帳簿を許さないと言えばよいと思います。
もうひとつは各認証機関に対して、当社では会社の定めた環境行動計画を全社に展開していること。各工場は割り当てられたものをISOの目的目標として扱うこと、ISO規格でいう環境実施計画というものをわざわざ作らず、各工場が策定した工場の環境行動計画をISOの環境実施計画とみなすこと。
各認証機関には、それを前提として審査を行うことを要請する。
ということを公文で出すことが必要かと思います。
1%とか継続的など細かいことはどうでもいいと思いますが」
![]() 「おお、なるほどそれはいい、ワクワクするぞ」
「おお、なるほどそれはいい、ワクワクするぞ」
![]() 「そうしておけば工場も文句を言わないでしょうね。本社の言うことを聞いてISO対応の書類を作らずにいて、不適合を出されたら本社へ苦情がくるでしょうし、今後本社の指示を聞いてくれませんから」
「そうしておけば工場も文句を言わないでしょうね。本社の言うことを聞いてISO対応の書類を作らずにいて、不適合を出されたら本社へ苦情がくるでしょうし、今後本社の指示を聞いてくれませんから」
![]() 「まあ表も裏もなく、あるがまま見てもらうことが第一義だろう。だって省エネ計画は投資と結びついている。会社は全社を俯瞰して投資効率の高いところに金を投入する。だから一つの工場を見れば、10年間に二度くらい大きく改善が進むが、その他の年はそんなに省エネが進むわけはない」
「まあ表も裏もなく、あるがまま見てもらうことが第一義だろう。だって省エネ計画は投資と結びついている。会社は全社を俯瞰して投資効率の高いところに金を投入する。だから一つの工場を見れば、10年間に二度くらい大きく改善が進むが、その他の年はそんなに省エネが進むわけはない」
![]() 「ちょっと話はそれますが、問題というか疑問ですが……当社に工場は30くらいあります。工場一つ当たりISO14001の審査費用が200万はかかりますから、毎年6,000万以上審査費用がかかり、審査に対応する費用や工数もかかります。都合1億をはるかにこえるでしょう。単純に費用から考えると、認証することによって売上が30億は増えないと、認証の効果はでませんね」
「ちょっと話はそれますが、問題というか疑問ですが……当社に工場は30くらいあります。工場一つ当たりISO14001の審査費用が200万はかかりますから、毎年6,000万以上審査費用がかかり、審査に対応する費用や工数もかかります。都合1億をはるかにこえるでしょう。単純に費用から考えると、認証することによって売上が30億は増えないと、認証の効果はでませんね」
![]() 「まあすぐに認証を返上するわけにもいかない。それはまたとしよう。もちろんそういう施策も考えておかねばならないが……
「まあすぐに認証を返上するわけにもいかない。それはまたとしよう。もちろんそういう施策も考えておかねばならないが……
とりあえず発信文だが、先ほど言ったように品質保証部も二重帳簿を問題にしている。だからこれは……生産技術本部長名で出さないとまずいかな……」
![]() 「まさか、そんなことを常務名で発信するわけには……」
「まさか、そんなことを常務名で発信するわけには……」
![]() 「そいじゃ品質保証部長と生産技術部長の連名で出すか」
「そいじゃ品質保証部長と生産技術部長の連名で出すか」
![]() 「それでも工場から見たら、まさに神の声レベルですね」
「それでも工場から見たら、まさに神の声レベルですね」
![]() 「山内さん、社内はそれで良いとして、認証機関に出すレターはどうしますかね。まず、当社の30の工場でISO14001認証しているのは4つの認証機関に分かれています。
「山内さん、社内はそれで良いとして、認証機関に出すレターはどうしますかね。まず、当社の30の工場でISO14001認証しているのは4つの認証機関に分かれています。
それから審査契約はすべて工場が認証機関と結んでいるわけで、本社は関わっていません。ですから本社がレターを出すのは筋違いに思えます」
![]() 「なるほど契約の主体ということであれば工場それぞれが、さっき磯原君が語った文章のレターを認証機関に出すべきかもしれないが……4社といっても均等ではないだろうから、多い認証機関には10枚以上の同文のレターが行くわけだ。それもみっともない話だな。
「なるほど契約の主体ということであれば工場それぞれが、さっき磯原君が語った文章のレターを認証機関に出すべきかもしれないが……4社といっても均等ではないだろうから、多い認証機関には10枚以上の同文のレターが行くわけだ。それもみっともない話だな。
それなら本社として環境行動計画が工場に展開されているかを確認してほしいという要請をしようか。筋は違うかもしれないが、本社指示が徹底しているかを確認してほしいということは、利害関係者である本社が認証機関の審査の信頼性を確認する行為と考えておかしくないだろう」
![]() 「具体的にはレターを出してから説明に伺うか、あるいはこちらが要請があると認証機関を訪問するかですね。いずれも地下鉄で20分、説明に1時間として、4社に行っても大して手間ではありません」
「具体的にはレターを出してから説明に伺うか、あるいはこちらが要請があると認証機関を訪問するかですね。いずれも地下鉄で20分、説明に1時間として、4社に行っても大して手間ではありません」
![]() 「よし、それで行こう。それじゃ磯原君、両部長の連名で社内・社外に出すレターのドラフトを書いてくれ」
「よし、それで行こう。それじゃ磯原君、両部長の連名で社内・社外に出すレターのドラフトを書いてくれ」
![]() 「承知しました。品証と連名であるなら、品証と打ち合わせてたたき台を作りましょう。今週一杯で良いですか?」
「承知しました。品証と連名であるなら、品証と打ち合わせてたたき台を作りましょう。今週一杯で良いですか?」
![]() 「あまりもめないような表現にしてくれよ、社内・社外ともにね」
「あまりもめないような表現にしてくれよ、社内・社外ともにね」
![]() 本日 言いたいこと
本日 言いたいこと
私が自らISO認証を担当したり、あるいは指導したりしていた頃は、認証機関や審査員は雲の人でした。そして彼らの語る、不適合ではないけれどこうしなさいという命令 or アドバイスを、いかに彼らの気を悪くせずに断るかが最大の課題でした。
 |
|
| 節穴審査員のおめめ |
つまり飯塚センセイの語る節穴審査員は実在したのです。いや節穴の意味が違うかもしれません。
一番気になるのは全社の活動と、ISO審査で見せている工場の環境実施計画が異なることでした。建前上、工場が独立しているにしても、計画の項目と数字が合っていれば許容範囲だろうとは思います。しかしテーマも数字も違うのは二重帳簿そのものです。
それは認証機関から言えば企業が嘘をついたのだと言えるでしょうか?
言えないと思います。なぜならISO審査は出された資料を見て、OK/NGを決めるものではないはずです。そもそもISO14001は制定当時から環境マニュアルを要求していません。しかし現実はISO14001認証開始のときから、多くの認証機関が環境マニュアル提出を要求しました。
なぜ?
審査が楽にできるからです。本来ならマニュアルなしで審査するべきです。現実にマニュアルなど送らなくても良いと語っている認証機関がいくつも存在していました。
まずISO14001の肝である環境側面についていえば、決める方法を議論するのではなく、受査組織が環境側面と決めたものが、審査員が工場を見て環境側面だと判断したものと齟齬がないかどうかを見るべきでしょう。その結果、組織が決めた環境側面を決める方法の妥当性が検証されるわけです。
計算式、重み付け、そんなことに拘っているようでは、
目的目標を認証組織がフリーハンドで決定できることはまずないだろう。
日本の多くの企業は単独で存在していない。企業グループに属する会社は、多くの場合グループの環境計画を共有しており、その実現のために親会社や親工場の支援と監督を受けている。
また省エネ法にあるエネルギー単位削減も工場単位ではなく、会社全体あるいはグループ全体で省エネを推進している。削減が困難な工場分を余力のある工場が負担してがんばるというのはよくあること。
1996年版/2004年版のアネックスA.2の末尾の文章に「組織の環境方針は、その組織が属するより広い企業体の環境方針の枠内で、かつ、その承認を得て、トップマネジメントによって定められ、文書化されるとよい」とあった。2015年版ではなくなってしまったのが残念だ。
方針だけでなくそれを展開した目的目標を、企業グループが共有していることはもはや普遍的だ。
マニュアルなんて見なくても、ISO審査で審査員は受査側の出した資料がそういう上位組織あるいは所属する組織との関係を示していないなら、それはどうなっているのかと突っ込むところだろう。
もし大企業の一工場が、天上天下唯我独尊という環境実施計画を出してくるなら、それは本社の認許を得ているのかと問うのは当然だ。
そんな審査員は見たことがないけど、
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
安衛法(労働安全衛生法)の照度基準は孫にあたる労働安全衛生規則の第604条で決めている。 厚生労働省ウェブサイト「職場における労働衛生基準が変わりました」(2021.12.01) | ||||||||||||
|
2021年改正後の事務所の照明基準
この文章を書いていて自分の部屋の明るさが気になり測定してみた。パソコン前のキーボードがたったの160ルックスでした。トイレ並みだね。部屋の照明を明るくすることを考えます。 | |||||||||||||
注2 |
エクセルの折れ線グラフがオレオレで見た目が悪いというときには、「データ系列の書式設定」⇒「スムージング」にチェックマークを入れるとなだらかなグラフに変わる。オレオレではなくなるが、正直言ってメリハリのない気持ち悪いものになる。 | ||||||||||||
注3 | |||||||||||||
注4 |
ISO14001:2015 6.1.1「継続的改善を達成する」(原文:achieve continual improvement) | ||||||||||||
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |