*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
 2017年12月である。日中で点灯していないイルミネーションの並ぶ通りを、木枯らしで舞うイチョウの葉を見下ろしていた山内は、会議室のテーブルに戻り口を開いた。
2017年12月である。日中で点灯していないイルミネーションの並ぶ通りを、木枯らしで舞うイチョウの葉を見下ろしていた山内は、会議室のテーブルに戻り口を開いた。
![]() 「2017年もいろいろあったな。1年前、この部屋で環境管理体制をどうしようかと考えたのが昨日のようだ。だがこの1年の成果は大きいと自負している。もちろん君たちが成し遂げたのだ。
「2017年もいろいろあったな。1年前、この部屋で環境管理体制をどうしようかと考えたのが昨日のようだ。だがこの1年の成果は大きいと自負している。もちろん君たちが成し遂げたのだ。
中でも一番実効が出たのは環境監査かな。それに付帯することだが、環境不具合の事例集を編集して関係部門へ配布したこと、それを使った管理者教育、担当者教育もした。
ああいったことはその辺に転がっている環境教育とかISO教育なんぞより、はるかに価値がある。
あれを見た広報部は、一般書籍として売り出そうと動いている。印税を期待してろよ。ISO規格の神学論争より、泥臭い遵法と事故防止が重要なのはサルでも分かる。
だがまだ道半ばで課題も多い。これからISO14001認証をどうするのか、現状の環境監査の仕組みをどうするのか、環境担当者育成の仕組み構築、大きなことは本社の環境管理体制をどうするか、来年早々には2018年の計画を立て予算も取らねばならない。
とりあえず今日は思うことをいろいろ語ってほしい」
![]() 「それじゃ私から。私事ですが、私は来年3月末で定年です。工場にいたときには、環境管理の仕事のままで嘱託にするという話がありました。44年特例を期待していたのです
「それじゃ私から。私事ですが、私は来年3月末で定年です。工場にいたときには、環境管理の仕事のままで嘱託にするという話がありました。44年特例を期待していたのです
今は本社に転勤になってしまったので、ここで嘱託をするつもりはありません。正直なところ通勤がきついので、できるなら工場に戻してもらい嘱託で働けないかなと考えています。もし工場で雇用してもらえないなら、定年になれば退職するつもりです」
![]() 「えー、そりゃ困るよ。これからも働いてもらえると思っていた。佐久間さんが欠けては計画は全面見直しだ。
「えー、そりゃ困るよ。これからも働いてもらえると思っていた。佐久間さんが欠けては計画は全面見直しだ。
それにわしだって、その1年後は引退だ。老骨に鞭打って頑張ってほしいところだ」
![]() 「佐久間さん、本音ですか」
「佐久間さん、本音ですか」
![]() 「高校を出て42年、退職前に本社勤務できたのは、まさに最後の花道です、アハハ」
「高校を出て42年、退職前に本社勤務できたのは、まさに最後の花道です、アハハ」
![]() 「分かった、それは別途考えよう。とりあえず今は佐久間さんも計画については身を入れて考えてほしい」
「分かった、それは別途考えよう。とりあえず今は佐久間さんも計画については身を入れて考えてほしい」
佐久間は立ち上げり、ホワイトボードに図を描く。
![]() 「昔は魚の骨なんて書いてみたものですが、主要なものは先ほど山内さんが挙げたものでしょう」
「昔は魚の骨なんて書いてみたものですが、主要なものは先ほど山内さんが挙げたものでしょう」
|
本社の環境管理体制 ・職制 ・役割分担 |
環境担当者教育 ・一般教育 ・資格取得 |
ISO認証のこと ・本社・支社の今後 ・工場・関連会社の扱い | |||
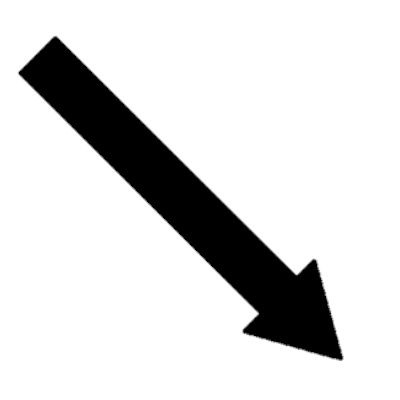 | 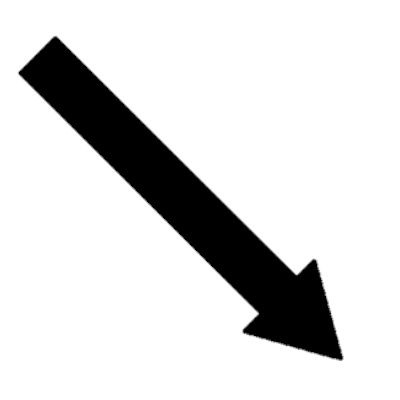 | 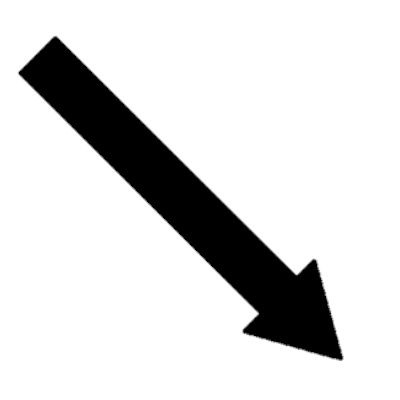 |
|||
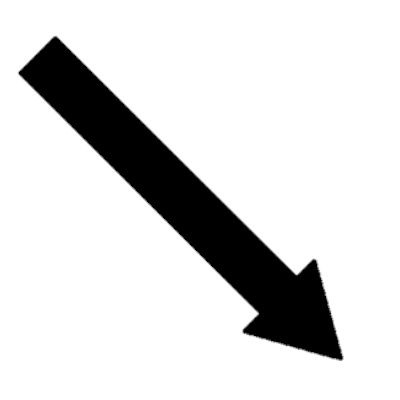
|
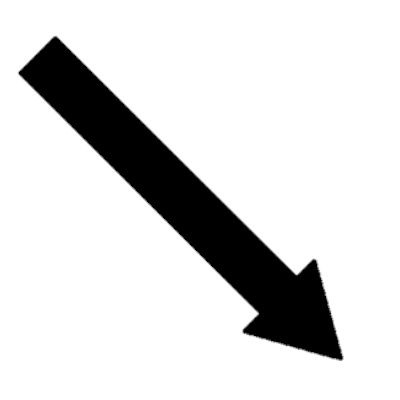 |
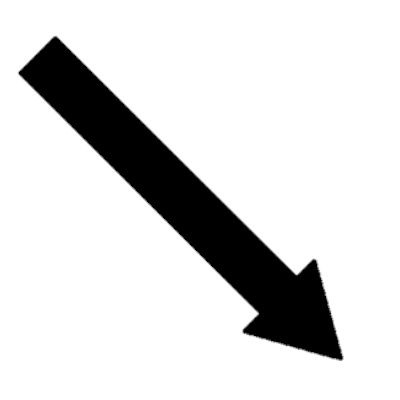 |
|||
|
環境監査 ・実効性向上 ・監査員教育 ・認定制度 |
過去の調査、対策検討 ・事故事例 ・違反事例 ・ISO審査トラブル | その他? | |||
![]() 「すべての要素を描けませんが、まあ、イメージは分るでしょう」
「すべての要素を描けませんが、まあ、イメージは分るでしょう」
![]() 「いや、さすがだ。ビジブルで分かりやすい」
「いや、さすがだ。ビジブルで分かりやすい」
![]() 「これに付け加えるとすると、守りというよりも攻めの項目でしょうか」
「これに付け加えるとすると、守りというよりも攻めの項目でしょうか」
![]() 「攻めとは?、具体的には?」
「攻めとは?、具体的には?」
![]() 「イメージでしかないですが、環境という範囲でなくSDGs的なイメージですかね
「イメージでしかないですが、環境という範囲でなくSDGs的なイメージですかね
SDGsのテーマで、貧困、飢餓などは企業の手に負えませんが、『作る責任・使う責任』とか『パートナーシップ』などは環境の中に取り込むというか、そういったことの改善に寄与しますというイメージの発信ですかね。
従来からの公害防止、事故防止だけでないという……」
![]()
 「確かにSDGsもこのところ露出度が高くなっている。とはいえバッチを付けただけで、環境貢献していると、どや顔しているのが多い」
「確かにSDGsもこのところ露出度が高くなっている。とはいえバッチを付けただけで、環境貢献していると、どや顔しているのが多い」
![]() 「我が社でも社長はじめ役員は、みなバッチをつけてますね。聞くところによると1個3千円くらいするそうですよ。環境保護とか言ってますが、早い話が銭儲けですね」
「我が社でも社長はじめ役員は、みなバッチをつけてますね。聞くところによると1個3千円くらいするそうですよ。環境保護とか言ってますが、早い話が銭儲けですね」
![]() 「環境は金になるか……まあ渡世の義理、我々もそういうことも考えないといかんか」
「環境は金になるか……まあ渡世の義理、我々もそういうことも考えないといかんか」
![]() 「話を戻しますが、私は植林しましたとか近隣の学校で環境教育をしましたというのは、企業のすることではないと考えてます。企業は本業で環境貢献するべきです」
「話を戻しますが、私は植林しましたとか近隣の学校で環境教育をしましたというのは、企業のすることではないと考えてます。企業は本業で環境貢献するべきです」
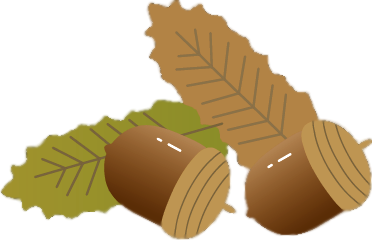
![]() 「確かに大手企業でドングリを集めて植林に結び付けようとか、日本固有のメダカを工場の中の池で増やすとか流行っているけど、私もそれはちょっと論理がおかしいと思いますね」
「確かに大手企業でドングリを集めて植林に結び付けようとか、日本固有のメダカを工場の中の池で増やすとか流行っているけど、私もそれはちょっと論理がおかしいと思いますね」
![]() 「磯原君の言う本業とは?」
「磯原君の言う本業とは?」
![]() 「言葉そのままですよ。製造業である我が社なら、環境に良い製品、資源採取時に環境破壊をしない原材料、製造時や輸送時そして使用時のエネルギーを減らす、製造時や製品に危険な物質を使わない、廃棄が安全で容易でマテリアルリサイクルが容易なこと、そういうことに邁進すべきですね。
「言葉そのままですよ。製造業である我が社なら、環境に良い製品、資源採取時に環境破壊をしない原材料、製造時や輸送時そして使用時のエネルギーを減らす、製造時や製品に危険な物質を使わない、廃棄が安全で容易でマテリアルリサイクルが容易なこと、そういうことに邁進すべきですね。
なにも環境のためにとゴビ砂漠まで行ってポプラを植えることはありません。まあゴルフトーナメントとかコンサートは、メセナとかでなく宣伝でしょうけど」
![]() 「うーん、その気持ちは分かるが、ちょっと違うのではないか。環境というのは定義というか範疇も決められていない。環境を大きくとらえると持続可能なんて我々の手の届く届かないことだし、狭義に考えれば、公害を出さない、事故を起こさないという昔からの範囲となる。
「うーん、その気持ちは分かるが、ちょっと違うのではないか。環境というのは定義というか範疇も決められていない。環境を大きくとらえると持続可能なんて我々の手の届く届かないことだし、狭義に考えれば、公害を出さない、事故を起こさないという昔からの範囲となる。
実際に2年前、当社では発展的解消という理由で環境報告書をCSR報告書として、それまで環境報告書を担当していた人たちを広報部に持っていった。また環境配慮設計も黎明期は終わったとして、事業本部の設計開発に移管した。省エネはエネルギー管理だから環境じゃないと生産技術部に移管した。
そんなわけで公害防止と廃棄物だけが残ったというわけだ。それが良いのかどうかはこれからの政策と運用で決まるだろう。
自画自賛ではないが、我々公害防止のメンバーは良くやってきたと思っている。
以前のように環境を広義にとらえて公害防止と一緒に社会貢献や広報も担当していたら、収拾がつかなかったのではないのだろうか?」
![]() 「ということは、山内さんは私のイメージよりもっと狭い分野を推進すべきということですか?」
「ということは、山内さんは私のイメージよりもっと狭い分野を推進すべきということですか?」
![]() 「いやそうではないよ。私は広義の環境活動をしなければならないと考えている。しかし我々は純粋に遵法と汚染の予防に努める部門であるべきだと考えている。
「いやそうではないよ。私は広義の環境活動をしなければならないと考えている。しかし我々は純粋に遵法と汚染の予防に努める部門であるべきだと考えている。
企業としては、植林をしてもよいし、メダカの養殖をしても良い……余裕があればだが。何しろ我々は営利企業であり、税金で動いている行政ではないからね。
だが我々の仕事は純粋に法を守り事故を起こさないためであるということだ。そして公害対策と環境広報が机を並べていても、互いに助け合うこともないだろうし管理するのも難しかろう」
![]() 「無関係な仕事をひとつにまとめずに、類似の職務をまとめて管理するということですか」
「無関係な仕事をひとつにまとめずに、類似の職務をまとめて管理するということですか」
![]() 「それが管理の基本だ」
「それが管理の基本だ」
![]() 「1990年代末、どこの工場でも環境関連の仕事をまとめて環境課なんて名前にしましたね。つまらないことですが、そのいきさつは山内さんも知っていたほうが良いでしょう。
「1990年代末、どこの工場でも環境関連の仕事をまとめて環境課なんて名前にしましたね。つまらないことですが、そのいきさつは山内さんも知っていたほうが良いでしょう。
初めてのISO14001認証審査のとき、審査員は驚くことを言いましたよ」
![]() 「驚くこととは、なんだろう?」
「驚くこととは、なんだろう?」
![]() 「当時、私がいた部署は施設管理課と言ったのです。していることは、設備や機械の保守、エネルギー供給のボイラーと電気の管理、排水処理、廃棄物処理ですか。
「当時、私がいた部署は施設管理課と言ったのです。していることは、設備や機械の保守、エネルギー供給のボイラーと電気の管理、排水処理、廃棄物処理ですか。
審査員はその名称を環境管理課に改名しろといったのです。それも推奨とかでなく、ISO認証するにはそれくらいしなければだめだというのです」
![]() 「はあ〜、どうしてですか?」
「はあ〜、どうしてですか?」
![]() 「当時の審査員は、これからは環境の時代だ、いやしくもISO14001を認証しようとする工場に、環境を冠した部門がないとは真面目さが足りないと考えたようです」
「当時の審査員は、これからは環境の時代だ、いやしくもISO14001を認証しようとする工場に、環境を冠した部門がないとは真面目さが足りないと考えたようです」
![]() 「環境を冠した部門がないと真面目じゃない……そんなことを語る頭の中を見たいものだ。それで名前を変えたのですか?」
「環境を冠した部門がないと真面目じゃない……そんなことを語る頭の中を見たいものだ。それで名前を変えたのですか?」
![]() 「いくらなんでもそれはISO審査とは無関係だろうと工場長が聞き流しました。
「いくらなんでもそれはISO審査とは無関係だろうと工場長が聞き流しました。
翌年また同じ審査員が来て名前を変えろと言いました。当時、私は係長で課長の指示で本社の環境部に電話で問い合わせました。するといくつかの工場が同じことを言われて、審査員からいちゃもんをつけられないように変えたと教えられました。
それを聞いた工場長はしょうがないと、その翌日に環境課に変えると説明して、審査員がニンマリしていましたね」
![]() 「確かにばかばかしくて驚いたよ」
「確かにばかばかしくて驚いたよ」
これは実話である。J△〇〇の中■さんがまだ存命なら、お会いして問い詰めたい。
会社の部門名を変えなさいという強迫的な言動が許されるのかどうか知りたいものだ。改名しないと認証しないと示唆したなら強要かもしれない。
善意に解釈すると、当時のISO審査員は使命感に燃え、張り切っていたのだろう。だけどそんなことは環境に良くないし、傍迷惑なことである。
注:脅迫とは脅すこと、強要とは脅して行動を促すこと、恐喝とは脅して財物を要求することである(刑法222条・223条・249条)。
![]() 「毎回そんないちゃもんをつけられてはいやになりますよ。あげくに嫌がらせの根拠不明確な不適合を出されては問題です。結局審査員に従うしかありません。
「毎回そんないちゃもんをつけられてはいやになりますよ。あげくに嫌がらせの根拠不明確な不適合を出されては問題です。結局審査員に従うしかありません。
しかし名前を変えるのも簡単ではないのです。施設管理課だけでは環境と名乗るには実態が合いません。それでそれまで総務管轄だった清掃や植栽と、保安課管轄だった危険物関係を施設管理課に持ってきて環境管理課としました。それぞれまったく別個の仕事なんですけどね。
やっと先ほどの山内さんの話につながるのですが、環境部門がいろいろな機能が持つに至ったいきさつがあったわけです」
![]() 「なるほど……となると先ほど私が語ったことは見当違いですね」
「なるほど……となると先ほど私が語ったことは見当違いですね」
![]() 「そうでもない。なにしろ環境部門の仕事は各社まちまちで、世の中も試行錯誤の状態だ。ともかく一見儲けにつながらない、定款にない自然保護活動であっても、それが株価とか就職の際の決め手になるなら、社会貢献かどうかはともかく、企業に貢献はしているわけで、やる意味はある
「そうでもない。なにしろ環境部門の仕事は各社まちまちで、世の中も試行錯誤の状態だ。ともかく一見儲けにつながらない、定款にない自然保護活動であっても、それが株価とか就職の際の決め手になるなら、社会貢献かどうかはともかく、企業に貢献はしているわけで、やる意味はある
![]() 「企業としては社会貢献やその他諸々しなければならないが、ともかくこのメンバーは、公害防止と事故防止そして廃棄物に限定していると考えればよろしいのでしょうか?」
「企業としては社会貢献やその他諸々しなければならないが、ともかくこのメンバーは、公害防止と事故防止そして廃棄物に限定していると考えればよろしいのでしょうか?」
![]() 「なし崩しだがそういう状況だな」
「なし崩しだがそういう状況だな」
![]() 「廃棄物は奥井君のはずだが、例の問題のとき馬脚を露してからは、我々を避けまくり業界団体に入りびたりだ。会社で仕事しないなら業界団体に出向というわけにいきませんかね。おっとまもなくいなくなる私が言うことじゃないか」
「廃棄物は奥井君のはずだが、例の問題のとき馬脚を露してからは、我々を避けまくり業界団体に入りびたりだ。会社で仕事しないなら業界団体に出向というわけにいきませんかね。おっとまもなくいなくなる私が言うことじゃないか」
![]() 「まあ……それは少し時間をくれ」
「まあ……それは少し時間をくれ」
![]() 「しかしそう考えると、環境監査を我々が仕切っている現状は問題ですね」
「しかしそう考えると、環境監査を我々が仕切っている現状は問題ですね」
![]() 「というと?」
「というと?」
![]() 「現時点、環境監査で点検しているのは、先ほどの広義でもないし狭義でもない中間、公害防止と廃棄物だけでなく化学物質関係、省エネ、それから本来環境に入らない消防やコミュニケーションつまりふつう使われる意味の環境についての苦情受付などをまでを含んでいます」
「現時点、環境監査で点検しているのは、先ほどの広義でもないし狭義でもない中間、公害防止と廃棄物だけでなく化学物質関係、省エネ、それから本来環境に入らない消防やコミュニケーションつまりふつう使われる意味の環境についての苦情受付などをまでを含んでいます」
![]() 「なるほどなあ〜、確かに環境監査には山内軍団だけでなく省エネや総務や広報も含めないとならないということになる」
「なるほどなあ〜、確かに環境監査には山内軍団だけでなく省エネや総務や広報も含めないとならないということになる」
注:消防法は一般的に設備部門や生産技術ではなく、総務部門担当である。
![]() 「うーむ、我々の役割から考えるとつじつまが合わないか」
「うーむ、我々の役割から考えるとつじつまが合わないか」
![]() 「一番簡単なのは、環境監査を監査部だけで実施すれば解決です。とはいえそれでは今まで見逃していたから問題があったから、我々が参加するようになり現在があるわけですが」
「一番簡単なのは、環境監査を監査部だけで実施すれば解決です。とはいえそれでは今まで見逃していたから問題があったから、我々が参加するようになり現在があるわけですが」
![]() 「話がどんどん流れていきますが、まずは山内軍団の職務範囲を明確にすることが必要ですね。我々は公害と廃棄物だけだとなれば、考えなければならないのは環境監査だけではないです。
「話がどんどん流れていきますが、まずは山内軍団の職務範囲を明確にすることが必要ですね。我々は公害と廃棄物だけだとなれば、考えなければならないのは環境監査だけではないです。
環境担当者教育もその範囲で留めるのかも考えなければなりませんし、環境不具合のまとめや講習会にしても落ち葉の苦情などのコミュニケーションは担当外ということになります。
しかしそれでは業務の取り合いが複雑だし、会社として無駄が多くなるように思えます」
![]() 「それだけじゃない、工場は本社と違い環境部門は広義の環境を担当している。それも複数の人で分担しているわけでなく、排水処理施設管理もISOもボイラーも廃棄物も少人数で担当していますから、何か問題があって本社に問い合わせというとき、これは本社の生産技術、これは本社の広報部というのは面倒ですね。それこそ本社機能のサービスと統制の真逆です。
「それだけじゃない、工場は本社と違い環境部門は広義の環境を担当している。それも複数の人で分担しているわけでなく、排水処理施設管理もISOもボイラーも廃棄物も少人数で担当していますから、何か問題があって本社に問い合わせというとき、これは本社の生産技術、これは本社の広報部というのは面倒ですね。それこそ本社機能のサービスと統制の真逆です。
工場と本社の部門名と業務内容を完全に一致させれば良いけれど、」
![]() 「なるほどなあ、2年前までの本社の体制がごった煮とするなら、今はただ解体しただけか。理屈もなく効率的でもなさそうだ」
「なるほどなあ、2年前までの本社の体制がごった煮とするなら、今はただ解体しただけか。理屈もなく効率的でもなさそうだ」
![]() 「環境そのものが単一の機能じゃないし、システムでもありませんからね。今時はやりの学際とか業際なんでしょう」
「環境そのものが単一の機能じゃないし、システムでもありませんからね。今時はやりの学際とか業際なんでしょう」
![]() 「やれやれ、来年の計画と予算を考えようとしたものの、現実には自分のいる座標すら定まらずか……
「やれやれ、来年の計画と予算を考えようとしたものの、現実には自分のいる座標すら定まらずか……
とはいえ明確にしなければならず、それが決まらないとなにも進まない」
![]() 「あるいは山内軍団は環境を取りまとめる部署だとみなすこともできます」
「あるいは山内軍団は環境を取りまとめる部署だとみなすこともできます」
![]() 「どういうことだ?」
「どういうことだ?」
![]() 「そもそも山内さんはラインじゃありません。環境担当役員である大川専務のスタッフです。環境担当役員のスタッフはスラッシュ電機の環境管理のとりまとめをしているわけで、公害だけでなく広報から省エネから環境配慮設計まで統括するのはおかしくありません。
「そもそも山内さんはラインじゃありません。環境担当役員である大川専務のスタッフです。環境担当役員のスタッフはスラッシュ電機の環境管理のとりまとめをしているわけで、公害だけでなく広報から省エネから環境配慮設計まで統括するのはおかしくありません。
そして公害防止や廃棄物については、大川専務の直下の部門が本社機能を持っていると考えるのです」
![]() 「それならもう一歩進めて、公害防止などは生産技術本部の生産技術部が担当しており、その課長を山内さんが兼務しているとみなしたほうが無理はなさそうだ。
「それならもう一歩進めて、公害防止などは生産技術本部の生産技術部が担当しており、その課長を山内さんが兼務しているとみなしたほうが無理はなさそうだ。
というのはスタッフがラインの指揮するのはおかしい。それに山内さんが異動したとき後任者が全般的な環境管理を見ることはできても、公害防止とか廃棄物の具体的なことは分からないかもしれない」
注:スタッフとラインの兼務はおかしいというかもしれない。だが組織論としてそれはおかしくない。参謀を持つのは通常旅団以上だが、下位の指揮官だって助言者を必要とするのは当然だ。小隊なら通常は軍曹、中隊なら小隊長がその任を務める。このとき中隊長の参謀(スタッフ)だから小隊長をしてはいけないという理屈はない。絶対に譲れないのは、参謀(スタッフ)というだけではラインの指揮はできないことだ
![]() 「なるほど、そういう風に考えればおかしくない。そうであれば環境不具合集の編纂は環境担当役員の本務であり、環境監査の支援は大川専務の環境担当役員が行っていると考える。そして具体的な公害防止の支援とか事故対応は生産技術課の本来業務であると考えるか。
「なるほど、そういう風に考えればおかしくない。そうであれば環境不具合集の編纂は環境担当役員の本務であり、環境監査の支援は大川専務の環境担当役員が行っていると考える。そして具体的な公害防止の支援とか事故対応は生産技術課の本来業務であると考えるか。
だが今はそうではないな?」
![]() 「職制表上は佐久間さんも私も環境課の鈴木課長の下にあります。そして昨年の廃棄物トラブルのときに、山内さんが私に鈴木課長ではなく、山下さんの監督下で仕事をするという指示だったじゃないですか。そのねじれが問題です。これを解消するには佐久間さんの意見を採用するしかありません」
「職制表上は佐久間さんも私も環境課の鈴木課長の下にあります。そして昨年の廃棄物トラブルのときに、山内さんが私に鈴木課長ではなく、山下さんの監督下で仕事をするという指示だったじゃないですか。そのねじれが問題です。これを解消するには佐久間さんの意見を採用するしかありません」
| 職制表 | 実態 | |||||||||
| 本部長 | ||||||||||
| 参謀 | ||||||||||
| 部 長 | ||||||||||
| 課 長 | ||||||||||
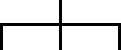 |
 |
|||||||||
| 担 当 者 | ||||||||||
![]() 「鈴木課長に異動してもらい山内さんが環境課長兼務となると、今 山内軍団が管理していない、公害担当の山下さんと廃棄物担当の奥井君の仕事を含めて管理することで筋が通ると思いますが」
「鈴木課長に異動してもらい山内さんが環境課長兼務となると、今 山内軍団が管理していない、公害担当の山下さんと廃棄物担当の奥井君の仕事を含めて管理することで筋が通ると思いますが」
![]() 「うーん、そうなると鈴木課長の処遇か、そして山下さんはあれだし、奥井君はもういらないか?」
「うーん、そうなると鈴木課長の処遇か、そして山下さんはあれだし、奥井君はもういらないか?」
![]() 「個人的にどうするかは別途お考えいただくとして、現状で庶務を除いても5人いるのは多すぎです」
「個人的にどうするかは別途お考えいただくとして、現状で庶務を除いても5人いるのは多すぎです」
![]() 「俺はいなくなるんだぜ」
「俺はいなくなるんだぜ」
![]() 「まともにとりかかるなら5人でも足りなそうだ。ISO認証返上検討、内部監査のレベルアップ、環境担当者のテキスト作成と教育の実施などやることを考えてみろ。今は忙しいからって先送りというか手を付けてないだろう。
「まともにとりかかるなら5人でも足りなそうだ。ISO認証返上検討、内部監査のレベルアップ、環境担当者のテキスト作成と教育の実施などやることを考えてみろ。今は忙しいからって先送りというか手を付けてないだろう。
佐久間さんにテキスト作成と教育を担当してもらいたかったのだが」
山内氏は2018年の計画を考えようとしていたのですが、まずは体制の見直しが必要なようです。グダグダしていても前進はありません。体制をしっかり決めて動かないと……
とはいえ物語ですから真剣になることはありません。ついつい、自分が担当してとりかかる気になってしまいます。
*
*
今回は何を言いたのか?
環境管理なんてお仕事はないということだ。いやもっと言えば、環境マネジメントシステムなんてのは存在しない。
注:ISO14001規格の定義は間違っていない。すなわち「(組織の包括的な)マネジメントシステムの一部で、環境側面をマネジメントし、順守義務を満たし、リスクおよび機会に取り組むために用いられるもの」である。
定義では環境マネジメントシステムがシステムであるとは語っていない。
環境マネジメントシステムの規格で取り上げられたものは、環境という切り口で組織を見たものであり、その切り口で見えたものを集めたものが環境に関わるのは間違いないが、それらは「相互に関連する又は相互に作用する要素の集まり(ISO9000:2015のシステムの定義)」ではなく、「環境に関連するが、相互に関連しないものや相互に作用しない要素」もあるのである。例えば省エネとグリーン調達は無縁であるし、リサイクルと騒音問題も無関係だ。つまり環境に関わるものを集めてもシステムじゃないんですよ。
では環境管理とはなんだろうか? 環境管理部門とは何をするところか? 環境監査とは何を点検するのだろう?
ご存じの方教えてください。
1990年代から政府も経団連もマスコミも、しっかり環境管理をしろと叫び始めた。
省エネしろ、廃棄物を出すな、リサイクルしろ、化学物質管理だ、通勤にも配慮しろ、景観も……それはもっともなことだ。だが、それは環境管理部門を作ることにつながるのだろうか?
設計部門とか調達部門あるいは製造というくくりは、確かに一つの関連するシステムでありワークフローである。しかし環境とはそこから赤い服を着ている人を集めたようなもので、赤い服を着ていてもお互いに関連もなく影響も与えない。
環境先進企業に環境部門はなく、CSR先進企業にCSR部門なしと語られたのはもう20年も前だ。その言い回しは単なる揶揄と受け取られたようで世間に膾炙しなかったが、真理である。
ではどうあるべきなのか?
残念ながら私は会社組織を作るような立場になったことはない。しかし思うことは工場レベルでは環境管理なんて部門はありえないだろうし冠する部署などいらないだろう。騒音苦情があれば総務が対応し、内容によって設備管理部門かもしれず、勤務形態なら製造部門とか、発生源が工場でないなら警察に暴走族取り締まりを頼むとか市に他をあたってくれと交渉するのが筋だろう。
要するに従来からある機能別組織で充分である。
全社レベルならどうか? やはり環境部門はいらないんじゃないか。広報部が関連する部署と打ち合わせ対応することで事足りる。その証拠にいまどき環境報告書なるものはドンドンCSR報告書あるいはサスティナビリティ報告書とかESG報告書に名称が変わっている。もちろん中身も環境だけでなく、ISO26000に対応するように広く記載されている(ものに移りつつある)。
と考えてくるとISO14001なるものは不要ということになる。私はISO26000のようなもの、しかも認証規格でなく指針とか手引きで充分と考える。
注:ISO規格として制定されたものでも、その性質により認証規格(standard)、指針(guidance)、ガイドライン(guideline)などに分けられる。
- 基準(standard):記述されたことを守らなければならないもの。
例「ISO14001環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引」 - 指針(guideline):強制力のない要件、基準、方法などをいう。
例「ISO14004 環境マネジメントシステム-実施の一般指針」 - 手引(Guidance):何事かについてのアドバイスや指導。
例「ISO26000 社会的責任に関する手引」
Shallを満たせば結果を保証するわけでもないのに、わざわざ大金を払って認証を受ける意味はない。それならガイドラインを参考に自分たちで最適を考えたほうが実がある。
元々品質保証規格であったISO9001:1987が認証規格……つまり助動詞がshallであったのは、それを認証すれば顧客が買ってくれるという前提があったからだ。
その前提のない規格で認証するというのは空売りと同じだ。無価値とわかっても売ったもの勝ち。それでも
当然ながら環境と冠する部署がなくてもISO認証に影響しないし、窓口が一つでなくても審査に問題はない。
ISO審査で審査員が「廃棄物を見たい」といえば施設管理課に連れていき、省エネ設計がと言えば設計に連れていき、コミュニケーションと言えば総務に連れていく。それで充分である。
誰が案内するんだって? 一番暇な人がすればいいじゃないか。
まてよ、そもそもなんのために認証するんだ?
1997年に「環境を冠する部門を作れ」と語った某認証機関の中■さんは、そんなことも知らなかったようだ。それでよくISO14001審査員になったものだ。ご本人の恥であるだけでなく、審査を受けた企業に多大な迷惑、損失をもたらしたことを自覚し反省し謝罪しなければならない。
中■さん、部門の看板を作るだけでもタダじゃすまないんですよ。審査料金を払い戻してほしい。中■さん個人の考えでなく認証機関の見解だったのだろうか?
|
|
| ||
| 看板書き換えるだけ でもタダじゃない |
||||
部署名を変えれば変更するのは看板だけでなく、名刺もあるし、社内電話帳の書き換えもある。取引先にも連絡しなければならない。町内会に連絡している苦情窓口の変更もある。名前を変えるだけでも大変なんだよ。分かってるのかねえ〜
注:名前を変えるのが大変なのは、部署名だけではありません。
昔から改元には大金がかかり、皇室の威厳がなかった戦国時代には費用がまかなえず後土御門天皇が退位できないとか、譲位を受けても後柏原天皇は金がなく即位したのは21年後のだったと聞きます。
 今も改元には大金がかかります。それは皇室行事だけでなく、一般企業もコンピューターシステムの修整など膨大な費用がかかります。まあ、それは回りまわってGDPになるのですから良しとしましょう。
今も改元には大金がかかります。それは皇室行事だけでなく、一般企業もコンピューターシステムの修整など膨大な費用がかかります。まあ、それは回りまわってGDPになるのですから良しとしましょう。
犯罪が増えると刑務所の建設や刑務官の増員でGDPが増えるそうです。それは国民所得が増えてもうれしくないよね。
私は誰の挑戦でも受ける。反論をお待ちしております。
おっと、所信表明が全体の3割にもなってしまった。これはいけない。
![]() 本日の無駄話
本日の無駄話
今回の物語は話が進むにつれて、登場人物がどんどん変わります。
アメリカに帰ったアメリアは多分もう登場しないでしょう。佐久間さんも次回から出てこないかもしれない。現実の職場はそんなものです。
私が最後に勤めた部署には常時10名前後いましたが、出入りが激しくしょっちゅう人が変わりました。派遣の人を除いても、年度替わりの転勤だけでなく、海外駐在に出たり戻ったり、期中の採用もあり退職もありました。
 |  |  |
ミュージカルチェアーどころか、椅子のない立食パーティーです。
同じ部署であっても、直接仕事の関わりはないので、話す機会といえば、挨拶と歓迎会・送別会くらいしかありませんでした。
私はなぜか(たぶん能がないから)定年まで10年間居座っていましたが、その間にその職場に在籍した人の累計は30人以上になるでしょう。
人が代わっても、皆プロでしたから仕事は止まることなく進んでいきました。リストラなどでなく平常時にあれほど異動が多かった職場は、私の経験では他にありません。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
44年特例とは、現行の制度では44年以上厚生年金をかけた被保険者は「長期加入者の特例」として、65歳にならずとも退職した時点で満額年金を受けることができる。中卒の人は60歳で、高卒は62歳から受領できる。大卒の場合は、44年働けば以前の法律では年金がもらえる年になっていたから、特典にならない。だから高卒者は60歳定年の場合は2年と少し嘱託で働き退職という人が多かった。 今後は制度が変わって、そんな甘いことはなくなるだろう。 | |
注2 |
SDGsは2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」である。 2017年にはバッジがあちこちで見られるようになった。 | |
注3 |
定款に書いてない事業をすることは即法違反ではない。但し許認可を必要とする事業を行うには、定款の事業目的にそれが記載されていなければならない。 NPO法人では当然それが行う社会貢献などを定款を定めるが、一般の営利企業で社会貢献を定款に書いているのがあるのかどうか私は知らない。 判例を見ると、現代では定款に書いてなくても、事業上必要だとみなされる社会貢献事業を行うことは妥当と裁判所は判断しているようだ。 「法人の社会貢献活動と定款所定の目的」鈴木正彦、修道法学、2017 | |
注4 |
組織論の基本である。 「管理と組織」ルイス・アレン、ダイヤモンド社、1955 「宇宙の戦士」ロバート・ハインライン、早川書房、1967 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |