*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
10月も末となった。2017年の10月初めは、最高気温が30℃を超す日もあったが、10日を過ぎると10度台に下がり、以降は涼しくなる一方だ。
磯原も本社に来て初めての昨冬はさすが関東地方は暖かいと思ったが、2年目の今は暑さに強くなった分、寒さに弱くなった。昨冬は手袋なし、コートなしで過ごしたが、今年は手袋もコートも必要だろう。
 寒さで手をこすり合わせながら本社ビルに入る。すっかり本社の住人になった磯原は、偉い人に会ったらどうしようなどと思うこともなくなった。
寒さで手をこすり合わせながら本社ビルに入る。すっかり本社の住人になった磯原は、偉い人に会ったらどうしようなどと思うこともなくなった。
例によって生産技術本部で朝一番を争う大川専務とエレベーターで会い挨拶を交わす。大川常務は今年の株主総会で専務執行役に就任された。毎日会うが特に会話することもない。
 専務と並んで廊下を進むと、生産技術本部のドアの前に、見覚えのある人が立っている。ええと……昨年の会議に出席して質問した人だ。なぜか機嫌を悪くして、途中退場したはず。名前は忘れたというか覚えていない。
専務と並んで廊下を進むと、生産技術本部のドアの前に、見覚えのある人が立っている。ええと……昨年の会議に出席して質問した人だ。なぜか機嫌を悪くして、途中退場したはず。名前は忘れたというか覚えていない。
大川専務はさっさと社員証をドアのセンサーに当てて入ってしまう。磯原はその見覚えのある人に声をかけた。
注:ワケワカラン人もいるだろうと気が付いたので追記する。
多くのオフィスビルでは、訪問者は受付で入れてもらってもロビーや廊下しか入れない。
各部門の入口に入室を規制するために、会社に入ると同じくタッチキーなどがある。訪問者はインターホンなどで入室したい旨伝えて開錠してもらうことになる。当然、早朝に来た訪問者は受付で入れてもらえても、その部門の前で待つことになる。
役員室や情報システムなどセキュリティの厳しい部門は、社員でも関係者以外入れない設定になっている。
![]() 「おはようございます。ええと……浜松工場の……」
「おはようございます。ええと……浜松工場の……」
![]() 「浜松工場の大山です。お久しぶりです」
「浜松工場の大山です。お久しぶりです」
![]() 「あっ、大山さんでしたね。名前が出てきませんでした。だいぶお早いですが、どちらにご用でしょう。今8時20分、始業は9時ですので、皆さん出勤するまでまだだいぶ時間がありますよ」
「あっ、大山さんでしたね。名前が出てきませんでした。だいぶお早いですが、どちらにご用でしょう。今8時20分、始業は9時ですので、皆さん出勤するまでまだだいぶ時間がありますよ」
![]() 「ご存じと思いますが、12月に浜松工場の環境監査です。それで事前に磯原さんにご相談したいことがありましてお邪魔しました」
「ご存じと思いますが、12月に浜松工場の環境監査です。それで事前に磯原さんにご相談したいことがありましてお邪魔しました」
![]() 「それなら事前にご連絡いただければ良かったですね。今日はたまたま本社におりましたが、出張も多くお会いできなかったかもしれませんよ」
「それなら事前にご連絡いただければ良かったですね。今日はたまたま本社におりましたが、出張も多くお会いできなかったかもしれませんよ」
![]() 「いえ、お宅の庶務の方に磯原さんの予定を確認しまして、今日は出張も会議もないとのことでしたので」
「いえ、お宅の庶務の方に磯原さんの予定を確認しまして、今日は出張も会議もないとのことでしたので」
磯原は呆れた。いくら社内とはいえ、会いに行くのにアポイントも取らない人がいるものだろうか? ユミちゃんもどうしたんだろう。知らせてくれれば良いのにというか、知らせなければならないだろう。
数人、出社の早い人が現れて二人の脇を通り過ぎていく。
しょうがない、磯原はドアを開錠して大山を打ち合わせコーナーに案内する。そこに荷物を置かせてパントリーに案内し、好みの飲み物を取らせる。
それから打ち合わせコーナーに戻り、座る。
![]() 「大山さん、突然来られても困ります。事前連絡はいただきたいですよ。
「大山さん、突然来られても困ります。事前連絡はいただきたいですよ。
ええと、私は始業前にメールの処理をしなければなりません。毎日、工場からの問い合わせとか異常報告がありますので、それの処理をしなければなりません。
今は…8時40分ですか、1時間かからずに処理しますから、それから話を伺いましょう。私が時間を割けるのはそれから30分くらいですがご了承ください」
大山は何か言いたそうだったが、口を開く前に磯原は急いで自席に座りパソコンをオンにする。10分以上ロスした。朝の10分は貴重だ。もし工場や関連会社から異常報告とか重大な連絡があれば、山内が出社する前に問題をまとめ、それに磯原の見解を付けて報告しなければならない。
パソコンが立ち上がるとメールボックスを開く。退社以降の着信が約60件以上ある。自宅のパソコンなら60件あっても、メルマガと広告が8割、それに詐欺メールが少々で、意味のあるメールは10件もないから
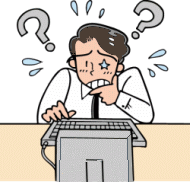 発信者を見ただけでパッパッと消していける。
発信者を見ただけでパッパッと消していける。
一方、業務のメールは、まず詐欺メールやウイルス付きはリジェクトされ個人まで配信されない。だからみな意味のあるメールだ。多くは定期報告や社内外の知り合いからの情報交換だが、中には事故発生とか重要な問い合わせが紛れているから油断できない。
真面目に読んで処理すると午前中かかることもある。「違反に気づいたどうしよう!」なんてのが工場から来ていれば一日かかりだ。
*
20件くらいメールを処理した頃、佐久間が出社してきて隣の席に座った。お互い軽く挨拶を交わす。
彼はラッシュは嫌いだが、早く家を出るのも嫌いで、定時よりは早いが磯原より20分遅く来る。とはいえ電車に乗る時刻は磯原より早いだろう。ご苦労なことだ。
彼は入社以来40年、通勤は歩いて15分だったのに、この年になって佐倉から東京まで通勤とは何の呪いだとこぼしている。山内は呪いではなく誉れだろうと相手にしない。
![]() 「磯原君、あそこに座っているのは、浜松の大山君だろう? 何かあったのかい?」
「磯原君、あそこに座っているのは、浜松の大山君だろう? 何かあったのかい?」
![]() 「浜松工場の環境監査が12月なので、事前打ち合わせをしたいそうです。私宛なんですが、もしできたら佐久間さんに対応してもらいたいです」
「浜松工場の環境監査が12月なので、事前打ち合わせをしたいそうです。私宛なんですが、もしできたら佐久間さんに対応してもらいたいです」
![]() 「俺は構わないけど、ご指名なら一応話は相手した方がいいよ。磯原君は朝は忙しいだろうから、とりあえず俺が話を聞いていよう」
「俺は構わないけど、ご指名なら一応話は相手した方がいいよ。磯原君は朝は忙しいだろうから、とりあえず俺が話を聞いていよう」
![]() 「申し訳ありません。それじゃ、ええと…ああ…始業ベルが鳴る」
「申し訳ありません。それじゃ、ええと…ああ…始業ベルが鳴る」
フレックスの人もかなりいるが、半分以上は定時出社だ。出社した人は全員立ち上がり、声を出して朝の挨拶をする。部門によっては朝礼をするところもあり、しない部門はすぐまた腰を下ろし仕事に励む。
佐久間はコーヒーの入った紙コップを持って、大山が座っている打ち合わせコーナーに行く。磯原はそれを視界の端でとらえたが、何も言わずメールの処理に精を出す。
*
メールを一通り見て返事の必要なものには返事を返し、報告すべきことはコメントをつけて山内や佐久間に転送する。 幸い今朝は、トラブルもなく、すぐ行動しなければならないものもない。
幸い今朝は、トラブルもなく、すぐ行動しなければならないものもない。
一段落してコーヒーを飲もうかと紙コップを見ると、大山と一緒に注いだコーヒーはとうに冷たくなっている。しばし考えるが、大山の件を片付けようと決心する。
磯原は立ち上がり、パントリーに行って紙コップの中身を捨てて、新たにブラックコーヒーを注ぐ。それから佐久間と大山が話しているところに座る。
![]() 「お待たせしてすみません。もうお話が済んでいたならうれしいのですが」
「お待たせしてすみません。もうお話が済んでいたならうれしいのですが」
![]() 「大山さんは今年から始めた環境監査について、大いに不満だそうだ。それで浜松工場に環境監査を行うなら、従来通りのマネジメントシステムの監査をしてほしいという」
「大山さんは今年から始めた環境監査について、大いに不満だそうだ。それで浜松工場に環境監査を行うなら、従来通りのマネジメントシステムの監査をしてほしいという」
![]() 「生産技術本部に話をするのは筋違いです。大山さんは監査部に要請すべきです」
「生産技術本部に話をするのは筋違いです。大山さんは監査部に要請すべきです」
![]() 「でも環境監査をしているのは、生産技術本部の磯原さんや佐久間さんですよね」
「でも環境監査をしているのは、生産技術本部の磯原さんや佐久間さんですよね」
![]() 「監査をするという意味合いですが、確かに私たちは監査員を承っています、しかし職責上監査を行っているのは監査部です。
「監査をするという意味合いですが、確かに私たちは監査員を承っています、しかし職責上監査を行っているのは監査部です。
大山さんもご存じと思いますが、監査の実施通知も、その結果の判断も、執行役会への報告も、是正指示もすべて監査部長名で行われています」
![]() 「監査部は経理とかの監査をするのではないですか?
「監査部は経理とかの監査をするのではないですか?
環境監査は環境部門が行うべきでしょう」
![]() 「環境監査というものが存在するわけではなく、監査部が行う業務監査の中の環境部分を、訳あって独立して行っていることはご存じですよね」
「環境監査というものが存在するわけではなく、監査部が行う業務監査の中の環境部分を、訳あって独立して行っていることはご存じですよね」
![]() 「それはどういうことですか?」
「それはどういうことですか?」
![]() 「ええと初歩的なことで恐縮ですが、基本からお話ししますね。
「ええと初歩的なことで恐縮ですが、基本からお話ししますね。
監査には三つの種類があります。ひとつは公認会計士・監査法人による監査、ひとつは監査役監査、そして監査部監査になります」
| 名称 | 責任者/実施者 | 被監査者 |
| 公認会計士監査 | 公認会計士 | 監査役 |
| 監査役監査 | 会社法上の監査役(または監査委員会) | 取締役 |
| 内部監査員監査 | 監査部/内部監査員 | 従業員 |
注:選択によって三つの監査をしない場合もある。
![]() 「公認会計士による監査とか、監査役監査は担当の人以外関わりはありません。我々がしているのは監査部監査です。
監査部監査とは、社内の各部署が法令や会社の規則を守って仕事をしているかどうかを点検するものです。
「公認会計士による監査とか、監査役監査は担当の人以外関わりはありません。我々がしているのは監査部監査です。
監査部監査とは、社内の各部署が法令や会社の規則を守って仕事をしているかどうかを点検するものです。
昔はお金の扱いだけを点検しましたが、だんだんとお金以外でも法を守っているかを点検するようになり、業務監査と呼ばれます。今ではいじめやハラスメントがないかまで点検するようになりました」
![]() 「ISOの監査はそのみっつのどこに入るのですか?」
「ISOの監査はそのみっつのどこに入るのですか?」
![]() 「ISOの監査を決めている会社規則はありません」
「ISOの監査を決めている会社規則はありません」
![]() 「はあ?
「はあ?
ええと、本社や支社もISO14001の認証を受けていますね。当然内部監査をしていると思いますが、それは会社の規則にないのですか?」
![]() 「ありません。以前はISOの内部監査を定めた文書がありました。しかしそれは会社規則ではなかったのです。
「ありません。以前はISOの内部監査を定めた文書がありました。しかしそれは会社規則ではなかったのです。
就業規則では『執務は就業規則及び会社規則並びに関係法令を遵守して』と定めています」
![]() 「ええと、今は内部監査の話ですが」
「ええと、今は内部監査の話ですが」
![]() 「もちろん内部監査の話ですよ。
「もちろん内部監査の話ですよ。
就業規則に基づき、従業員は就業規則、会社規則、関係法令を守って仕事をしなければならない。言い換えるとそれ以外はしてはいけない。
ですから、ISOの内部監査は会社規則で定めなければなりません。ですが本社・支社の内部監査は、先ほど言った当社の文書体系にないISO文書で定めていますから、それは実効力がありません。
会社規則で決めている内部監査は先ほど示した図では、監査部が行う監査だけです」
注:多くの会社ではISO認証のために多くの文書や記録を作っているが、その文書や記録が会社の中でいかなる地位を占めているのか、その前にその存在を決めているのは何かとなると、父なし子であることが多い。
法令の親子関係は明確である。まともな会社ならしっかりした文書体系を持っている。
存在を認められていない文書がいかなる権威があるのか、強制力を持つのか疑問だ。多くのコンサルが作らせる文書がその会社の文書体系と整合しているかは興味がある。
![]() 「本社や支社の内部監査は会社規則で決めてないと、理屈が合わないということですか?」
「本社や支社の内部監査は会社規則で決めてないと、理屈が合わないということですか?」
![]() 「昨年私が本社・支社のISO14001認証の仕事を引き継ぎました。それまで本社のISO認証を担当されていた方は、私と入れ違いに異動されてお会いできず、仕事の引継ぎもしていません。
「昨年私が本社・支社のISO14001認証の仕事を引き継ぎました。それまで本社のISO認証を担当されていた方は、私と入れ違いに異動されてお会いできず、仕事の引継ぎもしていません。
それで後任である私は、いろいろ検討した結果、監査部監査をISOの内部監査に位置付けることにしました」
![]() 「監査部監査を? 監査する内容がISO規格と全然違うんじゃないですか。
「監査部監査を? 監査する内容がISO規格と全然違うんじゃないですか。
それで審査はOKだったのですか?」
![]() 「大山さんも想像されたようにすんなりいかないと思いましたので、認証機関である品質環境センターにお邪魔して、本社・支社のISO認証を全面的に見直すことと、どのように変更するかを説明しました。もちろん内部監査だけでなく、環境側面も目的目標も力量もマネジメントレビューも全面変更でした。
「大山さんも想像されたようにすんなりいかないと思いましたので、認証機関である品質環境センターにお邪魔して、本社・支社のISO認証を全面的に見直すことと、どのように変更するかを説明しました。もちろん内部監査だけでなく、環境側面も目的目標も力量もマネジメントレビューも全面変更でした。
そのときこちらの佐久間さんのご協力をいただきました」
![]() 「それ以来、ここに住み着いてしまったよ、アハハハ」
「それ以来、ここに住み着いてしまったよ、アハハハ」
![]() 「ええと…すると工場も監査部監査だけでISO認証は大丈夫なのですか?」
「ええと…すると工場も監査部監査だけでISO認証は大丈夫なのですか?」
![]() 「それは無理です。というのはまず会社規則との関係が、工場と本社・支社では違うからです。会社規則は会社全体のルールだけでなく本社の仕事を決めていますが、工場の仕事を決めていません。
「それは無理です。というのはまず会社規則との関係が、工場と本社・支社では違うからです。会社規則は会社全体のルールだけでなく本社の仕事を決めていますが、工場の仕事を決めていません。
もう一つの違いは、監査部は本社機構の一部門ですから内部監査をしてもおかしくないです。しかし監査部は本社機構であり、工場の外にある組織です。ですから工場単位で認証しているときは、監査部は認証組織の外ですから内部監査と言えません。二者監査になりますね。
また監査部は本社の各部門をすべて監査しますが、工場はひとくくりの扱いで工場内の部門単位では監査をしません。
本社の部が、工場と同じ位置づけにあるとお考え下さい」
![]() 「なるほど、いろいろ違うんだ。
「なるほど、いろいろ違うんだ。
磯原君がそういうことを考えて、監査部監査を本社・支社の内部監査に位置付けたとはすごい発想であり、それを相手に認めさせたのは君の説得力だね」
![]() 「工場の内部監査は、会社規則では存在が定められているのですか?」
「工場の内部監査は、会社規則では存在が定められているのですか?」
![]() 「工場には工場規則があって、その中でISOの監査を定めているのでしょう。それなら会社の文書体系と矛盾はありません。
「工場には工場規則があって、その中でISOの監査を定めているのでしょう。それなら会社の文書体系と矛盾はありません。
私が今お話ししたのは、大山さんの質問である、工場のISOの内部監査を監査部監査で代用できるかは、できないということです」
![]() 「あ〜、分かりました」
「あ〜、分かりました」
![]() 「仕組みを理解されたとして話の初めに戻りますと、工場に対して行う環境監査の実施部門は監査部ですから、その方法についてご意見があれば監査部にお話ししていただくことがご理解いただけたと思います。
「仕組みを理解されたとして話の初めに戻りますと、工場に対して行う環境監査の実施部門は監査部ですから、その方法についてご意見があれば監査部にお話ししていただくことがご理解いただけたと思います。
佐久間さんも私も、はっきり言えば監査部への助っ人というか下請けです。監査部が大山さんの意向を受けて、方法や基準を見直したなら、我々はそれに従います。
しかし監査部が大山さんのご希望を受けて、ISO審査のような形にする可能性はありません」
![]() 「どうしてですか?」
「どうしてですか?」
![]() 「そもそも今年度から監査部の業務監査を改革したのには理由があります。昨年、設備投資の予算の目的外使用とか、当社の環境計画が工場の計画に展開されていないなどの問題が発覚しました。要するに会社の規則に従っていなかったのです。
「そもそも今年度から監査部の業務監査を改革したのには理由があります。昨年、設備投資の予算の目的外使用とか、当社の環境計画が工場の計画に展開されていないなどの問題が発覚しました。要するに会社の規則に従っていなかったのです。
これは大問題です。だから工場が独断で行為をしないように、監査部の業務監査において、特に環境の点検を強化するために方法が見直されたのです」
![]() 「でもそれは伝票をめくるとか細かいことをチェックすることでなく、マネジメントシステムがしっかりしているかをチェックすることで防止できるのではないですか」
「でもそれは伝票をめくるとか細かいことをチェックすることでなく、マネジメントシステムがしっかりしているかをチェックすることで防止できるのではないですか」
![]() 「監査の責任部門は監査部だと申しました。しかし私も今回の監査の仕組みを作ることに参画していましたので、理由は説明できます。
「監査の責任部門は監査部だと申しました。しかし私も今回の監査の仕組みを作ることに参画していましたので、理由は説明できます。
大山さんはマネジメントシステムとおっしゃった。その通りです。しっかりしたマネジメントシステムを作り、それを守って仕事をすることです。
ではマネジメントシステムが適正か、遵守運用されているかはどのように点検すればよいのでしょうか?」
![]() 「私はISOの審査員補です。そういうことは詳しいです。
「私はISOの審査員補です。そういうことは詳しいです。
ISO規格要求がシステムに組み込まれているか、運用されているかを見れば良いのです」
![]() 「マネジメントシステムがISO要求事項を満たしているかどうかは、文書を見ればイチゼロ判定できるでしょう。
「マネジメントシステムがISO要求事項を満たしているかどうかは、文書を見ればイチゼロ判定できるでしょう。
では運用はどのようにして判定するのですか?」
![]() 「記録を見ればよいのです」
「記録を見ればよいのです」
![]() 「記録が正しければね」
「記録が正しければね」
![]() 「記録が正しくなければ虚偽の説明ですから、監査で見つけないのは仕方ありません」
「記録が正しくなければ虚偽の説明ですから、監査で見つけないのは仕方ありません」
![]() 「オイオイ、予算の目的外使用や環境目標が本社指示と違うがあったからの対策なのだから、監査で見つけられませんは通用しないよ。
「オイオイ、予算の目的外使用や環境目標が本社指示と違うがあったからの対策なのだから、監査で見つけられませんは通用しないよ。
それを見つけるためにどうするかを考えないとならない。
裁判では被告人は嘘をついても罪にならない。じゃあ、裁判官は騙されてよいといえるのか? そうじゃないでしょう。騙されないためには証拠をしっかり見て、検察側が申し立てたことが事実か否かを判断するわけだ。
嘘をつかれたら見つけられないなら、そんなもの監査じゃない。我々はお遊びしているわけじゃない」
![]() 「でもISO審査では、嘘をつかれたから見つけられなかったと語っていますよ」
「でもISO審査では、嘘をつかれたから見つけられなかったと語っていますよ」
![]() 「じゃあ、ISO審査はお遊びなんだろう。金がもらえる仕事ではなさそうだ」
「じゃあ、ISO審査はお遊びなんだろう。金がもらえる仕事ではなさそうだ」
![]() 「ISO審査だって虚偽の説明を受けたと言っても通用するはずがない。それは単に審査員の力量が低いことの言い訳です。本来なら認証機関は、審査がまずかったことを謝罪して審査料金を払い戻さなくてはならない。
「ISO審査だって虚偽の説明を受けたと言っても通用するはずがない。それは単に審査員の力量が低いことの言い訳です。本来なら認証機関は、審査がまずかったことを謝罪して審査料金を払い戻さなくてはならない。
そもそもISO審査がごまかしを見つけられないなら、認証機関などやめるべきです。
ともかく審査や監査で嘘をつかれても見つけられないなら意味がない」
![]() 「するとごまかしとか本社指示と違うことがあれば、ISOの内部監査で見つけなければならないのですか?」
「するとごまかしとか本社指示と違うことがあれば、ISOの内部監査で見つけなければならないのですか?」
![]() 「当たり前だろう! 不具合を見つけるのが監査なのだから、見つけられないなら監査の意味がない。
「当たり前だろう! 不具合を見つけるのが監査なのだから、見つけられないなら監査の意味がない。
まさか浜松工場では、内部監査で見逃しても仕方がないと考えているんじゃないだろうな」
![]() 「それと、マネジメントシステムの運用状況を見るということは、なにかひとつのものを見てOK/NG判定できるわけではない。
「それと、マネジメントシステムの運用状況を見るということは、なにかひとつのものを見てOK/NG判定できるわけではない。
|
環境課長 23.03.03 桃之花 | |
|
定められた権限者 が決裁しているか | |
決裁に代行印があれば、代行者は代行する権限が認められているかどうか確認しなければならない。
課長の日付印を見て、その日に課長が出張や休暇でなかったことを確認するのは当然だ。
インプットとアウトプットの日付を見て、課長が決裁を滞留させていないか、異常に早く決裁していないか、とか見ることはたくさんある。
先ほど話に出た環境目標の展開だって、課の目標は本社が工場に割り当てられたものと整合しているか、その課ではどう展開しているか確認しなければならない。
大山さんの大好きな書面チェックだって一筋縄ではないよ。そう思えば内部監査ってやりがいがあるじゃないか」
![]() 「俺も同感だ。大山君は即物的な監査はレベルが低いなんて言うけど、レベルが低かろうが高かろうが現実をよく見ることが大事だ。そしてたくさんの証拠を集めて考えなければならない。その結果は大山君好みのマネジメントシステムの審査と同じ結果になるはずだ。
「俺も同感だ。大山君は即物的な監査はレベルが低いなんて言うけど、レベルが低かろうが高かろうが現実をよく見ることが大事だ。そしてたくさんの証拠を集めて考えなければならない。その結果は大山君好みのマネジメントシステムの審査と同じ結果になるはずだ。
要するに君が推奨する方法も我々がしている方法も、結果は同じになる。だがどちらにしてもサンプルは多くなければならず、しっかり見なくては監査ではない。
ISO審査だって頭で考えるのでなく、現場で現物と現実をしっかり見ることで、世のISO審査はワンランクアップするはずだ。現実はそうではないが」
![]() 「話を戻す。大山さんは従来通り『マネジメントシステムの監査をしてほしい』ということでしたね。今年から始まった監査の方法も本質は変わっていません。違いはたくさんのサンプルを見るということです。正確にはたくさんではなく、全部を見ることにしています。しらみつぶし監査と呼んでます。
「話を戻す。大山さんは従来通り『マネジメントシステムの監査をしてほしい』ということでしたね。今年から始まった監査の方法も本質は変わっていません。違いはたくさんのサンプルを見るということです。正確にはたくさんではなく、全部を見ることにしています。しらみつぶし監査と呼んでます。
そしてその結果、たくさんの問題を見つけています。先ほど述べた、工場が予算を目的外に流用したり、環境目標を本社方針と違えるなどです。マネジメントシステムだけ見る監査より、会社に貢献していると思いませんか。監査方法を変えたことを、執行役会議で誉められたそうです」
![]() 「じゃあ、工場としてはどのような準備をしておけばよいのですか?」
「じゃあ、工場としてはどのような準備をしておけばよいのですか?」
![]()
|
でも危険物貯蔵所の責任者名が最新化されているか、作業主任者は現場にいるか
![]() 「大山さんは、環境方針を知っているかを確認するにはどうしますか?」
「大山さんは、環境方針を知っているかを確認するにはどうしますか?」
![]() 「なかなか周知するのは難しいですね。ISO審査で審査員に質問されると答えられる人は少ないです。それで古典的ですが、浜松工場では毎年工場の環境方針を名札に入る大きさで作って配っています。
「なかなか周知するのは難しいですね。ISO審査で審査員に質問されると答えられる人は少ないです。それで古典的ですが、浜松工場では毎年工場の環境方針を名札に入る大きさで作って配っています。
審査員に聞かれたとき、それを見せればOKになります」
![]() 「私は思うんですよ、周知とは、方針カードを携帯しているとか、暗記していることじゃないって。方針の周知って単純な話、上長の方針を理解して日々の仕事で実践していることでしょう。
「私は思うんですよ、周知とは、方針カードを携帯しているとか、暗記していることじゃないって。方針の周知って単純な話、上長の方針を理解して日々の仕事で実践していることでしょう。
だったら監査で方針が周知されているかどうか確認するためには、この職場の今年の目標は何ですか?、あなたのお仕事ではどんなことを目指していますか?、あなたは何をしていますか?、そういうことでしょうね」
![]() 「そういうものには環境って言葉が入ってませんよ」
「そういうものには環境って言葉が入ってませんよ」
![]() 「そんなことないでしょう。品質を上げ、生産を上げれば、省エネと省資源です。現場の省エネは品質向上と生産向上しかないですよ。
「そんなことないでしょう。品質を上げ、生産を上げれば、省エネと省資源です。現場の省エネは品質向上と生産向上しかないですよ。
消灯しろって言っても安全上限界があります。意識づけとか努力で省エネができるはずがない。多くの人が努力と言いますが、まったく理解してません。
環境という言葉があろうがなかろうが、方針に整合しているか否かが判断できることが審査員の必要条件です。できない審査員は次回から忌避するしかありません。なにしろ我々は審査に金を払っている客ですからね」
*
*
それから30分ほどして大山は帰っていった。
磯原と佐久間は、顔を見合わせてため息をついた。
![]() 「彼はISO規格も環境問題も理解していないんだねえ〜
「彼はISO規格も環境問題も理解していないんだねえ〜
いや、その前に会社の仕事も理解せず、そもそも何のために働くのかも理解していないようだ」
![]() 「じゃあ、彼は何を目指してしているんだ?」
「じゃあ、彼は何を目指してしているんだ?」
脇から声がしたので、二人はギョッとして声がしたほうに顔を向ける。
山内がコーヒーの紙コップを持って立っている。
![]() 「話せば長いことながら……」
「話せば長いことながら……」
![]() 「それじゃ、長い話とやらを聞かせてくれよ」
「それじゃ、長い話とやらを聞かせてくれよ」
山内は今まで大山が座っていた向かい側に座る。
![]() 「環境部門というのは、昔は、いや今もでしょうか、掃きだめみたいなものでした。他の部門で使い物にならない人、引退間近な人、そういう人が環境部門に来て、廃棄物の処理とか植栽とか清掃の仕事をしていたのです。
「環境部門というのは、昔は、いや今もでしょうか、掃きだめみたいなものでした。他の部門で使い物にならない人、引退間近な人、そういう人が環境部門に来て、廃棄物の処理とか植栽とか清掃の仕事をしていたのです。
あるときISO14001なるものが現れて、どの会社も一刻も早く認証しなければというアホな競争が起きました。1997年から1999年頃のことです。
笑っちゃうんですが、当時は…いや今もか…規格を満たしたマネジメントシステムでも認証機関はOKしない。なぜかというと認証機関が付加価値を要求したのですね。規格要求事項にプラスアルファを、
それで皆、認証機関の講習を受けて、その認証機関が考えたものを追加することになりました。
いや実際の中身は、くだらないことばかりでしたよ。目標は3年以上でなければならないそうです。
 法改正のため今年中に対策しなければならないことは、環境の目標にならないわけです。そいじゃ法の施行までに間に合わないじゃないですか、アハハ
法改正のため今年中に対策しなければならないことは、環境の目標にならないわけです。そいじゃ法の施行までに間に合わないじゃないですか、アハハ
ともかく認証機関のご要望に合わせることは神学論争でしたので、担当者は知らない人に優越感を持ったのです。各部門の人はISO規格を知っていると思われる人の語ることに従いました。
昨日まで掃きだめだったのが、一挙に掃きだめの鶴にランクアップしたのです。
認証機関の語ることを本当は間違いだと認識して、しかし認証のためには仕方がないと考えているならまだ分かります。しかし認証機関独自の
大山氏も今までの考え方、価値観を否定するような新しい環境監査を見て混乱しているのです。
山内さん、そういう人たちは工場に大勢います。そういう人の目を覚まさせるか、入れ替えないと我が社の環境管理は良くなりませんね」
![]() 「そういう人の気持ちはわかる。だが、環境管理が良くならないとはどうしてかな?」
「そういう人の気持ちはわかる。だが、環境管理が良くならないとはどうしてかな?」
![]() 「今の形だけの役に立たない環境管理とか環境監査をしてきたのが彼ら、ISO第一世代なんです。
「今の形だけの役に立たない環境管理とか環境監査をしてきたのが彼ら、ISO第一世代なんです。
そして今まさに我々の役に立つ内部監査にしようという動きに抵抗しているのです。大山君が今日、本社に来たのは、12月に行う浜松工場の監査を従来のISO規格要求をチェックする形にしてほしいという要望です。
あげくに内部監査で嘘をつかれたら見つけることができなくて当然だと言うのです。それじゃ監査は何のためにするのかと問えば、答えはありませんでした。本音は監査もISOも役に立とうが立つまいが、自分たちが楽に過ごせれば良いのでしょうね」
![]() 「佐久間さんは、ISO第一世代でその病気に冒されなかった稀有な存在なのです。私はそういう時代が過ぎ去ってからISOに関わった第三世代です」
「佐久間さんは、ISO第一世代でその病気に冒されなかった稀有な存在なのです。私はそういう時代が過ぎ去ってからISOに関わった第三世代です」
![]() 「なるほどなあ〜、彼は己のレーゾンデートルのため、現状を変えたくないわけか。問題はいろいろあるね」
「なるほどなあ〜、彼は己のレーゾンデートルのため、現状を変えたくないわけか。問題はいろいろあるね」
![]() 本日の言いたいこと
本日の言いたいこと
私はISO9001が登場した黎明期からISO認証に関わってきた。
ISO9001の時代は、審査員が接待しろとか、お土産とか希少価値のあるノベルティを要求されたことはあったが、規格解釈はまっとうで、審査員や認証機関の
しかしISO14001が登場するとそういった悪弊は大幅に減った。しかし良くなったかというとそうではない。認証機関によって規格の解釈が正反対だったり
それを企業の担当者は真理だと信じ込んでしまった。洗脳である。
私は周りがどんどん洗脳される中で孤軍奮闘、同業者、認証機関、審査員と戦い続けてきた。その恨みは今も変わらない。
私は年代的には佐久間氏であり、磯原氏ではない。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
注1 |
「痛快憲法学」、小室直樹、集英社インターナショナル、2001、p.24 | |
注2 |
安衛則130条以降の各種の作業主任者の職務として ・直接指揮すること、 ・異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること ・使用状況を監視すること などをあげており、現場にいることが求められている。 | |
注3 |
うそ800の目次に戻る
ISO 3G目次に戻る
     |