�u�@�I�v�������v�ɂ��Ă��������K�v�ɂȂ肻���ł��邪�A�����ł͈ȍ~�P�Ɂu�@�K���v�ƌĂ��K�p�\�Ƃ������t�����āA�w�g�D���u�K�p�\�v���ƌ��ߕt���Ă������̂��낤���H�x�ȂǂƂЂ�������Ƃ������^���������l������B�����^����������B
���͐����@���D������Ȃ������Y���Ɍ��߂悤�Ƃ��A���������Ȃ�����e�����T�C�N���@�͓K�p���Ȃ��A���邢�͏ȃG�l������������ȃG�l�@�͓K�p�s�\���Ȃ�Ă��Ƃł���͂�������܂���B
- �����@�i���������ق��j�F���������h�~�@�̗���
- �e�����T�C�N���@�F�e���ɌW�镪�ʎ��W�y�эď��i���̑��i���Ɋւ���@���̗���
���ۂɋ��������Ȃ�����e�����T�C�N���@��K�p���Ȃ��Ɛ錾���������Ǝ҂��������B�s�@�s�ׂƂ�����肷�������f�ł���Ƌ����B
���̌��ʁA�ǂ��Ȃ��������āH�@�@������������悤���I�H - �ȃG�l�F�G�l���M�[�̎g�p�̍������Ɋւ���@���̗���
�@�u�K�Ȗ@�K���H�v
�@�ȂA��������������B
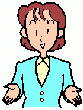 �u���̐ݔ��́����@�̊�ɓK���v�Ƃ����\���Ɉ�a���͊����Ȃ����A�u���̐ݔ��Ɂ����@�͓K���v�Ƃ����\���ňӖ����ʂ��邾�낤���H
�u���̐ݔ��́����@�̊�ɓK���v�Ƃ����\���Ɉ�a���͊����Ȃ����A�u���̐ݔ��Ɂ����@�͓K���v�Ƃ����\���ňӖ����ʂ��邾�낤���H ����ISO14001�Ɋւ����97�N���ɁA�u�K�p�\�Ȗ@�K���v�ł͂ǂ����҂����肵�Ȃ��̂Łu�K�p����@�K���v�Ɨ������邱�Ƃɂ����B
���₪�����ł����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��@���ł��邩��A�u�K�p�\�v�Ƃ��u�K�v�ł͂Ȃ��A�u�K������v���邢�́u�K�p����v�Ƃ����������K�ł��낤�ƍl�����̂ł���B�����Ă���ȗ������Ƃ����l���Ă����B
�{���͂��̂��Ƃɂ��ď����B
���Ԃ�ISO�̍u�߂�����Ă���l��E�F�u�͐��̐��A����
�Ƃ�����������B
�@���ɂ͂��낢��Ȏ�ނ�����B�����Ĕ����K�肪������̂ƂȂ����̂�����B
�����K�肪����@�K���ł��A�����̂��̂����邪�A�ᔽ�҂̎Ж����\�Ƃ��A���P�����Ȃǔɕ��t��̎葱�������X�Ƒ����Ĕ����܂łȂ��Ȃ����ǂ蒅���Ȃ�������A����Ƃ��ǂ蒅�����Ƃ���ł��������锱�����Ȃ����̂�����B�����琢�̒��̐l�X�͖@�����Ȃ��̂��낤���H
������������낤���Ȃ��낤���@���͎��Ȃ��Ƃ����܂���B
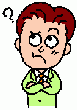 �����A�u���Ǝ҂ͥ���ɓw�߂�v�Ƃ��u�����ͥ���ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ȃ�Ă����̂���������܂��B�Ȃ�ł��w�͋`�����Ă��������ł��B�O�q�̘_���ɂ��ƁA�������������̂�����I�I���Ƃ����Đ�ΓI�`���ƍ��킹�ēK�p�\�Ȃ�Ƃ������Ƃ炵���B
�����A�u���Ǝ҂ͥ���ɓw�߂�v�Ƃ��u�����ͥ���ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ȃ�Ă����̂���������܂��B�Ȃ�ł��w�͋`�����Ă��������ł��B�O�q�̘_���ɂ��ƁA�������������̂�����I�I���Ƃ����Đ�ΓI�`���ƍ��킹�ēK�p�\�Ȃ�Ƃ������Ƃ炵���B�Ƃ����Ă��A���ɂ͂킯���킩��Ȃ��B
����ɂ͂����āA����Ȃ��̂�����I�ɑI������]�n�̖��Ȃ̂��낤���H�@����ȗ����͂Ȃ��������B
�܂��āu�w�͋`���荞�ނ��Ƃ����̉�Ђ̊��o�c�̃��x���������v�Ȃǂƌ�����ƁA����ȗ����ɐ�`�ɓ��ӂ������Ȃ��Ƃ����C�����Ă���B�@
����ɋ`�������傾�Ƃ����Ă݂��Ƃ���Ŏ������͓���ł���A臒l�E���f��̈Ⴂ�̂悤�ȋC������B
���͂��ŋ߂̂��Ƃł��邪�A�^�̔���Ђ�ISO14001�����̂��b������������@��������B�����ʂ���͂��܂�A���܂ł�ISO�̊����Ȃǘb���e�̂ł��邪����
�����Ŋ��@�K���ɂ��Ĕ��ɋ�������Ƃ��낪�������B
���̉�Ђł͋Ǝ킩�炢���ē��R�A�c�Ɗ��������C���ł��邪�A����������ł͂Ȃ��A�r���Ǘ��A�������܂߂������̏㗬�E�����̊Ǘ��A���邢�͎Ԃ̎g�p�ȂǁA�H��Ƃ͈قȂ��Ă͂��邪�����ʂ͂��̂���������ɂ킽���Ă���B�����ĉc�Ƃɂ���������̎��W�`�B�Ƃ����R�~���j�P�[�V���������������ʂƂ��Ă����B
�ǂ�ȋƎ�ł������ʂɊւ��@�K������������c�������炷��̂́A�d�v�ł���̂͂������ł��邪�A�܂����ɍ���ł�����B
�ǂ��ɂ����Ĉ��l���P�ӂ̐l������B�@�����ŐV�N�������̂́A���ۂɋK������@�K�������łȂ��A�r�W�l�X�ɂ����Ċ��p�ł���@�K����K�p�\�Ȗ@�K���ƈʒu�Â��Ă������Ƃł���B ����͂��Ă����āA
����͂��Ă����āA
-
���Ƃ��A���낢��ȏ��i����舵���Ă���̂������
- ���q�l�̏ȃG�l�ɖ𗧂��i�ł���Ǝv����̂Łu�ȃG�l�@�ɊY���v�Ƃ���B
- �e�����T�C�N���@�̋K�����Ȃ��ގ��Ȃ̂Łu�e�����T�C�N���@�ɊY���v�Ƃ���B�@�ӂ��̍l���Ƌt��
���ɂ͂��Ȃ苭���Ȃ������Ǝv������̂������������̂�������
���̂��Ƃ��ƁA�u�����ċK�i�ɂ͓K�p�\���ď����Ă���܂���ˁB���Ђ̖{���Ɩ��ł���c�ƂŖ��ɗ��Ȃ�����ʂɓK�p�\�ł͂Ȃ��ł����B�v �ނ�͈����Ă��鏤�i�ɂ܂���Ă��q�l���ւ����@�K�����A�Ȃ̑��ʂɓK�p����Y���@�K���Ƃ݂Ȃ��Ă���̂��B
�ނ�͈����Ă��鏤�i�ɂ܂���Ă��q�l���ւ����@�K�����A�Ȃ̑��ʂɓK�p����Y���@�K���Ƃ݂Ȃ��Ă���̂��B�����ăr�W�l�X��i�߂��Łu���q����A�����q�����܂���v����Ȃ��āu���q����A���̏��i�͂��q�l�ɓK�p�����@�K���ɖ��ɗ����܂���v�Ɣ��荞��ł���̂ł���B
���������Ƃ����ׂ����n�C���x���Ƃ����ׂ����A�������Ǝv�����B�܂��Ɏ��ł͂Ȃ��U�߂ւ̊��@�K���̊��p�ł���B
��������u�ԁA����10�N�Ԏv������ł����u�K�p����@�K���v�Ƃ��������͌�肾�����Ǝv���܂����B
ISO14001�K�i�̐���҂��{���͂ǂ̂悤�ȍl�����wthe applicable legal requirements�x�ƕ\�����̂��킩��Ȃ��B�������AISO14001��2004�N�ɉ��肳��A�u����`�F���[�s�b�L���O�͂��߂�v�A�u�{���Ɩ��łȂ��Ƃ��߂���v�ƌ����Ă��鍡���݁A�{���Ɩ��𐄐i����ɓ������Ė��ɗ����̂Ȃ�A�蓖���莟��݂��ISO�����Ɏ�荞��ŗǂ���Ȃ����H
�������c�Ɛ�������Ă���g�D�ɂƂ��āA��舵���Ă��鏤�i�Ɋւ���d�v�ł���A��������W���̌n�����c�ƃ}���ɋ��炵���H�������т��o���Ȃ��ƁA�s��o�ςł͔e�҂ƂȂ�Ȃ��ǂ���ł͂Ȃ������c�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
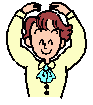 �Ȃ�K��������@�K���ł͂Ȃ��Ă��A���������Ŗ��ɗ��@�K���́u�K�p�\�Ȗ@�K���v�ł���A�����ɗ��p���邱�Ƃ́u�ǂ̂悤�ɓK�p���邩�v�ł���A�@�K���𗘗p�����̔���@�������邱�Ƃ́u�͗ʂ���������v���Ƃł���A������Ȃ�ӂ�\�킸�����Ȃ��W�����W�������i���邱�Ƃ́u��E���Ȃ����߂̉^�p�v�ł���ɈႢ�Ȃ��B
�Ȃ�K��������@�K���ł͂Ȃ��Ă��A���������Ŗ��ɗ��@�K���́u�K�p�\�Ȗ@�K���v�ł���A�����ɗ��p���邱�Ƃ́u�ǂ̂悤�ɓK�p���邩�v�ł���A�@�K���𗘗p�����̔���@�������邱�Ƃ́u�͗ʂ���������v���Ƃł���A������Ȃ�ӂ�\�킸�����Ȃ��W�����W�������i���邱�Ƃ́u��E���Ȃ����߂̉^�p�v�ł���ɈႢ�Ȃ��B�܂���ISO14001�K�i�A�����ɐs����̂ł͂Ȃ����낤���H
����͏�k�����ł͂Ȃ��A�{���ł���B
���͋K�i�̐��݂̐e�̈�l�AISOTC207�̈ψ��ł��鎛�c�@�������ISO14001�K�i�̍u���Łu�K�p�\�łȂ��A�K�p�����ƖĂ����ׂ��������v�ƌ���Ă���ꂽ�B�i2006/1/26�j
�������A���̌����������Ⴉ�猩��wthe applicable legal requirements�x���u�K�p�����@�K���v�Ƃ��u�K�p����@�K���v���邢�́u�K�Ȗ@�K���v�łȂ��u�K�p�\�Ȗ@�I�v�������v�Ɩ��̂́A���̂������[�ǂ݂ő吳���������̂ł͂Ȃ����낤���H
�����A���������萔�̋l�ߏ������l�ߌ���Ċ����ł��ˁB
�i���ł��낤�Ɗ��ł��낤�Ƃ��̑��̐V�QISO�ł��낤�ƁAISO�Ȃ�ĉ�Ж{���̎d�g�݂ɓ���������A�����ǂ��s�v�A�R���@�ւ��s�v�A��������̂Ɠ�����������O�̂��̂ƂɂȂ�A���Ղ�łȂ��Ȃ�̂������Ƃ���������ׂ��p�ł��낤�B
�����v���Ɓu4.3.2�K�p�\�Ȗ@�K���v�Ɍ��炸�AISO�K�i�̏�������A�l�b�N�X�܂łǂ̍��Ԃ��A�z���͂������܂���������ǂݎ߂���ǂ݁A���������߁E�g����߁A���܂ł���Ԃ��Ď����i�����j�Ɋ��p���ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���H
�K�i�K�����Ƃ����ׂ͖̂������z�Ŕ��f����̂�������Ȃ��B
�{���̋��P
�����ɗg��������́A�K�i�̐��������߂łȂ��ƌ����邩������Ȃ��B
�R���@�ւ̂��ڂ��ڂ��ƌ�����������Ȃ��B
�ł��ˁA��Ђ�ǂ����A���ɍv������Ȃ�ISO�K�i�̑̌�����Ȃ��ł����H
�ŋ߁A�^���[�����O���X�g�ł��̌��t�ɍĂтЂ����������̂ł��̈ꕶ���������߂��B
Yosh�l�Ƃ̂��Ƃ���A�b�v�������܂��i2006.04.06�`10�j
- Yosh�l
- �Ƃ����l�A�wthe applicable legal requirements�x�̌����Ă��镶�͂͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��܂����H
- ����
- ������̕��͎͂��̒ʂ�ł��B
4.3.2 Legal and other requirements
The organization shall establish, implement and maintain a procedure(s)
a) to identify and have access to the applicable legal requirements and other requirements to which the organaization subscribes related to its environmental aspects, and
b) to determine how these requirements apply to its environmental aspects.
The organization shall ensure that these applicable legal requirements and other requirements to which the organization subscribes are taken into account in establishing, implementing and maintaing its environmental management system. - Yosh�l
- ���̏ꍇ�ɂ́u�K�Ȗ@�I�K�v�����v���D�܂����Ƃ������܂��A���B���łɒN�����u�K�p�\�Ȗ@�I�v�������v�ƖĂ�����̂����\����Ă���̂ł��ˁH
- ����
- ISO�K�i�̌����͉p��ƃt�����X��ł����A�e���͂��̂܂܂ł͉^�p�ł��܂���̂ŁA�����̍��̌��t�ɖ܂��B
���{�̌�����̌��t�͊Y�����镔���͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B
4.3.2�@�I�y�т��̑��̗v������
�g�D�́A���̎����Ɋւ��菇���m�����A���{���A�ێ����邱�ƁB
a)�g�D�̊����ʂɊW���ēK�p�\�Ȗ@�I�v�������y�ёg�D�����ӂ��邻�̑��̗v����������肵�A�Q�Ƃ���B
b)�����̗v��������g�D�̊����ʂɂǂ̂悤�ɓK�p���邩�����肷��B
�g�D�́A���̊��}�l�W�����g�V�X�e�����m�����A���{���A�ێ������ŁA�����̓K�p�\�Ȗ@�I�v�������y�ёg�D�����ӂ��邻�̑��̗v���������m���ɍl���ɓ���邱�ƁB - Yosh�l
- �Ƃ����l�A�ǂ������͓��{�ꂪ�����ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�u�K�p�\�Ȗ@�I�v�������v�̈Ӗ����鏈�͉��Ȃ̂ł��傤���H
�t�ɍl���āh�K�p�s�\�Ȗ@�I�v�������h�����邱�ƂɂȂ�킯�ŁA����ł͖@�I�v�������͖@�Ƃ��Ė��ɗ����Ȃ��悤�ɂȂ�܂��H - ����
- �ǂ������͓��{�ꂪ�����ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B
����Ȃ��Ƃ͂���܂���B���̈ꕶ���Ƃ��Ă����E�̓��{�l����������Ȃ̂ł�����B
�t�ɍl���āh�K�p�s�\�Ȗ@�I�v�������h�����邱�ƂɂȂ�킯�ŁA����ł͖@�I�v�������͖@�Ƃ��Ė��ɗ����Ȃ��悤�ɂȂ�܂��H
�m���ɂ����l����Ƃ����Ƃ����v���܂���ˁB���{���͂�K�ł͂Ȃ��̂ł��傤�B
�����������Ɋւ���@�K�������I�Ƃ������͂����������Ƃ������܂��B�@���͎��Ȃ����B�ꌾ�ł��݂܂��B�Ȃ��������Ȃ̂��H���ꂪ����Ƃ���������Ȍ����̂��ׂĂł͂Ȃ��ł��傤���H
KK�l���炨�ւ���܂����i06.04.11�j
����͎��͗����Ƃ�������������܂��ˁB
|
KK�l�A���w�����肪�Ƃ��������܂��B
�H���̋����\�ŌR���̔h���͈͂����߂Ă���̂ł����I�H
�C���p�[����쑾���m�̓��X�ɔh�����ꂽ���{������������Ȃ�Ƃ����ł��傤���H
�R���Ń��W�X�e�B�N�X�i��⋁j�͔��ɏd�v�ł����A�����Ă̓��{�R�́u�n�d���i�����傤�ւ��j�������Ȃ�A�`���E�`���g���{�����̂����v�ƕ̂����ł��B
���ꂶ�Ⴀ�A�키�O�ɔ��z���炵�ĕ����Ă܂���
�m�����l���炨�ւ���܂����i06.04.16�j
�S�^�P�T�X�V�@�x�������l�Ƃ̂��Ƃ��q�����܂����B ����l�̒m�I�ȑΘ_�A�����[���q���v���܂����B �m���ɁA���ׂ��܋��̒ʂ�A�u�@���͎��Ȃ����v�ōςޘb���Ǝv���܂��B ������u�K�p�\�ȁv�ȂǂƁA�g�D�C���̕\���i�a��j�ɂ��Ă��鎖���A�K�ł��������ǂ����A�傢�ɋ^�₪�c��܂��B �����wapplicable�x�͋��炭�wapplication�x�i�K�p�A���p�j�̔h���ꂾ�ƍl����A���ʂɖw�K�p�\�x�ƌ�����Ԗ�������̂����m��܂���l�E�E�E �����u�h�r�n�v�͑����Ɩ��ŗ���ł���̂ł����A���������X�O�O�P���P�S�O�O�P���u�����v�u�ǂ��܂Łv�u�ǂ̂悤�Ɂv�ɂ��Ă͂���Ӗ��A�u���P���v�I�Ȕ��z�ŋK�肵�Ă��܂��B�i�h�r�n�͈�ʓI�ɂ́w�������x�Ɋ�Â��Ă���Ǘ���@���Ɨ�������Ă��܂����E�E�E�j �Ⴆ�u�����������ʁv�ɂ��Ă�������u���肷��E�E�����ɂ������菇���m�����A���{���A�ێ����邱�Ɓv�Ƃ����v������Ă���킯�ŁA�����őg�D������u���ʁv�ӓI�Ɂu�����������ʁv����O���Ă��܂��댯���ɂ��ẮA�g�D�̃������ƐR�����̗͗ʂɁA�ς˂��Ă��܂��E�E�E�E(��) �^�C�v�~�X�i�H�j�Ǝv����ӏ�������������܂��̂ŏC���肢�܂��B |
�m�����l�@���w�E���肪�Ƃ��������܂��B
���̉p��͂��o���o���ł������܂��B�����C���������܂����B
�m�����l�̂悤��ISO�Ɋւ���Ă��邱�Ƃ��B���Ă���i�H�j���������̂ł́A����͂����Ƃ������ď����Ȃ��ƐQ��������ꂻ���ł��B
�C�����˂E�E�E
����ܗl���炨�ւ���܂����i06.04.16�j
���ׂ��܁@����܂ł� �u�����́A�����ƁA�p�ꂪ�����ł��B�v�ƁA�������������̂������Ȃ�ł��ˁB �������A�Љ�ɏo�āA���₨���Ȃ��ɉp��ɌW����Ă���ƁA����ĂĂ���������̂ł����A�A���R�[���Ŕj�s�����ꂽ���]�ł́A���͂��x��ł���܂����B ���āA�p�����͂��߁A�O���ꂪ�����ȗ��R�́A�Ȃ�ł�����ł��u�t�v�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��̂ł��B�P��̕��ѕ����t�̂悤�Ȋ��������܂����A�l�������t�̂悤�ȋC�����邱�Ƃ����X����܂��B�́A�O�ԂƂ����u�n���h�����t�v�Ƃ�������ɁE�E�E�B �Ƃ���ōŋ߁A�u�����|��v�Ȃ���̂��Aweb��ł������Œ���Ă���̂ŁA�g�������Ƃ�����܂����B����́u���v�܂��ˁB�����v���Ă���u�t�v��@���ɔ��f���Ă���悤�ŁB ���ׂ��܂Ƃ̂����̗l�q�����āA����Ȃ���t�g�v���Ă��܂��܂����B �Ƃ���ŁA�u�X�[�v�̗�߂Ȃ������v���A�u�߂��v�ƌ����Ӗ��̂ق��ɁA�u�H���⋋�̉\�ȋ����v���甭�W���āA�u���\�����v�܂ł��Ӗ�����Ƃ́E�E�E�B�m��܂���ł����B |
����ܗl�̘_�_�����X�ł����A���t����������Ȃ�E�E�E
���Ƃ͂�����D���Ȃ����Ƃ�������܂���B���͕����D���Ƃ����l�́A���ł͂Ȃ����ꂪ��Ȃ̂������ꂸ�A��ł��������w�ɂ�������ł����h���Ƃ͌���Ȃ��悤�ȁH�H�H
���_�A�|��\�t�g�Ŏv���o������܂��B����10�N�ȏ�O�ɉ��\�y�[�W�����鏑�ނ̖|����Ǝ҂ɗ���A�����|��\�t�g���g���Ă���Ƃ����Ă܂����B�\�t�g�ŊY������P��𗅗��Ă����l�͂ʼnp��̕��͂Ƃ��Ēʂ���悤�Ƀ��t�@�C�����Ă����̂������ł��B�܂��˂�����߂�̂Ɏ�h���C�o�ł��낤�Ɠd���h���C�o�ł��낤�Ɩ�ڂ��ʂ��������Ȃ�����������ق����悢�̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤��
�b���܂��ς��܂��āA���̖{�œǂ��Y��܂������A�C�M���X�������V�A���̐H�������āu����Ȃ��̂�H�ׂĂ���Ȃ�푈����߂�v�Ə����Ă������C�����܂��B�܂Ƃ��Ȃ��̂�H�ׂ��Ȃ��Ȃ�푈����Ӌ`���Ȃ��Ƃ������ƂȂ�ł��傤���H
�j���[�M�j�A�̓��{���A�C���p�[���̓��{���ɕ���������Ȃ�Ă������H�@�Ȃ�Ę_���Ă��Ӗ�������܂���ˁB
���߂č�����{�̊�@������A�키�l�ɂ͍ō��̎x�����������Ɗ肢�܂��B���_�I�ɂ������I�ɂ�
���l�T�}�l���炨�ւ���܂����i10.02.01�j
���̑��v�������̉��߂ɂ��āH ���̑��v�������̃K�C�h���C���́H �h�r�n�P�S�O�O�P�̔F���擾���Ă����Ђ́A�h�r�n�Ǘ����ɏ������Ă��܂��B���Ђł́A���̑��v��������o�^��ɓo�^���ĊǗ����Ă��܂����A�o�^������e�̊�����m�ł͂���܂���B���f��ɂ��āA�����Ē����������[���������܂����B ��P�F����悩��A�����̊����j�ւ̋��͈˗��������͂��A��̏��ɓ�ĕԑ������B ��Q�F����悩��A�����̊����j�ւ̋��͈˗��������͂��A���ӏ��ɓ�ĕԑ������B ��R�F����悩��A�����̊����j�ւ̋��͈˗��������͂��A����攭���H���ɂ������̓I�A�����E�T�[�r�X�ɑ��鏇��ɂ��Ẳ��ɓ�ĕԑ������B �P�`�R�ŊY������̂́H�܂����A�S�āH �܂��A�̓��e�ɂ����܂����A����]���́A�ǂ��܂ŕK�v�Ȃ̂ł��傤�H |
���l�T�}�l�@���ւ肠�肪�Ƃ��������܂��B
�펯�I�ɍl���āA���Ђ̕��j�ɋM�Ђ��]���`���͂���܂���B�����v�������e��Ђł����Ă��A�����܂ܓK�p���邱�Ƃ͉�Ж@�ɒ�G����͂��ł��B
ISO14001�̃A�l�b�N�X���u�g�D����������L����Ƒ̂̊����j�̘g���ŁA���A���̏��F�āA�g�b�v�}�l�W�����g�ɂ���Ē�߂��Ƃ悢�i�ꕔ���j�v�Ƃ���܂����A����͂������K�{�����ł͂���܂���B
�܂�A�����Ȃǂ����l�̊����j�������Ă��Ă��A����͌������̓s���ł����āA��Ђ��]���`���͂���܂���B
����ɂ��Ă͈ȑO�����܂����̂����������Q�l��
������ɂ��Ă��A�����j�������������̂́A���̑��̗v�������ɒl���Ȃ��Ǝv���܂��B�Y�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�l���Ȃ��̂ł��B�����ĉ���������ǂ����킩��Ȃ��̂ł�����A����ɏ]���ĂȂɂ����悤������܂���B
����Ĉ�ԖڂƓ�Ԗڂ͂��̑��̗v�������ł͂Ȃ��ƍl���܂��B
�O�Ԗڂ́u�H���ɂ����ċ�̓I�v���v������A����͂��̑��̗v�������ƂȂ�܂��B
�����H���Ή��ŌX�̗v�����قȂ�̂����ʂł��B���̏ꍇ�A�u�H���Ȃǂɂ�����q��d�l�v�����̑��̗v�������Ƃ��āA�X�̍H���ɂ�����v���͓s�x�Ή��Ƃ��Ă��܂����B
�lj��ł��B
����]���ł����A���Ђɂ��둼�Ђ̂ɂ���A�����j������Ă��邩�H�Ƃ������Ƃ͔��R�Ƃ���OK/NG����͕s�\�ł��傤�B
����]���͋�̓I�Ȃ��Ƃ��A�������邱�Ƃł���A���ꂪ�ł��Ȃ����̂͑ΏۊO�ł��B
����{�@�Ȃǂ�����]�����悤�ƌ����͖����Ƃ�������
���������Ă���̂ł͂���܂���B�Q�c�@�@�����Ȃǂ����Ă��������B��{�@�͍������K��������̂ł͂Ȃ��A�����K��������̂ł��B��{�@�Ɋ�Â��ʖ@�𐧒肵�A��������������炷��̂ł��B
���j����{�@�Ƃ��Ȃ��悤�Ȃ��̂ł��B
���l�T�}�l���炨�ւ���܂����i10.02.03�j
���p�l ���X�̂��L��������܂��B��������₳���Ē������h���l�T�}�h�ł� �����j�ւ̑Ή��ɂ��ẮA����������Ă���ʂ�Ɗ�������܂����B ��̗�悤�ȕ\���ƂȂ��Ă���ꍇ�����l�ɁA���̑��v�������ɒl���Ȃ��Ɣ��f���Ă����Ȃ��ł��傤���H�i�����͒l���Ȃ��ƍl���Ă��܂��j ���̑��v�������Ɋւ���A�T�O���ǂ̂悤�ɑ���������̂ł��傤���H ���f��Ƃ��Ă̎w�W��T�O��������������肢�������܂��B �P�D��̗� �Q�D�܂��A���L�@�`�E�ɂ����ĊY�����Ȃ����̂͂���܂����H �����́A �@�̏ꍇ�Y�����Ȃ��̂ł͂ƍl���܂����H �A�`�D�͊Y���B �E�͊��Ō������̑��v�������ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A���炷�ׂ����̂Ƃ��ē��l�ȊǗ������邱�Ƃ͂����̂ł͂ƍl���܂��B ���ӌ��X�������肢�\���グ�܂��B �L�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�| �@����̊�{�_�ł̏����ɂ��āi�ڋq�v���j �E�_��̗��s�Ɋ֘A���Ċ��j��ɂȂ��鋰�ꂪ����ꍇ�́A���j���h�~���邽�߂̏\���ȏ��u���u���� �E�_��̗��s�Ɋւ��A�����A�p�����A�ޗ��̖��ʂ̔r���y�яȃG�l���M�[�A�Ȏ����A���T�C�N���ɓw�߂� �E���ނ̔[�����̑��̌_��ɂ�����A�@�߁A��Ⴑ���Ɋ�Â��ʒB�A�w���A�w���̏���@�@���Q�K�������̎g�p�֎~ �E�����s�̉ߒ��y�ђ��B�i�ɂ��āA���ւ̕��ׂ��y������悤�w�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@���̂悤�ȏ����́A���̑��v�������ɊY���H �A�O���[�����B�K�C�h���C���̏���i�ڋq�v���j �B�qoHS�w�߂̋֎~�����̊܂܂Ȃ����i��[�i����(�ڋq�v���j �C���{�����ԋK���̊o���i�m����/Sox�Ɋւ���s���̋K���ɑ������A�ʂ̌ڋq�v���j �D�u�|�������r�t�F�j�[���p�����̓K���ȏ����̐��i�Ɋւ�����ʑ[�u�@�v�Ɋ�Â��ۊǏ��͏o��(�s������̗v���j �E�����Ԏg�p�Ǘ����ѕ��i�s������̗v���j �ȏ� |
���l�T�}�l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B
�����Ȃ��Ƃ������܂��ƁA���l�T�}�l�Ǝ��̔F���Ƃ��������o�Ƃ������A������ƈႤ�Ȃ��Ǝv���܂��B
���͊��@�K���Ƃ������̂����݂���ƍl���Ă��܂���B��Ƃ��邢�͑g�D�ɂ����āA�K������̂͂��̒芼���邢�͎��ƖړI���������邽�߂̕��j�ł���A����Ɋւ��K������͂̈ӌ���v�����ƍl���Ă��܂��B
����ɂ̓Z�N�n��������ł��傤���A�ٗp��A�ߗЉ�ւ̍v���i�����b����t�j�A���̑��������ł��B
���̂Ƃ��A���Ɋւ��K�����ǂꂾ�Ƃ킴�킴���肷��܂ł��Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B
���݁A�͂邩�n���̗�����Eup��Rohs�Ȃǂ����{�̖@�K���Ɠ����A���邢�͂���ȏ�ɏd�v�Ȉʒu�Â��ɂ���܂��B���ꂪ���ԋK�i�ł��낤�ƁA�O���[���s�[�X�̈ӌ��ł��낤�ƑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂͑Ή����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�����ƁA����ȗ��������Ɗ��������Ǝv����̂ŕʂ̗�������܂��傤�B���N�O�A���{�̊�Ƃ����[���b�p�̓Ƌ֖@�Ɉᔽ���Ă���Ɖے����𐿋����ꂽ���Ƃ��o���Ă���ł��傤���H
���̊�Ƃ̓��[���b�p�ɗA�o���Ă��܂���ł����B���[���b�p�ɗA�o���Ă��Ȃ��ŁA�Ȃ�Ń��[���b�p�̓Ƌ֖@�ᔽ�ɂȂ��Ă�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���H
�ςɎv���܂��H
�v����ɁA�A�o���Ȃ��Ƃ������f�ɂ���ă��[���b�p�Ŋ�Ƃ̎��R�������N���Ȃ��������߂ɁA�s�����Ƃ��@����Ƃ�����Q�������Ƃ́A���̊�Ƃ��A�o���Ȃ���������E�E�Ƃ������ɃX�o���V�C�_���������悤�ł��B���ۂɂ͗����\������̂ł��傤���ǁE�E�����������Ƃ́A�������ɓ������āA�ǂ�ȋK��������̂��H�Ȃ�čl���Ă����傤���Ȃ��̂ł��B
���̊�ƁA���邢�͑g�D���ړI���������邽�߂Ɏ��Ɗ������s���ɂ������āA�����Ȃ�K������̂���c�����A�����đΉ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�����Ă���͖@�������łȂ��A�s��̐���������ł��傤���A���q�l�̗v�����d�v�ł��B
�A���A���q�l�͐_�l�ł��Ƃ͗ǂ������܂����A���ۂ͖@���͓�����Ȃ����A���q�l��I�Ԃ��Ƃ͉\�ł��B�����Y�͖@�������ꂽ�悤�ł����E�E�����炻�̑��v�������ɂ��ẮuISO14001�F2004�@4.3.2�@�g�D�����ӂ���v�ƌ��肵�Ă���킯�ł��B
�Ƃ����̂����̔F���ł���A���̔F���Ɋ�Â��ߋ�19�N�A���͐R�����Ă��܂����B
�����đ��Ђ̎w�����s�����́A���̃X�^���X�͂͂����Ă��܂���B
�Ȃ��Ȃ�A���ɂƂ��Ċ�ƂƂ͋N�Ƃ̗��O���������邽�߂ɑ��݂��Ă���̂ł���AISO�Ȃ�Ă��̊��������������邢�͍���������c�[���ɉ߂��Ȃ�����ł��B
�Ƃ����A���������͌����Ă����ł��傤�B
���̉��l�ςł����A����͊��Ɋւ�邩��E�E�ł��Ƃ��A����͊O�ז@�Ɋւ�邩��E�E�Ȃ�Ę_�͑S���Ӗ��������܂���B
���Ƃ𐄐i���Ă����ɓ������đΉ�����K�v�����邩�A�l������K�v�����邩�A�Ƃ����ϓ_�ŕ]�����Ή����邾���̂��Ƃł��B
���l�T���l�̒��ꂽ���܂��܂Ȏ���ɂ��āA��������Ȃ���r�W�l�X���p���ł��Ȃ��A��Ƒ����ɂ������A���V���l�̉�������Ȃ��Ƃ����Ȃ�Ή����K�v�ł��B
���q���u�E�E�����Ă���v�Ƃ����Ȃ�A�@��������Ǒ��ɔ������A������Ή����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Ή����邾���̂��Ƃł��傤�B
��������̑��̗v�������ƌĂԂȂ�Ăׂ悢���A�����ł͂Ȃ��J�e�S���[��݂���Ƃ����Ȃ炻���ł����Ƃ��������̂��Ƃł��B
��ISO�̂��̗v�������ł͂Ȃ����A�c�ƓI�ɂ͑Ή����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Č������͏��b�ł��傤�B���������Ă��̃t���[�Y���l���ď��Ă��܂��܂����B
���������܂��āA�����O�^�Ђ̐R���ɗ�����܂��āu�������H�L�^���H�v�Ȃ�Ę_������܂����B
�R�����Ƃ��̉�Ђ̒S���҂��c�_���Ă��܂������A���ɂƂ��Ă��̂悤�Ȑ_�w�_���͖��Ӗ��Ƃ������A�S������܂���B
�Ǘ����Ȃ���Ȃ�Ȃ���A���Ђ̕����ł��낤�ƁA�L�^�ł��낤�ƁA�ЂƂ��܂��쐬�������̂ł��낤�ƁA�����ƊǗ������邾���ł��B
���܂�Ƃ������A�S�R�ɂȂ��Ă��܂��A���̓��l�T���l�̂����₪���ɂƂ��Ă��܂�Ӗ����鎿��Ƃ͍l�����܂���B
���l�T�}�l���炨�ւ���܂����i10.02.05�j
�����W�O�O�Ǘ��l�@���p�l ���J�Ȃ��L��������܂����B ���p�l�̂���ǂݐi�ނ����ɁA�}�l�W�����g�V�X�e���̖{�����Ă����悤�ȋC�����܂��B �����̕i�����̂Ƃ����Ă��A���F��ƃ}�l�W�����g�̂����ꕔ�̑��ʂł��������̂ł���ˁB ���܂�ɂ������Șg�g�݂ōl���Ă������ƂɁA�Ԗʂ��Ă��܂��B ���ہA�u���p�l�v�̂�������邱�Ƃ��d�g�݂Ƃ��ĉ^�p���Ă�����A�S�����͔������Ȃ��ƍl���܂��B ��Ɗ����������ŁA�W����@���i���̑��̋K�����܂߁j���A���炵�Ă������Ƃ͓�����O�̂��Ƃł��B �������Ȃ���A�����I�ɂ���m�ɂ��Ή����Ă����Ђ͂ǂ�قǂ���ł��傤�H ������肪���������̂ɑ��āA���ł��Ă�̂������̂悤�ȋC�����܂��B�i�s�ˎ����N��������Ɓj �����ŁA�Ή����l����Ƃ��h���X�N�h�Ɍ��������Ή��Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B ��̎w�W�Ƃ��āA�u��Ђ��^�c�i�����j���Ă������߂ɕK�v���H�v�Ƃ������Ƃ������Ă��܂����B �h�r�n�𐄐i���Ă����҂Ƃ��āA�h�r�n�̃}�l�W�����g�V�X�e���������Ƒ傫�Ȏ��_�ő����A�����̖{�������������Ή����o����悤���i���Ă��������Ǝv���܂��B �����W�O�O�A�����Ƌ����������Ĕq�������Ē����Ă��܂��B ���ꂩ����������X�������肢�������܂��B |
���l�T�}�l�@���x���肪�Ƃ��������܂��B
���f�肵�Ă����܂����A���������Ƃ��ߐ悪�f���炵���Ƃ������Ƃ͂���܂���B
�����A�i���Ƃ����Ƃ���ň͂�ł��܂�Ȃ��ŁA��Ƃ̖ړI�Ƃ����ϓ_�ōl����ׂ����Ƃ������ƁA�����Ă����l����Ɗ��̂��̑��̗v�������ɊY�����邩���Ȃ����Ƃ������ƂłȂ��A��ƂƂ��Ă̋`���ƐӔC�Ƃ��čl������̂����瓚���͂���Ƃ������Ƃł��B
�����\���܂��ƁA����15�N���炢�O�A�ȑO�̉�ЂōH��Ŋ��Ǘ������Ă����Ƃ��A���̂悤�ȍl���͂���܂���ł����B
���낢�뎖������Č��E��ɗ��ꒅ���A�����ŃR�[�|���[�g�S�̂�{�ЂƂ�������Ō���悤�ɂȂ��č��̍l�������悤�ɂȂ�܂����B�l�ԋ�J���Ȃ��Ɗw�Ȃ��悤�ł��B