だから審査登録することの最大のメリットというか本来の目的は、第三者というか外部の者に対して、基準(規格)に適合(満足)していることを保証することである。しかし、1990年代初頭ならいざ知らず、21世紀の現在では審査登録機関が数多くあり、審査機関同士の競争はきわめて激しい。だから『「何かの基準」に適合していることを確認しました』というだけでは面白みもない上に他の審査登録機関と差別化ができず、審査ビジネスにおいて注文をかちとり勝者となることは困難な状況である。そのために各審査機関は審査ビジネスにおいてコンペティターにうち勝つために、単に審査するだけでなく、経営に寄与するなどの付加価値を提供しますと宣伝している。適合していない場合、わざわざ外部に発信することはない審査機関そのものが第三者なのだから、第三者の使い方がおかしいなんて言わないでください。
宣伝文句の具体例を挙げてみよう。
- これらはすべて雑誌やウェブサイトに記述してあるものである。どの審査機関かお分かりになる方もいるだろう。
- 組織のパフォーマンス向上に寄与します
これはすごい!ぜひともわが社の省エネや廃棄物削減の指導をお願いします。 - 経営に役立つ審査をします
経営コンサルタントはもういりませんってわけだ
- 組織のビジネスに付加価値を与えます
付加価値って儲けってことですよね? 組織の利益拡大を保証してくれるのかしら? - 付加価値のある審査をします
何が付加価値なのか? 謎 - 競争優位性をサポートします
サポート=支援=コンサルタント? - 他社に比べローコストです
これは合い見積もりをとれば簡単に比較でき検証可能である - 質の高い審査員を派遣します
審査員の質とはなんだ? 力量とは違うらしい。
他社の審査員の質より高いことはなんで証明するのだろう? - 顧客満足の審査をします
ちょっと待てよ? 貴社の考える顧客満足って何ですか?
その前に貴社の顧客とは誰なのだろうか? 審査登録の顧客とは審査を受ける組織ではなく、一般消費者や世間一般なのであるが・・・
だって当社は審査の質が悪いですよというより、当社の審査の質は他社より良いですよという方が、言うほうも聞くほうも気持ちが良いではないか?
でも、すべての審査機関が「他社より審査の質が良いです」というのはちょっと不思議というか、おかしい気がする。
1980年代日本では国民全部が中流と言われた。そりゃ大間違いである。全員が中流になれるわけではない。誰かが上流、誰かが下流になるのは現実である。 ちなみに21世紀に日本は格差社会になったというのは間違いだと思う。そう言えるのは、20世紀に上の方にいて今現在低下した方であって、昔も下のほうにいた私のような者は格差が広がったのかどうか気付かないのだから判断するすべはない。 |
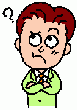
|
自動車の燃費というのは自分勝手に走行条件を決めるわけではない。法令で一定の条件を決められていて、その走行パターンでリッターあたり何キロ走るのか比較するのである。はたして審査の質とはいったいどのような指標で図るのだろうか?
ちょっと考えると、私なら次のような条件を思いつく
審査を受ける組織に一定条件の不適合を設定しておく、そして各審査機関の代表チームがその組織を審査して、設定しておいた不適合をいくつ見つけるか、同時に判定を誤って適合を不適合とした件数で評価すればよいだろう。
しかし、待てよ、
どの審査機関にも数十人から数百人の審査員がいる。審査機関を代表するチームとなれば、えりすぐりが出場するのは目に見えている。じゃあ、全員が出場すればよいのだろうか? ちょっとそれじゃ、大変だ。
各審査機関から審査員をランダム抜き取りし、チームを編成させて審査競争をすればよいのだろうか?
 | |||
 | 1 |  | |
| 2 | 3 |
現在の認定審査と同じじゃないか?なんて言ってはいけない。これは審査ではなく競技である。単に審査の適合・不適合ではなく、点数がついて順位がつけられるのだ。
しかし、ここまで来て気がついたことがある。
審査はIAFの基準に基づいて行われる。それ以上でもなくそれ以下でもない。
とすると、あるべき審査は隠された不適合をすべて検出し、適合を不適合とする勇み足、いや違ったあわて者の間違いがあってはならないことになる。万が一あわて者の間違いがあれば異議申し立て事項だから。
するとこの審査競技大会は全員が満点を取らねばならず、満点以外は不合格になる。
アッツ、するとやはり認定審査と同じになってしまう。
いや、私の勘違いであった。すべての審査機関はこの評価方法ではすべて満点になる。そうに違いない。
審査の質というのはそういった不適合を見つけたとか見逃したという当たり前のレベルの低い話ではないのだろう。
そもそも審査の成果物はなんだろうか?
認証証の提供ではない。
簡単である。研究開発の成果物は研究報告書である。じゃあ審査のアウトプットは審査所見報告書ではないか。審査の質を比較するならば、審査所見報告書の品評会を行えばよろしい。
ふつうの方は長年ISO事務局を担当していても、大抵はひとつの審査機関としかお付き合いはないだろう。途中で審査機関を換えたとしてもまあ二つ三つである。同じく、審査員の方でもほとんどの方は、ひとつの審査機関か審査機関を替わってもせいぜい2社とか3社だろう。だから所見報告書の様式も二通りとか三通りしか知らないことになる。
私は品質と環境双方で複数の審査機関とお付き合いしてきた。また同業者から相談など受けて、私が対応したことのない審査機関の所見報告書も見る機会がある。その結果、各審査機関の所見報告書の形式・内容は多種多様であることに気がついた。同じ審査機関でも、日本と外国では組織に提供する所見報告書の形態が異なることもある。
じゃあ、各審査機関の成果物である所見報告書を比較して順位付けしようではないか?
各社の所見報告書が、IAFのガイド(まもなくISO17021になると聞く)と引用規格などの審査基準に適合しているか否か、所見の適切さあるいは的外し具合、報告書の文章に品格があるかないか(あまり関係ないかもしれない)など、審査項目を定めておいて評価すればよい。
誤解を恐れずに申し上げるが、この品評会の審査員は、所見報告書の内容を評価する以前に、文章が国語として判然としないもの、理屈がおかしいもの、意味のわからないものなどなどに出会うことを保証する。困ったことだがそれが実情である。それには多くの事務局の方の同意を得られると考える。
まず所見報告書といっても一様ではなくそのボリュームからしてきわめて開きがある。A4サイズで3ページくらいの報告書しか出さない審査機関もあるし、50ページもある報告書を組織に提出するところもある。
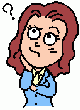 量が多ければ良いなんてことは言わないが、3ページや4ページでは経営に寄与する提言を書くには足りないのではなかろうか?
量が多ければ良いなんてことは言わないが、3ページや4ページでは経営に寄与する提言を書くには足りないのではなかろうか?  だって、報告書の文字数が全部で2000文字もないのだ。
だって、報告書の文字数が全部で2000文字もないのだ。
そしてそのわずかな文章が、経営にどのように寄与するのか?ぜひ知りたいものである。
しかし待てよ、審査所見には要求事項の各項目について適合・不適合を表明しなければならないし、かつそのエビデンスを明示しなければならないように記憶している。それだけ書くにも2000文字では足りないような気がするのだが・・
あるいは経営に寄与するというのだから、どのような面においていかほど経営に寄与したのかを評価し判定するという見地もある。
経営に寄与するというのだから、そのような経営層・管理者層へどのようなインプットをしたのか? 適切であったのかを評価することも考えられる。
しかしこのときの判断基準として何を用いるのだろうか?
前に述べたように審査機関の審査の質競技の基準はIAFガイドをはじめとする公知のものに限定されるのだから、そのようなコンサルともいえるような経営への提言を測る基準はないし、そのような提言自体が審査基準に反するような気がする。
いろいろと考えると結局、あるべき審査の質とは、経営に寄与するなんてものではなく、客観的に定められた基準に対しての適合審査ではないかという気がする。
しかし、浅学でボケのはじまりつつある私のことである。各審査機関は、私の考え付かないことを考えてらっしゃるのに違いない。ぜひ、審査の質の尺度と指標をお教えいただければ幸いである。
ぜひともお便りを期待しております。
本日の疑問
各審査機関が質の高い審査を提供しているならば、負のスパイラルはありえないだろう。
負のスパイラルどころか現実に、審査機関の認定取り消し、認定停止があるということは、質の高い審査を提供していないということなのだろうか?
うそ800にもどる
しかし、ここまで来て気がついたことがある。
審査はIAFの基準に基づいて行われる。それ以上でもなくそれ以下でもない。
とすると、あるべき審査は隠された不適合をすべて検出し、適合を不適合とする勇み足、いや違ったあわて者の間違いがあってはならないことになる。万が一あわて者の間違いがあれば異議申し立て事項だから。
するとこの審査競技大会は全員が満点を取らねばならず、満点以外は不合格になる。
アッツ、するとやはり認定審査と同じになってしまう。
いや、私の勘違いであった。すべての審査機関はこの評価方法ではすべて満点になる。そうに違いない。
審査の質というのはそういった不適合を見つけたとか見逃したという当たり前のレベルの低い話ではないのだろう。
そもそも審査の成果物はなんだろうか?
認証証の提供ではない。
簡単である。研究開発の成果物は研究報告書である。じゃあ審査のアウトプットは審査所見報告書ではないか。審査の質を比較するならば、審査所見報告書の品評会を行えばよろしい。
ふつうの方は長年ISO事務局を担当していても、大抵はひとつの審査機関としかお付き合いはないだろう。途中で審査機関を換えたとしてもまあ二つ三つである。同じく、審査員の方でもほとんどの方は、ひとつの審査機関か審査機関を替わってもせいぜい2社とか3社だろう。だから所見報告書の様式も二通りとか三通りしか知らないことになる。
私は品質と環境双方で複数の審査機関とお付き合いしてきた。また同業者から相談など受けて、私が対応したことのない審査機関の所見報告書も見る機会がある。その結果、各審査機関の所見報告書の形式・内容は多種多様であることに気がついた。同じ審査機関でも、日本と外国では組織に提供する所見報告書の形態が異なることもある。
じゃあ、各審査機関の成果物である所見報告書を比較して順位付けしようではないか?
各社の所見報告書が、IAFのガイド(まもなくISO17021になると聞く)と引用規格などの審査基準に適合しているか否か、所見の適切さあるいは的外し具合、報告書の文章に品格があるかないか(あまり関係ないかもしれない)など、審査項目を定めておいて評価すればよい。
誤解を恐れずに申し上げるが、この品評会の審査員は、所見報告書の内容を評価する以前に、文章が国語として判然としないもの、理屈がおかしいもの、意味のわからないものなどなどに出会うことを保証する。困ったことだがそれが実情である。それには多くの事務局の方の同意を得られると考える。
まず所見報告書といっても一様ではなくそのボリュームからしてきわめて開きがある。A4サイズで3ページくらいの報告書しか出さない審査機関もあるし、50ページもある報告書を組織に提出するところもある。
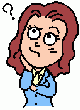 量が多ければ良いなんてことは言わないが、3ページや4ページでは経営に寄与する提言を書くには足りないのではなかろうか?
量が多ければ良いなんてことは言わないが、3ページや4ページでは経営に寄与する提言を書くには足りないのではなかろうか? 実際に数えたら、1200字から2000字の間であった。
仮に2000文字として一回の審査費用を100万円とすると、一文字500円につくことになる。きっと一文字一文字の価値がものすごくあるのだろう。ありがたいお経のようだ。そしてそのわずかな文章が、経営にどのように寄与するのか?ぜひ知りたいものである。
しかし待てよ、審査所見には要求事項の各項目について適合・不適合を表明しなければならないし、かつそのエビデンスを明示しなければならないように記憶している。それだけ書くにも2000文字では足りないような気がするのだが・・
参考までにこの拙文はだいたい5000字である。
あるいは経営に寄与するというのだから、どのような面においていかほど経営に寄与したのかを評価し判定するという見地もある。
- 前にあげたキャッチフレーズから推察するに、
- 審査後、いかにパフォーマンス向上させたかで評価するのだろうか?
- 経営に役立ったかどうか、組織の経営者にアンケートでもするのだろうか?
- 組織が審査後にどれほど業績が改善されたのかをみるのだろうか?
それは、売り上げとか株価であらわすのだろうか? - 顧客満足・・組織の顧客にアンケートするのだろうか?
組織に顧客満足を測りなさいとのたまわく審査機関は多いが、今度は審査機関が組織の顧客満足を測らねばならないし、その結果を組織に提示しなければ立証責任を果たさないことになる。
これはとんでもない理屈ではない。何事も最終顧客の要望に応えることが最終目的なのだ。それは審査機関と受査組織というBtoBの取引であっても同じである。
経営に寄与するというのだから、そのような経営層・管理者層へどのようなインプットをしたのか? 適切であったのかを評価することも考えられる。
しかしこのときの判断基準として何を用いるのだろうか?
前に述べたように審査機関の審査の質競技の基準はIAFガイドをはじめとする公知のものに限定されるのだから、そのようなコンサルともいえるような経営への提言を測る基準はないし、そのような提言自体が審査基準に反するような気がする。
私は経営層や上級管理者のインタビューの結果が所見報告書に反映されたのを見たことがない。大体会社を経営している者に対して、審査員がご意見することができるのだろうか? 会社を経営する力量がなければ経営者に相対することはできないと思う。そして、そのような方の時間をとらせるならそれなりの効果がなければやめた方がよいとアドバイスする。 『品質(環境)に関してよくご認識され方針を出されている。マネジメントレビューにおいて状況を把握しマネジメントシステムの見直しを行っていることを確認した』なんて文章を書くだけなら、やめときなさい。 実を言って、経営者や上級管理者からインタビューが何のためなのかという苦情を受け、やめて欲しいとこぼしている事務局を複数知っている。 |
いろいろと考えると結局、あるべき審査の質とは、経営に寄与するなんてものではなく、客観的に定められた基準に対しての適合審査ではないかという気がする。
しかし、浅学でボケのはじまりつつある私のことである。各審査機関は、私の考え付かないことを考えてらっしゃるのに違いない。ぜひ、審査の質の尺度と指標をお教えいただければ幸いである。
ぜひともお便りを期待しております。
本日の疑問
各審査機関が質の高い審査を提供しているならば、負のスパイラルはありえないだろう。
負のスパイラルどころか現実に、審査機関の認定取り消し、認定停止があるということは、質の高い審査を提供していないということなのだろうか?
もしこの拙文を読んで、うそ800はデタラメだ! ISO審査登録制度に反抗する者だと思われた方もいるかもしれない。
しかし、それは違う。
私は誰よりもISO9001やISO14001を愛し、第三者審査登録制度の行く末を心配している。そしてそれを良くしようと過去よりずっと努力してきた。審査において、また審査機関に出向いてご意見などしてきた。このうそ800もその活動のひとつである。
うそ800にもどる