 第6条1項 (2003.12.21)
第6条1項 (2003.12.21)
「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。」
非常に短い項であります。
日本国憲法には珍しくSVOCもありますし、一見まともな文章に思えます。
しかしこの短い文章についても私は疑問が沸々と湧き出してきます。
エッ、あなたは疑問を持たないですか? 困りましたね、そういった純粋無垢な方ほどアジテーションに弱く、すぐ平和ボケ菌や自虐史観ウイルスにやられてしまうのですよ、
悪いことは言いません、偏向テレビ局の番組を見るときはマスクと保護めがねをつけて見るようにしましょう。テレビから放出されるばい菌があなたを冒す危険があります。昔、ウルトラマンで怪獣がテレビ局を占拠し、放送電波に乗って全国の各家庭に現れるというストーリーがありました。(覚えていらっしゃいます?)
そのとき、ウルトラマンはいかに闘ったか?
ウルトラマンも電波で各家庭に現れてその怪獣と闘ったというオハナシでありました。
荒唐無稽だけど発想はすごいですよねでは検討開始!
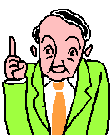
- まずニュアンスについて
この条項では「任命する」と粛々、淡々と無色透明な表現であります。
しかし原文では「The Emperor shall appoint ・・・・・」であって直訳すると「天皇は・・・・しなければならない」とかなり失礼な言い回しなのです。
天皇も公僕でありそれでよろしいというお考えもあるでしょうが、それなら「理想の憲法」の第1条で「天皇は日本国民統合の象徴である」なんて持ち上げないほうがよろしいのではと愚考いたします。
せいぜいが「天皇は日本国民の代表として国事行為を行う」とすべきではないのでしょうか?
まあ、ここでつっかかってもしょうがない、次に進もう。
いずれにしても国会の指名に基づくパッシブ(受動的)な行為でしかないのだから
- 基づく?
この日本国憲法の他の部分でもそうだが、一般的に「基づく」とは議決や法規制などを根拠に何事かを実施するときに判断が伴う場合に使用する。
具体例としては、
人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基く(前文)
天皇は日本国民統合の象徴であり、この地位は日本国民の総意に基く。(第1条)
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する。(第24条第1項)
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使する。(第83条)
一方、実施に当たり裁量範囲のないときは通常は「従い」と記述する。
法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。(第73条第4号)
本当は「天皇は、国会の指名に従い、内閣総理大臣を任命する。」ではないのでしょうか?
先に述べた「shall」と同じく、そのような文章では天皇に失礼であると考えたのでしょうか?
- 第6条と第7条の違いは?
天皇の国事行為はこの第6条と第7条に分けて記述しています。
第6条ではさらに二つの項に分けて、この内閣総理大臣と最高裁長官の任命を規定しており、第7条では項を分けずに10個の号に羅列しています。
なぜ国事行為を二つの条文に分けたのか?
某司法試験の参考書によると「国事行為の中で特に重要なものだから条を分けて記述している」とある。
オイオイ、それって論理的な解釈でしょうか?
内閣総理大臣が国会の指名によるものならば、国会の召集の方が内閣総理大臣の任命より重要でしょう。 国会の指名した内閣総理大臣が指名する最高裁長官の任命はずっと格下の行為となるのではないですか?
まあ、条項をどのように分けようと分けまいと生き死に関わることはないですか?
先に行こう。
- 使われている言葉は適切なんだろうか?
任命とか指名とか言葉の使い方はどうなっとるんでしょうか?
- 内閣総理大臣については
「指名」とは「誰さんがいい」ということで「任命」とは「じゃあ頼むわ」ということでしょうか?
- 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。(第67条第1項)
- 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。(第6条第1項)
そう簡単に決め付けちゃいけません。原文を確認しましょう。
指名の原語はdesignate任命の原語はappoint
- To mark or point out:特筆すべき印をつけるとか指し示すこと
- To denote:重要なことを示す
- To name:称号などを与える
- To nominate or select:責任や職務を行う者として指名あるいは選ぶこと
- To name or assign officially:重要な職務に付いた新任の者を明示する
- To fix:会合の時間を決める
- To designate (a person) to take the benefit of an estate created by a deed:職務を立派に遂行できるであろう人物を選定すること
- To equip:備える・与える
- To arrange:取り決める
えーっと、簡単に言えば「指名」も「任命」もあまり意味は変わらないようです。
まあ指名は「責任や職務を行う者として指名あるいは選ぶこと」で任命は指名された人を「重要な職務に付いた新任の者として称号を与える」と理解することにしましょう。
- では国務大臣はといいますと
- 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。(第68条1項)
- (天皇は)国務大臣を認証する。(第7条5号)
- 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。(第68条2項)
- 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。(第70条)
それでは分析を開始しましょう。
- 任命はappoint
前の文では「重要な職務に付いた新任の者として称号を与える」と解釈することとしました。(誰が? おばQですが)- 認証はattestation of appointment
- An act of attesting:宣誓すること
- An attesting declaration:法廷など公の場における証明や宣言
これを取りまとめますと、「内閣総理大臣は国務大臣という職務につけることを決め、天皇は公にそれを宣言する」とでも表現すればいいのでしょうか?
総理に比べて平大臣は称号を与えるのがワンランク低くてもよろしいという発想なのでしょうか?
ちょっと待ってください、(刑事コロンボ流)総理大臣を認証するのは誰なの?
天皇が内閣総理大臣を任命し認証するのかな?
- 罷免はremove
内閣総理大臣が任命するのだから、罷免してもよいという理屈は成り立ちそうです。
そして新たに任命された大臣を天皇が認証する。ものごとは粛々と・・・・
あれ、待ってくれ!
「天皇が公に『国務大臣であるぞ』と宣言した」行為をいったん取り消さないと筋が通らないのではないか?
すなわち、「天皇は罷免された国務大臣の認証を取り消す」という文言と行為がないと論理は通らない・・・・と私は思う。
上記はジジイの間違いでございました。取り消しいたします。(下記参照)
★
ななし様からご指摘を受けました。(2004.01.25)
「天皇は罷免された国務大臣の認証を取り消す」という文言と行為がないと論理は通らないと論じていますが、第7条第5号には、「國務大臣及び法律の定めるその他の官吏…の任『免』を認証すること。」とありますので、任命の認証を取り消すという形ではなく、罷免することを認証するという形を採用していると思うのです。
ななし様
おっしゃるとおりです。私の間違いです。
ジジイ不明を恥じ、再び過ちをせぬよう、上記のとおり取り消し線を付け、今後も晒すことといたします。
- 辞職はresign
辞職とはみずから職を辞すること(そのまんまじゃないか?)、しかしながら辞職が許される職務・場合と許されない職務・場合がある。志願兵といえど戦闘中の戦線離脱は銃殺と決まっている。
この場合、任命者である内閣総理大臣が不在あるいはその職を失ったのだからよしとしよう。
おお!マスマス分からなくなってきました。
内閣総理大臣に関してだけなら、理解できたのですが・・・・国務大臣に関する規定と合わせて理解しようとすると・・・・・難解です。イエ、理解不能といったほうがいいのかもしれません。このホームページに寄せられるお便りにも理解不能、意味不明という文章がけっこう多いのですよ、
いえ、文字化けじゃあありません。日本語になっていないものが多いのです。
今までそういった文章を書くのはまさか非論理的な頭脳の持ち主ではないだろう、あちこちの記事をカットアンドペーストで作っているからだろうと推察しておりました。
しかし本日、偉大なる日本国憲法を信じていると支離滅裂・意味不明な文章を書くようになるということが分かりました。
本日のまとめ
いやあ、今日は大変ためになるお勉強でした。
全然、ためにならなかったという声ありけり
日本国憲法の目次にもどる