1998年
夏休み後半のできごと |
8月4日にサーバーの修理を依頼したのに,業者さんがまだ来てくれません。 最初の約束が,8月5日か6日。 次の約束が,8月10日〜14日のいずれか。 3度目の約束が,8月17日か18日。 明日こそ来てくれるかなあ。20日からコンピュータ研修会が予定されているので,来てくれないととっても困るんですけど。 お願いします。 仕事始めの今日は,ToDoリストを作りました。というか,山積している仕事を思い出し,書き留めておきました。 パソコン関連: ・コンピュータ研修会(8/20,21)の準備 地区の教員を対象とした研修会(7/28の続き)のテキスト作成と会場準備です。あと少しで終わります。 →達成度:90パーセント,必要時間:あと2時間,期限日:8月19日 ・研究授業の指導案作成 10月に予定されている研究授業の指導計画の立案です。やりたい内容は決まっているのですが,使う(使える)ソフトがまだ決まりません。9月1日に提案します。 →達成度:20パーセント,必要時間:あと8時間以上,期限日:8月31日 ・パソコン利用教育研究会の発表の準備 「子どもたちが作るホームページ」というテーマで発表します。その原稿作りです。 →達成度:0パーセント,必要時間:10時間ぐらいかな,期限日:9月6日 ・郷土資料集作成委員会のhtml資料の作成 締め切りは10月2日ですが,全部で20ページほどありますから,夏休み中に少しでもやっておきたいです。 →達成度:0パーセント,必要時間:軽く10時間以上,期限日:10月1日 その他: ・運動会の競争遊技の計画 →達成度:0パーセント,必要時間:運が良ければ2時間,期限日:8月31日 ・書類A(保健関係)作成 →達成度:0パーセント,必要時間:5時間ぐらい,期限日:8月4日(過ぎちゃった) ・書類B(授業関係)作成 →達成度:0パーセント,必要時間:6時間以上は確実,期限日:1学期(とっくに過ぎてる) ・書類C(学級関係)作成 →達成度:0パーセント,必要時間:3時間ぐらい,期限日:8月31日 考察: あと50時間ぐらい仕事したらすべて終わります。(たぶん) 業者さんがやっと来てくれました。 2週間前にサーバーの修理の依頼したのですが,とても忙しいらしく,来校予定が2度も延期されるなど,延び延びになっていました。明後日にコンピュータ研修会が予定されているので間に合うかどうかずいぶん心配していたのですが,とにかく助かりました。(でも約束した時間より50分も遅刻ですよ。) しかも来てくれたのは,地元の業者さんではなくて,本社のサービス事業部の方でした。これまた助かりました。今回のようなケースでは,地元の業者さんに来ていただいても時間の無駄,二度手間になるだけです。 これまでの私の観察から判断すると,地元の業者さんはちっとも頼りになりません。ケーブルの抜き差しとか,アプリケーションのインストールぐらいはできると思うのですが,原因不明のトラブルについては,ろくに調べもしないでそそくさと帰ってしまうほどの力量なのです。 地元の業者さんもそのあたりは自覚しているようで,今回は最初から本社のエンジニアの方を手配したのでした。 しかしながら,来校した本社の業者さんの話によると,今日の目的は,修理じゃなくて,”調査”なのだそうです。これから行う調査の結果を踏まえて,地元の業者さんと今後の対策を相談して欲しいとのことです。 「そんなあ。今日直してもらわなきゃ困ります!」 「私の役目は調査だけですから修理は行いません。道具も持ってきていませんし。」 呆然。 それで,本社の業者さんが難しそうなプログラムや見たこともない機器を駆使して調べた結果,CPU,キャッシュ,メモリ,マザーボードなどには異常がなく,壊れているのはやはりHDとのことです。 「修理に出すと時間もお金もかかるので,新品に交換していただいた方が良いですよ。」 やっぱりなあ。先日修理を依頼した際に,症状を記したレポートを地元の業者さんにFAXで送ったところ, 「症状は軽そうなのでおそらく部品の修理だけで済みそう」 と言われたのですが,HDが壊れているらしいのに修理で済むなんてちょっとおかしいと思っていたのです。HDが壊れたら普通は交換でしょう? あーあ,システムの再構築か。 ところがところが,とってもうれしい誤算がありました。サーバーのHDは,1つのHDをパーテーションで分けてA・Bのドライブ構成になっていると思っていたのですが,実はパーテーション分けされていたのではなく,HDは2つあったのでした。壊れているのはBドライブに割り当てられている方だけ,システムや大事なデータが入っているAドライブの方は異常なしとのことです。 壊れたHDを外していただいたら,サーバーは正常に立ち上がるようになりました。 Bドライブは,バックアップデータとかフリーソフト(クライアントにインストールしたもの)とか,通常は使っていないものばかり入れてあるので,使えないのは少々残念ですが,システムを再構築することに比べれば,ほとんど実害なしです。 やれやれ助かりました。コンピュータ研修会は無事開催できそうです。 明日からのコンピュータ研修会の準備を行いました。 明日(8/20)の研修内容はイメージスキャナの操作と名刺作りです。 イメージスキャナは,コンピュータ室には1台しかないので,私とM先生が所有しているものを持ち込み,3台を使って行います。プリンタも,コンピュータ室には5台しかないので,M先生の学校のプリンタをお借りして,10台で行います。 私ができる範囲の準備はすでに済ませたので,あとは明日M先生が持ってくるスキャナとプリンタをセットするだけです。 名刺作りは,1学期末に行った「PTAパソコン講座」で使ったものを流用できますから,特別な準備は必要ありません。 明後日(8/21)の研修内容はホームページ作りとビデオプロジェクタの操作です。 ホームページ作成ソフトには「Netscape Communicator」を使います。これはすでにインストール済みです。 ホームページ作りのテキストは,昨年度パソコンクラブで使ったもの(ただしNetscape Gold用)を流用するつもりだったのですが,手直ししているうちに,結局ほとんど全部書き換える羽目になってしまいました。 テキストの冒頭に,「作品をホームページ形式(html)で作るメリットは?」という文章を載せてみたのですが,こんなので良いでしょうか。まだ1日余裕があるので,アドバイスいただけるとありがたいです。
それから,ホームページの閲覧に関して,先日”発見”した便利な機能を早速使ってみることにしました。コンピュータ研修会用のフォルダを「仮想ディレクトリ」に設定したので,アップロード作業を行わなくてもリアルタイムに更新されるはずです。 それと同時に,任意のファイル名をつけた”白紙のページ”(人数分=20個)と,それらのページにリンクした”コンピュータ研修会トップページ”を作っておきました。受講者がその”白紙のページ”にホームページを作成すれば,わざわざアドレスを入力しなくてもトップページからのリンクをクリックするだけで,各自のページを閲覧することができるはずです。 これらが果たしてうまく機能するでしょうか。少々心配です。 大方の準備は研修会初日(7/28)までに済ませておいたつもりだったのですが,テキストを見直したり,機器やファイルの準備をしているうちにいつの間にか6時間も費やしてしまいました。 ふぅ。いつものことですが。 研修会2日目が終わりました。 イメージスキャナの操作を練習した後,取り込んだ画像を使って名刺作りを行ったのですが,今日は作戦失敗でした。私たち講師3名は,最初から最後までの2時間半,息つく暇もありませんでした。コマネズミのようにくるくるくるくる走り回っていました。とっても疲れました。 前回は,研修内容をいくつかのステップに分けておき,全員ができるようになったことを見届けてから次のステップに進むというやり方で行いました。 ところが今回は,用意した機器(イメージスキャナとプリンタ)の数が少ないので,一斉に行うのは無理です。それに順番待ちによる時間のロスが心配でした。 そこで今回は,とにかくやれることから取りかかっていただこうということで,一連の手順「スキャナの操作−名刺作り−印刷」をすべて説明した後で,作業を始めていただいたのです。そうしたら大混乱でした。もちろんマニュアルは用意しましたし,つまずきそうなところは念入りに話したつもりですけどね。でも頭に詰め込む量が少々多すぎたようです。 しかし気分的にはずいぶんラクなもので,「PTAのパソコン講座」の時は,保護者の方がうまくできないと,自分の説明の仕方が悪かったのではないかと自責の念にかられていたのですが,先生方が相手の今回は,「あ,そうでしたね。さっき説明してもらったことでした。忘れてました。えへへ。」などと答えていただけるので,精神的に疲れることはありませんでした。 今日最大の誤算は,”強制終了”が大量に発生してしまったことでした。わずか2時間ほどの間に5回も発生してしまった方もいたほどです。 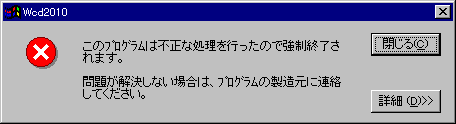 とにかくこのメッセージが出てしまったら一巻の終わりです。(たまに助かることもありますが。) 「PTAパソコン講座」で名刺を作ったときには,強制終了など起こらなかったので,今回は途中でセーブしておくようアドバイスしていませんでした。ですから,皆さん最初から作り直す羽目になってしまいました。 「残念ながらこのボタン(閉じる)を押して,ソフトを終了させるしかありません。」 「作ったところまでは保存しておきたいのですが。」 「できません。」 強制終了ラッシュの原因は,おそらく,名刺に組み込んだ画像のサイズが大き過ぎたことによるメモリ不足じゃないかなと思います。たくさんの画像を組み込んでカラフルな名刺にした方ほど強制終了の発生率が高かったですから。これが24MBしか積んでいない私の学校のパソコンの限界ですね。 そういえば今思い出したのですが,「PTAパソコン講座」のときも,一人だけ強制終了になってしまい,泣きそうになりながら作り直していた方がいたのでした。その点先生方は,日頃から強制終了には慣れているせいか,”最初から作り直し”という冷酷な事実を,(表面上は)わりと冷静に受け止めていたようです。内心ではどう思っていたか分かりませんが。 色々ありました。でも今回の「名刺作り」は,先生方にとっても楽しんでいただけました。 研修を終え,笑顔でコンピュータ室を後にする先生方を見ていると,本当にうれしいです。 疲れ切った様子で帰っていかれると,私たちも悩んでしまいますからね。 でも帰るときに椅子の整頓ぐらいはしてほしいなあ。子どもでもできるよ。それが残念。 研修会&明日の打ち合わせが長引いてしまったので,家に帰らずに学校から直接飲み会に出かけました。 それで今,コンピュータ室にいます。(苦笑) (8/21 1:00) コンピュータ研修会3日目が終わりました。 研修内容はホームページ作りとビデオプロジェクタの使い方です。ビデオプロジェクタの使い方は説明のみで済ませ,ホームページ作りを中心に進めていきました。 今日もほとんど休みなしに動き回りました。2時間ほどの間に1人平均2回程度として計40回以上はコールされたと思います。しかしながら昨日ほどはしんどくありませんでした。 昨日は強制終了などの予期せぬトラブルが頻発しましたし,質問やトラブルの内容も多岐にわたっていたのですが,今日質問された内容は,リンクや画像挿入の仕方など,戸惑うことが事前に予想されていたことばかりだったので,昨日よりも対応しやすかったです。 いや,それよりも,昨日あんなに疲れてしまったのは,ただ単に休みボケのせいだったのかも。 終わりに感想を書いていただきました。社交辞令とはいえ,好意的な内容が多かったのはやはり嬉しいです。 (多くの方から指摘された代表的な意見。) 良かった点 ・講師の方がとても親切に教えてくれた。 ・色々な機器やソフトの使い方を知り,今まで以上にパソコンに興味が沸いてきた。 悪かった点 ・研修で使った機器やソフトが自分の学校にはない(あるいは種類が違う)ので,すぐには役立たない。 ・どの教科のどの授業で機器やソフトを使えばよいかという具体的なアイディアを教えて欲しかった。 良かった点として,研修の中身よりも態度が評価されたのはちょっと寂しいです。 機器やソフトが学校ごとに異なるという問題点はもちろん最初から承知していました。ですが,機種によって操作方法が多少異なっていても,基本的な機能の差異はほとんどありませんから,ただ単に機器の操作方法を教えるだけでなく,データの扱い方(ソフトを使っての活用法)をも提示するようにすれば,それなりに役に立つのではないかと考えていたのです。しかしそれが授業に即したものではなかったため,受講者の方にとっては少々物足りない結果になってしまいました。 毎度のことですが, 機器やソフトを駆使した授業例を紹介すると,まずは使い方などの初歩的なことからやって欲しいと言われます。 それなのに, ごく基本的な操作の仕方を教えると,授業ですぐに役立つようなもっと具体的な内容を扱って欲しいと言われます。 困ってしまいます。 夏のコンピュータ研修会が終わり,少々虚脱気味です。この3日間は,デジカメ,画像編集,スライドショー作り,イメージスキャナ,名刺作り,プリンタ,ホームページ作り,ビデオプロジェクタの操作と,かなり欲張ってしまったので準備も大変だったのですが,講師である自分にとっても大いに勉強になりました。 明日からは次の”宿題”に取りかからねばなりません。研究授業の指導案づくりです。 授業のネタはすでに決まっていて,子どもたちがコンピュータを使う場面は,自分で作った資料(主に画像)を紙芝居風にプレゼンテーションするところです。 プレゼンテーションというと,MS「Power Point」などの高機能な市販ソフトがありますし,オンラインソフトも数多くありますし,インターネットブラウザを使うという手もあります。しかし,この数ヶ月間色々調べてきたのですが,今度の授業で使えそうなものは見つかりませんでした。 新たなソフトを購入するための予算は皆無の貧乏な公立小学校ですから,お金のかかるソフトは論外,それに使い手はわずか9歳の子どもですから,複雑な操作を要求されるものやメニューの表記が難しい(漢字・英語)ものも無理,直感的に操作できるものでないと子どもたちの手には負えません。 当初は「Tiny Slide Show」というフリーのツールを使おうと考えていて,校内研修会でも取り上げたのですが,最近は使う気がなくなってしまいました。理由はうまく言えないのですが,「何か面白くないなあ」という気がするのです。(苦笑) それでここにきて新た注目しているのが,”html”によるプレゼンテーションです。ブラウザの操作は少々練習すれば大丈夫だと思いますが,作るのはいくら何でも小学3年生では無理だと思い,当初は念頭にはありませんでした。 昨年度パソコンクラブでホームページを作った際,子どもたちが失敗したことで最も多かったのが,ファイル名を”半角英数”にすることでした。日頃日本語のみしか扱っていない子どもたちにとって,”全角かな”と”半角英数”を切り替えながら作業することは,想像以上に困難だったようです。 とはいっても,htmlファイルのファイル名だけの問題ならば,あらかじめ”001.html””002.html”などのように,子どもたちにも意味が通じるような名前を付けた白紙のファイルを用意し,そこに記述してもらえばOKです。しかし他のファイル,例えば画像ファイルについてはお手上げなのです。あらかじめ私がファイルを作っておくことは不可能です。その都度子どもたちが自力で”半角英数”のファイル名を付けなければなりません。 それは9歳の子どもには無理です。 ところが,先日コンピュータ研修会の準備をしていて,解決の糸口を発見したのです。「Netscape Communicator」付属のエディタ「Composer」を使えば,この問題をうまく回避できそうです。 「Compser」なら,グラフィックソフトからのコピー&ペーストができるのです。(ペーストした画像は自動的にJPGに変換され,自動的にファイル名が付けられます。) それ以外にも, ・BMPファイルを挿入しようとすると,自動的にJPGに変換してくれる。 ・別ドライブにあるファイルならば,htmlファイルがある場所に自動的にコピーしてくれる。 などの機能があります。 つまり,子どもたちは半角英数というファイル名のルールを気にせずに済むどころか,画像フォーマットやフォルダの場所も意識することなく,画像を編集することができるのです。これは大変便利です。 実は昨日の研修会は,私の授業がうまくいくかどうかのテストも兼ねていました。(苦笑)どこに落とし穴があるか分かりませんから。 20人の先生方によるテストの結果,特に問題は生じませんでした。どうやらうまくいきそうです。 仮想ディレクトリを設定することにより,アップロード作業を行わなくても更新結果がリアルタイムに反映されるかどうかもテストしていたのですが,こちらも大丈夫でした。 実は,「Composer」よりもIE4.0付属の「FrontPage Express」の方が使い勝手が良いのですが,使う度胸はありません。 もし万一不具合が起こり,Win95&アプリケーション&ドライバの再セットアップという最悪の事態になったら悲惨ですからね。 コンピュータ室が1週間使えなくなってしまいます。 明日は朝から学校の草取りです。(泣) 午後から「サーバー管理」の研修会に飛び入り参加しました。 この研修会は教育委員会が主催する研修会の一つで,コンピュータ室管理者を対象とした講座なのですが,私は講師の立場で別の研修会を出席していたため,過去2回は受講できませんでした。最終日の今日だけは日程の都合がついたので,ちょっと覗いてみました。 予告では,研修内容は「昨年度の続き」,受講対象者は「昨年度も受講した教員」とされていたですが,いざ参加してみたら研修内容は昨年度と全く同じでした。どうやら上記の条件があったにも関わらず,受講者の顔ぶれが大幅に入れ替わってしまったのでしょうね。昨年度受講してみたもののさっぱりついていけなかったので役に立たなかったという声も聞かれましたし,私のように他の研修会の講師をやらされて出席できなかった方も多いのじゃないかと思います。 それで私は,目新しいこともありませんし,飛び入り参加の立場なので実際に自分が操作することもできませんから,手順の説明だけ(それでも45分間)聞いて帰ってしまいました。 ところでこの講座では,WindowsNT4.0Serverのセットアップ,Lan構築,IIS(Microsoft Internet information Server)のセットアップなどを実習しているのですが,個人的には大変興味があるものの,小中学校のコンピュータ室管理者が行う研修内容としては不適切ではないかと思っていました。 私たちの地区の小中学校の場合(他の地区でも同様だと思いますが),サーバー及びLANは最初から組まれているので,教員がセットアップする必要はありません。トラブルのサポートはもちろん業者の方にやっていただくことになっています。中学校においては業者による定期メンテナンスも行なわれています。 それに,コンピュータ室内のみのLAN環境において,Webを閲覧するのに,Webサーバー(IIS)をセットアップしてアドレス指定などという面倒なことをする必要はありません。最初から組まれているネットワーク機能(Net BEUIによる?)を使って直接ファイルを指定してやれば事足ります。しかもファイル指定ならば,現在インストールされているIE3.02からなら,ファイル名が”日本語”であっても開くことができますから,子どもたちにホームページを作らせることを考えると,むしろファイル指定のほうが好ましいとも言えます。(それなのに自分の学校にIISを導入したのは,ただ単に私の好奇心からです。(笑)) ところがあれから一年を経て,私の考えも変わってきました。 今秋から地区の全中学校が,2年後には小学校でも,インターネットに常時接続されます。しかもホームページを公開することを前提として,ドメインも取得します。 そこまで話が進んでいるとなると,例え業者任せにするにしても,自分の学校で運用されているシステムの基本構成や機能を知っておくことは,もしかしたらとても大切なことなのかも知れないと思い始めています。というよりも,知ってなきゃホームページの公開などできませんよね。 ところが,このレベルの研修になると,受講者の方にとっては相当きついようです。Windows95の操作ぐらいはそこそこできる方が集まってきているはずなのですが,それでも,NTserverやIISとなるとギャップは相当大きいようです。 例えば私の学校では,私が出れない代わりにH先生にお願いしました。H先生はちょうど3年前の夏に私の勧めでパソコンを買った方です。買わせた責任をとって,周辺機器のセットアップ,Win95へのアップグレード,インターネットの設定,LANの構築など,事あるごとに何度も家に足を運んでお手伝いし,今ではこれらのことをすべて自分でできるようになりました。それでもこの研修会では「言われたとおりにやってはいるものの,今自分がいったい何をやってるのかさっぱり分からない」とこぼしていました。 考えてみると,私にも大いに責任があるかも知れません。H先生はパソコンにはずいぶん興味を持っていて,日頃自宅でいろいろいじっているのですが,コンピュータ室のサーバーについては,なるべく触らせないようにしてきました。もちろんそれはH先生の失敗をフォローできる自信が私には無いからです。そういう意味では私もまだまだ勉強不足です。とは言っても,もうこれ以上はやりたくありませんが。(苦笑) しかしこれからはもう少し触ってもらうようにしなくっちゃ。 ちょっと反省ぎみです。 そう言えば,私の学校のwwwrootは,クライアントからページを修正したり,ノートパソコンからのファイル転送を簡単に行なうために”everyoneフルコントール”にしている(爆)のですが,やはりこれはちょっとまずいですね。 夏休みも残すところあと2日になってしまいました。今日は最後の日曜です。でも,夏休みの宿題が山積しているので,仕方なく,一日中仕事してました。 昼過ぎに学校に出かけましたが,さすがに今日は誰もいませんでした。まだ宿題が終わっていないのは私ぐらいのものです。とほほ。 9月1日発行予定の”学年通信9月号”を1時間ほどで片付けた後,研究授業の指導案作りに取り掛かりました。これも9月1日に提案する予定の急ぎの仕事です。 本年度の目標が「自己表現の手段としてコンピュータを効果的に活用する」なので,それに沿った内容を考えています。 当初は,「Tiny Slide Show」というソフトを使って,プレゼンテーションをするつもりでした。ちょうどMS「Power Point」で資料を提示しながらプレゼンするようなスタイルをイメージしていました。 ところが,一週間程前に考えが変わり,ソフトを変更することしました。独自フォーマットを使用する「Tiny Slide Show」では,汎用性がありませんし,「Netscape Communicator」付属のエディタ「Composer」がかなり使いやすい(特に画像の扱いが)ソフトであることを発見したので,「Tiny Slide Show」を使うのはやめにして,htmlでプレゼンテーションすることに決めたのでした。 ところがところが,よくよく考えてみたら,手書きならいざ知らず,3年生の子どもが,お絵描きソフト&「Composer」を駆使(ちょっと大げさ)して,一人あたり平均7枚ものプレゼン資料を作るのは無理だということに気付きました。授業の1単位時間は45分で,2人で1台しか使えませんから,1回わずか20分程度の作業時間しかありません。やってやれないことはありませんが,途方もなく時間がかかってしまいます。おそらく子どもたちは途中で飽きてしまうでしょう。 そう言えば,昨年パソコンクラブで4〜6年生の子どもたちがホームページを作ったときでさえ,1人1台のパソコンを使ったにもかかわらず,わずか4・5枚のページを作るのに,6時間以上かかったのでした。 ということで,スライドショーはやめました。 指導案作りはスタートラインに戻ってしまいました。 それで,カリキュラムを熟読しながら2時間ほど思案した結果,「好きな本の紹介カード」作りをすることに決めました。 これならあまり時間がかからず,楽しくやれそうで,なかなか良さそうな気がします。お絵描きソフトのみで作れますが,級友の作品を自由に閲覧できるように,出来上がった作品(画像)を「Composer」で編集して,htmlファイルとして保存させることにします。 これまでは,スライドショーのツールとしてhtmlを使うことを考えていたのですが,この授業では,いつでも自由に閲覧するためのツールとしてhtmlを使うことになります。 指導案を検討していただく際に参考例として見せるため,サンプルを作ってみました。子どもたちはこのようなページを作ります。 実際に作ってみると,わずか1枚のページでも,全体の構成,文章,フォントの種類やサイズ,色合い,カットなど,工夫することはいくらでもあります。こんなのを7枚も作らせようとしていたなんて,ずいぶん浅はかでした。 4ヶ月以上も前から考えてきた構想が,わずか一日で崩壊してしまうとは。見通しが甘過ぎました。 でもとにかく,授業の目処が立って一安心です。 明日も仕事です。もちろん。 PHSとデータ通信カードを繋ぐ”ケーブル”を家に置いてきてしまい,今日はコンピュータ室からアクセスできませんでした。 がっかりでした。 昼過ぎに学校に出かけました。今日も大忙しです。 まず運動会の競争遊技(ゲーム)の計画案を作り,次に子どもたちの読書感想文を読み,コンクールに出品するためのクラス代表を選びました。ここまでで3時間です。 雑務を済ませた後,昨日の続きの研究授業の指導案作りに取りかかりました。昨日は授業の内容を練り直したり,サンプルの作品を作ったりしているうちに時間が過ぎてしまったので,指導案として文章化する作業はこれからです。 授業は全部で4時間ほどかかるのですが,研究授業として先生方に公開するのは,そのうちの1時間のみです。 初めは子どもたちが作品作りをしている場面を見ていただこうと思ったのですが,それよりも,出来上がった作品をホームページに貼り付け,ブラウザで閲覧し合う場面の方が良いような気がしてきました。子どもたちの技能をアピールするなら実際に作っている場面を見せた方が良いのですが,今後のことを考えると,ブラウザを使ったネットワーク機能の活用法やそのメリット(級友の作品を自由に閲覧できる)をアピールする方が”将来性”があるような気がします。 ということで,この線に沿って指導案を立ててみました。 これを明日,3年生の先生方に提案します。私たちの学校では,研究授業の際は,事前に他のクラスで”お試し授業”をやることになっているので,他クラスの先生方に理解していただき,了解をいただかなくてはなりません。 先生方に覚えていただき,子どもたちに教えなければならない技能は以下の通りです。 ・お絵描きソフト「キューブペイント」上での日本語入力(文字修飾含む) ・「Netscape Navigator(ブラウザ)」を使ってのホームページの閲覧 ・「Netscape Composer(エディタ)」の一部の操作(画像貼り付け,保存,呼び出し,背景,日本語入力) 私のクラスだけなら大丈夫だと思うのですが,ブラウザとエディタの操作は,他のクラスの先生方にはかなり抵抗があるかも知れません。もちろんサーバー側の設定はすべて私がやりますけど。 引き受けていただけるかどうか,少々不安です。 夏休みは終わりです。 愚痴っても仕方ないので,気分を切り替えてがんばります。 |